2019年06月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

旧三井家下鴨別邸のアジサイ苑
旧三井家下鴨別邸(重文)下鴨神社の南に建っています。この地に三井家の祖霊社顕名霊社(あきなれいしゃ)が遷座されて参拝の際の休憩所にするために三井家11家の共有の別邸として大正14年に建築されたそうです。昨年、庭内の西側に約400本のアジサイやガクアジサイなどを植えて整備され初公開されたところ好評だったそうで今年も無料一般公開されました。アジサイ苑の中央に夫婦椋(みようとむく)樹齢推定250年、二本の椋の木が寄り添うように立っています。アジサイはどこで見ても同じなのでこれくらいにして・・・。旧三井家下鴨別邸望楼のある主屋(おもや)を紫陽花の陰から・・・望楼は特別公開の時のみ一階は拝見できるので入ってみます。
2019.06.30
コメント(9)
-
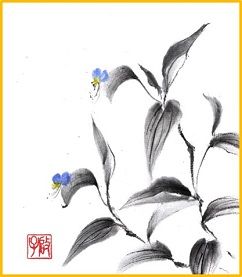
幸せカップルは国際結婚!?
梅雨入りより台風が先!大阪サミットが台風を連れてきたの!?新緑の中の上賀茂神社にて茅の輪が設置されていました。6月(水無月)の末におこなわれる「夏越の祓」(なごしのはらえ)の茅(ちの)の輪くぐり。半年のもろもろのものを祓い後半も無事に過ごせるように茅の輪をくぐります。一足早くくぐってきました。結婚式を終えられたご様子(わざとぼかしています。)雨が降っていましたので式を終えて記念写真は屋根のあるので土屋で撮っておられました新郎のご家族のようです。皆さんくぐっておられました。すらりと背の高い新郎さんは外国の方でしたご家族と友人たちでバスで来られていたようでした。幸せなご様子を拝見して頬が緩みます。・・・・・水無月とは田に水を引くので「水の月」「無」とは「の」の意味旧暦なら梅雨が明ける時期になるので「水の無い月」と言われる場合もあります
2019.06.28
コメント(25)
-

賀茂の水まつり 上賀茂神社
上賀茂神社の花菖蒲の時期と思い出かけましたが・・・。境内を流れる「ならの川」のほとりその代わりに[賀茂の水まつり」の準備が始まっていました水を司る龍神を祀る摂社・新宮神社が境内にあるので2012年から始まったそうです。7月の第四日曜日に境内の「橋殿」に神様をお招きし水に感謝し酷暑を無事に過ごせるよう祈願する祭典だそうです。(祈願用の短冊は200円)賀茂の水まつりは境内を巡行して境内を流れる「ならの川」を渡るそうです。微笑ましい様子に出会いました。さて?
2019.06.26
コメント(22)
-

早乙女たちの手植えで・・ 田植祭
伏見稲荷大社の田植祭が境内にある神田でおこなわれました。自前の神田がない場合は地元の田の一角を借りてしめ縄を張り御幣米を作られる神社があります雅楽と舞の「御田舞」が奉納される中田植えが始まりました。早乙女さん三人は息も合って順調に進んでいますこちらは男女混合組「そんいぎょうさん植えたら・・・後の苗が足らんようになるやろ!」「反対の手で苗を一本ずつ繰り出すんやぁ」外野がうるさいです~。「苗は一本でええんやー 上手やぁ」早い人、遅い人、進み具合はバラバラ「ほれ見ぃ 一馬身半も離されてるやぁ」《競馬やないちゅうのに・・・》北の方の米(収穫)は早いが京都の米(収穫)が遅いので今頃植えてもちょうどええねんや。と、言っておられました。また、子どものころは宮中祭事・新嘗祭(にいなめさい)11月23日(現在の勤労感謝の日)で天皇さんが新米を食べるまではその年の新米を食べさせてもらわれへんかったなぁ。と言っておられました。世の中が変わりました。・・・後始末・・・祭事が終わった後で残りの苗を別の方が植えておられましたお疲れ~・・・・番外・・・・雨がひどくなってきました。猫も石灯籠に雨宿り・・(^▽^)田植えは難しいですね!ー完ー
2019.06.24
コメント(17)
-
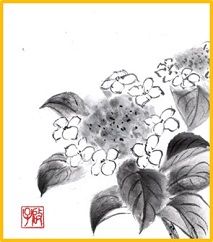
京都の梅雨は・田は青々と 伏見稲荷大社の御田祭
ガクアジサイどこの田を見ても植えられた苗が青々と涼やかです京都・伏見稲荷大社の御田祭ご神前に日々供えるご料米を早乙女たちは神田に植える祭事が6月10日におこなわれました。田植えの男衆と女衆の面々です田が清められて早苗が運ばれて祭壇へ神官により田の両サイドに印が・・・(理由はわかりません)祭壇から苗が田へ運ばれます。「ちゃんと植えられるんかぁ?」「俺が指導したろか!」周りでは手植えの経験がある趣味のカメラマンさんたちが騒々しいこと。(^▽^)この先は・・・。
2019.06.22
コメント(22)
-

緑の風がさわやかに 東山三十六峰を眺める
大悲閣千光寺からの眺めは・・・ここが亀山公園の展望台から見えるところです。今日は逆に眺めて見ましょう。展望台に子どもたちがやって来たようです遠足かな・・・?緑の風を受け正面に東山三十六峰の峰々!東山三十六峰の北の端比叡山大文字山の如意ヶ岳清水寺の裏山の清水山や阿弥陀ヶ峰(あみだがみね)あたりまで眺められます。ちなみに東山三十六峰の南の端は伏見区の稲荷山です。眼下にトロッコ列車!後の方に席を譲って下山します。保厨川下りの船この辺りまでくると流れが穏やかになり櫓を使われます日よけ用のテントを張っている船もあります。屋形船流れに任せた船頭さんの後ろ姿がいいなぁ・・・。大悲閣千光寺へ”ぶらり散歩”でした。
2019.06.20
コメント(16)
-
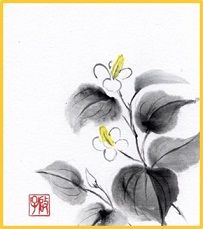
遠くから見ていた五色幕が お出迎えは…? 大悲閣千光寺
ドクダミ嵯峨嵐山・亀谷公園と対面の山中に五色幕が緑の中に美しく見えるのが大悲閣千光寺です。一度行ってみたいと公園の展望台からみていましたが行くなら新緑の綺麗な今でしょう!と出かけました。大悲閣千光寺まで「200段」と聞けば気が引けるかもしれないですが一段 一段の高さ(蹴上げ)が低いので苦にならないと思います。右から「大悲閣」と書かれていますひなびた感じがいいです。山門を入ってだらだらと坂道をあがって鐘楼お出迎えは「ワンちゃん」ですが・・・【噛みます】という札が下がっていますお参りするのに犬が寝ている横を通らなければなりません。お尋ねしたところ「寝ている時に触ると怒ります」何もしなければ噛みません。とのこと可愛いので頭を撫でに来る人がいて寝ている時に触られると怒るそうです人も動物も同じですね。(^▽^)大悲閣へどんな景色が見られるのかな・・・。
2019.06.18
コメント(20)
-

新緑を訪ねて 遠くに見ていた大悲閣
嵯峨嵐山の亀山公園・展望台から望む「大悲閣千光寺」へ新緑を楽しみながら行ってきました。ここから対面の山中に大悲閣が見えます。大悲閣の入り口です。渡月橋から大堰川の右岸を上流へ約1キロの所です大悲閣山号は「嵐山」寺号は「大悲閣千光寺」大堰川を開削するため工事で亡くなった方たちを弔うため、江戸時代の豪商・角倉了以(すみのくらりょうい)が嵯峨野・清涼寺の近くにあった千光寺を移転し建設したものです。本尊は恵心僧都作と伝えられる千手観音。眼下に大堰川を見下ろす岩肌に建つ観音堂です右や左に曲がりながらだらだらとした道や石段(200段)を上がりますご一緒にどうぞ。(微笑)ここで中ほどを過ぎました。山から引かれた水が冷たく気持ちが良いです曲がり角には椅子が置かれています優しいご配慮です。山肌にへばりつくような木が。。。頭を打たないように黄色い布が下がっていました。面白い光景です。だらだらとした坂と石段を上ったらやっと山門が見えました。昭和34年の伊勢湾台風で屋根も飛び半倒壊し、大悲閣はワイヤーで補強され仮本堂を設けておられたようですが2012年より大悲閣の修理が始まり2012年11月より一般公開になりました。・・・・・・…編集に手間取り遅くなりました。…これから動画の修正をしますので今日はここまで・・・。
2019.06.16
コメント(9)
-

スイレン 雨もまた良し! 平安神宮にて
菖蒲が咲くころに一日のみの無料公開いつもなら人が多いのですがこの日は雨、いつもより人出は少ないようです。と言っても人影がないタイミングはなかなかありません。スイレンは少し早いようでした。河骨も植わっていますが花が三輪ほどいかにも《見て! 見て!》というような一輪雨の中の花しょうぶにスイレンでした。
2019.06.14
コメント(20)
-
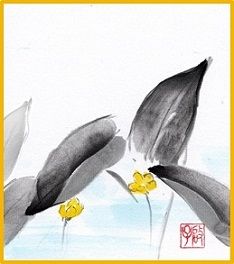
雨の日のしょうぶ 平安神宮にて
毎年、アヤメが咲く時期におこなわれる平安神宮の一般公開雨の予報でしたが出かけました。途中で降りだしましたが強行神苑の入り口を入ったところが南神苑、西、中、東神苑へと続き大極殿、本殿をとり囲んでいます。菖蒲を見たいので「西神苑」へ直行カメラの中へ入ってこられたお二人≪パチリ≫いただきましたぁ~。鷺さんも一般公開につられておこしかな。(^▽^)菖蒲は急に暑くなって咲き急いだようでした。スイレンが咲く中神苑の池へ回ります。
2019.06.12
コメント(20)
-

上賀茂神社へ向かう 葵祭 2019
葵祭は天皇のお使いである勅使が賀茂社(上賀茂神社と・下鴨神社)で祭典をおこなうことです。賀茂社へ到着後「路頭に儀」がおこなわれ勅使が御祭文を奉上し、御幣物を奉納します。この一連の儀式が「社頭の儀」です。葵祭は勅使が主役です。賀茂社まで行く勅使一行の再現が葵祭です。江戸時代までは「賀茂祭」と呼ばれおり日本最古の祭りで、平安時代に出てくる祭は賀茂祭で葵祭のことです。天候不順で穀物が実らず五穀豊穣を願って行われたのが始まりです。下鴨神社へ入った行列は午後、賀茂川の土手の道を通って上賀茂神社へ向かいます。ひと際、きらびやかに飾られた馬に騎乗葵祭の主役、勅使代をつとめる方です。斎王代と女人列斎王代、本来は斎王になるのは未婚の皇室の女性でした。天皇の代わりに神に仕える巫女が斎王です。伊勢神宮に置かれていたのにならって賀茂社にも置かれるようになったそうです天皇が交代するか身内の不幸の場合以外は都に戻ることはできなかったそうです。第64代 斎王代負野梨花さん京都 薫玉堂のお嬢さんです。村田製作所にお勤めです。大学時代に海外留学の経験もある才色兼備の斎王代です。(報道された内容です)葵祭までの流れは・・・5月1日の賀茂競馬足汰式(かもくらべうまあしそろえしき)5月3日の流鏑馬神事(やぶさめしんじ)下鴨神社の糺の森の馬場(約400m)で騎乗して駆け抜けながら3つの的を射る葵祭の道中の道を清める神事5月4日の斎王代・女人列御禊の儀(さいおうだい・にょにんれつぎょけいのぎ)斎王代と供の女人50名が禊をおこない身を清める神事(上賀茂神社と・下鴨神社で隔年交代)5月5日の歩射神事(ぶしゃしんじ)と葵祭の行列が歩く道を清め安全を祈願する。賀茂競馬(かもくらべうま)二頭ずつ馬が走り互いの速さを競う5月12日の御阿礼神事(みあれしんじ)と御蔭祭(みかげまつり)祭神の玉依姫命(たまよりひめのみこと)とその父、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)の荒御魂(あらみたま)を迎える5月15日の「葵祭」に至ります。
2019.06.10
コメント(24)
-

花が咲き乱れ バラの香りに癒されて
未央柳(ビョウヤナギ)ちょっと暑い日の京都府立植物園バラが見ごろだろうと出かけました。昨年の台風で花壇がほぼ全滅状態になりわびしい姿が続いていましたが花壇が花で埋まった植物園に戻りました。恒例の手作り位置が開かれライブも・・・アルバムも出しておられるようでしたがお名前は・・・?バラの香りが園を覆っています絵画クラブの方、数名がおれれましたアジサイ園では「甘茶」が先に咲いていました。此方はお食事中!北門に近い噴水が止まっていて藻を食べる姿に子供たちは大はしゃぎこちらは前撮りのお仕事中!素敵なアルバムが出来ることでしょう!バラ園を楽しんできました。
2019.06.08
コメント(18)
-

下鴨神社へ向かう 葵祭 2019
五月の御蔭際に始まり斎王代の禊の儀などの祭事を経て5月15日は御所を出た葵祭の行列は下鴨神社から上賀茂神社までの巡行がおこなわれます。行列は500人に及ぶそうです。時期がだいぶずれましたが投稿します。下鴨神社へ入る様子を見たくて出かけましたが糺の森(ただすのもり)の参道は何重にもなった有料席で埋まっていました。一般が見られるのは糺の森の入り口のみ…想定外でした。とりあえず入り口付近で・・・。警衛の列御幣物を奉じる列走馬の列があって(走馬の儀などに使われる馬)勅時の列触診方が通られるのですが写真がありません。次回、場所を変えますのでそちらで斎王代と女人列警衛の列、御幣物の列、走馬の列、勅使の列、斎王代・女人列の五つの分かれています。写真は大まかに区切っていますのでご容赦ください。下鴨神社で「社頭(しゃとう)に儀」がおこなわれます。(下鴨神社で昼食休憩をされます)葵祭を続けます。
2019.06.06
コメント(20)
-

寂光院から三千院・勝林院へ 大原女時代行列
寂光院を出て急いで行列を追いかけてバス停の近くの道路で大原女時代行列の一行に追いつきましたが・・・。行列が通る間は足止め、先へ進めません。秋のミニ大原女まつりの時(子どもたちのみ)コスモスが咲いている畑です。記念写真には間に合いませんでしたが出発される様子だけでも・・・。いつもの休憩場所です。雪の日に大原へ行ったとき雪だるまが作ったあったお店の前ですお土産物などのお店が並んでいる道です。工程の半分が過ぎたのでホッとされているのか…楽しそうです。三千院前の道に向かう石段です。三千院へ参拝の後はゴールの勝林院です。この橋を渡れば正面が勝林院です。この日は暑く、大変だったようです。ゴールの勝林院です。にぎにぎしく記念写真に納まって解散お帰りの方を捕まえて写真に・・・こちらの外人さんがもう一度、撮らせてほしいと申し出られて・・・その結果!その後、各自のスマホで撮ってほしいと逆に依頼されておられました。笑いながら引き受けて写真を撮って帰って行かれました。アジサイに似ていますがヤブデマリです。以上で大原女時代行列を終わります。
2019.06.04
コメント(18)
-

新緑が清々しい寂光院!
恒例の大原女時代行列は寂光院を出発して三千院へ参拝後、勝林院まで歩かれます(正式名:魚山大原寺勝林院)行列参加の大原女さんや尼さんは事前に応募された一般の方です。大原女時代行列が出発されたので新緑の寂光院を拝観してから行列を追いかけることにしました。山門の手前にある茶室「孤雲」秀吉寄進の雪見灯篭四方正面の池参拝者は池の周りを歩けませんが四方から池を眺めても美しいと庵主さんのお話でした。池の奥に高さと角度が異なる三段の滝があり流れ落ちる音も異なっているそうです。水は池に流れ込んでいます。お話を聞いていて滝の写真を撮り忘れました。初秋のころ、池の周りに秋海棠(シュウカイドウ)が咲き可愛いピンクの花が美しいです。本堂前西側の庭園は平家物語の当時のままだそうです。池は汀(みぎわ)の池諸行無常の鐘建礼門院御庵室跡二年前に出かけた時のものですが庵跡の様子は建礼門院 庵跡寂光院横の大原西陵(高倉天皇・皇后徳子)行列を追いかけてみます。
2019.06.02
コメント(24)
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
-
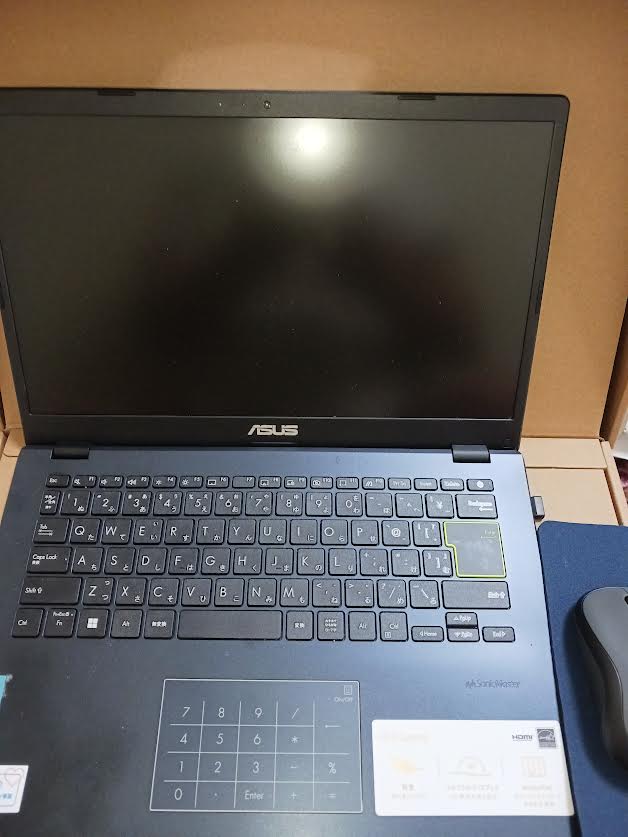
- 『眠らない大陸クロノス』について語…
- クロノスリハビリへの道リハビリ!!
- (2025-02-16 13:45:16)
-
-
-

- 模型やってる人、おいで!
- ドイツPkw.K1 キューベルワーゲン82…
- (2025-02-18 05:55:35)
-
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-







