2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
◆たらの芽ドロボー!!◆
来るだろうとは予想していた。しかし、こんなにひどいとは思わなかった。友人が見つけた緑のタラノメが根元からノコギリで切り倒されている。先端の芽を取るためだ。届かないところはノコギリで切っている。こういうことをするのは「ニンゲン」だけだ。あさましい。おまけに缶コーヒーの缶を捨てている。おそらく指紋が残っているだろう。これは刑事事件だ。勝手に人の所有地に入り、育てたタラノメをノコギリで倒すなんて。今年はおとなくしているが来年はそうはいかないぞ。ニンゲン用の罠を仕掛ける。おぃらは深く怒っている。怒りを共有してくださる方はクリックお願いします。こちらです。人気blogランキングへ
2005年04月30日
コメント(13)
-

◆桜・謎な茶◆
実は甘いものが苦手。それは、失敗をしたから。小学生の時だった。同級生の家に遊びに行った。同級生は「食べていいよ」と羊羹を出してくれた。出してくれたのはよかったんだけど、まるまる一本だったんだわ。それを、羊羹なんてあまり食べたことがなかったよ。むしゃむしゃ食べ始めた。バナナみたいに。羊羹の満腹は、キモチワルかった。それ以来甘いものが苦手。だから「桜餅」も苦手だった。でも葉は好きだったな。甘いものはいらない→葉だけ食べたいそんなふうに思うようになったのはいつからなんだろ。*オオヤマザクラとヤマザクラの違いがわかるか?と聞かれたら答えは「ぅうむ・・」だよ。更にカスミザクラとミネザクラと・・・そんなふうに疑問が重なると図鑑を眺めてもラビリンスに入ってしまう。はじめは、「あ。ミネザクラね。」と思ったんだ。でも良く見ると枝が違うピンクが違う。 明らかに別種なのだわ。初めは同種と思ってたけど。枝が違う。幹も違う。こうなってしまうと同定はお手上げだ。*花と芽の味は、枝がまっすぐな桜のほうがすっきりした感じがする。香りは枝の色が黒い桜があきらかに「濃い」。どちらも、ソメイヨシノほどのアクはない。先日の天麩羅パーティーで食べたけど油で揚げても香りがしっかり残っている。もしかするとこれはだよ。(笑)「枝ごと塩漬け謎な桜茶」にしてみようか。でも集めるのが大変。新芽の先に写真ぐらいの花しか咲かないから。*桜の種類はあまりにも多い。そして変種はそれぞれに味が違う。そうだ☆いろいろな桜で桜茶を作ったら「味なきき桜」を企画しようか。桜茶のもとなる幹の前に白磁の器に湧き水から湯を沸かして。それぞれに味わい花と語らう沈黙の半月。*少年の日の失敗を取り戻すにはあまりにも長い時間が必要だ。そして少年が確信した筈のものが実は偽りかもしれないと思ったとき、構築してしまった現在を処する手段はあまりにもリスクが大きい。でも私はここに帰る。この香りとこの味に。楽しみの日は短く、悩みの日は長い。でも悩みつづける楽しみもある。この二つの桜を調べるように。おまえの名前を教えておくれ。愛したいから。人気blogランキングへ
2005年04月29日
コメント(4)
-

◆アネモネは風に◆
金田一京助は、知里幸惠の墓の前で泣き続けたと言う。「アイヌ神謡集」は出版された。「アイヌ土人法」というものが最近までこの国にあった。この事実を忘れてはいけない。知里幸惠は、東京の金田一京助のところに行かなければ19歳の若さで死ぬこともなかったかも知れない。でもそれは彼女が選んだ道だった。北海道を訪れた宣教師はアイヌの人々の「悲惨」を見た。でも知里幸惠は教育のチャンスを得た。その聡明さは18歳で「アイヌ神謡集」を書き上げた日本語の文面を見ればわかる。彼女の中には2つのリズムが明解にある。日本語を書くときの彼女。そしてアイヌの「神謡」を歌う彼女。英語も楽々と話したのではなかろうか。学校に行く前にカミソリで腕の毛を剃る少女がこの国にいた。アイヌ語の神謡を聞くと短いフレーズがリズムに乗って繰り返される。鳥の歌のように。これは「ミニマムミュージック」だ。タンジェリンドリームとピンクフロイドを思い出したあなたは正しい。*私の母は俳句も好きだけど山野草も好きだった。どこかにでかけるときは、必ず根堀を持っていろいろな植物を庭に植えた。「イチヤクソウ」もね。もちろん特定の菌類と共生している植物は「里」では生きてはいけない。しかし、とある所で「すべての植物は菌類と共生している」と聞いた私はそうかもしれないと納得した。それは母親の沢山の失敗を見ていたから。*「山のものは山のもの。里のものは里のもの。」そんなふうに山野草を掘る母親にある人が語りかけたことがある。彼らは冬になると山をおりて町で働き、春になると山で耕作をするという。現代にもそんな人たちがいる。山の人は警戒心が強い。でもひとたび心を開けば聞かないことまで教えてくれる。これは「アネモネ」。和名は、「キクザキイチゲ」。本を開いてごらん。そして学名を読むとわかるよ。ギリシャ語では「アネモス」だ。方角という意味をもっている。そして方角とは風がおきる場所のこと。水亀さんが紹介して下さった、般若心経の最後にある「ぼーじそわか」と通じるこの不思議さはなんなんだろうね。3月14日のコメントを参考にしてみてね。*今、一国二制度な共産主義の「中国」の「富裕層」ではチベット犬を飼うのが流行っているらしい。蹂躙されたチベット難民たちは山と峰を越えインドに逃れた。しかし、そこで次々に倒れて死んでしまったという。原因は不明らしい。そんな話しを聞くと知里幸惠を思い出す。生き延びた人たちは今もダライ・ラマと共にいる。*山でしか生きられないものは山にあるべき。我が家はもう、「キクザキイチゲ」を掘ることはないだろう。それは小さな「歴史」から学んだ教訓だから。歴史に学ぶとは、「悲惨」を知ること。そして未来人に聞くこと。現代の構築にはそんな理念が必要だと思うよ。*図鑑を開いてみよう。イチリンソウもアネモネ。「食べられる」(笑)ニリンソウもアネモネ。アズマイチゲもアネモネ。ぜーんぶアネモネ。古い山野草の本を見ると、ニリンソウが食べられると教えてくれたのはアイヌの人らしいと書いてあった。アネモネが咲くところには岩魚がいる。一尺じゃないよ。二尺優にを越える大きさだ。もう一度、小刻みに繰り返される鳥の歌のような「神謡」を聞いてみよう。そこは風のふるさと。アネモネが咲くところ。クリックしてね!人気blogランキングへ
2005年04月28日
コメント(12)
-

◆頑固にイワガラミ◆
ある夏の日、ふと目に飛び込んで来た。「これは何なのだろう。」子供が小学校に入るとPTAの行事がいろいろ待っている。PTAは、なんとなく、ねっとりと絡むような感じの人が多そうな気がして避けていた。その日も山の神に「PTAの旅行ですからね。一日だけですからね。」と言われてしぶしぶ同行していた。でも、その一日旅行は楽しかったよ。でも、絡む人はいたけどね。(笑)ヤマアジサイのような白い花が枯れ木を登っている。山野草はほとんど頭に入っているつもりが、「樹木」となると全然知識が無かった。特徴を頭に入れて家に帰ってからすぐ調べてみた。そしたら「イワガラミ」だって。樹木にからんでいたんだけどね。つる性の樹木は日本海側に多いようだ。世界でも類をみないほどの豪雪地帯には様々な樹木が「蔓(つる)」作戦をとっている。なおかつ、この植物の一群を見ていて思うのは、木が倒れるか自分が倒れるかといった場面で、微妙なバランスを生態系の中でとっていること。絡まれた木はいつかは枯れる。枯れてもなおその木を利用しつづけて種を飛ばし、最後には木もろとも森の深みに倒れるのだろう。イワガラミもそうした植物群のひとつなんだけど、樹木はもちろんのこと、「岩」も利用してしまう。樹木を相手にするとラッキーだよ。なぜなら、日差しを樹木といっしょに受けて水は樹木が受けてしばらく枝においた雨をしっかり吸い取るから。ところが岩の上では水分の確保が難しい。でもあまり強くない日差し、そして湧き水などの条件がそろえばしっかり生きて行ける。太いイワガラミのようにはなれないけれど、そんな所に木が生えると、いつのまにやら、からみついていくのだろう。もちろん「食べられる」。山菜の図鑑に掲載されているのは少ないかもしれないけれど。庭に植えたくて、何年か前に挿し木してみようとしたけどうまくいかなかった。そして山を買ったら、あったよ。イワガラミ。 生で齧ると、はじめ香りが来てあとから苦味が来る。ふわっとした香りを逃さないで料理したいね。熱湯をかけて冷水に浸してもいいよ。そのあと、今日みたいにあたたかい春の日に細めの人肌のほどのあたたかさのうどんに散らしてもいいな。もちろん、「現場で天麩羅」が最高だけど。(笑)なんとなく風味が「湧き出す水」を思い出させてくれる。そんなさわやかさがある。それに「ユキノシタ科」だからね。何かの効能があるかも知れない。名前はいかにも頑固ジジイのコブラツイストなんだけど・・(笑)やさしい風にゆれる花だよ。一見はね。わが山は私を待っていたかのように次々と・・不思議です。あなたのことも待っているかもね。クリック!人気blogランキングへ
2005年04月27日
コメント(10)
-
◆コシアブラの秋◆
それは、もう15年以上前のことだろうと思う。山の中でマムシを捕まえるじぃさんと会った。左手で誘い、右足で頭を踏み楽々と首を押さえてしまう。聖書の創世記を思わせるその鮮やかさ。私は子供を連れていたので相手は警戒することなく、蛇の入ったペットボトルを渡してくれた。イザヤ書のように我が子は蛇と戯れたよ。いろいろと話しをするうちに、庭に植えたい木の話しになった。私はタラノメを植えたいと言ったら、彼は冬は西日であたたまり、夏は西日を塞ぐなら「コシアブラ」がいいと言う。私は図鑑でしか「コシアブラ」を知らなかった。*それからしばらくして、炭を焼く仙人からコシアブラを教わった。「ほれ。そこにある。」「どこに?」「オメの目の前。」高さ30cm程のコシアブラの若木だ。これかぁ。私はコシアブラを見つづけた。いくつかの春夏秋冬が過ぎた。山を渡り、刻んだ記憶をたよりに探してみたよ。結論から言えば、数十年前まで炭焼きをしていた山には絶対に無い。なぜならこれは「役に立たない」木だから。里山は「役にたつ山」。つまり、身近で利用できる山のこと。炭を焼くため、柴を取るため、伐採して更新してを繰り返している山のこと。または、子孫を思い木を育成するための山のこと。コシアブラは仲間はずれだった。今はタラノメよりもこっちが幻の山菜かもしれないけど、昔は現金収入の対象ではなかった。かつて薪炭の基地だった我が山にはこれが無かった。捜したよ。*コシアブラをみつけた。ヤマウドは夏に花をみつけておくでしょ。それと同じ。この木は秋に探す。紅葉は薄緑だ。すぐわかる。冬には閉鎖される山岳道路を走って、見晴らしのよいところで秋のツンとした空気を吸う。モミジやカエデが葉を落とした後、雪を予言するかのようにコシアブラの葉は白い。そして山地には、ぼつぼつと絵を描いたかのようにコシアブラの大群落がある。役にたたなかった筈の場所にこれほどまでに。そこは知っている人だけが知っている。*コシアブラの群落を見ていると不思議に思う。なぜあそこは平らな土地なのだろう。なぜ落葉広葉樹の極相林にコシアブラだけがあるのだろう。「鳥と木地師だ。」ひらめいたよ。まちがいない。かつて木地師は山を渡り、よい土地でその地の木を切り漆工芸の木地を作った。木地師が木を切った場所は、木が切りやすい場所だ。だから平らな土地だ。そして木地師が去った後、鳥たちがコシアブラの種を蒔く。鳥たちが運ぶのはコシアブラだけではなかったろうけどコシアブラは他の陽樹よりちょっと背が高い。コシアブラの戦略は第一段階を成功させた。そして木地師のいた跡に群落を作ることに成功したんだ。でもコシアブラの戦略はまだ終わっていない。*私はコシアブラを捜していた。山に植えたからったからね。そしたら、いつのまにか我が山に来ていた。まだ発芽して2年ぐらいだろう。若い木だ。この木は大木になるまで、大切に育てよう。おまえは来たくてここにいるんだからね。*春は北上している。でも、もうひとつの春は1000mを遥かに越える山を駆け上がっている。「待ってるよ。」高山の清浄な大気の中でコシアブラは言う。行くよ。私は言う。かつて木地師がいた場所へ。人気blogランキングへ
2005年04月26日
コメント(7)
-

◆絶滅危惧種をパクッ!◆
山を買って2年目の春に、気がついた。なんだろう・・くんくん。。足元から匂いがする。なんだこれわ・・しかし、精神状態がめちゃくちゃだった私はそのまま忘れてしまった。私の心はどうすれば決算書が形になるか、そればかりだったからね。本来は逆なんだけど。監査法人とあれこれしているうちに匂いを忘れてしまった。3年目の春、また匂いがする。足元をみたらナンダコレワ?会社を辞めた私は足しげく通うようになって初めて花を見た。ネギの花を知ってるかなぁ。あのネギの花のひとつだけが、紫色して地上に、「ぽちっ」と咲く。気がつくとクリの木の下一面にあったよ。「ヒメニラ」 写真はつぼみだから花は想像するかネットでググッてみてね。大きさはスギの葉から大体わかるでしょ。とても小さい。ところが群落をつくると歩いてるとすごい匂いだ。ギョウジャニンニクとも違うしノビルとも違う。その数、30坪程の一面。千本は優にあるだろう。環境省のレッドデータな植物だけど、目の前にあった。これは土地所有者の特権でしょっ。(笑)もちろんそのまま食べたよ。ぱく!ぱふぅ~ん。何といいますか。あの。ナニですよ。これは。強い香りは醤油と豆板醤に刻んで混ぜるとかえって強くなります。野菜のニラよりも凝縮されたこの香り。これは、一夜限りの禁断の炭火焼肉用です。もちろんレッドデータな植物を食べることを推奨するものではありません。たまたまね。山にあったからね。おぃらが山を買ってなかったらどうなってたことか。ま。ヒメニラ君。もちつもたれつ。我が子孫まで、久しくおつきあいさせてくださいましっ。小さな球根も、ぱくっ。ぱふぅ~ん。「こもれび広場」の隣に「ヒメニラ畑」か。それもいいな。そのうち七輪を持っていって焼肉するべ。ぱく!クリックしてね!人気blogランキングへ
2005年04月25日
コメント(7)
-

◆誠実なタラノメ◆
山を買った翌年の春、まだつきあいはじめたばかりの彼は、私に対して敬語を使うべきかどうしようか、半分悩む口ぶりで電話をかけてきた。「山を見せて欲しいんだが・・」「ぃいよ。」国家公務員で事務職である彼の愛読書は「現代農業」だった。私は爆笑してしまった。彼はいろいろ試してみたくて100坪ほどの農地を借りている。彼の実家が山間地で農業をしていると聞いて納得した。ある日、自己紹介欄に「顰蹙買うがなぁ。」と言いつつ趣味に「食えない農業」と書いた。でも彼はいつも何かを探している。私が数千個の元祖チョコエッグを見せたら目が爛々と光った。彼は菓子問屋と直接取引きをはじめた。私がチェンソーを買ったら、彼もチェンソーを買った。そして今日は草刈機を持って我が山に来た。私はまだ草刈機を持っていない。初めて私の山を訪れた時、彼は「7種類か8種類のタラノメがある。」と言った。タラノメの優良品種を長いこと捜していた事を初めて知った。伐採された跡地だったから、まだどのタラノメも高さ1メートル程で小さかった。彼は私の山で優良品種を見つけたらしい。2年が過ぎた。彼と私はもう仲良しだ。「こらんしょ。」(来てごらん)「いぐ。」(行ってみる)私たちはそこで意外な様子を見た。腰の高さ程のところで、タラノメの芽がきれいに「食われて」いる。「なんだべ?」「なんだべなぁ?」サルか、カモシカか。3年が過ぎた。食われなかったタラノメは堂々とした大きさになった。1年に1メートルの成長速度だ。やはり腰ほどの高さで食われ続けている芽がある。私たちは糞をみつけた。「ウサギだ。」てことは。ここが雪の高さかぁ。彼は「来年はすごいぞ。」と予言した。そして今日。「これなんだよ。これ。」彼はタラノメを指差した。「葉がちょっと開いてもトゲがない。そして緑色で食うと苦味が全然ない。」なぁるほど。これかぁ。「掘らせてくれ。」彼は根を掘りはじめた。木を殺さずに、根を分けてもらうのだという。その根を植えると品種が確保できるそうだ。彼は、「どうも、どうも。」とニコニコ顔で山を降りてきた。「来週には食えないやつ。」ポケットからぼろぼろと出てくる食べごろのタラノメ。「好きなだけ取っていいってキモチいいなぁ。(笑)」・・そうだよ。ここは「ネオ・エデン」だからね。不思議なんだが・・と彼は続ける。普通「緑のタラノメ」は遅いんだが、この山は出るのが早い。それはね。タラノメがあんたを呼んでるから。なぁんて言わなかったよ。彼はその木を覚えているらしい。たぶん、タラノメもあんたを覚えているよ。今日は天麩羅パーティーだから子供たちも連れて来た。剪定ハサミで枝を引き寄せる道具をぱちぱちと作ってやったら、子供たちは15分もしないうちに食べきれないほどのタラノメを取ってきた。割り箸はマッチ棒でないよ。左はハリギリ。中央はスーパーでは手に入らない「あたしんち」のタラノメ。でっかいでしょ。(笑) これが本当の「鱈乃芽」。小麦粉持って、油を持って山に行ったよ。ガソリンストーブで油があたたまったら、じゅわじゅわっ!キクロモジは枝を持って衣をつけたら油にじゅわっ!。おお。うまぃ~!取りたて即揚げの天麩羅パーティー。ヤマザクラは桜の葉の香りがふんわり。コナラがうまい~!。ホオの芽もじゅわ。コブシの花芽もじゅわ。そこにカタクリの花。うぅん~甘い~! そしてカエデも、何の芽かわからないけどとりあえずじゅわ!じゅわっ。天麩羅パーティーに参加したいかぁ(笑)。クリックしてね。人気blogランキングへ!
2005年04月24日
コメント(4)
-

◆うこぎと白ごはん◆
桜を散らす雨が降ったらもう大変!じぃさんの所に行ってみたよ。「こごみ、どうだぃ。」「もう、一気に開いちまったよ。」「なにぃ~!」おいしい春はたちまち過ぎて行く。急がないと、あれもこれも。「計画的に念を入れて」過ごそうか。でもちょっと待って。今年でなくとも来年があるさ。またその次の年も。ある人は言ったよ。「山は逃げて行かない。」確かに。忘れない限りね。里には忘れ去られたものもある。この家の主は、かつて毎年春に芽を摘んでいたのだろう。そんな樹形をしている。でも、摘むことをやめてしまったようだ。 「ウコギのご飯がたべてみたい。」そんな事を少年の私は母親に言ったことがある。でも、我が家にウコギはなかった。母親の実家にはあったよ。大きなケヤキがある「屋敷森」には必ずといってよいほどある。フクロウ類を捜しをしているとふと気がつくんだよ。ウコギの垣根を大切にしている家もあるって。そういう家では指と枝がつくった垣根になっている。20年ほど前の春の日に、ウコギを摘んだ。ゆでて刻んで塩で揉んで、たきたてのごはんに混ぜた。いい香りだったよ。でも父親は食べなかった。そのとき、わかった。「ウコギごはん」が家に無い理由。*東京から友人が来たとき、刻んで味噌に混ぜて焼いたよ。炭火をおこして。冬を越えたモクレンの葉の上で。味噌とウコギの香りがふぁぁ~ん。それを縄で縛れる豆腐に乗せて。ぱくっ!イタ飯にもあうよ。焼く料理ににも、パスタにもね。おっと、でかけなきゃ。続きはまたね。人気blogランキングへ
2005年04月23日
コメント(9)
-
◆タンポポの味◆
「全部食べられる」と本には書いてある。先日の毎日新聞にセイヨウタンポポの由来について書かれていたけど、アスファルトの亀裂に咲くセイヨウタンポポは本当にセイヨウタンポポなのかは疑わしい。「教えてgoo」で調べてごらん。図鑑で「種」と分類して学名をつけてしまったものたちが、実はなだらかなDNAを持っているのかもしれないよ。外見から様々に名前をつけられたタンポポたち。セイヨウタンポポは在来種と雑種を構成しているらしい。植物形態学は正しくタンポポを分類しているのだろうか。むしろ植物味覚分類学(爆)が、正しいかも。「セイヨウタンポポ」は食物として日本に持ち込まれた。持ち込んだ人も特定されているらしい。明治政府に破格の条件で日本に呼ばれた学者が、海を越えてでも持っていきたかったその味は・・葉を食べてみたよ。 ぱく。*ぉお。この味は。。「ベニバナの若い芽」そっくり!。実は、ベニバナも食べたんだ。おととしね。ぱくっと。あちこち、食べてみたよ。ぱく。そうしたら・・場所と外見とでだいぶ味が違う。このタンポポの葉の味の違いは、「好み」に左右されるし「家の伝統の味」になる可能性がある。*半日陰で、ふさふさとしたタンポポを見つけた。ぱくっ。うまい。こういうタンポポはプランターに引き上げて、株分けして「あたしんち味」にするとよいですね。日本に持ち込まれたタンポポも実は「家伝の味」だったのかもね。*オリーブオイルはエキストラバージンのほうがいい。白胡椒と、赤と白のワインビネガーを好みで混ぜる・・が。をを。うちには、白濁して飲み忘れて透明になった「米酢」がありました。米酢味噌マヨネーズに交雑タンポポか・・パンにはさんで。。ぱく。根はゴボウサラダのように。花は・・菊のように?人気blogランキングへ
2005年04月22日
コメント(9)
-

◆桜色の雪の下で◆
私は、病院で生まれていない。萱葺き屋根の家で生まれた。幼い記憶をたどれば、蚕を飼っていた家の間取りを思い出すことができる。祖母が死んだその部屋も。土間が3つある家だった。私は言葉を覚えた日を覚えていない。ヘレンケラーのように記録されているわけでもない。私が生まれた母親の実家には気づいたときには咲いていた。その花の名は「ユキノシタ」。*ある日、誰かがこの葉を揉んで、肌に貼り付けてくれた。 それは何のためでだったか記憶にはない。しかし、肌に貼り付けられた葉は記憶になった。今、ニコチンパッチを安心して貼っているのもその記憶のせいなのかもしれない。時折、「山の人」は里に蛇を売りに来た。幼い私は買われたマムシが焼酎に漬けられ一升瓶の中で長く伸びるのを見ていた。それが何のためなのかも知らない少年は、瓶の中で息絶え沈むマムシを眺めていた。どこから来たのだろう。*蝶を捜して山形県の深山に入った時のこと。轟々と流れるゆきどけ水のほとりにユキノシタは群生していた。まだ融けていない雪の上にヤマカガシが現れた。私が生まれた家にあったユキノシタの故郷は、そんな幽谷だった。冬にあっても表は緑で裏は紫色の葉を古代人は肌にあてたのだろう。そして蛇を売る山の人は里に運んできたのかもしれない。伝えられた知恵をもって。*雨があがった。桜はつぼみから咲くときに「気」を吸うのだろう。そして風が吹いて止んだ。花は散りはじめる。一昨年も去年もそうだった。来年の夕暮れも雨の後に桜が散る。樹下に立つ女(ひと)は、夕暮れに散る花の「気」を全身に浴びる。彼女は今も花の下にいる。そして湯浴みのあと、肌から吸った「気」を発散さる。私は笑ってしまった。しかし彼女は真剣だった。花は彼女の肌の色と心の色とを変えてしまった。一言が忘れられない。その後のことも。「魔性の女と呼ばれてみたいわ。。」クリック!!人気blogランキングへ
2005年04月21日
コメント(12)
-

◆傘貼りヤブレガサ◆
NHKの夕方のラジオで「フリーター」問題をとりあげている。聞いていると解説者よりも投稿者の方が「雇用」「労働」「生きがい」について多様な地平を開いているような気がする。息子の通っていたPTAの監査を引き受けていたけど監査して驚いた。13年間PTAに雇用され、勤めていた人がいた。彼女は今年でやめたという。でも雇用形態は毎年解雇で毎年雇用だったんだけどね。そんな雇用が学校の中にあったのだわ。*ふと思えば「役所」というところは「使い捨て雇用」の温床でもある。そして学校もね。ドストエフスキーを思い出したのは「罪と罰」ではないよ。「貧しき人々」だ。*私自身の中にこんな言葉があるとは思わなかったよ。「労働とは能力の切り売りである。」「経営とは労働力の搾取である。」そしてわが内なるホモ・ルーデンスは言う。「労働とは対価を得る遊びである。」しかし、ラジオからは縦割り発言に対して痛烈な言葉もあった。「なんとかして月20万円を得たい。」「行政は若年層にしか向いていないがこのままだと国が老化する。」*東京大学労働組合はさすがに方向性を打ち出している。よい教授はよい教師とは限らないからね。そして私学はあきらかに教授時間数において臨時講師から時間を搾取している。東京大学の臨時講師の時給は何をもとにどのように決定されているのだろ。そしてかつて結婚、出産によって能力を放棄せよと迫った社会は困惑している。沢山の無能な正社員よりも「有能な臨時雇用者」がなだれこんできたから。亀の背を追う「モモ」は笑うかもしれない。時間泥棒の部屋で。 ヤブレガサとトリカブトの違いは何か。それは雇用者が社会保障に関する経費を負担するか否か。企業に問う問題ではなく役所が、特に厚生労働省が自らに「使い捨て労働を」問い直してみなさい。そして未来への過程の中でフリーターをなぜいまさら問題視するのか。昔から結婚退職を迫られた人たちはフリーターの道を選んだのだし、そこにバブル崩壊で若年層が浮かび上がっただけのこと。*ヤブレガサは「苦い」。でもね。焼いたチーズと合うんだ不思議にネ。雨が降ってきたよ。静かな雨だ。雨は木の芽を膨らませる。床屋さんは「雨の日は眠る人が多いよ。」そんな話しもしたっけ。かわいらしすぎるヤブレガサ。猫は死ぬほど眠いかも。人気blogランキングへ
2005年04月20日
コメント(11)
-

◆大痛鳥・けほっ◆
「予防医療に保険は利かないのよ。病気になって初めて保険の対象になるの。今の医療制度は絶対に間違ってる!」薬剤師の彼女は禁煙パッチが高価なことが話題になったとき、怒りの目をしてきっぱり言いました。「んでもよぉ。山間地で安定した収入が得られる作物ってタバコだぞ。」農林にかかわりある国家公務員の彼は言いました。「なやましぃなぁ。」「んだなぁ。」そんなことが仲間たちで話題なったことがありました。それで。実は。。おぃら、ヘビースモーカーだったんです。それが肺炎おこしてから禁煙パッチをぺたんと貼られて。「ケイゾク」してます。順調です。(笑)なんでこんな話題になるかって?タバコの代用品だったんだって。ためしたことないけど。「野草の料理」甘糟幸子・中公文庫に紹介されている。 その名は「オオイタドリ」。山菜の本を何冊か持っているけど、どの本も「ポキンと折って皮をむいてまるかじり」をすすめています。少年の私は確かにまるかじりをしていました。何の味に似てますか?と聞かれても「イタドリの味です。」としかいいようがありません。野鳥大好きさんの問題にも登場しましたけど、「オオイタドリ」私には忘れられない思い出があります。そこは、日本海に浮かぶ「飛島」です。飛島はとても小さな島ですが縄文時代から人が住んでいたようです。そして水を確保するための歴史の跡が残っています。大きなタブの木。水源地。佐々木勉という友人が島を巡り歩きながら言った一言。「この島は煮炊きをするときにイタドリを使ったんだってよ。小さな島だからできるだけ木を切らずに水源を確保するためなんだそうだ。」その話しは本当であったかどうか、死んだ彼に確認する方法はありません。もしもう一度飛島に行くチャンスがあったら聞いてみようと思っています。家を改築するときに薪ストーブを置くか否かの参考にするためにね。イタドリは高山では「メイゲツソウ」と名を変えると山頂に向かう小学生の私は聞きました。メイゲツソウの種を平地で蒔いたらイタドリだったとか。でも、それを検証したことはありません。*うつ病ひどかったとき、河原で膝を抱え、小学生の時に登った白い山を仰いで「あの山にはもう登れない。」と暗澹としたよどみにいた私を思い出します。しかし、今は思います。一歩ずつ、一歩ずつ。休みながらだったら山頂に立てるかも知れないと。オオイタドリは薄い輪切りにして、しっかりとした春のシイタケのマリネにさりげなく混ぜ込むと「うふふ」だろうと思います。オイカワを油でカリッと揚げてマリネ風にしてそこに・・でも、これは「釣れたら」の話しですけどね。でも友人は言うのです。「ゆでてゴマあえもおいしいんだってよ。」それは試したことがありません。「ならばエゴマとあわせたらどんな味になるだろうねぇ。」「エゴマってアレだよ。「じゅうねん」だよ。」「ためしてみるか。」「種を蒔くかぃ。」「来年かよ。」「・・・エゴマならあるよ。」「!!」仲間との話題は尽きません。そんなとき、ふと遠い白い山を見て思うのです。国立公園からちょっと外れたあの山頂で。「メイゲツソウ、齧ってみようか。」「けほっ。」としなくなった私には、変化が訪れつつあるようです。禁煙したい理由、もうひとつあるんだけど。ヒ・ミ・ツ。(笑)クリック!人気blogランキングへ
2005年04月19日
コメント(13)
-

◆シンビジウムの食べ方◆
毎年この花を見ると考え込んでしまう。今年はどうして食べようか。食べられるのを知ったのは、中学生の時の図書館だったよ。そして、ラテン語の学名が「シンビジウム」と知ったのは高校生の時だった。「シプリペジウム」はクマガイソウ。次々と学名を覚えて行った。「デンドロビウム」は元禄のの古典園芸セッコクだ。そして春蘭も古典園芸で一部の人たちに愛されている。おぃらも「イワヒバ」こっそり集めているんだけどね。(笑)でも、鉢に生まれ鉢に育った彼等はこの先どうなることやら。 小学校の遠足で、この花を見つけた誰かがいた。その不思議な形。そして花を見つけた場所は心に刻み込まれた。少年の私は何度も春になるたびに、この花を見るために遠足で行った所を訪ねた。食べられる事を知ったとき、塩水ゆでにして、そのまま食べてみた。「う・ま・い。」ゆでるときの塩加減を調節してみたよ。ちょっと濃い目の塩がいい。そして、ピンクにしたいときは酢を少し入れるんだ。塩漬けは「蘭茶」でしらべてごらん。お手本は沢山あるよ。でも悩むんだよね。春の野にある気品を損なわずに香りも壊さずにどうしようか・・。ちいさな椀がいいだろう。若布の株の一切れとあわせようか。それともハマグリの椀に小さなミツバとあわせようか。硬く締まった春シイタケのうすぎりにしようか。ベーコンと岩塩のスープもいいな。昆布ダシで炊いた粥に置いてもいいな。温サラダにもできるけど菜の花とはちょっと出会いがよくないようだ。菜の花は土の香りがするけれど、シュンランは「風の香り」がするからね。土を掘って、真っ白な山百合の芽をみつけよう。タニシの汁とあうかもしれない。春が過ぎないうちに。塩は・・ どこの塩にしようか。ガンジーのように海をめざそう。花が咲いているうちに。海草を焼いて舐めてみよう。そして海が汚れていたら、悲しみのページを開こう。淡水と海水が出会う場所で。香りも味も舌ざわりも繊細。一年に一輪だけいただきます。クリック!人気blogランキングへ
2005年04月18日
コメント(11)
-

◆聖なる所◆
ライアル・ワトソンは著書の中で南の島のある場所を紹介している。島の宗教はイスラム教だけど、人々は昔からの場所をしっているらしい。ある日、ワトソンが「いやな気分」になった。そのとき、島民から「その場所」を教えてもらったというんだ。場所は海の近くの洞窟だった。しばらくそこで過ごした彼は、すっきりして帰って来た。「聖なる所」それは、癒される場所。「里山を買おう!」で岩をくりぬいた祠を紹介したよね。それがこれ。この隣には、曲線の屋根と本体と土台でできた、今でも神社の境内でよくみかけるようなものがある。でも、これは違う。明らかに古い。そして、この作者は岩に四角の立体をくり抜くための確かな技術を持っている。この周りには大きな石灰岩がいくつかころがっている。そしてその中心にこれがある。この祠の前だけが「特別な場所」。苔むした祠の前で深呼吸をすると心が落ち着く。何故だろう。*少年の頃から山を歩いていたけど、じいさん、ばあさんに教えられた場所は「特別」だった。家のこの場所にこれを置いて・・という風水とは全く違う。まして、雑誌についてくるシールの風水なんかじゃない。鳥や昆虫と接している人は思い出すかもしれない。「あの場所」。毎年、ツバメは「あの場所」に集まってから南に渡る。昆虫は「あの場所」にひきつけられるように集合する。そして「鷹柱」の場所は毎年決まっている。どうしてなんだろ。いろいろ理由は「言葉」にできるかも知れない。しかし、神秘の扉は「特別な場所」に立っている。少年の私はじいさんに連れられて水が湧き出す水源地に行った。それは小学生になる前だったと思う。不思議な力を感じた。高校生の時、「畏れ」という言葉を知った。私の中で「畏れ」という言葉は不思議な場所とシンクロした。*森林セラピーなど、マスコミでも紹介されるようになったけど、また行政は「どんなデザインでナニを作ってどのような効果が期待できるか。」など「御用学者」を使ってプランを作るかもしれない。しかし、形をつくってもどうしようもない。更に森林の樹木や水系と人間とのかかわりをデータにしようとすれば膨大な作業になる。古代人の感覚のすばらしさに学ぼう。そして、里山の老人は少年に伝えるかもしれない。「聖なる場所の探しかた」私が買った山の隣にこんな場所があるとは知らなかった。導いてくれたのは幼いカモシカだった。*午前9時に家を出て、隣の土地だけど、この祠の周りの倒木をチェンソーでぶつ切りにしてかたずけた。腐った杉の木の根を掘り起こしたらガラスのコップが出てきた。何十年前のものなのか。湧き水で洗って祠に置いた。誰かが祈るときのために。*天気予報は晴れなのに雨がぱらついてきた。わが山をみおろせば、タラの芽が数百本。来週には、赤ちゃんの手のひらぐらいのタラの芽が大豊作になるだろう。ウサギにもカモシカにも齧られず、大きくなったもんだ。炭焼き窯の跡にもタラの芽が出ていた。そういえば、この窯の場所、どうして決めたんだろう。空を仰ぎ鳥に風を聞き、足元の水脈に地下の巌を知る人。彼がいたのだろう。私は今、ようやく祠の作者である彼になれるかも知れないと思う。森の中で目を閉じる。鳥の声、蟲の羽音、樹木のざわめき、苔の触感。彼は言葉にはしないかも知れない。しかし、クリスチャンの私は言うかもしれない。「聖なる所。それは石の枕がある所。」*この国はかつて「やおよろずの神」を滅ぼそうとした。たしかに都市や町にあった神々は明治政府によって滅ぼされたかもしれない。しかし、山奥には手が届かなかったようだ。この祠は威厳と大地の気を集めて私を呼んだ。そして私はいつのまにか呼ばれていた。これは一神教の「人格神」とは全く違う異質なものだ。古代人はその「名」を知っていただろう。現代人の私には伝えられなかった、聖なる場所につけられた「大切な名前」を。ある日私は誰かをここに連れて来るかもしれない。「助けて」と呼ばれたそのときに。雨は上がった。光が森に帰ってきた。深呼吸しよう!クリック!人気blogランキングへ
2005年04月17日
コメント(17)
-

◆マロニエな森◆
「おーぃ。こげす、どすたーぃ。」(あたくしの依頼したこけしの進捗状況は如何でせう。)「それが、がおっちまってよぉ~。」(体調芳しくなく遅れて御座る。)弥治郎の彼に電話しました。どうも体調すぐれず、進んでないようです。一昨日は、はるばる福島県まで行ってまたチェンソーで梨畑の整理をさせてもらいながら35本ほど、よさそうな木を手に入れたそうです。こけし工人もつらいよ。今日、顔をだしたら、本当につらそうな顔をしていました。「入院して点滴すべし。(笑)」お互い、腹の底はわかってますからね。「明日、いや、午後になればだいじょぶだぁ。」「体温計ったのがぃ。」「ほだごど、しねぇ。」(左様な事は致し間敷ク候)ま。頑固です。再会を約して後にしました。途中、崖を見上げれば、ぉお。ザイルでもないと取れない水のしたたる所にヤマワサビ。さぞかし根茎は太っていることでしょう。明日は、おぃらの山のヤマワサビ調べるべ。*別れたあと、まっすぐ帰るのもナニなので、あちこち寄り道しました。ま、寄り道っていっても藪こぎですが。某有名観光名所から山に入ること15分。ぉお。サルナシだぁ。太い。おぃらの足より太いサルナシみつけたぁ。アントニオ猪木のコブラツイストよりも卍固めよりも強く木にからみついてます。ナタで、途中の枝をバッと落としたら。こぼれおちるサルナシの滴。あーんと口をあけてしばし、あーんとして、したたりおちる滴をごっくんしました。山の中だと誰もいないので、口をあーんとしてても。(笑)うまかったよ。サルナシの滴。*そこからまたてくてく歩いたら。うにゃ。足元にセリバオウレン。たしか薬草だったよな。とみれば。うぁ。数百株ありましたぁ。これわすごい。オウレンを踏まないように歩いて行ったら。おお。 冬を越えたトチの実ではありませんか。フキノトウもでかいが、この実もでかい。木の幹の直径は50cmほどあります。たしか、小学校の教科書に「モチモチの木」ってあったでしょ。それがこのトチの木。福島県、奥会津の「大内宿」に秋に行ったとき、水路であく抜きしてたっけ。すごい量だった。最近仙台市内でも街路樹にしているよね。ヨーロッパだと、パリでしょ。だって「マロニエ」って「セイヨウトチノキ」だから。いい蜂蜜がとれるんだよ。種を手にとって重さを確かめた。しっかりしている。庭で芽吹きさせて山に植えるべ。その下にニホンミツバチの巣箱を置こう。明日はよい天気らしい。いよいよ「こもれび広場」の準備をはじめるよ。チェンソー点検。よーし!!ブナの木の芽を齧ったらあっさり味だったよ。人気blogランキングへ
2005年04月16日
コメント(8)
-

◆樹木パステル天麩羅◆
ときおり「けほっ!」としながら、山道を歩いては休み、休んでは歩き、水を飲んで、乾燥したひだまりで横になって、また歩いたよ。今の森の木の芽は、あれも齧ってみよう。これはどうかな・・だよ。コナラを齧ったら。うげ苦。でも後に栗の香りが残る。これは天麩羅になるわ。次、ガマズミ。うぅむ。不合格。・・ソメイヨシノは・・ほのかに桜の香り。でも苦味が強すぎるなぁ。おお。マタタビ科のサルナシの芽だ。けっこういけるわ。(笑)ぜ~んぶ生で齧ってるから「油」に会ったらどうかな。縄文にもなくて弥生にも万葉にもなかったもの。それは「油」。油と木の芽の出会いはすばらしいよ。今日の天麩羅5品が決まりましたぁ~。コンセプトは「うすぎぬ衣」です。◆イロハカエデの芽 3寸ほどの枝は、ちょっと赤みがある。 枝に葉がついたまま衣をつけて二度あげ。 ぉお。しっかりしたメイプルの味です。 枝を手に持ってポリポリ食べます。ウマイです。◆ミツバアケビの芽 冬を越えた枝が水を吸い上げてよい芽を出しています。 蔓ごと揚げます。じゅわじゅわっ。 塩をパラパラかけて。 ほぉ。くせがありませんねぇ。 ◆オオヤマザクラの芽 ソメイヨシノは苦くて味も濃いけど、これはあっさりしてる。 へー。枝ごと揚げて、むしゃむしゃ。 ヤマザクラの方が苦いと思ってた。これは、「新・発・見」 口の中にほんのりひろがるサクラの葉の香り。 よいですねぇ。 ◆ハリギリの芽 樹木の山菜といえばタラノメが出回ってるけど、次の勝負はハリギリかも。 でも、コシアブラかも。(笑) これはね。あるところにはいっぱいあるの。 そこはね。おぃらの山。10メートル以上の大木になるの。(笑) 枝ごと天麩羅ってわけにはいかないね。 「やみつき」になる味。ぉお。樹木菜。◆ホオの芽 ホウ葉味噌はすっかり有名だけど。 うふっ。軽くゆがいて、味噌をちびっと塗ってから衣をつけるのです。 「この味なんですかぁ~」と聞かれても、 そこに御座ゐますと庭をさす。 ちっとキザかな。(笑)さてち。食っちまったぞ。うまかったぞ。 おっと忘れた。仕上げはこれだよ。◆クロモジ茶 昨日、c.m.さんに教えてもらったとおり作ってみたよ。樹木パステル天麩羅の口をまたふんわり包んでくれる。ふぁぁあ~って 心がパステルカラーに染まるよ。これは。碧山窟の樹木パステル天麩羅、食べたいかぁ~。食べたかったらクリックしてね。人気blogランキングへ
2005年04月15日
コメント(16)
-

◆カケスの羽◆
「ぃいですねぇ。あと3日だけ抗生物質を飲んで下さい。」おぉ、私の肺炎は完治に向かったようです。仕事先には電話しておきました。「医師に安静にするように言われたので、明日まで休んで、月曜から出勤しますぅ~。」こうなったら☆山へ行こう! マイ・マウンテン。*雪解けが沢の水を濁流にしている。この水が土地を豊かにした。沢の濁流はあらゆる音を消して、頑固で好奇心旺盛な少年の日の私が現れる。さてと、ぼちぼち登りはじめたら。雪が秋の枯れ草を押しつぶしている。ウサギが木の芽を齧ったあとが高さ1.5mぐらい。病み上がりだからね。休みながら途中まで登った。遠くの白い山が水色に光る。サシバが来た。オオタカも鳴いてる。おとしものを見つけたよ。 人が絵を描くときは植物系の染料、鉱物系の顔料を使うけれど、昆虫の光る羽や鳥の羽は「構造色」だ。これはカケスの羽。ぴかぴか光ってとても綺麗だ。そう思う私。そう思うことを不思議に思う私。携帯電話に透明マニュキュアで貼り付けようかと思う私。私の中には頑固な少年の私だけでなく、いろいろな私がいる。それはマニュアル化できない不安定な私でもある。でも、こういう羽を拾って「きれいでしょっ。」て、人に見せたがる人恋しがりの私が一番好きなのかもしれない。「きれいでしょ。カケスの羽。」休み休み、途中まで登ったところでダウン。鳥の声に耳をすませたら、沢の音で頭がまっしろになった。「ピッツ、ピィー。」まっしろな頭に響く、サシバの声。ありがとう。おぃらは生きているよ。クリックしてね。人気blogランキングへ。
2005年04月14日
コメント(12)
-

◆記憶の赤い実◆?◆
「この味なっだっけ・・?」。もう6年以上前のことだけど高級中華料理店で、以前に勤めていた会社の人たちと営業会議の打ち上げをした時のことだった。前菜から始まって、いろいろな料理が赤い回転テーブルに並べられていく中で、黄金のフカヒレスープが一人ずつ配膳されたときのこと。ゆらゆらとしたフカヒレスープに赤い実が浮いていた。そして緑の葉も。ひとくち、その赤い実を食べたとき・・「なんだっけ・・この味。」その後は皆さん、愚痴こぼしとごますりしながら飲んで食っての大騒ぎだから思い出せなかった。何だっけ、あの赤い実・・。思い出せなかった。黄金スープに浮かぶ赤い実。*3日ぐらいして、あっ!と思い出した。あれは生の「クコの実だ!」。思い出すのに時間がかかっただけに、あの黄金のフカヒレスープとクコの実は忘れられない味になった。「少年の日」の味は、あの盆栽が好きなじぃさんの庭を思い出させてくれたよ。そのじぃさんはもう亡くなって、家の跡はコインランドリーになっている。コインランドリーの一番奥に行くと、この場所だなってわかるよ。そこには、じぃさんの話しを聞きながら、芽ぶきはじめた広葉樹の盆栽を眺めている少年の私がいる。カエデ、ニレ、ケヤキ、ハゼ・・盆栽の奥にあったあの赤い実をつける小さな木。それが「クコ」だった。*昔は薬効があるとかでブームになったこともあったらしい。でも、じぃさんはそんなこと、一言も言わなかった。「食ってみな・・。」差し出されるままに赤い実をそのまま食べた。*フカヒレスープを食べてから、自分の庭にも植えてみたよ。ウドンコ病に弱いんだけど、竹酢液を使ったら効果があったよ。でも、いつのまにか抜かれて焼かれていたけどね。父にね。もう、植えなくてもいいや。そんなことを思ったのは子供の頃は行けなかった所に何箇所も自生している場所を見つけたから。 クコの緑の芽はおいしいよ。アクがないし素直な味だ。軽くいためたあと「塩焼きそば」に入れると合うよこれは。おこのみ焼きに入れたりクコチャーハンにしたり、アイデア次第だね。応用できる幅は広いよ。マカロニ・クコ・サラダ、クコのはるさめスープ、かきあげにしてもいい。おお、木の芽だ。という味がなんともいえない。そうそう。味噌汁にもね。安心しておすすめできる「樹木菜」。*雨が降ってきた。木々の芽がいっせいに萌えだした。昨日の山の色、今日の朝の山の色、今の色。勢いをもって、刻々と変わっていく。太い筆で絵の具を塗るように。*採集できる場所は何箇所も見つけたけど、また庭に植えよう。赤い実をフカヒレだけじゃなく、いろいろなスープに浮かべてみたいから。ピザのトッピングにも使ってみたいから。この緑の芽を食べるチャンスを逃したくないからね。一雨で一気に伸びるんだ。クコは挿し木で簡単に増えるよ。そして強い。そういえば、あのじぃさんの家にはクコの盆栽もあったっけ。盆栽を愛する人に引き取られて、今も生きているかもしれない。会ってみたいよ。あの木に。縁側に座って聞いた言葉を、何か大切な言葉を、忘れかけた言葉を思い出させてくれるような気がする。とても身近な「樹木菜」、チャンスがあったら食べてみてね。人気blogランキングへ
2005年04月13日
コメント(19)
-

◆つくし◆スギナ食べた?◆
「つくし」のおいしい食べ方。佃煮とか、卵とじとか山菜本やサイトにはいろいろ書いてあるね。う~ん。じゃ、おいらは「土筆と泥鰌の柳川鍋」なんてあまりにBE-PALすぎるし・・(笑)もちろんはかまを取って2分ぐらいゆでて水にさらして。そこから先だよね。小学生の時に読んだ学研の「科学」にかつお節と醤油をかけて・・なんて掲載されてたっけ。マヨネーズをかけたり味噌あえにしたり、いろいろできるよね。でも、おぃらだったらどうしよう・・?現地確認してきたよ。 うぅむ。そのまま生で齧ったら。(笑)ひらめいた。ぴか☆◆その1「つくし花塩ラーメン」塩ラーメンなんだけどね。「桜茶」があるでしょ。つくしは春ならではのものだから、それに「桜茶」をあわせようってわけ。爆!ラーメンの玉買って、いっしょに塩ラーメンのたれも買うの。自信がある人はネギ油と塩と鶏がらスープ自分で作ってもいいよ。桜茶と塩ラーメンのたれがいっしょになると塩辛くなるから、適当に味見してでも煮立てて香りを逃がさないように。ゆでて水にさらした「つくし」と「桜茶」。そしてそこに懐石料理で使う「花麩」を浮かべる。器は、そうだねぇ。天目の暗黒の輝きがぃいよ。黒い器に桜とつくし。そして花麩がひらり。とってもシンプル。だから春。◆その2「つくしとスギナの花パスタ」桜茶を使うのは同じなんだけど。今日、スギナの芽の先をちっとつまんで食べてみたら・・(笑)おぃしいよ。いままでにない味かも。写真のつくしの隣にスギナが出てるでしょ。そのスギナの先だけを使うんだ。1cmぐらい。つまむと、すきっと折れるよ。これは、卵焼きに入れて謎かけ料理にいいかも。(笑)さぁて。あなたが食べたものはなんでしょう?スギナはフライパンでさっと油でいためるぐらいでいいよ。桜茶は刻んでぐい飲み一杯ぐらいの湯でもどしておくんだ。そしてオリーブオイルがあたたまったら、アルデンテのディチェコ(おぃら好きなの)と「つくし」と「スギナ」と「桜茶」をからめるだけ。これもシンプル。つくしを摘むときに、スギナの先をちょっとつまんで食べてごらん。「新・感・覚!」*桜茶とつくしの組み合わせ、いろいろ使えるでしょ。散らし寿司とか、サラダとか。あとはみんなで考えてみてね。そしてスギナも食べてみて。*子供のとき、草刈をしている爺さんがね。スギナのこと、「こいづわえんまさまのしげだ」って言ってたよ。今、思い出すとあ。「これは閻魔様の髭」なのねん。刈っても刈ってもまた出てくるから。(笑)つくしのレシピ考えてたら、そんなこと、ふと思い出したよ。◆つくし摘みあそびし子らは母となりつくし摘むとうまたその子らと◆(東京都)志摩華子:朝日新聞2005/4/11皆さんの春に祝福がありますように。クリックしてね。人気blogランキングへ
2005年04月12日
コメント(21)
-

◆シロモジ◆ニワトコ◆
「武士は食わねど高よーじ」って木枯紋次郎でないよ。その「楊枝(ようじ)」に使われるのは「クロモジ」。みやびな菓子についてることがあるから見たことあるかもね。*毎年、昨日のクレソンの場所とカタクリの群落に行っていたんだ。それはね、10年ぐらい前に「ヒメギフチョウ」が飛んでいたから。でも8年ぐらい前かな。5月のある日、張り紙を見たんだ。「マツノマダラカミキリ防除のためヘリコプターにて薬剤散布します。」その張り紙を見てね、しばらく動けなかった。もうダメだ。ここはあきらめよう。でも、春の水音が聞きたくてカタクリの群落が見たくて、それだけじゃなくてね。 花の大きさは小指の先ぐらい。これはシロモジの雌花。かわいいんだ。「見事」じゃないよ。「清楚」だよ。そしてこれが雄花。 これも小指の先ぐらい。園芸植物にはない美しさだよ。でも、それは、おぃらが「美しい」って思うからだけなのかもね。みんなが「美しい」って思ったら商売になってるもんな。(笑)ただね。おぃらは好きだよ。そしてシロモジの花が好きになってくれる人が好き。 星のように見える粒粒がぜーんぶこの花。これも見納めだね。サクラ並木を作って、道路拡張するためにね。歌詠んで、ぺたっと貼り付けてこようかな。(笑)のーみそがとーふで言葉が浮かばないナ。*あ。もちろんシロモジだけじゃないよ。何年も通っていると、同じ時期に同じ人に会うんだ。「今年(こどす)もなん。」(今年も会いましたね。)「んだなす。」(そうですね。)山で会う人は、険しい顔をした人は少ないよ。でも、その人はちっと陰があった。顔はニコニコしているけどね。 ニワトコの芽を摘むときの手つきが玄人だった。(笑)その人と初めて話しをしたときね。頭が??になったんだ。あっちの山の話し、こっちの山の話し。急に宮城県から福島県と山形県に話しが飛ぶからね。彼の推定行動範囲は、半径100kmだわ。山菜のプロだぁ~!!もう会えないかも。でも、どこかの山でまたばったり会うかも。あ、ニワトコはてんぷらにして食っちまった。うまかったぁ~。残ってないよ。クリックしてね。人気blogランキングへ
2005年04月11日
コメント(13)
-

そのまま◆クレソン◆
子供の頃から遊びに行った山が、桜を植えて、その上道路拡張するらしいから行ってみた。桜の名所にするんだって。だから、カタクリの群落も潰すし、シロモジっていうかわいい小さな花の木も伐採されている。誰も調査なんてしないよ。これから桜の名所なんかにしてもつまんないよ。四季を通していろいろな小さな木の花が咲いている。そんな財産がとても身近にあるってこと。そしてそれは、未来人への財産だってことに気づいてほしいよ。*来年はもう会えないかも知れないから、行ってきたよ。そうしたらね。(笑)道の下から音がするんだ。足の裏でも感じるよ。ごぼっ。ごぼって。そして、あちこちから水が噴出している。雪どけ水が地下を通って噴出してるんだ。大地の地下水脈が地表に現れると流れをつくる。 それが流れが窪地に小さな沼をつくってる。*ウォータークレソン。店で売ってるよね。明治時代に日本に入ったらしいけど、あちこちで野生化してる話しは聞いたことあるでしょ。水の中で光合成するから、観賞用にもいいよね。100円ショップで気に入った瓶をみつけて水耕すると楽しいよ。そして、ときどき、子供といっしょに「命をいただく」んだ。目の前で植物が育つこと。成長を見ること。命をわけていただくこと。食物はね。全部「命」なんだ。*小さな沼にゆきどけ水がそそいできれいだよ。このみどりは、全部クレソン。「ゆきどけクレソン」。そのままちべたい水に手を入れて、つまんで、水で洗って、ぱく、ぱく。うまうまっ。春の天然サラダ。しばらく横になって、地下水の音を聞いて、また一本、むしゃむしゃ。静養。静養。でも、この場所、来年には道路拡張で消えるんだよ。いっしょに水脈の音を聞いて、クレソン食べよう。クリック!人気blogランキングへ
2005年04月10日
コメント(13)
-

カタクリ◆なぜぇ?
うちの親戚の裏山にいっぱいあったの。別に手を加えたわけじゃないよ。いつのまにか、いっぱい増えていたの。そいで、おぃらの山はまだ雪の中だから出てないけど・・*カタクリ粉が昔、カタクリの根から取ったのは知ってるよね。でも、どうしてカタクリって言うか知ってるかなぁ。「片栗」つまり、栗の実を半分にしたような球根だから「カタクリ」なわけ。根は、深いよね。とあるカタクリ移植、国家プロジェクトでカタクリのほりかた教えたけど、大変だったよ。できるだけ斜面になっているところを選んで下から上に堀あがるんだ。何千本掘って移植したかなぁ。・・・遠い目。 どうして根が深いかは知ってるよね。それは、種が甘い蜜を出して蟻さんに巣穴に運ばせるから。花が咲くようになるまで7~8年かかるよ。小さな芽を見てるとそれが、とてもよくわかる。全部食べられるんだよ。特に、花だけのおひたしはね、さっと湯をくぐらせて、白醤油をちっとかけるだけにするんだ。そうするとね。花の蜜の味が逃げなくておぃしいんだよ。甘くて。エイディブルフラワー(食べられる花)の代表だね。*もちろん根は「ゆり根」と同じだよ。ほくほくしておいしい。子供が小さいころ、素あげにしてたら、揚げるさきから食うもんだから、「こら、食うな。父の分も残せ!」と怒ったことあったっけ。うらみ持ってるかな。でも、うまいもんいっぱい食わせたからな。*葉はもちろん、てんぷらにしてもおひたしにしてもおいしいよ。そうだね。おぃらみたいな病人(けほっ)には、お米とカタクリの根をゆるく炊いて、そこにカタクリのおひたしと花で、「カタクリ粥」なんていいかもね。期間限定、季節限定。もちろん、「マイマウンテン」があるからこんな贅沢できるんだけどね。*最後にひとつ。あのね。カタクリの種ってみたことあるかな。その若い種を集めてピクルスにするんだ。ワインビネガー、ワイン、ローリエ、グローブとか使う野菜のピクルスの作り方、ネットにあるでしょ。その方法とほとんど同じ。蜂蜜を使うのはカケル流かな。(笑)あっさり火が通るぐらいにゆでたら、海水より甘い感じ(20パーセントぐらいかな)の食塩水に1時間ぐらい漬けて、それからピクルス液に漬けておくの。冷蔵庫で保管して、1週間~1ヶ月がたべごろ。これがね、焼肉しながら食べると、「すっぱうまにが」なんだわ。それと、マリネに使うとおいしいんだ。そういえば、ドジョウのマリネ、作ったのは10年ぐらい前だったよな。作って冷蔵庫に隠しておいたら、子供たちに食われっちまった。おとーさんは食ってないんだぞっ。カタクリのうんちく、気に入ってくれたかな。クリックしてね。人気blogランキングへ
2005年04月09日
コメント(11)
-

◆ピリッ◆カラシナ◆
マスタード、自分で作ったことあるかな?おぃらは、カラシナの種から作ったよ。土手にいっぱい「菜の花」が咲いてるでしょ。あれは「カラシナ」なんだよね。花が終わって柔らかい茶色の種をつけたころをみはからって、種を取りに行くんだよね。そして、大さじ2杯ぐらいの種が集まったら、すり面に釉薬のある小さいすり鉢でごりごり潰すんだ。そしたら、ぬるま湯少しを入れて酒を少し入れてまたごりごり練るように潰すとできあがり。仕上げに醤油をほんの少しね。ビリッ!と辛くないよ。「じんわり苦辛い」んだ。ソーセージに合うよ。多分、土手のカラシナは「セイヨウカラシナ」だと思うよ。ここいらでは、今がちょうど食べごろ。 辛味を出すため、番茶で煮るとか、いろいろな人がいろいろ書いてるけど、わかってみると簡単。心得は、「湯をくぐすだけ。煮ない。」「氷水できっちり冷やす。」それだけなんだよネ。指で湯の温度が測れるかな。慣れるとできるよ。湯の表面を指でピッと触るだけ。お湯の温度はね、75度~80度ぐらい。そこに「よくばって入れすぎないように」カラシナを泳がせるんだ。色が変わったらそれでOK。20~30秒ぐらいかな。そしたら、氷水でしっかり冷やすこと。芯の芯まできっちり冷やすんだ。あとは、水気を切って、密閉容器で3時間ぐらい寝かせるだけ。3時間もすると、ビリビリ辛い、カラシナのできあがり。*そのまま塩をしてごはんといっしょに食べてもいいけど。おぃらはね。納豆に刻んで入れるのが好き。ピリピリって、ああ「春だっ」て思うもんなぁ。*それとね、結構油と相性がいいんだ。カラシナ&ベーコンスパゲティー。これも「苦辛」うまいよ。あとね。応用編。普通に、キャベツとかで野菜いためつくるでしょ。火を止めてから仕上げにこれをからめるの。おぃしいんだよ。人気blogランキングへ
2005年04月08日
コメント(13)
-

「ノビル」★食べた?
点滴生活に入ったあたくしは、ふがぁ。。と、安静にしてます。安静です。でもムリかも。。でも、安静。非常識的悩殺誘惑乱打芽琉が来ても安静。点滴は受けてますよ。いずれにせよ、あたくしの場合、安静になる場所が問題なのです。白い箱の中はヤ!です。(笑)それはね、「おいしい季節」がはじまったから。 どこにでも普通にあるって図鑑には書いてあるよね。万葉集にもたしか「蒜」で書いてあった筈。でも、「ノビル」って実物を見たことあるかなぁ。うちの庭では、珠芽(むかご)から育ててるけど、小指の先ぐらいの大きさになるのには、5年ぐらいかかる。まして、自然界だったら、もっと年数がかかるだろうね。近所では「普通に」みかけなくなった。1箇所だけ、30年以上前から群生している所は知ってるんだ。でも、いつまでもつかな。せめて庭で保護して環境が整ったのをみはからって珠芽(むかご)をばらまくよ。除草剤のない場所にね。セリの芽をちっと摘んできてね、ノビルは庭から調達。ノビルを葉ごと刻んだら包丁の柄で潰して、セリの芽もみじんぎり。それをおちょこ半分のオリーブオイルの中に入れたらぐるぐるかき回して、黒コショウちびっと。これがオイルソースだね。パン(適当。こだわらない。)に、スプーンでぬって、オーブンでこんがり焼くとできあがり。ま、ガーリックトーストの応用みたいなもんです。はふ、はふ、がり、がり。 うまうま がり がり 。*ノビルはね。そのまま齧るのが一番だという人がいるけど、そのとおり。赤み魚の刺身にノビルの粒があると嬉しいよね。おぃら、カツオのタタキはニンニクよりもノビルがいいなぁ。そういう店に行ったことないけど。(爆)*味噌焼きも欠かせないよね。ノビルに味噌つけて、焼いて、うまうま。*あ。葉はね。刻んだら、熱したフライパンで3秒だけ、じゅわっ。要するに、オイルソースだよ。これとパンがあればそれだけでうまうま。*ノビルのピクルス!つくったよ。10年ぐらい前だけどね。ラッキョウ漬けの要領で、ワインビネガーと蜂蜜を使ったっけ。輪切りのトウガラシだけ入れたシンプルなやつ。*うちのぢぢばばは、あると全部取らないと気がすまないらしい。沢山取れたとき軽く湯通ししたあと、味噌漬けにしたよ。5年ぐらいすると飴色になる。これは夏に素麺をたべるとき、3粒ぐらいあるといいよ。塩漬けにもしたよ。焼肉食べるときに、塩辛くてビールがうまい。*まだまだあるんだけどね。ノビルのおしい食べ方。気に入ってくれたかな。人気blogランキングへ
2005年04月07日
コメント(16)
-
自宅療養
「ご家族の方は何といいましたか?」「入院です。」「それであなたは、どうしますか?」「出来れば通院させて下さい。」「・・・」「・・・」「特別ですよ。動き回っちゃいけませんよ。」「ァィッ。」ということで、点滴通院になりました。皆様、ご心配かけてすみませんでした。かきこみのアドバイスやらお励まし、ありがとうごさいます。病院が怖いだけなんですぅ。大きな病院に行けば行くほど、沢山の病気や怪我がいっぱいあるから。しばらくは点滴をうけながら動き回らず春を楽しもうと思います。でも、一瞬でもバランス崩したら、即入院ですぅ。。ぼそっ。あ。「新・地底旅行 奥泉光」読んでなかった。医師のいいつけを守って静かにします。ぅぅ。静かにするって。いつも静かなんだが。静かにします。でも・いや、なんでもありません。人気blogランキングへ
2005年04月06日
コメント(12)
-
入院!
医師は、「すぐ入院して下さい。」といいました。「そりゃ、困る。」私はいいました。結局、点滴して帰って来ました。なんかね。熱がさがってから胸の痛みがとれなくて、これは「恋わずらいではない・・」と思ったので、思い切って病院に行ったのです。「インフルエンザの反応はありませんよ。でも、それ通り越してますよ。これはね、急性肺炎です。キュウセイハイエン。」。。おぃら病院はやだなので、ごちゃごちゃ説明したら。「明日来てください。」だって。入院してよかったっていう話、聞いたことないもん。人気blogランキングへ
2005年04月05日
コメント(11)
-

おいしいぃ~ヘメロカリス
名前は「ヘメロカリス」なんだけどね。夏が来れば思い出す。ニッコウキスゲならわかるっしょ。あれに限りなく近い仲間がこれ。葉だけみると、「なんだべ?」ですが、アクがなくてうまいっす。 で、うまいことを知っている人はここいらでもあまりいないので剪定鋏を持って野に遊びます。さっとゆでて、氷水で冷やして、マヨネーズがすきだったら、ぷちゅっとかけて食べるとおいしいよ。もちろん、酢醤油もいいし、ミツカンのポン酢でもいいよ。とくにかくシャキシャキしておいしい。カンゾウが「甘草」ってなるほどだよ。ところで。もっとうまい食べ方があるんだけど、それわねっ。(笑)ガーリックオリーブオイルでアサリの酒蒸しをつくるときにいっしょに入れるのです。アサリの塩味とからんで絶品! もちろんいっしょにアサツキを入れてもいいよ。ということで、ここいらの地方では食べるのはおぃらだけみたいなので食べ放題。ところで。アサリの産地表示ないぞ。。(爆)人気blogランキングへ
2005年04月04日
コメント(10)
-

バイオインフォマティクス
昨日は、長男の入学式だったのですが、おぃら行かなくてもいいべ・・と、ちらっとでも言うと山の神が・・ぉぉこわ。なのでてくてく、出かけました。風邪治ってないけど。。けほっ。大学は本当に危機感持ってるねぇ。近いうちに私立大学は、文部科学省によって強制的に合併させられるかもしれないなぁ。官僚はわが身のリストラは最後においとくからね。つくづく思うんだけど、なんで年金と税の徴収を別部門でしなくちゃいけないの。積極的理由が何もないよ。せっかく納税者番号を(グリーンカード案から20年)つくるんだから、それが個人特定コードになればいいわけで、一般国民は困らない筈。困る人を撲滅するのも国民に対する「税の公平の原則」に基くサービスでそ。国会できちんと説明しなさい。さぼるな。国会議員。*昨日は楽しかったよ。気づいたら11時だった。子供たちは、「アキバ巡礼」でもりあがってたな。*帰ってきたよ。梅の花が咲いていた。それからね。キバナノアマナが咲いていた。 アマナの学名は Tulipa (チューリップ) なんだけどそれに近い。*ところで・・昨日新聞を読んでいたら、あ゛嘆きたい。という記事があった。それはね、東大の「バイオインフォマティクス」なんだけど、2005年度予算しかないし生徒も集まらないので閉鎖されるらしい。実は、これって、ゲノム解析が終わったあと、アミノ酸からたんぱく質(酵素)の立体構造と生体における働きを予知することができるかもしれない分野なです。集中講座のテキストを見たとき、私は、「おお!これは、酵素解析に終わらないし、生物形態学と生物情報工学なんて分野も切り開ける可能性があるぞ!!」って、ワクワクして、「植物と人間とのインターフェイスはバイオインフォマティクスの先に可能になるかも・・」と思ったりした次第です。しかし、予算ないからやめるのかよ。バイオインフォマティクス。予算はそれほどかからないと思うんだけど。ていうか、文部科学省に基礎科学に対する危機感があるのかよ・・せめて東大だけでもバイオインフォマティクス継続してほしいっす。あ。バイオインフォマティクスについてご存知の方は、補足していただければ幸いです。人気blogランキングへ
2005年04月03日
コメント(5)
-
アーモンドの花
ただいま友人宅におります。エレミア書1章11節にアーモンドの花が登場します。アーモンドの花をみたことありますか。桃の種がアーモンドに限りなく近いです。桃の種をみたことありますか。バーチャルリアルは便利ですけどリアルに手に取ることなくバーチャル世界を語ると罠にはまります。*ただいま、家族と旧友と酒をくみかわしております。・で、世界はどうなるの。あ。。それはこっち。
2005年04月02日
コメント(8)
-
ガーデンレストランふたたび
ふたたび庭の話題に戻ります。わが庭には、「鳥海山の石」があります。とても現代では手にはいらないしろものです。私は少年のときに第一のじいさんからイワヒバ科の「ヒモカズラ」というものをいただき、粘土と練り合わせてぺたっ。と石に貼りました。「ヒモカズラ」は、いまでは絶滅危惧種です。それから30年、「ヒモカズラ」は岩の上に広がり、雨にぬれるとキラキラと緑色に輝き、私の楽しみでした。父は、ある日、「ヒモカズラ」を削り落としてしまいました。私は何も言いませんでした。理由も尋ねませんでした。*私の夢は、ガーデンレストランです。あらゆる野菜と樹木を配置してどの枝から食べてもよいし、どの実を食べてもよい。キャベツと紫キャベツを並べて植えたり、岩の間にはシュンランを植えて花を食べます。夏にはトウガラシを植えて、秋にはアサツキを植えて春には残りの花を楽しむ。*また、抜かれて焼かれるかもしれないけれど、はじめてみます。梅の木は絶対にイヤダというけど植えるぞ。おいらが好きだから。*私が庭を私がしたいようにしはじめたら、何か、話ししてくれるかもしれない。そのとき、誰かがこの庭のことをこう言ってたことをもう一度言おう。「稼ぐけれど金がたまらない家だ。」だからね、「野菜の庭」。樹木菜(うこぎ、たらのめ、はりぎり、くるみなど)の庭にするよ。子孫のことを考えてほしい父へ人気blogランキングへ
2005年04月01日
コメント(8)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 蝶好きっ♪
- 9/6-8:熊本旅行 黒川温泉で見かけた…
- (2025-09-14 15:28:29)
-
-
-
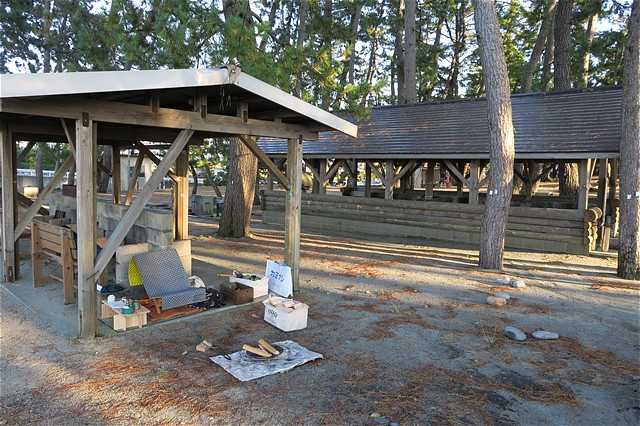
- キャンプを楽しむ方法
- 園家山キャンプ場で焚火&車中泊(20…
- (2025-11-23 14:02:13)
-
-
-

- 今日は何処へ行きましたか?
- 久しぶりに絹の道を歩く
- (2025-11-16 15:07:58)
-






