2007年03月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

日本酒にも旨い古酒あり!/3月31日(土)
ウイスキーや焼酎は熟成の年数を重ねたものほど一般的に言って、旨いとされる。ワインも、モノによるが、ボルドーの一級シャトーなど上質のフルボディの赤ワインは、古いビンテージのものほど珍重される。 一方、醸造酒であるビールは、出来たてが命。時間が経てば経つほど味は劣化していく。せいぜい1年以内か。日本酒も同じだというのが常識だった。 ところが、いつもブログのネタをよくくれる行きつけのBar「C」のマスターが、「日本酒でも古酒ってあるの知ってます?」と来た。「えー?! ほんま? そら飲んでみなあかんなぁ…」と僕。 Bar「C」はさほど広くないキャパなのだが、ウイスキー(モルトを含め)からワイン、リキュール、日本酒、焼酎に至るまで、なぜかお酒の品揃えが普通のBARのそれではない(しかもマニアックな銘柄も多い!)。 で、マスターがしたり顔で出してきた。まずは、岐阜は白木恒助商店(「だるま正宗」という酒を造っている酒蔵だが、最近は「熟成古酒」の造り手としても有名だとか)の古酒。3種類出ていて、それぞれ「五年古酒」「十年古酒」「十五年古酒」とラベルにはある(写真左)。 見た目の色は、まるでウイスキーの琥珀色。もちろん古いものほど色は濃い。匂い(香り)は、「五年」「十年」は少し米酢のような酸味を感じる。しかし「十五年」は、ボトルの口で香りを嗅いでみて驚いた。「まるで醤油やんか…」。 しかし、味はどうか。とにかく3種類をグラスに注いでもらう。「五年」はまだ若々しい。古酒と言われても分からない。色は、木樽醸造の有名な銘柄「樽平」や「住吉」に近い。「十年」はやや赤っぽい色。芳醇な甘口で、奥行きもあって旨い。「五年」も「十年」も、香りとは違って酢のような味はまったくしない。 さて、問題の「十五年」。色はかなり濃い、ブランデーのような琥珀色。が、飲んでみると、なぜか、あの強烈な醤油の香りが消えている。まったく感じない。日本酒というより、リキュールっぽい。 「う~ん、どっかで飲んだことあるなぁ、この味わい。何やったかなぁ…」と思い出そうと悩む僕。そしてしばらくして、「そうや、これ、紹興酒に一番近いなぁ」と思いつくと、マスターも「そうですね、紹興酒に似てますね」と同意。 さて、古酒探訪と言っても、1種類で終わらないところが、このBar「C」の凄いところ。続いて、マスターが出してきたのは、高知の酒「美丈夫」の古酒「美丈夫・群田鶴」(浜川酒造、1998年醸造)=写真右上。 飲んでみると、これは上品な、ほのかな甘味が心地よい。酸味のバランスも絶妙。普通の保存状態では、9年前の日本酒なんて飲めたものではない(必ずや「米酢」になってしまっている)。 酒の品質をどうやって長期間保つ工夫をしているんだろうか。もちろん厳しい、徹底した温度管理をして保管しているのだろうが、造り方にも何か秘密があるのかなぁ? この夜の最後の古酒は、「慶(よろこび)」という愛知県の銘柄(山忠本家酒造、1999年醸造)=写真左。こちらは2つ目の「美丈夫・群田鶴」とは違って、さっぱり、すっきりの辛口系。 聞けば、3年物を中心に5年物の古酒をブレンドするという独特の造り方。だが、とても古酒とは思えないフレッシュさ。ほど良く冷やされた酒は、喉越しも良くて旨い。 「日本酒に古酒なし」という先入観が見事に覆された夜。何事にも先入観はいけないということを学んだ、嬉しい、楽しい夜でもあった。Bar「C」のマスター毎度毎度有難うございました!こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/31
コメント(2)
-
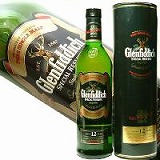
グレンフィディック:シングルモルト大衆化の立役者/3月27日(火)
僕が子どもの頃、亡き父(父は21年前に亡くなった)がウイスキーを飲んでいた姿の記憶は、あまりない。もっぱらビールや日本酒で、ときどき紹興酒だった。 しかしリビングルームの一角に、扉付きの上等そうな木製キャビネットがあり、その中の棚に、いつもウイスキーが何本か並んでいたことは、今でもよく覚えている。 必ずいつもあったのは、サントリーの角瓶。そしてジョニー・ウォーカーの赤や黒。そしてモルト・ウイスキーも、1本あった(もちろん、それがモルトであると知ったのはかなり後になってからだ)。 そのモルト・ウイスキーが「グレンフィディック」(写真左)という銘柄だった。独特の三角形をした緑色のボトルは、一度見たら忘れないフォルム。それが、僕が初めて見たスコッチモルト・ウイスキーでもあった。 おそらく1960年代、日本で一番出回っていて、有名だったモルト・ウイスキーは「グレンフィディック」だったろう。当時、日本国内で出回るウイスキーは、国産のを除けば、すべて「舶来の酒」と呼ばれていた。 「舶来の酒」は高かった。当時は従価税時代。ウイスキーの値段の半分は税金だった時代だ。それが、80年代後半、サッチャー英首相の圧力のおかげで日本の従価税は撤廃され、それまで、例えばジョニ赤で6~7千円していたのが、驚異的に安くなった。 父はそう酒に強い方ではなかった。しかし、モルトの瓶が棚に並んでいたということは、スコッチは好きだったのだろう。きっと、子どもが寝静まった夜中に、一人しみじみとこのモルトを飲んでいたのだろうなと想像すると、なんだか楽しい。 だからという訳でもないが、亡き父の思い出につながる「グレンフィディック」には、格別の思い入れがある。今でこそ、マッカランやボウモアなどの有力銘柄に埋没してしまっているが、僕は今でも、「グレンフィディック」は大好きだ。 グレンフィディック蒸留所(写真右上 (C)公式HPから)は1887年、それまでモートラック蒸留所で働いていたウィリアム・グラントという男性が独立して創業した。グレンフィディックとはゲール語で「鹿の谷」を意味する。 彼が目指したのは(おそらく)大衆の支持を得る欠点の少ないモルト・ウイスキー。そしてレモンや洋梨を思わせる香りを持ち、ライトでスムースで、芳醇な味わいを漂わせる素晴らしいモルトを産み出した(写真左=多彩な商品ラインナップも魅力。これは1972年もの限定ボトル)。 しかし当初は、ブレンディド・ウイスキーのキーモルトとして出荷するだけで、シングルモルトとして独自の製品は市場に出さなかった。実際、オフィシャル・ボトルのモルトが発売されたのは1963年と意外と新しい。 海外旅行に出ると、帰国時の最後の空港の免税店で、必ずと言っていいほど、グレンフィディックは大きなスペースを占めて売られている。それほど全世界でお馴染みの銘柄。シングルモルトとしての年間生産量(約1万kl)も、実はスコットランドではナンバー1だという。 グレンフィディックは、オフィシャル・ボトルでも、いろんな個性を持った商品を造り出していることでも知られている。とくにシェリー樽熟成の「長熟もの」(15年以上の)に素晴らしい商品が多い。 僕がとくに好きなのはシェリー樽熟成のボトルの「ソレラ・リザーブ」(写真右)というグレンフィディック。シェリー造り特徴でもある「ソレラ・システム」(詳しい説明は長くなるので、御免)で造られた長熟モルト。 豊かなアロマ、なめらかで奥行きのある旨さ。上品なシェリー香もよく出ている。まだ味わったことのない方には、ぜひおすすめしたいモルトの一つである。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/27
コメント(4)
-

披露宴ライブ本番!/3月23日(金)
21日(水)の結婚披露宴ライブ、無事に(?)終えてまいりました。あれこれ文字で報告するより、今回は主に写真で雰囲気なりを味わってもらえたらと思います。 披露宴会場は、阪神間の住宅街にある、素敵な1軒家のレストランの個室です。 この日の出席者は計18人。部屋は人数に見合った、ちょうどいい広さでした。 店側のご厚意で、レストランごと貸し切りにしてくださいました。 個室は細長いレイアウトで、一番奥にグランド・ピアノがあります。 ほかのお客さんもいないので、楽器を鳴らして、歌って騒いでも安心です。 テーブルの中央あたり、右側で手を挙げているのが新郎。その手前、オレンジ色のショールをまとっているのが新婦です。 ライブは宴たけなわになった披露宴後半にスタートいたしました。まず、最初は女性の友人。 歌は、前のブログにも書いたように今井美樹の「Piece of My Wish」(1991年発表)です。 メロディーも詩の内容も、新しい2人の門出にふさわしい、素晴らしいバラードです。 アコースティック・ギターは、僕の昔のバンド時代の友人がつとめてくれました(ちなみに弾いてるギターは僕の持っているマーチンD-41です)。 2人目の友人はプレスリーの「好きにならずにいられない(Can’t Help Falling In Love)」です。 もう50年近く前の歌なのに、名曲は何年経っても色あせません。バックで演奏していてもとても気持ちいい曲です。 歌もチョー上手くて、声量もたっぷりの友人は、身ぶり付きで聴き手をすっかり魅了してくれました。 歌の最後は、参加者も一緒に歌ってくれて大盛り上がりでした。この後、新郎も飛び入りで、井上陽水の「少年時代」を披露! 歌もなかなかのもんでした(写真は後日、アップしまーす)。 なにわともあれ、無事に演奏も終えてホッとしているうらんかんろであります。新郎新婦の前途に幸多かれ!
2007/03/23
コメント(12)
-

披露宴ライブの準備で何かと多忙な中、携帯を更新/3月19日(月)
今週の21日(水)の「披露宴ライブ」の準備で、ここのところ何かと多忙でーす。歌を歌ってくれる友人2人とのリハーサルは無事(?)終わりましたが、それ以外にも、まだまだ宿題があります。 譜面台の用意、楽譜や歌詞カードの用意、ギター担当の友人との音合わせ、ギターのカポタストや(万一のための)ギター弦の予備準備、当日のマイク(PA)をどうする等々…、あぁ、気がかりなことはいっぱいあります。 他にも、当日飛び入りで歌を歌う人が出てくるかもしれない(参加者は30~50代がほとんどなので、お酒が入ってくると、俺も私もということに?)ので、一応、「心の準備」(=リクエストが出そうな歌の練習)もしなければなりません。 会場は、一軒家の素敵なレストランの個室ですが、どちらかと言えばカジュアルな感じの場所なので、その場の雰囲気や流れでどう展開するかは、今からあまり読めません。 リクエストが出ると言っても、もちろん一応、「結婚披露宴にふさわしい歌」には違いないのですが、どんなリクエストが出るかわからないので、かなり不安でーす。 そんなこんなで、あれこれ忙しくて、気ぜわしくて、きょうのブログの日記はちょっと中身のない内容になってしまいました。どうかご容赦を! PS.携帯電話をほぼ5年ぶりに買い換え(機種変更)ました。メーカーはこれまでずっと使っている東芝で、「810T」という機種(写真=僕が選んだのは右端のブラックです)です。一番安いシンプルな機種にしたのですが、お値段は結構しました(割引ポイントを使って、基本契約料も一番安いのにねぇ…)。 携帯の会社は相変わらず、以前と同じところですが、その会社は現在、「ソフトバンク」と名前が変わっています。僕が使っていた携帯は、その前(ボーダフォン)の前のJ・Phoneという会社の時代の機種。ショップのおねえさんにも「長く大事に使ってらっしゃいますねー」と笑われてしまいました。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/19
コメント(4)
-

Barアルテミス・萬川さんの旅立ちに幸あれ!/3月15日(木)
僕が時々お邪魔するBARの1軒に、大阪キタの「アルテミス(Artemis)」という店があります。そのアルテミスの店長の萬川達也さん(写真左)が、今月20日をもってお店を辞めることになりました。 アルテミスの特徴はシェリーです。シェリーの品揃えでは関西では1、2を争うBARです。そして、萬川さんはそのシェリーを扱う日本でも数少ない公認「ヴェネンシアドール」です。 「ヴェネンシアドール」とは、ヴェネンシアという名前の1mほどもある、細長いい金属のひしゃくのような道具を巧みに使って、シェリーをグラスに注ぐテクニックを持った人のことを言います。萬川さんは、その「ヴェネンシアドール」の公認資格を本場スペインで取りました。 シェリーを入れたヴェネンシアを肩越し高く振り回し、頭上20~30cmほどの高さから自分の腰くらいの高さで手に持っているグラスに一気にシェリー(とくにオロロソやアモンティリアードが多い)を注ぐのです。注がれるシェリーは中空で空気に触れ、まろやかな味わいに変化します。 ウイスキーやカクテルも充実しているアルテミスですが、ここにに来るお客さんの約7割はシェリーを頼みます。そして、萬川さんの「ヴェネンシア」の技を見るのが楽しみで、遠くからやって来る人も多いのです(写真右=アルテミスでは極上のシェリーが味わえた)。 僕は萬川さんが10年ほど前、アルテミスに来られた頃からの馴染みです。気さくで親切な人柄も大好きですが、その落ち着いた振る舞いもあって、オーナー・バーテンダーだとずっと思っていた時期もありました。 その萬川さんがことし初め、「実は、3月で店を辞めようと思ってるんです」と打ち明けてくれました(いつもは届く年賀状が来なかったので、何かあったのかなと思っていたところでした)。 今後の展開について、萬川さんは「まぁ、10年も頑張ってきたのでそろそろ独立してもいいかなぁ…と。とりあえずスペインやフランスなどヨーロッパに1カ月ほど行って、帰ってきてから新しい自分の店を開こうと思っています」と語りました。 新しい「自分の店」について、萬川さんは「オーセンティックBARというよりスペイン・バルのような気軽な、肩の凝らない店にしたい。もちろん引き続きシェリーにも力は入れますよ」と夢を語ってくれました。フードも得意な萬川さんだから今から楽しみです(写真左=アルテミスの店内)。 萬川さんがいなくなってもアルテミスは残ります。しかし萬川さんのいなくなったアルテミスには当分、足を向ける気持ちは起こらないでしょう。それを考えると、少し寂しくなります(どういう雰囲気のBARになるんでしょうか…)。 でもここは、新しい旅立ちを祝福しましょう。アルテミスでの萬川さんのパフォーマンスを目に焼き付けたい方は、ぜひ20日までにお越しください。萬ちゃん頑張れ!【Bar Artemis】大阪市北区茶屋町1-5 茶ビン堂ビルB1F 電話06-6377-0707 午後4時~午前1時 月休※残念ながら、アルテミスは現在は閉店して、別のお店に変わっています。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/15
コメント(6)
-
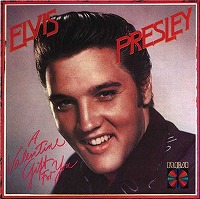
結婚披露宴で歌伴を/3月13日(火)
ひょんなことから結婚式の披露宴(21日)で、歌伴をすることになりました。あと1週間くらいしか準備期間はありません(汗)。 ヴォーカルをとる友人が2人(男性&女性です)いて、僕がピアノ、もう一人、昔バンドを一緒にやっていた友人がギターを弾いてくれます。ヴォーカルの友人2人はデュエットではなく、それぞれが別の歌を歌う予定です。 で、何を歌うのか。基本的にはヴォーカル担当が歌いたい曲目を決めればいいのですが、時間もないので、僕が伴奏をできないような難曲や知らない曲はNGです。 また、披露宴という目出度い場面にふさわしい曲でなければなりません。古今東西、結婚披露宴にふさわしい、よく歌われている曲は数多くあるのですが、いざ自分たちがやるとなると選ぶのはなかなか大変です。 和ものがいいか、洋ものがいいか。とりあえず、最近は披露宴でどんな曲が歌われることが多いのかネットで少し検索してみました。 あるサイトでのベスト10は、1.乾杯、2.Can You Celebrate? 3.てんとう虫のサンバ 4.ベスト・フレンド 5.世界に一つだけの花 6.Story 7.3月9日 8.ハナミズキ 9.永遠にともに 10.ハッピー・サマーウェディング、というランキングでした。 どんな世代を対象にした調査かは知りませんが、「乾杯」がいまだに1位なのはすごく意外でした。2は相当上手くないと難しいぞー。3なんて今どき歌う人っているのかなぁ…。4や6、8は確かに今風で、良い曲かもしれません。7と9、10は恥ずかしながらまったく知りませんでした。う~ん、これは難しい! 悩んだ末にとりあえず、男性の友人が選んだ歌は、エルビス・プレスリー(写真左上)の名曲で、今やスタンダードにもなっている「Can‘t Help Falling In Love」。Wise men said~♪という歌詞で、歌い出すあの甘いメロディーの曲です。 スローなバラードで、コード進行も比較的簡単です。練習時間も短いので、友人はまさに最適の選択をしたかもしれません。ギター担当の友人にはキーが決まれば楽譜をFAXで送って、家で事前に練習しておいてもらうつもりです。 しかし、女性の友人の方の歌はまだ決まっていません。近々、曲のキーを決めるための打ち合わせをBar「M」でするので、そこであれこれ歌ってみて決めてしまうつもりをしています。さて、彼女は何を歌うことになるんでしょうか。【追記】14日にヴォーカル担当の2人とリハをしました。男性の方の「プレスリー」は、原調通りのDというキーになりました。女性の方は、「パパ」「ハナミズキ」「Close To You」等々をあれこれ歌ってみた末に、最終的に今井美樹(写真右上)の「Piece of My Wish」に決めました。キーは原調(E♭)より一つ下のDでやります(奇しくも男女とも同じキーです)。本番でも、リハ通りうまくいけばいいのですが…。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/13
コメント(10)
-

アイリッシュしばりの夜/3月9日(金)
「今夜は気分を変えて…何かいつもと違うものを飲もうかなぁ…」と馴染みのBAR「C」のカウンターでつぶやく。それを聞き逃さなかったマスター。「じゃぁ、今夜は、アイリッシュしばりでいきますか? ブログのネタにもちょうどいいですよ」と。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。 という訳で、その夜は珍しくアイリッシュ・ウイスキーを堪能した。アイリッシュと言えば、大麦麦芽だけでなくライ麦や小麦などを使い、単式蒸留器での3回蒸留が特徴。麦芽の製造にはスコッチのようにピートは焚かず、石炭を焚くことでも知られる。 「ジェイムソン」「ブッシュミルズ」「タラモアデュー」の3大銘柄が有名で、この3銘柄はほとんどのBARで置いている「マストアイテム」と言っていい。他にも最近は「コネマラ」「グリーン・スポット」「レッドブレスト」という銘柄も結構ポピュラーだ。 しかし普通の銘柄を飲んで満足する僕ではない(笑)。まず、最初は「ワイルド・ギース(Wild Geese)」(写真左上)。久々のアイリッシュの新銘柄だ。その名は「野生のガンたち」。 アメリカがまだ英国の植民地だった17世紀半ば、プロテスタント教徒に弾圧されたスコットランドのカトリック教徒たちの一部は、新天地を求めてフランスへ渡った。 そんな人たちのことを、渡り鳥にちなんで「ワイルド・ギース」と呼んだという。このウイスキーはそんな人たちに捧げられたもの。モルト含有率が高く、しっかりしたボディ。しかもバランスの良さもウリだ。 2杯目は「ロックス(Locke‘s)」(写真右上)という銘柄の8年熟成のモルト・ウイスキー。アイリッシュには、モルトの銘柄は少ないので稀少な存在とも言える1本だ。 オレンジ色のやや派手なラベル、最近はあちこちのBARで目にするようになった。その名は19世紀の蒸留業者の名にちなむ。90年代初めに、そのロックスの造ったウイスキーを別の業者が再現し、復活させた曰く付きの酒。芳醇で柔らかい味わいがたまらない。 さて、3杯目は「ヒューイッツ(Hewitts)」(写真左中)。これもBARで時々、目にする銘柄。ただしこの夜、頂いたのは(たぶん80年代の)オールド・ボトルだった。 当然だが、オールド・ボトル特有の麦芽臭というか、「ひね香」がある。しかしそれはまた、オールド・ボトルの魅力でもある。上品な甘さ、優しい喉越し。スコッチにはない魅力を再発見した夜でもあった。 4杯目。「ジェイムソン・クレステド・テン(Jameson Crested Ten)」(写真右中)。アイリッシュのトップブランドである「ジェイムソン」蒸留所の子会社が造る姉妹ウイスキー。 シェリー樽熟成で、マイルドで、洗練された味わい。ライト&スムースがウリの「ジェイムソン」と飲み比べてみるのも面白いかもしれないと、ふと思った。 さて、最後に頂いたのは「メリーズ(Merrys)」(写真左下)という初めて聞く名のアイリッシュのシングル・モルト。アイルランド中南部のクロンメルという町にある小さな蒸留所で細々と造られているという。 聞けば、大量生産はしていないため、日本はおろかアイルランド国内でもなかなか目にできない稀少銘柄なんだとか。そんな銘柄を大阪で飲めるなんて、嬉しいね(マスターはいったいどうやって入手したんだろう?) 「メリーズ」は、元々はアイリッシュ・クリーム・リキュール製造用に造られたウイスキーという。華やかな香り、なめらかな味わいには理由がある訳だ。運良くBARで見つけられたら、迷わずお試しを! 一口で「アイリッシュ」と言っても、いろんな顔を持つブレンディドやモルトがある。スコッチに少し飲み疲れた時、ライトで、喉越しのいいウイスキーの多いアイリッシュは、「酒呑みの清涼剤」になる(笑)。 そう言えば、もうすぐ「聖パトリック・デー」(3月17日)。アイルランドの聖人をしのびながら、今夜も乾杯!こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/09
コメント(4)
-

サクラがもう咲き始めた!/3月5日(月)
昨日(4日)の関西地方は、最高気温が20度以上になる、とんでもなく温かい日曜でした(きょうからは全国的に荒れ模様の天気になるって、テレビでは言ってましたが…)。 東京も一度も雪が降らなかったそうですが、結局、ことしの冬は、冬らしい寒さが一度もないままでしたね。僕が知る暖冬でも、ことしは記憶に残る年でしょう。 で、我が家のサクラ(「暖地桜桃」という早咲きの品種で、高さは2mくらいに育っています)も、春の足音とともにつぼみがどんどん膨らみ、とうとう昨日、花が咲いてしまいました(写真左)。 早咲きなので、ソメイヨシノよりは例年2週間くらい早く、3月の15日前後に咲き始めるのですが、ことしはさらに10日も早いのです。 まだ二分~三分咲きという感じですが、地球温暖化という異常気象もここに極まれりです。 バラの世話をしていると、道行く人からも「(サクラ)もう、咲いてますね。綺麗ですね」と声をかけられましたが、心境は複雑です。 この調子だと、あと1週間くらいで満開になって、みなさんが花見をする頃には、きっと葉桜でしょう。 「暖地桜桃」は以前にもブログ(05年3月20日の日記)&(05年5月10日の日記)で書きましたが、早咲きのうえ、自家受精(結実)で、サクランボがいっぱい成る珍しい品種です。花と実を両方楽しめるので、これからサクラを育ててみようという方にはお勧めですよ。 でも、この冬から春の異常気象がサクランボの出来(5月中旬です)にも影響するのではと、今から少し不安です。実がたくさん成ったら、また写真をお見せいたしましょう。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/05
コメント(8)
-

友人と一緒に、久しぶりのピアノBar「M」/3月1日(木)
久しぶりに大阪キタのピアノBar「M」。今回は歌のめちゃ上手い友人(♂)と一緒に行って、歌伴いたしました。 友人は大学時代、軽音楽部に入っていて、ギターを弾きながら歌っていました。だから横文字の歌もわりと得意なんですが、ジャンルはポップス、フォーク、カントリー、オールディーズ等々が中心で、若干偏っています。 で、この日歌ったのは、横文字では「明日に架ける橋」「ダニエル」「コットンン・フィールズ」「デスペラード」「エンド・オブ・ザ・ワールド」くらいかな(横文字のレパートリーでは、僕の方が勝っているかも(笑))。 あとは、日本語の歌でした。「瞳をとじて」「涙そうそう」「悲しい色やね」「プカプカ」「未来予想図2」「サイレンスがいっぱい」「遠くで汽笛を聞きながら」「やっぱすきやねん」なんて感じ…。 友人ははっきり言って、めちゃ上手いんです。音域も広いし、何より高音が綺麗(小田和正か徳永英明ばりの声です)。プロの歌手になっても十分やっていけそうなレベルです。 この夜、Bar「M」に来ていた他のお客さんも、彼が歌い始めるとおしゃべりをぴたりとやめて、その歌にじっくり聴き入っていました。 友人は最後に、最近練習中だという中島美嘉の「雪の華」(写真右下=ジャケット写真)を歌いたいと言いましたが、残念ながら、僕は一度も歌伴をしたことがなくて、曲もサビくらいしか知らないので、ここはBar「M」専属のピアノの先生「Syn」さんにお任せいたしました。 フルコーラスで聴くのは初めてだったのですが、「雪の華」ってほんとに素晴らしいバラードです(冬の季節しか歌いにくいのが問題ですが(笑))。「次回は僕も歌伴できるように練習しておくよ」と彼に約束しました。 で、「伴奏ばっかりじゃなくて、(お前も)何か歌えよー」と友人に言われ、最近めちゃくちゃ気に入っているミスチルの「しるし」をまず歌いました。 この曲の話を以前ブログ(06年12月17日の日記で書いた時は、音域が広すぎてちょっと無理と書いたのですが、キーをG(ミスチルはC♯です)でやると、出だしの音はは少し低すぎるのですが、サビの高音はなんとかぎりぎり歌えることが分かりました。 何度歌っても、この曲はメロディーも詩も素晴らしいの一言です。自分で歌っていてもめちゃ気持ちいい歌です。僕の音域がもっと広ければ、もっとかっこよく歌えるのになぁ…とこの夜も思いました。 僕がこの夜、「しるし」以外に弾き語りした歌は、「君をのせて」(沢田研二)、「どんなときも」(槙原敬之)、「花」(オレンジレンジ)、「僕の倖せ」(はちみつぱい)、「Jolie」(アル・クーパー)、「Cry Me A River」(ジャズ・スタンダード)。はっきり言って、アーチストも時代(曲)も自分で言うのも変ですが、すごい幅で、滅茶苦茶ですね(笑)。 次回のBar「M」は約2週間後、このブログで登場したのとはまた別の歌の上手い友人と一緒にお邪魔する予定です。楽しみだなぁ。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2007/03/01
コメント(6)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-
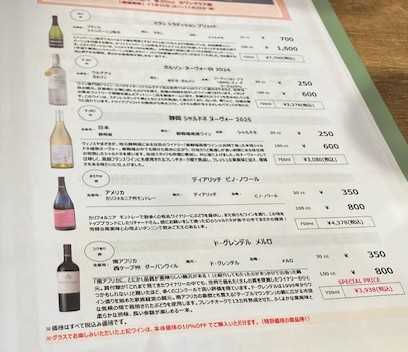
- たのしいお酒飲んでますか。
- 1週間遅れのボジョレー・ヌーヴォー☆…
- (2025-11-28 22:42:46)
-
-
-

- 日本酒の良さを広めよう!
- 光武(佐賀県)手造り純米酒
- (2025-11-25 21:13:17)
-
-
-

- イタリアワイン大好き!
- イタリア第2の島「サルディーニャ島…
- (2025-11-23 11:50:04)
-







