2011年02月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
【復刻連載】 「コクテール」前田米吉著 (6) カクテルレシピ<3>/2月27日(日)
23. ホノルルコクテール【注29】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ドライジン 三分の二オンス オレンジジュース 四分の一オンス 砂糖 テースプーン一杯 レモンジュース 二分の一個 アンゴスチュラビタ 二振り キュラソー 二振り アブサン 一振り 玉子の白味 一個分 を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、ワイングラスに漉してすすめる。【注29】「ホノルル(Honolulu)コクテール」は、サヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的カクテルの一つだが、レシピは微妙に違うほか、サヴォイはシェイク・スタイル。…………………………………………………………………………………………24. ホワイトコクテール【注30】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ドライジン 一オンス アンゴスチュラビタ 一振り アニセット 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にオリーブを加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注30】「ホワイトコクテール」は、サヴォイ・カクテルブックの著者ハリー・クラドックが1920年代に考案した古典的カクテル。サヴォイ・カクテルブックは、この前田氏の「コクテール」が世に出た時期にはまだ出版されておらず(6年前)、前田氏がどのようにしてこのレシピを知ったのかは謎である。…………………………………………………………………………………………25. ボウメランコクテール【注31】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ジン 三分の一オンス 伊太利ベルモット 三分の一オンス フレンチベルモット 三分の一オンス マラスチノー 一振り アンゴスチュラビタ 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にマラスチノー・チェリー一個を加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注31】「ボウメランコクテール」とは、1920年代にはすでに知られていた「ブーメラン(Boomerang)・カクテル」のことと思われるが、様々な文献に当たっても、前田氏のようなレシピは見当たらない。もっとも、「ブーメラン・カクテル」自体も今日では、ジン・ベースのもの(ジン、スイートベルモット、パイナップルジュース)と、ウイスキー・ベースのもの(ウイスキー、ドライベルモット、スエディッシュ・パンチ、レモンジュース、アンゴスチュラビターズ)の2種が伝わっている。…………………………………………………………………………………………26. ペルフェクトコクテール【注32】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に ゴルドン・ドライジン 六分の四オンス フレンチベルモット 六分の一オンス 伊太利ベルモット 六分の一オンス アブサン 一振り を加え、よくセーク(攪拌)したる後、コクテールグラスに注ぎ、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注32】「ペルフェクトコクテール」とは、「17」で登場した「パーフェクトコクテール」と綴りは同じものと思われ、材料も基本的に同じである。しかし作り方が「パーフェクト」がステアで、「ペルフェクト」はシェイクという点と、材料3種の比率も両者で異なっている。「ペルフェクト」の名は他の文献では見られないため、前田氏の創作かも。…………………………………………………………………………………………27. ベンネットコクテール【注33】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に オールドトム・ジン 一オンス アンゴスチュラビタ 一振り ライムジュース 少量 を加え、よくセークしたる後、コクテールグラスに注いですすめる。【注33】「ベンネットコクテール」とは、レシピの内容からして1920年代には誕生していた「ベネット・カクテル」のことと思われる。「ベネット(Bennett)」はニューヨーク・ヘラルド新聞社の2代目オーナーで、見境なくお金を使うことで有名だったジェームス・ゴードン・ベネット(1841~1918)の名に由来するという(出典:Bar VespaのHP 引用多謝!)。…………………………………………………………………………………………28. ベルモットコクテール【注34】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に 伊太利ベルモット 一オンス アンゴスチュラビタ 三振り フレンチベルモット 少量 を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にオリーブを入れてすすめる。【注34】「ベルモット(Vermourth)コクテール」は、かのジェリー・トーマスのカクテルブック(1862年刊)にも登場する最初期の古典的カクテル。ただしトーマスのレシピは、ベルモット(ワイングラス1カップ)、マラスキーノ2dash、ビターズ2dash、レモン4分の1個分というもので、前田氏のレシピは何を参考にしたものかは不明。…………………………………………………………………………………………29. トロカデロコクテール【注35】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に フレンチベルモット 二分の一オンス 伊太利ベルモット 二分の一オンス オレンジビタ 一振り グレナデン 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にマラスチノー・チェリー一個を加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注35】「トロカデロ(Trocadero)コクテール」はサヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的カクテルで、前田氏のレシピもサヴォイとほぼ同じ。…………………………………………………………………………………………30. トムジンコクテール【注36】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に オールドトム・ジン 一オンス オレンジビタ 一振り マラスチノー 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注36】「トムジン(Tom Gin)コクテール」は現時点では前田氏の本以外には見当たらないカクテル。…………………………………………………………………………………………31.ドクトルコクテール【注37】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に カロリック・ポンチ【注38】 六分の四オンス レモンジュース 六分の一オンス オレンジジュース 六分の一オンス アブサン 一振り を加え、よくセークしたる後、コクテールグラスに注いですすめる。【注37】「ドクトルコクテール」とは「ドクター(Doctor)・カクテル」のことで、ハリー・マッケルホーンのカクテルブックなどいくつかの文献に登場するが、マッケルホーンのレシピはカロリック・ポンチ、レモンジュース、オレンジジュースが各3分の1ずつ等量となっている。【注38】「カロリック・ポンチ(Caloric Punch)」とは北欧スウェーデン産のリキュールのこと。「スウェディッシュ・ポ(パ)ンチ」とも言う。ラムに薬草やスパイス類を配合し、オーク樽で熟成させてつくる。現在では「カロリック・パンチ」という表記が一般的。…………………………………………………………………………………………32. チストルコクテール【注39】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ライ・ウイスキー 三分の二オンス 伊太利ベルモット 三分の一オンス アンゴスチュラビタ 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注39】「チストルコクテール」とは「シスル(Thistle)・カクテル」のことで、サヴォイ・カクテルブックにも登場するが、そのレシピ(スコッチウイスキー2分の1、スイートベルモット2分の1、アンゴスチュラビターズ2dash)と、前田氏のレシピとは少し異なる。ちなみに「Thistle」とはスコットランドの国花「アザミ」のこと。………………………………………………………………………………………… こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/27
コメント(0)
-
【おわび】「カクテル(混合酒調合法)」秋山徳蔵著: Vの項で修正があります/2月26日(土)
皆さま、すみません。故・秋山徳蔵氏の「カクテル(混合酒調合法)」の復刻版について新たに1カ所修正すべきところが見つかりました。本文「V」の項です。 「V」の項で当初、「ヴェルモット・カクテル」が2カ所出てきましたが、後の方は間違いで、正しくは「ヴェルモット・ゴムメ」(Vermouth Gomme)でした。WEB復刻版ではすでに修正を反映いたしました(Gommeは「ガムシロップ」のことを意味しています)。 きちんと、何度もチェックしたつもりでしたが、誠にお恥ずかしい、極めて初歩的な校閲ミスでした。大変申し訳ありません。 以上とり急ぎ、お知らせまで。何卒よろしくお願いいたします。 ※復刻版の小冊子をお送りした方BARのマスター、バーテンダーの皆さま、大変お手数ですが、本文68頁の見出し部分の修正を何卒よろしくお願いいたします。
2011/02/26
コメント(0)
-

Bar Anthem(アンセム): カクテルへの情熱が高じて…/2月25日(金)
埋もれてしまった古い時代のカクテルブックの復刻作業に取り組んでいるうらんかんろですが、先日、あるBARのマスターから「**さん、そんなに古いカクテルブックに興味をお持ちなら、銀座のこのBARにはぜひ一度行ってみてください」と言われました。 そのBARのマスターは、かつて業界のコンクールでも全国優勝したほど凄い実力の持ち主ということはもちろん知っていましたが、実は、「日本でも指折りの古いカクテルブックのコレクター」とのことです。そう聞いては、僕としてはぜひとも行かねばなりません。 そういうことで先週、東京へ日帰り出張があった際、早速お邪魔してきました。その店の名は「Bar・Anthem(アンセム)」=写真左。マスターのAさんとは実は7、8年前に、彼が以前勤めていた霞が関の「ガスライト」というBarで一度お目にかかったことがあります。 その際は店内がほぼ満員でとても忙しく、ほとんどお話をすることができませんでした。お勘定をする際、Aさんは「きょうは忙しくてまったくお構いできませんでしたので、チャージはいただきません」と言って、お酒の料金しか受け取りませんでした。その心憎い接客・サービスを僕は今でも鮮明に覚えています。だからAさんには好印象しか残っていませんでした。 初めてお邪魔するAnthemは、銀座でも僕が以前よく訪れていた「ル・ヴェール」というBAR(現在はSマスターの故郷である秋田市へ移転)と同じビルの同じフロア(2F)にあったので、迷うことはありませんでした(ちなみにAnthemとは「聖歌、讃美歌」との意)。 まずはAマスターに、大変長いご無沙汰を詫びるご挨拶。そして、まずはジン・リッキーを頂きつつ、早速、この夜の最大の目的であるカクテルブックのことに話題を移しました。 「ブログで、秋山徳蔵さんという方の古い、おそらくは日本で最初のカクテルブックの復刻に取り組んだのですが、秋山さんの本のことは当然、Aさんもご存じですよね?というか、本も持っておられますよね?」と尋ねました。 するとAさんは「えーっ、**さんだったのですか! 実は先日、うちのお客さんから『ブログでこんな連載(秋山さんの「カクテル・混合酒調合法」の復刻)をしている人がいるよ』と教えてもらったばかりなんです。そして、そのお客さんに『その連載、プリントアウトしておいてよ』と頼んだところだったんですよ!」と驚きの声を上げられました。 自分で言うのもなんですが、「世の中狭い」と言うか、こんな絶妙のタイミング(の訪店)って、時々あるんですよね…。連載の話を聞いたAさんも、僕が(こんなにすぐに)突然訪れるとは思っていなかったでしょう。僕は、Aさんにブログのことを教えてくれたそのお客さんに感謝しなければなりません。 それはともかく、僕は秋山さんの本の復刻版(小冊子)を一冊差し上げました。Aさんは「秋山さんの本は現物は知っているけれど、持っていないので嬉しいです」と言ってくださいました。僕はさらに「引き続いて前田米吉さんのカクテルブック(こちらはAさんは現物をお持ちでした)の復刻も始めているので、これも完成したらまたお届けします」と約束しました。 Aさんの古いカクテルブックのコレクションは、Anthemのホームページ上でも少し垣間見ることができますが、実際店で見てみるとただ凄いの一言です。キャビネットの本棚一杯にコレクションが詰まっています。約200冊ほどが展示されていますが、これでもまだ蔵書の10分の1だとか。 貴重なコレクションは(もちろん扱う作法と注意は必要ですが)実際に手に取って見ることもできます。Aさんはその中から、貴重本をいくつか見せてくれました。まずは、サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)の初版からまもなく出たという第二刷の本(おそらく1931、32年刊?)、ジェリー・トーマスのカクテルブックの次に出たという米国のカクテルブック「Apple Green's Bar Book」(確か1898年刊とか)=写真右上。 そして、なによりも驚いたのは、Aさんが「**さん、実は明治時代にも洋酒の本は出ているのですよ。一つにはカクテルのレシピも紹介されています。もう一つはお酒の造り方みたいな内容ですが…」と言って紹介してくれた2冊。 1冊は「袋井五郎編・四季飲料混成方」(東京・有隣堂刊)という本=写真左上=で、明治40年(1907)の出版です。秋山さんの本の出版から遡ること17年前。内容はパンチ類の造り方が中心で、純粋な意味でのカクテルブックとは言えないかもしれませんが、カクテルもいくつか収録されています。 もう一冊は明治20年出版の和書で、「新撰洋酒銘酒製造傳法簿」という本=写真右=で、明治23年(1890)の出版で、内容は純粋に(家庭で?)簡単にできるお酒の造り方の紹介という感じす。 いやぁ…、古い酒類の本探しに注ぐAさんの情熱にはただただ頭が下がるばかりです。個人的には、こうした貴重な本や資料を公開・活用できる形できちんと管理してくれる機関・施設があってほしいと願います。メーカーさんが共同で設立してくないかなぁ…。 Anthemでの楽しい時間は瞬く間に過ぎていきました。Aさんのコレクションの中にはまだまだ僕の興味をそそる本がいっぱいありました。近々また再訪したいという思いが、いま募っています。 Aさん、温かいもてなしと美味しいお酒、そして素晴らしいコレクションの数々を拝見させていただき、本当に有難うございました。また近いうちに!【Bar Anthem】東京都中央区銀座6-4-8 曽根ビル2F 03-5537-2545 午後6時~午前2時(土曜は午後5時~午前零時) 日祝休 (※ちなみに、現在放映中のテレビ朝日系のドラマ「バーテンダー」では、主演の相葉君らへの技術指導はAさんともう1人のバーテンダーの方が担当されていまーす。これも凄い!)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/25
コメント(0)
-
「カクテル(混合酒調合法)」秋山徳蔵著: Sの項で修正があります/2月22日(火)
故・秋山徳蔵氏の「カクテル(混合酒調合法)」の復刻版について新たに一カ所修正があります。本文「S」の項です。 「S」の項の「シャンデー・ガーフ」で、当初、英文表記が「Shandy Guff」となっていました。これは原著での表記をそのまま再現したものですが、正しくは「Shandy Gaff」でした。原著は誤植と思われますので、復刻版では修正いたしました。 以上とり急ぎ、お知らせまで。何卒よろしくお願いいたします。 ※復刻版の小冊子をお送りした方BARのマスター、バーテンダーの皆さま、大変お手数ですが、本文(61頁の見出し部分と64頁の脚注)の修正をよろしくお願いいたします。
2011/02/22
コメント(0)
-
【復刻連載】 「コクテール」前田米吉著 (5) カクテルレシピ<2>/2月20日(日)
11. ロスコクテール【注18】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ドライジン 四分の二オンス フレンチベルモット 四分の一オンス デュボンネット 四分の一オンス グレナデン 二振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之に一個のマラスチノー・チェリーを加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注18】「ロスコクテール」は、現時点では前田氏の本にしか見られないカクテルである。英文表記の綴りも不明。…………………………………………………………………………………………12. ハーバードコクテール【注19】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ブランデー 二分の一オンス 伊太利ベルモット 二分の一オンス アンゴスチュラビタ 一振り ガムシロップ 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注19】「ハーバード(Harvard)コクテール」は、ハリー・マッケルホーンのカクテルブックやサヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的なカクテル。前田氏のレシピは両著とほぼ同じ。…………………………………………………………………………………………13. ハレムコクテール【注20】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に ウイスキー 三分の二オンス 伊太利ベルモット 三分の一オンス オレンジビタ 一振り を加え、よくセーク(撹拌)したる後、コクテールグラスに注ぎ、之に一個のマラスチノー・チェリーを加えてすすめる。【注20】「ハレム(Harlem)コクテール」は、1910~20年代には欧米では飲まれていた古典的カクテルだが、前田氏のレシピは欧米の標準的レシピ(プリマスジン45ml、パイナップル・ジュース10ml、マラスキーノ5ml)とはベースも含めてまったく異なる。前田氏は何を参考にしたのかは不明。…………………………………………………………………………………………14. ハンディカップコクテール 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に グランドマルニエー 一オンス 三矢レモン 半本 を加え、バースプーンにて静かに混ぜ、ワイングラスに注ぎ、レモンの皮の小片を入れてすすめる。…………………………………………………………………………………………15. ハラウハラウコクテール コクテルセーカにニ三塊の氷を入れ之に ドライジン 三分の二オンス キュラソー 二分の一ティースプーン オレンジジュース 三分の一オンス 三矢レモン 半本 を加え、よくセーク(撹拌)したる後、コクテールグラスに注いですすめる。…………………………………………………………………………………………16. パルメットコクテール【注21】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ジャマイカ・ラム 二分の一オンス 伊太利ベルモット 二分の一オンス オレンジビタ 二振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注21】「パルメットコクテール」は、サヴォイ・カクテルブックでは「パルメット(Palmetto)」の名で登場する古典的なカクテルである。前田氏のレシピはサヴォイとほぼ同じ。なお、原著は「ハルメードコクテール」となっていたが、明らかに誤植と思われるので復刻版では修正した。…………………………………………………………………………………………17. ハアランドコクテール【注22】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に ハアランド・ジン 一オンス アンゴスチュラビタ 二振り ガムシロップ 一振り を加え、よくセーク(攪拌)したる後、コクテールグラスに注ぎ、之にマラスチノー・チェリー一個を入れてすすめる。【注22】「ハアランドコクテール」とは、現時点では前田氏の本にしか見られないカクテルである。英文表記の綴りも不詳(何か情報をお持ちの方はご教示ください)。…………………………………………………………………………………………18. パラダイスコクテール【注23】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に ドライジン 三分の一オンス アップルコット・ブランデー【注24】 三分の一オンス オレンジジュース 三分の一オンス を加えよくセーク(攪拌)したる後、コクテールグラスに注いですすめる。【注23】「パラダイス(Paradise)コクテール」は、ハリー・マッケルホーンの本やサヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的なカクテルの一つで、今日でもバーでよく飲まれている。前田氏のレシピはマッケルホーンの本とまったく同じだが、サヴォイ・レシピ(ジン2分の1、アプリコット・ブランデー4分の1、オレンジジュース4分の1)とは分量比が異なっている。【注24】「アップルコット・ブランデー」とは「アプリコット(あんず)・ブランデー」の誤植と思われる。…………………………………………………………………………………………19. パーフェクトコクテール【注25】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に オールドトム・ジン又はドライジン 三分の一オンス 伊太利ベルモット 三分の一オンス フレンチベルモット 三分の一オンス を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注25】「パーフェクト(Perfect)コクテール」は、「パーフェクト・マティーニ」とも呼ばれ、ハリー・マッケルホーンの本やサヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的なカクテル。前田氏のレシピは両著と同じだが、サヴォイ・レシピではシェイク・スタイルになっている。なお、この三つの材料を各3分の1ずつ等量にするレシピは「トリニティ」という別名のカクテルとして区別している本もある。…………………………………………………………………………………………20. バンブウコクテール【注26】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ドライパール・セリー 二分の一オンス フレンチベルモット 二分の一オンス オレンジビタ 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注26】言わずもがなだが、「バンブウコクテール」とは今日でもバーで人気がある「バンブー(Bamboo)カクテル」のこと。ハリー・マッケルホーンの本でも紹介されている。現代では、シェリー3分の2、ドライ(=フレンチ)ベルモット3分の1、オレンジ・ビターズ1~2dashが標準レシピ。…………………………………………………………………………………………21. バカルデーコクテール【注27】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に バカルデー・ラム 一オンス ライムジュース 三、四振り を加え、さらにシュガーシロップを加えバースプーンにて試嘗(ししょう)しつつ、適当な甘味を持つ迄(まで)之を加えて攪(か)き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注27】「バカルデー(バカルディ=Bacardi)コクテール」はハリー・マッケルホーンの本にも登場する古典的カクテルの一つだが、マッケルホーンのレシピは、バカルディ・ラム3分の2、ジン6分の1、ライム(またはレモン)ジュース6分の1と、ジンを加える点が前田のとは少し異なっている。…………………………………………………………………………………………22. ニックオンコクテール【注28】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ブランデー 二分の一オンス 伊太利ベルモット 二分の一オンス アンゴスチュラビタ 一振り アブサン 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にマラスチノー・チェリー一個を加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注28】「ニックオンコクテール」とは「ニックスオウン(Nick’s Own)・カクテル」のこと。サヴォイ・カクテルブックにも紹介されている古典的なカクテルだが、今日のバーでの知名度はさほど高くない。前田氏のレシピはサヴォイがシェイク・スタイルでつくること以外、ほぼ同じ。スイート(伊太利)ベルモットの代わりにコアントローを使うレシピもある。名前の由来は不詳。…………………………………………………………………………………………こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/20
コメント(0)
-
【復刻連載】 「コクテール」前田米吉著 (4) カクテルレシピ<1>/2月17日(木)
コクテール 【編者おことわり】本書で登場するカクテルはアルファベット順でも、五十音順でも、ベース別でもなく、なぜか「イロハニホヘト順」となっている。なお、原著では頭の番号は付られていないが、復刻版では便宜上、番号を付した。また、原著のレシピでは副材料→ベースとなる酒の順で紹介されているが、復刻版ではベースとなる酒→副材料の順で紹介することにした。各カクテルには、可能な限り補足的な【注】を添えた。【注】の中で、比較の意味で頻繁に例をひいたハリー・マッケルホーン(Harry MacElhone)のカクテルブック「Harry’s ABC of Mixing Cocktails」は1919年の発刊、サヴォイ・ホテルのチーフバンテンダーだったハリー・クラドック(Harry Craddock)が著した「サヴォイ・カクテルブック(Savoy Cocktail Book)」は1930年の発刊である。1924年に世に出た本書「コクテール」は、その歴史的な二大カクテルブックのほぼ中間の時期に、はるか遠く離れた東洋の国で発刊された名著である。1.インカコクテール【注1】 調合グラスに約半分の氷を入れ之に プリマウス・ジン【注2】 三分の一オンス フレンチベルモット【注3】 三分の一オンス ドライパール・セリー【注4】 三分の一オンス オルゲートシロップ【注5】 二振り オレンジビタ 二振り を加え、バースプーンにてよく攪(か)き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之れに小さいパインアップルの一切れ及びレモン皮の小片を入れてすすめる。【注1】「インカ(Inca)コクテール」は、ハリー・マッケルホーンの本やサヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的なカクテルの一つだが、両書では、上記に加えてスイートベルモットも使うレシピとなっている。前田氏のレシピは何に依拠しているのかは不明。【注2】「プリマウス・ジン」は現在の一般的な表記では、「プリマス・ジン」(Plymouth Gin)。英海軍基地のあるプリマスで製造されている歴史と伝統あるジン。ギムレットのオリジナル・レシピで使用されたジンとしても有名だ。【注3】「フレンチベルモット」とは、今で言う「ドライベルモット」を指す。【注4】「ドライパール・セリー」の「セリー」とは「シェリー」のこと。「パール」とは現代の表記では「ペール(Pale)」。「ドライペール・シェリー」とは、残糖分が限りなくゼロに近いフィノ・タイプのシェリーのこと、或いはフィノに濃縮ぶどう果汁を少量加えたフルーティなシェリーのこと。【注5】「オルゲート(Orgeat)・シロップ」とはビター・アーモンド・シロップのこと。オルジェート・シロップとも呼ばれる。現在でも「MONIN(モナン)」社のシロップ・シリーズで入手可能。…………………………………………………………………………………………2.イミニテーブルコクテール【注6】 コクテールグラスに小さい氷の一塊を入れ之に オールドトム・ジンまたはドライジン 一オンス 砂糖 テースプーン半杯 アンゴスチュラビタ 一振り を加え、レモンの皮の小片を搾り込み、テースプーンにて静かに混和してすすめる。【注6】「イミニテーブルコクテール」は、現時点では前田氏の本以外では見当たらないカクテル。「イミニテーブル」とはどういう意味かは不明。英語表記の綴りで似たような言葉には「immutable(不変の、変えられない)」があるが…。…………………………………………………………………………………………3.インデアコクテール【注7】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ブランデー 一オンス アンゴスチュラビタ 一振り オレンジキュラソー 一振り マラスチノー 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、一個のマラチノー・チェリーを入れ、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注7】「インデアコクテール」は、現時点では前田氏の本以外では見当たらないカクテル。…………………………………………………………………………………………4.イディスコクテール【注8】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に アニセット 三分の二オンス アブサン 三分の一オンス アンゴスチュラビタ 二振り を加え、よくセーク(攪拌)したる後、コクテールグラスに注ぎ、之にパインアップルの小片を入れてすすめる。【注8】「イディスコクテール」は、現時点では前田氏の本以外では見当たらないカクテル。「イディス」も何を指すのかは不明。「セントイデス(St.Ides)」というハーブ系ベルギービールの銘柄があるが、このカクテルもレシピを見れば、ハーブ系の酒が中心なので、その辺りと関係あるのかもしれない。…………………………………………………………………………………………5.ロンドンコクテール【注9】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ロンドン・ドライジン 一オンス オレンジビタ 一振り ガムシロップ 一振り アブサン 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之にオリーブを加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注9】「ロンドンコクテール」は、サヴォイ・カクテルブックにも登場する古典的カクテル。前田氏のレシピはサヴォイのと同じだが、サヴォイはシェイク・スタイル。…………………………………………………………………………………………6.ロンツリーコクテール【注10】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に オールドトム・ジン或いはドライジン 一オンス フレンチベルモット 少量 を加え、稍(やや)久しくセーク(攪拌)したる後、コクテールグラスに注いですすめる。【注10】「ロンツリーコクテール」は、「ローンツリー(Lone Tree)」の名でサヴォイ・カクテルブックやNBAカクテルブック(1963年刊)にも紹介されているが、サヴォイやNBAのレシピ(ジン、ドライベルモット、スイートベルモット各3分の1ずつ、オレンジビターズ2dash)は前田氏のとかなり異なっている。…………………………………………………………………………………………7.ロブロアコクテール【注11】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に ライ・ウイスキー 二分の一オンス フレンチベルモット 二分の一オンス キュラソー 一、二振り アンゴスチュラビタ 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之に一個のマラスチノー・チェリーを加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注11】「ロブロアコクテール」(現代の表記では「ロブロイ(Rob-Roy)」)は、ハリー・マッケルホーンのカクテルブック(改訂版)や、サヴォイ・カクテルブックにも登場する代表的な古典的カクテルの一つ。後書の著者でもあり、サヴォイ・ホテルのバーテンダーだったハリー・クラドックが、1920年代前半に考案したと伝わるが、渡英前のクラドックが1910年代に米ニューヨークで考案し、渡英後にサヴォイ・ホテルで職を得てから発表したという説もある。 前田氏は、現代の標準的なレシピではスイートベルモットを使うところをフレンチ(ドライ)ベルモットを使い、さらにキュラソーも少し加えるなど、若干異なったレシピにしている。…………………………………………………………………………………………8.ロシングトンコクテール【注12】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に ゴルドン・ドライジン【注13】 三分の二オンス チンザノ(スイート)ベルモット 三分の一オンス オレンジジュース 少量 を加え、よくセーク(攪拌)したる後、コクテールグラスに注ぎ、之にオレンジの皮を浮かべてすすめる。【注12】「ロシングトンコクテール」は、サヴォイ・カクテルブックにも「ロージントン(Rosington)・カクテル」の名で紹介されている。前田氏のレシピはサヴォイにほぼ同じ。【注13】言わずもがなだが、「ゴードン・ドライジン」のこと。…………………………………………………………………………………………9. ロワイヤールコクテール【注14】 調合グラスに約半分の砕き氷を入れ之に オールドトム・ジン 三分の二オンス デュボンネット【注15】 三分の一オンス オレンジビタ 一振り アンゴスチュラビタ 一振り を加え、バースプーンにてよく攪き廻したる後、コクテールグラスに漉し、之に一個のマラスチノー・チェリーを加え、尚ほレモン皮の小片を搾り込んですすめる。【注14】ハリー・マッケルホーンの本やサヴォイ・カクテルブックにも同名の「ロイヤル(Royal)・カクテル」カクテルが登場するが、レシピ(ジン+ドライベルモット+チェリー・ブランデー+マラスキーノ)は前田氏のものと大きく異なっている。このレシピが前田氏の創作かどうかは不明。【注15】「デュボンネット」とは、赤ワインにキナの樹皮、オレンジの皮、コーヒー豆とスパイスを漬け込んで、樫樽で熟成させたリキュールで、欧州では食前酒として親しまれている。名前は、1800年代中頃に考案したデュボネ氏に由来する。現在では、単に「デュボネ」と表記されるのが一般的。…………………………………………………………………………………………10. ロングレンジコクテール【注16】 コクテールセーカに二三塊の氷を入れ之に 伊太利ベルモット【注17】 五分の二オンス アブサン 五分の二オンス ブランデー 五分の一オンス ガムシロップ 一振り アンゴスチュラビタ 一振り を加え、よくセーク(攪拌)し、レモンの皮を搾りたる二三滴の汁を以て内面を濡らしたるコクテールグラスに注いですすめる。【注16】「ロングレンジ(Long Range)コクテール」は、現時点では前田氏の本にしか見られないカクテルである。【注17】「伊太利ベルモット」とは、現在の「スイートベルモット」を指す。…………………………………………………………………………………………※復刻版監修者の能力不足のために不明の点が多々あります。もしご教示頂ける点がありましたら、メール(arkwez@gmail.com)でお寄せいただければ幸いです。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/17
コメント(0)
-
【復刻連載】 「コクテール」前田米吉著 (3)例言・原材料並びに器具/2月15日(火)
例言/原材料並びに器具 本書に掲ぐるコクテールの調合は、コクテールグラスに一杯、即(すなわ)ちコクテールグラス七分目(量に於いて一オンス【注1】)を単位として、其の何分の一或いは二と言う様に各種材料を調合したるものを、コクテールセーカ【注2】若(も)しくは調合グラス【注3】に入れ、能(よ)くセーク(攪拌)して之をコクテールグラスに注ぐ時は、氷の溶けたのとマラスキーノ・チェリー等を加えて、丁度コクテールグラスに八分目位になります。 是を以てコクテール一杯の定量とするので御座います。従って二盃、三盃、四盃と調進する時は各種材料を二倍、三倍、四倍するので御座います。書中の「一振り」とはストローの孔(あな)から振り出す二三滴【注4】を言うので御座います。 書中、調合グラスとは、ジョキの浅い形をなしたグラスの事を言えども、普通コクテールセーカの蓋(ふた)を取り除き、其の胴にて調合するを最も簡単とす。其の他グラス、スプーン等総じて客にすすめる器の外は能く洗浄し、清潔なるものなれば何を利用するも差し支えなし。素人仕事の道具倒れになっては詰まりません。 ▼バーに備ふべきコクテールに要する洋酒及其他の原料並に器具 フランスベルモット、イタリーベルモット、スコッチウイスキー、ブランデー、ピーチブランデー、アプリコットブランデー、ドム【注5】、ドライジン、オールドトムジン、スロージン オレンジキュラソー、ホワイトキュラソー、ウォヅカー【注6】、クレームデカカオ、クレームデヴァイオレット、グリンシャートリユーズ、エイローシャートリユーズ、マンダリン、マラスチノー、アニセット、ボルスクンメル【注7】 アミヤピコン【注8】、メドツク(ワイン)、ラインワイン、マデイラ、ノワイヨー【注9】、ジャマイカラム、ポートワイン、ホワイトポート、マラスチノーチェリー、平野水【注10】 オリーブ、シャンペン、オレンジビタ、アンゴスチュラビタ、ピパーミント、オルゲット、ガムシロップ、ライムジュース、グレープジュース、ジンジャエール、三ツ矢サイダー【注1】1オンスは約30ml(次回以降のカクテル・レシピにおいても、分量は原則としてオンス単位で表示されている)。【注2】「コクテールセーカ」とは言わずもがなだが、「カクテルシェーカー」のこと。【注3】「調合グラス」とは現代で言う「ミキシング・グラス」のこと【注4】「二三滴」の「滴」とはカクテルづくりの単位の「drop」のことと思われる。1dropは約0.2ml。【注5】「ドム」は、別名「ベネディクティン・ドム(DOM)」。27種ものハーブとスパイスが調合された世界最古のリキュールのひとつ。【注6】「ウオヅカー」は驚かされる表記だが、言うまでもなく「ウオッカ」のこと。【注7】「ボルスクンメル」の「ボルス」とは1575年にオランダ人ルーカス・ボルスによって創業された世界的なリキュール&スピリッツメーカー。「クンメル」とは香草系リキュールの「キュンメル」のことで、「ボルス」社では現在でもキュンメル・リキュールを製造・販売している。【注8】「アミヤピコン」とは「アメールピコン」のこと。リンドウの一種ゲンチアナを主成分にキナの樹皮、オレンジの果皮などを配合したリキュールである。「アメール」とは仏語で「苦い」の意。ピコンの名は開発者であるフランスの元軍人ガエタン・ピコンの名からとられた。【注9】「ノワイヨー」とは「クレーム・ド・ノワイヨー(Cr?me de Noyaux)」(桃や杏の核を主成分とするリキュール。アーモンドの風味を持つ)のことか。【注10】「平野水」とは兵庫県川西市平野地区で湧き出た自然の炭酸水のこと。1888年(明治21年)、明治屋が「三ツ矢平野水」の名で売り出した。その後1907年(明治40年)、帝国鉱泉株式会社が平野水を使って、この地で清涼飲料水の「三ツ矢サイダー」の生産を始めた。「三ツ矢サイダー」は後にアサヒビールに事業が受け継がれたが、平野地区でのサイダー生産は1954年(昭和29年)で終了している(出典:Wikipedia)。 ・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/15
コメント(0)
-
【復刻連載】 「コクテール」前田米吉著 (2)コクテールの傳説/2月13日(日)
コクテールの傳説【注1】 コクテールの起源は今を去る約百年前、英國アイルランド【注2】の某市に一人の富豪が在りました。此の富豪は当時流行の非常に優秀な一羽の闘鶏の持ち主で御座いました。而(しか)して此の富豪は又日本なれば小野小町とでも云う様な一人娘の娘が御座いまして方々から結婚申し込みが絶え間が御座いませんでしたが、此の娘は極めて父親に従順で、未だ誰にも婚約もなく、家事の手伝いなどをして居りました。 然るに某日、此の富豪が愛育して居りました闘鶏が見えなくなりました。サァ、大変。家中の人が総掛かりになって捜しますけれども、皆目行方が判りません。夜になっても鶏は帰って参りません。主人は非常に心配致しまして、夜の目も眠れません。遂に翌日になって主人は闘鶏の行方を捜すべく旅立ちました。而して処々方々尋ね廻りましたが、舌切り雀ならで遂に闘鶏の行方は知れず、尋ねあぐんで空しく家に帰りまして悲嘆の余り遂に床に臥(ふ)しました。 親孝行な美人の一人娘は非常に心配して父親に次のような事を申しました。「若(も)しも彼の闘鶏を探し出して連れて来た人がありましたら、私は其(その)人と結婚しましょう」と。父親は大変喜びました。そこで、其の事を新聞に広告しました。そうすると二三日たちますと、富豪の門前に馬に乗った騎兵中尉が参りまして馬から下りて、家へ案内を求めて主人に会いたいと申しますから、病臥して居ります父親に代わって、娘が面会を致しました。 ところがその騎兵中尉は美目(びもく)秀麗氣品高雅な貴公子で御座いましたので、処女の小町娘は唯恍惚として此の青年将校に見とれ、青年将校も又アイルランド一の美人に見惚(と)れ、互いに暫し言葉も出ませんでした。 やがて、騎兵中尉がマントの裏から取り出した物を見ますと、明け暮れ尋ねる秘蔵の闘鶏で御座いましたから大変。今迄(まで)で青年将校の美貌に見惚れて居りました娘は驚いて、病室の父親に闘鶏が帰った事を申しますと、父親も病床を飛び出して応接間へ行って、いきなり闘鶏を抱き上げ、青年将校に堅い握手を求めました。 厚く礼を言い乍(なが)ら見ますと、是れ又、娘にとっては三國一の婿殿。二人の喜びは元より、娘は闘鶏の帰った喜びよりも初恋の胸轟(とどろ)かせ、父の命ずる儘(まま)にサイドボールに有りつ丈(たけ)の酒を運んで中尉にお酌を致しましたが、嬉しさに手の舞い足の躍るをも知らず、氣も狂わん計りにて手当たり次第に色々の酒を注ぎ混ぜて青年将校にすすめました。中尉も又、此の佳人と結婚して多くの人の羨望となる嬉しさに、美しき尾を持って居る此の闘鶏を抱き上げて其の混合酒を乾盃しました。 青年将校は連隊に帰って此の事を吹聴致しました。而して其の無茶苦茶に注ぎ混ぜた酒が非常に美味かった事を話しました。そうすると此の事が連隊中の評判になって、其の混合酒を名づけて「コック(雄鶏)テール(尾)」と呼ぶ様になったのがコクテールの由来で御座います。其の後、医薬上や嗜好上より色々の混合法が研究されまして、今日の隆盛を来したので御座います。 因みに、傳説に依りまして、男女同席する時にはコクテールに限り、男子が先に飲んで婦人が後ちに飲むのが慣例になって居ります。【注1】カクテルという言葉の起源・由来については様々な説がある(主な説だけでも5つほど)。 →監修者のブログ「酒とピアノとエトセトラ」・2009年2月11日の日記 をご参照。ここで前田氏が紹介した説(挿話)は、1982年に初版が出版された「カクテル入門」(福西英三氏著)で紹介された説とよく似ているが、福西氏の本では場所が「英國アイルランド」ではなく、「アメリカの片田舎」となっており、若干の異同が見られる。もっとも、前田氏も福西氏も出典資料を示していないため信憑性は不明である。【注2】「英國アイルランド」という表記について怪訝(けげん)に思われる方もいると思うが、1924年当時アイルランドは「アイルランド自由国」と呼ばれ、独立国ではなく、英国の自治領であった。1938年にようやく英国から独立が承認され「アイルランド共和国」となったが、北アイルランドの一部は主に宗教上の理由で英国に留まったため、その後、カトリック・プロテスタント間の血なまぐさい紛争が最近まで長く続くことになった。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/13
コメント(0)
-

最近はまっている作家(3) 今野敏/2月12日(土)
最近はまっているミステリー作家として、池井戸潤、佐々木譲と紹介してきたけれど、3人目として今野敏も紹介すると予告しながら、多忙のために、大変遅くなって申し訳ございません。 ということで、最近読んだ今野氏の作品について、ひとことコメントとともに、独断での評価を★の数(★5つで満点)で紹介いたします(必ずしも最近の作品じゃないのも含まれていますが、ご容赦を…)。※本の表紙画像は基本的にAmazon上のものを引用しています。Amazon.Japanに感謝します。 「隠蔽捜査」 ★5つ ※2005年の作品。吉川英治文学賞新人賞を受けた。主人公は警察庁のキャリア官僚である竜崎伸也が、警察組織を揺るがす連続殺人事件に向き合い、解決していくという本筋の話と、麻薬に手を染めた息子にどう向き合うかという家族内の出来事が同時並行的に展開していく。 竜崎のエリート臭ぷんぷんとした姿勢にややムカツクけれど、そこは家庭内の不祥事(出世競争での汚点)ということで帳尻は合わせている。とにかく最後までテンポがよくて飽きさせない。テレビドラマ化されたらしいが、残念ながらうらんかんろは見ていない。 「果断 隠蔽捜査2」 ★5つ ※隠蔽捜査の続編。長男の不祥事で所轄署へ左遷された竜崎が、今度は立てこもり事件に立ち向かう。事態の打開策をめぐって警察内部で対立が表面化する中、竜崎は現場の指揮をとり、事件は解決したはずだったが、その裏にはとんでもない真実が隠されていた。2008年の山本周五郎賞と日本推理作家協会賞をダブル受賞した傑作。寝不足になること間違いなし。 「朱夏 警視庁強行犯係・樋口顕」 ★5つ ※ある日突然、妻が誘拐された警部補・樋口。脅迫状は公表されていない自宅の住所宛てに届いた。犯行に警察内部の人間が関わっている疑いが出てきたため、樋口は警察には届けず、信頼する友人の刑事・氏家に助けを求めながら、妻の行方を探し、救出するために立ち上がる。スリリングな展開で、まさに今野敏流・警察小説の真骨頂が楽しめる。1998年の作品。 「曙光の街」 ★4つ ※2001年発表の佳作。かつてKGBのスパイとして日本で活動していたヴィクトルは、ソ連崩壊で解雇され、失意のどん底にあった。そこへ、日本でヤクザの組長を殺す仕事の依頼を受ける。一方、ヴィクトル再来日の情報を得た警視庁外事課の捜査官たちは、ヴィクトル逮捕を目指す。ヤクザ、警察、ヴィクトル三者のスリリングな駆け引き・闘いの中で浮かび上がってきた驚くべき事実とは…。 「白夜街道」 ★3つ半 ※2006年発表の作品で、「曙光の街」の続編でもある。警視庁公安部の捜査官・倉島は、過去に因縁のある元KGBの殺し屋・ヴィクトルがひそかに日本に入国したことを知る。ロシア人貿易商のボディガードに雇われたためというが、倉島は本当の理由は別にあるとにらむ。貿易商が密会していた外務省官僚が謎の死を遂げ、ヴィクトルを追って、倉島はモスクワへ飛ぶが、追跡捜査の結末は果たして?。話のスケールは大きいが、若干の荒唐無稽感はぬぐえないのが減点理由。 「BEAT」 ★4つ半 ※警視庁の刑事・島崎は、「罠」にはめられ、銀行本店への家宅捜索情報を漏らしてしまう。銀行のスパイに仕立てあげれ苦悩する父親を救うために、17歳の息子・英次は無謀な行動に出た。ハイテンポで進む展開。父と子の絆が胸を打つ感動のラストシーン。とにかく面白い。この作品、近々WOWOWでドラマ化されるとか。2000年発表の傑作長編。 「特殊防諜班 連続誘拐」 ★3つ ※宗教団体教祖が被害者となる奇妙な誘拐事件が相次いで起こった。しかし無事解放された教祖たちは皆、事件のことをなにも覚えていない。しかし唯一、雷光教団教祖の事件は違った。首相官邸から秘密裏に事件の真相究明を託された真田は、誘拐事件の裏には巨大な陰謀が潜んでいることをつかむ。1986年発表の初期の作品。オカルトっぽい、いささか荒唐無稽な組み立て。今野敏もまだ若かったということか。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/12
コメント(0)
-
【復刻連載】 「コクテール」 前田米吉著 (1)序文/2月11日(金)
コクテール 前田米吉 著 (東京市四谷区・カフエライン発刊 大正十三年(1924)十一月十日 初版発行) ********************************************************************** 【復刻版監修者から】 1860年(万延元年)、横浜の外国人居留地に開業した「横浜ホテル」に我が国初のバーが誕生し、その半世紀後の1910年(明治43年)には、銀座に日本で初めての街場のバー「カフエ・プランタン」が生まれました。大正時代(1912~1926)に入ると、大正デモクラシーの雰囲気も相まって、大都市では相次いでカフエやバーが開店して行きます。本書はそうした世に出版された日本最初期のカクテルブックです。 著者の前田米吉氏は当時、東京・四谷の「カフエライン」という店に勤めるバーテンダーでした。本書「コクテール」では287種のカクテルのレシピを紹介されていますが、その内容(書き方)は実用に徹したものとなっています。洋酒に関する情報や材料が乏しい時代に、このような完成度の高い本を書き上げる苦労は並大抵のものではなかったと思います。故に本書は、「バー業界の先駆者の汗と涙の結晶」とも言えます。 不思議なことに、本書「コクテール」には、6年後に出版される歴史的名著サヴォイ・カクテルブック(Savoy Cocktail Book 1930年刊)のなかで、欧米では初めて紹介されたカクテルがいち早く、30数種類も!登場しているのです。なかには、明らかに著者ハリー・クラドック(Harry Craddock)のオリジナルと思われるカクテルも含まれています。大きな謎で、6年も前に遠い東洋の日本でどのようにレシピを知り得たのか、非常に興味をそそられるところです。 著者・前田氏は経歴等がほとんど分からない謎の人物ですが、「復刻連載」の監修者・編者である私は「前田氏はおそらく、『カフエライン』に勤める以前に、外国航路の客船でバーテンダーとして働いていて、同僚だった外国人バーテンダーや外国人乗客から直接、サヴォイ・ホテルのバーで1920年代につくられていた(印刷物として紹介される前の)カクテルについて細かな情報を得ていたのではないか」などと想像をかき立てています。そういう意味でも、この「コクテール」は実に味わい深い「読み物」だと思います。 本文中、旧かなづかい、古語的な用語・表現のうち、現在馴染みにくいものは可能な限り現代語法に直しましたが、時には、原文の良さ・雰囲気を伝えることに重きを置き、旧かなづかいのままにした部分もあります。補足的な説明・解説ができる部分があれば、末尾に【注】として付記しました。また、原著は縦書き表記ですが、復刻版では脚注に英語表記がしばしば登場するため読みやすさを考えて、横書き表記としました。 なお、編者の国語的能力の限界が故に、不明な部分は手を加えず原文のまま紹介したほか、当時のお酒、カクテル関係の専門用語で分からないものもそのまま紹介していますが、ご容赦ください。ご指摘・ご助言等があればご教示いただければ幸いです。********************************************************************** 「コクテール」發行に就いて コクテールは欧州戦後【注1】間もなく東京に芽生えまして、お客様の御愛用になる医薬上・衛生上・嗜好上乃至(ないし)交際上快く可からざる新しい飲み物で御座いましたが、震災【注2】の為め生活必需品にあらざるコクテールは一時その影を潜めました。が、段々東京の復興に連れまして、此頃又コクテールの御愛用が多くなりました事は誠に結構な事と存じます。 奢侈(しゃし)を戒め、勤倹を勤むるは勿論の事で御座いますけれども、徒(いたずら)に思想や生活問題の悲観にのみ沈んで向上を唱えないのは、個人としても発展の途ではありません。東京としても復興の意氣ではありません。又國家としても新興の策ではないと存じます。 この意味に於きまして寧(むし)ろ恐ろしき震災の記憶を新たにするよりも、過ぎ去ったことは忘れて仕舞い、希望ある将来を追求して大いに働き、大いに食ふと云うことが、今日の東京のお方に尤(もっと)も必要な事ではないかと存じます。 コクテールには医薬・衛生・嗜好或いは交際場に於きまして、必ずしも奢侈品とは申されません。一日の労務に依って得た一部を以(もっ)て、此の無量の快感を与える一盃のコクテールを傾けるのは同時に翌日の為に無限のお活動力を貯えるので御座いまして、如斯くにして個人も社会も國家も向上発展して行くのではないかと存じます。 閑話休題。コクテールは其の配合すべき各種飲料並びに香料等に一定の分量が極まって居りまして、此の分量が違っては医薬にもならず嗜好にも適しませんのみならず、却って身体に害があります。又、各種分量をコクテールセーカに入れてセーク(攪拌)するにも、一つの技術を要します。 そこで優秀なバーテンダーが居ない処のコクテールは多くお客様の嗜好に適しません。是はコクテールの流行が最近でありまして、其の知識が普及されて居りませんのと、研究すべき何等の材料も御座いませんので止むを得ない次第で御座います。 其の為め、多くのカフエー業者並びに一般の御家庭でも何かコクテールに関する著述を渇望して御出でになる矢先に、多年コクテールの研究者前田米吉さん【注3】が此の大方の御希望を満たす為め、其の蘊蓄(うんちく)を極めたバーテンダーの「六韜三略(りくとうさんりゃく)」【注4】とも申すべき所謂(いわゆる)「虎の巻」を開放して、茲(ここ)に此の処方を發刊する事になりましたのは勿論、一般御家庭に取っても天来の福音でありまして、同時に日本コクテール界の為め祝ばしき事で御座います。 因みに著者は当分、弊店のバーテンダーとして働かれますから本書に就き御氣付きの点は御遠慮なく御叱正賜り度く御願ひ致します。 大正十三年十月【注5】 カフエライン【注6】主人 天草 よし 識(しる)す【注1】「欧州戦後」の「欧州戦」とは第一次世界大戦(1914~1918)のことを指す。【注2】この「震災」とはもちろん、この「コクテール」発刊の前年の1923年に発生し、首都圏を中心に死者・行方不明者約10万5千人余という惨事となった関東大震災のこと。【注3】本書の著者である前田米吉氏については、その写真は本書に掲載されているものの、「当時、カフエラインに勤めていたバーテンダー」ということ以外、生年没年、経歴などはまったく不明の謎だらけの人物である(※その後2017年、本書監修者はご子孫と連絡をとる機会に恵まれ、生没年は判明しました。しかし経歴についてはまだ謎の部分も多く、もし前田氏に関して何か情報・手掛かりをお持ちの方は、ご一報くだされば幸いです。→ arkwez@gmail.com までお願いします)。【注4】「六韜三略」とは、中国古代の代表的な兵法書である「武経七書」のうちの「六韜」と「三略」を指す。紀元前11世紀、周の軍師・呂尚が編んだとされるが、著者については他にも諸説あるという。ちなみに呂尚は別名を「太公望」とも言い、釣り好きの代名詞として今日でもその名を残している。また「六韜」の中の「虎韜」は、今日で言う「虎の巻」の語源(由来)であるとされる(出典:Wikipedia)。【注5】この前書きが書かれた日付は「大正十三年十月」だが、本書が実際に発刊されたのは翌「十一月五日」だった。このため、「日本初のカクテルブック」の称号は、同年十月にいち早く出版された秋山徳蔵氏の「カクテル(混合酒調合法)」に譲ることとなった。【注6】本書の出版元でもある「カフエライン」は大正期に東京に数多く開店したカフエの一つだが、現在は存在していない。本の奥付によれば、住所は「東京市四谷区鹽(しお)町2丁目1番地」とある。「鹽町」は東京の旧町名専門サイトによれば、1947年まで存在した町名で、現在の地下鉄・丸の内線「四谷三丁目駅」付近だという。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/11
コメント(0)
-
「カクテル(混合酒調合法)」秋山徳蔵著:本文 Mの項、Oの項の脚注を修正しました/2月11日(金)
故・秋山徳蔵氏の「カクテル(混合酒調合法)」の内容を紹介するにあたって、うらんかんろが付けた脚注で、「分からないので情報をください」とお願いをしていたうちの一つが判明しました。 「M」の項の「モーニング・カクテル」と「O」の項の「オールドファッションド・カクテル」で、「ボカース」又は「ボカース・ビター」の名で登場していた材料についてです(うらんかんろが懇意にしているBARのマスターからの情報です。この場をかりて厚く御礼申し上げます)。 「ボカース」とは、1828年にドイツ系米国人のジョン(ヨハン)・ボウカーが製造・販売を始めたビターの銘柄「ボウカーズ・ビター」(Boker’s Bitter)のこと。かの有名な伝説のバーテンダー、ジェリー・トーマスも愛用していました。 英文サイトで調べた情報によれば、19世紀にはニューヨークではとても人気のビター銘柄だったとのことです。禁酒法時代の1920年代に製造中止となりましたが、近年、その味わいを再現した製品が再発売されています。 ※日記で紹介した本の脚注も修正しています。以上とり急ぎ、お知らせまで。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/11
コメント(0)
-
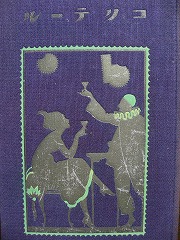
「コクテール」前田米吉著(大正13年刊):復刻版連載予告/2月10日(木)
日本最初のカクテルブックである「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年=大正13年=10月刊)について、私はその「復刻連載」を30回に渡って続け、先般、ようやく完結することができました。 しかしながら、秋山氏の本が世に出てからわずか1カ月後の同年11月に、前田米吉という方も「コクテール」という本=写真左=を出版しています(ハードカバーで約260頁)。 秋山氏の本が個々のカクテルの作り方をすべて文章だけで表現しているのに対して、前田氏の本は、約300種のカクテルについて、「***2分の1、***3分の1」というように、今風の分量表記で作り方を説明しています。だから、当時のプロのバーテンダーにとっては、前田氏の本の方がより実用的で、仕事に役立つカクテルブックだったに違いありません。 「コクテール」は定価「金五円」(末尾【注1】)と当時としては決して安くはなかった本ですが、数多くの飲食業界(とくにカフエやバー関係)の人たちに支持されて結構売れたためなのか、発売後にすぐ再版されています。 しかし残念ながら、前田氏の本もおそらくは戦前の段階で絶版となっており、現在では古書市場でも手に入れることは極めて困難です。私は、今回、幸運にも前田氏の本「コクテール」をお持ちのバーテンダーの方と出会い、「貴重な内容がこのまま陽の目を見ないのはもったいない。現在のバーテンダーにもその内容をぜひ紹介したい」とその趣旨を説明したところ、快くお貸しいただけました。 そこで、次回から秋山氏の本に引き続き、前田氏の「コクテール」の内容を出来る限り、忠実に紹介していきたいと思います。秋山氏の連載時にも記しましたが、出版から50年以上が経過しているため、出版元の著作権は切れています(一般的には、出版社に帰属する場合がほとんどとのこと)(写真右=「コクテール」の中で掲載されている前田米吉氏の顔写真)。 ただし、前田氏のご遺族がもし著作権を継承していた場合は微妙です。死後まだ50年が経過していなかった場合は、著作権侵害になる恐れがあります。前田米吉氏本人は生年没年不詳で、現在ではご遺族や関係者等まったく消息不明の方です。出版元で勤務先でもあった「カフエライン」も現在はありません。私自身は、前田氏のご遺族と連絡をとりたいと強く願っていますが、未だ叶っていません(末尾【注2】)。 万一、前田氏のご遺族からクレームがあった場合は、「前田氏の偉大で貴重な功績を後世に伝えるための連載で、私自身一切の利益は得ていないこと」を伝えて理解していただくつもりですが、ご理解を得られない場合は、その時点で連載は中止し、過去分についてもすべて消去しますので、あらかじめご了解ください。【注1】大正13年当時の「金五円」はどれくらいの貨幣価値があったのか。「値段史年表」(朝日新聞社刊)によれば、SPレコード1枚1円50銭、板橋の3LDKの家の家賃が5円20銭、小学校教員の初任給(月給)は12~20円だったといい、この本の値段は相当高価なものだったことがわかる。【注2】その後の2017年、筆者は幸運にもご遺族と連絡をとる機会に恵まれ、前田氏の生没年も判明(1897~1939)した。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/10
コメント(2)
-
浅草サンボア、今月21日オープン!/2月5日(土)
ホットなニュースです。銀座サンボアが、浅草に支店(浅草サンボア)を出すとのことです(サンボア・グループとしては13店目となります)。【ご参考】→ サンボア・グループ なんとオープンは間もなく、今月(2月)の21日とか。しかも毎日午前11時から店を開けるんだとか(まるで昼間から開いてる浅草の老舗・神谷バーみたい)。 さすが銀座のオーナーのSさん、なかなか出店場所の目のつけどころがいいですね。浅草は観光客も多いし、周辺には住んでる人も結構いるし、早い時間から開けてもきっとはやると思います。 今月、東京出張があるのですが、まだオープンより前なのが残念です。訪店は次回の楽しみにとっておきましょう。 【浅草サンボア】東京都台東区浅草1-16-8 電話03-6231-7994 午前11時~午後11時 水休(電話はまだつながらないと思います)
2011/02/05
コメント(0)
-
「カクテル(混合酒調合法)」秋山徳蔵著: (30)<完> 附緑/2月4日(金)
附録 この混成酒の調合法は、外國から伝来したものであるところから、その用いられる酒類も舶来のものに限られる傾きがありますが、ここに國産葡萄酒のあることを見逃すことはできません。 次に、國産葡萄酒中の「ビィー」コーザン・ワイン(蜂印香竄葡萄酒)【注1】をもって試みた。存外に優秀な風味と気分を求め得た七種の混成酒調合法を附記して、國産奨励の一端とします。 コーザン・コッブラー(Kozan Cobbler) まず、ごく細かに砕いた氷を、普通の水呑の中に入れておき、別に小さい調合器の中へ別の砕き氷を三分の一位まで入れて、砂糖小匙で一杯と「ビィー」コーザン・ワイン一ジガーを加え、キョラサオ二三滴をたらします。充分に振蕩して前に用意しておいた水呑の中へ漉してうつし、水か或いはソーダ水を九分目までつぎ入れ、レモンかオレンジの輪切一片を浮かすか、又は季節の果実を浮かし、麦稈をさしてすすめます。 コーザン・カクテル(Kozan Cocktail) 調合器に砕き氷を入れ、「ビィー」コーザン・ワイン二分の一ジガーと、オールド・トム・ジン二分の一ジガーを入れ、アンゴスチュラ・ビター二滴と、キュラサオ(白色の分)二三適とを加え、充分に振蕩してカクテル・グラスに漉してうつし、レモンの皮一そぎを押しつまみ、浮かしてすすめます。 コーザン・フリップ(Kozan Flip) 小さい調合器に砕き氷を入れ、砂糖小匙で一杯と鶏卵の黄身だけ一個分を加え、一寸(ちょっと)かき混ぜ合わせてから「ビィー」コーザン・ワイン一ジガーを入れ、充分に振蕩してフリップ・グラスに漉してうつし、ナツメグほんの少しをおろしかけてすすめます。 コーザン・フロート(Kozan Float) ソーダ水呑に氷の塊一個を入れ、壜(びん)詰のレモネードをつぎ入れるか、又はソーダ水呑に砂糖大匙で一杯を入れ、水二匙を加えて溶かし、レモン一個の露を搾りこみ、一度かき混ぜ合わせてから水かソーダ水を七分目までつぎ入れ、更によくかき混ぜ合わせて「ビィー」コーザン・ワイン一ジガーを浮かし、麦稈をさしてすすめます。 コーザン(ホット)(Kozan, Hot) 水呑に砂糖小匙で一杯を入れ、「ビィー」コーザン・ワイン一ジガーを加え、熱湯を八分目までつぎ入れ、丁香【注2】一芽と、レモンかオレンジの輪切一片(きれ)を浮かしてすすめます。 コーザン・ピック・ミー・アップ(Kozan Pick Me Up) シェリー・グラスに「ビィー」コーザン・ワイン三分の一ジガー、フレンチ・ヴェルモット三分の一ジガー、およびチェリー・ブランデー三分の一ジガーを、右の順序で順々につぎ入れてすすめます。 〈注意〉これは、自然に交じり合うところに妙味があるので、わざわざ混ぜ合わせてはなりません。 コーザン・パンチ(Kozan Punch) 水呑に氷の塊一個を入れ、砂糖小匙で一杯半を加え、レモン半個分の露を搾りこみ、「ビィー」コーザン・ワイン一ジガーを加え、ソーダ水を九分目までつぎ入れ、よくかき混ぜ合わせ、レモンかオレンジの輪切一片を浮かし、麦稈をさしてすすめます。【注1】「コーザン・ワイン」とは、「電氣ブラン」で知られる浅草の老舗「神谷バー」の創業者・神谷伝兵衛(1856~1922)が、1885年(明治18年)、輸入ワインを原料とし、日本人の好みに合わせて蜂蜜を加えて調製し、「蜂印葡萄酒」(翌年、「蜂印香竄葡萄酒」と改名)の名で売り出した甘口ワイン。海外でも高い評価を受けたという。「香竄」(こうざん)の名は多芸多趣味に身をやつしていた神谷の父の雅号に由来し、豊かな芳しい香りが隠れ忍んでいるという意味も込めたという。 神谷はその後、1898年(同31年)に茨城県牛久市にワイン醸造所「シャトー・カミヤ」を開設した。「蜂印香竄葡萄酒」は現在でも、神谷バーにおいて「ハチブドー酒」の名で、通常のワイン(カミヤワイン)とともに販売されている(出典:Wikipedia)。【注2】「丁香(ちょうこう)」とはクローブ(Clove)のこと。クローブはフトモモ科の植物で、その花蕾を乾燥させた香辛料。日本には6世紀にすでに輸入されていたといい、正倉院の宝物にも残されている。現代では「丁字(ちょうじ)」または「丁子」という表記が一般的。 完 ※長らく連載してまいりました「秋山徳蔵著:カクテル(混成酒調合法)復刻版」は、今回をもって終わります。あらためて、80年以上も前に、日本においてカクテル発展の礎を築いた秋山氏の多大なる貢献に対して、心から敬意を表したいと思います。 この連載が、こうした先人たちの努力に光を当てる機会となり、その貴重な研究成果が現代のバーテンダーの心に刻まれ、次世代へ継承されていくならば、復刻版監修者としてこれに勝る幸せはありません。本連載が日本のバー業界の発展につながることを心から願ってやみません。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/03
コメント(0)
-
「カクテル(混合酒調合法)」秋山徳蔵著: (29)本文 Wの項/2月2日(水)
W ウォーターメロン・ア・ラ・モード(Watermelon a la Mode) まず普通より強い「ブランデー・パンチ」六合ほどをつくり、別に熟した座りのよい大水瓜一個を選び、へたの方を八分の一位の辺で横にはつって蓋(ふた)を取り、その切り口から前に用意して置いた「ブランデー・パンチ」を、徐々に一杯につぎ入れます。 はつり取って置いた蓋をして元の形に直し、砕き氷で囲んで約三十分間乃至(ないし)一時間を冷やして置き、後、ナプキンを折り畳んで敷いた盆の上にのせ、別にグラス、スプーン、ナイフ、フォーク、およびナプキンを添えてすすめます。 ウェリングトン・パンチ(Wellington Punch) これは「B」の項で説明しました「ブランデー・パンチ」に、ストロベリー・シロップ一注と、よく熟した苺(いちご)二つ三つを浮かしてすすめます。 ウイスキー・エンド・ビター(Whisky and Bitter) グラス・ウイスキー・サァワルに、アンゴスチュラ・ビター二三滴をたらし、軽く流しまわして余分のビターを捨て、別にウイスキーを壜のままと、氷水を添えてすすめます。 ウイスキー・コッブラー(Whisky Cobbler) これは「C」の項で説明しました「クラレット・コッブラー」の場合のクラレットを、ウイスキーに代えるほか、すべて同じに調合してすすめます。 ウイスキー・カクテル(Whisky Cocktail) 調合器に砕き氷を入れ、トッデー・ウォーター小匙で一杯とオレンジ・ビター二注、アンゴスチュラ・ビター二滴、およびウイスキー一ジガーを入れ、充分にかき混ぜ合わせてカクテル・グラスに漉してうつし、レモンの皮一そぎを押しつまんで浮かし、別に氷水を添えてすすめます。 ウイスキー・カクテル・ファンシー(Whisky Cocktail Fancy) まず、カクテル・グラスに砕き氷を一杯に詰めて置き、別に小さい調合器に砂糖小匙で四分の一杯を入れ、水半匙を加えて溶かし、砕き氷を二分の一位まで入れます。 次にキュラサオ一注と、アンゴスチュラ・ビター二滴、およびウイスキー一ジガーを入れ、レモンの皮一そぎを押しつまんで加え、充分にかき混ぜ合わせて、前に用意して置いたカクテル・グラスの氷をすてて、その凍ってる中に漉してうつし、季節の果実を浮かし、別に氷水を添えてすすめます。 ウイスキー・パンチ(Whisky Punch) これは「B」の項で説明しました「ブランデー・パンチ」の場合のブランデーを、ウイスキーに代えて調合するほか、すべて同じであります。 ウイスキー・サァワル(Whisky Sour) これもまた「ブランデー・サァワル」の場合のブランデーを、ウイスキーに代えて調合します(「B」の項参照)。 ウイスキー・トッデー(Whisky Toddy) これには、冷たいものと、熱い調合法とがありますが、いずれも「B」の項で説明しました「ブランデー・トッデー」の場合のブランデーを、ウイスキーに代えるほか、すべて同じに調合してすすめられるのであります。 ホワイト・ロック・ハイボール(White Rock Highball) ソーダ水呑に氷の塊一個を入れ、別に好みの酒を壜のままと、ホワイト・ロック・ウォーターを添えてすすめます。 ホワイト・サタン(White Satin) これは、過去の英国人等が「ジン」を呼ぶのに用いた遺語です。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/02
コメント(0)
-
「カクテル(混合酒調合法)」秋山徳蔵著: (28)本文 Vの項/2月1日(火)
V ヴァニラ・パンチ(Vanilla Punch) パンチ・グラスに氷の塊一個と、コギャク一ジガーを入れて置き、別に中位の調合器に砂糖小匙で一杯を入れ、ゼルツェル・ウォーターかまたは水二匙を加えて溶かし、次にレモン二個の搾り汁と、クレーム・ド・ヴァニュ一ポニー、ゼルツェル・ウォーターかまたは水をつぎ入れます。充分にかき混ぜ合わせて、前に用意して置いたパンチ・グラスに漉してうつしてすすめます。 ヴァニラ・クリーム・パンチ(Vanilla Cream Punch) ソーダ水呑に砂糖小匙で一杯を入れ、水二匙を加えて溶かします。次にコギャク一ジガーと、クレーム・ド・ヴァニュ一ポニーとを加え、砕き氷を三分の二位まで入れ、乳酪(クリーム)を九分目までつぎ入れ、静かによくかき混ぜ、麦稈をさしてすすめます。 ヴェルヴェト・ガーフ(Velvet Guff) シャンパンと、スタウトとを壜のまま冷やして後、半々もしくは好みの分量に合わせてすすめます。 ヴェルジン・カクテル(Ver-Gin Cocktail) 調合器に砕き氷を入れ、オレンジ・ビター一注か二注と、イタリアン・ヴェルモット二分の一ジガー、およびホワイト・クロッス・ジン【注1】二分の一ジガーを加え、充分にかき混ぜ合わせてカクテル・グラスに漉してうつし、レモンの皮一そぎを押しつまみ、浮かしてすすめます。 ヴェルモット・カクテル(Vermouth Cocktail) 小さい調合器に砕き氷を入れ、オレンジ・ビター二注とアンゴスチュラ・ビター二滴、フレンチ・ヴェルモット四分の三ジガー、およびイタリアン・ヴェルモット四分の一ジガーを加え、充分にかき混ぜ合わせてカクテル・グラスに漉してうつし、レモンの皮一そぎを押しつまんで浮かし、別に氷水を添えてすすめます。 ヴェルモット・フラペ(Vermouth Frappe) 小さい調合器に砕き氷を四分の三位まで入れ、好みのヴェルモット一ジガーを入れて充分に振蕩し、カクテル・グラスに漉してうつしてすすめます。 ヴェルモット・ゴムメ(Vermouth Gomme) ソーダ水呑に氷の塊一個を入れ、ガム・シロップを好みにより二注か四注とフレンチ・ヴェルモット一ジガーを加え、サイフォン・ソーダ水か、又は好みの沸騰水を九分目までつぎ入れ、静かに充分にかき混ぜ合わせてすすめます。 ヴィクトリア(Victoria) 小さい調合器に砕き氷を入れ、クレーム・ド・ヴィオレット二分の一ポニーと、アブサント二分の一ポニーを入れ、充分にかき混ぜ合わせ、ポニー・グラスに漉してうつしてすすめます。【注1】この「ホワイト・クロッス・ジン」は詳細不明です。何か情報をお持ちの方はメール(arkwez@gmail.com)でご教示いただければ幸いです。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2011/02/01
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆
- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…
- (2025-07-15 05:52:26)
-
-
-

- イタリアワイン大好き!
- ヴェネト州の陰干しブドウで造る華や…
- (2025-10-11 11:01:01)
-
-
-

- 中国茶好き集まって!
- 2025/10/4-5 世界茶文化展
- (2025-10-03 16:52:58)
-







