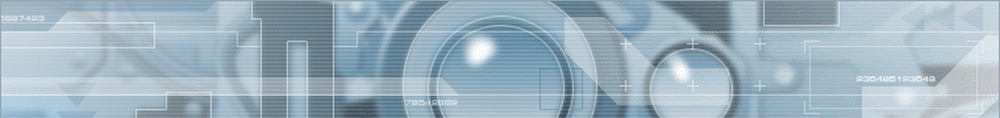2009年01月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
漱石にできたこと・できなかったこと
鴎外が明治国家と一体化したかのようにヨーロッパそのものを学び取ろうとしたのと対称的なケースが漱石であった。いやいやながらロンドンに赴き、ほとんど引きこもり状態に近かった。 にもかかわらず、結果としては漱石は自我というものにこだわり、ひとのこころの深みを探りえたということになっている。 坂口安吾だったかが漱石を批判したことがある。 登場人物の苦しみ、それによって深みが増しているともいえるのだけど、自我の苦しみ以前に、たとえば家庭なら家庭において、男と女のつながりを強めさせ、愛欲にひたむきになることで、漱石文学の苦悩というのは解消されていたのではないか。その意味では偏った文学である(まあ、偏っていない文学なんて捜すほうがムズカシイかもしれないけど)。過ちだらけの藤村のジンセイを見よ。 そんなことばがずっとわたしの喉にひっかかっていた。 ところが眼からウロコが落ちた。 もともと漱石は漢文学の出である。漱石にとって文学とは「男と男」の世界である。 だから漱石、英文学に面食らったわけである。ジェーン・オースティンやらブロンテ姉妹はものの見事に「男と女」の世界になっている。つまり近代文学とは「男と女」との物語として要約できる。漱石は、それを理解しようと試みたうえで、それでも男対女にあらがい続けたのではないだろうか。その抽出性にしてはじめて漱石文学の達成があったのかもしれない。ただでさえ、漱石は奥さんとのつながりにしろ、母親とのことにしろ、どこか女性嫌いのところがありそうだ。 上記の話は、小森陽一の「春樹論」およびそのなかで引用されている木村美苗ペーパーに拠っている。 (2007/03/13)
2009.01.31
コメント(0)
-
個人のヒミツと国家の秘密
ドイツ映画「善き人のためのソナタ」を御覧になったかたが何人かいらっしゃって、口々に称賛していらっしゃる。これ、オスカーの外国映画賞も獲った。 二十年ほどまえの、ひとびとの盗聴、密告の記録がすべて保存してあり、だれがだれに対してどういう密告をしたかわかるものらしい。疚しいところのあるひとにとっては、たまったものではない。 個人のヒミツとはみなされず、時代の証言とかいうふうに見なされるのだろうか。 ひるがえって、「ちくま」1月号のなだいなだの連載コラムによると、あの米国公文書の公開の件が触れられている。 戦後、CIAは自民党に秘密資金援助をつづけていたという。その中心はアンポをめぐってのことであった。しかし、ライシャワー元駐日大使は64年の段階で、この資金援助を中止したほうが妥当だという報告書を時のジョンソン大統領に送っていたのだという。 そのライシャワー報告書には、ニホンのだれにどのくらいの額の資金が渡っていたのか、記してある可能性がある。 それが公開された場合に、自民党にとってどれだけの打撃になることか。それがずばりこの公文書の公開を渋る理由である。ここでは秘密は守られる。 なんか合点がいかないな。 (2007/03/09)
2009.01.30
コメント(0)
-
イタリア「内戦」が残したもの
パヴェーゼの怪物発生論についてもうすこし触れます。 第二次大戦でおなじくファシズム陣営を組みながら、ニホンとイタリアはあまりにも大きなちがいがあった。 そのひとつは、ニホンではオキナワを除けば実質的に肉弾戦というか、混戦は避けられた。しかしイタリアでは、国土全体が二分される。隣人同士が、家族までもが陣営を異にした例がすくなくない。その争いは悲惨である。その争いの苛酷さ、あるいは体制への反抗というふうにも取れるが。 なぜこれほどまで、ひとびとは敵対し、憎しみあい、争うのか。その起源というか神話的理由づけを、パヴェーゼもいっしんに考え込んだというわけらしい。パルチザンに属していたパヴェーゼは、争いから抜け落ち、山にこもって神話に身をゆだねたということらしい。 それがパヴェーゼの生き方であった。パヴェーゼは現実との接し方にゆがみを感じ、悲劇的結末へと至る。 パヴェーゼには「生きるという仕事」という日記文集があって、スペイン語版を持っているけど、未読。 残念ながら、わたしはいまにいたるまでカルヴィーノのよい読者になりえていないのだけど、このふたり、基本的にはおなじような体験をし、おなじような深さの思いをたどってきたはずで、結果としての作品傾向のちがいがどんなところから出てきたのか、興味は尽きない。 この機会に触れておこうと思う。 ニホンでのいわゆる、きけわだつみのこえシリーズは、日本的ウエットな感性にひたされている。いわば怨み節である。悔いの記録である。 しかしイタリアでは、いくら正規軍(ファシスト)に徴集されようと、自分の信念しだいで離脱し、パルチザン側に加わっていった。ニホンとまるっきりちがう。 この件、むかし富山房新書かにイタリア抵抗戦線の話として書簡などから成立っていた。これを訳したのもK先生であった。 (2007/03/08)
2009.01.29
コメント(0)
-
怪物あらわる。。。。。
なぜ怪物というのは、現れたのか。 かつてニンゲンは好きなときに生きることができた。自分の思いとおりに生まれたり、死んだりできた。 つまり、むかしのニンゲンは神々とほぼおなじだったのだ。 もちろん、神々はねたましい。 神々は怪物をニンゲンに立ち向かわせた。ニンゲンは、怪物と、あるいはニンゲン同士で争うことになる。 南イタリアの神話byチェーザレ・パヴェーゼbyK先生。 細部はよく思い出せないや。 ン十年前のクラスで聴いたことだからね。 パヴェーゼ全集はかつて、晶文社が刊行していたけど、途中で挫折。集英社がおいしいところをもぎる。 その後、音沙汰なかったけど、岩波文庫から続けて出始めてる。K先生の顔はやはり広いのかな。 (2007/03/06)
2009.01.25
コメント(0)
-
だれもが知っているが知らないことにしている米国のヒミツ
またナルコの話なんですが。 米国の反メキシコ人不法移民への風当たりはますます強くなるばかり。お金もじゃんじゃんつぎ込む。国境パトロール隊員の増員。レーダー、やら無人機やら、高い壁を築くやら。なんか眼の敵にしている。 たしかに米国の地域によっては影響が現れているようで、不法移民者が眼に見えて減ったところもあるらしい。 しかし、あらかじめ分かっていたように、単純労働者の不足が目立ってきて、一部農園などはかなり影響をこうむっているらしい。 ついには刑務所から囚人を引き出して、強制労働的に働かせる場合もあるという。ここまでこなくては分からないのか。 一方で、ラテンアメリカのドラッグは、潤沢に(!)米国に届いている。もちろん、発見、摘発される量もかなりのものだが、メキシコ・米国国境をドラッグが渡っているのは紛れもない事実。つまりボーダーパトロールの有効性とはどこにあるのか? つまり、つまり。。。。いかに米国のボーダーに恣意性が存在するか。 (2007/03/03)
2009.01.23
コメント(0)
-
スコット・フィツジェラルド
このところ、ハルキ訳グレイト・ギャッビーを読んでいらっしゃるかたたちがちらほらいる。 べつにそれにのせられたわけではないのだけど、わたしも初めて読んでみた。もちろん映画のほうはん十年前に観ているが、ほとんど覚えてない。このあいだ、ミラ・ソルヴィノ主演のヴァージョン、見逃した。ミア・ファローより軽薄そうでよかったかもしれない。 それでわたしが読んだのは、昔の野崎孝訳。 それでひとこと、あんまりおもしろくない。男のほうに重きを置くか、女のほうこそ意味があるのか、それとも語り手の息遣いに注目するべきなのか、あまり波長があわなかった感じ。 ついでに、ということもないだろうけど、短編集も読んでしまった。角川文庫版の「雨の朝パリに死す」。原題のバビロン再訪とはえらいチガイだけど。 短篇のほうが口あたりがいいんじゃないかな。ギャッビーだって、もっと贅肉とって、締まった作品にしたほうがいいんじゃなかったかな。 どっちみち、ストーリーでなく雰囲気で読ませるものならば、その長さなんて二の次かもしれないけど。 それで、フィツジェラルドを読んだホントの理由とは。。。 ホセ・ドノソの「隣の庭」(邦訳あるみたい)の冒頭にフィツジェラルドが出てくるという単純な理由なのでした。 (2007/03/02)
2009.01.22
コメント(0)
-
七十三歳
このところ、きな臭い話がつづく。 ドラッグシンジケートの横行に業を煮やした(と、何気なく書いたけど、これ、間違ったことばの使い方みたいね)政府は、軍関係を前面に出して戦いを挑む。 いみじくもこのあいだ、軍関係の給与の大幅アップが告知されたばかりで、他の部門で不平不満の声が高まっているのだけど。 勘ぐれば、はたして軍の配置はドラッグ関係と直面させるだけでなく、地方の社会的不満分子を意識したものだとの声もある。 ということで軍関係が前面に出ている。それは、ごくろうなこともあるだろうが。。。 ベラクルスの原住民系の部落では、ひとりでいた七十三歳のおんなのひとが、日曜にレイプされた挙句、月曜に死亡。 発見されたときは、さるぐつわをはめられ、全身、縛られた状態。 そうですね。。。絶句、というところだろうか。 それなりに事情とか経緯とかあるのだろう。 ことは簡単ではないのかもしれない。 これは昨日の記事で、今日は四人の兵士が逮捕されたという記事。 地元民はもちろん激怒していて、道路を封鎖したり、軍に抵抗しようとしている。 繰り返すが、これはタイヘンなこと。 しかし、聖なる国軍にまつわること、大きなニュースにはできない。知らないひとも大いにちがいない。 これは、ニホンからはるか彼方の山奥の出来事だと考えないほうがいいと思う。オキナワやらどこやらで、おなじようなことはいくらでも発生しているし、なにかより本質的なことなのではないだろうか(バルガス=ジョサの「パンタレオンと女たち」をあげるまでもなく)。 これをよくあることと思うか。こだわったほうがいいことだと思うか。ひとによってまちまちかもしれない。 おんなのひとの最後のことばはこうだった。 "Los soldados se me echaron encima" (兵隊さんにやられたのよ) (2007/03/01)
2009.01.21
コメント(0)
-
国家の肥大化vs個人の自由?
これは、先のリバタリアンについてのメモの続き。 これを取り上げる理由は、朝日新書から、蔵研也「リバタリアン宣言」が出版されたから。 PR誌「一冊の本」二月号には、松原隆一郎と香山リカによる「リバタリアンをめぐって」、および著者本人による「21世紀の思想」というコラムが掲載されています。 リバタリアンというのは、「極小の国家と最大の自由を目指す主張」なのです。 この用語は、わたしはあまり知りませんでしたが、まずあのネオリベラリズムのバリエーションなのではないかと思ったのでした。まずもって勝ち組エリートによる主張という線からして。 もうかなり前から、いまの世界は経済優先で政治は遅れているとかいわれています。政治のほうも、国際関係など問題が多いわけですが、やはり経済の移り方は、予測しにくく、かつ劇的なケースもあります。でも、こういう総論的なことをべらべら喋っていてもしかたがない。 「個人の自由を軸にして国家・政府の役割を再編すること」。 たとえば蔵さんは、年金的蓄えは国家にまかせるものではなく、個人で用意するべきもの。国家では、けっしてまかないきれるものではない、なぜなら世代間の調整ができないから、等。 医療についても、国家的コントロールはやめて民間にその育成もまかせたほうが適当。そうでもしないと、医療の地域格差は埋められない。 教育も私立学校化を進めるべき。カリキュラムにも柔軟性をもたせる。 外国人労働者問題(在日朝鮮人問題もおそらく含まれるのでは)、も現在のような政府によるコントロールがあっては、社会制度から疎外されつづけるばかり。とりわけ、ニホンの排外性は有名だし。 リバタリアンには、国家は個人の自由の制約にのみ没頭し、「硬直化・官僚化・非人間化しがちである」という認識があるようです。 ここでわたしがひとつ、思いついたのは、たとえば世界的な性の自由化です。 ゲイ、あるいは同性婚、性の転換、より大幅なポルノの自由化、等。おそらく、かつての米国にあったようにswapのみならず、一夫一婦制の崩壊にまで至るのではないでしょうか。 個人の自由、個人の嗜好は擁護されるべきだから。 でも、たとえば香山リカさんは、リバタリアンに異議を投げかけます。 「リバタリアンが前提とする社会とは、そこに参加する個人に 情報収集力と自己決定能力があり、自己責任で行動できること」 そんなに自己とは無邪気に自らを信頼できるものなのでしょうか。 たとえば、男性から女性になろうとする米国人を描いた「トランス・アメリカ」という映画では、性変換をするまえに、もちろん本人は悩みます。自分の性的アイデンティティに納得ができない生き方をしてきたが故の決定なのでしょうが、じつはほかの要素もあるらしく、変換後、けっして後悔しないという保証はありません。 まだ語るべきことは多いと思うけど。 世界的にみて、ニホンは政府の介入が多いと思う(部門にもよるかもしれないけど)。そこでは、リバタリアンは反面教師にはなるかもしれない。 しかし、自分のやることに全然、自信がもてず、ひとの後で右往左往することしかできないひとも多い。わたしみたいな負け組みにとっては、もう生きる希望はナイのかね?(言いすぎかな?) ということで、今夜もあれこれくよくよと悩んでおります。。。 (2007/02/25)
2009.01.19
コメント(0)
-
リバタリアンについて考えるまえに
いまのニホンはだれが見ても、格差社会になりつつあるらしい。なぜなら、いつかは勝ち組になれるかもしれないという幻想をもてるからなのか。 とくに若者。いまの若者は何を考えているのか、数日まえにも触れた。しかし、あえて一般化するのは危険がともなうのだろう。 リバタリアンなることば、ほとんど知らなかった。 しかし、それほどめずらしいことばではなくなっているらしい。 「民間人に自発的な経済あるいは慈善活動による問題解決を目指すのがリバタリアン」らしい。 あるいは、「個人の自由を軸にして国家・政府の役割を再編すること」。 いまの若者、その大部分は、かつての「独身貴族」とはうってかわって、ワーキングプアに近いような。 なぜ黙っているのか。 一説によると、ユニクロやら百円ショップなど、ワーキングプアでも一応、暮らしていけるインフラがあるかららしい。 そんなものだろうか。 なぜコイズミさんを若者が支持したのか。 「オモシロいから座布団一枚」的発想だったのではないか。 以上、松原隆一郎と香山リカの対談に基づいている。PR誌「一冊の本」2月号所収。 (2007/02/23)
2009.01.18
コメント(0)
-
フィエスタの功罪
ニホンにいたころ、週末は何してたんだろう。たいていはひとりでぐだぐだしてたと思う。けっこう人恋しいときもあったはず。 ところが、ヒスパニック圏にはいると、事情が一転する。フィエスタに次ぐフィエスタ。金曜の晩、土曜、日曜なんてフィエスタをかけ持ちすることも少なくない。 わたしもはじめのころは、物珍しさもふくめて、フィエスタはおもしろかった。かなり貴重な体験でもある。まあ、それも、だれと行くかにもよるのだけど。 フィエスタの価値は、ともだちのともだちは、ともだちで、そのともだちもまたともだち、という論理。フィエスタで得る人脈というのは、侮りがたいものがある。 それにフィエスタは何といっても、パートナー探しに役立つ。ニホンのようなお見合いなんてあるわけないから、刹那的パートナーにしろ、永続的パートナーにしろ自らの手で捜し出さなくてはならない。(アタリもあればハズレもあるのは万国共通だけど(爆)) しかし、メキシコのフィエスタに関してはあまりにもワンパターン。 脂ぎった食事を肩をすくめて食べ、クンビアやらノルテーニャの騒々しい音楽につきあう。大音響だから、まともな話なんてできない。はてはニホンとおなじで、おれの酒が呑めないのかよ、なんてことにも。 踊れれば踊れたで、いちおう、愉しめるが、それも限度がある。ああ、それだったらウチで映画観てたり、本読んでるほうがいいなあ、うらめしやあ~~、ということになる。 これはわたしだけのことなのか? いやあ、今日のCNNに大胆なニュースあり。 「結婚式に招待しないで」と新聞広告 アルゼンチン 2007.02.20 Web posted at: 17:22 JST - REUTERS ブエノスアイレス(ロイター) 毎週末ごとに結婚式に招待され、お祝いに駆け付けるのに疲れ果てた妻がこのほど、アルゼンチンの全国紙に、「結婚式に招待しないで」と訴える新聞広告を出した。 広告を出したのは、アドルフォ・カバレーロさん(66)。有力紙ナシオンには、「私たちの予定はもういっぱいで、前もって私どもの願いを理解してもらいたい」との書き出しで、招待を受けても出席出来ないと訴えている。 カバレーロさんがナシオン紙の記者に語ったところによると、数十人のいとこの子どもたちや友人、カバレーロさんの弁護士事務所の顧客などから、毎週毎週、山の様な招待状が届くという。 アルゼンチンの結婚式は長時間にわたることで知られており、カバレーロさんは週末のほとんどを、結婚式の出席に時間を取られているという。 特に、最近では郊外での結婚式がはやっており、移動時間も含めると、拘束時間は12時間にも及ぶという。 カバレーロさんは、「朝の5時まで踊りたい若者にとっては楽しいのだろうが、わたしは疲れてしまって、翌日にテニスしたくても、動けない」とぼやいている。 以上。。。 はいはい、その気持、よくわかります。 わたしの知り合いにもアルゼンチン通がすくなくないけど、いやあ、アルゼンチンのフィエスタも聞きしに勝るものらしい。からだの仕組みがちがうのか、ぜんぜん酔わない。コルドバに滞在していたわたしの先生のひとりは、「いやあ、アルゼンチン人に張り合おうなんて気はすぐうせました。フィエスタがおわるまえに、そそくさと逃げ出します」とのことであった。 フィエスタといっても、たとえばコヨアカンとかの文化人系のフィエスタなんて、それこそ話自体が盛り上がる。 だいたい欧米系のフィエスタって、話中心じゃないかいな? そりゃあ、破目をはずすこともあるだろうけどさ。 まあ、話すことを持ってないと、話中心のフィエスタって成立たないわけだけど。 (2007/02/22)
2009.01.17
コメント(0)
-
世代論の試み
某文藝時評において、83年、84年生まれのモノ書きの内面に少々、触れている。 http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20070220bk01.htm ところで青山氏はインタビュー「流れゆく世界を見つめて」(文学界)でこう語っている。「ちゃんとモノが考えられるようになってからは、ずっと世の中は下り坂と言われていた気がします。そもそもいい時代を知らないわけですから、暗いという感覚もないんですよ」 社会に対するこの距離感は、バブルの記憶を持たない彼女ら世代に共通のものであるのかも知れない。日常を見つめる静かな視線を備えた島本氏の新作にも、この世代に特有の空気は確かに流れていた。 (以上、上述記事からの引用) 若いひとたちのなかには、ただひたすらニホンは下り坂だと認識しているひとたちがいるというのは、ひとつの驚き。 たしかに世相は、時代倫理はかわる。でも、やはり自分の底にあるのは、自分の生きてきた時間のなかのどこかの価値観ではないかと思う。 よく知られた例。 ご飯のひと粒ひと粒にもお百姓さんのこころがこもっているのだからムダにしてはいけない、と感じやすいときを過ごしてきた(たとえばわたしの場合)。 しかし、それからほんのちょっとたっただけで一変。消費は美徳。それから石油危機やらトイレットペーパーがなんだかんだ。 しかもニホン人はすっかりうまくそのとき、そのときにのせられてきた。ふりまわされる。意識的にも無意識的にも。あるいはもっとも煽動しやすい国民か?(一生を貫く処世観なんてないにひとしい) わたしの場合でいえば、あのバルブ期、ほとんどニホン、およびニホンの情報に疎く過ごしてきた。だからバブル期の実感がじつにとぼしい。「狂乱期」とは無縁。 話を戻せば、下り坂しら知らなければ、暗さがなく、おなじく昂揚も知らないのか。生きていく希望はどこにあるのか。 いや。責めてはいけない。希望がないからこそ書くという行為に頼っているのかもしれないのだから。 では書けないひとは。いまほど娯楽手段が整っている時代はない。しかしナイーブすぎるところもあって、すなおの信じてしまうことがある。自分勝手である一方で、相手をわりと受け止めてしまう。それが政治の分野になれば、一見、もっともらしい話に巻き込まれる。そうじゃないかな? また話は移るが、「もったいない」という意識はニホン人にはとりわけ強いのだろうか(あるいは時代限定)。むかしなら、おてんとうさまに申し訳ない、なんてことになるのだろうけど。食べ物を残してはいけない、ということで。 JICAの募集する中学作文コンクールに、ニホンの「もったいない」を広めようという内容のものもあったとか。 http://www.yomiuri.co.jp/book/news/20070220bk03.htm ということで、なんかオチをつけないとだな。 いま、ここで、自分がゼッタイだと思ってることだって、あした、隣町(最近の流行り言葉ですな)では、まったく通じないかもしれない。そういう、通じないかもしれない、ということを意識しているだけで、すべてがずいぶん違ってくると思うんだけど。 (2007/02/21)
2009.01.16
コメント(0)
-
なぜ石を投げると強盗に当たるのか
ただしくは、地域限定。 なぜメキシコでは、石を投げると強盗に当たるのか? たとえば、ガビーノ・ロペス・サンチェスくん、26歳。 強盗により有罪になるが、刑務所に一ヶ月以上、留まったことがない。この五年間に四度、逮捕される。前回の出所から一ヶ月半で再犯。 ひと月に二回ある給料日、すると検察局出頭所(Ministerio Publico)には、強盗がみるみるうちに捕まって引っ張られてくる。年末もそこにいて、わたしは一部始終、見てたけど。 でも、逮捕されるのはまだいいほう。住民がパトカーに突き出し、パトカーが本署に連行する。しかし、その途中にて、もう泥棒なんかするなよな、といって見逃す。ポリスだって、いちいち、強盗にかかわっているのも、楽じゃない。(ノルマってものもあるかもしれないけど)これ、クリスチナ・パチェコのクロニカで読んだ。 捕まっても、あるいは、捕まえても、まともに処分されない。あるいは、刑務所にいる連中は、ポリスにリベート等を払えなかった連中。腹黒い奴らは通りを横行し、トロイ連中だけが臭い飯を喰う。 ここまでくれば、ひとが考えるのはひとつしかない。 私刑。 ポリスに手渡さずに、樹に縛り付けられたり、殴りつけられたりする。 何年もまえに地方であったけど、樹に縛り付けたままガソリンをかけて火をつけちゃう、とか。 ラテンは陽気な国ではあるが、カノアとかポキアンチとか(わかるひとだけ、分かって!)。なんともいえない。 極め付きは、わたし自身の強盗体験(複数回)を記せばいいんだけど、さすがにそこまでやるとねえ。。。メキシコにだれも来なくなっちゃうし。。。って、一回は書いたか。 (2007/02/17)
2009.01.15
コメント(0)
-
日曜日はゲイでいく?
日曜日。朝は豆腐ラーメン。 近くの運動公園にて、とりわけこどもクラスのバスケの試合を眺める。 小学高学年から中学の女の子のチームが、男の子のチームと試合。見知った女の子に見入る。からだこそ子どもだけど、きっとかわいい娘になるにちがいないって子が何人かいる。若紫(だっけ?)の心境。男のチームのほうが押し気味。でも、女の子たちがいいプレイをすると、快感めいたものを感じる。 その後、近くのマーケットに子犬を売りにいく。二匹ともメスだから「可愛い、可愛い」ってたくさんのひとがいって、買いたそうにするが、メスと知ってしり込みする。チャチャウ系の雑種、黒で小太り。ぬいぐるみのよう。でもようやく売れる。 遅い昼食はクリームスパゲッティに、ツナオムレツ。 今晩もいい映画を観たけど、ゆっくり記せない。 代わりに綴ろうと思ったのは、米国プロスポーツ界でのゲイ。ゲイについては最近、マイミクさんたちも触れていた。 わたしの知り合いの絵描きさんも、ものの見事にゲイ系の方たち。 米国スポーツ界にてゲイの宣言は、水泳飛び込み選手によって1994年になされたという。 現在、米国のプロスポーツ界にてゲイ宣言した選手は六人ほどいるのだそうな。 プロバスケット界ではじめて宣言したのは、ナイジェリア・英国系のジョン・アマエチという選手。このひと、「中心の男」という暴露本めいたものを出版する直前。 英国にてシングルマザーにより育てられたこのひと、どのようにしてゲイ・クラブに通うようになったかなどを語る。 ゲイは孤独でつらい人生だと思っているひとも多いようだが、じっさいは和気藹々とし、愉しい日々らしい。 米国のスポーツ雑誌によると、78%のひとがプロスポーツ界にゲイがいてもかまわないと思っているらしい。 ちなみにメキシコではゲイでないアーティストをさがすほうがムズカシイくらいだものね。 (2007/02/12)
2009.01.13
コメント(0)
-
俗に、シン・マイス、ノーアイ・パイス(もろこしなくして国なし)
メキシコ主食の価格高騰、米国の燃料用コーン需要増で 目下のホットなテーマ。 トウモロコシをめぐっては、これほど大事なテーマなのに、よくわからないことも多い。 メキシコのそれなりに美味いトウモロコシは米国に輸出され、米国の家畜用のトウモロコシがメキシコに売られて、トルティージャの材料になってるとか。それなりに信用のできる筋から聞いたことなんだけど。 たしかにおなじトルティージャでも、気をつけるとずいぶん味がちがうようだ。 フォックスにつづくカルデロンの中道右派(でもかぎりなく極右にも近し)になってまもなくのこのトウモロコシの高騰。オケイちゃんでなくても「だから言ったじゃないのお~~」とぼやきたくなる。 なぜ高騰したのか。 当地での、わたしの知る限りでは、投機的、ないし買占め的、値段の吊り上げが操作されたという説が有力。 それが、真相はバイオ燃料か? ニホンのCMだったかでも、そんなことを言ってたことがそういえばあったな。ヨーロッパの交通機関のことだったかな。いま、ちょっとうろおぼえ。shohojiさんあたりがやっぱり詳しいかな。 メキシコといえば、ネオリベラリズムの歯牙の前でおろおろしてる。金持ちはより金持ちね、貧乏人はより貧乏に。 そんななかでのトルティージャの高騰。まさに死活問題。さあ、貧民よ、立ち上がるときがきたか。怒るときには、怒んなくちゃダメだぜ。怒んないのはニホンジンぐらいにしときな。 でも、ほんとはメキシコ政府に責任はないの? しばしば触れられているように、これからの世界は、単純な兵器より、食料(あるいは水とか)のほうが、戦略的な重要性を担ってくる。 ニホンの食料品の自給率が低いとか騒がれるけど、メキシコの自給率なんて、そら怖ろしいことになってる。 そうすると、いつも繰り返すように、土地への投資、灌漑や農地改革などのインフラの遅れが致命的、というつながりになる。 どうすりゃいいのかね。 さっきのカナル・オンセのニュースでもやってたけど、中国にフォゴンシートというタコスのチェーン店が上陸。四人のメキシコ人シェフが、タコス屋を養成中だとか。 ここでちと脱線。 コロナビールの宣伝ビデオのひとつ。 万里の長城にて、兵士が敵の来襲を告げる。緊張感が高まる。敵はウンカのごとく。すると大写しになり、押し寄せてくるのはマリアッチのチャーロ姿のチュウゴク人。そこでコロナビールが出てくるという仕掛け。 (2007/02/06)
2009.01.12
コメント(0)
-
タイヘン&93年目
昨日にひきつづき、タイヘンだあ~。 夕方、ちょっと近場まで出かけようとして車に乗ってると、走行中、突然、エンジンが停まる。なんとか道の端に寄せる。 たまたまパンク修理屋のそばだったので、居合わせたひとにヘルプを求める。数人、いろいろ触る。 まずはバッテリーが怪しい。しかし接続もわるくないし、ほかの車にもバッテリーをつないで、バッテリーは平常。 どこかのヒューズか。でも、あまりモンダイなし。 なんかエンジンにガソリンが届いてないんじゃないかという話になる。いれかわりたちかわり、ひとが見る。 でも、なんかよくわからない。ふつうの修理屋はどこもすでに閉まってる。 けっきょく、ウチまでコンビ(ワゴン車)で押していってもらうことになる。善意からかと思ったら、かなり高くお金をとられた(それでも50ペソ値引きしてもらったけど)。 こう綴るとシンプルだけど、まあ、けっこうタイヘンで一時はどうなることかと。 でも不幸中の幸い、というか、わりとウチから近かったので助かった。これが夜中の、強盗の出そうなところだったら、ナニが起こっていたか予想もつかない。 でも込み入ったトラブル風。明日はどこもやってないだろうけど、アサッテの憲法記念日だったかには、みてもらわないとだな。 (2007/02/04)一昔前(っていっても、ついこのあいだのような気がするけど)までは、メキシコ人漁師はいるかをマグロ漁のときに殺してるから、という理由で、米国はメキシコのツナ缶の輸入を禁止してた。 この話、いまでも真相はよくわからない。 いるかは、まぐろをたらふく喰うらしい。だからまぐろ漁師にとっては目の敵(かたき)。沖合いでこん棒で殴り殺してるらしい。いまは殺してない、ということにはなっている。 アボガドについては、衛生上の理由から(検疫等)米国はメキシコ産のアボガドを輸入禁止にしてた。 それも徐々に緩和され、ご存知のようにニホンのマーケットまで席捲している。 しかしカリフォルニア州だけは断固として輸入禁止処置を続けてきた。なんと1914年以来だという。 それがとうとう、輸入解禁に到ったというニュースあり。 これには、脇ネタもあり米国一部の寒波により、主要生産地のサン・ディエゴの生産が壊滅状態に近いこともあるらしい。 よく知らないけど、米国のスーパーボウルあたりでは、ワカモレ(アボガド)を食べるのが習慣なんだって? 知り合いにアボガド生産者がいる。でも、あまり力を入れてない。アボガドは、米国が突如、禁輸措置とか取ると、あっというまに大規模な値崩れをおこし、ホンキでは打ち込めないのだとか。どこでも農家には行政のシワ寄せがくるらしい。 (2007/02/05)
2009.01.10
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 『 REAL 15 』 井上雄彦
- (2025-11-24 15:48:35)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 風に向かって クリスティン・ハナ
- (2025-11-24 16:36:01)
-