2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年04月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
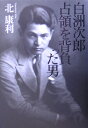
「白洲次郎 占領を背負った男」を読んだ。
随筆家として名高い白洲正子の著書は何冊も持っているけれど、その夫君である白洲次郎という人について、私はほとんど知識を持っていませんでした。白洲次郎 占領を背負った男今月の初め、NHK「その時歴史が動いた」で、この本の著者がゲスト出演して白洲次郎の特集が組まれたのですが、当時鼻炎の薬を服用していたせいか常に眠気に襲われていて、番組が始まってすぐにテレビの前でうたた寝してしまったのでした…先日、図書館へ行ったときに、その時の反省も込めて(?)借りてきて読んでみたらなかなか面白く、興味深い人物伝でした。ケンブリッジ大学での留学生活。ビジネスマンとしての筋の通った生き方。日本ではじめてジーンズを履いた男とも言われるダンディぶり…と、死後なお稀代の目利きとして人気のある正子の伴侶にふさわしい、一流の「かっこいい」男性。しかし、私がもっとも夢中になって読んだ部分は、次郎本人のエピソードではなく、次郎が吉田茂の懐刀として深く関わった「終戦連絡事務局」とGHQとの壮絶な攻防を描いたくだりでした。以前、憲法改正論議がマスコミで大きく取り上げられていた頃、新聞か何かで「憲法改正は自民党結党以来の悲願」というフレーズを目にし、え??そうだったんだっけ??と、とても不思議な思いがしたのですが、この本に紹介されている「新しい憲法を自分たちが作れるか、占領側に作られてしまうか」という駆け引きの壮絶さは、大変不謹慎な言い方ではありますが、とてもスリリングで、ぐいぐいと引き込まれてしまいました。様々な紆余曲折を経た末、GHQ主導による憲法案を日本政府の案として公表するに至るわけですが、閣議決定を天皇に報告した国務大臣の冒頭の言葉は「敗北しました」というものだった、というのが象徴的です。そして、「今回の憲法は、独立を回復した後にわれわれの手で改正すればいい」という思いが、首相の吉田茂以下関係者の共通の思いになった、と書かれており、先に挙げた「結党以来の悲願」という言葉は、なるほどそういう訳なのですね。次郎が当時記した手記には「斯くの如くして、この敗戦最露出の憲法案は生まる。「今に見ていろ」と云ふ気持抑へ切れす。ひそかに涙す」と記されています。また、戦後20年以上を経て「この憲法は占領軍によって強制されたものであると明示すべきであった。歴史上の事実を都合よくごまかしたところで何になる」とも、述べています。ただ、「終戦後、六、七年間小学校の子供にまで軍備を持つことは罪悪だと教えこんだ今日、無防備でいることは自殺行為だなんていったって誰も納得しない」と書いた彼が、一方では以下のように語っているところに、白洲次郎という人の本当の大きさを感じます。「新憲法のプリンシプルは立派なものである。(中略)マックアーサーが考えたのか幣原総理が発明したのかは別として、戦争放棄の条項などその圧巻である。押しつけられようが、そうでなかろうが、いいものはいいと率直に受け入れるべきではないだろうか」5月3日の憲法記念日を前に、あらためて多くを考えさせてくれた一冊でした。皆様、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。【読後、こちらを改めて読み返すとまた面白かったです】白洲正子自伝
2006.04.27
コメント(8)
-

かもめ食堂だより
実家の母から、大きな封筒が送られてきて、開けてみるとボール紙で出来た旅行カバンが出てきました。実はこれは、最近話題の映画「かもめ食堂」のパンフレット。夫婦ともに、すでに還暦を過ぎた私の両親は、もともとは大の映画好きというほどでもなかったのですが…シニア料金が適用されるようになり、また、車で気軽に出かけられる場所にシネコンが次々出来て、ここ数年は「二人で気軽に出かけるところ」としてやたらと映画館に行くようになりました。夕食を終えた後、ちょっと行ってみるかね、という感じでフラリとレイトショーに出かけるらしい。この頃は、携帯メールで、映画情報について母とやり取りすることもたびたび。(本来、機械音痴で携帯電話もまったく興味を示さなかった母ですが、彼女の世代にも着実にメールはコミュニケーションツールとして定着しているらしく、いつの間にか使いこなすようになっていた)こちらも、「これは」と思う映画を観たときはメールでお奨めすることにしているのですが、「それはもう、封切日に見た」と返事が来てしまうことも(笑)ある日「かもめ食堂っておもしろいのかしら。友だちがすすめてくれました」というメールが来ました。とても観たいと思っているのに、こちらの方では公開予定がないため、ぜひ私の代りに観て来て…とくやしまぎれに(笑)返事をしました。「私の代りに」という言葉を律儀に受け止めてくれたのか、それともよほど映画が気に入ったのか、わざわざパンフレットを送ってくれたらしい。手紙には「お父さんも大好きな映画になりました」と書いてありました。パンフレットのスチール写真は、どれも美しく温かい光景。ほんとうに、いつか必ず観たいと思う映画です。(「かもめ食堂」のパンフレットは、mayao5さんのブログでもっと美しい写真が公開されていました。まさか私の家にも同じものが来るとは思わず、ビックリでした)【片桐はいりさんがフィンランドロケの思い出を綴ったエッセイ集が出ました】わたしのマトカ【私の母はその昔、マリメッコの食器や布地が好きでした】
2006.04.25
コメント(16)
-

春のつれづれ
先週の何曜日だったか、朝の8時過ぎにご近所を歩いていたとき(何か、風景がいつもと違う) と、目の前に広がる光景の何かが、私の中で引っかかりました。新しい建物が出来たのではないし、花が咲いているわけでもないのに、何だろう?…あらためて目を凝らしたとき、違和感の正体は「まぶしさ」にあると気がつきました。前に通ったときには存在しなかった、朝の光を受けてキラキラと輝くものの正体。それは…水田です。 要するに、数日前まで土の地面が広がっていただけの田んぼに、田植えのための水が張られた。そういうことだったんですね。私たち夫婦が暮しているのは、住宅地といっても、家と家の間の一区画が当たり前のように田んぼや畑になっている、そういうところです。コンクリートジャングルで生まれ育った私には、梅雨間近になると始まるカエルの大合唱や、一年中次々に違う作物が実っては収穫されていく畑の様子はカルチャーショックでした。しかし、朝や夕方、太陽の光が斜めに差し込む時間帯に、水田が風を受けてさざなみを煌めかせている様子の美しさは、なぜか今まで気がつかずにいたものでした。春が来たうれしさを、あらためて実感したひとときでした。季節の変わり目で不安定な天候が続いていますが、いつの間にか日が長くなったのもうれしく。せっせと春キャベツやアスパラガスやそらまめを買い込んで、キッチンでも春の訪れを実感しています。【春野菜はシンプルレシピでいただくのが好きです。そらまめはさやごと焼くだけ】【一日おきに食べていると言っても過言ではない、春野菜とベーコンのパスタ】パスタが茹で上がる少し前に、野菜も入れて一緒に茹でてしまう、お鍋一つでラクチンなパスタが今のわが家の定番です。しょうゆベースの味付けも合いますが、バジルペーストで仕上げるレシピもなかなか。お手頃な価格のをよく買いますが、たまに高級なペーストを買うとやっぱり…美味しい(笑)【チキンや魚のソテーにもよく合いますね。】バジルペースト 90g
2006.04.21
コメント(11)
-

赤糸で縫いとじられた物語
NHKの「知るを楽しむ」、四月の火曜日は、美輪明宏が寺山修司を語る「私のこだわり人物伝」を、保存版として録画しながら見ています。中学生の頃、大好きで聞いていたNHK-FMの「サウンドストリート」というラジオ番組があって、夜10時からの45分放送だったのですが、それが終わると流れてくるのが、短い朗読劇でした。週代わりで取り上げる本や作者が決まっていたのですが、私が寺山修司と出会ったのはまさにこの時でした。「赤糸で縫いとじられた物語」というのが、ある夜、ラジオから流れてきて私の心をわし掴みにした、彼の本の題名でした。「鳥は鳥でも飛べない鳥はなぁんだ それは ひとり という鳥だ」・・・十代の、多感で、自分で自分の感情が制御しきれず、エネルギーのやり場を持て余している女の子にとって、寺山の紡ぎだす言葉が、どれほど魅力的に響いたことか。図書館で、宇野亜喜良の美しい絵が表紙に描かれたこの本を見つけたのを皮切りに、すでにこの世を去っていた寺山修司の本をむさぼるように読みました。(当時買い集めた角川文庫の本は、未だに本棚の特等席にあります)その結果として、美輪明宏(私の中では「美輪サマ」・笑)という俳優の存在を知ることが出来たというのも、自分にとっては本当によかった、あの時自分は、未来の自分へ大きな贈り物を届けたなぁ・・・と、思っています。この頃は「近頃の日本人に物申す」という趣旨の言動が増えて、あわよくば細○○子センセイとごっちゃにされがちな感のある美輪サマですが、ロココ調の豪華な家具に囲まれて暮す美意識を持つ一方で、小劇場のアングラの世界にも飛び込んでいったというところに、芸術家としての彼の真骨頂があるのでは。ご本人の中でも、あの70年代という活気に満ちた時代に、寺山修司と三島由紀夫という二人の才気あふれるアーティストの崇拝を同時に受けていたというのは、もうとびっきりの誇らしくて美しい、どんなに自慢しても足りないほどの輝かしい記憶なのだと思います。「知るを楽しむ」は、来週が4回シリーズの最終回となりますが、寺山の元妻、九條今日子さんとの対談、というすごい企画が!さらに言えば、5月の同シリーズは、リリー・フランキーが松田優作を語る・・・とあって、もうテキストブックを買うしかない、という勢いの私なのでした。【現在はハルキ文庫から出版されているようです。】赤糸で縫いとじられた物語【番組ではこの映画のほか、寺山作品がふんだんに紹介されていて充実の内容】書を捨てよ町へ出よう【番組のテキスト。放送スケジュールなどは番組公式サイトで。】私のこだわり人物伝(2006年 4ー5月)
2006.04.19
コメント(14)
-

春の高山祭(で、しーちゃん発見?の巻)
土曜日、夫と春の高山祭を見物に出かけてきました。昨年出かけた時は、快晴で、歩いていると汗ばんでくるような気候だったのですが、この日はどんよりとした曇り空から、時折雨が落ちてくるあいにくのお天気。前回友人と出かけた時は、名古屋から高山本線に乗って、線路沿いの桜が満開なのを眺めながらお弁当を食べつつ飛騨を目指す・・・という、非常に優雅な時間を過ごせたのですが。今年は桜のつぼみはまだ固く、高山の近辺ではところどころ雪が溶け残っておりました。スプリングコートの前をかき合わせて、寒さに震えながらのお祭り見物となりましたが、何より残念だったのは、雨交じりの天候のため、お祭りのメインイベントとも言える「屋台の引き揃え」が中止されていたこと。からくり屋台の奉納も、通常なら広場に3台の屋台が並べられて、順番に精緻なからくり人形の芸を目にすることが出来るのですが、今回は屋台は蔵に納められたままで実演されるということで、残念でした。そのからくり、私たちが見られたのは「石橋台」という、美女が瞬時にして獅子舞(獅子の精)に変わるという人形がついた屋台でした。可笑しかったのが、踊りのフィナーレの部分で、お人形が前かがみの姿勢からぐっと背中をそらせる振りがあるのですが・・・その瞬間、屋台を取り囲む群衆の中から、異口同音いっせいに上がった声が「イナバウアーだ!」「イナバウアーだ!」・・・うん、私もそう思った(笑)【夫が写した決定的瞬間(?)実際はもっと激しくバウってました】 それにしても、小さな町並みのあちらこちらで、美しい衣装をまとった子ども達が踊っていたり、ご神体の行列が通ったり、獅子舞が始まったり・・・歩いているうちに思いがけず、祝祭の空間に出くわす、というのが素敵なお祭りだなぁと思いました。【駅近くのお店でいただきました。懐かしい味の中華そば、美味しかったです。】飛騨の中華そば 『 甚五郎らーめん 』 (10食分)【お土産に、わが家のイチ押しはこちら!岐阜産桃太郎トマトのケチャップ】飛騨・美濃すぐれもの・明宝特産セット昨年の旅の日記はこちらから・・・
2006.04.17
コメント(8)
-

「プロデューサーズ」を観た。
「プロデューサーズ」というミュージカルがブロードウェーで大成功しているらしい、という話は、日本で放送されたトニー賞の授賞式などで数年前から耳にしていました。メル・ブルックスが四十年近く前に映画として制作し、その後、21世紀になってから彼の脚本・作詞・作曲によって、ブロードウェイミュージカルとして生まれ変わったものが、さらに映画になった(あぁややこしい)・・・という経緯があるそうで。何やらすごく笑えるようだ・・・という話で、映画化の話を聞いて以来、見られる日を楽しみにしていたのです。“落ち目の演劇プロデューサーと、ショービジネスに憧れていた小心者の会計士が出会い、ある企みを思いつく。『出資者から制作費を集めたあと、ショーが失敗すれば、出資者に配当を払うこともなく出資金をくすねることができる!』というカラクリ。そこで、大コケ確実のショーを作るため、「史上最低の脚本」と「史上最低の演出家」を探すのだが、そこで出来上がったミュージカルの行く末は・・・?”ユダヤ系の主人公コンビが生み出した「史上最低のショー」というのが、ナチス崇拝者のドイツ移民が書いた「春の日のヒトラー(Springtime for Hitler)」(!!)・・・というのがそもそもスゴイ。全編、悪趣味すれすれの「おバカ系」の笑いがこれでもか、これでもかと続きます。(最初は、アクの強い主演二人のキャラクターにちょっとついて行けなかったのですが、ヘンな登場人物が次々登場すると、もう可笑しくておかしくて・・・)クスッとかニヤリ、というよりは、手を叩いてギャハハハ、という笑いがピッタリ。レイトショーの劇場内も盛り上がっていました。観終わった後、夫と「映画館でこんなに大声出して笑ったのって、久しぶりかも」と、大満足でした。「雨に唄えば」とか「キスミー・ケイト」とか、古いミュージカル映画のように、映画を観終わったあとで、すぐに歌のフレーズを口ずさめるような、耳なじみのいい、メロディアスな音楽。ゴージャスなダンスシーンに舞台装置、衣装など、ショーアップされたシーンも楽しくて・・・笑いの質はすごくバカなのに、ミュージカルとしての作られ方は超・正統派、というのが、すごく好きでした。古今の名作ミュージカルの引用やパロディが随所に散りばめられていますが、予備知識がなくても十分笑えると思います。主演のマシュー・ブロデリックについては、アホの坂田にどこか似ているとっつぁん坊やという印象が強くて(ファンの方申し訳ありません)この人とサラ・ジェシカ・パーカーの夫婦というのはなんだか不思議な組み合わせだなぁと思っていたのですが、バカもやれるし歌も上手いし、芸達者な人だったのね・・・と、目からウロコでした。ユダヤ系にゲイに英語の下手な移民に・・・アメリカ社会におけるマイノリティ(いや、もはや多数派なのかな?)の、徹底的な自虐ギャグに圧倒されました。でも、「これから2時間は何も哀しいことは起こりませんよ、安心して笑っていてくれていいですよ」と約束してくれているようなこの映画は、大人がストレス解消するのにぴったりなエンタテイメントです。憂さ晴らしにおすすめ。ちなみにこのミュージカルの生みの親、メル・ブルックスは、映画でもところどころにピンポイントでカメオ出演しています。そうそう、これからご覧になる方は絶対に、エンドロールが終わるまで席をお立ちにならないで・・・
2006.04.11
コメント(15)
-

花泥棒と呼ばないで
東京より一週間ほど遅れて、桜が満開となりました。風の強い午後。花が散らないうちに・・・と、近所の桜並木まで、夫とお花見がてら散歩に。すると、一本の木の下に人だかりがしていました。見れば、歩道をふさぐようにして、桜の木の太い枝が横たわっています。幹の内部が、すっかり虫に喰われていたようで・・・強い風に耐えきれず、二股に分かれた部分がボッキリと折れてしまったらしいのです。万が一、下に人が通りかかっていたら大怪我していたのでは?というくらいの立派な枝ぶりで、もったいないことに花は満開。そういう訳で、近所の方々が片付けの作業がてら、ハサミやのこぎりで枝を切り分け、通りがかりの人に配ってくださっていたのでした。この桜の木の、最後の花になるかもしれない。そういう思いで、分けてくださっていたのだと思います。私達も、数本の桜の枝をいただいて、喜んで家路についたのですが・・・私達と同じように、桜を見に訪れた人々が、こちらを見る視線が妙に鋭い。・・・ハッ!!違うんです!私たち、桜を無断で折った訳ではないんです!!誤解しないで~・・・!・・・と、いっそ大声で叫びながら歩きたい気分にかられたのでした。【玄関に飾ったら、やっぱりきれいです。うれしくなりました。】そういえば、渋谷の東急ハンズの近くに「花泥棒」という名前の喫茶店があって、周囲の喧騒がウソのような静かな雰囲気がお気に入りでした。ベトナム風のコーヒーやバゲットサンドがいただけるのもポイント高し、だったのですが、あのお店はまだ健在なのかなぁ?と、懐かしく思い出しました。【桜を見ていると、花よりあんパンな気分になります(笑)】桜あんパン 5個入り
2006.04.08
コメント(15)
-

心配な映画ニュース
映画館の少ない環境で暮していて、封切で新作映画を見る機会も非常に限定されている私。そのせいか、新作情報にもすっかり疎くなっているのですが、そんな私が、このところずーっと、制作過程の行方をドキドキしながら見守っている作品があります。まず一つめは、90歳になる市川昆監督が、新たに撮影する「犬神家の一族」。横溝正史の生み出した名探偵、金田一耕介は、様々な俳優によって演じられていますが、私にとってはどんなキャストよりも、石坂浩二が市川監督作品で演じた金田一がベストなのであります。最近では、豊川悦司や稲垣吾郎など、個人的に好きな人が金田一ものに主演していますが、う~ん、やっぱりあの石坂バージョンには足元にも及ばないわね、と(勝手に)思っていたのです。でも、でも・・・そうは言っても、64歳になる石坂さんの金田一って・・・一体どんなことになるのやら?はっきり言って、期待より不安の方が大きい、フクザツなファン心理。最近目にする石坂さんが、髪を伸ばして役作り(?)に励んでいるのを見ては、何とも言葉に出来ない思いを飲み込んでいる私・・・。今日、テレビで主要キャストが揃っての記者会見の模様を見ました。(詳しい記事・写真はこちらから。)旧作は、主要な登場人物の一人を演じた高峰三枝子のド迫力の存在感が素晴らしかったと思うので、この役の人選が一番心配だったのですけど、今回キャスティングされたのは富司純子さんと聞いて、これはイイかも?と納得。(記者会見での着物姿も、さすがの貫禄であります)犬神家の、松子・竹子・梅子の三姉妹を、富司純子・松坂慶子・萬田久子が演じ、松子の息子・佐清は尾上菊之助、つまり実際の親子で母と息子の役を演じるわけですね!加藤武や大滝秀治など、かつての金田一シリーズのファンにはたまらない常連役者の名前もクレジットされていました。記者会見の様子を見ると、あぁ、お歳をめされたなぁ・・・と遠い目になってしまうのですが、旧作の出演陣でずいぶんお亡くなりになった方も多いことを思えば、お達者なのは何より。って、何だか敬老会の祝辞のようになってきましたが(笑)【犬神家もいいけど、病院坂も好き。】 【こういうパックをすると、つい夫に「佐清マスク♪」と言ってしまう・・・】さて、もう一つ、映画の製作発表を聞いて大ショックを受けたのが、スタジオジブリの新作映画「ゲド戦記」です。私はジブリアニメの大ファンなので、ル・グィンの書いた原作が、宮崎駿監督に多大な影響を与えたということを色々なところで見聞きしていました。それだけに、ついに映画化?と思いきや、監督をするのは実の息子ということを知ったときは、がく然としました。世襲とか、親の七光で・・・というようなことを最も嫌いそうな人が、なぜ自分にとって大事な作品を、わざわざ息子に作らせる?・・・と。スタジオジブリというのが、後継者のなかなか育たない組織なんだなあ~というのは、多くのファンが感じていることだと思いますが。ジブリの鈴木プロデューサーは、そういう世間の反応を十二分に予知していたのか?その後公式ブログに、こういう制作経緯を辿ることになったいきさつが事細かに掲載されました。インタビュー記事を読むと、やっぱり駿監督は息子が映画を作ることに激怒しているというので、ちょっと安心したりして(笑)「ゲド戦記」の制作日誌はこちら。「ジブリでは若い人が一度作ってもその後が難しい」など、赤裸々な発言続々のインタビュー、読み応え十分です。(本日夜、NHKの「プロフェッショナル」に出演との情報も。)まぁ、「ハウルの動く城」の声優にキムタクが!というニュースを聞いたときも「あり得ない!」とプンプンしていたくせに、いざ映画を観たらそんなことはすっかり忘れてボロボロ泣いていた私のこと、実際に映画を見てどう感じるかは、そのときになってみないとわかりません。実際にスクリーンで完成された作品を目にする日まで、このドキドキ感も楽しみのうち、と思って、腹をくくりましょうか・・・
2006.04.06
コメント(8)
-

着物ことはじめ ~どこへ行く?わが着物道~
着付けのお稽古を始めて、早いもので半年が過ぎました。楽天で購入した着物セットで、時折自習に励んでいる成果もあって、名古屋帯でお太鼓を結ぶまでは一人で出来るようになりました。来週からは、袋帯の結び方に一歩進みましょう、と先生からのお達し。出来なかったことが出来るようになる、というのは、いくつ歳を重ねてもうれしいものです。いやむしろ、「以前は出来たことが出来なくなる」ことを何度も実感しているからこそ、何か新しいことがまた身につくというのはしみじみありがたく、うれしい。大人の手習いの魅力や醍醐味は、そんなところにあるのかもしれません。しかし、着物の畳み方さえ覚束なかったのが、何とか一人で着られるようになる・・・という最初の目標をクリアしてみると「さて、これから先はどこまで行くんだ?」という思いがムクムクと湧き上がってくる、最近の私。自分のお金をかけて通っている習い事だし、最初から目的をはっきりさせておきたい・・・惰性でだらだら続けるのは、もったいないなと思ってしまう。このあたりが、大人ゆえの世知辛さというかセコさというか(笑)同じ曜日に教室に通っている生徒は、上級者チームと、私のような初心者チームの混成なのですが、上級者の皆さんのお稽古の内容は、マネキン人形を相手にした華麗な帯結びの研究とか、15分できれいに訪問着を着付けるとか・・・つまり、プロの着付け師として「人に着せる」練習なのです。着付けのお稽古というのは、つきつめればこの、他人に着物を着せる腕を磨く・・・というところへステップアップしていくもののようなのですが。これからそういう職業を目指すならまだしも、私の場合「そういうことは、別にいいんです。自分さえちゃんと着られれば」というのが本音。さらに言えば、自分のライフスタイルにどう着物を取り入れるか?というのも思案のしどころであります。着物を着ることには、ある意味「約束ごとを楽しむ」という側面もある訳で。湯水のようにお金を箪笥に注ぎ込める身分ならともかく、どんな場面で着るのか?という狙いを定めないと、着物を誂えることも難しいよね・・・と、考えてしまうのであります。大きな本屋さんを覗いたとき、ずらりと並ぶ着物関連の本を眺めていたら、「あぁ、このセンスは好きだなぁ」と強く魅かれる一冊に出会いました。【タイトルはちょっとスゴイ(笑)けど、紬を中心とした着物のコーディネートがとても素敵。】森田空美の知的きもの入門肩に力を入れすぎるのではなく、すっきりと上質な装いを楽しみたい・・・まだまだ試行錯誤は続きそうですが、美しく着こなせるよう努力も続けつつ、ゆっくりと「私の着物道(けものみちではありません)」を見つけていきたいと思います。東京ではもう満開となった桜。私の暮す地域では、まだ五分咲きというところなのですが、今回のお稽古の最後に先生から「来週は、お天気が良かったら着物で近くまでお花見に出ましょうね」というお誘いがあり、一同大歓声。どんな服装で見ても桜は桜だけれど、やっぱりこの「ふだんとちょっと違う」高揚感が、着物をまとうことの歓びであるなぁと実感しました。【家で一人で練習するときは、この番組の録画にお世話になってます】市田ひろみのはじめてさんの着物塾 DVD(月末発売)
2006.04.04
コメント(4)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- コストコ行こうよ~♪
- コストコで初購入品のレポと無料のも…
- (2025-11-10 08:40:41)
-
-
-

- 今日の出来事
- 多治見の永保寺の紅葉ライトアップ …
- (2025-11-18 06:00:05)
-
-
-

- 暮らしを楽しむ
- 18日限定🉐 7大アレルゲン不使用!!や…
- (2025-11-18 06:41:45)
-







