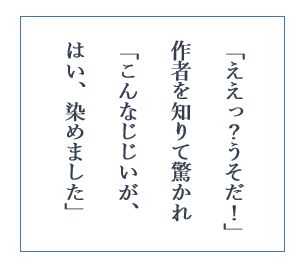2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年08月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

ある映画広告から。
今年の8月15日、新聞は小泉首相の靖国参拝を大きく取り上げ、終戦の日にまつわるいくつかの記事を掲載していました。その中で、私が一番強く引きつけられたのは、秋に公開される、ある映画の全面広告でした。「日本の皆様へ」という、手紙形式の文章の差出人は、クリント・イーストウッド。61年前、日米両軍は硫黄島で戦いました。…という書き出しで始まるこの文章を、私は2回繰り返して読みました。そして、「私が見て育った戦争映画の多くは、どちらかが正義で、どちらかが悪だと描いていました。しかし、人生も戦争も、そういうものではないのです。私の2本の映画も勝ち負けを描いたものではありません。戦争が人間に与える影響、ほんとうならもっと生きられたであろう人々に与えた影響を描いています」というくだりに、大いに共感を覚え。「父親たちの星条旗」「硫黄島からの手紙」という、日米それぞれの視点から硫黄島の激戦を描いた映画をぜひ観てみたいと思いました。イーストウッドの手紙の全文は、ワーナーの公式サイトで読むことが出来ます。同じ日に、BSでは「二十四の瞳」を放映していました。この映画は過去に観たことがあったのですが、なぜか、偶然チャンネルを合わせたところから途中でやめることが出来ず…オイオイ泣いてしまうってわかっているのに(事実その通りになりましたが)最後まで見てしまいました。【童謡の美しさを再認識させてくれる映画でもあります。いつか小豆島に行きたい私。】戦争なんていいこと一つもないじゃないか、寿命の限りに生きていけることはなんてありがたいことなんだろう。そんなことを学ぶには、この映画とか「火垂るの墓」とか、他にも良質な映画や本やマンガやドラマがたくさん、たくさんあります。しかし一方で、「戦争の犠牲者」として描かれている市井の人々ですら、視点を広げてみれば、戦争をしている国の国民なのであり、争いに参加する当事者なのであって。争う相手の側から見れば、加害者の側に立っていることに代りはないのだ…ということも、覚えていたい。映画の題材になることの多い、特攻隊員にしても同じです。大事なものを守るためと信じて、命を犠牲にする若者のドラマに「可哀想だ」と泣いて終わってしまうだけでいいのか?彼らが命を犠牲にして殺した相手もまた、誰かにとっての大切な人だったのだ…ということまで考えないと嘘じゃないのかな。「今日われ生きてあり」などを読むと、「こんなに高潔な精神を持っていた人たちが、どうして誰かを殺すために生きなければならなかったのだろう」と、そのことが一番哀れに思えてしまいます。「善」と「悪」、「勝ち」と「負け」、「加害者」と「被害者」…そんな区分けを前提に“あぁ、かわいそうでした”で終わるだけでは、戦争というものの本当の醜さ、むごさは見えてこないのだと。その点においても、このような形で作品が撮られるという点に、意義を見出したいと思います。こんど日本の総理大臣が変われば、確実に憲法を変えるということが現実味を帯びてきます。もっともっと危機感を持って、「戦争」を自分たちの問題として考えないとヤバイ時代に来ているんじゃないか、その今の率直な思いを、8月の最後に残しておきたいと思って書きました。私は戦争で死にたくないし、誰かを殺すことに加担したくありません。そのためにはどうしたらいいのか、間違えないでちゃんと選択しないと…
2006.08.31
コメント(8)
-

ドライブBGM考
車を新しく買い換えることになって、一番の懸案事項はもちろん「どの車にするか?」ということですが、それだけでは終わらないことがわかって来ました。現在のわが家の愛車は、夫曰く「電気系統が弱い」そうで、トラブルを避けるために、カーナビやETCは「つけたいけど、怖いからつけない」ということだったらしいのです。(↑私は、このあたりの技術的な話がまったくわからないので、すべて伝聞形でスミマセン)その分、今度は国産車で、便利なオプションもたくさんつけられるし、カーナビだって!ETCだって!…と、夫は非常に鼻息荒く、目が爛々と輝いているのです(笑)確かに、典型的な「地図の読めない女」である私が助手席で「えぇっと…あっ、今過ぎた交差点を左に曲がるんだ~」…なんて言っているよりは、ナビゲーションシステムが案内してくれる方がどれ程便利かはわかりませんね(笑)【宮本恒サマのCMだったかな?こちらの機種になる予定みたいです】Panasonic パナソニック HDDカーナビ ストラーダFクラスCN-HDS910TDその方面に興味がなかったので、ディーラーで最新のカーナビについて色々伺ったところ、カーオーディオとしての機能もすごい、ということを勉強しました。地デジだの、DVDだの、色々ついているようなんですが、真顔で「車の中で、なんのためにDVDを見るんですか?」…と発言し、営業の担当者を一瞬絶句させてしまった私です(恥)(でも、マジメな話、ドライブ中に映画を観るなんて発想がまったくわいてこなかったもので…)カーステレオの方も同様。わが家の音楽のデジタル化は、CD・MDの段階で停まっており、ダウンロードなど全く無縁の生活なので、「HDD搭載で、携帯やi-Podとの音楽データのやり取りも可能ですよ」などと言われても、急にはピンと来ませんでした。…いいんだもん、時代遅れだって!(開き直り)でも、これからは大量の音楽データを搭載し、かつ簡単にお目当ての曲がピックアップできるといのは素直にうれしいです。いや、技術の進歩というのはすごいものです、本当に。「夜の高速」とか「緑の峠道」とか、シチュエーションに合わせて定番の「お気に入り」をBGMにすることが多いですが、これを機に、新しいCDも色々と聴いていこうと思っています。そういえば、時々、すれ違う車の中で、ハンドルを握りながら気持ちよさそうに歌っている人を見ることがあります。実は私も、よく助手席でBGMに合わせて歌ってたりするんですが(自分が運転するときはその余裕はない)…。傍から見ると、やっぱり間抜けなものですね、あれは(笑)
2006.08.30
コメント(8)
-

「ゲド戦記」を観た。
「スタジオジブリの映画に、楳図かずおの絵が出てきてはイカンよね、やっぱり…」映画館から帰る車の中で、こんなことを言ったきり、夫と私は黙り込んでしまいました。たとえばこれが、周辺情報を何も持たず、期待もしないで偶然に目にしたアニメ映画だったとしたら(実際には起こり得ないことですが)…。人に感想を尋ねられれば、「まぁまぁかな。」とか、「それなりに面白かったけど?絵も音楽もキレイだったし」とか、そんな言葉が出てくるのかもしれない。「お金損するから観に行かないほうがいいよ」なんていう風には、きっと言わないと思う。でも、帰り道の私たちの心を支配していたのは、もうちょっと苦いテイストの気分だったように思います。「素直な作り方で、よかった」…これが、この映画を観終わった、宮崎駿の感想だったのだといいます。(間接的に伝えられた言葉として、公式HPで宮崎吾郎監督が公表しています)そう、素直に、真摯に、現代に生きる私たち(特に、若い人たち)のことを一生懸命に考えて「ゲド戦記」という作品が作られたのだということは、よくわかるのです。作り手が、この物語を通して伝えようとしているメッセージ。それはわかりやすいし、シンプルで、今の私たちが見失いがちな、大切なことだと思いました。でも、心が動かされないのですよ。・・・・・・・・恐らくその最大の理由は、あまりに何もかもを、言葉(セリフ)で説明してしまっていること。次いで、キャラクター造形の多くが「どこかで見た感じ」の新鮮味のないものだ、というあたりでしょうか。(その「どこか」が、過去のジブリ作品であることは言うまでもない)さらに、主人公にどうも感情移入が出来ないというか、なかなか応援したいと思えませんでした。うつろな目をむき、口元に皺を寄せてギャァギャァ叫ぶアレン王子を見ていると(これでは、楳図センセイの描く恐怖マンガで「キャアァァァ」って叫ぶ人の顔では…)と、身もフタもないことを思い浮かべるしかなかったわけで。監督の宮崎吾郎氏と私は、ほぼ同年代です。豊かなモノと情報の洪水の中で育ち、リアルな体験は乏しくても、頭でっかちに多くのことを見聞きしたつもりになって大人になってきました。父が、アニメーションの中に描こうとする架空の世界を「実際に生きる」ことが出来るのに対して、息子は「思い描く」ところまででとどまっているようだ。…と言ったら、言葉が過ぎるかもしれませんが。でもそう考えると、これが私たち世代のクリエイターの限界なんだろうかという思いも芽生えはじめ、ますます哀しくなってしまった次第です。それにしても、本当によく監督をやるなんて話を引き受けたなぁと思う。比べる対象が、あの父の映画の数々でなければ、この作品も、もう少し世間の評価は穏やか(あるいは黙殺)だったでしょうに。どうしても死ぬまでにもう一作、ゲド戦記を宮崎駿に作らせたいという、鈴木プロデューサーの深慮遠謀があったりして…だとしたら、魔法使いより怖すぎる。【関連日記】◎ハウルの動く城◎心配な映画ニュース
2006.08.28
コメント(10)
-
昼下がりの空耳
わが家のマンションの前は、すぐ近くにある小学校の通学路になっています。学校のある時期は、毎朝決まった通学時間に、集団登校のにぎやかな声が聞こえます。今は夏休みですが、校庭が開放されているのか、登校日なのか?時折、窓の外から子どもたちの声が聞こえてくることがあります。今日も、昼食の片付けをしていたら、突然「いんちきはきち~♪♪」と声をあわせて歌う、甲高い声を耳にしました。インチキは、吉…?子どもが歌うにしては、なんともモラルの欠如した歌詞ではないか、と目を丸くしておりましたら、続いて「いんにはに~、いんさんはさん~♪」と続いたので、あぁ、九九を覚えてるのね!と気がついた次第。掛け算の九九って、小学2年生くらいで勉強するのでしたか。私が習ったときは、先生も1の段は「まぁ、言わなくてもわかるよね」という感じで(笑)みんなで一生懸命暗唱したのは、「ににんがし」からだったように記憶しています。今日耳にした声は、妙にメロディアスな節回しだったので、もしかしたら覚えやすい「九九の歌」みたいなものが作られているのかな。1×1=1、を「いんいちがいち」と読むのは、全国的にそうなんでしょうか。16年間学校教育を受けた中で、身についた勉強よりは忘れてしまったことの方がはるかに、はるかに多い私ですが、九九は日常生活の中で使わない日がないと言っても過言ではありません。これを発明してくれた人、教えてくれた先生、しっかり覚えこんだ子どもの頃の自分、すべてに感謝です(笑)やっぱり、学問のすべての根っこは「読み、書き、そろばん」なんですねぇ。江戸時代の寺子屋教育では、割り算の九九というのも教えていたらしいですが。そういえば、昨日大きな話題になった「冥王星、惑星から脱落!」というニュース。太陽系の惑星をいくつにするか、という議論については、先日から盛んに取り上げられていましたが(数が増えるのかと思いきや、終わってみれば1つ減ってしまうんですね)、どんなニュース番組でも「水金地火木…」とキャスターが唱えていました。太陽系の惑星を聞かれれば、世代を超えて誰でも同じフレーズを頭に浮かべて答えることができる。九九にしても、“すいきんちかもく”にしても、こういうことが「文化」なんじゃないかなぁ、なんて思った昼下がりでした。「勉強は、しないよりはしておいた方がいいわ」っていう、森高千里の名曲もありましたね。歳を重ねるごとに痛烈に実感します。
2006.08.25
コメント(12)
-

愛しのめかぶたたき
九州に居座った台風の影響で、お盆休みのあいだはずっと雨模様。それが、今週に入ってからは一気に真夏日が続いています。こう暑いと、キッチンで火を使うのも意外と汗をかくもの。特に昼間は。そんな訳で、短時間で出来る料理がいちばん!と、毎日毎日飽きもせずそうめんばかり茹でている夏の私。めんつゆの薬味は、おろし生姜・青じそ・みょうがが三種の神器だった私ですが、今年はそれに加えてめかぶという新アイテムが加わりました。それも、楽天で注文する、魚辻というお店の、めかぶたたき専門であります。スーパーで見かけるようになってから、パック入りのめかぶが好きになったのですが、残念なのがほとんどが中国産であるという点…食べ物に関しては、「国産」「無添加」という二大キーワードにすごく弱い私は、なかなか国産のめかぶってお目にかかれないなぁ、と嘆いていたので、このめかぶたたきは「長崎産」だというのがまずうれしかった。(補足:こちらのショップで扱われている他のめかぶ製品には、中国産のものも多いです。私も、なにも輸入食品を完全否定するつもりはないのですが、何となく“同じ食材を買うならできれば国産品”というこだわりがあります。まぁ、こういう事は「気分」と「好み」の問題ですよね)そして、細長くカットされた普通のめかぶと異なり、細かく刻んだ「たたき」状態になっているので、めんつゆに入れるとうまい具合にそうめんにからんでくれて、“ずるずる”するのにちょうどいいのです(笑)繊維もたっぷり、体にいい栄養素もたっぷり。冷蔵庫に常備して、今日もツルツル、ずるずると夏のランチタイムを楽しむ私です。*夫がいるときは、ちょっと手間をかけて「ぶっかけ麺」スタイルに。) この日の具材…豚薄切り肉、オクラ、湯むきしたプチトマト、キムチ、そしてめかぶたたき ネバネバ食材がお好きな方には絶対おすすめです。毎日が新鮮できたて!総量無料 めかぶたたき15本セット
2006.08.24
コメント(12)
-

睡蓮の刺繍バッグ
旅先で、昼間は動きやすいスタイルであちこち観光し、夜は気分を変えてドレッシーなディナーを…なんてことがあります。が、王侯貴族のようなトランクを持ち運べるわけでなし、荷物の取捨選択は頭の痛いところです。以前のベトナム旅行の際、ホーチミンの雑貨店で見つけた、小さな手提げバッグ。日本円にして二千円程度だったと思うのですが、サテンの光沢が思いのほか上品な印象で、合わせる服を選ばない上、布バッグなので小さく畳める…というスグレモノ。旅行カバンの片隅にちょっと入れておくと、思わぬときにおしゃれのアクセントとして活躍してくれることがあって、もう何年も愛用中です。おだやかな色合いの蓮の刺繍が気に入っています。この夏休みの、奈良の旅にも持参し、ゆかたでお出かけしたときに使いました。ゆかたや着物のおしゃれを楽しむとなると、着るもののみならず、いわゆる「和装小物」も必要になってきますが…。履物は仕方ないとしても、手に持つものをどうするか?旅先のこととなると、意外と悩ましい。ショルダーバッグをそのまま使うわけにもいかず(笑)かごバッグは旅の荷物にはかさばるし。巾着もいくつか持っているのですが、意外に物が入らない(無理矢理入れるとパンパンにふくらんでカッコがつかないし…)。そんな訳で、ふと思いついてゆかたとこのバッグを合わせてみましたら、なかなかいい感じに思えてうれしくなりました。使用例…といっても全然見えませんね、ごめんなさい底のマチが正方形になっていて、持ち手の布を、四辺の上部につけられたリングにぐるっと通してしぼるような感じにするだけの構造です。同じデザインのものがないか探しましたが、すぐには見つけられませんでした…強いていえば、こちらのバッグのデザインが近いかも。タフタシルクの三角バック ライラック材質の季節感を合わせて暑苦しくならないようにする…とか、色々な気配りは必要になると思いますが、ゆかたにアジア雑貨というのはすんなり馴染むものですね。それにしても、もう8月も終盤に近づき、すぐにゆかたをしまう時期が来てしまいそう。コーディネートのアイディアは、来年へのお楽しみにしておきましょうか…【歩いていけるご近所のお祭りなら、こんなお財布一つでふらっと出かけるのもいいかも…】椰子の実雑貨店 ロータス刺繍コインパース
2006.08.22
コメント(4)
-

ゆかたで歩く奈良・燈花会
あっという間に夏休みが終わり、またいつも通りの日常が戻ってきました。今年は帰省を見合わせたのですが、台風の影響で思わぬ長雨…親不孝者には罰が当ったということでしょうか(涙)8月に入ってすぐ、何となく見ていた楽天トラベルのメールマガジンで「なら燈花会」というイベントを知りました。わが家は近鉄沿線なので、大阪・奈良・京都・名古屋へ出て行くのはとても楽で、意外と早いのです。駅の構内でも、美しい燈花会のポスターを見かけて、ふらりと行ってみようか、と思い立ちました。東大寺や奈良公園といった、修学旅行の王道コースを再訪するのは、よく考えたら高校の修学旅行以来です。奈良盆地特有の「うだる」暑さにはちょっと参りましたが、一泊二日の小さな旅を満喫してきました。まずは、興福寺を見物した後、奈良公園の中の「塔の茶屋」でお昼ごはん。【茶粥を食べてお店を出たら、お庭でこちらが休憩中でした。】 一応野生とはいえ、鹿さん達はまったく人間を怖がりません。食欲は旺盛で、鹿せんべいを買って手にした途端に襲われる観光客続出です(笑)しかし、おばあさん達が並べて売っているおせんべいには絶対に手を出さない。なぜ?どうして?おばあさん達、実は念力で結界でもはってるのか??と、夫と首をひねっておりました。国宝館では、阿修羅像や金剛力士像と対面。彫刻とは思えないほどの、魂を感じさせる迫力。ちなみに、私の頭の中のBGMは、向田邦子ドラマ「阿修羅のごとく」のテーマ(トルコの軍楽隊の音楽)でした…【猿沢池から見た興福寺の五重塔。宿はこの池のほとりの“さるさわ池 よしだや”。】 【部屋の灰皿があまりにキュートだったので、夫が吸殻を押し付ける前にパチリ。】 クラシカルなホテルが大好きな私。奈良にお泊りなら、宿は奈良ホテル!といきたいところだったのですが、今回は散策の途中でお茶をするだけに。というのも、今回はどうしても燈花会見物の「地の利」を優先したかったのです。なぜかというと…浴衣持参で、下駄はいて夜のお散歩をしたかったから。今年新調した有松絞りのゆかたは、皺の心配をしなくていい上、とっても軽いので、これならバッグの底に入れてもいいかな?と思ったのです。なぜか夫も断然ノリ気になり「俺も浴衣着たいなぁ」と言うので、二人して「浴衣で奈良散策」を決行することに。【春日野園地会場の燈花会。遠くに、ライトアップされた南大門が見えました】 デジカメの「夜景モード」で何枚か写真は撮ったのですが、美しい夜の光景はこちらの公式サイトでたっぷりとご覧いただくのをお奨めします。*なら燈花会 公式サイト幸い、下駄の鼻緒で足を痛めることもなく、翌日も大仏さまや二月堂をゆっくりと見てまわり、日本の古都の風情を堪能して帰ってきたのでした。自分用、友達用、実家用…今回のお土産はすべてこちらで決まり!白雪ふきん真っ白なふきんはふだん使い用に。かわいい模様入りもたくさんあって、迷った末にやっぱり「鹿」柄を選びました(笑)十数年前から、京都にあぶらとり紙ブームが起きたように、今や奈良みやげの定番は「ふきん」になったようです。さらりとした使い心地は、家事のやる気を起こさせてくれます。そんな訳で、今日から元気に(?)台所仕事も本格稼動です。<おまけ>【ゆかたで夕食後、出かける前に宿の方がシャッターを押してくださいました。】※たらふく食べて飲んで、二人とも若干ヨレヨレ(笑)
2006.08.20
コメント(6)
-

バカ殿さまの城
ノイシュバンシュタイン城といえば、ドイツ観光の目玉としてあまりにも有名です。バイエルン国王ルートヴィヒ2世が、歳月と資金を湯水のように注ぎ込んで造り上げた「王の夢の城」。ルキノ・ヴィスコンティとヘルムート・バーガーが大好きな私にとっては、この城は、映画「ルートヴィヒ」で目にして以来、いつか訪れたいと憧れていた場所でありました。今回、ワールドカップ観戦でドイツを訪れることになったので、ミュンヘンに滞在して試合の予定のない一日を利用し、城のあるフュッセンの地を訪ねました。観光ツアーだと、バスで城の麓まで乗り付けて一気に見学するようですが、私たちはミュンヘンから、ローカル列車で約2時間ののんびりした行程を楽しみました。城のあるホーエンシュバンガウの村は、メルヘンチックな小さなホテルやレストランが立ち並び、観光客を運ぶ馬車が待っていて…村全体が、一つの舞台のようです。 一方、村のチケットセンターは、機械化が進み非常に近代的な感じでした。バスでマリエン橋のそばまで山を上り、後は炎天下を汗をかきつつ歩きます。 このアングル、ノイシュヴァンシュタイン城の撮影スポットとしても名高い、マリエン橋から撮ったもの。ちなみにその橋を、逆にお城の側から見てみると…こんな感じです。 チケットを買う時に、ガイドツアーを申し込むと集合時間を指定されます。私たちは早めに着いてしまったので、ギラギラと太陽が照りつける下で延々、中に入れるのを待っていました。う~ん…想像していたより、ずっときれい。というか、キレイすぎる。あまりに新しくピカピカした感じが保たれている(のか、お化粧したのかは謎)ので、19世紀の城に来た!というよりは、ディズニーランドにいるみたいな気分になりました。 いよいよ中へ入場。…でも、室内は撮影禁止なのでした。ザンネン。しかし、ワーグナーのオペラをモチーフにした壁画や彫刻にビッシリと埋め尽くされた城内の、あまりにも絢爛豪華な様子に圧倒されてしまった私たち。一つひとつの装飾はとても美しいのだけれど、どこまでもどこまでも理想の美を求めようとするあまり、「きれい」というよりは一種「すさまじい」空間でした。ただ、お城のバルコニーから見る風景は、それはそれは心洗われる美しさで、見とれてしまいました… 見学を終えて、友人の一人が思わず口にした「いやぁー、ここまで来ると“バカ殿”だな、ルートヴィヒって」…という、身もフタもない一言に、一同激しくうなづいてしまったのであります。城の建築に熱中した挙句、引きずりおろされるように退位させられ、直後に不審な水死を遂げたルートヴィヒ2世。しかし、その彼が残した城が、今では莫大な利益をドイツにもたらしているのですから、バカ殿さまも捨てたものではありませんね。永らく中途半端に放り出していた、旅のフリーページを整理しました。新しく、今回のドイツW杯の旅のページも作りましたので、よかったらぜひご覧ください。明日からは夫の夏休みで、お弁当づくりも早起きも9連休です。物騒なニュースも続いていますが、どうぞ皆様、楽しい夏をお過ごしください。
2006.08.11
コメント(8)
-

「海のふた」を読んだ。
私には、海水浴へ行った思い出があまりない。夏に泳ぎに行くとしたら、圧倒的にプールでした。そういえば、ビーチリゾートに行っても、どちらかというと海より、ホテルのプールで泳いでいることの方が多い気が…よしもとばななさんは、子どもの頃から、夏になると家族で土肥の海に出かけ、そこで休日を過ごしていたのだといいます。(そういえば、お父上が海で溺れたという事件もありましたね)その、大事な思い出の地である海辺の町への思いを込めて書かれた小説。元々は、讀賣新聞の土曜日の朝刊に連載されていたものです。私は、連載中から毎週、欠かさず愛読していました。そして、少なからぬ回、朝から、新聞片手にあふれる涙を拭いていました。都会から西伊豆の実家へ帰ってきた主人公の女の子が、すっかり寂れてしまった故郷で、かき氷の店を始める…という物語。普通は、主人公が様々な困難を乗り越えつつ夢を実現させようとする、そのプロセス自体がストーリーになりがちですが、この本の中では、種々の問題は「まあなんとかうまいこといって」あっという間にかき氷店はオープンし、やがて軌道に乗ってしまいます。でも、その先に続く、彼女の過ごしたひと夏の日々は、淡々としていながらとても大切な事柄に満ちていて。海水浴場なんて何年も行っていない私も、砂浜の暑さとか、海辺の旅館街の雰囲気とか、夕方の海の水のぬるさとか…その一つひとつをリアルに想い起こすことが出来る、それはやっぱり文章の力なのでしょうか。物語の横糸を織り成すもう一人の登場人物が、ある日主人公の家へやってくる「はじめちゃん」。主人公にとっては、母親の友人の娘である「はじめちゃん」は、ある事柄でボロボロに傷つき、心身を癒すべく海辺の町に送られてきて、主人公のかき氷店を手伝うことになるのですが…。この「はじめちゃん」にまつわるいくつかのエピソードや設定に、私自身の体験と重なる部分があって、何度読んでも泣けてしまうのですけど。だからこそ、ゆっくりと、でも着々と立ち直り、人生の扉を開けていく彼女たちの姿に励まされます。う~んと若い、それこそ中学生くらいで出会えたらいい本かもしれないな、と思う。あぁ、夏って人を成長させる季節なんだなぁ。…と、改めて実感させてくれる一冊です。大げさな出来事は何もないし、主人公達も決して声高に何かを叫んだりはしないのだけれど、読後に残る爽やかな満足感が好きで、夏が巡ってくると手に取る本なのです。名嘉睦稔さんの、美しい版画による挿絵の数々も素晴らしい。今度出た文庫版にも、表紙や本編にちゃんと収録されています。「海のふたを閉める」“夏の終わり”の気分を表現するものとしては、この言葉、まさに「言い得て妙」ではないでしょうか。【私が持っているのはこちらの単行本。発行元はロッキン・オン社】海のふた以前の日記で紹介した、行きつけのカフェの店主夫妻にこの本をお奨めしたところ、「とっても良かった」と喜んでくださいました。「カキ氷、出したくなっちゃいましたよ~」と言ってくれたので、ぜひメニュー開発を!!とお願いしてしまった図々しい私(笑)
2006.08.10
コメント(11)
-

バジルペーストとゆかたパーティー
土曜日は、通っている着付け教室の先生が主催する「夏のパーティー」でした。毎年この時期、先生が教えていらっしゃる各曜日の生徒さんが一堂に会し、夏ということもあって、ゆかた姿でランチをいただいて歓談、というイベントをされているそうで。お稽古を始めてまだ1年未満の私は、初めての参加でした。一口に「ゆかたで集合」と言っても、先輩の生徒さん達の着こなしには様々なバリエーションがあって、三十人ちょっとの小さな集まりでしたが、とっても勉強になり楽しかったです。…で、実は本題はそこではなく、この日先生からいただいた、素敵なおみやげのこと。先月のお稽古のときに「今日はお帰りになる前に、ちょっとおやつを召し上がってね」…と出していただいたのが、う~んと冷やしたトマトをバジルペーストで和えた、シンプルなサラダ。小皿に3、4切れずつ取り分けて、冷たいお茶と一緒にいただいたら、慣れない帯結びと格闘した疲れがすーっと引いていきました。何より、立ち上るバジルの香りの力強いこと!トマトの美味しいこと!…もしかして?と思って伺ったら、やっぱり、バジルもトマトも先生のお母さまが畑で丹精された、自家製とのことでした。話はパーティー当日に戻って。帰りがけ、私たちのクラスでリーダー役をしてくださっている方から「これ、先生からお土産です!」といただいたのが、小さな瓶に入ったバジルペーストと、そのレシピ。何でも、バジルはこの時期、次から次へ元気に育つそうで、もし自分でも作ってみたくなったら、いつでもお分けします、とうれしいコメントつきでした。【帰宅後、湯むきしたトマトをざく切りにして、サラダを作ってみました】 先生のバジルペーストレシピ:<材料> バジルの葉 どんぶり一杯分 オリーブオイル 300cc にんにく 一かけ 塩・黒胡椒 適宜(小さじ2程度) 松の実 25g*すべての材料をミキサーにかけてペースト状にすれば完成。準備でいろいろお忙しい中、手間をかけて手作りの贈り物をしてくださった先生に、改めて感謝しながら美味しくいただきました。次はどこで浴衣が着られるかな…夏限定の楽しみ、ひとつでも多く機会を見つけたいものです。【恥ずかしながら、これが今年のゆかた&帯。年甲斐もなく赤い帯&首チョンパですみません】 絞りの浴衣と博多帯、両方楽天のこちらのショップで購入しました。(ゆかた購入の日記はこちらから)品物はもちろん素敵ですが、対応もとても丁寧で大満足でした。有松鳴海絞り浴衣と着物 「ゆかた屋」
2006.08.05
コメント(15)
-

離婚と病気
久しぶりに編み物をしました。こんな季節に編み針を持つのは、滅多にないことなのですが。綿・レーヨン混紡の、フワフワとした糸を使って、一見タオル地のような感じのニット帽を編みました。自分用ではなくて、人に差し上げるためのもの。親しい友人が、二ヶ月前に癌の診断を受けて入院しました。それでも、数時間に及ぶ手術を乗り越えた彼女。この度、めでたく一時退院し、あと数回の抗がん剤治療ですべて終わる…と報告が来ました。急な入院話に仰天したので、順調に回復している様子に、ホッとした次第です。ただ、副作用による脱毛は避けられないようで…かつての同僚の中では、誰よりもおしゃれが好きで、サラリーを高いお洋服につぎ込んでいた彼女の気持ちを思うと、いくら一時的なこととはいえ、切なくなります。退院祝いと、あと少し、がんばって…という思いを込めて、キレイな色で頭をすっぽり包む帽子を編んだというわけです。かぎ針でグルグルと編むだけのシンプルで簡単なものでしたが、「サイズもピッタリでうれしい、今度の入院にも持っていくから」…とお返事が来て、安心しました。【テキストにしたのはこちらの本です。表紙はベビーちゃんですが、大人用から子ども用までたくさん作り方が載っていて、写真がきれいです。】細編みと鎖編みでできる帽子それにしても、去年あたりから、周囲の同年代で大きな病を経験する人が多くて、驚かされています。脳腫瘍とか難しい心臓の病気とか癌とか…幸い、どの人も大変な経験を乗り越えて、快方に向かってくれているのが本当にありがたいのですが。三十代から四十代へ足を踏み入れる頃というのは、そういう年代なのでしょうか。思い返すと、そのちょっと前の1~2年間に、やたら耳に飛び込んできたのは離婚の知らせだった気がする…「え!よりにもよって、あなたたちが、どうして??」と、絶句するようなケースも、いくつか。今ならまだ、新しい人生を切り拓けると思える、切り換え期ということ?まぁ、「七年目の浮気」という映画もあったように、結婚生活がそれくらいに差し掛かると、色々なことが起こるのでしょうね。わからなくもないです。「旦那が退職金をもらったら熟年離婚してやる!」と息巻いている、別の意味ですごい友人もいますが(苦笑)ひと昔前は、毎月のように結婚式に招かれていたし、出産祝いを次々に選んでいた時期もあった。人生は四季のように移り変わるものだと、あらためて考えさせられます。どんなお金持ちも貧乏人も、平等に歳だけは取っていくのです。それにしても。とても苦しい思いをしている当事者を前に、他人がその辛さを共有することは、本当に難しいとつくづく考えます。心配してオロオロするばかりで、何とか手を差し伸べたいと思うけれど、どうしたらいいやらいつも途方にくれてしまう…人生の、困難な時期に直面している友の話を聞く度に、年の功が身につかない自分が歯がゆいこの頃です。
2006.08.04
コメント(11)
-
火曜日の気になる彼
私はどうも「笑い」に関する感覚が狭量なのか鈍いのか、TVのお笑い・バラエティ番組を見て(面白い!)と感じることがあまりありません。何度かやって来ている「お笑いブーム」なるものも、小学生の時の漫才ブーム(!)を除くと、ずっと乗りそびれている気がする…しかも、年齢とともにますますその傾向が強まってきているようで、「最近のテレビって、本当に見るものがないなぁ」と嘆いている自分に(あんたは年寄りか!)と自己ツッコミを入れてしまいたくなるほど。熱心に見ないから、面白いものにも出会えないだけなのかもしれませんが。でも、その分「これは好き!」と思える番組やドラマを見つけると、のめりこんでしまいます。今、久しぶりに「あ~、今日は○○がある日だー」と朝から楽しみにしているのが、火曜10時のドラマ「結婚できない男」。これ、友人が“ホントに笑える”と強く奨めるので、先々週から見始めたのですが(実は登場人物の細かい設定とか全然わかっていません)、もう笑えること笑えること。主人公の、結婚できない四十男を演じる阿部寛さんが、おかしいったらない。先週からは夫も巻き込んで、二人で大笑いしながら見ています。阿部ちゃんの演技もさることながら、主人公のキャラクター設定が細かいところまで気がきいているのですよね。潔癖症でクラシック好きで…というあたりまではまぁ、ありがちかな?と思いきや、「男はつらいよ」の大ファンで、48作全部DVDを持っている、とかね(笑)自分では「結婚しない男」のつもりでも、他人の目から見ると「結婚できない男」…っていうケースは、私の友人・知人にも心当りがないわけでもなく、このドラマの行く末がとーっても気になります。そして、ドラマの後は11時からNHKの「サラリーマンNEO」でもう一笑いする、というのが、火曜日の夜の定番コースです。こちらは春の放映開始から大好きでずっと見ているのですが、いくつかあるコーナーの中でも、沢村一樹さんの演じる「川上くん」というキャラクターのコントが大好き♪いつも、必ず窮地に追い込まれてしまう小心者のサラリーマン、川上くん…思い出すだけでもおかしい。阿部ちゃんといい沢村一樹といい、黙っていれば本当に美しい顔立ちの男性が、真顔ですっごくおかしな人を演じるというのは、何だかとてつもなく贅沢なものを見ているような気がします。(いつも遊びにいくせしるんさんのブログでも、まったく同じTVの内容に触れられていてうれしくなってしまいました。火曜日にこのパターンを確立している視聴者は意外と多いかも?)
2006.08.02
コメント(10)
全12件 (12件中 1-12件目)
1