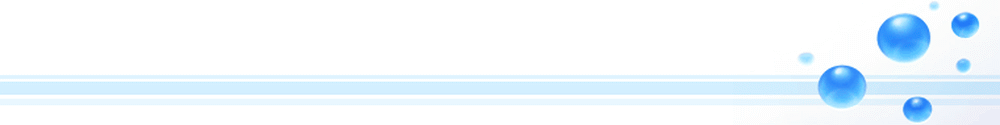2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
天使の正体
昔からずっ~~と疑問だった天使の正体がわかりました。なるほど~~!なるほどね~~。そこでレッスンが終わった後で教室の天使たちを集めて瞑想
2010年01月28日
-
海外で拙著「靖国」をテーマにした勉強会が開かれる
たいへん嬉しい情報が舞い込んできました。ニューヨークはマンハッタンで、拙著「この国を愛するために 靖国」をテーマにした「勉強会」が開かれるというではありませんか。http://nyjapan.com/postDetail.jsf?post_id=27766海外に住む日本人は自分たちのアイデンティティーを、改めて自覚させられるとはよく聞きます。このような形で「靖国」が話題になることは、一過性の本に終わらずに済んだという意味では、とても嬉しく思いました。ベストセラーになって欲しいのは当然ですが、一過性に終わらずに読み継がれて欲しいと言うのが、毎回作品を執筆する際の私の願いだからです。
2010年01月27日
-
47都道府県終了!
小六の息子が中学に上がる前に四七都道府県を覚えさせようと、父親塾を始めて約一ヶ月余り。無事に子供たちは県庁所在地まで覚えることができました。あとは卒業までに河川や山地山脈までが目標です。算数は九九を覚えないと始まりません。私も子供時分に九九を泣きながら覚えさせられました。「社会科の地理で九九に相当するのが、四七都道府県ではないか?」ふとそう思い立ち、これは九九同様に小学生のうちに覚えさせねばと思ったのです。私自身、地理が苦手だったのもそれをしてこなかったからではなかったかと思ったからです。そこでたまたま自宅にあった「クレヨンしんちゃんのまんが都道府県おもしろブック」をコピーして、教材代わりに使い始めたのですが、やり始めるとアイデアもいろいろと浮かんできます。そんなことをしているうちに、気づいたことがありました。今のように世の中がサラリーマン社会でなかった昔は、子が親の仕事を覚えて跡を継ぐことが当たり前でした。すると子は親に習い、伝統芸能の世界に生きる親子のように、そこから師弟関係も芽生えたと思います。自分は親に育てられ、一人前にしてもらったという恩義もそこから生まれます。でも今のサラリーマン社会では、親が直接子供に教え伝えられることが限られてしまいます。親に自分は仕込まれ、育ててもらったという感覚も、昔に比べて持ちにくくなりました。小学生が習う勉強なら、親が本気になれば、すべての科目でもなくても、まだ十分に子供に教えられるレベルです。親が自ら子供に勉強を教えることは、自分は親に仕込まれ、育てられているという実感を子供に抱かせる、大切な機会です。親のおかげで自分は九九をいえるようになった。親のおかげで自分は四七都道府県をいえるようになった。親のおかげで自分は社会で生きていくために必要なものを身につけられた。だから、塾や家庭教師に最初から丸投げせずに、可能な限り親が直接子供に勉強を教えることは、子が親を敬い、恩を感じて、ゆくゆくの親子の絆を深めるためにも、とても大切なことだと思いました。
2010年01月26日
-
久々のセミナー
Kさんの勧めで午前中、久々にセミナーに参加しました。Win Win 育成協会の主催で「良い子の陥りやすい落とし穴と、そのメンタルケア」です。とても良かったです。1.子育てに正解はない。子供はみんな個性があって違いがあります。長男には通用した育て方も、次男には全く当てはまらないことは当たり前のこと。それを上の子供はちゃんと育ったのに下の子はだめだと、あたかもその子に問題があるような発想は子にとって不幸なことです。2.崩れない子供は居場所がある。「あなたの仕事は勉強でしょ」と言ってしまうと、成績が下がってしまったら、子供は家庭に居場所がなくなってしまい、精神的に追い詰めてしまうことになります。勉強以外の家の手伝いを与えることが、自分が家族の一員であり、役割があり、自分はここにいてもいいという精神的な拠り所になります。3.期待しておいて「好きにしていいよ」は無責任。この説明を聞いていたときに、矢沢永吉の言葉を思い出しました。「僕は自分の子供には期待しない。自分自身に期待する。それが子供への愛だ」親の期待は子供にとっては精神的な負担。それよりも親が自分自身の人生に期待することが、かえって子供を伸び伸びと活かすことになります。親が子供に期待するのも、親自身の人生が思い通りにならないから、その思いを子供に託している、一種の依存である場合が多いのです。他にもセミナーを受けて学んだことや気づいたことが沢山ありました。Kさん誘って下さり、ありがとうございました。
2010年01月23日
-
新年の瞑想レッスンは創造力がテーマ
年始めのリラクセーション講座の一部をまたまたYoutubeにアップいたしました。★新年の瞑想レッスンは創造力がテーマhttp://www.youtube.com/watch?v=ohqu2hDDxAc&feature=channelhttp://www.youtube.com/watch?v=jgkDNY5cHo8&feature=channelhttp://www.youtube.com/watch?v=-f4fQU8BmZ8&feature=channelhttp://www.youtube.com/watch?v=STn96ExIWvk&feature=channelhttp://www.youtube.com/watch?v=pt9vKnnJw44&feature=channel
2010年01月21日
-

ISE神宮参詣2010
今回のISE神宮参詣はマイクロバスを出せませんでしたので、こぢんまりした人数での初詣となりました。その代わり機動力を活かした臨機応変な対応ができ、今までにない面白味もありました。まず外宮の最後に、普段まず行かない細道を通って、人知れず信仰されているご神木へ到達。ここはたぶんTatsuツアーで初めて皆さんを案内したところです。その後、内宮へ向かったのですが、これが予想以上の大渋滞。高速道路が千円になった初の神宮参詣でしたので、例年になくマイカー参拝者が多かったようです。いつもよりもだいぶん手前からの渋滞でした。そこで運転手(私)を除くメンバー全員を猿田彦神社の数百メートル手前で降ろして、先におかげ横丁へ向かってもらうことにしました。私は駐車場へ車を停めて、後から合流。内宮では式年遷宮に向けて、宇治橋が新しくなっていました!ほんとうにきれいで、陽に当たっていると輝いて見えます。ご祈祷を終えて、一通りの参拝を終えた後、今回は別宮 月讀宮へもお参りしました。すでに5時半を過ぎていましたので、暗闇の中での参拝です。参道途中の灯籠のわずかな灯りが道を指し示してくれます。月讀尊は美の神、光の神、そして、人々にインスピレーションを与えてくださる神だそうです。闇夜を歩いているような迷いの中を生きているときに、まるで月明かりが暗い夜道を迷わぬように照らしてくれるように、インスピレーションを与えてくれるのでしょうか。月讀宮の灯籠のわずかな灯りが、それこそ私にそんなインスピレーションを与えてくれました。今回、月讀宮を参ろうと思った理由の一つは光の神ということからでした。元旦の日、実家近くの総合公園へ子供を連れて遊びに行ったら、ガラガラの公園にもう一組の親子がいました。かえって話しかけない方が不自然なほど閑散とした公園でしたので、どちらからともなく親同士が話しかけました。その間、双方の子供たちもいつの間にか打ち解け合って、楽しく遊んでいます。そこでびっくりしたのが、双方の子供の名前が偶然にも「光」だったのです。新年早々、何とも縁起の良いことだと喜びました。そうしたら今年の皇居での歌会始のお題も「光」。今年の神宮参詣はこんなこともあって、月讀宮へお参りしようと思ったのです。そうしたら今回の参加者にご子息と同伴された方がいたのですが、そのご子息の名前もなんと「光」。「光」は幸せの象徴だとは、レッスンで常々話していることですが、この一連の「光」にまつわるエピソードに、きっと今年は光り輝く素晴らしい一年になるのではないかと、期待膨らませた神宮初詣でした。
2010年01月17日
-

新年の滝行は喜び
新年の禊ぎに椿大神社へ詣でました。さすがに一月ともなれば寒いです。こんな冷たい滝行は何かテーマを決めて、それを支えに受けないとどうにかなってしまいそうです。そこで今年一年をどのようなものにしたいか、それを言い表す漢字一文字を思って、厳冬の滝に挑むことにしました。新年早々に決めた語は …「喜」喜びで一杯の一年にしよう!ところがこの底冷えする寒さの中、裸同然のふんどし姿で順番待ちをすることに喜びはなかなか感じられません(笑)いきなりくじけそうです。と次の瞬間…そうか!喜び一杯の一年にしたいと願っても、受け身にそれを待っていたのでは、とても叶わないのではないか。何ごとも喜びと感じられるような意識を作らなければ、「喜び一杯」の一年にすることはなかなかできないのではないか、と悟ったのです。よし、この厳冬の滝行を「喜び」と感じられる意識を作ろう!改めてテーマが決まりました。およそ一時間。震えながら心を一つに集中して、凍えるこの状況を「喜び」と感じられる意識を作ろうと、順番待ちをすることにしました。そして、いよいよ順番がやってきた時、自分も含め、人々の喜んでいる姿を走馬燈のように思い浮かべながら、滝に打たれました。
2010年01月11日
-
意識改革を起こすための初詣
欧米人にとってクリスマスが特別であるように、日本人にとって新年は特別な行事です。日本人には禊ぎの思想があり、禊ぎは意識の生まれ変わりを起こすためのものです。初詣をただお正月気分を楽しむためではなく、意識改革のきっかけとするにはどうしたらよいか?年始めのリラクセーション講座の一部をYoutubeにアップいたしました。初詣についてではありますが、まだ年が改まって間もない時期ですから、お聴きいただければ幸いです。★意識改革を起こすための初詣http://www.youtube.com/watch?v=S8mGJtRHurkhttp://www.youtube.com/watch?v=Q8zqHbsZAhM
2010年01月10日
-
謹賀新年 龍馬伝が始まりました。
明けましておめでとうございます。大河ドラマ「龍馬伝」が始まりました。これほど龍馬が人々に好かれている理由の一つに、そこに日本の心があるからだと思います。薩長同盟に象徴されるように、龍馬の思想の根底には、「和をもって尊しとなす」という、聖徳太子以来の日本人の「和の精神」が、常に息づいているのです。仲良しが仲良くするのは当たり前のこと。それをことさらに和の精神とはいいません。仲良くできない人といかに仲良くするか、それが和の精神です。そして、仲良くできない人と仲良くするためには、たとえ相手がどのような者であったとして、その人を赦し、受け入れ、認めることが出来たときに、初めて和することが出来ます。すなわち日本の和の精神は、あのイエスが説いた「愛」に匹敵する「許しの思想」なのです。そしてその典型が薩長同盟といえるでしょう。龍馬はイエスの説いた思想に通じる「愛の人」だったのです。一介の浪人が世の中を変え、歴史を動かしたこと。ユーモア溢れるキャラクター。それだけではなく、和の精神を持った愛の人・龍馬だったからこそ、今日なお多くの人々の琴線に触れ、共感するのではないでしょうか。
2010年01月03日
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- 歯医者さんや歯について~
- 美容院に歯医者さんに忙しいぞ。
- (2025-11-20 06:54:24)
-
-
-

- 今日の体重
- 2025/11/20(木)・「プラスマイナス…
- (2025-11-20 13:00:00)
-