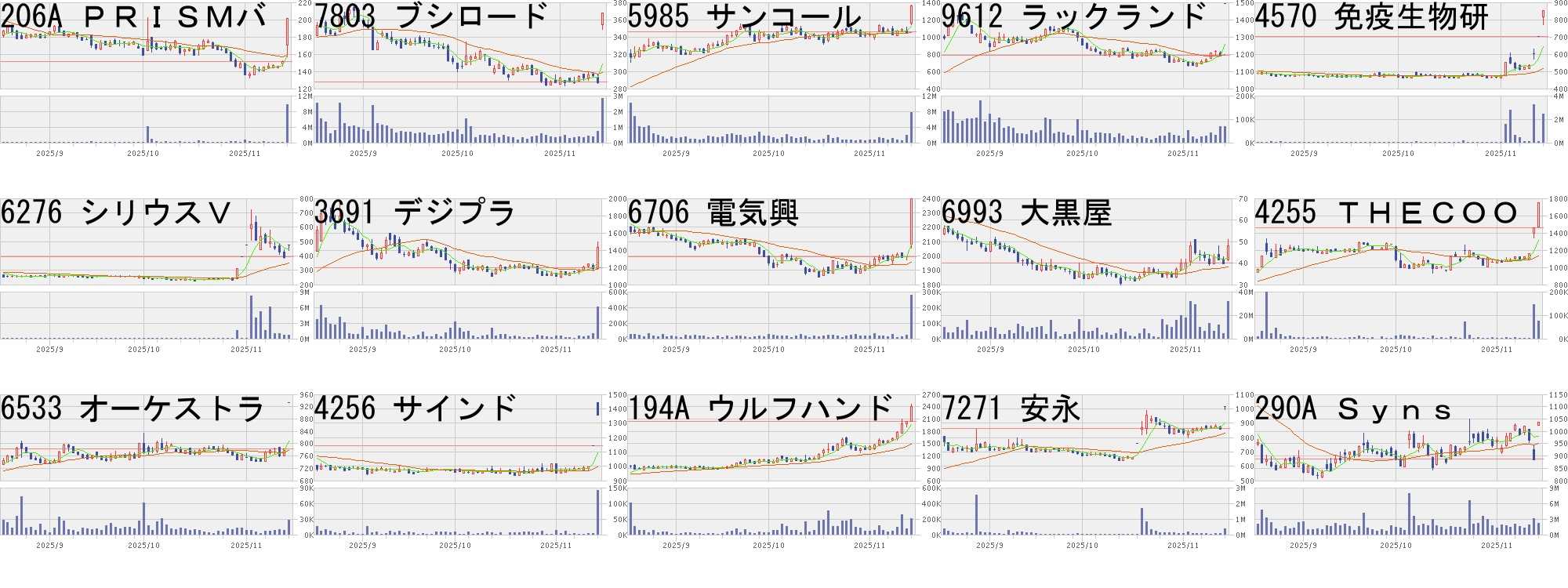2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年03月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
求められる人材は「仕事を創る」人
コスト削減について一巡した企業で次に考えないといけないのは、「仕事を創る」ことです。あれ、これまでは「仕事をいかに少なくするか」が焦点でしたが、仕事を極限まで減らしても、必ずしも、みんながhappyになったわけではありません。もちろん、無駄なことを続けることや、意味のない仕事を増やすことは論外ですが、意味のある新しい「仕事を創る」ことこそが今後の「バリュー」です。仕事を創る人に、報酬をあげましょう。仕事を創る人に、投資しましょう。新しい仕事が生まれることで、雇用が作り出され、それによりいきいき楽しく仕事ができれば、それこそが社会貢献でもあります。新しい仕事を創れる人、これがこれから求められる人材です。
2004年03月27日
コメント(0)
-
プロジェクト・ポリシー
どんな仕事でも仕事の「目的」があるわけですが、最近はそれにプラス、「ポリシー」が必要です。ポリシーというのはただこなすだけではなく、どんな気持ちで、どんなモチベーションで、どんな夢をもって、どんな方針で、その仕事をやっているか。「ビジョン」というのも似ているかもしれません。目の前の仕事の「目的を明確にする」だけでも一苦労ですが、さらにどんな「ポリシー」をもっているか。このポリシーが輝いているかどうか。これをチェックしてみましょう。(自分自身のポリシーも、一度書き出してみるのがいいかもしれません)ひいてはプロジェクトや部署の「ポリシー」があるはず。プロジェクトのポリシーも輝いていて欲しいです。
2004年03月25日
コメント(0)
-
会社といっても人間の集まり
「会社」と言葉には、なんとなく巨大な、得体の知れない力を感じさせますが、結局は人間の集まりが会社なんです。確かに、カルチャーとか、見えない資産はあるでしょうけれどそれも人間が作ったものですよね。それを運用しているのも人間。上司も社長もお客さんもみんな人間。会社もビジネスのシーンも、演劇の舞台と思ってみると楽になります。その舞台で社長の役をしているだけ、嫌な上司や取引先の役をしているだけで、舞台裏では、みんな一人の人間なんです。会社や上司や会社に関わるものすべてが「悪」に見える、という人がいます。(私もたまにそう思うことがあります)そういうときは悪役ばかりが揃っていると思ってください。舞台裏を見たら、みんなおんなじ人間なんです。(「悪役」の人ほど「いい人」だって言いますしね。)
2004年03月17日
コメント(0)
-
復活しました! 「モチベーションの低い上司とのつきあい」
しばらくご無沙汰しておりましたが、復活しました。ご心配頂いたかた、どうもありがとうございます。歩みはのろいですが、ぼちぼち頑張っていきたいと思います。今後とも、ご声援、よろしくお願いします。------------------------------業績の落ちている会社、部署は、雰囲気が暗いだけではなく、モチベーションの低下している人が極端に多くなります。業績がよくてもモチベーションが低いところというのは時間の問題で、業績は必ず落ちていきます。場合によっては、管理層自体のモチベーションが下がっていることがあります。これでは、従業員や派遣の層だけモチベーションが高いことを期待するのは難しいですよね。上の人のモチベーションが落ちている状態は、下の人にとっては大きなポイントになってきます。なぜこの上司はモチベーションが低いのか。そんなの知らないよ、と思ってしまいがちですが、これは下の人にとっては死活問題と心得るべきです。評価が低かったからか、給料が上がっていないのか、部下がついてきていないのか。仕事が面白くないのか。いずれにしても上のモチベーションが下がったら、組織にとってよいことはありません。ひどい場合はさらにその上司に直訴、なんて例もあるでしょうが、それは最後の手段。部下なりにモチベーションが低い理由を考えてあげましょう。そして、愚痴でも聞いてあげましょう。上司はなぜモチベーションが低いのか、上司の問題意識は何か、一緒に考える場を作れればベストです。「部下の立ち入る領域ではない」と自分でカベを作っている人も多いし、上司の立場でもそのように思っている人もいるでしょう。ただ、上司のモチベーションの低さが組織に与えるダメージを、その上司にも十分に認識させる必要があります。できる部下は、上司のモチベーション管理、を常に考えています。
2004年03月16日
コメント(1)
-
東急本店前
先週末、渋谷の東急本店前が見える某喫茶店から東急本店前で交通整理をする方々の姿が見えました。ちょうど道が細く、人通りも多いので、その交通整理をなさっていました。その交通整理の腕もすばらしいことながら、東急所属?の方なのに、警官と間違われてか、お年寄り連れや、就職活動中とおぼしきスーツの似合わぬ学生さん、などなど、道を聞かれています。それもかなりの頻度です。それに対しても、丁寧に手際よく、答えていらっしゃいました。もちろん、交通整理しながら。その丁寧さと、仕事に対する真摯さが、伝わってきて、感動しました。プロの仕事だ、と。道を聞かれても、本来業務じゃ答える義務などたぶんないはずですが、これらをこなしながら、本来業務である交通整理もきっちりこなす。私が、東急の経営者なら、彼らに特別ボーナスを支給します。それくらいのプロの仕事を見せてもらったような気がしました。ちなみに、道を教えてもらった就職活動中とおぼしき学生さんは、彼らに道を教えてもらったあと、走っていきましたが、察するに、道を教えてもらったおかげで、面接に間に合ったことでしょう。学生さんの人生を間接的に、助けたことになるかもしれないよなー、などと勝手に想像しておりました。見ていて、心が豊かになりました。
2004年03月08日
コメント(2)
-
チップ再考ーサービスにお金を払おう。
海外にはチップという制度が健在ですが、日本では、「サービス料」なる不可解な料金が、合計飲食料の10%などと問答無用で乗せられていたりします。チップやサービス料というのは、提供されたサービスについて、サービスを受けた人が、サービスの質によって、金額を決めて支払うものですが、払う人の自由意志、というのが基本です。よいサービスをしてくれた従業員にはチップがはずむ。提供したサービスがよければ、それがダイレクトに報酬として跳ね返ってくる。海外のサービス業従事者には、チップで稼ぐためによいサービスを提供しよう、といったインセンティブが働きます。日本のサービス業は、世界で誇るべき質のある産業ですが、「あの人のサービスがすばらしいから、あの人に報いたい」と思っても、すぐにその人に報いることはできません。チップがないことによる利点もありますが、感謝の気持ちを表す場としてのチップというのも悪くないと思います。日本でも素敵なサービスをしてくれた人には、十分に報いたいのです。(今の状況では、仮にチップを渡しても受け取ってもらえない可能性大ですが。)これまでは、モノを買ってもらわなければ、いくらよいサービスをしてもお金はもらえませんでした。サービスはモノを買ってもらうための「おまけ」だったわけです。逆に、「モノ」の値段に隠れた「サービス」の値段(コスト)が組み込まれているのです。(サービスコストがタダと思っている人は意外と多いんですよ。世の中にタダなものはありません。)サービスをモノの付属物ではなく、サービスはサービスとして対価を払うようになってくれば、現在のサービス業はもっと変わってきます。これからは、売っているモノはよくない「営業マン」でも、教えてくれた情報や、ソリューションがよければ、モノは買わなくても、そのサービスに対してお金を払う。そんな時代が来ます。「タダ」だったサービスについても、サービスに応じて値段がつくようになれば、日本もモノ依存の社会ではなく、サービス主体で経済が成り立つ成熟した社会になっていくでしょう。日本では、サービスと水はタダ、と言われていますが、水についてはおいしい水を、ガソリンより高い値段で買っている、ということについて違和感がまったくなくなってきました。10数年前からは考えもつきませんでした。10数年後はサービスに対する考えもずいぶんと変わっているでしょう。また変えていかねばなりません。
2004年03月01日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1