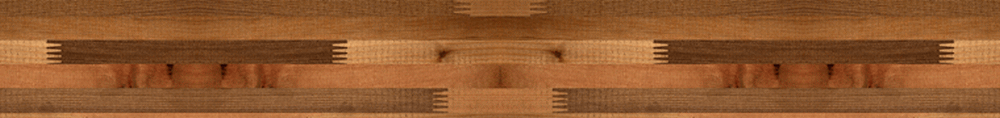2010年12月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

ミニとして特別な扱いをしない その1
こんにちはenoです。 『 ミニとして特別な扱いをしないようにする 』 【その1】 バスケットボールの基本プレー、基礎技術は大人と子供と何ら変わることはない。 その為、大人が考えるバスケットボールをそのまま伝える努力をするべきである。 しかし、子供の体力、筋力、感性が成長過程において質や量の面で大人と異なる点が多々あることも現実である。 そこで、限られた時間やコートで効果的に成果をあげるためにも明確なテーマを持った練習内容や、練習時間以外での練習方法等を指導者が創意工夫することが重要となってくる。 この頃の子供達は筋力・体力に限りがあっても運動神経の発達は著しく、むしろ大人が考える以上に優れている点もある。 バスケットボールの基礎的な動き、ボディコントロール、ボールコントロールや、俊敏性の体得等の吸収力はすばらしいものである。 特に、初期の子供にとってそのような観点を中心に段階的に指導することが将来に繋がることと確信する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー PS:今年もあとわずかですね。今年はどんな年だったでしょうか。目標、夢を達成した人。力及ばず辿り着くことが出来なかった人。しかし、大事なことは前を見て進むことです。2011年に幸あれ。皆さん、よいお年をお迎えください。 By : 榎本日出夫 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2010年12月31日
コメント(0)
-

バスケットボールを通して子供の人格を育てる
こんにちはenoです。 ミニバスケットボール精神の「友情・微笑み・フェアプレー」は、ミニのみではなく、広く普及されねばならない。人間性を否定してまで、勝負を追求すべきではない。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 『 バスケットボールを通して子供の人格を育てる 』 勝った、負けた事のみにこだわるのではなく、子供達自身の中で努力する心や、向上心を植えつけさせるような指導を、指導者として意識的に練習の中に含まなくてはならない。 チームという集団生活を通して、チームのために何が出来るかを考える。 その為に、少々の自己犠牲を払っても、チームのために頑張るといったフォア・ザ・チームの精神。 さらに、チームの規律やルール等の秩序を全員で守る意味や価値観。 また、チームメイトのことを思いやる心や協調性。 そして、挨拶、礼儀等も強調すべき点であり、さらにバスケットを謙虚に受け止める心を養うことも重要である。 そして、指導者自身が「率先乗範」すべき点でもある。(人の先頭に立って物事を行い、模範を示すこと) 自分の思うようにいかなくても我慢して、忍耐することや、ボールやシューズ、ユニフォーム等の物を大切に扱う事もしっかり指導すべき点でもある。 さらに、試合場、体育館、ロッカー、シャワールーム、公共施設の使い方、生活の仕方も他人に迷惑をかけない、自己管理できる選手になるように指導していくべきである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2010年12月29日
コメント(0)
-

勝利至上主義は好ましくない! その2
こんにちはenoです。 手っ取り早く勝つために、基礎的な練習時間が十分に取れず、選手の促成栽培が行われているとすると、子供たちの才能をただ浪費することになる。 優秀な人材を自らの手で潰すことになりかねないとしたら、由々しき問題である。 技術が中途半端だから戦術も中途半端にしか身につかず、子供達もただ負けて叱られるだけ。それでは一体何のためにバスケットをやっているのか疑問になる。 指導者自身が原点に帰るべき時に来ているのではないかと思う。 ただ単に勝敗のみを強調するのではなく、必要な厳格さと、寛大さをもって広い視野に立って子供達を指導するべきである。 もちろん、競うことは人間を進歩させる大切な要素であるが、いつまでもその勝負にこだわらない心の広さを指導者自身が持つべきである。 子供達にも日々の練習で競うことを楽しむゆとりや、プレーしながら競うことと、楽しむことをバランスよく指導することが大切である。 さらに、プレーの結果だけをみて、うまく出来ない子供達に体罰のみを与えることは何ら根本的な問題可決にはならない。 その子供達にどのように自信と勇気を与えて、育てていくかが、指導者として大きな問題である。 とくに、バスケットボールへの入り口であるミニバスケットボールにおいては、このことはさらに強調され続けなければならない。 ミニバスケットボール精神の「友情・微笑み・フェアプレー」は、ミニのみではなく、広く普及されねばならない。 人間性を否定してまで、勝負を追求すべきではない。その試合に負けることにより、全てが否定されるものでもない。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2010年12月28日
コメント(0)
-

勝利至上主義は好ましくない! その1
こんにちはenoです。 他県、他地域、出来るならば、海外にも積極的に遠征して、バスケットを通じて見聞を広め、多くの人達と触れ合うことが子供の将来に有意義な体験となる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 『 勝利至上主義のみは好ましくない 』 : その1 試合は子供達にとって非常に魅力的であり、ハッスル場所でもある。 とくに全国大会出場の感動は、子供はもちろん。保護者を含め、指導者にとっても一生の思い出となる。 そして、勝って泣き、負けて泣く。努力した成果をチームメイトや指導者と一緒に体験できることがスポーツの良さである。 子供達のこれからの人生にとって何物にも替えがたい貴重な経験となるわけである。 しかし、優勝熱に浮かされた指導者が、ただ勝ちたいがために、子供達に過酷な条件を押しつけて勝利へ駆り立てたり、また、何が何でも勝つという考え方のみを子供達に教え込んではいけない。 手っ取り早く勝つための大人びた戦術のみを追求することにより、基礎的な練習時間が十分に取れず、選手の促成栽培 【 野菜および花などを温室,温床,ビニール ハウスなどの施設を用いて露地栽培よりも早く収穫する栽培法 】 が行われているとすると、子供たちの才能をただ浪費することになる。 優秀な人材を自らの手で潰すことになりかねないとしたら、由々しき問題である。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2010年12月24日
コメント(0)
-

バスケの面白さを教える その2
こんにちはenoです。 上手に出来たことに対しては、自分のことのように子供達と一緒に喜んであげることも必要である。 練習の中に遊びの要素を取り入れながら、いかに相手より速く、正確に、どれだけ数多く出し抜けたかという成功感を競い合うこともよい練習となる。 とくに、直接・関節攻撃いずれの中でも、1対1におけるオフェンス・ディフェンスの駆け引きの中に、相手の逆を取る醍醐味を日々実感して、積み重ねていくことが重要である。 加えて、子供達自ら上手になりたい、強くなりたい、という気持ちを湧き立たせて、意欲的にバスケットボールに取り組ませるように指導してあげるべきである。 将来、上級レベルの学校でもバスケットボールを続けていきたいという気持ちを、ミニの時代から子供達に植え込むことも大切である。 県や国で1位になることも意義深く、価値あるものであると思うが、ただそれのみに追われてはいけない。 広くアジアや世界に目を向けて、夢と希望を持つことが出来るように指導すべきである。 そして、他県、他地域、あるいは海外にも積極的に遠征して、バスケットを通じて見聞を広め、多くの人達と触れ合うことが子供の将来に有意義な体験となる。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2010年12月22日
コメント(0)
-

バスケの面白さを教える その1
こんにちはenoです。 日々の練習において、練習のための練習に陥りやすいので、指導者は常に「ゲームライクな練習」をするように、子供達を指導しなければならない。 何故なら、練習にできたプレーがゲームの時にできない。というケースの多くはこのことが原因であるからだ。 スピード、緊張感等を最大限ゲームに近い状態で常に練習を行うべきである。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『バスケットボールの面白さを教える』 その1 子供達にはまずは運動すること(体を動かすこと)の楽しさと、特にバスケットボールでは、シュートを決める面白さを教えることが一番である。 そして、技術の失敗、戸惑いをしかるのではなく、丁寧に指導し、うまく出来た時には褒めてやり、長所をみつめ、プレー1つ1つに自信を持たせるように指導することがより効果的である。 さらに、上手に出来たことに対して指導者が自分のことのように子供の笑顔と一緒に喜んであげることも必要である。 練習の中に遊びの要素を取り入れながら、子供達の個性を尊重し、型にはめ込まない伸び伸びとしたバスケットを指向することもポイントの一つである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。 ■ ブログランキングに参加しています。ポチッと押して頂ければ幸いです。
2010年12月20日
コメント(0)
-

良い習慣で出来るよう指導していく! その3
こんにちはenoです。 ディフェンス(特にマンツーマン)においては、ただオフェンスにつけば良いのではなく、チャンスがあったらオフェンスのボールを取る。 あるいは、シュートに行く前にミスをさせる等、常に意識させることも重要である。 ディフェンスの強化がオフェンスの強化に直結する。 さらに、練習に臨むにあたり、ストレッチ等の準備運動、また、クールダウン等は、心身ともに切り替える為に必要なことであることと、自分の体は自分で守るぐらいの意識を子供の頃から植えつけて欲しい。 練習以外での休養や栄養面でも、保護者を巻き込んで指導することが重要である。 また、子供達が今出来なくても、JBLや全日本、そしてNBA等の試合を見ることを通してバスケットボール全体のイメージから、常に上級のプレーへの意識・意欲を高く持たせるイメージトレーニング等も積極的に取り入れる必要性もある。 具体的に自分のプレーをイメージさせ、良い選手、良いプレーは、理屈抜きに真似させることから入る方法もある。 日々の練習において、特に留意しなければならないことは、練習のための練習に陥りやすいことである。 指導者は常に「ゲームライクな練習」をするように、子供達を指導しなければならない。 何故なら、練習にできたプレーがゲームの時にできない。というケースの多くはこのことが原因であるからだ。 スピード、緊張感等を最大限ゲームに近い状態で常に練習を行うべきである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。 ■ ブログランキングに参加しています。ポチッと押して頂ければ幸いです。
2010年12月16日
コメント(0)
-
良い習慣で出来るよう指導していく! その2
こんにちはenoです。 通常の練習はボールを中心としたプレー、(直接攻撃)を主体的に取り上げて組み立てる傾向になりがちであるが、ボールを持たない選手(関節攻撃)に着目して、それをチームプレーとして指導をすることも重要である。 また、習慣化することが、チームの総合力アップへの早道ともなる。 目まぐるしく展開するプレーの中で、常に冷静に判断ができるためにも視野を広く、先の予測ができなければならない。 その為には、常時顔を上げて全体を見ながらプレーする基本姿勢が重要である。 さらに、視野のないところを補うためにも、的確な情報を声で味方に伝達できなければならない。 見ること、声で伝えることはバスケットボールにとって重要な技術の一つでもある。 また、瞬時に変わる攻防の切り替え、コートの往復(トランジション)、頭も体も瞬間的に対応できるように日々の練習で習慣化することが望まれる。 さらに、ディフェンス(特にマンツーマン)においては、ただオフェンスにつけば良いのではなく、チャンスがあったらオフェンスのボールを取る。 あるいは、シュートに行く前にミスをさせる等を、常に意識させることも重要である。 ディフェンスの強化がオフェンスの強化に直結する。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。
2010年12月15日
コメント(0)
-
良い習慣で出来るよう指導していく! その1
こんにちはenoです。 これからのチーム運営にあたっては、 指導者がもっと経営感覚をもってスタッフをより充実させ、分業化も含め組織化させていくところに大きな発展が望まれる。 様々な立場から違った観点で、より多くの目で、子供達を支援していけるような体制つくりが急務でもある。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『良い習慣でのバスケットができるよう指導していく』:その1 バスケットボールは「ハビットゲーム」と言われている。 日々の練習でいかに無駄な動きや、習慣を排除して、良い習慣を子供達に身につけさせることが出来るかが重要である。 そして、ボールを持ったらとにかくゴールに向かっていく。思い切ってシュートに行く。そんな意識を初歩のうちから、子供達に持たせることが大切である。 子供達は経験がなく、知識もないが故に、ともすれば自分のやりやすいい方法でプレーをしてしまう。 バスケットボールに慣れる初期の段階では致し方ない面はあるが、出来るだけ早い時期に、自然体で、特に基礎技術、基本プレーにおいては正しく指導していく。 さらには、チームの中での自分の役割を認識させていくころが子供達の将来に大きな影響を与えるものである。 そして、通常の練習はボールを中心としたプレー(直接攻撃)を主体的に取り上げて組み立てる傾向になりがちであるが、バスケットボールは当然ながら、5人の攻撃者にボールは1つである。 その為、ボールを持たない選手(関節攻撃)に着目して、それをチームプレーとして指導をすることも重要である。 また、習慣化することが、チームの総合力アップへの早道ともなる。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。
2010年12月14日
コメント(0)
-
バスケを指導するうえでの原点(原則) その3
こんにちはenoです。 練習のやり方として、一般的には回数を消化する方法が多いと思います。 しかし、体力運動は別にして、ボールハンドリング等の基礎技術の習得においては、ある一定の時間の中で何回出来たかといった時間の概念を練習に取り入れるのも効果的である。 さらに、試合中に指導者が、子供達のプレーした結果だけを見て、(特に、ミスしたプレー時に著しい)ベンチから立ち上がり、大声で叱っている光景を見ることがある。 指導者が選手に対して叱ることは否定しないが、末だ未熟な子供達に対して、結果だけでなく、そのプレーをやろうとした動機を見つめて指導することが必要な時もある。 指導者は、あくまでも子供達のヘルパーであり、良き理解者である。 そして、常に親という位置にあることを忘れてはならない。 親としての知識・見識・胆識を持って子供達に触れて、いかに選手が気持ちよくプレーし、かつ集中できるかを、あらゆる環境を整えるべく努力をすべきである。 そういう意味も含めて、これからのチーム運営にあたっては、指導者がもっと経営感覚をもって運営にあたるのが重要なテーマである。 その為には、スタッフをより充実させ、分業化も含め組織化させていくところに大きな発展が望まれる。 様々な立場から違った観点で、より多くの目で、子供達を支援していけるような体制つくりが急務でもある。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。
2010年12月10日
コメント(0)
-
バスケを指導するうえでの原点(原則) その2
こんにちはenoです。 1対1における攻防の駆け引き、面白さを教えることが大切である。 その為にも、基礎技術、基本プレーを正確に出来るように、 [ 創造性→予測→攻撃性 ]ということを初期の段階で身に着けさせることが重要である。 子供達の技術の向上は必ずしも練習時間に比例しない。 練習方法や目的が不明確であると、練習すればするほど技術も精神状態も低下することは、しばしばであることです。 チームとしての目標や個々の選手のテーマを明確にして、年間を通しての計画を、チーム全員および、保護者にも理解してもらい、共通の認識(コミュニケーション)を持って練習することが効果的である。 特に、ミニバスにおいては、バスケットボールを経験した保護者にチーム運営を積極的に応援してもらうのも一つの方法である。 また、練習のやり方として、一般的には回数を消化する方法が多いと思います。 しかし、体力運動は別にして、特にボールハンドリング等の基礎技術の習得においては、ある一定の時間の中で何回出来たかといった時間の概念を練習に取り入れるのも効果的である。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。
2010年12月08日
コメント(0)
-
バスケを指導するうえでの原点(原則) その1
こんにちはenoです。 さて、今回からは、「ミニバスケットボール指導にあたっての基本的な考え方」についてお話ししたいと思います。 と言っても、ミニバスだけにとどまらず、全てのジャンル、コーチングの原点だと思っています。 壁にあたった時、原点に戻ると意外と答えが出ることがあります。 そんな意味も含めて、話していきたいと思います。 『バスケットボールを指導するうえでの原点(原則)』 : その1 子供達に自らが自分のディフェンスをいかに出し抜きシュートを決めるか、あるいはチームとして得点を重ねていく、その成功感と、満足感を数多く経験(知識ではなく体感)させること。 それを子供同士はもとより、指導者が共に実感していくことである。 フォーメーション等、型、ルールのみを追求したり、あるいは、子供達に押しつけるのではなく、まずボールを持ったらゴールを狙い、何とか自分のディフェンスを出し抜いてシュートを決めてくる。 つまり、1対1における攻防の駆け引き、面白さを教えることが大切であり、その中で子供達自身がお互いに考え、研究しながらプレーするように指導することが大切である。 その為にも、基礎技術、基本プレーを正確に出来るよう指導して、何故こうするのか?何のためにプレーするのか?[ 創造性→予測→攻撃性 ] ということも含めて、初期の段階で身に着けさせることが重要である。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。
2010年12月05日
コメント(0)
-
いかにして杉野は強くなったか! その18
こんにちはenoです。 「他のチームが研究していないだろう。練習していないだろう。」という考え方からとにかく静止している状態の多い、ストップ・オフェンス・フォーメーションを考えました。 この他にも、広く攻めるためのフォーメーション、そして、広くしておいてからのカット・イン・プレー等、色々と攻め方の感じが違うものを練習しました。 そして、ゲームの運び方は、速攻を止めて、ゆっくり攻めさせるディフェンスを根本に、プレス=速攻という考え方もやめて、オフェンスは相手を焦らすほどゆっくり攻めることを主眼にリーグ戦に挑んだわけです。 結果は、第1戦に日本体育大学とあたり、このストップ・オフェンスと、見境なしのディフェンスがうまくかみ合い、日本体育大学の焦りを引き出すことに成功して、1勝することが出来ました。 その後は、6勝4敗という成績で2位になることが出来ました。 これからは、4年制、体育系大学等がいよいよ強く成長してくることを考えるとき、2年制、服飾制の大学というハンデを負っている杉野がどうそれに対処していかなくてはならないか、もっと私自身考え、対策を練らなければいけないと思いました。 この話は一旦これで終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。 数十年前の話になりますが、掻い摘んでお話をさせていただきました。現在では当たり前のことが、当時は画期的だったと思います。この話が少しでも参考になり、そうやって挑戦しながら、新たなプレー、練習が生まれることを願ってやみません。 この件に関して、ご意見、ご質問、お待ちしております。コメント、もしくはenosann★gmail.comまでお願いします。(★を@に置き換えてください) 次回からは、「ミニバスケットボール指導にあたっての基本的な考え方」を少し話したいと思っています。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html
2010年12月03日
コメント(0)
-
杉野はいかにして強くなったか! その17
こんにちはenoです。 頑張って、ボールを楽に持たせないディフェンスをすれば、相手もボールをキャッチしたときは、かなり窮屈な体勢なわけで、わざわざスチールを狙うことはない。 ボールが来たら途中でカットしてやろうとは考えずに、ボールの下をくぐって共に移動して、相手と一緒にボールキャッチするつもりで行こうとすれば、悪くても、自然に相手の足元へは必ず行っているこれを「キャッチ・ディフェンス」と名付けました。 一方、オフェンスですが、ディフェンスの練習に時間を取られて中々思うようにいきませんでした。 それでも、色々な動きからのシュート練習をしていたので、その動きからのフォーメーションプレーを考えました。 そして「静」からのプレーを根本として決めてあったので、「ストップ・オフェンス」と名付けました。 これは、最初に述べたように、「他のチームが研究していないだろう。練習していないだろう。」という考え方からで、とにかく静止している状態の多い、オフェンス・フォーメーションなのです。 この他にも、広く攻めるためのフォーメーション、そして、広くしておいてからのカット・イン・プレー等、色々と攻め方の感じが違うものを練習しました。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。
2010年12月01日
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1