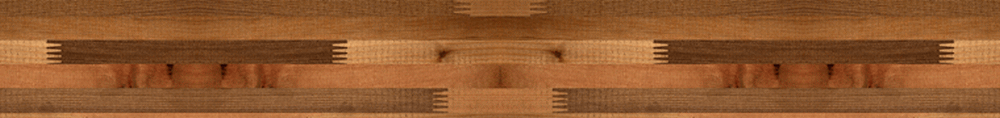2014年12月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
選手生命に関わる膝のケガ その1
「靭帯」って何だか知っていますか …(1) 人間のからだというのは、とても複雑でデリケートなものです。 微妙なバランスで成り立っているということは、 ケガや病気をして、そのバランスを崩してみるとよく分かります。 このバランスを意識的に、積極的に作っていこうというのが、 コンディショニングです。 テクニックの習得に努力することは当然大切ですが、 そのせっかくの努力を無駄にしないためにも、コンディショニングが 大切なのです。 単に注意を払う程度ではなくて、もっと積極的な意義を持つこと。 テクニックばかりに努力するのではなくて、コンディショニングにも 努力することが必要です。それがいいプレーヤーになる条件です。 さて今回お話ししたいのは、私たちのからだの中にある、「靭帯」についてです。 靭帯というのは、足首や膝などのような関節の部分にある結合組織で、 関節を補強したり、運動を制限したりする役割があります。 硬質ゴムのように強靭なものだと言われています。
2014年12月29日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その10
スポーツ医学的に言うところのオーバートレーニングは、 トレーニングによる疲労がたまって、病的になった状態と言えるでしょう。 どこからどこまで病的なオーバートレーニングの状態と言うかの境界線を引くのは 簡単ではないでしょうが、オーバートレーニングによってパフォーマンスが低下する レベルは、私たちのまわりにも少なからず見られます。 このオーバートレーニングはトレーニング計画、コーチの指導の問題が大きい わけですが、選手の側も自分のからだとの「対話」を通してオーバートレーニング に陥らないコンディション作りを図って欲しいと思います。 ハード・トレーニングがプラスに出るかどうかは、選手が自分のからだと上手く 付き合っていけるかどうかにも、大きく関わっているからです。 この他、試合に向けて体調をピークに持っていく「ピーキング」においても、 自分自身のからだと「対話」が上手く出来る事が大切です. 試合直前にはトレーニングをやりすぎないこと(量を減らし、質を高める)が、 ピーキングの方法の一つと言われています。 このように、からだの「声」をよく聞き、よりよい「対話」を作っていくことが ベスト・コンディションを作ることに大切です。 それが試合でのベスト・パフォーマンスにもつながるのだと言えます。
2014年12月24日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その9
日本の小・中・高校生は、欧米のジュニアに比べて、年間の練習日数・ 練習時間が恐らく2~3倍以上は多いのではないでしょうか。 こうした練習の過密さが、オーバーユースになりやすい下地としてあります。 だからこそ、なおさら選手が自分のからだの「声」に耳を傾けて、 速やかに対応することが重要になるわけです。 私たち指導者の側も、選手がからだと「対話」して、 大切にする練習環境を心掛ける必要があります。 オーバートレーニングでパフォーマンスが落ちる …(1) オーバーユースと似た言葉に、「オーバートレーニング」というのがあります。 このオーバートレーニングという言葉は、単にトレーニングのやりすぎという 意味です。 別の言葉で言えば、オーバーワークという意味で使われる場合と、 もっと専門的な意味で使われる場合とがあります。 専門的と言うのは、スポーツ医学もしくはトレーニングなどの分野のことで、 ここでオーバートレーニングの状態で言うと、トレーニングが過剰になって、 体調を崩したり、パフォーマンスが低下したりする状態を言います。
2014年12月22日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その8
スポーツ障害の進行の程度を図る「痛みの目安」として、 (1)練習中は痛まないが、終わると30分ぐらい痛い。(2)練習中にも痛みが出るが、何とか全力を出して行える。(3)練習は行なえるが、練習中の痛みがさらに強く、全力の動作が出来ない。(4)練習を行えないほど痛い。日常の生活でも痛みが続く。 (2)や(3)の段階以上になると、数日程度の休みでは良くならないし、 試合にも影響がでてきます。 競技でよい成績を出させるためにも、いかに(1)の段階を見つけ、 対処するかということです。 そのためには、選手自身にも「痛みの4段階」を理解してもらい、(1)の段階の痛みが出たら、すぐにコーチに伝えるような「状況」を 作ることで、(1)の段階で痛みに対処する習慣をチームの中に作ることが 大切です 福岡氏も言っているように、痛みというからだの「声」に対処すべきは (1)の段階です。ところが、(1)や(29の段階ではその「声」を無視して続ける からこそ、(3)や(4)の段階になるわけです。 オーバーユース(使い過ぎ)という言葉を思い出してください。 日本の小・中・高校生は、欧米のジュニアに比べて、年間の練習日数・ 練習時間が格段に多いと言えます。ごく普通のチーム同士を比べれば、 恐らく2~3倍以上は多いのではないでしょうか。
2014年12月17日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その7
スポーツ障害で生じる痛みの4段階 …(2) 一口に痛みといっても、いろいろな痛み方、程度、感受性もさまざまです。 痛みの意味をどのように考えたらいいのか、分かりにくい。 分からないので、ついついまだ大丈夫ではないかと無理してしまいます。 そこで、スポーツ障害の進行の程度を図る「痛みの目安」を紹介しておきます。 スポーツドクターの福岡重雄氏(スポーツ整形外科・膝および足関節の 関節鏡専門医)は、診察の時の痛みについて、色々と本人に質問しますが、 次の4段階のどの痛みに該当するかを訊くそうです。 (1)練習中は痛まないが、終わると30分ぐらい痛い。 (2)練習中にも痛みが出るが、何とか全力を出して行える。 (3)練習は行なえるが、練習中の痛みがさらに強く、全力の動作が出来ない。 (4)練習を行えないほど痛い。日常の生活でも痛みが続く。 「(3)までは、日常生活ではあまり痛くない段階ですが、(4)になると日常生活にも ハッキリと支障をきたすほどの痛みがでてきます」 「(3)で『 全力を出して動作が出来ない』というのは、例えば練習中のランニングやジャンプなどを全力で行えないということを意味します」 (1)の段階は、練習を1~2週間休めば、良くなるのが一般的です」
2014年12月10日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その6
「からだとの対話」スポーツ外傷と障害について …(3) 「オーバーユース(使い過ぎ)」という言葉を覚えてください。 スポーツ障害は、オーバーユースによって生じます。 足首、スネ、膝、腰など、からだのさまざまな部位に起きるスポーツ障害は、 オーバーユースが直接的な原因です。 それでは、スポーツ障害をなるべく早い段階で食い止めるためには、 からだの「声」をどのように聞けばいいか、その具体的な例を、 以下に見てみます。 スポーツ障害で生じる痛みの4段階 …(1) 私たちは、痛みによってからだの変調を知らされます。 痛み以前にも、変調の兆しはあるのでしょうが、なかなかそれに気づきにくい。 ですから、痛みというからだの「声」が聞こえてきたら、その「声」にきちんと 応えるべく、対応したいものです。 しかし、一口に痛みといっても、いろいろな痛み方があるし、痛みの程度も違う。 人によっては痛みに対する感受性もさまざまです。 痛みの意味をどのように考えたらいいのか、分かりにくい。 分からないので、ついついまだ大丈夫ではないかと無理してしまいます。
2014年12月05日
コメント(0)
-
この時期、体調は万全ですか? その5
「からだとの対話」スポーツ外傷と障害について …(2) 少しくらいの痛みは我慢して練習しようとする。 また、捻挫が十分に治っていないのに、早め早めに練習に参加しようとする。 からだが発している「声」を聞こうとしない。 痛みはグズグズと続く。練習は楽しくない。 完治しきらないうちに、また同じところを傷めてしまうこともある。 試合が近いと、なおさら無理をしがちです。 「からだの声」は、ますます聞こえなくなる。 「コンディショニングのピラミッド」を築いていくどころか、 「ピラミッド」はガタガタです。 高い「ピラミッド」などは、とても築けません。 スポーツ障害については、からだの発する「声」に耳を傾けて、 きちんと「対話」していくことが、予防の決め手となります。 少なくとも、障害を早い段階で食い止めることができます。 逆に言えば、からだの「声」を聞かず、 やりすぎてしまうことで、スポーツ障害は生じるわけです。
2014年12月01日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…
- ホークスを日本一に導いた小久保監督…
- (2025-11-13 22:51:08)
-
-
-

- スノーボード
- 2回目の日記(スノーボード編)
- (2025-06-11 19:00:05)
-
-
-

- サッカーあれこれ
- FC今治×北海道コンサドーレ札幌J2
- (2025-11-23 18:28:03)
-