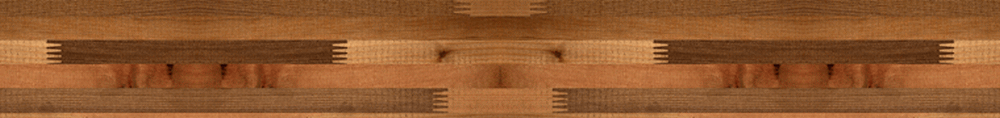2011年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

メトロノームとラジオ体操 その7
こんにちはenoです。 何種類ものテープ(つまりプログラム)の質(目的や効果など)新しさ(選手を飽きさせないため)といったことが最も重要である。 言い換えれば、プログラムそのものの運動効果、斬新さが求められると同時に、それに対する選曲、編集にもしっかりとした指針、細やかな配慮が必要なのである。 その曲の持つリズム、音楽性、イメージ、フィーリングなどが最大限に活きるようなものにしなければならない。 このミュージック・テープの利用は選手に大変好評だった。 我々のような専門競技のトレーニング・プログラムの利用とは違うが、最近のエアロビック・ダンスもミュージック・テープを利用して、成功している一例であろう。 しかし、こうした方法でのミュージック・テープの利用が、スポーツのための音楽の最終形態とはとても言えないし、是非、次の段階に進んでほしいと思う。 私が考える次の段階とは、スポーツのために既存の音楽を使うのではなく、スポーツのための音楽を"作る"ことだ。 現在の段階は、いわゆる「音楽にスポーツを合わせている」という言い方もできるであろう。私達のような素人が自分の主観で曲を選ぶのは、非常に遠回りだという気がする。 年代が違うので、私のフィーリングによる選曲は、選手に合わなかったかもしれない。 ましてや、リズム・ボックスを使った場合のような大失敗も忘れることは出来ない。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月28日
コメント(0)
-

メトロノームとラジオ体操 その6
こんにちはenoです。 失敗を重ねて、次に試みたのが、既存の音楽をテープに録音・編集することである。 テープの編集方針は先に試みた方法と同様で、あらかじめ考えられているトレーニング・プログラムの内容に適した音楽を、時間ごとに区切ってつなぎ合わせていくのである。 音楽は、欧米のジャズやポピュラーを中心に出来るだけ幅広く選曲するようにしたが、この方法で最も苦労し、時間を要したのが選曲と編集である。 何種類ものテープ(つまりプログラム)を作っていく中には、1本のテープを作るのに、毎日、夜中までの作業で数か月かかることもあった。 こうして出来上がったテープとプログラムは、私としては大成功だったと思う。 テープンの数も10本以上に増えていった。 テープの編集のポイントは、その曲がプログラム中の運動にどれだけマッチしているかというところにある。 曲と曲のつなぎの部分もスムーズに行われないと音楽として不快である。 そして、プログラムやそのものの質(目的や効果など)新しさ(選手を飽きさせないため)といったことが当然ながら最も重要である。 言い換えれば、プログラムそのものの運動効果、斬新さが求められると同時に、それに対する選曲、編集にもしっかりとした指針、細やかな配慮が必要なのである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月26日
コメント(0)
-

メトロノームとラジオ体操 その5
こんにちはenoです。 リズム・ボックスのトレーニングが全くの失敗に終わり、新たに思いついたのが、リズムを中心にした音にメロディを入れることであった。 色々なリズムを使いたいという気持ちが強かったので、知り合いのジャズ・バンドに頼んで、自分なりに納得のいく音作りを試みた。 その方法は、まずリズム・セッションの人にテンポの違うリズムを10秒間とか20秒間おきに、変えていってもらい、そのテンポに合わせてメロディーをつけるというものだ。(私が作った計画表をあらかじめ渡しておく) ※ リズム・セッションとは、バンド・オーケストラの中で、 主にリズムを受け持つ部分。ポピュラー音楽では、ドラム、 ベース、ピアノ、ギターが一般的。 管楽器や弦楽器が入らないロックバンドではドラムとベースを指す。 秒数を区切ることの意味は、トレーニング・プログラムのなかで動きの速さを変えたり、または全く違うタイプの運動を行ったりする区切りや、リズムを作ることにある。 こうした試みで録音を行い、早速トレーニングの時に使ってみたのだが、いざ音を聞いてみるとあまりにも録音状態が悪く、この方法は"音作り"の段階で失敗してしまった。 以上のような2つの失敗を重ねて、次に試みたのが、既存の音楽をテープに録音・編集することである。 テープの編集方針は先に試みた方法と同様で、あらかじめ考えられているトレーニング・プログラムの内容に適した音楽を、時間ごとに区切ってつなぎ合わせていく。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月24日
コメント(0)
-

メトロノームとラジオ体操 その4
こんにちはenoです。 リズム・ボックスでは音の速さを自在に操れるので、選手の動きも機械の操作一つで、面白いように変えることが出来る。トレーニングを行わせる側(機会を操作する側)としては、非常に満足のいくものであった。 ところが、これが選手達には大いなる不評だった。 「私達は機械じゃない!」「牛が何かに追われて走っているみたい!」などの不満が選手達から続出した。 私自身も、「これはまずい。」と思うことがあった。 所用があり、練習に遅れてしまい、トレーニング・ウェアにも着替えずに、そのまま体育館に顔を出した時のことだ。 選手達は、丁度この時間はリズム・ボックスを使ってランニングをしているところだった。 自分が機会を操作する側としてではなく、いわばチームの外側(第3者)からこのトレーニング風景を見て、何か息が詰まるような、異様な感じを受けた。 結局、メトロノームやリズム・ボックスを使ったトレーニングは10回も行わないうちに止めることにした。 「これは絶対いける!」と半ば確信していたリズム・ボックスのトレーニングが全くの失敗に終わり、しばらくはガッカリと落ち込んでしまった。 そうして、気を取り直したところで、新たに思いついたのが、リズムを中心にした音に、メロディを入れることである。 色々なリズムを使いたいという気持ちが強かったので、知り合いのジャズ・バンドに頼んで、自分なりに納得のいく音作りを試みた。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月21日
コメント(1)
-

メトロノームとラジオ体操 その3
こんにちはenoです。 色々なトレーニングを考えて、選手に行わせているうちに、トレーニングを行う時の苦しさ、単調さなどから、何か重苦しく、味気ない気がしてきた。 何か音を流したら‥‥‥思いつきだが、きっとうまくいくに違いないと思った。 それでは、どんな音にしようかと考えた。動きには常にリズムが大切なのだから、リズムのあるもの、リズム、リズム、リズム‥‥‥ そうだ! メトロノームだ ! と興奮しながら、その夜早速メトロノームの音をテープに録音することにした。 速い音や、遅い音など、色々な音を組み合わせてテープを編集。 そして、例えば、ランニングを行うときにメトロノームの音に合わせて、スピードを上げ下げさせたり、ゆっくり走らせたりというような形で利用してみた。 さらに、メトロノーム音のテープよりは、リズム・ボックス(主にテンポのガイドのためや、それ自身で音楽のリズムパートを自動演奏するために作られた電子楽器の総称)の方が便利なので、借りてきて使ってみた。 リズム・ボックスでは音の速さを自在に操れるので、選手の動きも機械の操作一つで、面白いように変えることが出来る。 メトロノームやリズム・ボックスの利用は、トレーニングを行わせる側(機会を操作する側)としては、非常に満足のいくものであった。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月19日
コメント(0)
-

メトロノームとラジオ体操 その2
こんにちはenoです。「スポーツはリズム」と言う考え方は、私にとっては強いものがある。そこで、まずリズムに関するトレーニングのエピソードから話を始めたい。もう数十年も前のこと。その頃は、まだチームを見始めてまだ間もない時期だったが、私にとって何もかも新しい試みだった。トレーニングについても、まさに試行錯誤の繰り返しだった。当時はバスケットボールのための特別なトレーニングという認識は一般的にほとんどないときだったし、実際的なトレーニングの参考書などもほとんどなかった。そして、何より、人の真似をするよりも自分独自のものをつくりたいと考えていました。バスケットボール以外の色々な競技のトレーニングなども参考にしながら、自分なりの方法を模索した。当時から膝の怪我が多かったので、筋力強化でなんとか予防できないかと、フリー・ウェイト(ダンベルやバーベルを使用するウェイトトレーニングの一種)のトレーニングも積極的に試みた。こうして色々なトレーニングを考えて、選手に行わせているうちに、トレーニングを行う時の苦しさ、単調さなどから、何か重苦しく、味気ない気がしてきた。何か音を流したら・・・・・思いつきだが、きっとうまくいくに違いないと思った。>■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月17日
コメント(0)
-

メトロノームとラジオ体操 その1
こんにちはenoです。 私の持論に「トレーニングも結局人間がやるものなんだから・・・」と言うものがあります。 考えてみると、"トレーニング"と言う言葉と、"人間臭い"と言う言葉は、とても不似合いな言葉のようです。トレーニングをもっと幅広く、新たな発想で捉えていく必要があるような気がします。 そうした一面を考える材料、ヒントとして、これからの話を活かしていってもらえたらと思います。 『 メトロノームとラジオ体操 』 スポーツはリズムだ! 冒頭から感嘆符 "! "のついた文章で唐突だが、「スポーツはリズム」と言う考え方は、それだけ私にとっては強い。 また、私はバスケットボールを専門としているので、これはそのまま「バスケットボールはリズムだ!」ということでもある。 非常に感覚的な表現だが、おそらく同じような感想を持っている人は多いのではないかと思う。 そこで、まずリズムに関するトレーニングのエピソードから話を始めたい。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月13日
コメント(0)
-

終わりに・・・
こんにちはenoです。 『 終わりに・・・』 子供達とって指導者とは、バスケットの短なり指導者ではなく、バスケット指導以外の指導者の様々も見ている。 従って、バスケット指導のみの指導者としてではなく、子供達に対してすべての模範となるよう心掛けるべきである。 ミニバスケットボールの指導者には、過去にバスケットの経験のない方も多くいらっしゃるが、経験の有無が指導者のハンデとはなり得ない。 なぜなら、バスケット経験のある指導者が自身の経験だけにこだわり、新しい考え方や指導方法を勉強せずに従来からの指導に固執すれば、指導者のとしての進歩はない。 逆に、バスケットの経験がなくても、バスケットの指導書、ビデオでの研究や、優秀な指導者たちの話や意見などを拝聴して、より良い指導者になるべく創意工夫を行うべきである。 かつ、熱意を持って自チームの指導にあたることこそ最も大切である。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月11日
コメント(0)
-

細かいところまで注意する
こんにちはenoです。 『 細かいところまで注意する 』 子供達だけでの練習は避けて、指導者が最初から最後までコートの上で細かいところまで注意を払う必要がある。 特に充分なウォーミングアップは怪我の予防にも繋がるし、クーリングダウンにも充分時間を取るようにしたい。 特に練習や、練習試合において個々のフェースチェック(顔色をみる)を、ウォーミングアップ時や、練習中にプレーヤー全員に行い、プレーヤーの状況をチェックすることも必要である。 異常を感じた場合には、本人への確認や、本人の練習中止の指示及び、医者へ行かせるなど的確な判断が望まれる。 練習中は皆がお互いに声を掛け合って、励ましあいながら練習できる雰囲気や、バスケットボールに集中できる環境作りも重要である。 『 ゲーム化の工夫 』 技術指導を行う時、基礎練習をゲーム化して、グループ別の競争的要素なども取り入れる等の興味を持たせながら指導していく工夫が必要である。 そのゲーム化は、試合中に多く繰り返されて行われるケースを考慮して、工夫性、連続性、発展性のあるものが望ましい。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月08日
コメント(0)
-

初歩の段階で規則に縛られない
こんにちはenoです。 『 初歩の段階では競技規則にあまり縛られないようにする 』 決められた基本的な規則は必ず守るように指導しなければならない。 しかし、始めからあまり規制しすぎるのではなく、初期の子供達には伸び伸びと遊び心でプレーできるように指導することが必要である。 規制をあまり厳しく適用しすぎて子供達を枠にはめ込んだり、子供達がプレーすることを尻込みしてしまうようなことがあってはならない。 あくまでも子供達に規制を尊重することを教えていかなければならない。 罰則を恐れて規制を尊重するのではなく、規則を守って正しい技術を身に着けたいという気持ちを尊重するように指導していかなければならない。 そして、特にミニ最終学年においては技術、ルールも合わせて一通りマスターしていけるよう段階的に指導していく必要がある。 その為には、子供達同士で審判が出来るように工夫すべきである。 全てのミニバスケットボールの指導者はこのことを心にとめて、厳格になりすぎないように子供達を指導し監督すべきである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月04日
コメント(0)
-

指導者自身が思い込んではいないか
こんにちはenoです。 『 指導者自身が思い込んではいないか 』 指導者自身の経験・知識あるいは、大人としての基準においてドリルの難易度を決めていないだろうか。 難しいかなと思うドリルでも子供達は初めてプレーをすることにとまどうが、すぐに消化してしまい、褒めてあげると得意になってプレーするものである。 新しいことが夢中になってトライするところに、良いバスケットが生まれ発展していくものである。 子供が失敗したり、上手く出来なくても、励まして自信を持たせるよう指導することが大切である。 出来ることなら、指導者が1~2回でもよいから、見本(正しい例、悪い例)を見せてあげられる程度の技術を身につけて欲しい。 また、特にバスケットを経験された指導者にありがちなこととして、自分が体験した、例えば練習方法や考え方のみを子供に押し付けることだけはやめなければならない。 この時期に習得した技術は大人になっても忘れず、全てのプレーの基本となり、正確にマスターしておくことが将来において一層幅の広いプレーヤーに成長していくベースとなる。 将来、全日本の一員として活躍する選手の能力や技術に大きな影響を与えると言っても過言ではない。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月03日
コメント(0)
-

ミニとして特別な扱いをしない その2
こんにちはenoです。 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 1年の計は元旦にあり。何事も最初に計画や準備をすることが大切です。夢、目標に向かって頑張りましょう。 By: 榎本日出夫 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 子供達は筋力・体力に限りがあっても運動神経の発達は著しく、バスケットボールの基礎的な動き、ボディコントロール、ボールコントロールや、俊敏性の体得等の吸収力はすばらしいものである。 初期の子供にとってそのような観点を中心に段階的に指導することが将来に繋がることと確信する。 とにかく、ボールとゴールがあればドリブルやシュートがしたいとか、仲間と一緒にバスケットをしたい等の気持ちが自然と湧き立つ選手に育てることが大切である。 まず、バスケットボールをプレーすることが楽しい・面白い、と思わせることが指導上の重要なポイントである。 ただ、この時期に気を付けたいことは、子供の筋力・骨格がまだ発育途上であり、未熟なため、安全で適切な筋力トレーニングの具体的方法は医学的に言ってまだ確立されていない。 持久力、パワーアップといった本格的な体力づくりは成長後に取り入れるべきである。 また、健康面、栄養面も含め充分な注意を払ってほしいと思う。 これは、指導者、保護者、プレーヤー自身の自己管理を含めて重要魔ポイントである。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2011年01月01日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1