2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年09月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
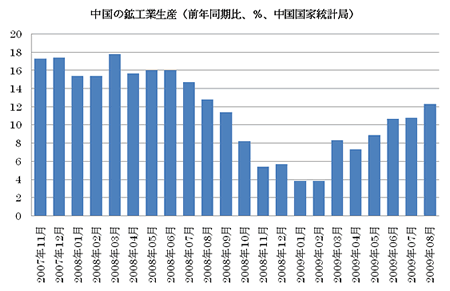
第184回 中国の8月の経済指標
今日のまとめ 1.8月の経済指標は市場参加者の懸念を払拭するものだった 2.唯一の問題点は貿易が引き続き低調だったことである■概ね良好だった8月の経済指標中国の8月の経済指標は先月の統計よりも内需の加速を示すものが多く、市場参加者を安心させるものでした。1月から8月の都市部における固定資産投資は+33%で、市場予想を若干上回りました。また1月から7月までの固定資産投資が+32.9%だったことから8月のペースはピックアップしていると言えます。8月の鉱工業生産は+12.3%と7月の+10.8%より大きく改善しました。8月の小売売上高は+15.4%でした。これは7月の+15.2%より高い数字でした。次に物価に目を転ずると消費者物価指数は前年同期比▼1.2%、生産者物価指数は前年同期比▼7.9%と相変わらずインフレを感じさせない数字となっています。さて、人民銀行によると8月の人民元建て銀行融資は4,104億人民元で、7月の3,559億人民元より多い数字でした。これはポジティブ・サプライズでした。唯一の懸念点は貿易です。輸出は前年同期比で▼23.4%ですが7月に比べると+3.4%でした。(なお7月は6月に比べて+5.2%でした。)輸入は前年同期比で▼17%であり、7月に比べると+1%でした。(なお7月は6月に比べて+3.5%でした。)これらのことから貿易に関しては基調としては改善途上にあるけれど、回復のモメンタムは先月より鈍化していると言えると思います。結論的には中国経済は先月同様、しっかりした足取りを辿っていると言えます。しかし貿易の回復が遅々として進まないことから、引き続き緩和的な金融政策に依存するかたちになっていると言えるでしょう。
2009年09月14日
-
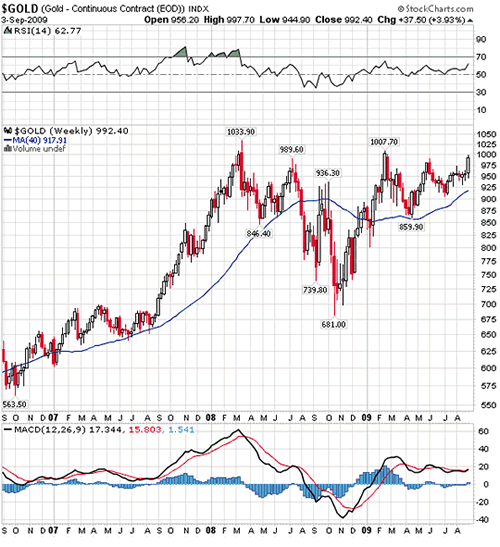
第183回 1,000ドルをうかがうゴールド
今日のまとめ 1.ゴールドの価格は主にチャート妙味から動いている 2.ETFを取引するのと金鉱株を取引する方法がある 3.値動きの荒さに大きな違いがあるなぜゴールドに物色の矛先が回ったか?ゴールドの価格がふたたび1,000ドルの大台を狙う展開となっています。なにが金価格上昇の原因なのか?その背景に関してはいろいろな議論があるのですが、どれも説得力に欠けるものが多いです。先ず指摘されるのはこのところのドル安です。確かにこのところはドル安に振れていますし、一般的には「ドル安=ゴールドにとってはプラス」と考えられているのでこれがある程度影響しているのは間違いないと思います。しかし、今のゴールド相場をドル安ですべて説明してしまうには少し説得力が足らない気がします。もうひとつ最近話題になっているのが、中国の国営テレビ、CCTVで個人投資家の投資対象として貴金属への投資が紹介されたことです。昔は中国では個人が金の延べ棒などを所有する事に対して制限がありました。テレビのニュース番組で貴金属投資が取り上げられたこと自体、自由化が進んでいることのなによりの証拠だというわけです。三つ目の理由として単純にゴールドのチャートが重要なポイントにさしかかっているからという意見もあります。実際、ゴールドのチャートはペナント(三角旗)を形成しており、上に抜けても、下に抜けても大きく価格が動きやすい、「煮詰まった」形になっていると言えるでしょう。(出典:ストックチャーツ・ドットコム)ゴールドの動きをトレードするにはさて、ゴールドの動きに実際に投資するにはどういう方法があるのでしょうか?先ず国内ETFとして「SPDRゴールド・シェア」(コード番号1326)と「金価格連動型上場投資信託」(コード番号1328)が挙げられます。これらのETFはいずれも金価格に連動するように設計されたものです。またゴールドのETFではなく、金鉱株に注目するという方法もあります。なぜ金鉱株に注目するかというと、それはボラティリティーがゴールドそのものよりも倍以上大きいからです。ボラティリティーというのは価格のブレの大きさを指します。するとボラティリティーが大きければ大きいほど、上昇局面でも上げ幅は大きくなることが予想され、逆に下落局面では大きく下げることが予想されるのです。実は最近のゴールドのボラティリティーはかなり低くなっており、半年前に比べると半分程度のブレしかありません。投資家によってはもっと値動きのある投資対象を選好する人もいるわけです。その場合、下のグラフにあるように金鉱株のボラティリティーはゴールドそのもののボラティリティー(グラフ右端の「ゴールドETF」を基準に、他の金鉱株と比較してください)より2倍以上あります。但しこれは金価格下落局面では金鉱株の方が2倍危ないことを意味しますのでご注意下さい。なお金鉱株の株価評価について簡単に振り返っておきます。ここでは産金会社各社の時価総額を確認埋蔵量で割り算し、1オンスの埋蔵量に対して株式市場での投資家が幾らの株価を支払っているかを計算してみました。この数字が大きければ大きいほど、その産金会社の評価が高いと言えますし、同時にそれは株価が割高であると理解することも出来ます。なお、この株価評価が決まる要因としてはおのおのの会社の採掘コストが大きく影響しています。たとえば下のグラフ中、一番右端にある(=つまり最も評価の低い)DRDゴールド(DROOY)は非効率な鉱山を所有しているため、採掘コストが高く、利益が出にくいコスト構造になっています。逆に評価の高いゴールド・コープ(GG)やキンロス・ゴールド(KGC)は採掘コストがきわめて低いです。金鉱株の時価評価(時価総額÷確認埋蔵量、オンス当たりドル、9月4日現在、コンステクスチュアル・インベストメンツ)これはあくまでも一般論ですが、ゴールドの価格が横ばいで、将来の金価格の見通しにあまり変化が無い場合(=最近までそういうトレンドが続いてきました)、毎期の決算でしっかりと利益が出せる、採掘コストの低い産金会社の評価が高まる傾向があると言えます。逆にゴールドの価格がどんどん上昇するような局面になると各社の採掘コストの微妙な差は余り投資判断の上では重視されなくなります。そしてむしろ「含み」、つまり莫大な確認埋蔵量があるかどうかに投資家の関心が移ってゆくと予想されます。その場合は下のグラフにあるようにバリック・ゴールド(ABX)、ニューモント・マイニング(NEM)、ゴールドフィールズ(GFI)のように確認埋蔵量が多い企業に物色が移ってゆくシナリオも考えられるわけです。
2009年09月07日
全2件 (2件中 1-2件目)
1










