2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
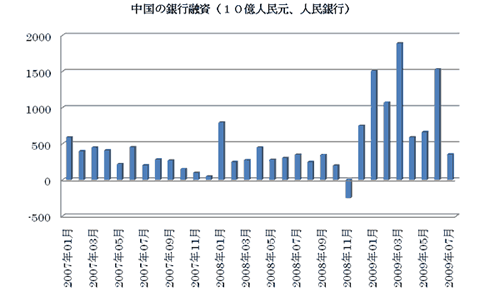
第182回 中国株の「独歩安」と当面の投資戦略
今日のまとめ 1.上海総合指数が調整局面に入った直接の原因は融資成長の抑制にある 2.中国株の「独歩安」は続かない 3.グローバルにビジネスを展開している企業に新鮮味がある上海総合指数の調整上海総合指数は高値から一時20%下げ、いわゆるベア・マーケットの定義にあてはまる展開となりました。その直接の原因は銀行融資の鈍化に対する懸念です。人民銀行によると7月の人民元建て銀行融資は3,559億人民元と6月の1.53兆人民元から大幅に抑え込まれました。銀行融資が株式市場へ直行本来、産業への貸付による景気てこ入れを目指した銀行融資が、そのまま株式市場へ直行してしまったのにはわけがあります。まず世界不況の状況に関しては中国の経営者も良く理解していますから、新しい運転資金を融資してもらっても、本業にそのお金を投入して、満足なリターンを得られる保証はありません。ましてや多くの産業分野ではそもそも設備自体がだぶつき気味です。するといちばん堅いやり方は金余りで活況を呈する可能性の高い株式市場にこの余資を投入し、融資の返済期限に利子をつけて返さなければいけない金額以上のリターン(大体5%程度だと言われています)を狙うという方法です。また、四兆人民元の景気刺激策によって建設資材やコモディティーの値段がいずれ高騰するだろうという読みから、先回りして素材を投機、転売の目的で仕入れるという方法も当然、実業家なら考え付く方法です。つまり中国でそうした投資行動が盛んに取られたということは、ある意味では企業の経営者が経済原則に従って合理的に行動した結果だと評価することも出来るのです。現在のコンセンサスは下半期の銀行融資成長は鈍化するだろうというものです。ただ、折角復活してきた景気が腰折れするリスクが出るのであれば、ふたたび融資を増やし、景気刺激のための追加予算が積み増しされる可能性も無いとは言い切れません。したがって銀行融資成長は必ず鈍化するときめてかかるのは早計だと思います。中国株の「独歩安」は続かないここ数週間だけの動きを見ると急伸した後、いち早く調整局面に入った中国株に対して、他国のマーケットは比較的切り離された動きをしています。インド株やブラジル株は今年の高値の水準にありますし、調整していたロシア株ですら、今年の高値からそう遠くない位置につけています。この状況はアメリカや欧州など先進国の株式市場でも同じです。つまり今は中国株の「独歩安」の状況になっているのです。ブラジル株の市場参加者の意見を聞くと、「確かに中国経済は一番大事だ。でも幸い世界の他の地域の景気が戻ってきている。だから中国からの素材の需要が一段落した分はその他の世界からの需要でおぎなえる」という考えのようです。問題は工業コモディティーの消費者として、中国は突出した存在となっており、若し中国の工業コモディティーに対する需要が減退したならば、それを他の世界からの需要で埋め合わせするのは容易ではない点です。実際、鉄鉱石や石炭などの工業コモディティーと密接に関係しているバルチック海運指数(BDI)は6月以降、右肩下がりのトレーディング・チャンネルにがっちりと囲い込まれており、じりじりと値を切り下げています。(出典:ストックチャーツ・ドットコム)若しバルチック海運指数が正しいのであれば、世界の素材・資源株はある程度の調整を余儀なくされると考えるのが自然です。その場合、たとえば素材・資源株への依存度の高いヴァーレ(VALE)などのブラジル株は調整局面に入るリスクもあります。あるいはその全く逆で、いまは「独歩安」となっている中国株が切り返し、世界の市場に追い付き、再びリーダーとしてのポジションを奪回するというシナリオも十分考えられると思います。いずれにせよ世界が中国にサヤ寄せするか、あるいは中国が世界にサヤ寄せするかのどちらかが起こり、現在のちぐはぐな状況に訂正が入ると考えるのが自然だと思います。グローバルなビジネス展開をしている企業に注目中国の景気刺激策は株式市場での投機を助長するなど「ムダな部分」もありましたが、それが世界景気の下支えに役立ったことは大方の投資家が賛成するところだと思います。実際、先週好決算や業績予想の上方修正を発表したティファニー(TIF)、マーベル(MRVL)、インテル(INTC)、デル(DELL)などの発表内容を見るにつけ、世界的な景気底入れの恩恵は既に極めて広範な分野でじんわりと感じられ始めていることが確認できます。当面はこれらの企業のように間接的に世界経済復活の恩恵を蒙るグローバル企業の方に新鮮味があるような気がします。
2009年08月31日
-
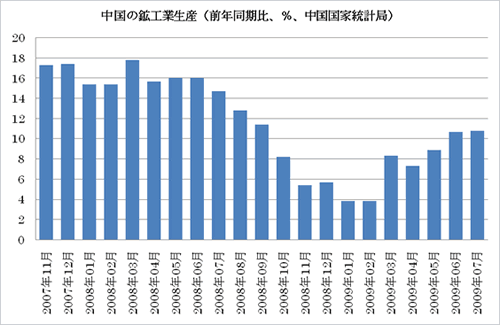
第181回 中国の7月の経済指標
今日のまとめ 1.今月から中国国家統計局はまとめて経済指標を発表することになった 2.7月の経済指標は中国経済がちょうど良い状態にあることを示唆している中国国家統計局が記者会見を定例化これまで中国国家統計局は大体各月の中頃にバラバラに数字を発表していました。しかし今月からなるべく一回にまとめて指標を発表する方法にすると発表しました。そして記者会見を持ち、質疑応答の時間を設けることにしました。これは中国の経済統計の透明性、信頼性を少しでも改善しようとする当局の前向きな姿勢のあらわれとして評価できると思います。7月の経済指標7月の都市部における固定資産投資は+30%と6月の+35%から減速しています。1月から7月の通算では+32.9%で、去年の1~7月に比べて5.6パーセンテージ・ポイント高い数字となっています。7月の鉱工業生産は+10.8%と6月の+10.7%より若干改善しました。7月の小売売上高は+15.2%でした。これは先月より0.2%高い数字でした。物価に目を転ずると消費者物価指数は前年同期比▼1.8%、生産者物価指数は前年同期比▼8.2%といずれもインフレの兆候をまったく感じさせない数字になっています。国家統計局以外の発表する経済指標さて、人民銀行によると7月の人民元建て銀行融資は3559億人民元と6月の1.53兆人民元から大幅に抑え込まれました。一方、7月の輸出は6月に比べて+5.2%、同じく輸入は+3.5%と、両方とも改善基調にあります。理想の状態にある中国の経済運営これらのことをまとめると中国の経済の状態はちょうど良い具合で回復しつつあり、今のところは大きな政策の手直しは必要ないと思います。ただ、不動産や株式などの資産価値の上昇は将来バブルを生ずる可能性があります。バブルを未然に防ぐ方策の一つとして現在レッドチップとして香港で上場されている中国企業を本土へ誘致し、株式の供給を増やすことでA株市場を冷やす準備が進められています。これはレッドチップの再評価を促すきっかけになる可能性があります。
2009年08月12日
-
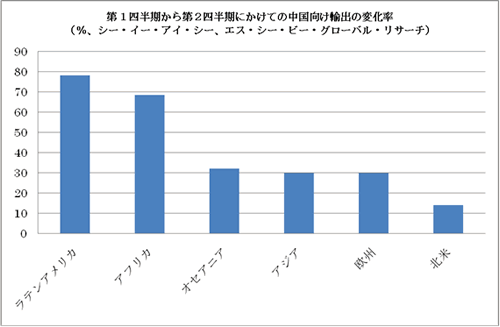
第180回 ブラジル企業の近況
今日のまとめ1.中国の貿易パートナーとしてブラジル経済は力強く回復しつつある2.ブラジル企業の第2四半期の業績は全般的に良好中国向け輸出のリバウンド世界各国の中国に対する輸出が回復しています。下のグラフは第1四半期から第2四半期にかけての変化率を示したものです。上位に来ているのはいずれも原材料を主要輸出品目とする地域です。その中でもラテン・アメリカの変化率の高さが目をひきます。ラテン・アメリカの中では鉄鉱石や大豆を輸出するブラジルの存在が大きいです。世界不況を危なげなく乗り切ったブラジルそのブラジルですが、去年、商品価格が急落した際、ブラジル・レアルも急落しました。このため為替予約で大きな損を出す事業会社が続出しました。昔のブラジルならそのような場面では海外への資本逃避が起きていたことでしょう。しかし今回は予めブラジル中央銀行が予防的な金融政策を取っていたため、資本市場の混乱はありませんでした。中国からの旺盛な原材料の引き合いでブラジル企業は活気を取り戻しています。アラクルーズ(ティッカー:ARA)同社はブラジルで生育の早いユーカリの木から紙の原料となるパルプを作っている林業会社です。去年、ブラジル・レアルが下落した際に為替予約で大きな損を出しました。このためライバル企業で、かつ大株主でもあるヴォトランチン(VCP)から事業統合の提案を受けました。当初は合併が生き残りの唯一の方法のように思われたのですが、このところの市況回復で独立を維持出来る可能性も出てきました。今年の1月から5月までの世界全体でのパルプ需要は下のグラフのように▼6.6%でした。日本、アメリカ、欧州が軒並み前年同期比で▼20%以上の落ち込みを記録する中で中国だけが+66%と突出した成長を見せています。中国のパルプ輸入が激増している理由は、ひとつには去年のオリンピックの前に輸入が控えられたことの反動という事があります。それに加えて中国の製紙会社はどんどん最新鋭の機械を導入しており、最高品質の紙を生産し始めています。その原料にはBEKPと呼ばれるユーカリの木から採れるクラフト・パルプが必要になるのです。さて、アラクルーズの負債の返済のスケジュールですが、現在、同社の手許には6.15億レアルのキャッシュがあるため今年年末までに返済しないといけない4.7億レアルの都合はつきます。でも同社が来年以降も無理無く借金を返済してゆけるためには市況がこれ以上悪化しないということが条件になります。ゴール(GOL)ブラジルを代表するディスカウント航空会社のゴールは2001年に創業された若い会社です。創業以来、極めて安定した財務パフォーマンスで順調に成長してきたのですが、2007年に業績の低迷していたヴァリグ航空を買収した後、一挙に増えた輸送能力を消化するのに苦しみました。下のグラフはゴールのロードファクター(どのくらい客席が埋まっているかの指標)を示したものですが、2006年までは悠々と採算ライン(赤で示してあります)を超えていたのがヴァリグを買収した2007年第2四半期から採算割れしていることがわかります。その後の合理化の努力で採算ラインの引き下げに成功し、最近はようやく黒字体質に戻っています。なお、8月7日に発表された7月のロードファクターは71.5%と久し振りに70%台に乗せています。エンブラエル(ERJ)旅客機のメーカーは世界に数えるほどしかありませんが、参入障壁の高いこの業界で頑張っているブラジル企業がエンブラエルです。同社は座席数にして100席程度のリージョナル・ジェットに強いです。同社の顧客は世界中に分散しています。航空機のビジネスは世界の航空会社が顧客であるため、景気の影響を受けやすいです。エンブラエルのビジネスも世界不況の影響を受け、今年の第1四半期は僅か4機の納品にとどまりました。しかし今期は56機の納入があり、ビジネスは力強く戻ってきています。その上、厳しい経営環境が当分続くだろうという想定の下で費用を大幅に圧縮したので営業マージンは去年の通年の7%から今第2四半期は12%へと拡大しました。ただ、今期は同社の商品群の中では比較的高価な製品が多く売れたのでマージンもそれに助けられた面があります。エンブラエルは外貨建て負債の整理を進めており金利負担は下がっています。エンブラエルのビジネスは航空機の輸出であるため契約がドル建てのケースが多いです。そのためブラジル・レアルの為替が動くと同社の純利益は大きく増減します。エンブラエルは為替ヘッジの際に一切レバレッジをかけない主義ですがそれでも為替変動の影響を大きく受けます。コーザン(CZZ)ブラジルで砂糖ならびにエタノールの生産・販売をしている企業です。世界最大の砂糖の生産ならびに消費国であるインドが今年は旱魃に見舞われています。このため今年のインドにおける砂糖の生産は去年の3分の2程度に落ち込むと予想されています。インドは砂糖の輸出国から輸入国へと転落する見込みです。この恩恵を蒙るのがコーザンです。またコーザンは去年、エクソン・モービルのブラジルのガソリン・スタンド網を買収しました。ブラジルでは「E85」と呼ばれるエタノール対ガソリンの混合比率85:25の燃料が標準化しつつあります。同社はサトウキビの収穫からエタノールの生産、小売販売までの一貫体制を確立した世界最初の企業でもあります。同社の商品はいずれも市況に左右されるものであり、世界の天候の影響を大きく受けます。従って業績の予想は極めて立てにくくさらに資本集約的なビジネスなので借入金の利払い能力や資本市場の環境変化にも敏感です。バンコ・ブラデスコ(BBD)ブラジル第2位の商業銀行です。同行の第2四半期の決算はビザ・カードのブラジルの子会社、ビザネットのIPO(ブラジルで過去最大の新規上場案件でした)によるキャピタル・ゲインなどに助けられています。またフィー収入や純金利収入も好調です。これに水を差すのが融資ポートフォリオの悪化であり、貸倒引当金が積み増されています。融資ポートフォリオがひとたび悪化しはじめると焦付きの損金で折角、他で稼いだ利益が吹っ飛んでしまいます。今期までのところでは遅延融資比率がピークアウトしたかどうかは判然としません。(下のグラフの青線を参照してください)
2009年08月10日
-
第179回 大きく転換する中国のグローバル石油戦略
今日のまとめ 1.世界金融危機が中国政府にチャンスをもたらした 2.これまで欧米の縄張りだった中東に中国が正面攻撃をかけた 3.世界最大級の開発プロジェクトへの割り込みに次々に成功金融危機が中国にチャンスをもたらした中国の海外での石油開発はこれまでアフリカ大陸やカザフスタンなど、どちらかと言えば欧米のオイル・メジャーと呼ばれる大手石油会社と正面からかち合わない地域でおこなわれてきました。ところが世界金融危機以降、中国のグローバルな石油戦略が大きく転換しています。ひとことで言えば、伝統的に欧米企業の本拠地であった中東に正面攻撃をかけているのです。そして中国は僅か数か月のうちに大きな成果を上げています。これらの成功に共通する点はいずれの場合も資金調達力をフルに生かしているという点です。イラク ルマイラ油田ルマイラ油田はイラク南部の低地に位置する同国第2位の油田です。現在は日産96万バレルです。これはイラク全体の生産量のほぼ半分に匹敵する大型油田です。可採埋蔵量は150億バレルと言われています。イラク戦争以来、外国の石油会社にイラクの油田の開発権が競り落とされるのは今回が最初です。落札者はちゃんと先行投資や技術供与を行ってルマイラ油田の生産量を大幅に増やすことが条件となっています。具体的には向こう6年間で日産285万バレルに持ってゆく計画です。これを落札したのは BP-CNPC(中国石油天然ガス集団)連合でした。BPにはいろいろな面で有利さがありました。なぜなら同油田はもともと1953年にBPが発見した油田だからです。また現在、BPのロシア子会社、 TNK-BPが操業しているシベリアのサマトロール油田とルマイラ油田の構造が似ている点も指摘されています。サマトロール油田で蓄えたノウハウが生かせるのです。具体的にはウォーター・インジェクション(水攻法)などの手法が使われると予想されます。契約比率はBP:イラク政府:CNPC=56.25%:25%:18.75%です。なお、同契約は地下資源の所有契約ではなく、油田運営/生産役務に対して一定のフィーを得る、所謂、サービス契約です。具体的には現在の生産量を超えて生産出来た分に関して、バレル当たり2ドルの役務フィーを受けます。入札当初はBP-CNPC連合はバレル当たり$3.99の対価を要求しましたが、これが2ドルまで値切られたわけです。このため実際の契約価値は30億ドルしかないとも噂されています。イラン・アザデガン油田アザデガン油田はイラクのルマイラ油田から国境を超えてイラン側のアフワズ近郊にあります。ここはもともと日本の国際石油開発帝石が75%の権益を所有していました。しかしアメリカからの圧力などがあり、なかなか開発に着手できなかった案件です。イラン政府は重い腰を上げない日本側に業を煮やして「開発しないのなら、別の企業に権益を付与する」としてCNPCを引き入れたのです。現在の契約比率はCNPC:イラン石油:国際石油開発帝石=63%:27%:10%です。同油田開発には少なくとも25億ドルの先行投資が必要だとされていますが、中国側がそれを賄うのだと言われています。イラン・サウスパース天然ガス田イランのペルシャ湾沖合にある世界最大級の天然ガス田、サウスパースの「フェイズ・イレブン(第11鉱区)」の開発権も最近、所有関係が変わりました。これまでフランスの石油会社、トタールが持っていた30%の権益が最近、CNPCに肩代わりされたのです。「フェイズ・イレブン」の開発総額は47億ドルだと言われています。当初このプロジェクトの運営責任者として開発を請け負ったトタールは日産300キロBOE(=barrels of oil equivalent)の生産量を計画していたとされています。こうしたイランでの一連の契約は折からの世界不況で石油の市況が悪化し、イラン政府の財政がひっ迫したタイミングで行われました。西側企業が資金用立て面、市況悪化による採算懸念などでひるんだ隙を狙って中国が躍り出たわけです。これらの一連の権益獲得で、CNPCの海外投資計画としては、これまでポッカリ穴が開いていた中東がいきなり予算の最大の部分を占めることになりました。ロシア・ブラジルとの友好関係の樹立さらに中国は世界金融危機で債務の借り換えに困ったロシアのロスネフチに対しても巨額の融資を約束する見返りとしてロシアの石油の安定的供給を受ける約束を取り付けています。またリオデジャネイロ沖で次々に超深海油田を発見したものの、その開発のための先行投資費用のやりくりに困っていたブラジルのペトロブラスに対しても資金を用立てると約束しています。これらの一連のディールにより中国の海外石油戦略のポートフォリオは短時間のうちにとてもバランスの取れたものに変貌しつつあるのです。
2009年08月06日
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 11/20 20時〜数量限定‼️もち吉『ブラ…
- (2025-11-20 21:59:07)
-
-
-

- 楽天写真館
- 21 日 ( Friday ) の日記 寒い…
- (2025-11-21 04:00:04)
-
-
-

- ひとり言・・?
- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション
- (2025-11-19 22:39:26)
-







