全262件 (262件中 1-50件目)
-

『ムトゥ 踊るマハラジャ (Muthu)』
1995年、インド、K.S.ラビクマール監督、ラジニカーント。オープニングで”スーパースター ラジニ”との文字が大写しになりますが、これは誇張ではなく、主演のラジニカーントは南インド随一の出演料をほこるスーパースターです。ただ、スーパースターとはいいましても、彼は別に二枚目ではありません。どこにでもいるような”オッサン”ですね。口髭を生やした吉幾三や石立鉄男などと称されたりもしています。しかし、初めて彼の映画を観る人は、彼のパフォーマンスに圧倒されることでしょう。ラジニカーントのパフォーマンスは歌とダンス、そして大げさな演技です。つまり、彼の作品はミュージカル映画です。しかもコメディやユーモアといった笑いのペーソスたっぷりの。歌はインド民族音楽を軽快なテンポでアレンジした感じで、ダンスは非常に切れがいい動きですね。そして、表情に愛嬌があります。彼のダンスの特徴は手と腰の動きですが、腰の動きが結構笑わせます。衣装はもちろんインド風で、原色を大胆に多用した華麗なもので、これで大人数でダンスするのですから圧巻です。ショットの合間に顔(目や口)のアップを挿入するのも特徴ですが、目のパッチリしたインド美人はこのテクニックで結構映えますね。この辺の雰囲気は他のミュージカル映画ではちょっと味わえない類のもので、それに笑いが加わるのですから飽きることはありません。ただダンス・シーン以外は凡庸で、往年の香港映画を思い出してしまいました。しかし、テンポのいいセリフ回しや進行には映画としてプリミティヴな魅力があるようで、さして映画が好きでない私の子どもたちも熱心に観ては笑っていました。ストーリーはさして重要ではありません。この映画は166分あり、やはりちょっと長いですか。ミュージカル好きでブロードウェイにちょっと飽きがきたような方で、かつ腹の底から笑いたい方にお勧めの作品です。
Jun 5, 2005
コメント(4)
-

『モンスーン・ウェディング』
2001年、インド、ミーラー・ナーイル監督。インド上流階級の結婚式、その数日の日常生活をドタバタ劇風に描いた作品で、これがなかなか面白く、ヴェネチア映画祭で金獅子賞を受賞したのも納得です。**********ニューデリーに住むビジネスマン、ラリット・バルマ氏の庭では結婚式の準備が始まった。長女アディティが親の決めた縁談を急に承諾し、彼女はテレビ局の仕事も辞めて、彼の住むヒューストンに行くことになっていた。バルマ氏は世界各地に散らばった親戚縁者を集めて伝統にのっとった豪華な式を挙げようとする。しかし、これがはからずも集う人々の複雑な愛のタペストリーを織り成すこととなった---心揺れる花嫁、聡明な従姉、不器用なウエディング・プランナー、貞淑なメイド。そしてバルマ氏は、結婚式までのゴージャスな宴が繰り広げられる中、それぞれの悩み、愛に対して様々な選択をしていく。季節は厳しい夏の日差しを一掃するモンスーン。生命の再生と喜びをもたらすモンスーンの雨が苦悩を洗い流し、躍動感に満ち溢れた未来を指し示していく・・・・・・・**********ミーラー・ナーイル監督は女性ですが、日常のありふれた風景を繊細な感性とユーモアにあふれたタッチで、さらに少々の残酷さを加えるという、女性らしい視点の映画だと思います。普段は一同に会することのない親戚縁者がほぼ全て揃う冠婚葬祭では、はからずもいろいろな人間模様が展開されることになり、それを題材とした作品は古くから映画の定番としてあります。私なども葬式や結婚式でいろんな所にいきますが、面白いのはやはり何と言っても自分の田舎でのそれです。なにしろ赤ん坊の頃から私を知っている連中がたくさんいるのですから、嫌でも話は盛り上がります。とりわけ面白いのは婆さんたちで、遠慮もなにもあったもんじゃない(笑)。この映画では、そういった人間模様のうち、恋愛物語に焦点を合わせています。結婚するアディティ(花嫁)とビクラム(花婿)はもとより、アディティと不倫関係にあるヘマント、式場の準備をするウェディング・プランナーのデュベイとメイドのアリス、奥手のラーフルと美貌でスタイル抜群のアイシャ、そしてちょっと倒錯したところでは幼いアリアと叔父のテージ、精神的にやや不安定なリア。涙あり、笑いあり、悲劇ありのこれら多数の恋愛物語を、結婚式(の準備)という場で同時進行的に描き出すミーラー・ナーイル監督の技量はなかなかのものがあります。この映画の特徴を一言でいえば、【雑多】ということになりましょうか。上で述べた多様な恋愛はもとより、衣装、モザイク状に配置された華やかな複数の原色、インド、イギリス、アメリカ、オーストラリアという雑多な人種(もちろん混血あり)、英語がメインですが時折飛び込んでくるヒンディ語やパンジャブ語。これらの【雑多】は、インドという国の縮図にもなっているわけですね。ドキュッメタリー出身らしくミーラー・ナーイル監督の作品は、リズムやテンポがいいです。ストーリーの進行もそうですが、歌唱やダンス・シーンの雰囲気、とりわけ結婚式前夜にアイシャが官能的に踊るシーンは最高でした。この作品では個人にスポット・ライトをあてるとともに集団(社会)としての視点からインド人や人間関係を描いているのですが、個人として特に目についたのがこのアイシャ、そしてウェディング・プランナーのデュベイでした。アイシャは若くてスタイル抜群、いかにもインド風の美人で性格も素直で開放的、美人揃いの女優陣のなかにあってその華やかさは一際輝いていました。デュベイは演技とりわけ表情が最高で、とにかく笑わせてくれます。アリスとは性格や行動のリズムはむしろ正反対に近いのですが、その二人がお似合いのカップルになるのですから世の中分らないものです。いろんな意味で、インド映画の面白さを再確認させてくれる傑作でした。
Jun 3, 2005
コメント(0)
-
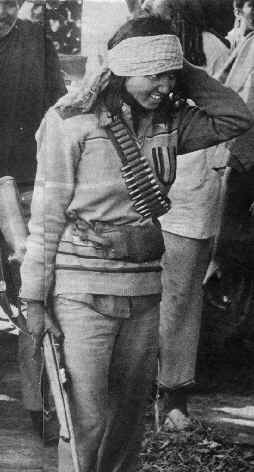
『女盗賊プーラン』
1994年、イギリス=インド、シェーカル・カプール監督。80年代初頭インドで、女盗賊(義賊)として群盗を引き連れて荒し回ったプーラン・デヴィという女性が送った波乱万丈の人生を映画化したものです。*****************プーランは、1958年インド北部(ウッタルプラデシュ州南部ゴルハカルプワ村)で下層カースト(シュードラ:「マッラ」)の貧困農家の娘として生を受けました。この時点で彼女には、カースト制度と「女性」という二つの差別がついて回ることになりました。彼女は、11歳で30過ぎの男と訳が分からないうちに結婚します(ちなみに、インドでは法律上は18歳未満では結婚できないことになっていますが)。夫による虐待に耐えきれず、数年後には飛び出して生家に戻っています。出戻りの女性はその辺りではほとんど人間扱いされず、彼女は村人たち(とりわけ上位カーストたち)から村八分、白昼のレイプ、盗みの濡れ衣、取調べ警官による性的暴行など、ありとあらゆる嫌がらせや虐待を受けます。当時ダコイットという盗賊がインドを荒し回っていたのですが、この集団は富める者から奪って貧しい者に分け与えるというようなことをしていたそうで、義賊を自称していました。彼女は20歳の頃、このダコイットに誘拐され、棟梁のオンナとして慰みものになります。ダコイットにはヴィクラムという優しい青年がおり、彼はプーランと恋をするようになります。やがて、ヴィクラムは、プーランへの虐待をくり返す棟梁を銃殺し、ダコイットを率い義賊として活躍するようになります。そして、プーランはヴィクラムと二度目の結婚をします(21歳)。しかし、ヴィクラムは対立する盗賊―――頭が上位カースト・クシャトリヤ(王侯・武士)に属する「タクール」(地主)の一派―――によって殺害され、プーランはビーマイ村に拉致され集団レイプを受けたうえ、奴隷扱いされます。脱出したプーランは、夫の意思を継いで義賊として暴れ回り、ビーマイ村でかつて集団レイプに関わった「タクール」の男性22人を復讐として射殺し(1981年)―――ただし、プーラン自身は直接関与を否定しています―――、この事件でメディアはプーランを「美人盗賊」や「カリ(悪を退治するヒンズー女神)の生まれ変わり」などと書き立て、彼女は一躍有名になりました。事態を重視した警察当局はプーラン逮捕に本腰を入れはじめ、彼女は多くの仲間を失い徐々に追い詰められていきます。インディラ・ガンジーが首相をつとめていた1983年、プーランは司法取引に応じて投降します(ちなみに、ガンジー首相はこの直後84年に暗殺されています)。*****************映画はここまでですが、後日談があります。1994年2月(映画が公開された年ですが)に出所したプーランは、1996年にインド下院選挙に出馬し当選を果たし、カーストや性による差別の撲滅を目指し政治家として活動を始めました。その頃、三度目の結婚をしています。ほぼ同時期に自叙伝(『プーラン・デヴィの真実』1997年)を出版しています。この本は、(文盲だった)彼女自身の言葉をテープレコーダに録音して、そのまま文章に起こすと2千ページにも及ぶものを二人の作家が刈り込みをし、原稿を本人に読み聞かせ、確認を取ってから本にしたとのことです。えらい気の使いようですが、実は、映画『女盗賊プーラン』は、インド本土では、プーラン本人より「伝記」を大幅に脚色されているとして起訴され、インド政府からは上映禁止をくらっていたのでした。そうかと思うと、こういう話しもあります。映画では、プーランは好感を誘う存在(義賊)として描かれており、村を襲撃しても貧困層の安全は保証し、金持ちから奪った戦利品を貧しい者に分け与えた英雄であって、彼女が降伏セレモニーの臨んだ時には群衆が称賛の声を上げるシーンがあります。しかし、地元の住民によると、例えば、ビーマイの隣村で育った新聞記者スリードハル・チャウハン氏(44)は「我々はどんなにプーランを恐れたことか。彼女を英雄視するメディアには怒りを感じた」と語っており、降伏セレモニーを見た大学教授ビシャセル・シン氏(57)によると、人々は「盗賊をひと目みようと集まっただけ」で、プーランをたたえる者はいなかった、ということです(「読売新聞」 http://www.yomiuri.co.jp/tabi/world/abroad/20041116sc22.htm)。2001年7月、プーランはニューデリーで暗殺されました。享年43歳。地元警察は犯行グループの7人を逮捕しましたが、主犯格の男は「ビーマイ村事件の仕返しだった」と供述しており、復讐が復讐を呼んだともいえそうです。本の印税などもあって、プーランは210万ドル(2億5600万円)の財産を残したそうですが、これを巡ってまた悶着が生じています。生前、不仲で別居中だった3番目の夫が、「妻の夢を果たすため政界に入る」と宣言し、相続の正当性を主張する一方で、プーランの家族(実妹ら)は「財産目当てに結婚したペテン師」と彼を非難し、射殺事件への関与さえ示唆しています。さらには、一番目の夫までもが「離婚手続きを経ておらず、正式な夫は自分だ」と名乗りを上げ、「遺産を相続し、貧困者のための基金を設立する」と裁判に訴える構えをみせているということです。なんか「貧者同士の争い」をみる思いがしますね。以上は2001年現在の話(報道)です。 ◇ ◇ ◇ ◇近年、インドの経済発展は、IT産業に代表されて目覚ましいものがあります。しかし、カーストに基づく差別は根強いものがあり、法律でいくら規制しようとも社会構造としてしっかりビルトインされているようです。プーランがあのおぞましい虐待を”当然のごとく”受けた時代というのは、ほんの2、30年前であって、とりわけインド人口の7割が暮らす農村部では依然としてカースト差別が根強く、少女婚など女性虐待も後を絶たないとのことです。ブッダが戦いを挑んだ相手は、このカースト制度だったのですが、結局は仏教は殆ど駆逐されてしまいました。現在では、下位カースト者が仏教を選択することも多いそうです。刑務所で多くのことを学んだプーランにしても、自分よりももっと下に続くカーストがいることを知り、ヒンドゥから反ヒンドゥを掲げる仏教に改宗したのでした。経済発展を控えたインドでは、国際化という波のなか、この問題は今後ますます重要視されることになるでしょうね。 ◇ ◇ ◇ ◇この映画自体ですが、映像はかなり粗いつくりとなっていますが、それがかえって埃や砂や岩だらけの風土にマッチしているようで、やけに生々しい印象です。母親譲りといわれるプーランの荒々しい気性に、よくマッチしていますね。景色は綺麗で、それがかえってプーランの境遇の悲惨さを際立たせています。プーラン率いる盗賊たちが、山肌を縫って警察から逃亡するシーンは、なかなか良かったです。シェーカル・カプール監督はこの映画で認められて、4年後には『エリザベス』という作品で、大英帝国の女王伝記映画をインド人が監督するという快挙を成し遂げています。ケイト・ブランシェットが主役を演じていることもあり、『エリザベス』も好きな作品のひとつです。
Jun 1, 2005
コメント(6)
-
『KILLER 第一級殺人』
1995年、アメリカ、ティム・メトカーフ監督、ジェームズ・ウッズ、ロバート・ショーン・レナード。主人公のカール・パンダラムは1920年代アメリカの実在の人物で、彼は自叙伝で、少年を含む22人の人間を殺害したことを告白したが、そのあまりの凶悪ぶりに全米メディアは沈黙せざるをえず、発刊されたのは1970年になってからでした。*****************1929年、米カンザス州北東部にある連邦刑務所に、ユダヤ人新任看守のヘンリー・レッサー(ロバート・ショーン・レナード)が着任した。レッサーは早速、新たに送られてきた囚人の一人カール・パンズラム(ジェームズ・ウッズ)が、不服従のかどで冷酷な看守グライサーらによって袋叩きにされている場面に出くわした。血だらけのカールを見かねたレッサーは、彼にそっと1ドル札を差し入れた。カールは、その返礼として、自分がこれまでに犯してきた凶悪な犯行の数々を綴った自叙伝を書くから、それを新聞社に売れと申し出てきた。しかし、囚人に紙や鉛筆を与えることは、明らかな服務規定違反。一度は申し出を断ったレッサーだが、好奇心も手伝って、ある夜、彼に紙と鉛筆を差し入れた。カールは、刑務所の暗い電灯のもとで、彼が犯罪者となったいきさつを何一つ隠すことなく綴った。レッサーは、貧しく複雑な境遇ゆえに犯罪に走ったカールが、すさんだ刑務所生活によってより一層凶悪さを増していったのだと悟った。少年を含む22人を殺したという、その冷酷な殺人記録に戦慄したレッサーだったが、迷った末にタイプで清書して出版社に送付した。しかし、内容のあまりの衝撃ぶりに、それを発売しようという出版社はついに現れなかった。また、カールの告白によると、彼が以前いた刑務所では、新任所長のケイシーが、囚人に自立心を養わせるために野球をさせたり、ブラスバンドを組ませたり、さらには囚人単独で町に外出することまで許可しようとしていた。その”実験”のモデル・ケースとして、カールが選ばれた。読書好きのカールは町の図書館に出かけ、親しくなった司書の女性の家に招かれた。しかし、カールは彼女をレイプしてしまった。ケイシーは失望し、責任を問われて免職となった。ある日、グライサーは、カールの房から鉛筆を発見し、罰として彼を真っ暗な独房に長期間監禁した。グライサーらは、鉛筆が誰からの差し入れであるか白状させようとしたが、カールは過酷な拷問にも耐え、ついに口を割らなかった。独房から出た後、カールはグライサーを撲殺してしまう。このままでは、裁判で有罪(第一級殺人)となり、カールは間違いなく死刑である。何とか彼を救いたいと考えたレッサーは、高名な精神科医メニンガー博士に相談し、精神異常による免責に持ち込もうとした。だが、カールはあくまでも“殺人鬼"としての極刑を希望し、診断を拒否した。審判が下り、彼は絞首刑に処せられ、(既に看守を辞職する意思を固めていた)レッサーもカールの希望により最後の瞬間に立ち会った。ラスト、カールの自叙伝の発刊にこぎつけた老いたレッサーが述べる。”ユダヤの律法にはこうある。「人は皆、一度は苦しむ人に手を差し伸べるべきだ」と。その手は、あなたではなければ誰であろう?今でないなら、いつであろう?”*****************カールの行動には一見不可解なものが多いです。 ・なぜ、彼は自叙伝を書いたのか? ・なぜ、彼は鉛筆を差し入れた者の名(レッサー)を白状しなかったのか? ・なぜ、彼はグライサーを殺したのか? ・なぜ、彼は死刑を望んだのか? ・なぜ、彼はレッサーに死刑の場に立ち会うよう要請したのか?囚人カール、レッサー看守、そしてケイシー所長は、三人とも同じ考えの持ち主です。それは、犯罪の根本原因は、不遇、差別、貧困といった社会的要因がメインであり、いかなる凶悪犯といえども更正可能だという考えです。さらに、刑務所の劣悪な環境が、犯罪の再生産・凶悪化の場になっているということも。ですからこの映画は、矛盾を犯罪者に押し付ける【社会(システム)】を糾弾するとともに、犯罪者を虐待する【刑務所】を告発する内容ともなっています。このことを念頭におけば、上のカールの一見不可解な言動も理解できるようになります。 ・自叙伝を書いたのは、社会や刑務所を糾弾・告発するため。 ・白状しなかったのは、ケイシーのような刑務所改革者としてのレッサーの将来に禍根を残したくなかったから。 ・グライサーを殺したのは、グライサーにレッサーの刑務所改革の邪魔をして欲しくなかったから。 ・死刑を望んだのは、レッサーに「正義」というものの厳しさを教え込むため。 ・レッサーを立ち会わせたのは、こんなバカな人生を送らせるのは俺で最後にしろと、レッサーの刑務所改革の意思をより強固にさせるため。カールがレッサーを庇護したのは、ケイシー所長の期待を裏切ったことに対する罪滅ぼしという側面と、刑務所の改革の芽を潰したくなかったいう側面があったのでしょう。レッサーが看守を辞任することを知って、カールは激怒します。そして、「グライサーを殺したのは、お前のためだったのだ」とレッサーに告げます。カールとしては、レッサーに出世してもらって刑務所を改革してもらうという、命をかけた計画が水泡に帰するような思いがしたのでしょう。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇1990年代に入り、いわゆる「刑務所映画」とでも称すべき作品が隆盛してきましたが、同ジャンルのそれ以前の名作といえば、『パピヨン』(1973年、スティーブ・マックウィーン)、『ミッドナイド・エクスプレス』(1978年、ブラッド・ディビス)、『アルカトラズからの脱出』(1979年、クリント・イーストウッド)でしょう。とりわけ私は『アルカトラズ』が好きで、終始緊張感に溢れた雰囲気や、イーストウッドのクールな演技は、映画ファンとしてたまらないものがあります。ただ、『パピヨン』にしても『アルカトラズ』にしても、刑務所そのものを社会的観点から表現したものではなく、前者は『大脱走』以来の、後者は「マカロニ・ウェスタン」で培った役者の演技を主体とした”脱走モノ”ですね。対して、90年代以降は、囚人をステレオタイプの快楽殺人者として描くのでもなければ、囚人の脱走によって爽快感を味わうものでもない、刑務所そのものがはらむ問題性を訴えた作品や、社会的観点から刑務所を捉えた作品が出現してきます。『宣告』(1990年、イタリア、ジャン・マリア・ヴォロンテ)、『告発』(1994年、ケヴィン・ベーコン)、『デッドマン・ウォーキング』(1995年、ショーン・ペン)、『スリーパーズ』(1997年、ブラッド・ピット)、『ハリケーン』(1999年、デンゼル・ワシントン)、『エス』(2001年、ドイツ、モーリッツ・ブライブトロイ)などです。変り種としては『ショーシャンクの空に』(1994年、ティム・ロビンス)や『グリーンマイル』(1999年、トム・ハンクス)などもありました。90年代からこのような社会派映画が増えてきた原因としては、やはりM.フーコの『監獄の歴史―監視と処罰』(1975年)の影響が大きかったのでしょう。フーコーは、監獄とともに「狂気」や「性愛」の歴史を独特の手法で読み解き、現在の世の中で「当然、そうあるべきことだ」と思われている規範やルールや価値観といったものが生成してきた現場を分析し、社会に潜む権力とイデオロギーを暴き出し、それらを突き崩したのでした。「刑務所映画」における90年代以降のパラダイムシフトは、フーコー抜きには語れないと思います。
May 31, 2005
コメント(4)
-

『ヒットラー』(二)
さて現在ですが、戦後処理が賞賛されているドイツや世界は、本当に「ナチス」なるものを払拭しえたのでしょうか?現在のドイツには、以下のような法律があります。【ドイツ刑法130条3項】ナチスの支配のもとで行われた、刑法第220a条(民族殺戮)第1項に示された行為を、公共の平和を乱す(ような)形で、公然とまたは集会において容認し、または事実を否定したり、あるいは矮小化した者は、5年以下の自由刑(禁固刑)または罰金刑に処せられる。ところで、現在「歴史修正主義」という潮流があります。それとの関連で最大の問題になっているのが「ホロコースト」です。”第二次世界大戦中、ドイツが多数の監獄や労働収容所を作り、ユダヤ人、戦争捕虜、レジスタンス、ジプシー、精神障害者、ゲイなどを送り込み彼らを虐待し、その最大のものがアウシュヴィッツ(ポーランド)でした。”このことに異論をはさむものはいません。そして、一般の書籍(「正史」)では、その後このように続くはずです。”これらの収容所では、600万のユダヤ人と500万の非ユダヤ人が殺人ガス室等によって虐殺され、それは今では「ホロコースト」と呼ばれています。”簡単に言うと、(ナチスによる迫害の歴史を否定しないものの)犠牲者の数やガス室の存在に疑義を呈する者が「歴史修正主義者(ホロコースト修正主義)」と称されています。====================論争ホロコースト修正主義ホロコーストの信憑性については早くから疑問が投げかけられており、「ホロコースト正史」に対する批判的研究も行なわれているが、この種の研究を刑事罰の対象として禁ずる国もある。 ホロコースト修正主義(Holocaust revisionism)は否定的な意味で「ホロコースト否定(Holocaust denial)」と呼ばれることがあるが、中立的観点から本項ではこの用語を採らない。・1948年、レジスタンス活動家としてブッヘンヴァルト及びドーラ強制収容所に収容された経験をもつポール・ラッシニエは、著書Passage de la Ligneの中で「ホロコースト生存者」の証言に疑義を呈した。今日、ラッシニエは「ホロコースト修正主義の父」と称されている。 ・1973年、アウシュヴィッツで空軍部隊将校として勤務した経歴のある西ドイツのシュテークリッヒ判事は、ホロコースト絶滅物語を検証するDer Auschwitz-Mythosを刊行したが、発禁となる。 ・1978年、Institute for Historical Review(歴史見直し研究所)設立。 ・1978年、『ル・モンド』紙でロベール・フォーリソンが「ガス室」に関する記事を発表し、「フォーリソン事件」が起こる。 ・1988年、アウシュヴィッツのガス室についての実地検証、『ロイヒター報告』。 ・1993年、アウシュヴィッツのガス室について化学的検証を行なった『ルドルフ報告』。 ・2000年、The Revisionist創刊 ドイツ・オーストリア・フランスでは「ナチスの犯罪」を「否定もしくは矮小化」した者に対して刑事罰が適用される法律が制定されているが、人種差別禁止法を名目に「ホロコースト否定」を取り締まる国もある。国際人権規約批准国では、B規約20条2項「国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」を根拠とする以外に、基本的人権たる表現の自由を制限することが難しい。このため、ホロコースト修正主義者は人種差別の罪で告発されることが多い。2004年にはイスラエルで、外国に対して「ホロコースト否定論者」の身柄引渡しを要求できる「ホロコースト否定禁止法」が制定された。『エルサレム・ポスト』(2004年7月20日)の伝えるところでは、ユダヤ人のホロコースト犠牲者は100万人に満たないという内容の博士論文を書いたことがある「ホロコースト否定論者」・パレスチナ解放機構の事務局長アッバス(前首相)を標的として極右政党国民連合が提出した法案であった。1994年からドイツでは「ホロコースト否定」が刑法130条第3項で禁じられており、ドイツ語版ウィキペディア (http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite)のホロコーストの項にはこの警告が文頭に掲げられている。論争上記のホロコースト修正主義の立場から、「収容所においてガス室などによる組織的殺戮はなかった」などのホロコーストへの懐疑論が唱えられている。1988年に「虚偽の報道」罪で裁判にかけられていたエルンスト・ツンデルが弁護側証拠として米国のガス室専門家フレッド・ロイヒターに依頼して作成した「ロイヒター・レポート」は、一般にガス室とされている建造物では技術的な問題からガスによる殺人は不可能であると結論づけている。ただし、このレポートに対しては「ロイヒターは工学の学位を持たず、また実績においても、彼は専門家としての能力に欠ける」との批判がある。ガス室実在論者が「ロイヒターは裁判において専門家としての証言を認められなかった」と主張することがあるが、ツンデル裁判ではガス室設計・運営の専門家と認定されて実際に証言に立っている。1993年には、マックス・プランク研究所で博士課程にあった化学者ゲルマール・ルドルフのルドルフ・レポートがロイヒター・レポートと同様の結論を提示した。ルドルフ・レポートに対する反論としてはインターネット上で発表されたRichard J. GreenのLeuchter, Rudolf, and the Iron Bluesがある。その他、ユダヤ人絶滅を明記した命令文書が存在しない、ニュルンベルグ裁判で拷問や脅迫を用いて得られた証言に矛盾がある、などが否定的根拠として良く挙げられる。我が国では、1995年医師西岡昌紀の「ナチ『ガス室』はなかった」という記事を掲載した『マルコ・ポーロ』誌が廃刊になったマルコ・ポーロ事件がある。このほか1980年代半ばに「ホロコーストという犯罪の比較可能性」をめぐってドイツ歴史家論争と呼ばれる一連の論争が起こったことがある。1998年フランクフルト書籍見本市の平和賞受賞講演で、作家マルティン・ヴァルザーはホロコーストがドイツ人に対して「道徳的棍棒」として使われていると述べて「ヴァルザー論争」が起こった。「ホロコースト」の疑問点1) 「毒ガス」で死んだ死体の解剖記録が存在しない。そして焼却処分したはずの数百万人分もの人間の灰が発見されていない。 2) ヒトラーやその他のナチスの有力者によるユダヤ人の物理的絶滅文書命令が発見されていない。 3) 絶滅計画には予算が計上されてない。加えて連合軍はドイツ政府・ドイツ軍の交信記録をすべてチェックしたが、秘密の無線通信やオフレコの会話でさえ絶滅計画に関したものは何も残っていない。 4) 遺体の死因は発疹チフス等の伝染病によるもので、毒ガスによって殺害されたと断定された遺体は一体たりとも確認されていない。これはアメリカ軍とともにドイツのダッハウなど約20の収容所に入り、遺体を実際に検分した唯一の法医学者チャールズ・ラーソン博士が宣誓証言している。 5) 戦時中、連合軍機が上空から収容所敷地内を撮影した航空写真には、一枚も遺体を焼却していたとされる焼却炉からの煙が写っていない。 6) いわゆる「ガス室」には、青酸ガスの使用に不可欠である、換気システムが設置されたという証拠がまったく存在しない。 7) アウシュウィッツ強制収容所ではチフスが流行していたため、殺虫・殺菌のためのマイクロ波殺菌装置が配備されていた。本気でユダヤ人を絶滅させるなら、収容所に入れた後、殺虫・殺菌なんてせずに放っておけば簡単に全滅させられる。それどころかドイツ政府の中でユダヤ人問題を総括する立場にあったハインリヒ・ヒムラーは、チフス等の病気によるユダヤ人の死亡が多いことに神経をとがらせ、収容所の管理者たちに対し、もっと死亡率を低下させよという命令を出している。 8) 1943年2月からドイツ降伏まで、全ての収容所で赤十字の監督が許可されていた。これによって囚人の待遇が全て赤十字によってチェックされるようになった。そして赤十字の報告書には1943年から1944年の間ですら、重労働者は最低でも一日に2750カロリーを摂取していたと記されている。そして国際赤十字委員会は、連合軍が無差別爆撃で援助物資を届けることを妨害していることに不満を訴えていたが、赤十字の訴えは連合国に無視される。1948年の赤十字の報告書には、中立の立場である赤十字が「ユダヤ人の大量死は連合軍の無差別爆撃が原因である」という結論を出している。 9) アウシュウィッツでは囚人同士の結婚式が認められていた。産科病院に3000人の出産記録があり、託児所には母親が子どもを預けることができた。 10) SSがユダヤ人を虐待することは犯罪だった。ブーヒェンヴァルト収容所司令官のカール・コッホは、ユダヤ人を虐待したために1943年にSS判事コンラート・モルゲン博士に死刑を宣告されている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88====================ここではホロコースト修正主義者たちの主張が正しいとか誤っているとか言うつもりはありませんが、もし、彼らに対する非難や「弾圧」が、単に「正史」という「事実」や「歴史」に反しているからだ、という理由でなされているのだとしたら、それは以下(再掲)を忘れた態度であり、ヒットラー(ナチス)に賛同した戦前ドイツ国民の姿勢となんら変るところがないと言えます。1) 自分の理想(=ほんとう)は、どんな外的権威、超越的権威にもよらず、自分自身の洞察と考慮によって(つまり「自己確信」として)内面化されている、ということを自らが深く納得するとともに他者たちにはっきりと示す。2) この「自己確信」が、独我のうちで自閉し絶対化されることなく、つねに他者による普遍化という検証を受け、たゆむことなく鍛え上げられてゆく。
May 29, 2005
コメント(2)
-

『ヒットラー』(一)
2002年、アメリカ、クリスチャン・デュゲイ監督、ロバート・カーライル、ピーター・オトゥール。「歴史」の”再”評価というのは難しいものです。「歴史」を「事実」の積み重ねを基にして解釈や評価そして価値を形成していく作業とするならば、そもそも客観(真実)としての「事実」なるものの存在が疑わしいのです。ポストモダンの最大の功績は、このニーチェの洞察(「客観なぞ存在しない!」)に現代的な光をあてたことです。客観としての「事実」が存在しない以上、客観としての「歴史」も存在しえないことになります。では、客観としての「事実」や「歴史」が存在しないのであれば、「事実」や「歴史」について語ることに意味がないのでしょうか?もちろん、そのようなことはありません。”事実”や”歴史”として、人間は「事実」を求め「歴史」について語る(言葉として社会に発する)ことを続けてきました。この営みは人間の<生>にとって本質的ですし、そうせざるを得ない理由があるのです。現在、無数の人間がネットに参加し個人ブログが存在しますが、それも同じ理由によると思います。「事実」や「歴史」に限らず、語るという営みは、人間にとって二つの契機をもたらします(以下、竹田青嗣氏の『近代哲学再考』を参考として)。1) 自分の理想(=ほんとう)は、どんな外的権威、超越的権威にもよらず、自分自身の洞察と考慮によって(つまり「自己確信」として)内面化されている、ということを自らが深く納得するとともに他者たちにはっきりと示す。2) この「自己確信」が、独我のうちで自閉し絶対化されることなく、つねに他者による普遍化という検証を受け、たゆむことなく鍛え上げられれてゆく。確かに、客観(真理)としての「事実」や「歴史」は存在しえません。しかし、上の二つの契機が常に担保される場合に限って、人は語られる内容について「客観的に正しい」=「共通了解が成立する」と判断しえるのであり、また理想(=ほんとう)を希求する人間の<自由>に現実的な命を吹き込むことができるのです。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇上で述べた「1)」や「2)」が担保されることなく、人間をして「正しい」と思わせる手法がプロパガンダというものです。そして、ヒットラーというのは、このプロパガンダの天才だったわけです。彼は『我が闘争』で以下のように述べています。=====================○ 集会で演説し自分の才能に気づくわたしは30分話をした。そして、わたしが以前から、よくわからないが、ただ内心で感じていただけのことが、今や現実によって証明された。わたしは演説ができたのだ。30分後、小さな部屋に集まった人々は深く感動させられたのである。○ 大衆へのプロパガンダについていかなる宣伝も大衆の好まれるものでなければならず、その知的水準は宣伝の対象相手となる大衆のうちの最低レベルの人々が理解できるように調整されねばならない。それだけでなく、獲得すべき大衆の数が多くなるにつれ、宣伝の純粋の知的程度はますます低く抑えねばならない。大衆の受容能力はきわめて狭量であり、理解力は小さい代わりに忘却力は大きい。この事実からすれば、全ての効果的な宣伝は、要点をできるだけしぼり、それをスローガンのように継続しなければならない。この原則を犠牲にして、様々なことを取り入れようとするなら、宣伝の効果はたちまち消え失せる。というのは、大衆に提供された素材を消化することも記憶することもできないからである。大衆の圧倒的多数は、冷静な熟慮でなく、むしろ感情的な感覚で考えや行動を決めるという、女性的な素質と態度の持ち主である。だが、この感情は複雑なものではなく、非常に単純で閉鎖的なものなのだ。そこには、物事の差異を識別するのではなく、肯定か否定か、愛か憎しみか、正義か悪か、真実か嘘かだけが存在するのであり、半分は正しく、半分は違うなどということは決してあり得ないのである。○ 宣伝の効果についてこの世界における最も偉大な変革は、決してガチョウの羽ペンでは導かれなかった。宗教的・政治的たぐいの偉大な歴史的雪崩をひきおこした力は、大昔から語られる言葉の魔力であった。○ 指導者の資質について偉大な理論家が偉大な指導者であることは稀で、むしろ扇動者の方が指導者に向いているだろう。指導者であるということは大衆を動かしうるということだからである。彼らは純粋の文筆活動だけに没頭し、演説によって実際に扇動的に活動することを諦めているからである。だが、こういうい慣習は時がたつにつれて、今日わがブルジョアジーを特徴づけているもの、すなわち大衆への働きかけと、大衆への影響に対する心理的本能の喪失に導くに違いない。 立派な演説家は---文筆家が常に弁論術を練習しない限り---立派な文筆家が演説する以上にうまく書くことができる。○ 知性と感情一定の傾向をもった書物は、たいていは以前からこの傾向に属している人が読むだけである。ここでは人間はもはや知性を働かせる必要はない。眺めたり、せいぜいまったく短い文章を読んだりすることで満足している。それゆえ、多くのものは、相当に長い文章を読むよりも、むしろ具体的な表現を受け入れる用意ができているのである。誤った概念や良からぬ知識と言うものは、啓蒙にすることによって除去することができる。だが、感情からする反抗は断じてできない。ただ、神秘的な力に訴えることだけが、ここでは効果があるのである。○ 演説について同じ講演、同じ演説家、同じ演題でも午前10時と午後3時や晩とでは、その効果は全く異なっている。良く知られている大演説家の演説もただちに印刷されるてのを見ると、往々にして幻滅を感じる、とそこで確認されてもいるのである。ロイド・ジョージが、その天才において優れているのは、演説において民衆の心を自分に向って開き、ついに民衆を完全に自分の思うままに動かした、その形式や表現に示されている。その言葉の質朴さ、その表現の形式の独創性、さらにわかりやすい最も簡単な例を用いることこそ、このイギリス人のすぐれた政治能力があることを示す。民衆に対する政治家の演説というものは、わたしは大学教授に与える印象によって計るのではなく、民衆に及ぼす効果によって計るのである。=====================ヒットラーは、このようにプロパガンダの意味や効用を深く理解していたわけです。その彼が自らの技術や能力を駆使して権力の座に就いたわけですが、彼の政治活動の根本モチーフは、ドイツ国家主義、アーリア人至上主義、そして反ユダヤ主義です。民族主義に基づいて対外的な戦争を引き起こし、反ユダヤ主義に基いて「民族浄化」を行ったわけですが、両者の根底にあるのがアーリア人至上主義という構造ですね。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇さて、TV映画『ヒットラー』ですが、この作品は、ナチスが最大政党となり、「全権委任法」によってヒットラーが独裁的権力を奪取する1933年頃までを描いています。ヒットラーのどういう面に注目しているかというと、主としてプロパガンダ(演説、弁舌)能力ですね。彼の演説風景は、『我が闘争』で述べられているポイントをよくおさえたものになっています。同じことを何度も繰り返す、リズム感、熱意、緊張感、単純明快、断固とした調子、結論から述べる、大衆の欲望を的確な言葉で代弁する、等々。第一次大戦の敗北後という不遇、それに追い討ちをかけた世界大恐慌という状況下にあって、ヒットラーはドイツ国民の不満というエネルギーを上手く吸収して自らの支持に結びつけることに成功しました。ここで、映画から感じたことをひとつ付け加えるとすれば、ヒットラーは決して嘘をついていないということですね。彼がユダヤ人の悪口を言うのは、彼自身心底からユダヤ人を憎んでいるからです。隣国や政権に対する不満を述べる場合も同様で、単なる政治的駆け引きとしてそれらを非難しているわけではありません。彼はそういう心情を自らの政治運動の糧とするとともに、その心情を臆面もなく吐露することにより大衆との間に共鳴感、すなわち「共通了解」の念を喚起こしていったわけです。その際、大衆の側には上述の「1)」や「2)」の契機は決して訪れませんでした。なぜなら、ヒットラーの手法は一方的な主張の垂れ流しであり、大衆には対話の機会、すなわち大衆自らがヒットラーに対して言葉を発する機会がなかったからです。大衆は、彼の言葉に納得するか、でなければ反抗して弾圧されるしかなかったわけです。ヒットラーの演説にはある種の狂気が宿ります。しかし、他方で(嘘をついてないという)彼なりの誠実さと(行動を予感させる)ヴァイタリティを感じさせます。ロバート・カーライルは、この狂気、誠実さ、ヴァイタリティを見事な演技で表現していますね。彼の言葉を理解するためには、聴衆は少し狂わないといけません。そうすると、彼の言葉には心に染みわたる魔力があることが分かります。少しも狂うことができなかった人間は、彼のことを一蹴しその場から去りました。しかし、当時の人々に鬱積していた不遇なドイツという心情は、少し狂うことによってもたらされる”心地よさ”に徐々に感化されエスカレートしていったのでした。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
May 28, 2005
コメント(2)
-

『ケン・パーク KEN PARK』
2002年、アメリカ=オランダ=フランス、ラリー・クラーク/エド・ラックマン監督。****************カリフォルニア州、スケボーのメッカとして有名な小さな街・ヴァイセリア。どの家庭も表面的には明るく平和な雰囲気に包まれているが、 家の扉を開けて一歩足を踏み入れるとそこには狂気の世界が待ち受けている。・ケン・パーク:近所の公園へスケボーに出かけ、持ってきたビデオカメラをセットし、薄ら笑いを浮かべながら自分の頭を銃で吹き飛ばしてしまう。・ショーン:小さな弟に馬乗りになって、自分を褒め称える言葉を言えばどと強要する。その後、ガールフレンドの家に行き、母親と関係を持つ。・クロード:マッチョな父親から執拗に責められたうえ、性的関係を迫られて彼は家を出る。・ピーチーズ:ボーイフレンドとのベッド・インを狂信的な父親に見つかり、 折檻される。・テート:一緒に暮らす退屈な祖父母への苛立ちをエスカレートさせ、 ある日、 抑え切れなくなる…。・再びケン・パーク:ガールフレンドから妊娠を告げられ、冒頭に自殺シーンへと回帰する。****************まあ、とにかく無茶苦茶な内容の映画です。主要な登場人物は、子どもも大人もどこか狂っています。子どもたちによる大胆なセックス・シーンがとりわけ問題視され、多くの欧米諸国で上映が禁止されたり保留されたりしました。しかし、日本ではR指定によりすんなり許可されています。これを、日本社会の寛容さの現れとみるのか、それとも、もともと日本は道徳規範が緩い社会とするのか。双方はコインの裏表のようなものですが。この狂気の世界によって何を描いているかというと、「家庭崩壊」ですね。いやむしろ「家庭破壊」といったほうが正確でしょう。「崩壊」という場合は、結果を受動的に表現するというニュアンスが強いですが、「破壊」の場合は、むしろ積極的にそれを押しすすめるという意味合いが強い。両監督は「ここで描かれている家庭の状況は事実なのであって、それを見つめるべきだ」という趣旨の発言をしていますが、私の眼からすると「確かにここで描かれている状況は事実かもしれないが、複雑多岐な事象のなかからこういう事実を抜き出してきた両監督の思想背景のほうが興味深い」ということになります。つまり、両監督はいかにも客観的な視線から家庭の「崩壊」の様を描いているようにみえますが、実は深層には家庭を「破壊」する意図または願望があるのではないのか、ということですね。映画の殺伐とした事実としてのリアリズムは、一方で生のリアリティを欠いており、幻想性(エロス性)というものがまったく感じられません。人間の尊厳どころか、命さえ軽々しく扱われます。つまり徹底的にニヒルなのです。そのニヒルがどこに向けられているのかというと、もちろん家庭ですが、それを衝撃的に象徴するのが、テートの場合です。テートは祖父母に育てられていたのですが、この祖父母は仲睦まじい夫婦で、作品中唯一”マトモ”です。しかし、テートは祖父の些細なミスや祖母の世話焼きが気に入らず、二人を殺害しています。殺害される直前の祖母の言葉が「愛しているわ、テート」です。それでもテートは、なんら躊躇することなく祖母の胸にナイフを突き刺したのでした。こうして、唯一”マトモ”な家庭さえも、それをあざ笑うかのように破壊してしまうわけです。ちなみに、この映画では、「赤」が印象的に使われていますが、「赤」は狂気に通じます。しかし、この作品の「赤」は彩度が抑えられたどんよりしたものが主体で、興奮するというより気分が滅入ってくる「赤」で、陰鬱な雰囲気によくマッチしています。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇(家庭というものの一切の破壊という)ニヒルを徹底した後に、何が見えてくるのか。所有、支配、暴力、闘争、ドラッグ、そしてとりわけセックスといったむき出しの(動物的)欲求です。しかも、ニヒルを徹底した後の、つまりロマンやエロスのないセックスですから、かなり”倒錯”したものになっています。所謂”マトモ”なセックスは一切なく、近親相姦、幼児愛、ゲイ、3P、SMと何でもござれです。つまり、家庭の破壊は、道徳や規範の破壊を意味しているわけです。破壊された家庭を飛び出した子どもたちは、自分たちの将来に何を見たのか。最終シーン近く、ショーン、クロード、ピーチーズは3Pを行いながら「夢」について語りあいます。象徴的なのがクロードが語る「夢」で、セックスだけが存在するユートピアを築くというもの。しかし、そのユートピアなるものは、3Pにふける今の自分たちの世界に他なりません。つまり、「夢」を語りながら、実は、もはや夢を持てない、と白状しているに等しいわけです。どうしようもない閉塞感が漂いますね。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇こうしてみると、「両監督の思想背景」として見えてくるものは、近代または資本主義社会に絶望して、反社会的心情のみが研ぎ澄まされたポストモダン(ポスト構造主義)的風景というものではないでしょうか。つまり、家庭もなく(反近代)、規律もなく(反道徳)、男も女もなく(ジェンダーフリー)、もちろんマルクス主義的世界でもなく(ユートピアの否定)、そこにあるのは荒涼とした世界における乾いたダイナミズム(身体的欲求の充足という運動)でしかありません。そのような世界に人間は価値を見出しえるのかどうか、耐えられるのかどうか・・・・両監督はそう問うているようでもあります。そして、ちょっとそら恐ろしくなってくるのは、両監督は、そういう世界をかなり肯定的にみているのではないか、ということです。ところで、この映画の題名は『ケン・パーク』ですが、ケン・パークという少年は冒頭と最終の短いシーンに登場するのみです。しかし、最終シーンの意味することは重要です。ケンは、ガール・フレンドから妊娠を告白され、中絶を拒否され、その直後に自殺します。つまり、親(大人)になることを拒否したのです。親(大人)になって家庭を築くくらいなら、死んだほうがましだ、というわけです。かようなまでに徹底的に家庭を中心とする近代型の社会を拒否・否定しているわけです。
May 27, 2005
コメント(4)
-

『ムルデカ 17805』
2001年、日本、藤由紀夫監督。“アジア、すでに敵に向かい、蜂起せり 己を捨てて全力を尽くす連合国を粉砕せんと 玉散ることもいとわず進め 進め 義勇軍 アジアとインドネシアの英雄 清き東洋に幸あれ古きアジア 不幸に苦しむ 烈しき圧制に 幾世紀も忍ぶ大日本 雄々しく立てり アジアを救い 我らを守る進め 進め 義勇軍 アジアとインドネシアの英雄 清き東洋に幸あれ…”上は、インドネシアで50年間歌い継がれてきた「祖国防衛義勇軍(PETA)マーチ」です。「大日本」という言葉がありますね。”日本の占領は、後に大きな影響を及ぼすような利点を残した。第一に、オランダ語と英語が禁止されたので、インドネシア語が成長し、使用が広まった。日本軍政の3年半に培われたインドネシア語は驚異的発展をとげた。第二に、日本は青年達に軍事教練を課して、竹槍、木銃によるものだったとはいえ、きびしい規律を教え込み、勇敢に戦うことや耐え忍ぶことを訓練した。第三に、職場からオランダ人がすべていなくなり、日本はインドネシア人に高い地位を与えて、われわれに高い能力や大きい責任を要求する、重要な仕事をまかせた。…”上は、インドネシアの中学校の歴史教科書からの抜粋です。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇インドネシアは、大東亜戦争で日本軍が侵攻し解放するまでの約350年間オランダの植民地だったのですが、大東亜戦争終了後、日本の敗北を受けてオランダ軍とイギリス軍が再び攻め込んできました。この時、約1000人の旧日本軍将兵がインドネシア独立軍に身を投じて戦いました。戦いは4年4カ月続き、1949年12月、オランダはついにインドネシアの独立を認めました。その間、半数の日本兵が戦いで命を落としています。さて、映画『ムルデカ 17805』ですが、「ムルデカ」はインドネシア語で独立を意味します。「17805」とは、皇紀2605年(西暦1945年)8月17日という意味です。皇紀元年とは、神武天皇が即位した年のことです。日本軍が降伏した1945年8月15日の2日後に、後に初代正副大統領となる独立運動指導者のスカルノとハッタが、この日付(皇紀)を書き込み独立宣言文を発したのでした。*****************1942年、第二次世界大戦時下のオランダ領ジャワ島。軍司令部に単身で乗り込み、見事オランダ軍を降伏させた南方戦線実行部隊の島崎中尉は、その後、インドネシアの自治独立を目指し、現地の青年たちを軍事教練する機関「青年道場」を開設した。オランダに政治犯として捕えられていたスカルノ、ハッタ、シャフリル等の民族主義者も釈放された。“サンパイマティ"(死ぬまでやれ!)の精神の下、集まった理想高き志の青年・ヌルハディ、アセップ、パルトらに厳しい指導をする島崎。初めは対立することもあったが、身をもって行動する島崎の態度に、やがてヌルハディらの心の中にも自分たちの手で独立を勝ち取るという気持ちが芽生えていく。ところが、日本の敗戦により状況は一変。オランダとイギリスの連合軍が再びこの国を統治下に置くべく進行を始める。そんな中、インドネシアにムルデカの気運が高まるも、島崎は敗戦処理を担当する将校として手出しの出来ない立場に追い込まれていた。戦友の宮田中尉と共にオランダ軍に身柄を拘束されてしまった島崎は、日々続く拷問を受ける。そして、戦争犯罪に問われ、宮田が処刑された。一方、ヌルハディらの手で奇跡的に救出された島崎は、彼らが率いる独立軍(祖国防衛義勇軍 PETA)に参加することを決意し、いつ終わるとも知れぬ戦闘に身を投じていくのだった。インドネシアの運命を決する最後の戦いに勝った夜、島崎は敵の銃弾に倒れてしまう。そして現代、今や平和な独立国となったインドネシアの英雄墓地に眠る島崎と宮田の墓に、宮田の忘れ形見である娘・文子が詣でる姿があった。*****************映画に登場する島崎中尉は架空の人物ですが、柳川宋成中尉がモデルとなっています。1942年西部ジャワに敵前上陸し、オランダ軍総司令部に単身で日本刀を持って乗り込み、司令官に降伏させたことは、柳川中尉の実話に基づいたものです。柳川中尉は青年道場と郷土防衛義勇軍(ペタ)の創設者でもありました。インドネシアには、12世紀から伝わる「ジョヨボヨ王の予言」というものがあったそうです。”わが王国はどこからか現れる「白い水牛」の人に乗っ取られるであろう、彼らは魔法の杖を持ち、離れた距離から人を殺すことができる。白い人の支配は長く続くが、やがて北からの「黄色の猿」の人が白い人を追い出し、とうもろこしの寿命の間、この地を支配した後に「ラトゥ・アディル=正義の神」の支配する祝福される治世がくる。”日本軍が侵攻した時、インドネシアの各地で紅白旗(インドネシア国旗)と国歌「インドネシア・ラヤ」の大合唱で迎えられた、というのは有名な話です。そして、これまた予言どおり、日本の軍政支配は「トウモロコシの寿命の間」の3年半で終わり、インドネシアは独立したのでした。予言には「天から白い布をまとって降りてくる」という落下傘部隊を示唆するものもあったらしく、日本兵は「空の神兵」とも称されました。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇独立軍の呼びかけにこたえて、戦闘に参加するために日本軍を離隊した宮山滋夫氏の置手紙には、以下のようにあります。 敢えて大命に抗して独自の行動にい出んとす 言うなかれ敗戦の弱卒天下に用なしと 生を期して米英の走狗たらんよりは 微哀に殉じて火による虫とならん 天道は正義にあり 歴史の赴くところ正義にあらずして何ぞ 敢えて不遜の行動に出ずるゆえん 乞うご容赦あらん事を 戦友諸君ジャカルタの「カリバタ英雄墓地」は、独立戦争に命をささげた将兵ら数千柱が眠るインドネシアの「聖地」です。戦闘を生き延びた元兵士たちは、死後はここに「英雄」として埋葬される権利を保持していることを最高の栄誉とし誇りにしています。根元に銀色の鉄かぶとが据えられた灰色の墓石の25柱に、日本人名がローマ字で刻み込まれています。現在もインドネシアで存命が確認されている11人の元日本軍人たちも、ここに埋葬されることになるのでしょう。 毎年、インドネシヤの独立記念日では、インドネシアの服装の男女2名に加え日本兵の服装をした者と3名で国旗を掲揚します。もちろん、独立を支援した日本軍に敬意と感謝の念を表しているわけです。終戦後、戦後賠償の問題でも、交渉に当たった国会議長のアルジ=カルタウイナタ氏は、岸信介首相に対して「独立のお祝いというつもりで賠償金をください。日本が悪いことをしたから賠償をしろというのでありません」といっていますし、当時のインドネシアでは「むしろ日本に感謝使節団を送るべきだ」という声もあがっていたそうです。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇このように、日本人として誇りにすべき歴史を有するインドネシアですが、映画『ムルデカ』は、残念ながら、その誇りを十分に受け止め継承する出来映えの作品とはいえません(同様のことは、映画『プライド』にも言えますね)。ストーリー展開、セリフの深み、演技、映像、音楽、どれをとってもお世辞にも一流とはいえません。インドネシア人の神経を逆撫でするような場面もあります。例えば、インドネシアの老婆が進駐してきた日本兵にひざまずいて、ブーツに接吻する場面や、島崎中尉がオランダ軍の狙撃で戦死した場面で、インドネシア人女性が国歌「インドネシア・ラヤ」を歌う場面がそうです。試写を鑑賞したインドネシア大使館側は、「インドネシア人の習慣や実態にそぐわない部分がある」として異例の削除や修正を求めています。同大使館のシャハリ・サキディン参事官は「ジャワ人には、どんなことがあっても他人の足の甲に口づけする習慣はなく、インドネシア人の威信を落とし、心を傷つける場面だ。また国歌が歌われるのは公の行事や儀式などの厳かな場合であり、鎮魂や闘争の歌ではなく、インドネシア人には非常に奇異に感じる。このままインドネシアで公開したら、観客がこの場面で全員起立してしまうかもしれない」と指摘しました。対して、東京映像制作の代表取締役社長・浅野勝昭氏は「申し入れを検討した結果、日本、インドネシアの友好関係を維持するためにも足の甲への口づけのシーン二~三秒間を公開時にはカットすることにした」とし(私が観たDVDには、このシーンはありました)、インドネシアでの公開に際しては、「インドネシア側の意見をよく聞いて、編集を変えるなど柔軟に対応したい」と述べています。実はこの年、インドネシアでは、イスラム教徒が忌避する豚の成分を使用したとして、「味の素」製品が回収される事態が起きていました。インドネシアでの『ムルデカ』の評判は芳しくなかったようで、インドネシアでは対抗上『CA BAU KAN』という反日B級映画が製作されてもいます。『ムルデカ』への出演を後悔したとされる女優ローラ・アマリアが、意趣返しのような見事な演技を見せているとのことです。『CA BAU KAN』とは福建語で「妓館」で、「慰安婦」「ロームシャ」が登場し、日本人を獣に、華人・オランダ人を美化しています。つまり、この映画は中国系インドネシア人による(『ムルデカ』への)対抗的プロパガンダ映画ですね(日本未公開)。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇日本は戦争で敗れはしましたが、精神的・文化的に破れたわけでは決してない。インドネシアで独立のために戦った日本人たちの行為は、そのことをこそ思い起こさせ、日本人が日本人であることの自信や誇りを自覚させてくれるものです。そうであるが故に、『ムルデカ』のような映画には、文字通り”完璧”を求めたいものです。
May 25, 2005
コメント(0)
-
『アイ The EYE』
2001年、香港、オキサイド・パン / ダニー・パン兄弟監督、アンジェリカ・リーかつてタイで、角膜移植手術を受けた16歳の少女がその1週間後に自殺するという事件があったそうですが、それをヒントにして製作されたホラー映画です。******************幼少の頃に失明した女性マン(アンジェリカ・リー)は、20歳になって角膜移植手術を受け視力を回復した。退院して徐々に視力があることに慣れるに伴い、彼女は時折、幻覚(フラッシュバック)、黒い影、そして不可解な人物や出来事に遭遇するようになった。やがて、それらの人物は自分にしか見えないことがわかり、しかも彼らは死者たちで、黒い影は死後の世界への水先案内人だと悟った。マンから相談を受けた心理療法士のワ・ローは、彼女を術後の精神不安定だと決めつけ、その話をなかなか信じようとしない。重い試練にうなされる日々を送るマンであった。彼女は入院中、ひとりの幼い少女と知り合い仲良くなっていた。脳腫瘍で何度も手術や化学療法を繰り返しながらも、明るさや無邪気さを失うことが決してなかったインインである。ある夜、インインがマンのベッドにやってきたが、インインの後ろには黒い影が。「マン、なにも心配することはないよ。もうちょっとだけ強くなればいんだよ。」微笑みながらそう言い残したインインは、黒い影とともにマンから去っていった。泣きながらインインの後を追ったマンではあったが、翌日から彼女の表情には生気が蘇った。しばらくしてマンは、インインが生前に撮ってくれた彼女の写真を手渡され、愕然とする。写真に写っている顔は、鏡に映る自分の顔とは似ても似つかないものだったのだ。角膜の提供者に原因があると考えたマンは、ワ・ローと共に、提供者であるリンという少女が住んでいたタイ北部の古い村を訪ねてゆく・・・・。******************この映画、セリフを日本語にすると、殆ど日本版ホラー映画と見紛うばかりですね。『リング』などの影響を強く受けたのかもしれません。映像は結構奇麗で、なかなかのセンスを感じさせます。ただ、音楽や効果音に若干の不満が残ります。主演女優のアンジェリカ・リー(李心潔)は歌手としても活躍しているそうですが、見事な演技ぶりでした。ただ、私としては、(角膜提供者のリンを演じた)チャッチャー・ルチナーレンのほうが目元が涼しげで好みですが・・・・もちろん、そんなことはどうでもいい話です(笑)。上で私は、この映画は『リング』などの日本映画の影響を強く受けたのでは、と書きましたが、それは主として画面構成に限った話で、ストーリやプロットは最近の日本のホラー映画とはかなり違うものになっています。かつて私は、日記で「ほんとうに怖い映画(ファンダメンタル・ホラー映画)が備えている要件」として、「小中理論」なるものを紹介しました(「ホラー映画」の構造(一)、「ホラー映画」の構造(二))。それと照らし合わせてみますと、『アイ』には「小中理論」に反する要件が多いですね。以下に「小中理論」の要件を列挙しますが、末尾に(*)をつけたものが「小中理論」に反する要件です。1)脚本構造 ・恐怖とは段取りである ・主人公に感情移入をさせる必要はない (*) ・因縁話は少しも怖くない (*) ・文学は忌まわしい (*) ・情報の統一は恐ろしい ・登場人物を物語内で殺さない2)脚本描写 ・イコンの活用 ・霊能者をヒロイックに扱ってはならない (*) ・ショッカー場面はアリバイに ・幽霊の「見た目」はありえない ・幽霊はどう見えたら怖いのか ・幽霊ナメはやってはならない ・幽霊はしゃべらない (*) ・恐怖する人間の描写こそが観客の恐怖を生みだす ・つまり、ほんとうに怖いのは幽霊しかないのだ (*)「小中理論」は、文学的な内面描写や演劇的な内面告白などにあまりこだわることなく、即物的でかなりドライに”幽霊そのもの”を描写することを画策するものですが、『アイ』の作風は逆にかなりウェットで、その辺の違いが上で表れているのだと思います。そのウェットさを象徴するシーンが、マンが、死んだインインが黒い影に手をとられて去っていく時に、彼女の名前を叫びながら号泣する場面です(このシーン、アンジェリカ・リーの演技は素晴らしいです)。「小中理論」からすると、この号泣シーンは”邪道”なのかもしれません。また、日本映画では、号泣シーンが「だらしなく」映ることが多い。日本人は、誰憚ることなくワンワン泣くシーンよりも、哀しみを内面的に抑えに抑えて、それでも抑えきれずに静かに涙が溢れるという局面のほうに魅力を感じると思います。しかし、この別れのシーンも実にリアルかつ自然なものに映りますね。つまり、『アイ』は、単に幽霊を怖がるホラーではなく、人間の”心の暖かさ”や”生きることの切なさ”をも感じさせる映画に仕上がっているのです。そういう点で、インインというキャラクターの存在や役割り、マンとの別れのシーンはこの映画の重要なポイントとなっています。マンは、インインという友人との出会いそして別れがなければ、つまり”イニシエーション”がなければ、(角膜提供者の)リンの人生を引き受け彼女を救い出すことはできなかったでしょう。単なるホラー映画とは違った、胸に迫ってくるものがある作品ですね。
May 24, 2005
コメント(0)
-
『生きてこそ ALIVE』
1993年、アメリカ、フランク・マーシャル監督実話に基きそれを忠実に再現した映画で、登場する人物はすべて実名です。*********************数十年ぶりの寒さを記録した1972年10月、総勢45人からなるウルグアイの学生ラグビー・チームと家族らの一行は、チリで行われる試合に参加するため、飛行機でアンデス山脈を越えようとしていた。しかし、不幸にも機体は岩山に衝突し墜落した。生き残った27人は、通信不能で捜索隊をじっと待つしかなかった。しかし、厳しい吹雪のため捜索は難航。3日目に上空を飛行機が飛来したが、結局救助隊は一向に現れなかった。数日後、ラジオで彼らは捜索が打ち切られたことを知った。10日目の朝、彼らは仲間の屍を食べることを選択し生存に望みをかけた。しかし、その後も徐々に仲間を失ってゆき、猛烈な雪崩に襲われ何人かの仲間を失うことにもなった。意を決した三人が、救助を要請するために山を越えることとし、ナンドとロベルトはついに山の麓にたどり着き、皆は救助隊に助けられて無事生還することができたのだった。こうして、夜には零下40度にもなる極寒や飢えに耐え抜き、事故から72日後に16名が奇跡的な生還を果たしたのであった。 **********************ロケは事故現場と同じくらいの寒さや雪があるロッキー山脈で行われましたが、雪山の映像は本当に奇麗ですね。ただ、そういう自然であっても一皮むけば人間にとって極めて過酷な環境に変貌するわけで、そうであるが故に景色の奇麗さがより一層強調されてきます。零下40度の寒さというのは、私の想像を絶しています。この遭難者たちは、飛行機の残骸(胴体)で寒さをしのいだのですが、人から聞いた話によると、雪に穴を掘るかカマクラを作ったほうが寒さはしのぎやすいということです。飛行機の残骸では、隙間風がきつかったでしょうね。この映画、DVDには”メイキング・オブ・アライブ”として、一時間ほどの特典映像が収録されています。そして、この特典映像が、何と言っても面白い!2時間ほどの本編は、この特典映像のプロローグといっても過言ではないとさえ思えてくるほどです(その理由は後述)。特典映像では、実際に事故に遭って生きのびた人物たちが実際に登場し、インタビューで救出されて以降の心の内を臆面もなくさらけ出しています。しかも、そのうちの何人かは、(彼らのアドバイスによって)事故現場を忠実に再現したロケ地を訪れて、当時の記憶を生々しく甦らせた後で語っています。ある者は、ロケに招待されたわけでもなかったのに、自らの意思で訪れています。彼らが語る「物語」は、どれも個性的です。当時の行動を誇りとする者、内心の忸怩たる思いを隠そうとしない者、臨死体験の告白、今風にいうと重篤なPTSDに陥った者、神への信仰(彼らは皆カトリック系の大学に通うカトリック信者でした)を語る者、等。事故から救出された直後、彼らは英雄として賞賛の的だったのですが、チリの新聞が「人肉食」を暴露してからは、賛否両論が入り乱れた議論の渦に巻き込まれていくことになります。また、彼らは皆、事故で亡くなった方々の家族とともに一つの小さな町で今でも暮らしており、日常的に顔を合わせて暮らしています。遭難事故はもちろん大変な出来事でしたが、生還後の社会的出来事もそれはそれで大変な出来事だったのです。そういう彼らを支えたのは、やはり宗教だったようです。映画をご覧になればお分かりだと思いますが、根底に流れるテーマは神への信仰に他なりません。彼らは何度か動揺しながらも”団結”を失うことは決してありませんでしたし、事故後のいまもそれは失われていませんが、この”団結”の強さは信仰を抜きにしては語れない面があったのでしょうね。遭難して過酷な環境にありながら、彼らの生活は規律が守られたものでした。それを典型的に象徴するエピソードが死体の管理で、メンバーのうちの三人によって終始厳格に行われています。しかし、それでも”心の疚しさ”に悩み続け、遂には「獣になる前に出発しよう」と山越えを決断したのでした。そういう彼らが保持した規律から私が連想したのが、ホッブスの唱えた「自然法」です。ホッブズは、社会契約説を説明するにあたり、まずは、社会的規範が何もなく自己保存のために「万人の万人に対する闘い」が行われる原初的な状態(「自然状態」)を想定します。「万人の万人に対する闘争」という時の「万人」とは、キリスト教徒のことではありません。キリスト教徒でないばかりか、いかなる意味でも宗教的人間ではなく、彼らは互いに他を傷つけあうような”野蛮人”です。そういう状態をホッブズは人間”本来”の姿だとして「自然状態」と呼んだわけです。「万人の万人に対する闘い」という過酷な状況にあって、やがて人々の間に理性が働くようになり、自分自身の安全を確保し生きのびるために関係の合理性を見出そうとします。これがホッブズのいう「自然法」です。実は、ホッブズの「自然法」は、キリスト教によって基礎づけられていた「自然法」(神の理性、神の定めた自然の理)とは一線を画するものです。なぜなら、ホッブズの「自然法」を基礎づけているのは、どんな人間も「自然状態」においては生きのびるためにあらゆる手段を用いるという”事実”(人間の本性)なのであって、そのような人間の本性は、キリスト教では神の意志に逆らうものとして悪であると規定されるからです。・悪として人間の本性を道徳的に否定するキリスト教的「自然法」。・人間の本性を事実として受け入れ、それによって基礎づけられるホッブズ的「自然法」。アンデスで遭難した者たちがみせた団結や規律、すなわち自然法は、キリスト教的だったのでしょうか、それともホッブズ的だったのでしょうか。映画『生きてこそ』では、キリスト教の聖体拝領を引き合いに出すなどして、キリスト教的「自然法」だと主張しています。しかし、どこか白々しさが漂う、という印象は否めません。はからずも、その白々しさを払拭し、ホッブズ的な「自然法」に他ならなかったと暴露しているのが特典映像(”メイキング・オブ・アライブ”)だと思います。
May 22, 2005
コメント(2)
-

『アレグリア 2』 (名古屋公演)
シルク・ドゥ・ソレイユの『アレグリア2』名古屋公演を観てきました。シルク・ドゥ・ソレイユはカナダのケベック州で生まれましたが、そこはサーカスや大道芸人のメッカで、毎年夏には世界中の大道芸人たちが集まるサマー・フェスティバルが開催されています。さらに現在シルク・ドゥ・ソレイユが拠点をおくモントリオールには、約30ほどのサーカス関連会社や国立のサーカス学校もあります。シルク・ドゥ・ソレイユの設立は1984年。ケベックで活動する二人のパフォーマーを中心として細々と大道芸を演じていたのですが、やがて評判となり、それに気をよくした二人はケベック州に後援を求めたのでした。その後はご存知のとおりで、現在は世界中から集まったアーティスト600名を含む2700人のスタッフたちにより、同時に世界でさまざまな作品の公演が行われています。シルク・ドゥ・ソレイユのオーディションには、有名となった現在では多数が応募してくるのですが、その面接風景はというと・・・・・。面接官のセリフは「君は何ができるのかね。得意な技を、いま、この場でやってくれたまえ」で終わり。後は、応募者が面接官を満足させる技をその場で披露できるかどうかです。完全な実力主義ですね。日本には、1992年に『ファシナシオン』、1994年に『サルティンバンコ』、1996年に『アレグリア』、2000~2001年に『サルティンバンコ2000』、そして2003~2004年に『キダム』と公演を重ねてきました。去年は、シルク・ドゥ・ソレイユの創立20周年、『アレグリア』誕生10周年を迎える年でしたが、これを記念してフジテレビの主導のもとシルク・ドゥ・ソレイユと会議を重ね、今もなお北米ツアー中の『アレグリア』に敢えて時間と労力と資金を投下し、再演出して出来上がったのが『アレグリア2』です。ただ、DVDの2001年オーストラリア公演と比較しまして、そう大きな変更はありません。さて、私の『アレグリア2』(稲沢駅横の会場)への旅ですが、稲沢駅の横の特設駐車場のチケットをとり忘れたので(「ぴあ」やコンビニであらかじめ駐車チケットを購入しておかないと利用できない。路上駐車すると、まずレッカー移動されるらしい))、また連休中ということもあって、米原まで車で行き、そこからは新幹線で名古屋、さらに東海道本線で稲沢という経路。これが正解で、新幹線から名神高速が見えたのですが、渋滞の真っ最中。あれに巻き込まれていたら、開演に間に合わなかったかもしれません。米原駅西口には、有料駐車場が多数ありますが、一日500~700円と低料金です。私が利用した駐車場は、爺さんたちが数人で管理しており、なかなかアバウトな方たちばかりで面白かったです。「この駐車場は管理人は6時までで、それまでに帰ってこなかったら、カギはフロント・カーペットの隙間にで挿んでおくから、適当にもってってくれ」だそうです。同様の雰囲気は、F1観戦で利用した、鈴鹿サーキット近辺の臨時有料駐車場でもありましたな。さて『アレグリア2』ですが、期待を裏切らない素晴らしいパフォーマンスでした。私はシルクの作品は、DVDやヴィデオ化されたものは殆ど観ており、実際に観たのは『キダム』に続いて2作目です。それだけの経験しかないのですが、やはり『キダム』が一番気に入っています。クールな雰囲気、オブジェっぽいアイテム配置の多用、現実との接点(「超現実」)と、シュルレアリスムの原点を観るような思いがするものですから。『アレグリア(2)』は『キダム』と比較しますと、パフォーマンスや技がダイナミックですね。そこに生じる躍動感は、確かに、「アレグリア」(スペイン語で「歓喜」の意味)という題名に相応しいものです。”動”の『アレグリア』、”静”の『キダム』ということですね。歌や音楽も、どこかもの悲しい雰囲気が漂う『キダム』に対して、『アレグリア』は壮大です。キャラクターは、たぶん、『アレグリア』は昆虫をイメージしており、『キダム』は自然(星、太陽、月、そして精霊)です。ストーリーは・・・・・シルク作品に、固定したストーリーがあるとするならばの話ですが・・・・・、『キダム』は、現代社会から疎外され居場所を見失った自閉気味の少女が、表面的には隠匿されている自然というものに接して、その豊穣かつ神秘的な世界の素晴らしさを感じ取りながら、遂には自分と世界との関係性を取り戻すというものです。『アレグリア』は、辛い過去を背負った男が、そこに展開される世界像の素晴らしさに接し、心の傷を癒して歓喜するといったもの。クラウン演じる「スノー・ストーム」には、そういう意味が込められていると思います。そして、『アレグリア(2)』で、私が最も印象に残ったのはこの「スノー・ストーム」でした。
Apr 29, 2005
コメント(4)
-

『 トーク・トゥ・ハー ( Talk To Her) 』(前)
2002年、スペイン、ペドロ・アルモドバル監督・脚本昏睡状態となり眠り続ける、二人の美貌の女性バレリーナの卵と女闘牛士話しかけ、触られた一人の女性にだけ奇跡が訪れる・・・・映像に装飾品、ファッション、そして色彩を”過剰”なまでにつめ込むことによって、独特のエロティシズムを表現してきたアルモドバル監督の最新作品です。しかし、この作品では”過剰”は若干抑えられたものになっており、そのぶん情緒性が増しています。1999年の『オール・アバウト・マイ・マザー』はアルモドバルのそれまでの集大成とされる作品ですが、それから3年、アルモドバルの作風には一つの転機が訪れたようです。◇ ◇ ◇ ◇【ストーリー】事故で昏睡状態に陥り、病室の清潔なベッドで深い眠りについたままのダンサーのアリシア。そんなアリシアを献身的に看護するのは、彼女を「生前」から慕っていた看護士のベニグノ。ベニグノは、眠り続けるアリシアの髪や爪を手入れし、体を拭き、クリームをぬり、服を替える。さらに、ベニグノは彼女に日々の出来事や感動的な舞台や映画について語りかけ続け(トーク・トゥ・ハー)、はや4年が過ぎようとしていた。ベニグノは、15年もの間、家に閉じこもり母親を介護するだけの生活を送ってきたという過去があり、アリシアの看護に全く抵抗感がない。一方、女闘牛士であるリディアが、競技中の事故によって昏睡状態に陥り、ベニグノが勤務する病院にやってきた。”話しかけてみて。女性の脳は神秘的だから。”突然の事故に困惑し、彼女の傍らで泣き、悲嘆にくれていたリディアの「恋人」のマルコを、ベニグノは「彼女に話しかけて」と諭す。しかし、マルコは、眠り続ける「恋人」に話しかけるどころか、触れることさえできない。愛する女性が同じ境遇にいるベニグノとマルコの2人は次第に心を通わせ合い、いつしか厚い友情が芽生えていた。ある日、マルコは、リディアの前恋人から、彼女の本音を聞かされ絶望に打ちひしがれる。失意のうちに、マルコは病院を去る。そんなある日、病院では、アリシアが妊娠していることが発覚する。そして奇跡が…。◇ ◇ ◇ ◇アルモドバルは、以下のような過去10年間に起きたいくつかの事件と日々の記憶からインスピレーションをえて、本作品を企画しました、 ・美は痛みたりうる(コクトー)---人は、予感できないほどの、また、信じられないほどの美しさに遭遇すると、喜びというより、痛みに似た感情に襲われ、それが涙を生むものだ。涙は、何かを失った人の目に湧き出て、不在や欠損を補うものだ。本作品では、マルコは頻繁に涙を流しますが(「泣く男 マルコ」)、アルモドバルはこういう意味を込めているわけです。 ・米国人女性が16年の昏睡状態から目覚めたという出来事。医学的に説明しずらい回復をとげた彼女が、看護婦に介助されながら歩く練習をする写真を見て、アルモドバルはいたく感銘を受けました。 ・ルーマニアであったのですが、死体安置所の夜警の男が、孤独にさいなまれて、また、あまりの美しさから、安置してあった女性の亡骸をレイプし、それがきっかけで彼女を息を吹き返したという事件。その女性はカタレプシーという病で仮死状態にあり、死んだように見えましたが実際には息があったわけです。夜警は逮捕され裁判を受けますが、娘の復活に感謝した家族は、彼に弁護士を雇い弁護料を払ったそうです。 ・ニューヨークの病院で、脳死状態の女性が妊娠した事件。犯人は病院の用具員と判明しましたが、脳が死んでいても命を宿すことが出来るという神秘にアルモドバルは驚きを覚えました。 ・アルモドバルは、『悪魔の人形』(1936年、トッド・ブラウニング監督)と『縮みゆく人間』(1957年、ジャック・アーノルド監督)を観て以来、「僕は家具の足や床のレリーフ模様が主な舞台の、小さな人間の出てくる映画を撮りたいと思っていた」と語っています。
Apr 27, 2005
コメント(4)
-

『鳥』 (ヒッチコック)
1963年、アメリカ、アルフレッド・ヒッチコック。60年に低予算映画『サイコ』が予想外の大ヒットとなり、ヒッチコックは『サイコ』を超える作品作りに奔走することになります。そして、自ら大の鳥嫌いであるヒッチコックがたどり着いたのが、実際に起こった鳥襲撃事件を基にしたダフネ・デュ・モーリアの短編『鳥』を映画化することでした。映画では鳥の襲撃をなかなか信じてもらえないのですが、実は鳥は結構人間を襲います。私も経験があります。子どものころあるトンビにつけ石を投げつけたら、しばらくそのトンビに付け狙われたことがあります。まあ、そのトンビは「札付き」で、数人の子どもを襲っており、ある子どもなどは右目の下数ミリのところに爪を突き刺されましたが(トンビは目を狙ったようです)。また、カラスが食べ物を持った人間を背後から襲う場面を、何度か目撃したことがあります。それと、襲われたわけではありませんが、近所にカラスの溜まり場となっている公園があり、夜中に数万羽にもなるカラスが木に止まっている中を歩いたことがあります。さすがに不気味でした。見た目は可愛いカモメなども、結構意地汚いですし獰猛でもあります。【ストーリー】ペットショップで出会った弁護士ミッチに無礼な態度をとられたメラニーは、気まぐれと好奇心からミッチを追ってデボラ湾に向かうが、その途中一羽のカモメに襲撃される。その翌日、カモメだけでなく、あらゆる野生の鳥たちが人間を襲い始め、小さな町は大混乱に陥る。普段は人間に無害なスズメやカラスといった野生の鳥たちが人間たちを襲いだす・・・・。ヒッチコックは本作のテーマについて「自然は復讐する」と語っています。映画の冒頭、ペットショップで籠に入れられたおびただしい数の鳥が映し出されますが、そのことに対する復讐でしょうか。または、環境破壊の危険を訴えていたのかもしれません。この映画は、馴染みがある鳥たちが得体の知れないモンスターに変じて集団で人間を襲うというものですが、これでひとつ思い出したのは、欧米映画に登場するモンスター、とりわけ集団で登場するモンスターは「アジア」のメタファになっている、ということです。「アジア」とは、中国人、イスラム教徒、そして日本人などを意味します。主人公のミッチとヘイワースは、それぞれ弁護士と新聞社社長令嬢で、容姿端麗で会話が上手く嫌味もない。つまり典型的なアメリカ中流階級に属するわけで、どこから見ても羨ましいカップルなのですが、実は共に「家族」的な病理を心のうちに抱えています(ヒッチコック映画ですから、当然ですか)。そして、その心の傷に忍び込むように、鳥が彼らを襲いだします。かつて「日記(2004年1月24日)」で述べたように、ヨーロッパ社会の根底には「アジア」というものに対する恐怖があるようです。古くはトルコ帝国、イスラム教徒、中国(黄禍論)、日本(「エコノミック・アニマル」)と。そして、欧米人にとってこの「アジア」というもののイメージは、不規則、迷路、集団主義(個が見えない)、「何を考えているかわからない」、「死を恐れない」といったものではないでしょうか。この「アジア」のイメージは、この映画の「鳥」とそっくりなんですね。ベトナム戦争がはじまったのが1960年。もしヒッチコックがベトナム戦争を念頭におきながら『鳥』を製作したのだとしたら、戦争の結末を見事に先取りした内容に仕上がっているといえるでしょう。
Apr 25, 2005
コメント(2)
-

『ビレッジ』
2004年、アメリカ、M.ナイト・シャラマン監督。いま私がもっとも気に入っているシャラマン監督の最新作で、期待を裏切らない内容でした。==============深い森に囲まれたそのでは、60人ほどの住民たちが家族のような絆で結ばれながら、自給自足の暮らしを営んでいる。金や個人所有がない地上の楽園のようなこの村に、決して破ってはならない三つの掟があった。森に入ってはならない、不吉な赤い色を封印せよ、警告の鐘に注意せよ。誰が何のために掟を作ったのか、確かなことは誰一人知らないが、村人は森に棲む怪物を恐れ、外界との接触を絶って慎ましく生活していたのだった。そんなある日、ひとりの若者ルシアスが、村にはない医薬品を手に入れるために、禁断の森を抜ける許可を申し出る…。==============シャラマン監督というと、デビュー作の『シックス・センス』以来あっと驚くどんでん返しが有名で、この作品にもそれが用意されています。ただ、この作品の本質はホラーやミステリーではありません(これらは、あくまでテイストにすぎません)。『ビレッジ』は紛れもなくラブ・ストーリーですね。この作品には、いろんなカタチの「ラブ」の表徴が描写されています。通常の恋愛はもとより、献身、勇気、庇護、秘密、嫉妬、狂気、恐怖、そして沈黙と嘘・・・・。彼らの「ラブ」はあまりに”イノセント”であり、そうであるが故に、相手への信頼や、「裏切り」に対する復讐なども尋常ではありません。閉ざされた村であるが故に、あまりにイノセントな住民たち。村の囲りを固めるのは、怪物が棲む森です。森の怪物を象徴するのは「赤」、村を象徴するのは「黄色」。「赤」は、血を意味します。血は生命のパワーの源泉であるともとに、不安や恐怖心に訴えそして狂気へと繋がります。「黄色」は、平和や安定を意味します。村は<心>、森は<身体>、という具合に一人の人間のメタファになていますね。村の結界が破られ「赤」が侵入してきた時、村は狂気に包まれ、それを契機として村の住民の一人が外界と接触するため森の深くへと旅立ってゆきます。この時、森は<杜>と化し、この住民とともに村全体がイニシエーションを受けることになります。つまり、この物語は一種の「メルヘン」ですね(この辺については、この日記以降を参照ください)。私がシャラマン監督に注目している最大の理由は、彼の作品が、シュルレアリスムをもっとも正統的かつ現代的に具現していると思われるからです。私はかつて「シュルレアリスムを現代的に読み直して、是非とも復活させたい」と述べたことがあります。具体的には、客観主義に偏りすぎていた(ブルトンらの)シュルレアリスムを、実存主義的・現象学的に読み解くというものだったのですが、なんのことはない、シャラマンがシュルレアリスムにラブストーリーを組み合わせて見事それを成し遂げてしまいました。そういう意味でも、忘れることが絶対にできない作品です。◇ ◇ ◇ ◇俳優陣はホアキン・フェニックス、エイドリアン・ブロディ、シガニー・ウィーバー、ウィリアム・ハートと豪華ですが、その中にあって新人のブライス・ダラス・ハワードの演技も輝いてました。エイドリアン・ブロディの狂人(ノア)ぶりも、アカデミー主演男優賞(『戦場のピアニスト』)を獲得しているだけあって見ごたえがありました。恐怖シーンを効果的に盛り上げていたのは、彼の「笑い」です。ワンシーン、ワンシーンの充実ぶりはいつものシャラマン流ですが、音楽は20代後半の新鋭バイオリニストのヒラリー・ハーンが奏でる音色が素晴らしい。私がもっとも好きなシーンは、前半、怪物が村を襲った時に、ルシアス・ハント(ホアキン・フェニックス)が、彼を信じて手をずっと差しのべ続けていたアイヴィー・ウォーカー(ブライアン・ダラス・ハワード)の手をとって地下室に駆け込む場面です。盛上げ方やスロー・モーションの使い方といい、音楽といい、感動的なシーンでした。
Apr 23, 2005
コメント(2)
-
『裸足の1500マイル』
2002年、オーストラリア、フィリップ・ノリス監督。1930年代から70年代にかけてオーストラリアでは、先住民アボリジニに対する隔離・同化政策がとられていました。この政策の対象となったのは、アボリジニと(イギリス系)白人との間に生まれた混血児たちです。その多くは、アメリカにおける黒人と白人との混血児同様、白人男性によるアボリジニ女性の「レイプ」によって産まれた子供たちです。「レイプ」のほうではなく混血児の存在そのものを問題視したオーストラリア政府当局は、幼い混血児をアボリジニ家族から引き離して隔離し、子供達に英語教育、白人文化、キリスト教を施して白人社会に適応させ、一定の年齢に達したら少年は農夫として、少女はメイドとして白人家庭で使用するという政策をとりました。隔離された子供たちは、施設から出ることはもとより、母親と再会することさえ禁じられていました。先住民女性のメイドという職業ですが、これまたアメリカと同様、白人男性の性の対象と暗黙に了解されていたわけですが、この政策の主眼は、混血女性を外見的(皮膚の色)にも白人化させることでした。白人男性とアボリジニ女性との間の混血児(ハーフ)を(アボリジニ男性から隔離して)メイドとして使用しながら白人男性と交わらせ(クォーター)、その子供に対してさらに同じことをくり返せば(オクタム)、外見上は白人と殆ど変わらない人間になってゆくという次第です。このようにして、現存する混血女性を<白人の側>に取り込み、もって混血児問題を”解消”しようとしたわけです。この隔離政策に遭った子供たちのことを「Stolen Generation(失われた世代)」と称します。シドニーオリンピックで現役の選手としては異例の聖火の点火役をつとめ、陸上女子400m走で金メダルに輝いたキャシー・フリーマンの祖母も、この隔離政策の犠牲者でした。オーストラリア政府としては、フリーマンを起用することによって、白人と先住民アボリジニとの「和解」を国際的にアピールしたかったのでしょうが、アボリジニたちからは、フリーマンのように華々しく活躍する者にだけスポットライトがあてられて、貧困にあえいでいる他の大多数の先住民に目が向けられない、と批判する声もあがったそうです。しかし、フリーマン自身は、いろんな声があることに悩みながらも、「自分がオリンピックで活躍することで、アボリジニの子どもたちに希望を与えることができる」という判断で、オリンピックでのさまざまな役割を引き受けたのでした。オリンピックで彼女がみせた複雑な表情の背景には、そういう事情があったのです。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇【ストーリー】1931年、オーストラリア。先住民アボリジニの混血児を家族から隔離し、白人社会に適応させようとする隔離・同化政策により、14歳のモリーと妹で8歳のデイジー、モリーの従妹である10歳のグレイシーという3人の少女が、強制的に寄宿舎に収容された。気丈なモリーは息がつまるような施設の環境が耐えられず、母のもとへ帰ることを計画。脱走した3人は、1500マイル(2400キロ)にもなる厳しい家路を歩き始めた。あてどなく荒野をさまよっていた3人だったが、ある白人女性に、故郷ジガロングへと通じるオーストラリア大陸を縦断するうさぎよけ用のフェンス("RABBIT PROOF FENCE"=映画の原題)を教えてもらう。フェンスを頼りに歩いていく彼女たちを、アボリジニ保護局の局長ネヴィル、そしてアボリジニの追跡人ムードゥが追い掛ける。やがてグレイシーが彼らに捕まってしまう。最後の気力を奮い起こし逃げ続けるモリーとデイジーだったが、フェンスは途中で途絶えていた。絶望する彼女たちだったが、やがて精霊の助けを得て、見事2人は故郷にたどり着いて母との再会を果たし、90日に渡った旅を終えたのであった。この映画の原作は、『RABBIT PROOF FENCE』という同名の本です。著者はモリーの娘ドリスで、母についての物語を綴ったノンフィクションです。この親子の物語りはまだまだ続きがあります。映画ではモリーが8歳の妹とともに無事母の元へ帰りついたところで終わっていますが、モリーはその後砂漠の奥地に移り住み、結婚して2人の娘を産み穏やかに暮らしていました。しかし、1940年11月、モリーと娘達は再び収容所へ移送され、その翌年、モリーは上の娘のドリス(4歳)を残し、1歳半の娘のアナベルを連れて再び逃亡し、なんと9年前と同じルートを辿ってジガロングへと戻ったのでした。さらにその3年後に、アナベルが再び捕まり南部の施設へ送られ、それきり家族はアナベルとは再会していません。収容所にひとり残されたドリスは母が逃亡したことを知らないまま収容所で暮らしていましたが、やがて隔離同化政策が見なおされ、キリスト教のミッションができ、ドリスはクリスチャンとなり、行政の思惑通り「完全に白人化した人間となった」ことをのちに自らも認めています。自らの出自を知ったドリスは、アイデンティティを求めてアボリジニの言語や歴史を修得するうちに、叔母にあたるデイジーから母のことを聞き本にしたのが『RABBIT PROOF FENCE』です。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇この映画には、明らかな「悪人」は一人も登場しません。モリー姉妹たちは逃亡の途中でいろんな人物に出会いますが、アボリジニはもとより白人にしても、皆彼女たちに同情的です。憎まれ役の隔離・同化政策の実権を握る保護局長ネヴィルにしても、隔離・同化政策は社会のためだと確信していたのですし、逃亡したモリー姉妹の追跡も、彼女たちを保護するためという動機が強かった。つまり、この映画に登場する者たちは、皆、普通の人間たちなのです。普通の人たちが、それぞれの使命、職務、善意にかられながら行動しているのです。それにオーストラリアの自然の優美かつ霊験的な描写や夢幻的な音楽(ピター・ガブリエル担当)が相まって、シーン全体が非常に柔らかい空気につつまれてます。従来の紋きり型の「糾弾映画」とは、一線を画する内容となっていますね。オーストラリアでアボリジニに対する過酷な「差別」があったのは事実ですし、現在でも完全に解消されてはいないでしょう。しかし、その「差別」の存在を単に糾弾するだけでは、「差別」は解消しません。勢いのおもむくところ、被差別側は「差別」をより一層残酷かつ非道なものとして描いて糾弾を続けようとしますが、しかし、残念ながら、それでも「差別」は解消することはありません。そうなると、被差別側に到来するのは絶望やニヒルという感覚で、反体制・反社会的に「差別」解消運動をより激化させるか、「差別」解消を諦めるか、二つに一つの選択を迫られることになります(最近は、人権意識の昂揚により、前者が選択されることが多いようですが)。では「差別」を解消するにはどうしたらよいのか・・・・この点についてはそのうち述べるつもりですが(『オペラ座の怪人』の項でも示唆しておきました)、この映画の作風はこれに関してヒントを提供してくれる内容になっていると思います。
Apr 19, 2005
コメント(6)
-
ホラー映画の構造(終)
幽霊というのは現実における存在でもなければ、まったくの虚構でもない(と考えられています)。現実と虚構の間に横たわり、時として現実世界に顔をのぞかせて「死」を示唆したり、我々の生存可能性を脅かすものが幽霊というものです。ただ、よく考えてみますと、現実と虚構(=あの世)の双方に佇む存在であるがゆえに、幽霊というのは魅力的でありますし、ある意味では希望にもなりえるのです。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇幽霊がなぜ魅力的であり、希望にさえなりえるのかについて説明する前に、「死」についてちょっと考えてみましょう。私は先に「”嫌悪”としてのホラー」について、以下のように説明しました。===========”嫌悪”とは、不快や驚きといった人間のエモーショナルな反応のことですし、人間の生存が脅かされる事態(死が示唆される状況、現実をコントロールできない状況)において生じる心的反応といってもよいでしょう。===========我々が幽霊を”嫌悪”する根本的な理由は、「死」が示唆されるからです。「死」は我々にとって最大の恐怖です。なぜ恐怖なのかといえば、「死」とは自分自身の消滅すなわち<無>を意味するからです。「死」すなわち<無>とは何か? などと問うてみても無駄です。対象として、我々の思考どころか(通常の)感覚さえも拒否するのが<無>という状態なのですから。人は必ず死ぬ・・・・・このことに異論がある人はまずいないでしょう。つまり、「人は必ず死ぬ」というのは、もっとも客観的な事実と我々は認識しているわけです。人間は「死」について、結構幼少の頃から恐怖の念を抱くようですね。私は小学生の頃でしたが、私の子どもたちもそうでした。小学生の末娘なども最近「私、絶対に死にたくない!」などと涙ながらに訴えてきております。「死」の恐怖を和らげるために、人間は、例えば宗教という「物語」を創り出してきたといってよいでしょう。宗教的な死後世界には、極楽、天国、浄土、地獄などといった「虚構」がつきものです。つまり、宗教の癒しのメカニズムは、「物語」の力によって「死」が孕む<無>を<有>へと転換することにあるわけです。そして、幽霊にも宗教と同様の「物語」性があるんですね。「現実と虚構の間に横たわり、時として現実世界に顔をのぞかせて我々の生存を脅かすものが幽霊」であるとして、もし、実際に幽霊が存在するのであれば、間接的にではありますが、現実世界のほかに虚構世界(=あの世)も存在することが証明されることになり、我々にとって「死」はまったくの<無>ではなくなるわけです。そういう意味で、「幽霊というのは魅力的でありますし、ある意味では希望にもなりえるのです」。つまり、幽霊という存在は「死」を示唆しつつも、「死」の乗り越えの原理をも到来させえる、ということですね。私はかつて、近所の寺の住職に、「幽霊というものを是非とも見てみたいものだ。死後の世界があるのなら、私は死を怖れるどころか、場合によってはすすんで死ぬかもしれません」と言ったことがあります。住職の答えは「そういう人間は、死んでも幽霊にはお目にかかれんよ」というものでしたが(笑)。バタイユによれば、エロティシズムとは「死の乗り越えの可能性」とほとんど同義なのですが、そう言われてみると怪談ってどこかエロティシズムが漂うものが多いですね。と言いますか、人間は(バタイユ流の)エロティシズムを求めて幽霊という「物語」を創りだしてきたのかもしれません。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇先に紹介したように、小中千昭氏などは、幽霊”そのもの”が「本当に怖い」と考えているわけです。皆さんは、小中氏による(観客を恐怖させるための)「小中理論」の骨子は、作品で 【 幻想に他ならない幽霊を、いかにリアル(客観的)に描写するか 】 に最大の力点がある、ということにお気づきなられたと思います。人智を超えた客観存在として幽霊を描写すれば、観客は本当に怖がる、と。「小中理論」で前提されているのは、幽霊というものは絶対的に怖い存在である、ということです。しかし、いかに映画や小説の中とはいえ、そう前提してよいものかどうか?その前提で作品をつくり続けると、たぶん、マンネリ化してしまうと思います。そうなりますと、観客受けするために、より衝撃的つまり”嫌悪”を増幅させるような刺激的なシーンを取り入れていかざるをえないことになります。つまり、技術的なアイデアの勝負になるということですね。実際、いまの日本の「幽霊映画」はそういう状況にあるのではないでしょうか。幽霊が怖いのは、幽霊の存在によって、普段の日常生活にまぎれて心の深層に隠匿されている「死」すなわち<無>の恐怖が顕在化させられるからです。さらに、幽霊が絶対的に怖いという前提に立つ限り、幽霊という存在によってこそ心に湧きあがってくる魅力や希望、さらにはエロティシズムについては、軽視され続けることにもなるでしょう。それでは、奥の深い幽霊映画を製作することはできません。幽霊=「本当に怖いもの」と先験的かつ客観的に扱うのか、それとも、幽霊を一度「心」に還元して意味や本質をとりだすのか・・・・そこが小中氏(前者)と私(後者)との根本的な違いです。
Apr 18, 2005
コメント(2)
-
オペラ 「トスカ」
本日、オペラ「トスカ」を観てきましたので、「ホラー映画」は一休みします。「トスカ」といえば、ご存知プッチーニの代表的名作オペラで、初演は1900年。この度、金沢観光会館で、オーケストラピットが前3列から6列に拡大され、そのこけら落としとして企画されたのでした。ソプラノは、地元金沢出身で現在はヨーロッパを中心として活躍中の濱真奈美さん。イタリアに留学した後、1990年ドイツ・フルト歌劇場にて「蝶々婦人」にてデビューを飾っています。レパートリーは他に「椿姫」、「トロヴァトール」、「ラ・ボエーム」等。10年ほど前に、彼女が歌う「ある晴れた日に」を目の前で聴いて完全に圧倒され、それ以来私のディーヴァ的存在です。声は全体的に伸びと厚みがあり、中低音域が特に魅力的です。彼女の同級生だった人を知っているのですが、その人によると、濱さんは小さい頃から腰周りに迫力があって(ただし、体型は太っているというわけではありません)、オペラ歌手になったと聞いて「ああ、彼女ならおかしくない」と友人同士で納得しあったそうです。容貌は、前回見たときよりぐっと色っぽくなっていましたし、歌声にもより一層の艶が出てきた印象です。彼女はいまが円熟期といってもよいようです。そういう彼女が歌ったアリア「歌に生き 愛に生き」、最高でしたね。 歌に生き恋に生き 決して他の人に悪いことなんかしませんでした 多くのかわいそうな人たちに会いました そのたびにそっと内緒で助けてあげてきました いつも心から神を信じて祭壇にお祈りを捧げてきました いつも心から信仰して祭壇にお花を捧げてきました それなのに神様、この苦しみの時にどうして、 どうして私にこんな仕打ちをなさるのですか 聖母さまのマントに宝石を寄進し 私の歌を星に、天に捧げ 天はその歌に優しく微笑んで下さったではないですか それなのにこの苦しみの時にどうして、どうして神様、ああ どうして私にこんな仕打ちをなさるのですか「歌に生き 愛に生き」の歌詞に象徴されているように、このオペラのテーマは「不条理」です。ストーリー)恐怖政治が行われていた1800年のローマ。画家のカヴァラドッシが教会で絵を描いていると、彼の友人で前の領事のアンジェロッティが脱獄してきた。ちょうどそのとき、カヴァラドッシの恋人、美貌の歌姫トスカが来たために、彼はアンジェロッティをかくまう羽目になる。トスカが帰った後、2人は慌てて逃げる。警視総監のスカルピアは、脱獄犯を探している最中にトスカと出会う。スカルピアは以前からトスカに横恋慕しており、言葉巧みにトスカの嫉妬心を煽るとともに、カヴァラドッシの隠れ家をつきとめる。ファルーネーゼ宮殿のスカルピアの執務室に脱獄犯をかくまった罪で、カヴァラドッシが連行されてくる。そこにトスカを呼び、隣室でカヴァラドッシを拷問し、アンジェロッティの隠れ家をトスカに白状させる。カヴァラドッシは投獄され死刑が宣告される。彼を助けるためには、トスカはスカルピアに身をまかせなければならない。一度はやむなく承諾するが、ふと目にとまったナイフでスカルピアを刺し殺す。殺害する寸前にスカルピアに書かせた通行証明書を手に、トスカはカヴァラドッシを救いに行く。死の覚悟を決めたカヴァラドッシのもとにトスカがやってくる。(トスカが身をまかせることと引き換えに、スカルピアの命令で)空砲による偽の銃殺刑を装うことになっており、その後2人で逃走しようという段取り。ところが、実際には実弾が込められており(つまり、スカルピアの命令は偽だったのだ)、トスカの目の前でカヴァラドッシは本当に処刑されてしまう。絶望したトスカは、「おお、スカルピア、神の御前で!(Avanti a Dio !)」と叫び城の屋上から身を投げる。歴史的背景)フランス革命の後、ナポレオンは1798年にローマを占領し「ローマ共和国」を建国した。(この時、ナポレオンはカトリックの総本山ヴァティカンなどにあった美術品を数多くフランスに持ち去っている)。しかし、同年11月には、ナポリ王国軍がローマを攻撃しフランス勢力を追い出した。フランス革命の「自由・平等」の精神を広まったために、「トスカ」に登場するアンジェロッティやカヴァラドッシのように「フランス支配下のローマ共和国」を支持するイタリア人もいた(ヴォルテール主義者=啓蒙思想主義者:理性と自由を掲げて封建制、専制政治、信教に対する不寛容に反対する)。一方、フランス革命は「反キリスト教」的でもあったため、カトリック教会のお膝元イタリアでは、これに抵抗するスカルピアらの勢力もまた強かった(スカルピア男爵は実在の人物で、この歌劇では悪者だが、実際には良い統治を行っていたらしい)。「トスカ」の時代設定は1800年6月で、イタリア勢力がローマを回復しており、フランス=ナポレオン支持派はローマでは弾圧されていたわけである。「トスカ」第2幕に「ナポレオン敗北の知らせは誤りで、ナポレオンが大勝利を収めている」との知らせが舞い込んでくるシーンがあるが、このマレンゴの戦いは、6月14日、ナポレオンが北イタリアでオーストリア軍を破った戦いである。そして、1808年に再びフランス軍がローマに侵入し、以後1815年のナポレオン没落までローマはその支配下にあった。「トスカ」で登場する主要な人物のうち、女性はトスカのみです。また、主要人物の4人(トスカ、カヴァラドッシ、スカルピア、アンジェロッティ)はすべて死亡してしまいます。つまり完全な悲劇なわけです。4人はそれぞれに思惑や謀(はかりごと)を有していたのですが、ことごとく裏目に出て失敗してしまいます。物事が成就するには「天の時、地の利、人の和」が必要とされますが、皆これらのうちどれかを欠いていたわけです。また、スカルピアが劇中で「目的は二つ」と言います。彼の目的とは、トスカをものにし、ヴォルテール主義者を根絶やしにすることです。他方で、トスカの目的は恋人の救出とスカルピアの魔手から逃れること、カヴァラドッシの目的は愛と革命です。彼らは、これら二つの目的を同時に成就させようとするのですが、性格や手法がこれを邪魔します。スカルピオは強引な手法と策を弄しすぎて、トスカは嫉妬心が強すぎて、カヴァラドッシは優柔不断な性格が災いして。「二兎を追うもの、一兎をもえず」といったところでしょうか。プッチーニはオスティナートと称される音楽技法を多用しているそうです。オスチィナートとは、ひとつのモチーフ(動機)が予想以上に長く繰り返されることを指しますが、ベートーヴェンが有名ですね。ベートーヴェンの5番第一楽章は、たったひとつのモチーフで構成されています。ただし、プッチーニの場合は、モチーフのリズムとメロディ、和声進行はいじりませんが、調性をめくるめく展開させて繰り返しており、真のオスティナートとは異なるようですが。「トスカ」は2時間もありますが、使われているモチーフは、10個にすぎないとのことです。そうそう、アンドリュー・ロイド・ウェバーの「オペラ座の怪人」もオスティナートが多用されているようで、さらに、メロディラインが「トスカ」にそっくりな部分も数箇所あります(考えすぎか?)。
Apr 17, 2005
コメント(0)
-
「ホラー映画」の構造(二)
『ホラー映画の魅力 ファンダメンタル・ホラー宣言』より、(観客を恐怖させるための)「小中理論」の紹介を続けます。2)脚本描写 ・イコンの活用 説明する台詞なしで、視覚的に伝える怖さというものは 強い。音響にも同様の効果がある。 ・霊能者をヒロイックに扱ってはならない 説明不能な不条理にこそ恐怖が宿るのであり、霊能者の 解説をその物語の真相としてしまうと、作品は「因縁話」 に堕してしまうことになる。あくまで、解釈の一つに留 めておくべきである。 ・ショッカー場面はアリバイに 観客を「びっくりさせる」ショッカー場面はもっとも印 象に残るものであるが、これはほんとうの怖さとは違う ものである。ただ、ショッカー場面は、「あなたが見て いるのはホラー映画なのだ。怖がっていいのだ」という メタ・メッセージとして伝わり、観客を自動的に「怖が るモード」へと移行させる手段として有効である。 ・幽霊の「見た目」はありえない これから襲われようとしている人物を幽霊の「見た目」 (=幽霊からみた主観描写、Point of View; POV)から 描写するのは安易な手法であり、観客を「はらはら、ど きどき」させる効果はあるであろうが、ほんとうの怖さ とは別の感覚である。 ・幽霊はどう見えたら怖いのか 半透明や青い照明を当てたような古典的な幽霊は怖くな い。ぼうっとボケたような不確かな見え方のほうが怖い。 また、不自然な場所に現れる幽霊や、不自然な大きさの 幽霊は怖い。 ・幽霊ナメはやってはならない 幽霊の背中越し(撮影用語でナメると言う)に犠牲とな る人物を映すアングルはホラー映画ではおなじみである が、これは恐怖する人物を客観視するアングルであり、 いわば「醒めた」観点といえる。人物の主観的な恐怖感 こそが観客に伝播されるべきものであり、幽霊ナメは やってはならないショットである。 ・幽霊はしゃべらない 人情話的な怪談ならいざ知らず、実話怪談では幽霊に会 話させるべきではない。幽霊が話すと肉体感が強調され、 「役者が演じている幽霊」にしか見えなくなるケースが 多い。ただし、幽霊の声そのものは、怖さの有効な要素 である。 ・恐怖する人間の描写こそが観客の恐怖を生みだす 観客に恐怖を感じさせるには、その場面に登場する人物 が感じている恐怖を伝播させることが最大の決め手にな る。ファンダメンタルな恐怖を生成する最大の要素とは、 そこに映し出されている人物のリアクションなのだ。 ・つまり、ほんとうに怖いのは幽霊しかないのだ ホラー映画でほんとうに怖いのは、怪物、吸血鬼、ゾンビ、 SF的な存在などではない。ほんとうに怖いという感覚を醸 し出す怪異は、結局のところ幽霊しかないのだ。小中氏は、以上のような「小中理論」=「恐怖の方程式」を示した後、最後を以下のようにしめくくっています。==============よく、サイコ・ホラー物を評すときに、「一番怖いのは人間の心だ」などとしたり顔で書かれているのを目にするが、私は問いたい。「あなたは、本当に怖いものに遭ったことがあるのか」と。暴力的なまでに不条理な存在と対峙したことがあるのかと。私はホラーを愛している。怪物が登場する作品は大好きであるし、私自身も作り、またこれからも作りたいと願っている。コメディ仕立てのホラーだって愛している作品もあるし、ホラーの様式ということについても、まだまだこれから掘り下げていくべき事柄だろう。だが、観客が座席から尻をずらしていくような、映画を観た後でも、悪夢にうなされるような本当の恐怖を与え得るホラーは、幽霊しかないのだ。==============この辺、私と小中氏とでは考え方が異なります。小中氏が「本当に怖い」と思っているのは幽霊”そのもの”ですが、私の場合はちょっと違う。私は過去の日記で以下のように述べています。===============我々は、作品を通してなにか「ほんとうのもの」を感じ取る。だからこそ、それが表面的な感情としては「快」を呼び起すものであれ、「不快」を呼び起こすものであれ、感動を覚えるのである、と。・その「ほんとうのもの」というのは、結局は、自分(鑑賞者)自身の「心のありよう」のことではないでしょうか? 芸術作品の鑑賞のように主観が大いに関わってくる場合は特にそうなのですが、物事の「見え方や感じ方」を規定するものは、結局はその人の「心のありよう」だろうと思います。例えば自分の心がはずんでいる時は、普段はなんでもないものも心地よく感じられることがありますし、逆に心が沈んでいる時は、なにを見ても不愉快に思えるものです。恋愛なんかの経験を思い出していただければ、このことがよく納得できると思います。つまり、自分が物事から受け取る印象というものは、自分自身の「心のありよう」の”逆投影”である、といえると思います。ですから、芸術作品は、鑑賞者自身の「心のありよう」を映しだす鏡のようなものということになり、さらに、優れた芸術とは、それを通して人の「心のありよう」をより深く、またはより明瞭にえぐりだすものということになります。そうしますと、芸術作品によって覚える「感動」の正体とは、「快」や「不快」の感情の生起をきっかけとして、我々が普段認識しえていなかった(認識することを拒んでいた)自分自身の「心のありよう」を新たに自覚する、そのことによって生じる「驚き」の感覚のことである、ということになるかと思います。つまり、「ああ、自分はこういうモノに魅力を感じる人間だったのか!」とか、「自分は本当はこういうモノを欲していたのだ!」とかいった感覚ですね。この現象は、作品を通した「自己了解」、もう一歩すすんで「自己確認」といっていいとも思います。自分の「心のありよう」というものを知る場合、自分自身で自己の心を把握するという努力(「内省」)が必要不可欠なのですが、純粋に「内省」するだけではなかなか窺い知ることができないものです。何故なら、自分の心を把握しうるのは、自分自身の心に他ならないのですから。例えば、人の心がある観念によって強固に捕らわれている時は、その観念によってその人の物事の見方(=心の作用)がいかに歪められていようとも、自分自身ではなかなか認識できるものではありません。典型例が、カルト宗教による洗脳でしょう。ですから、脱洗脳において重要なことは、心が抱いている絶対的な観念をいかに相対化するか、ということになります。普段は認識しえない、または種々の因習や慣習や道徳によって縛られていて認識することが拒まれている、「心のありよう(の深層)」=「ほんとうのもの」というもの、それを垣間見させてくれるのが芸術作品というものではないでしょうか?===============上は芸術一般について述べたものですが、当然ホラー映画にも通じるものがあります。普段は気づかないが自分自身の心のうちに潜んでいる残酷さを垣間見させてくれるホラー映画こそが、ほんとうに怖い作品である、私はそう考えているわけです。つまり、「一番怖いのは人間の心だ」と考えている者とは、私に他ならないことになるわけです。次回は、私と小中氏の違いをもう少し深く掘り下げて考察してみます。
Apr 15, 2005
コメント(2)
-
「ホラー映画」の構造(一)
最近、どういうわけか、日本のホラー映画を立て続けに観ております。刺激が欲しくなったのかもしれません(笑)。作品は『呪怨』、『リング(らせん)』、『ほんとうにあった怖い話』、『学校の怪談』などのシリーズです。「ホラー(horror)」には、”恐怖”または”嫌悪”という日本語があてはめられています。・”嫌悪”としてのホラー人に嫌悪感をもよおさせるような映画の作製は、現在の技術からするとそう難しいことではありません。典型が血のスプラッター描写です。あと、死体や化け物をリアルに・残虐に描くとか、画面を暗くしておいて突然または背後からモンスターや殺人鬼を登場させるとか。”嫌悪”とは、不快や驚きといった人間のエモーショナルな反応のことですし、人間の生存が脅かされる事態(死が示唆される状況、現実をコントロールできない状況)において生じる心的反応といってもよいでしょう。・”恐怖”としてのホラーほんとうの”恐怖”とはどのようなものでしょうか。私は、(人間の生存が脅かされる状況において生じる)”嫌悪”との対比でいえば、「自らの生存本能(欲望)に基づいて他人に残虐行為をなす者をみる時に湧き上がってくる”恐怖”感」と考えています。そして、その残虐行為をなす者が理性的であればあるほど、”恐怖”の度合いも増してゆくことが多いです。この”恐怖”の典型が「ホロコースト」におけるナチの行為です(逆に、ユダヤ人からすると、民族浄化はこの上もない”嫌悪”の対象となるわけです)。理性的であるということは、それだけリアルであるわけで、現実にいつ自分がそれと同様の残虐行為をなすか分からない、という恐れが生じるわけで、これはほんとうに怖いですね。ほんとうの”恐怖”を感じさせる映画について、小中千昭氏(ホラー、SF、ファンタジー系の脚本家)が面白い分析(「小中理論」)を披露してくれています。上で示した私の考えとは多少の違いがありますが。以下は、小中氏の『ホラー映画の魅力 ファンダメンタル・ホラー宣言』(岩波アクティブ新書)より。ほんとうに怖い映画(ファンダメンタル・ホラー映画)が備えている要件とは、「小中理論」によれば以下のようなものになります。1)脚本構造 ・恐怖とは段取りである 観客が恐怖を感じるまでには、段階的な情報を提示して いく必要がある。 ・主人公に感情移入をさせる必要はない 怖い映画では、観客は登場人物に対して感情移入してい るのではなく、自分とは異なる人間の、自分のそれとは 異なる人生を擬似体験している。 ・因縁話は少しも怖くない オチ、すなわち何故幽霊が現れ脅かしたのか、という理 由が明らかになるや、その幽霊は非常に「頭の悪い」存 在になってしまう。 恐怖とは不条理に宿るものなのだ! ・文学は忌まわしい ストーリーの流れを分断したり、展開を無機的に消化し たりして、いま観ている作品は普通のドラマではない、 というサインを強制的に送る。 ・情報の統一は恐ろしい 一人の人物だけの体験であるよりも、「幽霊を見てしま う」といった体験が伝染病のように多くの人に伝わって いくことが、恐怖を構造化してゆく。 ・登場人物を物語内で殺さない 実話ホラーに限った話であるが、主人公(報告者、語り 部)を物語中で殺してはならない。この後、「2) 脚本描写」の項が続くのですが、今日は時間が遅いので明日にでも。
Apr 13, 2005
コメント(5)
-
簡単な近況報告
2、3日、東京出張のついでに楽しんできましたので、ご報告を。・騎馬オペラ「ジンガロ」、日本公演『ルンタ』「ジンガロ」は、バルタバスという”正体不明”の人物が率いるフランスの舞台芸術集団。特徴は、なんといっても「馬」です。直径30mほどの特設スタジオで馬、ダンス、音楽、光、曲芸がミックスされて演出される表現は、なかなか夢幻的です。フランス流の舞台芸術といいますと、ケベック(カナダ)を発祥の地とする「シルク・ド・ソレイユ」が有名ですが、夢幻的な雰囲気という点で「ジンガロ」とよく似ています。「ジンガロ」とは放浪の民、「ルンタ」とはチベット語で風の馬という意味だそうです。『ルンタ』にはいろいろと見どころ・聴きどころがありましたが、本物のチベット僧侶たちによる読経にまず圧倒されました。なんでも、ダライ・ラマの許可をえて、彼らは『ルンタ』に参加しているとのことです。読経とはいいましても、殆ど民族音楽と言っていい趣があり、低音主体で単調にも思えるリズムで構成されているのですが、魂が揺さぶられる想いがしました。馬の演技は、サーカスっぽい曲芸などもありましたが、繊細なテクニックが素晴らしかった。馬の”横歩き”はかなり高度な技術のはずですが多彩なステップで難なくこなしていました。それらの動きは、一部、バレエのステップにも取り入れられてるのではないでしょうか。5分間ほどBKGなしで男性がひとりでダンスするシーンがあるのですが、これまた独特の雰囲気といいますか迫力がありました。私の席は前から3列目(プレミアム席)だったのですが、値段は24000円で、さすがにこれは高い!A席は8000円ですが、会場が狭いうえに、席は急勾配で配置されていますから、A席でも十分に堪能できるでしょう。席に下手にお金をかけるなら、DVDを買うお金にまわしたほうがいいかもしれません。・マシュー・ボーンの『白鳥の湖』バレエ「白鳥の湖」といえば、チュチュをまとった可憐な乙女たちが白鳥として舞うシーンが最大の見どころですが、この作品では上半身裸の男性たちがどこかユーモラスにそれを披露してくれます。もちろん、そのシーンは「ゲイ」の象徴となっているわけです。ストーリーは、高貴な身分に生れついた男性が、社会との葛藤のうちにあって自身の本性をなかなかつかめずに苦悩しながらも、最後は「ゲイ」という安住の地を見出すというものです。シーン構成や色彩感覚は繊細かつ官能的で、かつエロティシズムに溢れ、私としてはディレク・ジャーマンを連想してしまいました。遊び心やユーモア感覚は満載で、ダンスに手抜きはなく、殆どの方が楽しめるでしょう。・「ルーブル美術館展 19世紀フランス絵画 新古典主義からロマン主義へ」(横浜美術館)ルーブル美術館が所蔵する絵画のうち、新古典主義からロマン主義へ、そして写実主義の誕生に至るまでの73点を借り受けて展示しているものです。メインはアングルで「泉」、「トルコ風呂」、「スフィンクスの謎を解くオウディプス」、ジェラールの「プシュケとアモル」、ピコの「アモールとプシュケ」、ドラクロワの「怒りのメディア」等。題材としては神話、そして政治性の強いものが目立ちました。テクニックとしては、人間の顔の表情が精緻に描かれているものが多かったです。・「東京写真美術館」「Ten Views-スペイン現代写真家10人展」、「小林伸一郎写真展 BUILDING THE CHANEL LUMIÈRE TOWER」、「写真はものの見方をどのように変えてきたか 第一部 誕生」。・観逃したもの「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール展」「光と闇」、すなわち闇を一本の蝋燭が照らし出すような明暗のコントラストを特徴とする画家ですね。私が好きな画家の一人です。写真では散々観ていますが、実物ではあのコントラストはどのように描かれているのか興味津々だったのですが都合により断念。 「 瀧口修造:夢の漂流物 同時代・前衛美術家たちの贈物 1950s-1970s 」 瀧口修造はシュルレアリスムを日本に紹介した詩人かつ評論家で、彼が収集した作品を中心とした展示です。これも是非観たかったのですが、彼の収集作品は「富山県立近代美術館」に多数ありますから、今度でそこへ出かけることとしましょう。
Apr 12, 2005
コメント(6)
-
ホール&オーツ 金沢公演
厚生年金会館で、ダリル・ホール&ジョン・オーツのライブ・コンサートを観てきました。オープニング曲は「Man Eater」で、イントロが流れホール&オーツが登場するや大歓声とともに文字どおり会場は総立ちとなり、ほとんどそのままの状態でエンディング。ずっと踊っている方もおり、かなりの熱気でした。私も、前の席の客が立つものですから、仕方なく立って観ましたが、2時間そのままというのはちと辛かった。しかも、隣の席の女性が頭上で大きく手を振りながら手拍子をとるのですが、その手が私の眼前10cmぐらいのところをチラチラして、鬱陶しいことこの上なかった(笑)。かつては、ロック・コンサートというと、会場内の通路に鉄格子を置いて遮断したり(ステージ下に多人数で駆け寄って死人が出たのが原因で、そのせいで楽しみにしていたリッチー・ブラックモア&レインボウの金沢コンサートが中止になったこともありました)、席から立っただけで会場整理係りが飛んできて叱りつけたりと、それは息苦しいものがありました。しかし、今夜のコンサートは席から立つことはもとより、ラストでステージ下へ駆けつけて握手を求めるのもまったく自由でした。まさに隔世の感がありましたね。ホール&オーツはいろいろヒット曲を飛ばしてきましたが(アメレカで6曲のNo.1ヒット、16曲のトップ10)、私が好きなのはなんと言っても美しく切ない「Wait for me」、次いで軽快で乾いた「Private Eyes」ですね。他に印象に残ったのが「I can dream about you」。この曲は映画『ストリート・オブ・ファイヤー』(1984年、ウォルター・ヒル監督)の挿入歌として有名でしょう。オリジナルは、Dan Hartmanですね。いずれの曲も不思議な雰囲気がするのですが、ベースはソウルとR&Bです。それに、名プロデューサーであるデヴィット・フォスターのセンスや手腕が加わり、80年代に大ブレークするわけです。残念だったのは、厚生年金会館の音響が悪かったせいか、それとも機材がしょぼかったせか、音質がいまひとつだったこと。アップテンポの曲、ベースやドラムスがぎんぎんな曲は、ダリル・ホールの歌声がまったく聴き取れませんでした。まあ、ロック・コンサートは、だいだいあんなものですけど。
Mar 10, 2005
コメント(4)
-
『オペラ座の怪人』:芸術論的に
闇の世界に生きながら、魅惑的な芸術を創造し続けてきたファントム・・・・・。フェントム自身の相貌は、俗世間から隔離されざるをえないほど醜いもので、芸術的な<真>や<美>とは対極的なものでした。そういう彼にとって、芸術は以下のように二つの意味を有していたのです。・芸術は唯一、ファントムの不遇の意識や世間に対する反感を、積極的な生の目標(<真>や<美>)へと転化させうる可能性を秘めたものでした。つまり、芸術によってのみ、彼は(相貌の醜さに起因する)”生き難さ”を打ち消し、彼の惨めな境遇に抗うことができたわけです。・芸術は、<真>や<美>への予感を通じて、人間の生をもっと充実させたいという欲望を誘惑しますが(エロス・イメージ)、そのことは”生き難さ”の源泉ともなるのです。何故なら、生の充実は他者との交わりを抜きにしては達成できませんが、ファントムにはその交わりこそが欠けていたのですから。このように、ファントムにとっての芸術とは、自分を拒絶する世間への反感の表徴である一方、世間において自己実現と遂げたいという欲望の具現化でもあったわけです。彼にとって芸術とは、そういうアンビバレントな存在だったのです。たぶん、この傾向は、多くの実在の芸術家にもあてはまるのではないかと思います。クリスティーヌは、最愛の父が臨終の間際で約束してくれた「私が死んだら『音楽の天使』を授けてあげる」との言葉を信じて、その父の愛の印を必死で探すあまり、オペラ座でどこからともなく響くファントムの声を聞いた時、彼こそが「音楽の天使」だと思い込むにいたります。実際、ファントムが授けてくれる音楽は素晴らしいものがあったのでした。ファントムとクリスティーヌ・・・・どちらも心に傷を抱えた孤独な存在でしたが、芸術を通じて心を通い合わせることができたのでした。ファントムのほうは、クリティーヌとの交わりを通じて自己実現の可能性を求め、クリスティーヌのほうは、ファントムからの教授を通じて父の愛を実感するというかたちで。クリスティーヌとファントムが小舟にのり、オペラ座の地下に隠されたファントムの棲家へと向かうシーン。ここは前半のクライマックスで、クリスティーヌはファントムの魅力に完全に取り込まれていきますが、この時、両者にある転機が訪れます。クリスティ-ヌは純真な少女から魅惑的で情熱的なソプラノ歌手へと変貌し、ファントムは表情に自信が溢れ将来への手応えをしっかり掴んだかのようであります。そして、クリスティーヌは、戸惑いながらも「闇の世界(=狂気)」に幻惑され、そこへ踏み込みことの心地よさを覚え、他方で、ファントムは、クリスティーヌという存在が、自分の生を充実させるための触媒ではなく、彼女を愛すること自体が生の目的であると気づいたのでした。つまり、二人がファントムの棲家へと向かったこの行為は、両者にとってある種のイニシエーションとしての意味合いがあったわけです。そういう経験を共有した二人の前に割って入ってきたのが、クリスティーヌの幼馴染の青年ラウルでした。ラウルは、世間での成功者であり、礼儀をわきまえ、考え方に邪なところがなく、また女性を一目ぼれさせる美貌の持ち主でもあり、ファントムとは正反対の存在なわけです。そして、クリスティーヌは、この両者の間、すなわち恋愛と慈愛という感情の間で翻弄されることになります。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ここで、「ファントム=クリスティーヌ=ラウル」という”三角関係”について、芸術論的に考察してみましょう。まずは、過去の私の投稿から引用します。*************理性的、道徳的、美的等々のあらゆる制約や要請を無視・破壊し(意味性を徹底的に剥奪し)、「書く主体」を放棄する時、あとに何が残るのか? ダダは、この問いに対する解答を、根源的に追い求めたわけです。このような極端かつ極限的な手法は、破壊対象(理性、近代)に対して極めつけのダメージを与えるとともに、逆に、でてくる「解答」によってはダダ自らの限界を逆説的に露呈してしまうことにもなりえます。シュルレアリスムの場合、例えば自動記述は、外観としての私(意識、、理性、主体)が、内面に潜むもうひとりの私(無意識、感性、客体)によってとって替わられる「夢の書き取り」でしたが、どちらの「私」も私の一部にはちがいありません。ダダの場合、バラバラに解体された私が、偶然の産物と化したオブジェのなかで、根絶されます。自動記述が、深層の「私」を映す鏡であろうとしたとすれば、ダダの詩は、私の屍体置場でした(ダダのイメージには、常に、そういう不気味さがつきまといます)。人間存在の深部に下降して、そこから(人間の生を充実させる)何ものかを現実界へ持ち帰ろうと試みるシュルレアリスム。下降したまま、虚無の世界に留まり、そこに安住の地を求めようとするダダ。両者の根源的な違いは、この辺にありそうです。「シュルレアリスム:ダダとの違い」 *************ダダの魅力的な世界は、例えば、以下のような作品で窺うことができます。*************・・・・その日から、昼の内容は夜の大壜に注ぎこまれるだろう。この世界では、からだに燐を塗られた犬たちが放たれ、歩行者の足もとを照らす。人びとは悲しみという感情を失い、恐怖と残虐が新しい喜びとなる。ガソリンを腹いっぱい飲まされた犬の群れが、火を吐きながら、美しい裸の女たちに襲いかかる。老人たちは巨大な木製の本のページの間にはさまれて、押し花のように干涸びる。前部に鋼鉄の長い針をつけた自動車が、映画館のまえで列をつくっている連中を串刺しにする。そして、人びとは歩道にならべられた大箱にはいって、交代で夢のない眠りをねむる。死の恐怖が姿を消し、絶対的な忘却が第一の掟となったこの社会では、人間の生命はもはやなんの価値もない・・・・・「シュルレアリスム:アヴァンギャルド(5) 」**************私がここで主張したいのは、「ファントム=クリスティーヌ=ラウル」という関係は「ダダ=シュルレアリスム=リアリズム」と相似形をなす、ということです。・自らがつくりだした闇の世界にクリスティーヌとともに永住しようとするファントムは、「下降したまま、虚無の世界に留まり、そこに安住の地を求めようとするダダ」に他なりません。・狂気(=父へのコンプレックスが嵩じた幻想世界)から逃れるために、一度は狂気の世界(=ファントムの闇の世界、ダダ)へと舞い下りた後、ラウルの援けによって現実界へと復帰したクリスティーヌは、「人間存在の深部に下降して、そこから(人間の生を充実させる)何ものかを現実界へ持ち帰ろうと試みるシュルレアリスム」とピッタリ一致します。・もちろん、美貌のラウルは、経済的・社会的成功者で思考は理性的。つまり、俗世間的存在の典型でありリアリズムの権化ともいってよい存在なわけです。『オペラ座の怪人』からは、芸術論的にこういう意味を読み取ることができるという次第です。
Mar 9, 2005
コメント(2)
-

『オペラ座の怪人』:サン・シストの聖母
今回は、絵画や写真を楽しんでください。上は、ラファエロの「サン・シストの聖母」という作品です。ラファエロといえば、その洗練された感性や優美さが比類なきものとされ、聖母像の第一人者とされている画家ですね。この聖母は、ラファエロのどの聖母よりも威厳に満ちたものとされおり、全身立位像で描かれているのはこの作品のみです。画面左の老シクストゥスの手にみられる短縮法や、二等辺三角形に配置された人物像は、ルネサンス当時の技術の特徴がよくあらわれています。先の日記で書いたように、私は、『オペラ座の怪人』を観終わった時、「クリスティーヌ=聖母」とのイメージを抱いたのですが、そのイメージに相応しい絵画として真っ先に思い浮かんだのが、この「サン・シストの聖母」です。中央の聖母はもちろんクリスティーヌで、腕に抱かれているキリストはファントム、左の老シクストゥスは老ラウル、右の聖女バルバラはマダム・ジリーに対応するといった具合に。ちなみに、下方のおちゃめな二人の天使はカルロッタとメグ・ジリーに対応するともいえますか。下は、ファントム(ジェラルド・バトラー)ですが、ドラキュラの役をはっただけあって高貴な神秘性が漂いますが、どこか幼さが残る風貌です。さらにその下は、アンドリュー・ロイド=ウェーバーの元妻で映画『オペラ座の怪人』のクリスティーヌ役を当初に予定されてたサラ・ブライトマンです。彼女も、なかなかミステリアスな風貌です。
Mar 7, 2005
コメント(6)
-

『オペラ座の怪人』:ラブストーリーとして
この映画は、映像と音楽どちらも素晴らしいのですが、さらに両者の融合という点でも優れています。冒頭はさびれた感じのモノクロ映像ではじまり、そしてラストもモノクロ映像に戻るのですが、これには意味があります(後述)。1919年パリ、朽ちかけたパリ・オペラ座(別名オペラ・ガルニエ)で開催されたオークションのシーンからはじまりますが、そこである老人と老女が猿のオモチャを競い合い、結局は老人が落札します。老人はクリスティ-ヌをめぐってファントムと争ったラウル、老女はファントムの庇護者だったマダム・ジリーです。次に、錆ついた大きなシャンデリアがオークションにかけられるシーンへと続きます。豪華なシャンデリアは、パリ・オペラ座のそして時代の象徴です。1870年代のパリというのは、プロシアとの戦争がはじまる直前、ある種の黄金時代、イノセントな時代だったのです。対して、1919年は、第一次世界大戦によってヨーロッパが荒廃していた時期ですね。怒りに燃えたファントムがシャンデリアを落下させるシーンはこの映画のハイライトのひとつですが、高さ5メートル、幅4メートル、重さ2.2トン、二万個以上のスワロフスキー・クリスタルのフルカット・シャンデリアペンダントなるものが飾られた、殆ど実物に等しいものが用いられており、価値は130万ドルを下らないとのことです。このシャンデリアを実際に落下させて火災のシーンが撮影されたのでした。実は、1896年、オペラ座のシャンデリアが劇の上映中に火災で燃えて、破片が客席に落下して死者・負傷者がでるという惨事があったのですが、ガストン・ルルーはこの事故をヒントにして『オペラ座の怪人』の執筆にとりかかったといわれています。映画は、オークションの係員によってシャンデリアが吊るされた瞬間、時代は1870年へと遡ってゆきます。この時代遡行シーンが実に素晴らしく、シュマッカー監督の才能、センス、テクニック、そして情熱が存分に発揮され凝縮されたものとなっています。オープニング・ミュージックたる『OVERTURE』がパイプオルガンとフルオーケストラで荘厳かつ重厚に鳴り響くなか、色彩はモノクロから鮮明なカラーへと変化し、設備の埃が取り払われ、(文字どおり)豪華絢爛たるオペラ座がその全容を露にします。そして、オペラ座の内部、人々が活き活きと動き回る楽屋、リハーサルホール、衣装室、小道具製作室などが小気味よいテンポで次々と写し出されていきます。衣装は、素人にも”懲っている”ことが一目で分かるリアルなもので、ヴィスコンティやスコセッシに匹敵するものがありますね。衣装を担当したのは、映画『エリザベス』や『ハムレット』でアカデミー賞にノミネートされたことがある舞台衣装デザイナーのアレキサンドラ・バーンで、300着の手縫いの衣装を製作し、ヨーロッパ中の衣装室から2000着の衣装を集め修正を施しています。彼女がもっとも参考にしたのが、ヴィスコンティの『山猫』でした。音楽と映像を幻想的な手法で融合しうる手腕を見込まれて監督に抜擢されただけあって、シュマッカーが織りなすこのシーンに観客はいきなり圧倒されることになります。映画『アマデウス』の冒頭も、狂気のサリエリ、舞踏シーン、雪、馬車、精神病院が「交響曲25番ト短調 第1楽章」とよくマッチしていましたが、シュマッカーはそれを凌いでいる印象ですね。そして、雑多な人物が登場し迷路のような施設内部が描かれてゆきますが、実際オペラ座には絶頂期には750人もがそこで暮らし働いていたのです(映画では、クリスティーヌやジリーもそういう設定です)。総面積は11000平方メートルもあり、内部には無数の小部屋や迷路のような通路、地下には芝居に使う馬のための小屋、踊り子たちの部屋、舞台道具を置く施設がありました。オペラ座は、1861年、ナポレオン三世の命によりパリ大改造の目玉として計画され、シャルル・ガルニエの設計案が採用され建築がはじまりました。ところが掘削をはじめてみると、敷地の地下に大きな水脈があることが判明し、巨大な蒸気ポンプで水抜きしようとしましたが失敗しています。そこで、地下に巨大な水槽(湖)と川をつくって、その上に建物を建てるという方式に切りかえました。それでも、大量の水をくみだしたり、地下水の浸潤防止に二重三重の隔壁を設けたりと、さながら迷宮のような地下構造となってしまったのでした。ファントムのような人間が一人や二人、地下に潜伏しようと思えばたやすくできそうな雰囲気ですね。この雰囲気には、ガストン・ルルーも大いに刺激されたことでしょう。オペラ座に限らず、巨大なで複雑な施設には同様の雰囲気が漂います。私の田舎にあった旧い家ですらそうでした(屋根裏や土蔵などがありましたし、一度も足を踏み入れたことがない部屋がありました)。映画『ダイハード2』でも、空港施設内で密かに生活している男が登場して、マクレーン刑事(ブルース・ウィルス)を援けていましたが。 ◇ ◇ ◇ ◇映画の大きな構成は上述したように、冒頭とラストは1919年でモノクロ、その間が1870年でカラーのシーンです。メインである1870年の出来事は、現在(1919年)の年老いたラウルによる回想という体裁をとっているわけです。ただ、面白いのは、通常の映画では回想やフラッシュバックがモノクロで、現在がカラーであることが多いのですが、この作品ではその色の関係が転倒してる点です。このことは、何を意味するのでしょうか? 二つ考えられます。 ・一つは、この映画は、ラウルの記憶のうちにある物語がメインであるということ。そして、この物語に登場するファントムというのは、ラウル自身の、従って我々観客自身のうちに潜む「醜悪」を具現化した存在ではないのか、ということ。 ・もう一つは、モノクロの味気ない現在にはもはやファントムもクリスティーヌもいませんが、カラーで豊穣に彩られた過去は両者を中心とした世界であったということ。つまり、ラウルからすると、それほどまでに、ファントムとクリスティーヌは眩しく輝く存在だったということです。先述したように、この映画は、ホラーまたは探偵小説であったルルーの小説を、ウェバーがラブ・ストーリーとしてリメイクしたものです。ディズニーの『美女と野獣』にも通じるものがありますが、社会から見捨てられ、追放され、ゲテモノとして扱われ、そして心を打ち砕かれた人間(ファントム)が、彼のことを思いやり、理解し、ともに痛みを分かち合ってくれる仲間を求めて苦悩する、そういう彼に我々は共感を覚えるわけです。そのような彼に愛情の念を抱いたのがクリスティーヌですが、彼女の愛は男女間の恋愛感情というより、聖母マリア的な愛ですね。つまり、父親を求めてファントムに健気に接近していったクリスティーヌでしたが、ファントムはそういう彼女の態度のうちに慈愛に満ちた母親の姿を見出したわけです。ラブストーリーとしての『オペラ座の怪人』については、他の人がいろいろと語ってくれていますし、これ以上は私の守備範囲を逸脱しかねませんので、このぐらいにしておきます。ラブストーリー以外に、別の物語をこの作品から読み込むことができると思います。それは、「芸術論」と「差別論」の二つの物語です。次回からは、私がこの映画を観て解釈した、この二つの物語について述べることとします・・・・たぶん、週明けになると思いますが。
Mar 3, 2005
コメント(4)
-

『オペラ座の怪人』(序)
2004年、アメリカ、ガストン・ルルー原作、アンドリュー・ロイド・ウェバー製作、ジョエル・シュマッカー監督、ジェラルド・バトラー、エミー・ロッサム。『オペラ座の怪人』の原作者はガストン・ルルー(パリ、1868~1927年)で、1910年の出版です。ルルーといえば、『オペラ座の怪人』とならんで有名なのが『黄色い部屋の謎』(1907年)という推理小説です。『黄色い部屋の謎』は、密室ものの推理小説としていまだに最高傑作との誉れが高い作品です。私も大学生の頃推理小説にかぶれていましたから当然のごとく読んだのですが、確かにこのトリックは素晴らしいの一言で、これを超える密室ものは今後絶対に出現しえない、といっても過言ではない内容です。当時は、『モルグ街の殺人』のエドガー・アラン・ポオ、ホームズ・シリーズのコナン・ドイル、エミール・ガポリオによる『ルルージュ殺人事件』(世界最初の長編探偵小説)、アルセーヌ・ルパン・シリーズのモーリス・ルブランなど、古典的推理小説が全盛を迎えていたのでした。それらにならって、ルルーも『黄色い部屋の謎』を執筆したのでしょう(「イリュストラシオン」という週間新聞に連載)。ちなみに、推理小説の”型”はこの時期に既に完成されています。後に登場するトリックの殆どが『モルグ街の殺人』(世界最初の推理小説)で使われていますし、典型的な探偵(シャーロック・ホームズ)も悪役(アルセーヌ・ルパン)も、そして完全なる密室トリック(『黄色い部屋の謎』)も既に登場しているわけです。原作小説『オペラ座の怪人』は、そういう人物(推理小説家たるガストン・ルルー)がそういう時代(推理小説全盛時代)に執筆した作品ですから、ホラーとはいえ推理・探偵小説としての趣が濃い内容です。ただ、ルルーの作品は、『黄色い部屋の謎』こそ今でも絶賛されていますが、他の作品はそう評価されてきたわけではありません。現在、彼の作品は『黄色い部屋の謎』、『オペラ座の怪人』の他に『黒衣婦人の香り』が読めます。『黒衣夫人の香り』は、『黄色い部屋の謎』の続編と称すべき推理小説ですが、出来は秀逸とはいえません。小説『オペラ座の怪人』自体は、B級の推理小説(探偵・ホラー)で、トリックやストーリーは目を見張るほどではありません。ルルーは、ミステリ以外に、ファンタジー、歴史、政治、SF、ユーモア、スリラーとあらゆるジャンルの小説に挑戦しており、多才な人物だったようですが、それを反映してか『オペラ座の怪人』の内容は雑多な印象です(つまり、まとまりがあるとは言い難い内容です)。『オペラ座の怪人』は1930年に、『新青年』という推理小説誌(1920年創刊、江戸川乱歩、横溝正史、高木彬光らを輩出)に参加していた田中早苗によって日本で翻訳・紹介されましたが、完訳は87年に創元推理文庫から、89年にハヤカワ・ミステリ文庫から、00年に角川文庫から出ています。私としては、角川の長島良三訳が現代的な日本語でお勧めですね。『オペラ座の怪人』を有名にしたのは、1925年のユニバーサル映画『オペラの怪人』のヒットです。その後、B級ホラーやコメディとして、数多くリメイクされてきました。そして、1986年、『エピータ』、『キャッツ』、『ジーザス・クリスト・スーパースター』などのミュージカル作品で有名なアンドリュー=ロイド・ウェバーが、本格的なラブ・ストーリーとして、美しいロック調の音楽と豪華な舞台美術を用いてミュージカル化しました。この作品も大ヒットし、日本の「四季」等、世界18ケ国で上演され、現在までの観客総動員数は約8000万人にのぼり、『キャッツ』を抜いてギネスブックの記録を塗りかえる見込みですし、オリジナルアルバム(マイケル・クロフォード、サラ・ブライトマン)は現在までに4000万枚を売り上げており、キャストアルバムとしては史上最高のセールスを記録しています。小説『オペラ座の怪人』のラストでは、怪人の遺体が発見されて、その指にはクリスティーヌの指輪がはめられていたのですが、この情景に触発されてウェバーは、この作品は本来的にラブストーリーではないかと思い至り、ミュージカル製作のきっかけになったとのことです。88年にウェーバーは最初の映画化を計画しています。監督は、映画『ロスト・ボーイ』で印象的な音楽の使い方を披露したジョエル・シュマッカーを予定していました。しかしながら、ミュージカル『オペラ座の怪人』の初演でクリスティーヌ役を演じ映画の出演も予定されていた、ウェバーの妻にして彼のミューズ(芸術の女神)こと歌手・女優のサラ・ブライトンとの離婚により、ウェバーは映画化を一旦は断念します。その後、ウェバーは何度もシュマッカーに映画化の協力を求めましたが、シュマッカーのほうは『バットマン・フォーエバー』、『評決のとき』、『フォーリング・ダウン』、『フォーン・ブース』などの作品を手がけるのに忙しかったのでした。それが、02年12月、ようやく両者の思惑とタイミングが一致し(映画『シカゴ』の成功が大きかった)、本映画のプロジェクトが再開されたのでした。ウェーバーもそうですが、シュマッカーにしても、12日間で撮影した『フォーン・ブース』のような軽快な作品の直後に、本作品のような重厚、華美なものを見事に仕上げてしまうのですから、才能や技術、そして意欲は並々ならぬものがありますね。
Mar 1, 2005
コメント(4)
-
『ドリーム・キャッチャー』
2003年、アメリカ、スティーヴン・キング原作、ローレンス・カスダン監督、モーガン・フリーマン。スティーヴン・キング原作でモーガン・フリーマンと、相当に期待をもたせる作品です。ストーリー:メイン州の小さな町に住む4人の少年、ジョンジー、ヘンリー、ピート、ビーバーはある日、風変わりな少年ダディッツを助ける。4人はその時、ダディッツから彼の持っている不思議な力(テレパシーや予知能力)を分け与えられ、以後その秘密を共有することで強い絆が結ばれる。20年後、大人になった4人にとってそのパワーは今では重荷として彼らにのしかかっていた。そんなある時、ジョンジーが交通事故で重症を負うが、奇跡的に一命を取り留める。やがて4人は北方の森にある狩猟小屋で再会を果たす。それは彼らにとって毎年恒例の楽しいイベントのはずだったが…。 冒頭、青を基調とした秀逸なCGではじまり、これがなかなか奇麗です。この基調としての青は、映画の最後まで維持されます。ただ、この映画、私としては見るべきものは、これのみですね。残念ながら。上で紹介したストーリーは前半部分のみですが、なかなかミステリアスな雰囲気が漂い、後半の展開に期待をもたせはします。後半は、邪悪な地球外生命体(エイリアン)が登場し、それを軍の特殊部隊が退治してゆく、といった展開になります。エイリアンは映像的になかなか良くできていますし、特殊部隊の軍用ヘリコプターが登場してダイナミックな戦闘シーンを披露してくれもします。しかし、いまどきB級SF映画でも、こういった陳腐な内容にしないのではないのか、と思わせるほど内容は薄いです。イメージ・テクニックは決して悪くないのですが、プロットが安易で進行は平板です。どこにも驚きはありませんし、退屈ですらあります。これは、SFモノとしては致命的ですね。『エイリアン』、『遊星からの物体X』、『サイン』といった作品の影響が濃い、といいますか、それらを組み合わせただけで、新鮮なものは殆どないと言っても過言ではありません。これで、135分はきついでしょうね。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ドリーム・キャッチャー:昔、インディアンの人々は、棚の下にある大きな蜘蛛の巣を発見し、夢や人生におけるすべてのこ事はその蜘蛛の巣を通過してくるものと考えた。良い夢(事)は夜の空気と共に巣を通過し眠っている者のもとに届けられ、悪い夢(事)は巣に絡め取られて夜明けと共に太陽の光を浴び消えてしまうと信じていたのだ。そこで、信仰の対象として蜘蛛の巣をかたちどり、身近な素材で思いを込めて作ったのがドリームキャッチャーだ。今日まで「悪運を払って幸運を呼び、夢を実現する」お守りとして、伝統的に伝えられている。ドリーム・キャッチャーは、一つの輪を中心に四つの輪が取り囲む。中心の輪はダディッツ、四つの輪は四人の仲間を象徴している。ドリーム・キャッチャーが悪夢を取り払うように、四人は協力してエイリアンを退治し、人類の悪夢を払拭する。==============数日、ネット不在となります。
Feb 17, 2005
コメント(10)
-
『呪怨』
2003年、日本、清水崇監督。かつてヴィデオでヒットし、いまハリウッドでリメイクされ公開されている人気ホラー作品です。私は、『呪怨』シリーズは、本日のテレビではじめて観たのですが、正直いってあまり”怖さ”は感じませんでした。本作品はストーリーが淡白で、したがって”空気”でもって恐怖心を湧き上がらせる、そういう雰囲気は希薄なのです。幽霊・超自然といたアイテム、物陰や背後といった空間設定、血やメイクによる視覚効果、不気味な音などによって”怖さ”が演出されています。また、冒頭から「くるぞ、くるぞ」と思わせておいて、なんのケレン味もなく「はい、どうぞ」という具合に怨霊が登場します。これは、かつての楳図かずお氏などの「少女漫画」ホラー、最近では「トイレの花子」さんやRPG、そういったノリの作品で、心の底から怖さが湧きあがってくるというより、心地よく鳥肌がたつといった雰囲気の仕上がりになっています(これはこれである種の”快感”を覚えますが)。ホラーやオカルトの怖さを、私は二種類に分けて考えています。一つは、精神的な怖さで、もう一つは、肉体的な怖さです。精神的な怖さというのは、人間心理の深層に潜んでいる残酷さ、脆弱さ、怨恨などを抉り出してみせて、それらを観客自身に投影させることによって(観客自身の心にもああいった面が潜在しているのか、といった具合に)共感的に恐怖させものです。肉体的な怖さは、暴行するとか傷つけるとか、身体的に死を示唆して恐怖させるものです。精神的な怖さは”空気”や”雰囲気”によって心理的に、肉体的な怖さは”血”や”死体”によって視覚的に表現されるのが一般的です。それで、『呪怨』ですが、題名からすると、この作品の本来のテーマは精神的な怖さの表現にあるのではないでしょうか。ところが、この映画では、肉体的な恐怖の手法が多用されており、どうもテーマと手法との間でバランスを欠いているようですね。この原作(小説)やヴィデオ版を見て既にストーリーの細部やテーマを理解している人、または、肉低的・視覚的なシーンのみで十分にホラー映画を堪能できる人にとっては、面白い作品なのでしょうけど、私のようにそうでない人にとっては物足りなさが残る作品でしょうね。
Feb 16, 2005
コメント(8)
-
『半落ち』
2004年、日本、横山秀夫原作、佐々部清監督、寺尾聡。*************元捜査一課の警部で現在は警察学校の教職に就く梶聡一郎(寺尾聡)が、妻・啓子を殺害したと自首してきた。夫妻は7年前に白血病で息子をうしっているのだが、アルツハイマー病に苦しむ妻から「息子を覚えているうちに死にたい。殺して!」と半狂乱で嘆願され、止むに止まれずに首を絞めたという。だが謎が残った。梶が出頭したのは事件の3日後だった。空白の2日間に何があったのか?梶は頑なに黙秘、そして否認を続ける・・・・・。**************2002年のミステリー・ランキングを総なめにし直木賞の候補にもあがった、横山秀夫氏の傑作小説を映画化したもので、俳優陣は豪華です。俳優陣が豪華なのには理由があります。刑事、検事、新聞記者、弁護士、裁判官たちが、各々の立場から梶の行為の謎を自問自答し、解答を見出そうとするわけですが、立場が違えば、与えられる情報の質や内容もいろいろで、解釈も異なり、彼ら独自の苦悩を深いものとして表現する演技力が必要とされたからです。梶が関係者たちに投げかけた最大の謎は「高潔な人格の梶が、なぜ、自殺を思いとどまったのか?」ですが、裏を返せば「子供も妻も失った梶は、何のために生きているのか?」ということになります。この謎を解くために、皆、自分自身の内面に向かって問いかけることになります。「自分は、何のために生きているのか?」と。しかし、皆、「自分のため」という、ある意味消極的な答えしか思い浮かんできません。「自分のため」という答えが”悪い”と言いたいのではありません。ただ、単に「自分のため」という理由のみでは、自殺を思いとどまって敢えて生き恥をさらしている梶の行動が説明できないのです。なぜなら、梶という人物は、エゴイズムとは最も縁遠い人間なのですから。生きることには確かに価値があります。しかし、すべてを失って、生きることが無意味となった、否、それどころか(妻を殺害したのに、自分は自殺を思いとどまって)生きのびていること自体、恥辱に他ならない・・・・・あの高潔な梶が、なぜこの屈辱に耐えているのか?登場人部も観客も、終始この謎に惑わされることになります。
Feb 15, 2005
コメント(2)
-

『シェルタリング・スカイ』
1990年、イギリス、ベルナルド・ベルトルッチ監督、デブラ・ウィンガー、ジョン・マルコヴィッチ。ベルトルッチ監督の作品を観るたびに感心するのは、彼の映像は、”光と闇”の配置・コントラストが秀逸かつ絶妙であるということ。また、ダンス・シーンも、それぞれの作品で個性的で印象的なものが多いですね。 ****************終戦後まもない1947年、北アフリカ。ニューヨークからやって来た作曲家のポート・モレスビー(ジョン・マルコヴィッチ)とその妻で劇作家のキット(デブラ・ウィンガー)の目的は、単なる観光ではなかった。求めるべき夢を失なった彼らの深い喪失感を、あてどもない拡がりを持つ異国の世界で癒すためだった。その旅の道連れとなったのが、ポートの友人で上流社会に属するタナー。結婚して10年、夫との心のすれ違いを感じるキットに、かねてより彼女に心を寄せるタナーは接近してゆく。やがて3人は次の目的地に向かうが、車で向かうポートに対して、キットとタナーは汽車で別行動をとった。ある日、ついにキットとタナーは一夜を共にするが、アフリカ奥地の風土に嫌気がさしたタナーは別の土地へ向かった。二人きりになったポートとキットは、アフリカの蒼穹の下でひとときの愛を確認しようとするが、上手くいかない。やがて、ポートは伝染病(チフス)に罹患する。キットの献身的な看護も虚しく、医者もいない砂漠の果ての町でポートは息絶えた。一人きりになったキットの旅は、しかしまだ続く。彼女は砂漠を往来するアラブ人の隊商の中に身を埋め、男と体を重ねるが、彼女の眼はもはや何ものも映し出さないかのように虚ろであった。キットは砂漠からタンジールへと連れ戻されるが、もはや彼女はもとの自分へと返ることなどできない。タナーが一瞬目を離すともはや彼女の姿はどこにもなかった。****************原作はポール・ボウルズによる同名の小説で、ポール自身この映画に出演しています。それも、冒頭とラストの同じ飲食店のシーンで。つまり、キットは、ポールに見守られてアフリカのたびに出発し、そして最後にポールの前に帰ってくるのです。このようにして、物語の円環が閉じられるのでした。映画や小説では、夫であるポートが先に死亡し残された妻が旅を続けますが、現実には作者のポールは妻に先立たれています。ですから、作品と現実は鏡像の関係にあるわけです。ポールは、先立たれた愛妻のことを想いながら、(亡くなった妻のメタファとしての)キットに作中で旅をさせていたわけです。題名の「シェルタリング・スカイ」は「守りの空」といった意味です。・では、空とは何(誰)なのか?・また、空は、誰を何から守っているのか?私は、空は死亡したポートで、空(ポート)がキットを宇宙の闇・虚構(=死)から守ってくれているのだ、と解釈しています。この映画の前半・中盤の基調は、ポートとキットは確かにお互いに愛し合っているのに、お互いに自分を見失っていて、一緒にいてもどうしても幸福になれない、という重苦しい空気にあります。ポートは、この空気をニューヨークで既に感じ取っており、それを払拭するためにアフリカの地へとやってきたのでした。ポートは思い出の地にキットと二人でやってきます。その地は、ちっぽけな人間なぞゴミぐらいにか思えなくなる雄大な場所です。ポートは、自然と融合するかのごとくその場でキットと交わり、すれ違いの愛をなんとか克服しようとしたのでした。しかし、残念ながらその試みは失敗してしまいます。タナーという”触媒”によっても、この問題は解決しません。その後、ポートは伝染病で死亡し、キットが一人で旅をするのですが、この設定は原作者ポールの実生活の鏡像になっていることは前述しました。思うにポールは、亡くなった後も常に自分を見つめ庇護してくれる妻の存在を感じながら、アフリカで生活を続けていたのではないでしょうか。その感謝の意を伝えたくとも、妻はもうこの世にはいません。ですからポールは、小説を執筆し、そのなかで逆に自分(=空)が妻を庇護することをもって、感謝の意や愛情を切なく表現したのです。現世では幸福になれない愛しあう二人。先に亡くなったほうが空に登り、護りの天使となる。そういう愛のかたちもあるのだ、と。
Feb 14, 2005
コメント(4)
-

『13(サーティーン) みんなのしあわせ』
2000年、スペイン、アレックス・デ・ラ・イグレシア監督、カルメン・マウラ主演。スペインだけでも150万人の観客を動員し、2001年ゴヤ賞3部門の受賞ほか12部門にノミネートされるなど、スペインの映画賞を総ナメにしたヒット作です。***********不動産会社の女性営業員フリア(カルメン・マウラ)は、自らが担当する豪華な物件(アパートの一室)に失業した旦那を呼び寄せてともに一晩を過ごしたが、それが全てのはじまりだった。二人がベッドでくつろごうとした瞬間、天井の穴から大量の水とゴキブリが落ちてきた。翌日、消防員が調査したところ、上の部屋に住んでいた老人が腐乱死体で発見された。フリアは、偶然拾った暗号めいた紙切れを手がかりとして、老人が隠していた3億ペセタを見つけて歓喜した。しかし、その金は、アパートの住人たちが全員で以前から狙っていたものだった。彼らは、契約を交わして一致団結して、20年もの間老人が金を持ち出さないよう交代で監視し、彼の死後、皆で金を山分けする算段をたてていたのだった。そのことを察知したフリアは恐怖し、金とともにアパートからの脱出を試みるのだが、果たして成功するだろうか?************この映画の原題は『La comunidad』で、これは「共同体」という意味だそうですが、老人の金をめぐってアパートの住民たちが結束し一種の「(利益)共同体」を形成していたことの表徴となっています。実は、フリアが担当していた物件の前の住人(エンジニア氏)は、彼らの策謀に協力することを拒んだ結果、殺されてしまっていたのです。それほどまでに、彼らは欲の皮を突っ張らせていたのでした。そういうところへ、一人の中年女性(フリア)がやってきて金を独り占めしようとしているのですから、住民たちが黙っているはずがありません。そして、フリアと住民たちの間で、文字通り血みどろの死闘が演じられることになります。・・・・・とまあ、こう書きますとシリアスなサスペンス映画のように思えるかもしれませんが、実は遊び心満載のブラック・コメディまたはパロディ作品です。例えば、オープニングは『007』を彷彿させます。アパートを舞台として新参者が怪しげな「共同体」の思惑に巻き込まれるというプロットで、小物としてナイフや包丁が何度も登場しますが、これは『ローズマリーの赤ちゃん』や『デリカテッセン』のパロですね。冒頭でダース・ベーダーに仮装した男が現れますが、もちろん『スター・ウォーズ』。一人のオバさんが、『マトリックス』風アクションで大ジャンプを見せてくれたりします。終盤の追跡劇はヒッチコック風(『北北西に進路をとれ』、『めまい』)です。コミカルで気丈夫なフリア(カルメン・マウラ)から漂う雰囲気は『キカ』を連想させます。この映画でもう一つ特徴的な点は、表現の露骨さです。老人の腐乱死体、血やスプラッター、バイオレンス・シーンは必要以上にリアルです。通常、女性の主人公は、残虐な仕打ちを受けてもバイオレントな描写は抑えられるものですが、この映画ではその辺、容赦がありません。女同士の格闘も手加減なしですね。また、フリアにしても住人たちにしても、金に対するエゴイスティックな執着を隠そうともせず、殆ど開き直っています。「共同体」とは称しながら、住人たちはフリアと一対一になりますと、即座に二人で金を持って(つまり「共同体」を裏切って)一緒に逃亡しようと持ちかけます。さらに、フリアは、いい年をした女性なのですが、若い男性に対する欲望を隠そうとはしません。そのためには、自分の夫を死んだことにしてしまうくらいです。単なるブラック・コメディまたはパロディ作品にとどめず、血、暴力、エゴ、欲望、性といった暗部を露骨にかつ開けっぴろげに表現したことが、スペイン人気質に受けた要因のひとつではないでしょうか。それともうひとつ、円熟した役者が揃っているだけあって、演技はどれも素晴らしいものがあります。この映画は、「コメディ・パロ」と「露骨」との間で微妙なバランスを保つことによって独特の雰囲気を醸し出しているのですが、大根役者が演じてしまっては退屈なドタバタ劇に終わってしまったことでしょうね。
Feb 11, 2005
コメント(2)
-
『女と女と井戸の中(The Well)』
1997年、オーストラリア、サマンサ・ラング監督、パメラ・ラーブ主演。出演する役者や監督をはじめとして、製作陣の殆どが女性でしめられており、また作品内容も女性の解放をテーマとした、フェミニズム映画です。*****************足が不自由な中年女性へスター(パメラ・ラーブ)は長い間父親とふたりで暮していたが、そこへ家政婦として施設育ちの若い娘キャスリンがやってきた。質素で単調な田舎暮らしに嫌気がさして飛び出したキャスリンを追いかけて、なだめて戻るように説得するへスター。キャスリンとへスターのぎこちない共同生活が始まるが、やがてふたりの間には親密な感情が生まれる。父親が亡くなりへスターが遺産を相続すると、ふたりは思うままに金を使い、ぜいたくな生活を送るようになる。そのお金が底をつくと、ふたりは農場を売って大金をえて、外れにある小屋に移り住む。その家の庭には古い井戸があった。ふたりは将来の欧州旅行を約束しながら、お金を小屋の中に隠し田園暮らしを再開する。この時点では、お互いに必要とするものを与えあうふたりの関係は、バランス良く保たれていた。ある夜、酒に酔って車を運転していたキャスリンが、山の小道で見知らぬ男を轢いてしまった。怯えるキャスリンに代わってヘスターは、男の死体を庭の井戸に捨てる。翌日、偶然立ち寄った近所の人から、最近空巣が出るという話を聞き、もしやと思い確かめてみると、隠しておいた大金が跡形もなく無くなってしまっていた。ふたりは、昨晩轢き殺してしまったあの男が空巣だったに違いない、だからなくなったお金は死体と一緒に井戸の底にあるのだ、と思い至る。ヘスターは、キャスリンに井戸の中に入ってお金を取ってくるように言うが、キャスリンは人を轢き殺してしまったことに怯え、さらにヘスターの命令にも強い嫌悪を覚える。キャスリンはやがて「井戸の中の男はまだ生きており、自分は井戸の食べ物を与えてきた。彼は私を愛しているといい、私も彼を愛している」と言い出した。ヘスターは、男は死んでいたと説得しようとするが、キャスリンは聞く耳を持たない。かみ合わない言い争いを続けるうちに、ふたりが心に秘めていた確執が明らかにされていく・・・・・。外は嵐を前にして雨が降り続いている。涸れていた井戸の水位は雨で上昇し始める。彼は本当に生きているのか? 消えた大金はどこにあるのか? *****************原題は『The Well』ですが、井戸は二人の女性の関係のメタファとなっています。人は、井戸から水を汲み上げ、その水によって渇きを癒します。足が不自由で、少女時代のヨーロッパ旅行を唯一の華やいだ思い出として、あとは父を扶けて家を切り盛りすること以外になんの変化もみられない生活を当然のこととして甘受していた、クラシック音楽好きの中年女性ヘクスター。施設育ちで自由奔放、テレビやディスコやロック音楽がなければ生きていけない、キャピキャピの現代娘のキャスリン。タイプも性格もまったく違うこの二人の女性は、お互いに自らの生を充実させるためのアイテムを相手から汲み上げてきたわけです。中年女性のヘスターはキャスリンから自由への予感や恋を得、対してキャスリンはヘスターからお金や愛情を得てきました。つまり、両者とも相手と交わることを通じて、人生の新たな可能性(=エロス性)を相手(=井戸)から汲み上げていたのでした。かくのごとく、庭の井戸は、二人の良好な関係性のメタファとなっていたわけです。そこへ一人の男が登場します。酒に酔って車を運転していたキャスリンに轢かれ死亡(?)した男です。そして、その男の死体は、こともあろうに、二人の良好な関係を象徴する庭の井戸に投げ込まれてしまったのでした。このことによって、二人の良好だった関係に徐々に亀裂が生じてゆくことになります。なくなったお金は井戸のなかの男(空巣)が持っているとされ、また、その男は生きており、キャスリンはお互いに愛し合っていると述べるようになります。このことは、それまでのキャスリンはお金や愛情を(井戸たる)ヘスターから汲み取っていましたが、井戸に男が投げ込まれた結果、お金や愛情の源(井戸)がヘスターから井戸の男へと移行してしまった、ということを意味しています。恋人の片方に別の恋人ができて破局をむかえる物語・・・・こう書いてしまうとあまりに俗っぽいものになりますが、この作品の射程はもっと広いものがあります。どう広いのかというと、ひとつにはフェミニズム、もうひとつには「欠如」という要素がみられることです。フェミニズムについてですが、ヘスターとキャスリンの間を仲介するとともに破局に導いたものとして、「父」が重要な要素をなしています。ヘスターは、父権的な支配・被支配という関係のもと、キャスリンにお金と庇護的愛情というこれまた父性的なアイテムを与え続けていたわけです。ヘスターとキャスリンの関係は結局は破綻するわけですが、このように欺瞞的な父性に基いた(女二人の)人間関係の脆さを、この作品は告発しているといえます。「欠如」についてですが、足が不自由なヘスターは父親と二人っきりでずっと自閉的な生活を送ってきたわけで、彼女の生活には自由や恋愛というものが欠如していました。対して、施設育ちのキャスリンには、経済的基盤や家族愛というものが欠如していました。二人はお互いの欠如を補いあい埋め合わせあっていたのですが、このような消極的なモチーフに基いた関係では、将来的にそう長続きはしない、とこの作品は訴えているようです。つまり、このような関係からは一時的な癒しの効果は期待できるでしょうが、生を充実させるために本当に必要な環境は、欠如の埋め合わせではなく新たな創造性を喚起しあえるような人間関係なのであって、それが無理なら早晩破局をむかえるしかないのだ、と。◇ ◇ ◇ ◇ この映画では「足」が各場面で強調されています。足が不自由で杖がなければ歩けないヘスターの姿に対して、キャスリンの健康的な足は必要以上に露出され、ヘスターの不自由ぶりを表徴するとともに、二人の性的関係(レズ)のメタファともなっていますね。実は、この映画ではラブシーンらしきものは一切登場しません。他にもブーツ、髪の毛、鍵などが象徴的に用いられています。また、ブリーチ・バイパスと称される、青を基調とした映像、さらには、いかにも女性中心の作品らしい繊細な映像やアクションが印象的でした。
Feb 9, 2005
コメント(6)
-
続・『ノン、あるいは支配の空しい栄光』
”俺たちは、いったい何のために戦っているのか?”アフリカ植民地のゲリラを鎮圧するために派遣された部隊のカブリタ少尉が、軍用トラックで揺られながらこう呟きます。対して、まわりの仲間たちが思い思いに「戦う理由」をあげていきます。法律、愛国心、国益、家族・・・・しかし、本土防衛のためならいざ知らず、植民地の独立運動を弾圧するという行為を正当化しうる理由はついぞ提示されません。そもそも、この時代(第二次世界大戦後)に植民地を保持すること自体がポルトガルにとって良いことなのか悪いことなのか、という問いにさえ誰も答えが出せないのです。良いことといえば、植民地支配によってアフリカの部族同士が争うことを止めポルトガルに反抗し一致団結できたこと、また、これら部族の団結にあたって公用語(統一語)としてのポルトガル語が大いに役立ったこと、というブラック・ジョークのようなものしか兵士たちは思いつきません。カブリタ少尉は、やがてポルトガルの四つの敗北の歴史を語っていきます。1) ローマ時代、現在のポルトガルにほぼ一致する地域を支配したいたのはルシタニア族でした。紀元前2世紀、カルタゴを打ち破ったローマ軍は、その勢いをかってイベリア半島に攻め込みますが、ルシタニア族は指導者ヴィリアの活躍でこれを退けます。しかし、紀元前139年、ローマ軍に内通した身内の裏切りにあってヴィリアは暗殺されてしまいました。結局、紀元前後にポルトガルはローマに征服されます。2) 15世紀後半、イベリア半島はカスティリャ、アラゴン、ポルトガルの三つの王国が割拠しており、それぞれの王国が統一の機会をねらっていました。ポルトガル国王アフォンソ5世は、カスティリャの王位継承問題に介入してスペイン進出をねらいますが、トロの戦いに敗れて野望を打ち砕かれます。後を継いだジョアン2世は、政略結婚によって統一王国を目指しますが、息子のアフォンソ王子がカスティリャの王女の結婚した直後に落馬して絶命してしまいます。こうして統一王国の夢はついえたのでした。3) 16世紀、虚栄心が強く狂信的な気質をもつセバスチャン王は、イスラム征伐に固執し時代遅れの十字軍戦争を計画します。1578年、モロッコのお家騒動に便乗して北アフリカに上陸するも、アルカセル・キビルで歴史的な敗北をきっします。国王自身が行方不明となり、世継ぎがいなかったためアヴィス王朝は途絶え、ポルトガルは以後60年間スペインに併合されてしまいます。4) この映画の”いま”の舞台となっている20世紀後半。第二次大戦後の1960年は「アフリカの年」と称され、イギリス領やフランス領だった地域の多くは独立を果たしました。しかし,ポルトガルは国連の勧告にもかかわらず一切の独立を認めませんでした。1960年代後半から,ギニア=ビサウ、アンゴラ、モザンビークで独立運動が激化しましたが、サラザール独裁政権は多額の軍事費を投じ,勝つ見込みのない植民地戦争を継続させたのでした。戦争が長期化するにつれ、1974年4月25日リスボンで軍がクーデタをおこし,放送局や政府の諸機関を占領しました。首謀者は3月半ばにカエターノに解任された前参謀総長ゴメス将軍と同次長スピノラ将軍で、スピノラを中心に臨時政府が発足し,言論の自由・労働組合の許可・自由選挙の実施が宣言されるとともに(「カーネーション革命」)、ポルトガル植民地帝国も滅びたのでした。映画の舞台は「4)」の途中ですので、「歴史を語る」というより、歴史の反復性と運命にこの部隊の兵士たちが翻弄されながら破滅的な結末へとむかう「実体験」ということになります。つまり、カプリタ少尉をはじめとして、多くの兵士がゲリラとの戦闘で負傷し命を落とすことになります。しかし、この映画に終始漂う閉塞感は何でしょうか。もちろん、植民地支配は現代ではもはや肯定的に語ることはできませんので、植民地と密接不可分の関係にあるポルトガル近現代史を語ろうとすると、どうしても暗いものなってしまうという事情はあります。それに加えて、その暗さが、個人の内面にまで重く影をおとしており、それがえも言われぬ閉塞感の原因となっているようです。兵士たちは国家のために戦いますが、必ずしもその戦い自体の意義を理解しているわけでも、賛同しているわけでもありません。しかし、彼らは家族や生活を抱えているわけで、それを犠牲にしてまで政府の命令に逆らうわけにはいきません。この「生活の糧を国家に依存しているが故に、国家の命令には逆らえない」という構図がもたらす絶望的状況、それがもっとも明らかになるのが戦争という事態なのです。映画中、この絶望的状況をなんとか糊塗しようと、兵士たちは愛国心、正義、国益などを口にします。しかし、このような(絶望の)「飼いならし」は、遠い場所でデスクにふんぞり返って命令をだすのみの連中にとっては意味があるかもしれませんが、戦場という外面的にも内面的にも厳しい現実に直面している兵士にとっては偽善にしかうつらず、なんの説得力もないのです。なぜなら、彼らにとっての愛国心、正義、国益なぞ、戦闘相手のそれらと真っ向から対立するもの、つまり他者(戦闘相手)によって簡単に相対化されうるものなのですから。民主主義国家といえども戦争を行わざるをえない状況が出来しえますが、その時本当に怖いのは、この絶望感に捉われてニヒルに陥ることかもしれません。独裁国家や軍事主義国家のほうが、戦争の悪を国家に転嫁できるので、まだ気が楽ともいえます。この出口のない絶望感を、オリヴェイラ監督は「ノン」と称しているわけです。”NONとは恐ろしい言葉だ。それには表もなく裏もない。どちらから読んでもNONだ。まるで自分の尾を咬む蛇のようだ。”『プラトーン』、『フルメタル・ジャケット』、『地獄の黙示録』といった新しい戦争映画の基調をなすのは、戦争というものに対するこの感覚です。
Feb 8, 2005
コメント(0)
-

『ノン、あるいは支配の空しい栄光』
1990年、ポルトガル・フランス・スペイン、マノエル・ド・オリヴェイラ監督。90歳を過ぎてもなお現役のポルトガルのオリヴェイラ監督ですが(2003年、つまりなんと95歳で『永遠の語らい』を発表しています)、『ノン、あるいは支配の空しい栄光』(以下、『ノン』と略)は1974年4月25日のポルトガルの「カーネーション革命」に触発されて製作された映画です。ポルトガルというとスペインと一緒くたにされる傾向があるかもしれませんが、ポルトガル人気質は、スペイン人に比べ穏健で、熱狂的な面は少なく、交際能力に長け、地中海沿岸の諸国民のうち最も秩序があり、洗練されているとのことです。国民の90%がカトリックで、比較的同質的な人種集団を形成し、言語・風習も地方的偏差は少ないですが、ただ、南北の二重構造(貧富の差)が顕著で、北部の生活水準が高いようです。ポルトガルの歴史で我々にポピュラーなものは、大航海時代(15-17世紀)における活躍でしょうし、ポルトガル人が種子島に着き鉄砲を伝えたのもこの頃(1543年)でした。オリヴェイラ監督といいますと、男女間や共同体における個人的または内面的な葛藤をテーマにした作品が多いですが、『ノン』はポルトガル民族・国家という集団の歴史や命運に焦点を合わせています。”満たされない愛というテーマは絶対的なものを夢想する典型的に女性的な問題である。それに対して、敗北というテーマは男性に固有な問題だ。”(オリヴェイラ)つまり、それまでの作品は、個人の「満たされない愛」という女性的な問題が主なテーマでしたが、『ノン』の場合は、民族・国家の「敗北」という男性的なテーマを扱っているというわけです。確かに、『ノン』はそれまでの作品と比べて方向性(男性的か、女性的か)こそ違います。しかし、徐々に破滅へと向かう独特のリズムや、個人の内面から事象を捉えるというナイーブな視点には大きな変化はなく、これらの点ではいつものオリヴェイラの作風を踏襲しています。オリヴィラといえば、アンゲロプロスと並んで長回しをよく用いることで有名ですが、『ノン』でも冒頭でいきなり青々と茂った樹を360度から映す長回しと、それに続いて軍用トラックの長回しが登場します。樹という悠久の生命の象徴ともいえる自然をじっくり映した後で、無機質な鉄の道具を登場させ、両者のコントラストが嫌でも強調されることになるわけです。そして、今度はトラック上の兵士たちが映し出されるのですが、そこにいるのは通常の戦争映画のような”戦闘機能としての兵士”ではなく、一人一人が苦悩し迷う人間・個人として描写されていきます。このように、「樹→軍用トラック→人間」とじっくり描いてゆく映像シークエンスは見事という他はありませんね。観客の心には、この長回しの間、いろいろな想念がよぎることになるでしょう。兵士たちは、ポルトガルの植民地のゲリラを鎮圧するためにアフリカへ派遣されてきたのですが、やがて中隊長のカプリタ少尉が「俺たちは、いったい何のために戦っているのか」とつぶやき、ポルトガルの過去の壮絶な戦いの歴史を語ってきかせます。さて、このようにして始まるポルトガルの物語ですが、、四つの敗北の歴史が紹介されます。それぞれの物語にはそれぞれに意味があり、現在のポルトガルの苦悩や閉塞感へと繋がっています。======私事で数日ネットを離れますので、残念ですが続きは週明けになります。
Feb 4, 2005
コメント(2)
-

『アギーレ 神の怒り』
1972年、ヴェルナー・ヘルツォーク監督、クラウス・キンスキー。ドン・ロペ・デ・アギーレという実在の人物と実話を基にした映画で、『地獄の黙示録』に大きな影響を与えたとされています。**************1560年、南米の征服者ピサロが率いるスペイン軍が現地人奴隷たちとともに、黄金郷エルドラドを目指してアマゾンの奥地を進んでいく。しかし、糧食がつき先へ進むことが困難となり、ピサロは40人の先遣隊を先へと送り出すこととした。先遣隊の副長はドン・ロペ・デ・アギーレ(クラウス・キンスキー)。兵士の他に分隊長ウルスアの愛人イネス、15歳になるアギーレの娘フロレス、僧侶ガスパル・デ・カルヴァハル、貴族のドン・フェルナンド・デ・グズマンも一緒だった。三隻の筏に分乗したアギーレたちはエルドラドを目指すが、飢え、病い、そして人食い人種たちの脅威にさらされながら次々と倒れていく。しかし、アギーレはあきらめない。そして、彼の言動は徐々に狂気を帯びてくる。全員が死にただ一人の生存者となった”狂人”アギーレは、筏のうえで猿たちと戯れながらむなしく自分に語りかけるのだった。「これほど偉大な反逆があるだろうか。やがて新世界のすべてを奪おう。神の怒りである俺は、神話の通り自分の娘と結婚して、地上にかつてなかった大帝国を打ちたてるぞ」 ***************ヘルツォーク監督と主演のキンスキー(ナスターシャ・キンスキーの父ですね)は、ともに映画界でも屈指のエゴイストで、その凄まじさは伝説的です。とりわけキンスキーのエゴは強烈で、奇行のエピソードには事欠かず、ヘルツォーク監督より一枚も二枚も上手のようです。ちなみに、彼は、寺山修司監督の『上海異人娼館〈チャイナ・ドール〉』にも出演していますね。この映画の撮影中もキンスキーは、乱闘シーンで重い刀をふりまわしてエキストラに重傷を負わせたり、ジャングルで延々と続く撮影に飽き飽きして帰ると言い出したり。対して、ヘルツォーク監督は銃をつきつけて、「お前が帰るというのなら、お前を殺して俺も死ぬ」などとわたり合っています。キンスキーが”地”のままで荒れ狂い、それをヘルツォーク監督が無理やり映像に押し込め、その両者の激突から生まれたのがこの映画で、「ニュー・ジャーマン・シネマ」の金字塔的作品とも称されています。ただ、この両者のキレぶりもさることながら、この映画の真の魅力は表現の芸術的な素晴らしさにこそあります。まず、映像は褐色や濃厚な色彩を多用していおり、詩的かつ官能的な近代ヨーロッパ絵画を連想させるシーンが満載です。人物はもとより、自然にしても動物にしても、画面の隅々までスキというものがまったくない構成で、役者の衣装やメイクも、エクストラにいたるまで手抜きというものをまったく感じさせませんね。音楽はポポル・ヴーが担当しており、夢幻的なシンセサイザーの音色が全編にわたって流れます。映画の冒頭、霧のアンデス山脈の峠に連なるスペイン兵や現地人たちの姿を遠景ショットで撮ったシーンから、ヴーの音楽とも相まって、観客は否応なく幻想的な雰囲気に引き込まれることになるでしょう。これはもう、一大叙事詩または歌劇であって、ヴァグナーの世界の再現と言っても過言ではないのではないでしょうか。そうなると、ラストで孤立して狂気を顕わにするアギーレは、「超人」を目指しながら狂気に陥ったニーチェのメタファにも思えてきます。作品のテーマやストーリー性はともかく、映像や音楽としては完璧といってよい出来の作品です。
Feb 1, 2005
コメント(7)
-

『 L.S.D. (LOVE,SEX & DRUG)』
1996年、フランス・ポルトガル・オランダ、ヨランド・ゾーベルマン監督。日常の空しさにかられた若い女性ローラが、ドラッグを体験し元ボクサーのエミールに恋をするという物語です。フランスの大都市の郊外で、人生の意味や目的を失った若い男女たちが「どん底」の生活にあえぎドラッグに逃避しながらも、なんとかその閉塞的な状況から脱出しようとするわけですが、脱出すなわち自由の象徴が、ドラッグを絶つこととボクシングの試合に出て借金を返すことです。画面は全体的に暗く、状況設定といい『ポンヌフの恋人』を彷彿させるものがあります。もっとも、『ポンヌフの恋人』は最後(結末)でこけましたが。LSDという題名からも分るように、表現手法は「ドラッグ・カルチャー」(こういうカルチャーが存在するならばの話ですが)的です。サイケデリックな色彩の意味不明の模様で幕を開け、ドラッグ・パーティへのシーンへと連続します。映像や全編に流れる曲はなかなか官能的で、「トリップ」の雰囲気をよく表現しているのではないかと思います。女性監督らしく情緒的・感性的な展開で、「ドラッグ・カルチャー」作品にしては厭味や嫌悪を感じさせず、心地よい雰囲気の作品に仕上がっています。とりわけラストの拳闘シーンは秀逸ですね。面白いのは、ゾーベルマン監督は、一方で「ドラッグ・カルチャー」を魅力的に描きながら、他方でドラッグに溺れた自堕落な生活からの脱出(=自由の獲得)を根本テーマとしていることです。実際、エミールやローラは、この二つの世界・局面の接点に立ちながらなんとか<自分>を取り戻していくわけですが。また、若者の堕落の原因を社会のせいにして糾弾するといった「左翼」的な視点から描くのではなく(ですから、そういた作品のお決まりである、矛盾や偽善に満ちた社会や崩壊した家庭といったものは登場しません)、あくまで社会の底辺であえぐ彼らの目線に立ち、愛情を注ぐように彼ら生活ぶりを描いていきます。たぶん、ゾーベルマン監督の実体験が基になっているのでしょう。「ドラッグ・カルチャー」作品にしては肩の力を抜いて素直に鑑賞できる、監督のセンスが光っている作品です。
Jan 30, 2005
コメント(0)
-

『セッション9』
2001年、アメリカ、ブラッド・アンダーソン監督。19世紀に建てられ、現在は巨大な廃墟となっているダンバース州立精神病院。丘の上にそびえたつ赤レンガのアメリカン・ゴシック調のこの建物は、当時もっとも素晴らしい建物と賞賛され、(精神病患者がこんな立派な施設で治療してもらえることの皮肉もこめて)付近の住民からは「キャッスル(宮殿)」とも呼ばれていた。しかし、ロボトミー手術や数々のショック療法を施された精神病患者たちの忌まわしい記憶が宿る場所でもある。廃墟と化したこの建物が公共施設として改修されることになり、アスベスト除去のため5人の作業員がやってきた。作業を進めるうちに、鬱屈した男たちの心に封印されていた狂気が静かに覚醒しはじめる・・・・・。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ダンバース州立精神病院は実在します。そして、この映画は、その廃墟と化した病院において実際に撮影されたのです。この病院は、1874年から78年の4年をかけて、マサチューセッツ州セイラム近郊に建てられました。セイラム(サレム)といえば、17世紀の魔女裁判が有名ですが、この模様は『クルーシブル』という題名で映画化されてもいます。病院の基本構造をデザインしたのはトーマス・ストーリー・カークブライドという精神科医で、ペンシルバニア病院等で多くの患者を診てきた彼は、”カークブライド・プラン”なるものを考案し病院の構造に反映させました。このプランでは、入院患者の数は250人で、建物・部屋は、完全なプライバシーが確保され、庭はもとより農場や牧場もあり、窓からはきれいな景色が見え、日当たりがよく、換気がよいなどの条件が必須とされ、この環境下では80%の患者が治ると彼は確信していました。こうして、1878年、総床面積が70万スクエアフィートもあり、外壁にはレンガやみかげ石が、内装には樫やマホガニーがふんだんに使われ、ステンドグラスや大理石も使われた豪華な施設が誕生したのでした。このように最先端の治療法と快適な施設そして素晴らしい環境を確保した同病院は、アメリカでも屈指の精神病院との評判がたち、イギリス、ノルウェー、イタリヤ、ロシアといった外国からも患者が押し寄せてきました。こうして、1500人を収容するように設計されていた同病院はまたたくまに定員オーバーとなり、一時期は7000人もが収容される事態となり、部屋不足から、廊下の小児用寝台、屋根裏部屋、果ては暗いトンネルにまで寝泊りする者が大勢でてきました。かくして、カークブライドのプランは潰れたのでした。さらにその後、ロボトミー(この治療法はダンバース病院において確立された)、電気ショック療法、水治療といった治療法が安易かつ非人道的に用いられるようになり、ダンバース病院にとっても、また精神治療患者にとっても暗黒の時代を迎えることとなります。同病院の墓地には約300名の患者が埋葬されているとのことですが、墓石には番号しか刻まれていません。同病院は、1984年に閉鎖されました。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇評価が難しい映画ですね。ブラッド・アンダーソン監督は「この映画の成功には、ダンバーズ精神病院と言う実在の廃墟の存在が大きい」と語っています。しかし、(実際の廃墟を使って撮影を行ったという)予備知識がない状態でこの映画を観た人は、通常のセットと実際の廃墟との差を肌で感じ取ることができるでしょうか? 私は無理だと思います。私は、最初、まったく予備知識なしでこの映画を観たのですが、廃墟と称するわりには外観といい、内部といい、庭といい意外ときれいだな(つまり、あまり荒れていないな)と思ったほどです。埃やゴミが、あまりに少ないんですね。病院閉鎖前のカルテや診察時の録音テープ(これが「セッション(診察)」の意味です)、治療室、不気味な椅子や写真なんかが登場するのですが、それらは勿論セットであって、実際の廃墟であるという事実性とはあまり関係がないわけです。まあ、実際にあの病院に勤務していた人間なら、それなりの感慨がわくのでしょうけど、「実在の廃墟の存在」からは”映画の話題づくり”以上の意味は見出せませんでした。むしろ、監督や役者など製作サイドのモチベーションを高めるために役立ったのではないでしょうか。そういう意味で「この映画の成功には、ダンバーズ精神病院と言う実在の廃墟の存在が大きい」ということでしたら大いに納得ですが。俳優陣、とりわけデヴィッド・カルーソーとピーター・ミュランは、そう考えても何の違和感も生じないほど迫真の演技をみせてくれています。廃墟、精神病院の悲惨な実態、猜疑心、多重人格、殺人等と、ミステリーまたはスリラーの要素は満載ですが、あまり過激なシーンはありませんし、超自然的なアイテムが登場するわけではありません・・・・・この辺は、『シックス・センス』や『サイン』で超自然的アイテムをさらっと登場させるシャラマン監督と好対象をなし、なかなか面白いです。このようにアンダーソン監督は現実的な映像と人間心理でもって恐怖を演出していくわけですが、その恐怖の出所を探ってみますと、人間の一方的なエゴや暗部、つまり心の闇に行き着くんですね。例えば、精神病患者の楽園として構築されたダンバース病院が何故「収容所」に堕落したのかというと、あまりに多く入院希望者が殺到し、それを病院側がキャパシティを越えて安易に受け入れすぎたためです。そもそも、精神病患者を病院や座敷牢などに強制的に収容するという行為は、(一概には決め付けることはできませんが)臭い者には蓋をせよという”健常者”のエゴであるという側面は確実に存在してきました。そして極めつけが、ロボトミー、電気ショック療法、水治療といった治療法が安易に行われてきたという事実です。この「心の闇」を表徴する行為は、精神異常者に帰されるべき問題ではなく、”健常者”こそがもっぱら責めを負うべき問題です。つまり、我々”健常者”の心に潜む内なる狂気としての「心の闇」によってこそもたらされた悲惨な行為の数々、これが罪責としてじわじわと我々に迫ってくるのです。これがこの映画から感じる恐怖の正体です。この映画では、光と影のコントラストが印象的に描写されていますし、また暗所恐怖症患者も登場しますが、示唆的または象徴的な構成だと感じました。日本でも、「ロボトミー殺人事件」が起こったのは、そう遠い昔の話ではありません。
Jan 29, 2005
コメント(6)
-

『ザ・リング』
2002年、アメリカ、鈴木光司原作、ゴア・ヴァービンスキー監督、ナオミ・ワッツ。1998年に、中田秀夫監督、松嶋菜々子主演で大ヒットした映画(『リング』)をハリウッド(S.スピルバーグらが設立したドリーム・ワークス社)がかなり忠実にリメイクした作品です。なんでも、『リング』をヴィデオでみたプロデューサー氏が、その3時間後に交渉してリメイクの権利を買ったということです。このプロデューサー氏は、『リング』のどこをそんなに気にいったのでしょうか?ヴィデオという日常的にありふれたアイテムをホラーの題材とした発想の卓抜さ、日本的な井戸というアイテムの(アメリカ人にとっての)目新しさ、井戸の底からひたひたと迫り背筋を凍らせるような恐怖感、異端ゆえに迫害されて殺されながらも未だに母への愛にすがる貞子の切ない心情、日本独特の「幽霊」のスローなモーション、ラストのどんでん返し、・・・・・。以上、いろいろと理由が考えらますが、私は、論理的考察に基づいて謎が一つ一つ解かれていく、そのプロセスをこのプロデューサー氏は気に入ったのではないかと思っています。このようなプロセスは、『13日の金曜日』、『エルム街の悪夢』、『オーメン』など、アメリカのホラー映画でも見られるものですが、これらの謎解きはたぶんに暗示的であるのに対して、『リング』はより開示的・説明的なのです。そして、その開示性は、日本の『リング』に比べて、『ザ・リング』のほうが徹底しており、原作により近い内容となっています。そういった意味で、『ザ・リング』のヒロインには、人間的暖かみとともに冷静な知性を感じさせる行動的なキャラクターが要求されることになりますが、ナオミ・ワッツはそれにぴったりのキャスティングだったと思います。論理的・合理的に説明された解釈は、他のいい加減な解釈を寄せ付けません。それ故に、読者や観客の<感性>は、否応なく作者が設定した世界に同調させられることになります。『リング』にしても『ザ・リング』にしても、残酷さ、不気味さ、そして視覚や映像といったホラーに定番の恐怖アイテムはもちろん豊富ですが、それらの背後に空気のように漂って独特の雰囲気を醸し出しているのが、この、論理的・合理的に導出された「逃れようのない解釈」に基づいた<被拘束感>ではないかと思います。この辺は、TVゲーム(RPG)の影響があるのかもしれません。そうかと思うと、ラストでは、この解釈に基づいた妥当なはずの結論がひっくり返されてしまいます。このプロットは、観客を感嘆させると同時に別の恐怖を湧き起こし、それに加えて、上述した<拘束感>から観客を一気に<解放>するという二重、三重の作用を有することになります。見事なストーリーですね。最後に、問題の「ヴィデオ・テープ」の映像ですが、なかなか面白い内容です。ルイス・ブニュエルの『アンダルシアの犬』やヒッチコックの『白い恐怖』のシーン(両作品ともサルヴァドール・ダリがイメージを担当)を連想させる、シュルレアリスムのお手本のような映像です。
Jan 27, 2005
コメント(6)
-

『美しき虜』
1998年、スペイン、フェルナンド・トルエバ監督、ペネロペ・クルス主演。スペインの自然、風俗、芸術の美しさを描かせたらピカ一のトルエバ監督の作品です。その手腕は『ペル・エポック』で実証済みです。ヒロインは『ペル・エポック』にも出演していましたが、美貌のペネロペ・クルスです。彼女はスペイン女優にしては、清楚なキュートさが売り物です。確か、日本のシャンプーのCMにも出演していたと思いますが、現在はハリウッドで活躍中です。1938年、内戦の影響で映画の撮影が困難になっていたスペイン。そんな時勢、ドイツの啓蒙宣伝相ゲッベルスの提案により、スペイン・ドイツの共同制作でアンダルシアを舞台にしたミュージカル映画『夢の女』が制作されることになり、スペインの撮影隊一行(8人)は内戦下のスペインから意気揚々とヒトラー政権下のベルリンへ向かいます。主演女優のマカレナ・グラナダ(ペネロペ・クルス)に一目ぼれしたゲッペルスは、あの手この手で彼女をモノにしようと画策しますが・・・・・。スペイン内戦、ナチ、ゲッペルスとくると悲惨な内容かと思いきや、これがさにあらず。大いに笑わせてくれるドタバタ喜劇ですね。湿っぽいところは殆どありません。スペインの撮影隊として脇を固める俳優陣の演技が素晴らしいです。一人一人が個性的で、なかなか味のある演技を披露しては笑わせてくれます。また、笑いといえばゲイですが、もちろん、その辺の要素もはずしていません。破天荒かつ自由奔放な女性たちによる乾いたジョークや、すっ呆けた男性たちによるシニカルなジョーク。シリアスな状況を笑いで吹っ飛ばしてしまう、太陽のように熱いスペイン人気質には脱帽です。見所のひとつはペネロペ・クルスの歌と踊りのシーンです。彼女は高校を中退して仕事をしながらマドリード演劇学校でクラシック・バレエを学んだそうですが、酒場での妖艶なフラメンコは、そのキュートな相貌と好コントラストをなし圧巻でした。ドタバタ劇ですのでストーリー性やテーマ性は希薄ですが、スペイン流セットの芸術的な美しさやスペイン流のジョーク(アルモドバルの映画を連想させます)を楽しみたい人にはお勧めです。
Jan 26, 2005
コメント(4)
-
『アララトの聖母』(終)
****************映画作家のエドワード・サロヤン(シャルル・アズナブール)は、聖なる山アララトの麓で起きたアルメニア人虐殺の史実を映画にするため、カナダのトロントに撮影にやってきた。彼は、その虐殺で母を亡くした画家アーシル・ゴーキーに注目し、少年時代の彼を映画に登場させようと、ゴーキー研究家の美術史家アニ(アーシニー・カンジャン)に撮影の顧問を依頼した。未亡人のアニには二回の結婚歴があり、最初の夫との息子ラフィは、死んだ父親がテロリストなのか英雄なのか悩んでいた。二度目の夫の娘シリアは、ラフィと恋人関係にあり、自分の父親の事故死の原因がアニにあると考え、彼女を激しく憎んでいた。サロヤンの映画がクランク・イン。敵役のトルコ人総督には新人のアリ(トルコ系ハーフ)が抜擢された。アリには同性の恋人フィリップがいたが、そのことで、フィリップと空港関税検査官の父デイヴィッド(クリストファー・プラマー)の関係はこじれていた。撮影現場でラフィは雑用係として働いていたが、映画の内容に触発され、父の真実を知るためにアララトへと旅立っていった。やがて帰国したラフィは、空港の税関でデイヴィッドの取り調べを受けた。彼が持ち帰ったフィルム缶の中身が麻薬ではないかと疑われたのだ。ラフィはディヴィッドに、故国アルメニアへの旅で体験した喪失と回復の歴史を語り終え、解放された。そして、ラフィは、息子の身を案じて空港へと駈けつけたアニと固く抱き合うのだった。***************エゴヤン監督がこの映画を作ろうと思い立った理由は、作中で映画作家のエドワード・サロヤン(シャルル・アズナブール)が代弁しています。”分かるかね? なぜ今もこんなに胸が痛むのか。民族や土地を失ったせいではない。我々がいまも憎まれているからだ。なぜ彼ら(トルコ人)はこんなにも我々を憎むのか。なぜ今も事実(アルメニア人虐殺)を否定するのか。そして我々を憎む。より一層の憎しみで。我々の痛みとは、民族や土地が失われたことではなく、今もアルメニア人というだけで憎まれ、民族としてのアイデンティティを否定されているということの痛みだ。”アイデンティティというものは、「事実」が人間の肉体に蓄積されることによって育まれていくものです。「事実」とは、親兄弟との関係、言語、生活様式、文化、肌の色、そして共同体等における経験や歴史のことです。ところで、事実とフィクションとを(現実と夢とを、真実と虚偽とを)分け隔てるものは何でしょうか。それは反復と確かめの可能性です。ある事象を事実であると人が確信しうるのは、その事象を何度でも反復して結果の同一性を確かめることができるからです。いま目の前にリンゴがあるとします。人がそのことを事実と確信するのは、何度みてもそこに同じ色、形、臭い、肌触りの「リンゴ」があるということを確認できるから(または、そのような確認作業によって同じ結果がえられるであろうことが高い蓋然性でもって確信できるから)、さらには、他者による確認作業よっても同じ結論に達しうるから(または、そのことが高い蓋然性でもって確信できるから)に他なりません。アイデンティティの話に戻りましょう。アルメニア人、とりわけ外国に住むアルメニア人にとって、1915年のアルメニア人虐殺(強制移住)は決定的に重要な「事実」です。なぜなら、アルメニア人たる自分が何故外国に居住しているのか、という問いに対する答えがここにあるからです。つまり、アルメニア人虐殺を生きのびた祖先たちが外国に逃亡したから、という「事実」がその答えです。自分のアイデンティティの根拠としてアルメニア人を据える場合、この「事実(歴史)」は決定的に重要な意味合いを有します。エドワード・サロヤンが述べているように、母親からこの事実を物語りとして繰り返し繰り返し聞かされて、彼はアルメニア人としての自覚を育んできたのでした。しかし、この根源的な「事実」が否定されますと、アイデンティティ・クライシスすなわちニヒルが襲います。映画のなかで、アルメニア人のラフィとトルコ人(ハーフ)のアリとの間で、以下のような会話が交わされます。ラフィ: 本気で言ったんですか? 虐殺は事実じゃないと。アリ: 僕は虐殺の話を知らずに大人になった。 役のため下調べで”強制移送”について知った。 多くの人間が死んだ。第一次世界大戦だったからね。ラフィ: トルコはアルメニアと戦争していなかった。 ドイツもユダヤ人と戦争していなかった。 彼らは守られるべき市民だった。 あの場面は事実にもとづいています。 あなたが演じた総督は、アリメニア人を殲滅するために ヴァンに送り込まれた。 電報や公文書で・・・・。アリ: ”何か”が起きなかったとは言っていない。ラフィ: ”何か”?アリ: 僕はカナダ生まれだ。君もそうだろ。 ここは新しい国だ。 過去の嫌な出来事は忘れて仲良くやろう。 誰も君の家を壊さないし、家族を破滅させない。 だからシャンパンを抜いて一緒に乾杯しよう。ラフィ: ヒトラーは”ユダヤ人絶滅計画”を 将校たちにこう説明した。 ”アルメニア人絶滅を誰が覚えている。”アリ: 誰も覚えていない。今も昔も。被害民族(アルメニア人)であるラフィは、このように、加害民族(トルコ系)のアリという他者から、自らが信じる物語の事実性を共有することを拒否されてしまったわけです。ここでは、アルメニア人(ラフィ)とトルコ人(アリ)のアイデンティティが衝突しているわけですね。実は、この映画では、他にも、自らが信じる物語と「事実」との間の乖離に悩むシーンがあります。・ラフィ: 死んだ父親が単なるテロリストだったのか、それとも「自由の戦士」たる英雄だったのか。・シリア: 死んだ父親は事故だったのか、それとも母親(アニ)に追いつめられて自殺したのか。・フィリップ: 自分の息子は同性愛にはしり、堕落してしまったのではないか。・本映画のモチーフとなった、母親の手が白く塗りつぶされたアーシル・ゴーキーの絵(「芸術家と母親」)にしても、ゴーキーの絵画は未完だったのか? それとも完成後、母の手は消されたのか? という問いが提示されます。この母親の手は、虐殺とその後のトルコ側の否定によって祖国の温もりを失ったことのメタファなのか、それとも単なる未完なのか。エゴヤン監督はアルメニア人ですから虐殺の悲惨さを描いてはいますが、あくまで「劇中劇」としてそうしています。つまり、完全無欠の「事実」として押し付けるようなまねは決してしないわけです。彼は、アルメニア人虐殺とトルコによる否定いう悲観的現実から出発して、物語と「事実」との間の隙間を埋めることの困難さという、より普遍的なテーマへと射程を広げてゆきます。そして、双方の間の隙間を埋めることが極めて困難であるがゆえに、アルメニア人の心の慟哭の深さや閉塞感というものがよりいっそう伝わってくる内容となっています。最後に、引退間近い税関検査官のデビッドを演じ、息子の同性愛が理解できずに苦しんでいましたが、ラフィとの出会いによって「真実」(物語と「事実」との間の和解)を受け入れる気持が芽生えていく様子を見事に表現しきった、クリストファー・プラマーが特に印象に残りました。
Jan 25, 2005
コメント(2)
-

『アララトの聖母』(一)
2002年、カナダ、アトム・エゴヤン監督、デビッド・アルペイ、シャルル・アズナブール、アーシニー・カンジャン。アルメニア人画家アーシル・ゴーキーの絵画(「芸術家と母親」、ホイットニー美術館所蔵)をモチーフとし、自身アルメニア人であるエゴヤン監督が、「アルメニア人虐殺」の悲劇と現代の親子のエピソードを交錯させて描いた入魂の一作です。私の解釈では、本映画の根本テーマは「事実」ですね。映画の説明に入る前に、アルメニアという国と「アルメニア人虐殺」について簡単に述べておきましょう。アルメニアは古来重要な通商路,戦略的要衝に位置し,多くの資源にも恵まれていました。従って大勢力の野望を誘うことともなり、アルメニアという国の歴史は、他民族による被支配の歴史といってよく,国家を建設・維持できたのは断続的でした。宗教的には、紀元1世紀にキリスト教が伝道され,2,3世紀には,ローマ,イラン両帝国による戦争強要のなかキリスト教がひろまり, 301年、アルメニアは世界で初めてキリスト教を国教としています。アルメニア教会は,キリストの神性を重視するキリスト単性論に属する東方教会のひとつとして現在に至り,世界に独自の教会組織をもっています。5世紀初頭、メスロプ・マシュトツによってアルメニア文字が創始され,聖書のアルメニア語訳もなされ,文学が興隆し,教会建築もその基礎様式を固めるなど,5-6世紀は文学と建築が花開いた時期でした。16世紀以降,オスマン帝国とサファーヴィー朝イランの間で争奪戦が繰り返された結果,アルメニア地域は両国に分割され,「トルコ領アルメニア」「ペルシャ領アルメニア」となりました。後者は,後にロシアに割譲された結果「ロシア領アルメニア」と呼ばれることになります。 キリスト教徒の国アルメニアとイスラム教徒の国トルコは隣どうしで、トルコ(オスマン帝国)が強かった時代には、アルメニアのかなりの部分はトルコ領でした。オスマン帝国が縮小していった19世紀、極東で日本に封じられ、南進エネルギーをこの地域に集中するようになったロシアの勢力が南下してきてトルコと衝突し、1914年に起きた第一次世界大戦でアルメニアは戦場となりました。 当時、欧州の「列強」はドイツとオーストリアの同盟側と英仏露の協商側にわかれて戦争をしましたが、オスマン・トルコは同盟側に立って参戦しています。最盛期にはアジア、アフリカ、ヨーロッパにまたがる大帝国であったオスマン・トルコも、一九世紀に入ってからは領土内で諸民族が独立・分離する末期的状況にありました。トルコにとっての第一次世界大戦とは、英仏露の協商国に対して戦争するというだけでなく、自国領土内で独立しようと蜂起する他民族に対する内なる戦争でもあったのです。映画にもなった「アラビアのローレンス」が活躍するのもこの戦争で、これは愛国イギリス青年がアラブ人をオスマントルコに対して蜂起するように仕向けた話です。第一次大戦開戦後間もない1915年、春の雪解けとともにロシア軍が攻勢に転じ南進してきましたが、それに呼応してオスマントルコ領土内でアルメニア人が蜂起しました。トルコとしてみれば、背後からも攻撃され挟み撃ちされることは致命的で、現在のトルコ東部地域に居住していたアルメニア住民を強制移住させることにしました。「アルメニア人大虐殺」は、この強制移住と関連して起こったものです。強制移住は、突然、アルメニア住民に町や村ごとに住居から立ち退くように命じ、着の身着のままで南部のメソポタミヤに向かって歩かさせるというものでした。この移動中に、殺人、略奪、強姦等あるゆる残酷で凄まじい地獄絵が展開したとされ、また飢餓や病気や疲労で多数が死んでいます。これが「アルメニア人虐殺」です。この事件について、アルメニア人側は150万人から200万人が殺され、生き残ったのは60万人のみで外国に逃がれたと主張しています。対してトルコ側は、殺人、略奪、強姦といったあらゆる残酷な仕打ちがあったことは認めるものの、この強制移住の対象になったアルメニア人の数は70万人であるので、150万人という数はあまりに誇張されたもので、死亡者数はせいぜい30万人ぐらいであったと主張しています。さらに、この事件は戦時下の混乱状態で起こったことであり、「大虐殺(ジェノサイド)」の意図などなく、今まで証拠として提出された(大虐殺の)計画書もすべて偽作であった。また、アルメニア人だけが殺されたのでなく、第一次世界大戦とその直後の分離・独立戦争でトルコ側(回教徒であるトルコ人とクルド人)の戦死者は250万にも及んでおり、これは人口の18パーセントに相当した。このような時代状況を考慮してほしい、とするのがトルコ側の主張ですね。 ちょっと不思議に思えるのですが、アルメニア人は、虐殺が開始された時トルコ政府の移住の意図をほとんど疑っておらず、大半は従順に官憲の指示に従っています。戦争は開始されていましたが、戦闘は主として山間部で行われたため危機意識が薄かったせいでしょうか。徴兵を実施すると言う名目で成年男子を集合させ、多くは村落毎の集会所近辺で処刑するという方法がとられたようですが、残された女性・子供が集められ僅かな手荷物だけで騎乗の憲兵の監視もと、シリアのアレッポ周辺まで徒歩で行進させられました。この間、都市を除いてアルメニア人からの抵抗はほとんどなかったのです。これは、多数の民間人が猟銃程度で抵抗しても、組織された軍隊に勝つことは不可能であるという20世紀の現象の典型なのでしょうか。この事件を生きのびた多数のアルメニア人は、故郷を失い欧米社会で暮らすようになりましたが、彼らはトルコ人を恨み、事件について語り続けました。映画「エデンの東」のエリア・カザン監督も、フランスのシャンソン歌手シャルル・アズナブールも、このような運命にあったアルメニア人もしくはその子孫だったのです。
Jan 23, 2005
コメント(2)
-
風邪
どうも風邪をもらったようです。喉や鼻はたいしたことないのですが、手足の関節が痛むのはちょっと困る。今年の風邪の特徴らしいです。2,3日、休養しますが、皆さんの「日記」には顔を出したいとは思っています。「病人モード」で、変なことを言うかもしれませんが(笑)。
Jan 17, 2005
コメント(9)
-
『マイケル・コリンズ』
1996年、アメリカ、ニール・ジョーダン監督、リアム・ニーソン。アイルランドの独立運動の英雄、マイケル・コリンズ(1890~1922年)の半生をつづった映画です。監督のニール・ジョーダンも主演のリアム・ニーソンもアイリッシュですね。まずは、アイルランドの歴史を簡単にみてみましょう。アイルランドの地には紀元前265年ごろよりヨーロッパ大陸よりケルト人の渡来が始まり、5世紀ごろ聖パトリックらによってキリスト教が布教される。8世紀終わりごろより、ノルマン人(ヴァイキング)が侵入。1014年、アイルランド上王(High King)ブライアン・ボルーがクロンターフでヴァイキングを破り、これ以降ヴァイキングの侵入が収束する。1169年、ノルマン人の侵攻が始まる。1171年、諸豪族がイングランド王ヘンリー2世の支配下に下る。1652年、清教徒革命中、クロムウェルの遠征によって土地を没収され、事実上の植民地となる。以後、宗教上・政治上の差別も加わって,17~18世紀にはしばしば反乱が起こり,そのたびに激しい弾圧を受け、1801年、イギリス王国に併合される。1840年代後半より、ジャガイモの不作が数年続き、大飢饉となる(ジャガイモ飢饉)。この結果、多数のアイルランド人がアメリカ大陸へと移住。アイルランド問題といいますと、イギリスによる支配自体も重要ですが、アイルランド内部にも大きな問題を抱えています。その問題は、北アイルランドが、残りの26州と性質が大きく異っているということに由来します。北アイルランドの住民はカトリック教徒が約3分の1で、17世紀以降、スコットランド人の植民が行なわれ,人種的・宗教的に独自の地域を形成しました。一方で、南部の住民はケルト系で、9割がカトリック教徒です。つまり、大雑把に言うと、北はプロテスタントで、南はカトリック。どちらもキリスト教ですが、欧州の歴史をちょっと紐解けば、アイルランドに限らず両派の対立がいかに根が深いのものであるか、簡単に分かると思います。1916年、英国支配に抗してダブリンで武装蜂起。1919年、農民の武装闘争が始まる。1920年のアイルランド法、1922年のアイルランド自由国法によって、南部はアイルランド自由国が成立しイギリスの自治領となる。北部6州は、イギリスに留まる。1937年、アイルランド自由国は新憲法を制定し、国号をエールと改称。1938年、イギリスが独立を承認し、イギリス連邦内の共和国となる。 自由国は、第二次大戦では中立を維持。1949年憲法を改正し、国号をアイルランド共和国に改め、英連邦から離脱して、ようやく完全な独立国となった。↓でも分かりやすい歴史が紹介されています。http://www5.ocn.ne.jp/~kanebon/bstkitaireland.htmかくして、南部の独立がなった今、アイルランド問題とは、北アイルランドの帰属を争う「”北”アイルランド問題」を意味することになります。この問題をめぐって現在二つ立場が対立しています。 ・ユニオニスト(合同主義者)、ロイヤリスト(王室主義者) 北部は英国経済に守られ続けるべきだとする立場。英国は王国だから、王室派ということになります。 ・ナショナリスト(国民主義・国家主義)、リパブリカン(共和主義者) アイルランド全域の独立を目指すという民族派。英国の王国を否定しますから、王政に反対の共和主義派です。また、分裂状態は英国によってつくられたのだから、英国議会と、南北アイルランド議会をも認めません。シン・フェイン党やIRA(アイルランド共和軍)の主張はこちらに属します。南北の宗教的背景を基にして、現在のアイルランド問題の本質を「宗教対立」と読み解くむきもありますが、現在では「北部のユニオニストとナショナリストの対立」とするのが正確です。ですから、プロテスタント同士でも、ユニオニストはナショナリストを攻撃しますし、逆にプロテスタントでもカトリックでも、ナショナリスト同士は同一歩調をとります。このように複雑な歴史を有し、現在でも対立が続いているアイルランドですが、1910年代にアイルランド独立運動家(指導者)として活躍したのが、マイケル・コリンズです。コリンズは、有能かつユニークな人物でしたが、その特徴をあげてみます。1) ロンドン勤務のビジネスマンという経歴コリンズはビジネスマンらしく、資金調達能力に優れていました。また、几帳面でお金に細かく、領収書がないと闘士にお金を渡さなかったそうです。映画でも、数発の弾を無駄使いした闘士を叱責する場面があります。また、その所作において無駄がなく、きびきびと行動しますし、決断を下すのも迅速です。さらに、ロンドン帰りらしく洒落たセンスのファッションをまとい、ハンサムでヘアー・スタイルもいかにも紳士的です。外見的にもカリスマ性が十分だったわけですね。このような素養を背景に、コリンズは、農民中心の前近代的な形態であった抵抗勢力を、近代的なゲリラに組織したわけです。2) 情報戦コリンズは情報戦をすこぶる重視し、味方の情報網の構築と、敵の情報網の破壊や弱点をつくことに並外れた才能をみせています。3) (都市)ゲリラ戦コリンズはゲリラ戦術、とりわけ都市におけるゲリラ戦術の創始者といってもよい存在で、以後のゲリラやテロ組織はほとんど彼の戦術を手本にしています。それまでのアイルランド軍は、部隊が小規模だったがゆえに、正面からの正規戦でイギリス軍相手に歯がたたなかったのですが、都市においては、むしろ小規模部隊(ゲリラ)であることがかえって有利に働くのです。逆転の発想ですね。4) 優しさと冷酷さの二面性コリンズの部隊が暗殺した者の多くは、実は、イギリス支持のアイルランド人だったのです。ですから、後に続く「アイルランド内戦」の引き金を引いた人物と言ってもよいでしょう。彼は、ほとんどためらうことなく、これら「ユニオニスト」の暗殺司令を発したとのことです(彼自身が人を殺すシーンは、映画にはありませんが)。このような冷酷さの反面、彼は部下一人一人に対して、一人前の人格者として敬意をもって接したそうです。また、彼は、都市ゲリラという、人類を破滅に導きかねない戦術を創始した一方で、常に戦争の終結、すなわち平和を求めていたのでした。以上がコリンズの特徴ですが、映画ではこの辺がかなり淡白に描かれているという印象です。特に、「優しさと冷酷さの二面性」については、もう一工夫ほしかったなという印象でした。暗殺シーンはかなりリアルで、監督は必ずしもテロや暗殺を容認しているわけではない、ということが窺われますね。映画の全編にわたって流れるアイリッシュ・サウンドは、綺麗な音色ですがどこかもの哀しく、余韻が残ります。また、アイルランドの街を再現したセットは、かなり手が込んでリアルで、当時の雰囲気を堪能できると思います。アイルランドの“公式”の歴史は、イギリスに対する抵抗の歴史で、アイルランド人同士による殺し合い、すなわち「内戦」の事実は封印されてきたのでした。従って、「内戦」をもっとも過酷に戦ったコリンズも、あまり表舞台に出ることはありませんでした。その(作られた)既成概念を突破したのが、この作品です。実は、コリンズ自身も、最後はアイルランド人によって暗殺されているのです。以下のように。1921年、英国が休戦を布告し、デ・ヴァレラ(コリンズの友人にして、自由国の最高指導者)の命令でコリンズは交渉役として英国に赴きました。イギリスの提案は、アイルランド自由国の独立は認めるが国の分断(北部の分離)と英王室への忠誠を求めるというもので、平和を望むコリンズは渋々条約に署名したのでした。それをめぐりアイルランド国内の意見は賛成派と反対派に二分し決裂し、デ・ヴァレラは反対派の領袖となってコリンズと袂を分かち、ここに本格的な内戦がはじまりました。コリンズは、周囲の反対を振り切り、停戦条約のため反条約派の総本山ウェスト・コークへデ・ヴァレラとの会談に向かいましたが、血気にはやった青年たちから成る謀反者の待ち伏せにあい、頭を撃ち抜かれて死亡。1922年8月22日、享年32歳。葬儀には多くのアイルランド国民が参列しました。そのコリンズを主役にしたこの映画では、コリンズが暗殺する人物はイギリスの官憲や諜報員が殆どで、やはり「内戦」としての側面は希釈されたものになっています。アイルランド人自身が「内戦」を正面から見据え、内実をリアルに描けるようになるには、まだ若干の時間が必要なようです。まさに映画の製作中に、アイルランドでアイルランド人によるアイルランド人をねらった悲惨なテロが起こったのですが、大いなる皮肉ともいえます。
Jan 15, 2005
コメント(4)
-

『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』
1997年、ドイツ、トーマス・ヤーン監督。末期ガンで余命幾ばくもないと医師から宣告されたら、残された時間で何をするか?二人の若者、マーチンとルディが選択したのは、未だ見たことがない海を見にいくこと・・・・。こう書くとシリアスな作品のように思われるかもしれませんが、コメディ映画です。それこそ、10秒ごとに笑わせてくれます。役者一人一人が例外なく、実に個性的なユーモアを披露してくれますね。もちろん、ドイツ流に。つまり、真面目な顔をすればするほど笑えてくるアレですよ。ドイツ映画とはいえ、プロットは、殆どアメリカ(ハリウッド)流のドタバタ劇ですね。ギャングからの逃亡劇、カーチェイス、銀行強盗、銃撃戦、そしてお色気シーンも少々。トーマス・ヤーン監督は無類のアメリカ映画好きで、ドイツでタクシー運転手をしながら自主映画に携わっていましたが、ティル・シュヴァイガー(マーチン)よ偶然知り合い、書きためてあった脚本をティルに見せたことをきっかけとして、この映画は生れたのでした。タランティーノを連想させる作風ですが、作品としては『ビッグ・ショット』や『ブルース・ブラザース』なんかを私は連想してしまいました。映像はドイツ風に重厚ですが、アイテムはアメリカのものが多数登場します。アメリカ風のギャング、プレスリー、ピンクのキャデラック、トウモロコシ畑・・・・。ちょっと映像を修正してセリフを英語にすれば、ハリウッド映画と見間違えるでしょう。良くも悪くも、戦後ドイツはアメリカと切り離せない関係にありましたが、映画もそのことは無縁ではありえませんでした。とりわけ60~70年代のドイツ映画はそうだったようです。そのようなアメリカの影響から脱し、古き良きドイツを見つめ直すように『ニュー・ジャーマン・シネマ』なるものが登場してきたわけです。ともあれ、ドイツ的な無骨なユーモアとアメリカ流ジョークのハイブリッドのような映画です。フランスの『TAXI』と比べてみるのも面白いかもしれません。最後の海のシーンは、映像も音楽も素晴らしく、ほろっとさせられるのですが、エンドクレジットの後でまた笑わせてくれますのでお見逃しなく。
Jan 14, 2005
コメント(4)
-

『アンブレイカブル(UNBREAKABLE)』
2000年、アメリカ、ナイト・シャマラン監督、ブルース・ウィリス、サミュエル・ジャクソン。悲惨な列車の脱線事故で、乗員・乗客132人のうち、幸運にもただ一人生き残ったデイヴィッド・ダン(ブルース・ウィリス)。骨形成不全症という難病にかかり、ただひとつの楽しみであるコミックの世界にのめり込んだイライジャ・プライス(サミュエル・L・ジャクソン)。この二人の男の人生が奇妙に交差してゆくミステリーですが、最後にどんでん返しが用意されているところは、いつものシャラマン流です。二人の男の「自分探し」を扱った作品と言えましょうが、シャラマン監督らしくいろんな読み方が可能なプロットに仕上がっています。例えば、『ダイ・ハード』のごとくニュー・ヒーロが誕生する作品とも、『博士の異常な愛情』のごとく一人の狂人が社会や家族を翻弄する作品とも、『ツィンズ』のごとく両極端な特徴を備える二人の人物の物語とも、『スーパーマン』や『バットマン』といったコミック作品のオマージュとも読めるわけです。ですから、結末は敢えて曖昧なものになっていますが、この点は「ニュー・ニューウエーブ」の特徴をなすものです。シャラマン監督自身も、いつものことですが、「皆さん、好きなように読み解いて欲しい」と述べています。シャラマンが描き出す世界は、自然と超自然(現実と幻想、科学と魔術)といった対立的な状況が巧みに並置され、しかも、双方の境界が判然としないところに大きな特徴があります。つまり、シュルレアリズム的なのです。この結末(解釈)の多様性、および自然と超自然の並置という作風は、村上春樹や宮崎映画でも窺われますね。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇私はシャラマン監督のセンスが結構好きです。・解釈の多様性を求めるとは言っても、S. キューブリックやD. リンチのように、「説明」をわざと省いて観客を幻惑して、作品を宗教のように神格化することはない。・登場人物の内面に深くに踏み込こむことはせず、観客に感情移入をことさら求めるわけではない。・どんでん返しはあるが、意表をついた超越的なアイテムや人物が登場するわけではなく、オーソドックスなアイテムの組み合わせでそれを成し遂げている。・映像は濃密な色彩を多用するが、決して淀むことなく、鮮明なアクセントによって軽快感を醸し出している。・ドラマチックではないが、爽快な音楽。技巧を凝らしたカメラ・ワークやアングル。インド人らしく、どこか禁欲的で、しれっとしているんですね。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇シャラマン監督の作品は賛否が分かれることが多いですが、物語の解釈は作者が提供してくれるのではなく観客各々が行わなければならない、観客が感情移入すべき対象は登場人物ではなく実は観客自身である・・・・・・そういった心構えで観ることができますと、この上もなく面白いものになるでしょう。
Jan 11, 2005
コメント(8)
-

『永遠のマリア・カラス(CALLAS FOREVER)』
2002年、イタリア=フランス=イギリス=ルーマニア=スペイン監督:フランコ・ゼッフィレリ主演:ファニー・アルダン衣装(デザイン):カール・ラガーフェルドゼッフィレリ監督のマリア・カラスへの想い入れの深さが、しみじみと伝わってくる映画ですね。カラスは、1960頃より、それまでの喉の酷使がたたって、ディーヴァとして最大の武器である高音が出なくなり、1965年の『トスカ』を最後に実質的に引退しています。1973年にワールド・ツアー(ピアノ伴奏によるリサイタル)を行い、翌年11月11日の日本公演(北海道)を最後にステージを退き、1977年9月16日、53歳の若さで生涯を閉じています。最後となった日本公演ですが、かなり不評だったうえ、完全主義の彼女のプライドをいたく傷つけたようです。実は、彼女は日本公演の最中に風邪をひいており、声の質をさらに劣化させていたのでした。この映画では「日本公演」という言葉が何度も登場しますが、引退後もトラウマとして癒えることはなかったようです。ただ、彼女自身は、日本人の芸術に対する態度や日本の風土を愛しており、京都で老後を過したいと漏らしていたそうです。是非とも、そうして欲しかったですね。**************パリのアパルトマンで、マリア・カラス(ファニー・アルダン)は隠遁生活を送っていた。そんなある日、カラスのかつての仕事仲間であるプロモーター、ラリー(ジェレミー・アイアンズ)が、カラスの全盛期の録音を使い、カラス主演のオペラ映画を製作する企画を持ってくる。一度は反発したカラスだったが、苦しい胸中をジャーナリストの友人サラに打ち明けた末、ついに承諾する。作品はカラスが演じたことがない『カルメン』。たちまちヒロインの役作りにのめり込んでいったカラスは、相手役のドン・ホセに自らマルコを選ぶほどの熱の入れようだった。しかし、『カルメン』のテスト試写を見たカラスは動揺し、ラリーに『トスカ』を今の自分の声で歌いたいと提案する。それは却下されたが、やはり口パクの作品を公開することはプライドが許さず、『カルメン』のお蔵入りを要求するのだった。 **************映画はカラスの自叙伝ではなく、フィクションです。むしろ、フランコ・ゼッフィレリ監督の”心の自叙伝”のような内容となっています。ゼッフィレリ演出でマリア・カラス主演の舞台に、彼の父親が訪ねてきた時の話です。年老いて足が不自由だった彼の父親に、カラスは「私たちはみな息子さんを愛しています。本当に才能があるんですもの」、「こんな難しい息子さんを育ててきたのだから本当にあなたは素晴らしい人に違いない」という優しい言葉をかけながら、客席から楽屋まで身体を支えて20分もかけて連れてきたのですが、ゼッフィレリは、これ以来、カラスのことは何でも許せるようになったということです。ですから、映画では、ラリー(これはゼッフィレリのことですね)が財産をはたいて『カルメン』の制作費を半分負担していたにもかかわらず、結局はカラスの「真実(honest)じゃない!」との(我儘な)言葉に押され販売を断念することになるわけです。ゼッフィレリは過去、カラスの実写版『トスカ』を企画し、一万ドルもかけて準備に入りながら頓挫してしまった、という事実があります。オナシスが出資したと思っていたそのお金は、実はカラス自身から出ていたことを彼は後で知るのですが、このエピソードの反照になっているのでしょう。人生においては、時として、極めて重要な局面であるにもかかわらず、自らのどうしようもない無力ぶりを自覚させられることがあります。カラスの訃報に接した時のゼッフィレリの心情は、まさにそういう状態だったのではないでしょうか。その悔恨の念に基づいてつくったカラスへの鎮魂歌が、この作品といえましょう。◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇この映画では全編にわたってカラスの実際の歌声が流れますが、この点について、実は私は観る前に不安に思っていました。というのも、カラスの全盛期は60年前後までですので、現在のレベルからすると録音状態はお世辞にも良好とはいえないものが少なくありませんから(実際、CDはそうです)。しかし、これは完全に杞憂でした。最近のリマスタリング技術は凄いですね。カラスを聞きなれた方でも、この映画をDVD+高性能スピーカで聴けば、新たな感動を味わうことができると思います。また、リマスタリング技術の凄さは『マリア・カラスの芸術への招待』というCDでも実感することができるでしょう。このCDは2000円以下で手に入りますから、お勧めです。衣装はシャネルのラガーフェルドが担当しており、衣装自体は素晴らしいのですが、私としてはカラスのこの映画の雰囲気にはあまりマッチしていないという印象をうけましたね。また、ロココ調のインテリアは奇麗でしたし、『カルメン』の舞台は華麗で、それ自体として一つの映画がつくれるのではと唸らせるほど豪華なものでした。
Jan 9, 2005
コメント(10)
-

『ヘヴン』
2001年、アメリカ=ドイツ=イギリス=フランス、トム・ティクヴァ監督、ケイト・ブランシェット。”恋は始末におえぬ鳥 誰にも飼い馴らせやしない拒む気になりゃ呼んでもむだよ脅しも泣きも効き目なく 口説けば相手は押し黙る私の好きなのは別の人 無口だけどお気に入り恋!恋!恋はジプシーの子 法も掟もありゃしないあんたが嫌いでも 私は好き私が好いたら御用心あんたは捕まえたつもりでも 鳥ははばたき逃げてゆく恋が遠けりゃ待つがいい 待つのをやめりゃそこにいるあんたのそばに素早く来ては 素早く消えてまた舞い戻るあんたは逃げるつもりでも 恋があんたをとらえてる恋!恋!”(「ハバネラ」、ビゼー作『カルメン』より)映画『ヘヴン』は、小説『カルメン』(メリメ)の現代版と言っていい作品ですね。カルメンといえばファムファタールの代表のような女性です。『カルメン』の舞台はスペイン。騎兵伍長ドン・ホセの人生は、情熱的なジプシー女カルメンに出会ったことで狂い出します。春の祭でカルメンに出会ったホセは、ミカエラという婚約者がありながら、彼女に強く惹かれてゆきます。彼はカルメンの愛を独り占めするため、傷害事件を起こしたカルメンを逃がしてやり、彼女の為に人を殺し、軍歴も剥奪され、山賊にまで身をやつしてお尋ね者にまでなります。浮気なカルメンに深く嫉妬しながらも冷静な男をいじらしく装い、最後には闘牛士に浮気したカルメンを殺すことになってしまいますが、殺したあとも遺体を愛撫し体を重ねるほどの執着ぶりでした。『ヘヴン』の舞台はイタリアのトリノ。29歳の英語教師フィリッパ(ケイト・ブランシェット)は、夫や生徒を死に誘った麻薬売人に復讐しようと高層ビルのオフィスに爆弾を仕掛けますが、計画は失敗し、罪なき4人の市民を死なせてしまいます。逮捕・勾留されたフィリッパは、その事実を尋問中に聞かされ失神し、その時彼女の手を優しく握ったのが、21歳の刑務官フィリッポ(ジョヴァンニ・リビージ)でした。彼は、死を覚悟しながらも正義を貫こうとする潔い彼女の姿に運命の出会いを感じ、その生き方に恋してしいます。フィリッパに恋してしまった彼は、やがて彼女を逃がすことを考え始め、他方でフィリッパは麻薬売人を処刑したい気持ちから、フィリッポの立てた計画に乗ります。そして2人は刑務所から脱出し、麻薬売人の処刑を遂げます。復讐を遂げたフィリッパの生きる目的はすでになく、残されているのは罪のない人を殺したことへの贖罪だけで、「私は終わりを待っているの」と全てを覚悟していました。しかし、フィリッポの一途な想いに心が揺れ動き、もう一度生きようとします。その後、2人はトスカーナへと向かいますが、偶然にも誕生日が同じであることや名前が似ていることを知り、お互いの想いを深めてゆきます。しかし、逮捕されるのは時間の問題。やがて2人は、追ってきた警察のヘリコプターを奪い、そのまま上昇して空に吸い込まれていくのでした。 カルメンは言ってみればアバズレで、フィリッパは純真タイプと、この二人の女性は正反対ですが、男性(ホセ、フィリッポ)にとっては両女性とも紛れもなくファムファタールだったのであり、その女性のために日常生活の全てをかなぐり捨てて、「愛の楽園(ヘヴン)」を求めて逃避行をし、破滅へと向かうわけです。何不自由なく生活しているはずの前途ある男が、なぜ、偶然出会った、自分とまったく共通点のない女性に一目ぼれして、破滅すると分っていながら「悪」の道へと共に突き進んでいくのか?この映画は、『トリコロール』三部作や『ふたりのベロニカ』など多くの名作を残した、ポーランドの巨匠クシシュトフ・キェシロフスキの遺稿脚本を映画化したものですが、そのキシャロフスキがこういうことを言っています。”この世には自分と同じ人間がもう一人いて、自分の悲しみを受け取ってくれるはずだ。”つまり、フィリッポとフィリッパは、Better Half だっということですね。しかし、そのような消極的・受動的な動機(運命論)のみでは、二人の果敢な行動は説明しずらいと思います。ホセにしろ、フィリッポにしろ、彼らが積極的・能動的に求めたのは「エロス」に他なりません。===============わたしたちの欲望は、日常世界の中でつねに新たな存在可能を開こうとするときに現れるエロス性を求めている。それが実存的な欲望の意味である。しかし、この欲望は、日常性がそういった挫折の反復しかもたらさないという「体験」(フッサールの言う)の積み重ねによって、この日常性それ自体を破る可能性として予感されるようなエロス性(=”超越的”なエロス性)を求めることになるのだ。そして重要なのは、<社会>や<歴史>や<真理>に対する人間の欲望とは、まさしくそのような超越的なエロス性を意味しているのではないかということだ。・・・・・・いまある日常に対してより素晴しい日常を見出したとき、その場面でエロス性はやってくるこの意味でエロス性とはいまある日常性を破るときに生じる「陶酔」(ニーチェ)だと言える(『現代思想の冒険』、竹田青嗣)===============いまある日常に満足している者はそれでよいでしょう。しかし、それでは満足できない者もいるわけです。いまの自分は”ほんとう”の自分のありようとは根本的にどこか違う、なんとかしてこの閉塞的な状況を打破したい・・・・・世間体、慣習、ルール、常識によって心の深層に封印されていた、そういう”魂の叫び”が炸裂する契機が、人生に一度か二度は訪れるものです。人生の新たな可能性を感じた時にやってくる、あの心地よい感覚が、エロス性というものです。バタイユによれば、人間の性のエロティシズム(エロス性)というのは、人間が本来超え得ない<死>を「乗り超えうる」可能性の幻想として現れることになります。ですから、フィリッポとフィリッパのように、エロス性によってつき動かれた人間には、<死>への恐れがないのです。ちなみに、イエス・キリストが<死>すなわち「十字架」を受け入れることができた根底には、それによって「人間」や<死>を超越しうるというエロス性の生起があったのではないでしょうか。
Jan 8, 2005
コメント(2)
-
『最後の誘惑』(終)
映画『最後の誘惑 The Last Temptation of Christ』は、以下のテロップからはじまります。”神への到達を目指したキリストは、極めて人間的なものと超人間的なものの両面を持っていた。キリストのこの二元性は、私にとって以前から尽きぬ謎であった。若い頃から、私の悩みまた喜びと悲しみは、精神と肉体の間の飽くことのない苛烈な闘いから生れてきた。私の魂は、その二つの力が衝突する戦場である。”(『キリスト最後のこころみ The Last Temptation of Christ』、ニコス・カザンヅァキス)カザンヅァキスの著書も、この映画も、英語の題名は『The Last Temptation of Christ』と同じです。映画ではさらに以下のテロップが加わりますが、これはキリスト教グループによる激しい反対運動に配慮した方便であることは明白で、スコセッシの本音は、もちろん、聖書から垣間見られる”人間イエス”としての魂の葛藤を描写することにあったわけです。”この映画は、聖書の福音書に基づくものではなく、この永遠なる魂の葛藤をフィクションとして探究しようとするものである。”さて、スコセッシは「イエス・キリストは私たちと同じ人間の一人だ」と述べて、つまり二元論(イエスは人間であり、神とは異なる存在である)の立場から”人間イエス”を描写し解釈していくわけですが、これはキリスト教の正統である「三位一体」(イエスと神は同質・一体である)に真っ向から対立するものですね。ですから、この映画はキリスト教グループによる反対運動に晒されたわけです。では、何故スコセッシは二元論の立場をとり、人間としての側面からイエス像を捉えようとしたのかというと、それはイエスという存在をよりよく理解するためだったのです。一元論(「三位一体」)に基づいてイエス=神として考察しようとすると、「神が自らを人間に変えて、挙句に人間の犠牲になって十字架にかけられたのはどうしてなのか?」という疑問に十分に答えることができないのです。「十字架」という事実から、神の愛なるものを”感じとる”ることはできるのでしょうし、それで満足できる人は、それでよい。しかし、そうでない人にとっては、とりわけ私のような非キリスト教者にとっては訳が分らない(「十字架」の意味を実感として捉えることができない)わけです。私は先の「日記」で、「一元論のほうは、論理的に分析・説明・理解し難いという欠点を有する」と述べましたが、イエス=神とする一元論(三位一体)の立場では、そういう疑問に答えることがまったくできないわけなんですね。さらに、論理の問題としても、無限かつ絶対なる神(=イエス)の意思なるものを、有限かつ相対なる人間ごときが十分に理解することがそもそも可能なのか、というアポリアも出来します。ひとりの善意の人間が拷問を受け鞭打たれ、そして十字架にかけられた。しかも、この人間というのは実に優れた人物であって、悪事を働いたわけでもなく、人間誰をも愛し、しかも誰もが愛さずにはいられないほどの人物であった・・・・・我々がなぜ「十字架」に拘るのかというと、このイエスのイメージから強烈な感銘を受けざるをえないからです。そうすると、イエスや「十字架」というものを十分に理解したいという欲望が嫌でも湧き上がってくるわけですが、その欲望を満たすためには、神としてのイエスにではなく、人間としてのイエスに我々自身が深く関わっていくという道をとるしかないのです。スコセッシが敢えてイエスを人間として描いた意図は、そこにあったのです。映画では、イエスは当初一貫して人間の感情、心理で行動しています。ですから、彼は「自分が神の子である」という事実に困惑し、逃避し、苦悩し、そして恐怖します。なぜなら、彼は当初その事実を認識できても、その意味を理解することができなかったからです。やがて、彼は数々の奇跡を起こしながらも、それに満足するのではなく、内心恐怖に身を震わせることになります。奇跡を一つ起こすたびに、彼自身がなにやら抜き差しならない深みに一歩一歩はまりこんでいくのが自分で分ってきたからです。やがて、彼は、それが具体的には「十字架」への道であることに気づくことになります。ただ、奇跡にしても「十字架」にしても、この映画では自然と超自然が並置されるかたちで描かれています。例えば、イエスが盲目の男を治療する奇跡の場面では、イエスは薬草に唾をこすり合わせて目に当てるのですが、自然(医学)と超自然(奇跡)が並置されています。また、「十字架」にしても、神が定めた運命という超自然とも、「血の犠牲(生贄)」という我々の潜在意識に潜んでいる原始本能(自然)の顕れとも理解できます。つまり、これらは、超自然という神の側面に遍在して、人間イエスという存在が陳腐化しないよう配慮されているわけです。人間イエスは、人間としての実存的欲望(=悪魔の誘惑)と、神の意思という崇高な使命との間で葛藤しながらも、欲望(誘惑)を一つ一つ絶ってゆくことになります。欲望(誘惑)とは、女性、家庭、権力、そして支配などのことですが、十字架にかけられる直前に「天使」が現れて最後の欲望(誘惑)にかられます。それは、マルタとマリアの双方と結婚し、多くの子供をもうけ、平穏無事に老年を迎えるというものです。もちろん、イエスは最終的に「最後の誘惑」さえも断ち切るのですが。私がこの映画に不満を感じる点は、いかにして人間イエスがこれらの欲望(誘惑)を断ち切ったのか、その内面的葛藤が十分に描ききれていないということです。殆ど、「これらの欲望(誘惑)は悪魔の囁きだと分ったから」というような実に単純な理由で退けているんですね。これでは、「神 vs 悪魔」という対立図式において、一方的かつ安易に神に軍配を上げているに等しく、人間の実存としての側面が軽視されているわけです。つまり、スコセッシは「イエス・キリストは私たちと同じ人間の一人だ」としながらも、誘惑の排除という局面では、「神 vs 悪魔」という対立図式に仮託して明確に神の側面からイエスを描いていることになります。このことによって、人間イエスとしての深みが損なわれてしまっていますね。そういう意味で、私としては思想的な洗練不足を感じざるをえませんでした。最後に、スコセッシは緻密な映画作りで定評がありますが、その例に漏れず、映像、衣装、小道具、音楽などがリアルかつ味わい深いものが用いられており、これらのみでも十分に楽しめる内容となっています。映像はナス・エル・ギワネというモロッコ音楽から多くのインスピレーションをえたとのことで、またサウンドトラックはピーター・ガブリエルが担当して民族色が強いものに仕上がっておりお勧めです。
Jan 7, 2005
コメント(4)
-
『最後の誘惑』(二)
● 一元論と二元論「イエスがどの程度神であり、どの程度人間であるか」といった二重性質論争の本質は、イエスという存在を理解・解釈するのに【一元論】の立場をとるのか、それとも【二元論】の立場をとるのか、という問題に収斂します。一元論:イエスと神は同質・一体である。二元論:イエスは人間であり、神とは異なる存在である。一元論の立場は現在正統とされている「三位一体」に基づくわけですが、これは神、子、精霊という違う”モノ”を統一した理論ですね。「位」とは英語ではpersonのことで、「人称」や「格」と訳されますが、要するに「存在のしかた」のことです。その「位」が三つあるのですから、神は人間との関係において三つの存在のしかたをするということになります。第一位は、創造主としての存在で、「父なる神」のことです。第二位は、救世主(人間)としてこの世に遣わした「神の子=イエス・キリスト」としての存在です。第三位は、「聖霊」としての存在で、「聖霊」によって人間は直接神と結びついていると教えるわけです。このように、神は「父」・「子」・「聖霊」という三つの存在のしかたをするのですが、それらの本性(質)は一つ、つまり「一体」といっているわけです。ちなみに、この「一体」である神の本性が、他ならぬ「愛」です。「三位」のうちの第二位について現在、(「三位一体」に基づいて)一元論的に解釈するのが正統で、二元論的に解釈するものは異端と称されているわけです。つまり、イエスの二重性質論争の本質は、一元論の立場をとるのか、それとも二元論の立場をとるのか、という問題に収斂されるわけです。● 「一元論 vs 二元論」という構図「一元論 vs 二元論」(AとBは同じものか、別のものか)という戦いの構図----これは、キリスト教や思想に限らず世間一般でも頻繁に遭遇するものです。思想で古くからある「心身問題」(心と身体の一体性を説く心身一元論と、別のものと説く心身二元論)というのは正にこれの典型ですね。世界観については、アニミズム的な、事物(自然)と心的事象とが霊的に溶け合った世界観(一元論)と、近代科学的な、事物(自然)とそれを利用しつつ改変する人間とが分離する世界観(二元論)の対立。世俗的な例では、政治家(公人)について、常に公人=私人とする立場(一元論)と、公人でも私的な行為は別とする立場(二元論)の対立。戦争について、あらゆる戦争は悪だとする立場(一元論)と、侵略戦争は悪だが自衛戦争は正義だとする立場(二元論)の対立。夫婦や親子について、両者は一体だとする立場(一元論)と、個人として別々の人格的存在だとする立場(二元論)。雑談レベルでは、石炭もダイヤモンドも同じ炭素原子から構成されるのだから同じだとする立場(一元論)と、価値が違いすぎるとする立場(二元論)。● 一元論と二元論の長所および短所一元論の立場をとるのか、それとも二元論の立場をとるのか。実は、一元論と二元論とは、理論上は「等価」の関係にあるのです。つまり、ものごとの説明方式として(絶対的に)、どちらが優れているとか、どちらが劣っているのか、という類の関係にあるのではありません。あくまで、人間が、その時々の事情や動機や生活態様などに基づいて、自然な説明方法としてどちらかを選択しているに過ぎないのです。私は「元旦の日記」で、以下のように述べましたね。================私たちは心を持っていますが、心には二つの側面があります。自分はこうありたいという「自分によせる心」と、社会はこうあってほしいという「社会によせる心」です。================これは、人間の心というものを「自分によせる心」と「社会によせる心」という二つの側面から、つまり二元論的に解釈・分析したものになっています。何故そうしたかというと、そのほうが「お御籤の和歌」や思想というものの意味を説明しやすいからです。この「心」の例でも分かるように、二元論というのは論理的に分析・説明・理解しやすいという長所があります。裏を返せば、一元論のほうは、論理的に分析・説明・理解し難いという欠点を有するのです。例えば、「三位一体」という一元論は分り難いうえ、実は「イエスがどの程度神であり、どの程度人間であるか」という問いの答えには全然なっていないんですね。といいますか、一元論は、そういう問い自体を無効化してしまうのです。次に、二元論の欠点です。二元論では最終的に別々に立てられた二つの「元」の関係を説明することが要請されるのですが、それがなかなか上手くいかないことが多いのです。そのことについても、私は「元旦の日記」で触れています。=================”「自分」は自由を求めるが、「社会」はその自由を制限する。他方で、「社会」は「自分」の自由を実現する(欲望を満たす)ための前提条件(基盤)でもある。”このジレンマは、人々が社会生活を営む以上は必然であり、普遍的です。そして、このジレンマをどう扱うか、ということが思想の根本的モチーフなのです。ですから、思想はいつどんな時代においても、我々が社会生活を営む限り絶対に必要なものなのです。=================つまり、「自分」と「社会」を区別して二元論的に人間の生活態度(心)を説明しようとすると上のようなジレンマが必然的に生じ、「自分」と「社会」の関係(双方の間でどう折り合いをつけたらよいのか)について説明することが要請されます。しかし、この説明(ジレンマの解消)はすこぶる難しいのです。ですから、思想というのは永遠の課題なわけなのですが。逆に、一元論では、二元的な対立(ジレンマ)が生じませんので、このような説明が必要とされることはなく、この点は一元論の長所となっています。繰り返しますが、一元論と二元論は、説明方法としてどちらかが原理的に優れているわけではありません。正に一長一短なわけです。● キリスト教の問題点:一元論と二元論の二重性最後に、キリスト教における、一元論と二元論の二重性について述べておきましょう。キリスト教の正統は、一方で、イエスの性質については「三位一体」という一元論をとりますが、他方で、「自分」と「社会」という問題については二元論の立場を極限的に(!)とります。キリスト教は、「自分によせる心」と「社会(他人)によせる心」とを背立的にかつ極端に分裂させ、「自分によせる心」は悪だとし、「社会(他人)によせる心」のみを善としたのです。それが「愛」だと。この考えは、二元論の極致ですね。実は、『最後の誘惑』という映画は、この二重性(一元論と二元論の並存)に基づく”人間”イエスの葛藤や悩みを描いた映画に他ならないのです。・・・・・次回からようやく、『最後の誘惑』の内容について述べることができます。
Jan 5, 2005
コメント(4)
-
『最後の誘惑』(一)
1988年、アメリカ、マーティン・スコセッシ監督、ウィレム・デフォー、ハーベイ・カイテル、デビッド・ボウィ。”私のこの映画は深い宗教的感情によって作られている。私は十五年間この映画作りに関わってきたし、これは自分にとって特別な意味を持った作品だ。これは受難と、神を見出す苦難についての宗教的映画だと信じている。この作品は確信をこめて、愛情をこめて作られた。したがって、これは信仰の肯定の映画であって、決して否定の映画ではない。いかなる人々もイエスの神的な面同様、人間的な面にも一体感を持つことができるに違いないと私は強く信じている。”(マーチン・スコセッシ)『最後の誘惑』という映画は、「イエス・キリストは私たちと同じ人間の一人だ」として、神であることを否定せずにキリストのなかの人間的側面を強調した作品です。原作はギリシャの哲学者・小説家ニコス・カザンヅァキス(1883~1957)の小説『キリスト最後のこころみ』(1954)で、彼はこの小説を書いたがためにギリシャ正教会から破門され、死後その遺体は教会の墓地から撤去されています。そのカザンヅァキスの問題の作品を映画化しようというのですから、カトリックとりわけファンダメンタリスト(根本主義者)から執拗に攻撃されました。実は、1983年、この作品はパラマウント社のもと製作が開始されたことがあったのですが、キリスト教グループによる政策中止キャンペーンに屈するかたちで頓挫しています。その後、フランス政府から資金を仰いでフランスとの共同制作の話が浮上しましたが、その直前の、ローマ教皇による弾劾にまで発展した『ゴダールのマリア』(1985年)論争の余波を受けて、この話も立ち消えとなりました。その後1988年1月、ユニヴァーサル社(MCA)が、パラマウント社と同じ轍を踏まないように、キリスト教再生派で、ファンダメンタリストの利益を専門にするマーケッティング会社の社長ティム・ペンランドをこの映画の相談役(コンサルタント)に任命して製作を開始しました。しかし、それでもキリスト教グループからの攻撃が止むことはなく、それまで沈黙を守っていたスコセッシ監督が業を煮やして発表した声明が、冒頭に掲げた文章です。以後、ヨーロッパも巻き込んで賛否両論が入り乱れる大論争に発展したという、いわくつきの作品です。ちなみに、キリスト教圏では、この種の論争や攻撃は珍しいことではなく、『ジーザス・クリスト・スーパースター』、『E.T.』、『ハリーポッター』、さらには最近では『パッション』でも同様の事態が出来していますね。「攻撃」という表現は決して誇張ではなく、例えば『最後の誘惑』の場合、言論や法による上映禁止運動なぞまだ可愛いほうで(イスラエルやギリシアでは上映禁止、西ドイツやアイルランドでは制限つき上映)、パリでは示威運動のなかで封切られ、UGCオデオンのロビーでは暴力沙汰となり火炎瓶が投じられ警官十三名が負傷していますし、別の劇場では催涙ガスがまかれています。同様の事件が、アヴィニョン、ブザンソン、マルセイユでも起こり、映画館シネマ・サン・ミシェルが放火され十三人が負傷しています。ブラジルでも暴動が起こっています。歴史をたどれば、「イエスがどの程度神であり、どの程度人間であるか」といった二重性質論は、325年の「ニケア公会議」や451年の「カルケドン公会議」にまで遡ることができます。============= 西暦325年、現在のトルコのあるニケアという町で、教会の公会議が開かれ、キリストは神か、それとも 被造物かをめぐって大論争がなされました。そしてこの公会議は「キリストは父なる神とまったく同じ本質実態である」ということが明かになりました。また、聖霊が神であることも、この「ニケア信条」であきらかになりました。「ニケア信条」とは、わたくしたちクリスチャンのキリスト教信仰の根本である「三位一体」を確立した信条であり、キリスト教がキリスト教であるためのぎりぎりの信仰告白であるということができます。 ニケア会議によって、三位一体論を確立した、キリスト教は、西暦451年のカルケドン公会議によって、 キリスト論を確立することになります。キリストの本性は、果たして「神」なのか、「人」なのか、「キリスト論」の議論は白熱してきました。そして、「カルケドン信条」において、次のような結論が宣言されたのです。キリストは「真の神にして、同時に理性を有する霊魂と肉体から成る真の人間である」 http://www.christian.jp/history/index3.htm=============2教義をめぐる対立、教父(中略) キリスト教会の内部で繰り返し議論の対象となった問題があります。・・・・それは何かというとイエスの問題なんです。イエスはなんなんだ?初期の聖職者たちも疑問に思ったんだね。彼が救世主であることはいいんです。そう信じる人がキリスト教徒なんだから。問題はその先、救世主イエスは人間か、神か?そこで論争が生まれる。 人間だったら死刑になったあと生き返るはずはない。人は死んだら普通死んだままですからね。だから、イエスを人間とすると、やがてそれは復活の否定につながります。 じゃあ、神だったのか。それもおかしいんです。キリスト教も一神教です。神はヤハウェのみ。イエスも神としたら神が二人になってしまいます。だから彼を神とすることもできない。 この矛盾をどう切り抜けて首尾一貫した理論を作り上げるかで初期の聖職者、神学者たちは論争したんだ。 325年のニケーア公会議では、アリウス派という考えが異端、つまり間違った理論とされます。アリウス派はイエスを人間だといったんです。正統と認められたのはアタナシウス派という。このアタナシウス派の考えはあとでまとめます。 431年のエフェソス公会議ではネストリウスという人が異端とされます。彼はマリアを「神の母」と呼ぶのに反対したんで異端になった。実際には政治闘争だったようですがあえていえばネストリウスもイエスの人間性を強調したということでしょう。 451年カルケドン公会議では単性論派が異端とされます。このグループはイエスを人間ではないとする。単純にいえば神だ、というわけだ。 つまりイエスを神とか人間とか、どちらかに言いきる主張は異端とされていったんです。これらの論争を通じて勝ち残って正統とされたのはアタナシウス派です。この派の理論は「三位一体(さんみいったい)説」という。神とイエスと聖霊の三つは「同質」である、という理論です。注意しなければいけないのは「同質」という言い方。「同じ」とは違うからね。ややこしいね。「同質」というのは「質が同じ」なので「同じ」ではない。 もともと「生き返った人間」イエスを人間でも神でもないものに、別の言い方をすれば、人間でもあり神でもあるものにしようというんだから、分かりやすく理論を作るのは無理だね。そこをなんとかくぐり抜けて完成された理論が「同質」の「三位一体説」です。だから私実はよく分かっていません。このいきなり登場した「聖霊」はいったいなんだろうね。辞典を読んでも分かりません。知っている人はこっそり教えてください。 現在キリスト教は世界中に広がっていますがカトリックもプロテスタントも伝統的な教会は三位一体説にたっています。みんなそうだから現在ではあらためてアタナシウス派なんて言わないくらいに一般的です。教会の説教で「父と子と聖霊の御名において~~」というのを聞いたことありませんか。あれが三位一体ですね。アメリカ合衆国生まれの新しい宗派では三位一体説にたっていないものがあるかも知れませんがね。 異端とされた宗派のその後ですが、ローマ帝国内では布教ができません。アリウス派は北方のゲルマン人に布教活動をします。ネストリウス派はイランから中央アジアにかけて広がっていきました。単性論派はエジプトやエチオピアに残ります。http://www.geocities.jp/timeway/kougi-19.html*)「三位一体」論で言う「聖霊」とは、イエス復活後の五旬節 (聖霊降臨祭) に使徒たちに下された霊のことで、神自身の分身としての人格 (位格) を持つとのこと。まあ、そんじょそこらの精霊とは違うようです。 ==================
Jan 4, 2005
コメント(4)
-
新年によせて
新年明けましておめでとうございます。初詣のお御籤は、久しぶりに「大吉」でしたが、そのお御籤の歌です。 ふる雨は あとなく晴れて のどかにも ひとかげさしそう 山ざくらばな”生”の謳歌(桜花)をあらわす光と、その反照としての”死”のかげ(=花が散ること)が窺え、日本的な「はかなさ」や「もののあわれ」が情緒的にうたわれており、味わい深いものがあります。「山ざくら」はもちろん日本の国花で、その特徴は、若葉と花が同時に咲き、花もそうですが若葉も美しく、病虫害、特に天狗巣病に強く樹令が長く数百年を越すものもある、といったところです。「山ざくら」といいますと、真っ先に思い浮かぶのは本居宣長でしょうか。 敷島の 大和心を 人問はば 朝日ににほふ 山ざくら花ただ、上のお御籤の歌の雰囲気は、「新古118」により近いようです。 山ざくら 花の下風 ふきにけり 木のもとごとの 雪のむら消えさらにお御籤には以下のようにありましたが、和歌の意味の説明にもなっていますね。”御祐助(おたすけ)をこうむって 福徳増しなお日に進んで望事は心のままになる しかしそれについて心驕り身を持ち崩して災いを招く恐れあり 心正直に行い正しく身を守りなさい”これを、私なりにもう少し詳しく解説しましょう。 ◇ ◇ ◇ ◇私たちは心を持っていますが、心には二つの側面があります。自分はこうありたいという「自分によせる心」と、社会はこうあってほしいという「社会によせる心」です。この二つの側面は、現実には多くの局面で衝突します。何故衝突するのかと言うと、自由をめぐって対立が生じるからです。「自分」は自由を求めますが、「社会」はルールや罰則などによって個人(「自分」)の自由を制限する方向に作用するわけです。ただし、事情がこれだけなら、自由を求めて反社会的な行動に出れば、問題(対立)は解決しうることになります。しかし、単なる反社会は誤りである、と殆どの人が直観できると思います。もちろん、その直観は正しいのです。なぜなら、我々が自由を謳歌するためには社会というものの存在が不可欠なのですから。自由というものを欲望(=精神的に生を充実させること)を実現するための条件としますと、社会というシステムがない無人島においては、いま我々が望んでいる欲望の殆どが実現不可能になることは誰にでも分かると思います。無人島では、欲望どころか、日々生きるための欲求(=衣食住)を充足させることで精一杯なのですから。「社会」というのは、「自分」の自由を制限する一方で、「自分」の自由を実現するための前提条件(基盤)でもあるわけで、無人島ではその前提条件を欠いていますので、自由というものがそもそも問題にさえならないのです。”「自分」は自由を求めるが、「社会」はその自由を制限する。他方で、「社会」は「自分」の自由を実現する(欲望を満たす)ための前提条件(基盤)でもある。”このジレンマは、人々が社会生活を営む以上は必然であり、普遍的です。そして、このジレンマをどう扱うか、ということが思想の根本的モチーフなのです。ですから、思想はいつどんな時代においても、我々が社会生活を営む限り絶対に必要なものなのです。 ◇ ◇ ◇ ◇さて、上のお御籤にもどって、その「説明」を私なりに解釈しますと、以下のようになります。>御祐助(おたすけ)をこうむって 福徳増しなお日に進んで望事は心のままになる 「自分」は、「社会」の恩恵を蒙って、欲望を満たすことができるであろう。つまり、自由を満喫できるであろう。>しかしそれについて心驕り身を持ち崩して災いを招く恐れあり しかし、そこで「自分によせる心」が突出すると、「社会」からしっぺ返しを喰らうことになるであろう。>心正直に行い正しく身を守りなさい「自分によせる心」も大事だが、「社会によせる心」も重要なのだから、思想というものをもっと磨き上げなさい・・・・・。山ざくらのはかない花とは「自分」のことで、その頑丈な樹(幹)とは「社会」つまり日本のことに他なりません。思想とは、山ざくらのような”美”にあふれた木を育てる営みに似ています。 本年も宜しくお願いいたします。
Jan 1, 2005
コメント(6)
全262件 (262件中 1-50件目)
-
-

- おすすめ映画
- サマー・ウォーズを観ました
- (2025-11-24 00:18:47)
-
-
-

- どんなテレビを見ました?
- ちょっとだけエスパー 第6話
- (2025-11-26 18:30:00)
-
-
-

- パク・ヨンハくん!
- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…
- (2025-11-19 16:29:25)
-








