2006年05月の記事
全81件 (81件中 1-50件目)
-
和尚/OSHO(引用)
(そして花々が降りそそぐ:p248/p249:和尚/OSHO:市民出版社)より引用(一部変作)『あなたはもう存在しない過去について気に病む。それはまったく愚かだ。過去のことはどうしようもない。もう存在しない過去をどうすることができるだろう? どうしようもない。それはすでに去っているのに、あなたはそのことについて気に病み、自分自身を消耗する。 または、未来について考え、夢を見ては欲望する。気づいたことがあるだろうか? 未来はけっして現れない。未来がやって来るのは不可能だ。現れるものはすべてつねに現在で、現在はあなたの欲望や夢とはまったく違っている。だからこそ、あなたが欲望する物事、夢見る物事、心に描く物事、計画したり、思い煩う物事は何であれ絶対に起こらない。しかし、それはあなたを消耗させる。 そして死が現在においてノックする。生もまた現在においてノックする。神もまた現在においてノックする。在るものはみな、つねに現在においてノックし、在らざるものはみな、つねに過去か未来の一部だ。 思考の実体は偽りだ。それが現在において扉を叩くことはけっしてないからだ。これを現実の判断基準としなさい。何であれ在るもの、それはつねに今ここに在る。何であれ在らざるものは、けっして現在の一部ではない。「今」においてノックすることのないものはすべて落としなさい。そして今において行動するなら、新しい次元がひらく。永遠という次元が。』
2006年05月31日
コメント(2)
-
覚醒
必ず死ぬという事実に本気で取り組めば、何事にせよ、気に病むことはなくなる。気に病むことがなくなれば、楽しむようになる。
2006年05月30日
コメント(5)
-
クリシュナムルティ(引用)
(クリシュナムルティの瞑想録/自由への飛翔:p127/p129:クリシュナムルティ:サンマーク文庫)より引用(一部変作)『無数の昨日のほかに、はたして時間などあるのだろうか。昨日がなければ時間があるだろうか。 思考とは時間にほかならないのであって、それゆえ「時間とは何か」というような問いは無意味なのである。思考を生みだしたものは昨日であり、その思考が昨日、今日、明日という仕切りを立てるのである。あるいはまた、現在それ自体が昨日から生まれたものであることを忘れて、「あるのは現在だけである」などと言ってみたりするのである。 あるのはただ昨日に無関係な今だけではあるまいか。思考が止まるときにはじめて、時間は停止する。そうした停止の瞬間に、今が現れる。これは何かの観念ではなくて、現実の事柄であるが、それは思考のメカニズムが終止符を打ったときにはじめて現れるのである。そして今というものの実感は、所詮は時間の枠の中にある今という言葉とはまったく違ったものである。それゆえ、昨日、今日、明日というような言葉にとらわれないようにすることが必要である。今の実現はただ自由においてのみ可能であり、自由は思考によって養われるものではない。 そこで次に、「今における行為とはどのようなものを言うのだろうか」という問いが生まれてくる。われわれが知っているのは、時間と記憶に基づいた行為、昨日と現在との間にある行為だけである。こうした時間の間に、あらゆる混乱と葛藤が芽生えてくるのである。そこでわれわれが真実問いかけているのは、もしそのような間隙がなければ、行為はどのようなものになるであろうか、ということである。 意識的な精神は、「私は無心にこれこれのことをした」と言うかもしれないが、実際はそうではない。精神は元来が条件づけられたものであって、それゆえ無心で自然な行為はありえないのである。あらわな現実の姿だけが唯一の事実なのであって、それが今の実態である。ところが思考はそれに直面できないので、今についてのイメージを作りあげるのである。そのようなイメージとありのままの実相との間の懸隔こそは、思考が生みだした不幸にほかならない。 昨日の影を引きずることなくあるがままの実相を見ることこそが今なのであり、今は昨日の沈黙である。』
2006年05月29日
コメント(3)
-
和尚/OSHO(引用)
(老子の道(上):p23:老子(談):OSHO/和尚:めるくまーる)より引用『生きている間、人々と一緒に生きるのはいい。世間の中にいるのはいい。だが、人が死に近づいたときには、世間に汚されることなく、自分の絶対の純潔と孤独のうちに『根源』へと向かえるように、全面的な孤立にはいるのがいい。』
2006年05月29日
コメント(0)
-
龍樹/ナーガールジュナ(引用)
(龍樹:p425:親友への手紙:ナーガールジュナ/龍樹:講談社学術文庫)より引用(一部変作)『酒類を断ち、禅定を楽しみ、かくもみごとな生活をお喜びくださいませ。』
2006年05月28日
コメント(2)
-
クリシュナムルティ(引用)
(瞑想:p36/p38:クリシュナムルティ:星雲社)より引用(一部変作)『言葉をさしはさむことなく知覚すること 思考をさしはさむことなく知覚すること そのとき知覚は はるかに鋭敏なものになります 言葉抜きの知覚自体が瞑想の一部です そのような瞑想に いったいどんな意味があるのでしょう どんな意味もありません どんな効用もありません しかし そのような瞑想のなかで 大いなる恍惚が起こります それを快楽とまちがえてはいけません この恍惚は 瞳や耳や頭や心に 無垢の質をもたらします もし あなたが 生をまったく新しいものとして見ることができないとしたら 人生は決まりきった退屈な つまらない出来事になってしまいます だから瞑想はもっとも大切なことなのです 瞑想は 測ることのできないもの 測りようのないものへの 扉をひらきます 瞑想はけっして時間のうちにはありません 時間にできるのは 変化をもたらすことだけです あらゆる改革がそうであるように 変化はその後もさらに変化を余儀なくされます 瞑想においては 時間は止まります 時間のないところには自由があります 瞑想によってのみ 人生は自由という名の甘美な奇跡に満ちあふれます』
2006年05月28日
コメント(2)
-
覚醒
「何も考えていないときだって、空っぽでほがらかになんかなれないよ。言語化されていない心の奥深くで、何となく嫌な気分が渦巻いているんだから。」などと思考は言い出す。 ところで、「何となく嫌な気分が渦巻いている」というのは、事実として存在するのだろうか?「何となく嫌な気分が渦巻いている」という思考は、「何となく」「嫌な」「気分」「渦巻く」といった言葉で組み立てられている。「何となく嫌な気分が渦巻いている」という思考と、「何となく嫌な気分が渦巻いている」ということ自体とは別である。「何となく嫌な気分が渦巻いている」ということ自体に、「何となく」「嫌な」「気分」「渦巻く」といった言葉を使わずに、全身全霊入ってみると、そこには何も無い。 そこには何も無いと知覚されたとき、「何となく嫌な気分」も存在しない。
2006年05月28日
コメント(1)
-
覚醒
僕の「欲望」は、「たった今ここにいる」ことです。この「欲望」は、「本気」で取り組めば、いつでもどこでも瞬時に満たされます。ただし、「本気」はかなり難しいです。なぜなら「不注意」であってはいけないからです。「不注意」とは、ぼんやりしていたり、あれこれ考えていたりして、目覚めていないことです。「たった今ここにいる」という「欲望」が満たされるとき、(不必要な)思考は落ち、「欲望」も落ちます。「欲望」とは、(不必要な)思考(この場合は、「たった今ここにいる」という言葉です)によって組み立てられたものですから。
2006年05月28日
コメント(0)
-
表面崩れ
表面崩れ自分も含めて他人とのかかわりから離れて興味のない風景から 目をそらし表面になる用意された部屋の用意された椅子に すわりひとつの表面になる他人も含めて自分とのかかわりから離れて表面を震わす影は不特定の方角を示す表面が崩れる
2006年05月27日
コメント(0)
-
和尚/OSHO(引用)
(和尚タイムズ アジア版 vol.3:p10:和尚/OSHO:市民出版社)より引用(一部変作)『あなたがしなくてはならないことは、ただ(不必要な)思考を取り除くのみだ。そうすれば必要なことは流れ始める。濁った思考を取り除けばいい。そうすれば真理の川は流れ始める。それはもう事実なのだ。 あなたを重くしている「思考」を取り除いたら驚くだろう、あなたは真の自己など創らなくてもいいのだ。「思考」が落ちたとき、真理があなたに自らを明かすのだから。』
2006年05月27日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(子供たちとの対話:p341:クリシュナムルティ:平河出版社)より引用(一部変作)『愛と死はともないます。死は言います、『自由でありなさい、無頓着でありなさい、あなたは何も持ってゆけない』と。そして愛は言います。愛は・・・それには言葉がありません。愛は自由があるときにのみ存在します。 愛とは、完全な自由の感覚、とてつもない強さ、生命力、精力です。』
2006年05月26日
コメント(2)
-
クリシュナムルティ(引用)
(子供たちとの対話:p344:クリシュナムルティ:平河出版社)より引用(一部変作)『思考とは時間です。思考の生み出すものはすべて時間の中にあります。それでも思考は不滅を探求しています。思考自身の不滅と自分の作ったものの不滅を求めているのです。 意識を見て、観察し、それを空にする人は、刻々と生きて、刻々と死ぬのです。内容が存在しないのです。とてつもない精力の活動があるのです。 それで時間は止まります。その美しさをごらんなさい。まさにその美しさこそが不滅です。それは思考が作ったものではありません。したがって生きることは死ぬことです。』
2006年05月25日
コメント(4)
-
和尚/OSHO(引用)
(般若心経:p406:OSHO/和尚:めるくまーる)より引用『知性とは『現在』の中にいる能力にほかならない 過去や未来の中にいればいるほど あなたはそれだけ『知性的』じゃない 知性とはいまここにいる ほかのどこでもないこの瞬間にいる能力のことなのだ そうしたとき、あなたは目覚めている』
2006年05月25日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(自己の変容:p17:クリシュナムルティ:めるくまーる)より引用(一部変作)『あなたがしなければならないことは、途中で不注意にならずに、ただ終始気づいていることだけです。この、新しい質の気づきは『注意深さ』です。そしてこの『注意深さ』には、『私』によってつくられた限界がありません。この『注意深さ』は徳の最高の形であり、それゆえ、それは愛なのです。それは至高の英知ですが、あなたが『思考/私』の人工的な罠の構造と性質とに敏感でなければ、この『注意深さ』はありえません。』
2006年05月25日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(子供たちとの対話:p341/p342:クリシュナムルティ:平河出版社)より引用(一部変作)『あなたが生をめちゃくちゃにしたのなら、それを改めなさい。明日にではなく、今日それを改めなさい。あなたが不安であるなら、なぜかを見いだし、安心しなさい。あなたの思考がまっすぐでないのなら、まっすぐに、論理的に考えなさい。そのすべてが定まり、すべてが整わなければ、創造の世界には入れません。』
2006年05月24日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(あなたは世界だ:p24:クリシュナムルティ:星雲社)より引用(一部変作)『精神は、沈黙の状態にありながら行動することができるでしょうか? それは可能だ、と私は言います。 私がそう言ったからといってなんの価値もありはしないのですが。(真実は、誰かが言うから価値があるのではなく、たんに真実なのです) 私はそれは可能であり、それが瞑想なのだと言います。 それは精神が静まり、思考が必要なときにだけ考えるようになる状態です。
2006年05月24日
コメント(0)
-
覚醒
「たった今ここにいよう」と強烈に願い、「たった今ここにいない」状態を強烈に厭う、という強い思いの継続がなければ、「願うこともなく、厭うこともなく、たった今ここにいる」という状態は現われない。
2006年05月24日
コメント(5)
-
クリシュナムルティ(引用)
(クリシュナムルティの瞑想録/自由への飛翔:p236/237:クリシュナムルティ:サンマーク文庫)より引用(一部変作)『死とは何かを知るためには、人は死ななければならない。しかしそれこそは明らかに人があえてなしえないことである。なぜならば、彼は己れの知っているあらゆるもの、自分に最も身近な奥底に根ざした希望や幻像といったものに対して死ぬことを恐れているからである。 実際には明日などはないというのに、人は今日の生と将来の死との間に多数の明日を並べ立てる。人は今日の生と将来の死との間の時間において、恐怖や不安におののきながら、仕事や社会や家族や娯楽に逃避しつつ、しかも絶えず死という避けがたいものを心の奥底で畏怖しつつ暮らしている。死について口にしようとすらせず、自分の知っているあらゆるもので墓場を飾り立てて、自分が必ず死ぬという事実から目をそらそうとしているのである。 特殊なかたちの知識のみならずあらゆるかたちの知識、すなわち己の知っているあらゆるものに対して死ぬこと、それが死である。未来に必ず起こる死を今ここに招き入れて、今日全体を包みこむこと、それがすなわち全的に死ぬことである。そのときには生と死には何の間隙もなく、そのとき死は生であり、生は死である。 疑いもなく、そうしたことは人の望むところではない。けれども人は過去にしがみつきながらも、絶えず新たなものを求めている。片手には常に古いものを抱えながら、もう一方の手を未知の方に差し伸べて新たなものを模索しているのである。それゆえ事実と理想の姿との間に絶えず二元性が生まれ、葛藤をもたらすのである。 このような混乱は、既知なるものに終止符が打たれたときにはじめて、きれいさっぱりと消えてなくなるのである。既知なるものの終焉が死である。 死は観念や表象ではなく、事実であって、昨日に根ざした今日の出来事や人間関係にすがりついたり、未来に起こるだろう理想の達成にすがりついてみたところで、人は死から逃れることはできないであろう。 人は死に対して死ななければならない。そのときはじめて天真らんまんさが生まれ、そのときにこそ永遠の新しさが姿を現わすのである。神は常に新たであり、ひとたび記憶されるやそれは姿を消してしまうのである。』
2006年05月23日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(あなたは世界だ:p7:クリシュナムルティ:星雲社)より引用『心に留めておいていただきたいのは、ことばはそれそのものではない、ということです。言い表されたものというのは、それがどんなにくわしく述べられていようと、微に入り細をうがっていようと、どんなにうまくまとめられ、すばらしいものであろうと、言い表そうとしているそのもの自体ではないのです。』
2006年05月22日
コメント(0)
-
村上春樹(引用)
(「そうだ、村上さんに聞いてみよう」:p47:村上春樹:朝日新聞社)より引用『人生というのは、退屈しながら生きていくにはあまりにも貴重なものです。ほんとに。』
2006年05月22日
コメント(0)
-
日記
僕は学生のころ、人間の出てこない小説を書きたかったのでした。もちろん動物や静物の擬人化はだめである。となると、そんなもの書けるはずがありませんでした。論理的にはどうあがいたって不可能です。それでもどういうわけか、長らく、どこかにあるような気がしておりました。 今にしてわかったことは、人間は言葉でできておるのですから、「言葉抜きの小説」があればいいわけです。もちろんそんなものありえませんが、なんと驚いたことに、「たった今ここにいる」ときには、「言葉抜きの存在」があります。それは小説を書くことで現れてくることを期待していた「得体の知れないもの」どころのしろものではありませんでした。 というわけで、今後とも精進をつづけていきたいと思います。道元禅師のおっしゃられておるように (現代文/正法眼蔵4:p17/p18:河出書房新社)、『身心のはたらきの際限は、人間自身が知り尽くすことはできない』のでありますから。 努力することと報われることとはまったく関係ないのですが、にもかかわらず、驚くことに、努力は報われるのですから。
2006年05月21日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(自由への道:p221/222:クリシュナムルティ:霞が関書房)より引用(一部変作)『霊魂再来説には、なんら神聖にして尊厳なものはありません。 昨日についてのあなたの記憶が、今日また生まれ代わって、それに従ってあなたは行動している。つまり昨日の記憶が今日のあなたの行為を制御している。同様に、百年前の記憶が昨日も今日も働いている。このように過去がたえず生まれ代わって出現するのです。 ですから霊魂再来説など賢明な説ではありません。もしあなたが記憶の功罪を自覚したなら、霊魂再来説など口にしなくなるでしょう。』
2006年05月21日
コメント(0)
-
和尚/OSHO(引用)
(存在の詩:p296:和尚/OSHO:めるくまーる)より引用(一部変作)『誰にも執着しないこと どんなものにも・・・ どんな関係にも・・・ 楽しむのはいい だが、執着しないこと 楽しみはかまわない が、いちど執着しはじめたら いったん執着心が入りこんだら もうあなたは流れていない ん? そうしたら障害物が入りこんでいることになる どこにも安住しないこと そうしたらあなたは自分自身の中に安住できるだろう どんなものにも執着しないこと それではじめて あなたは自分自身の内にくつろぐことができるだろう』
2006年05月21日
コメント(0)
-
福田和也(引用)
(甘美な人生:福田和也:p212:ちくま学芸文庫)より引用『此岸を「彼方」として生きる明確な意志さえあれば、人生は「甘美」な奇蹟で満ち溢れる。』
2006年05月21日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(生の全体性:クリシュナムルティ:p282/p285:平河出版社)より引用(一部変作)『思考は根本的、基本的に、心理的な意味で安定を与えてくれるだろうか? 思考には、身体を危険から守るといったそれなりの役割はある。だが、「思考には心理的な安定をもたらす力もある」と考えて生きていると、あなたは幻想のなかで生きていくことになる。 思考は、頭脳のなかに記憶として蓄積された、経験、知識による反応である。したがって、その反応はつねに過去からやって来る。さて、過去のなかに安定があるだろうか? 本質的に過去のものである思考の活動が安定を与えるだろうか? 思考は、自分が作り出したもののなかに安定を求める。そしてその安定は過去のものである。 あるいは、過去にはどんな安定もないと気づいて、思考は今度は、観念や精神の理想的状態を未来に投影し、「いつかは理想的な状態が達成されるであろう」という希望のなかに安定を見出すのである。 人間は一生、思考と、思考が最も本質的であるとして組み立てたもの、つまり聖性、世俗性、道徳性、非道徳性、などに依存している。ある人がやって来て、「いいかね、そういうものはすべて思考の活動、過去の活動だ」と言う。その人と論じあった後、もうひとりが言う、「いいじゃないか。たとえそれが過去のものだとしても、思考を固守することのどこがまちがっている?」。彼はそういうものはすべて思考の活動、過去の活動だということを認めた上で、「私はそれを固守する。そのどこが悪い?」と言う。しかし、人間の精神が過去に生き、過去を固守するときには、真理を生きることはできない、真理を知ることはできない。 つまり、思考が何を作り出そうと、思考が作り出したものには安定はいっさいない。 では、どうすればいいのか? あなたにできることは、「思考が何を作り出そうと、思考が作り出したものには安定はいっさいない」という事実を全身全霊で「見る」ことだけである。それを「見る」ことにより、あなたはそれから解放される。「思考が何を作り出そうと、思考が作り出したものには安定はいっさいない」という事実を全身全霊で「見る」ことが英知である。このような英知は理性や論理ではなく、また非常に注意深い弁証法的説明でもない。弁証法的説明はさまざまな形をとった思考のひけらかしに過ぎない。そして思考は少しも知的ではない。 事実の知覚が英知である。その英知のなかにこそ、平安、安定がある。 思考は過去から生ずる活動であり、したがって時間的なものであり、測りうるものである。測りうるものは、測りえないもの、つまり真理を見出すことは絶対にできない。それができるのは、「思考が何をつくり出そうと、そのなかには安定などない」という事実を、精神が実際に「見る」ときだけである。その「見る」ことが英知なのである。 その英知があるとき、(苦悩をもたらす)思考はすべて終わる。そうなったら、あなたはこの世界に住んでいるにもかかわらずこの世界の外にある。この世界で何かをしようとしているにもかかわらず、あなたは完全にアウトサイダーである。』
2006年05月19日
コメント(0)
-
小林秀雄(引用)
(意味という病:p73:柄谷行人/小林秀雄:講談社文芸文庫)より引用『人生には在りさうもない事だけが起こっている。』
2006年05月19日
コメント(0)
-
ドストエフスキー(引用)
(群像2000年3月号:p333:ドストエフスキーという波紋:三浦雅士/ドストエフスキー:講談社)より引用『人生は、現実的であればあるほど、いよいよ信じ難いものになる。』
2006年05月19日
コメント(0)
-
岸田秀(引用)
(日本人と「日本病」について:岸田秀:p94:文春文庫)より引用『言語のはたらきは、目立たせることであって、ある限られたポイントをピックアップすることによって、相手に通じさせるわけです。たとえば、四つのポイントを言えば、全体が表現できる。この四つを聞けば、同じ文化の中ならば相手が全体を察知するわけです。そのポイントの置き所や、数が、言語によって違うということですね。正確な直訳が誤訳になるのもそのためです。』
2006年05月18日
コメント(0)
-
岸田秀(引用)
(日本人と「日本病」について:岸田秀:p116:文春文庫)より引用『大人というのは、一つの社会体制を維持するのに必要で、それに適した人間のことでしょう。』
2006年05月18日
コメント(0)
-
村上春樹(引用)
(「そうだ、村上さんに聞いてみよう」:p16:村上春樹:朝日新聞社)より引用『1日のうちの1時間くらいは、たとえ忙しくても、何かしらの運動にあてる』
2006年05月18日
コメント(0)
-
日
日つめた けだるい月の の い木にひかり もたれはげし 月の木 とがっい火の 火風金 た金はほのお 水の土 ひびきかすか ひそかな水の の な土をながれ ふんで
2006年05月18日
コメント(0)
-
岸田秀(引用)
(続ものぐさ精神分析:岸田秀:p313:中公文庫)より引用(一部変作)『怒りや悲しみの原因は、自分が現在直面している現実とは別の状態を幻想として持ち、その幻想の崩壊として現実を見ることにあります。』
2006年05月18日
コメント(0)
-
大乗仏典(引用)
(大乗仏典11:p84:三昧王経:中公文庫)より引用『彼は原因によって生じてきている現象的存在に落胆しており、世間のいかなることに対してもあこがれをいだかない。』
2006年05月17日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(子供たちとの対話:p225/p226:クリシュナムルティ:平河出版社)より引用(一部変作)『質問するのをやめたとたん、君はすでに死んでいます。それがたいがいの大人たちに起こったことなのです。質問するかぎり、君は突き破ってゆくのです。しかし、受け入れはじめたとたん、心理的に死んでいます。 一生を通じて何一つ受け入れずに、探求し、究明してごらんなさい。そのとき君は、心は本当にとてつもないものだと気づくでしょう。心には終わりがありません。そのような心には死がないのです。』
2006年05月17日
コメント(0)
-
覚醒
「たった今を生きる」というのは、「今さえよければいい」というのとは、まったくちがう。「今さえよければ」と考えるとき、「今さえ」というのは、過去や未来と比較した「今さえ」である。「たった今」に過去や未来との比較はない。 また、「今さえよければ」と考えるとき、「よければ」というのは、過去や未来と比べて「よいわるい」を判断しており、過去や未来との比較がある。
2006年05月17日
コメント(0)
-
覚醒
たった今ここにいること。別の場所にいないこと。 別の場所というのは、過去や未来のことである。 過去の「記憶/イメージ/映像」などを引きずっていたり、未来についての「憶測/願い/心配」などを思い煩っていると、たった今にいることはできない。 たった今ここにいるとき、思考はない。 たった今ここにいないと気づいたら、すみやかに「たった今」にもどること。 たった今ここにいつづけると、奇跡が起こりつづけているのがありありとわかる。
2006年05月17日
コメント(0)
-
覚醒
たった今(必要な)思考なら、「たった今考えなくてはいけない」などと考える間もなく、すでに考えている。 将来に対する準備や計画であっても、本当に必要な場合には、「準備や計画をしよう」などと考える間もなく、すでに考えている。(必要な)思考は迷うことなく進み、短時間で終わる。
2006年05月16日
コメント(0)
-
覚醒
偉大な瞑想家たちが、ときに瞑想を否定しているかのような発言をしているのは、瞑想自体を否定しているのではなく、「瞑想によって何かを得よう」としている心を否定しているのである。
2006年05月16日
コメント(0)
-
覚醒
ついつい習慣で、何であれ質問されたら自動的に返事をしてしまいがちだが、「わかりません」「答えたくありません」といった返事さえせず、たんに黙っている方が適切な場合もある。
2006年05月15日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(自己の変容:p153:クリシュナムルティ:めるくまーる)より引用(一部変作)『悲しみが終わるのは完全に自分を知るときだけです。 分析を通して自分を知ることはできません。人や物や思考との関係のなかで、どの瞬間にも過去を蓄積せずに出来事を見るときにだけ、あなたは自分を知ることができます。これは実際に起こっていることに、どんな選択もなく気づかなければならないことを意味します。それは、対立物や理想をもたず、過去の自分についての知識をもちこまずに、自身をありのままに見ることを意味します。つねに過去から脱皮しながら自分を見ることが、過去からの自由なのです。 悲しみが終わるのは、理解の光があるときだけです。この光は、ひとつの体験やひとつの理解のもたらす閃光によって灯されるものではありません。過去を持ちこまずに自分を見つづけることによって、つねに自らを照らしつづけるのです。 誰も、どんな本も、あなたにそれを与えることはできません。あなたを完全に知ることができるのは、あなただけです。 そして、あなた自身を理解することが、悲しみの終わりなのです。』
2006年05月15日
コメント(0)
-
クリシュナムルティ(引用)
(自己の変容:p96:クリシュナムルティ:めるくまーる)より引用(一部変作)『自分の生き方の破壊的な性質に気づいたなら、未来のいつかではなく、今すぐそれを終わらせることです。自分の生き方の破壊的な面に気づいているにもかかわらずそれを引き延ばすことは、英知の欠如を示しています。』
2006年05月15日
コメント(0)
-
大乗仏典(引用)
(大乗仏典11:三昧王経:p143:中公文庫)より引用(一部変作)『行為(の結果)に執着して喜んだり悲しんだりする人々、そういう人々は、行為を実践することに安住しており、行為(すなわち業を生み出すこと)から解放されることはない。』
2006年05月14日
コメント(0)
-
和尚/OSHO(引用)
(和尚タイムズ アジア版 vol.1:p5:和尚/OSHO:市民出版社)より引用(一部変作)『瞑想はあなたを直接、沈黙に導くのではない。 ただ、あなたに沈黙が起こる状況を作り出すだけだ。 沈黙が起こったかどうかは、どうやってわかるのだろう? 沈黙が起こったら、あなたの生に至福が訪れる。 あなたのまわりじゅうに至福が起こる。 悲しくなったり憂鬱になったりしない。 この世界から逃避したりしない。 あなたはこの世界のここにいる。 すべてを見事なゲームと見なし、すべてを楽しむ。 もはや深刻になることはない。』
2006年05月14日
コメント(0)
-
道元(引用)
(現代文/正法眼蔵2:道元:p232:河出書房新社)より引用『「夢に作(な)る」これが覚りの真実である。』
2006年05月12日
コメント(0)
-
ニーチェ(引用)
(若き人々への言葉:p24:ニーチェ:角川文庫)より引用『なにゆえに隣人の言うところに耳を傾けているのか。二、三百哩(マイル)も離れればもはや拘束力を失うような見解に、義務として服するというのは、いかにも田舎町じみた事柄である。』
2006年05月12日
コメント(0)
-
ブッダ(引用)
(ブッダの真理のことば・感興のことば:p19:ブッダ:岩波文庫)より引用『「わたしには子がある。わたしには財がある」と思って愚かな者は悩む。しかしすでに自己が自分のものではない。ましてどうして子が自分のものであろうか。どうして財が自分のものであろうか。』
2006年05月11日
コメント(0)
-
アントナン・アルトー(引用)
(『ヴァン・ゴッホ』:アントナン・アルトー:p87:筑摩叢書)より引用『何ひとつありはしないのだ、ひとつの美しい神経の秤をのぞいては。』
2006年05月11日
コメント(0)
-
石を育てる
石を育てる体から石が落ちる指から肘から首からぽろぽろ落ちて立ちつくすかろうじて石はとだえ溜まった石 足もとでふるえる通りすがりの出来事なら通りすぎたのだろう屈みこんで石をひろう硬くせつない肌触りこれを無機質というのかとあらためて発見する尖った指先で乾いた皮膚をさすっていたら裂け目も見せずまた落ちたじっとしててもせんかたないそれならば育ててみようかと体に穴を穿ち石をまくすみやかに石の芽は吹きぼくの体はふいに満ちる目を閉じ 心を落とし石の匂いに身をまかす
2006年05月11日
コメント(0)
-
覚醒
自分の意見にせよ他人の意見にせよ、「A」という意見があれば、「A」でないという意見も(同時に)出てくる。 突きつめれば、あらゆる意見は「ゲーム」である。「ゲーム」に参加するかどうかは選べるのである。「ゲーム」に参加せず「競技場」の外に出てみたなら、そこには膨大な空間が拡がっている。
2006年05月11日
コメント(0)
-
ニーチェ(引用)
(ニーチェ全集第十巻:p47:ニーチェ:白水社)より引用『変転・欺瞞・矛盾から、なぜ人間はよりにもよって苦悩を導き出すのか? なぜ、むしろおのれの幸福を導き出さないのか?』
2006年05月11日
コメント(0)
全81件 (81件中 1-50件目)
-
-
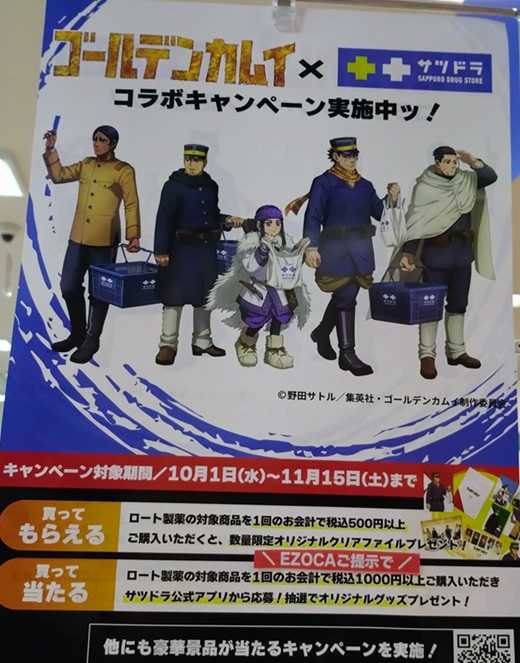
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 【レポ】内容違いで販売中「訳あり黒…
- (2025-11-15 20:12:44)
-









