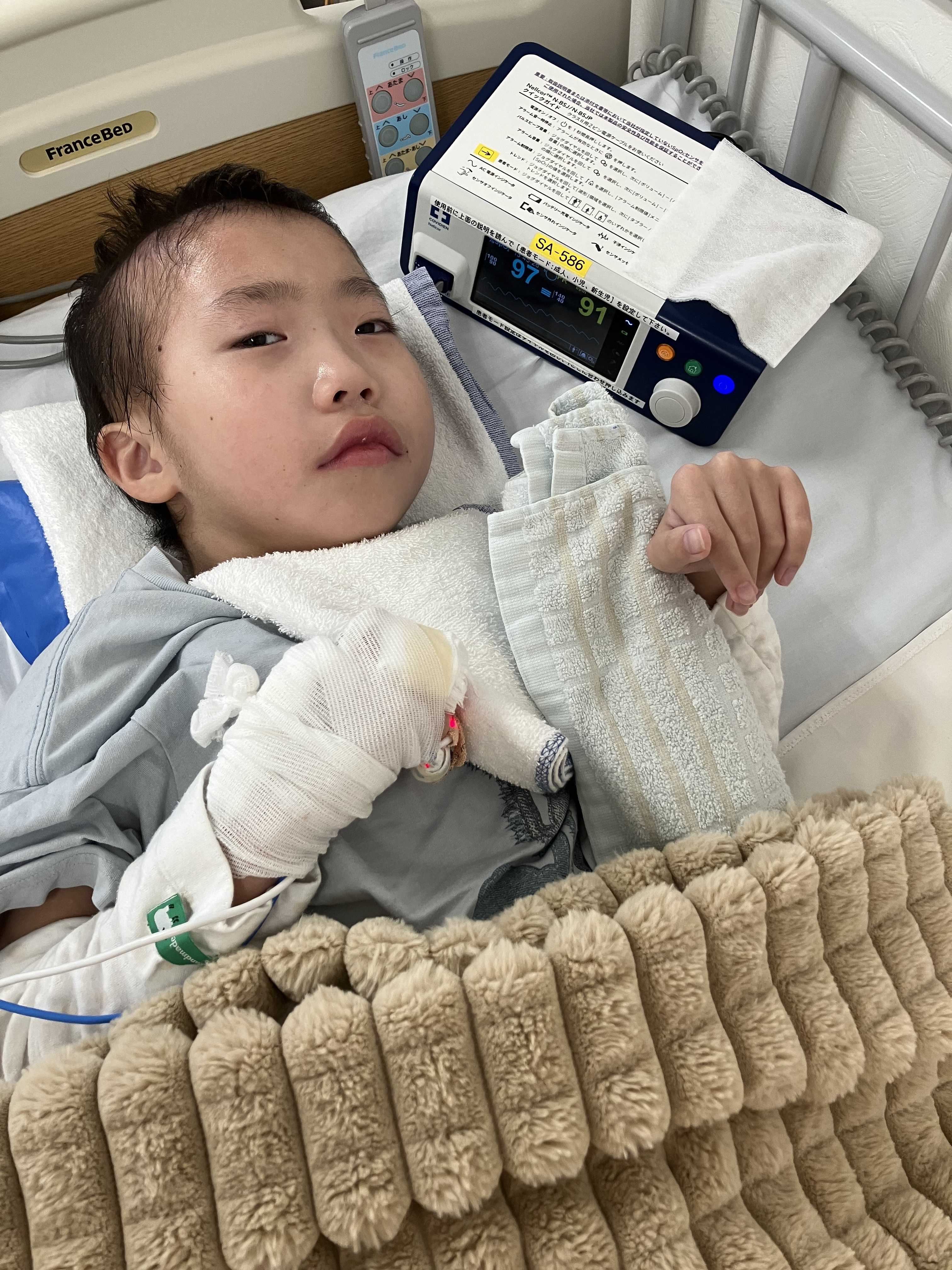2012年03月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
心筋梗塞、脳梗塞の原因と対策
真島医師の「食歴アンケート」で把握されたプラークの原因は『肉と砂糖』でした。プラークそのものは過剰なコレステロールや中性脂肪を白血球(マクロフアージ)が処理した残骸が血管にへばりついたものといわれますので問題は脂肪の過剰が原因ということです。肉 肉や牛乳などの動物性脂肪砂糖 一番目立つのが飲食物に使われる 砂糖ですが、広くは糖質です。 炭水化物=食物繊維+糖質ですから 食物繊維を排除した白米や白パン 白いうどんなども要注意です。 糖質が過剰に体内に入ると処理しきれない 糖質は脂肪に変換されます。 単純に言えば、砂糖の取り過ぎは脂肪を 増やすということです。プラークを減らす食事療法について真島医師は次のように言われています。 1.肉やフライ系の食べ物を極力控え、魚と野菜 中心の食生活にし、野菜や野菜ジュースを 薦めました。 またトコロテンやモズクなどの海藻類を 多く摂取していただくよう指導しました。2.砂糖を使う料理や食品添加物(砂糖、水あめ) 何気なく口にする飴などにも注意するよう 指導しました。 (食事では肉もあまり食べないのに、飴を 毎日しゃぶっていてプラークが大きい人が いたそうです。-飴製造会社の社員とのこと)又身体にいい食材を取り入れようとするよりも従来の間違った食習慣を改めることが、より重要としています。実際の食暦アンケートからすると『健康に良いことをするするのでなく、健康に よくないことをしないこと』という考え方の 人たちのほうが血管プラークが低かったと いう事実があるそうです。いずれにしても、従来のパン、牛乳、ハムハンバーグなどの欧米風食事を伝統的なご飯中心の和食に戻すだけで血管プラークは防げるはずと真島医師は言います。『30年以上前の「マクガバンレポート」が提唱した健康への提言を、いまこそ日本人は見直すべきだと思います。』(真島医師)参照 「脳梗塞、心筋梗塞は予知できる」 真島消化器クリニック院長 真島康雄著
2012年03月12日
コメント(2)
-
脳梗塞、心筋梗塞の元凶は肉と砂糖だった
『動脈硬化(血管プラークの肥厚)を進行させる一番の原因は、加齢や性別、コレステロール、肥満高血圧、糖尿病などではなく、子供の頃からの食習慣なのです』『動脈硬化で心筋梗塞などを発病する年齢が 急速に若年世代にも広がっているらしいのです。 原因が食習慣の欧米化にあることは 疑問の余地はありません』真島医師は、多くの脳心疾患の患者を診ている中で、コレステロールや中性脂肪などの血液検査では問題なく、痩せ型でもあるのに動脈硬化が進み心筋梗塞などの発症の危険性が高く 従来の常識では判断できない 患者がしばしば見られたので、病気のリスク判断は食習慣がより重要ではないかとの発想から詳細な「食歴アンケート」を作成、500人の患者の血管プラークと食習慣のデータを検証したところ、食習慣と血管プラークの高さが見事に相関していたのです。この結果、食習慣を聞くことで血管プラークの状況の推測も可能になったといいます。真島医師の示した結論 「血管プラークの元凶は、塩でも、タバコでも、 肥満でも、運動不足でもない 肉と砂糖!!」少し補足説明が必要ですが、次回にて参照 「脳梗塞、心筋梗塞は予知できる」 真島消化器クリニック院長真島康雄著 (幻冬舎)
2012年03月10日
コメント(0)
-
脳梗塞、心筋梗塞は100%予知出来る
『その後の研究で発見された新たな 観測ポイント。 「左右の頚動脈」「右鎖骨下動脈」 「腹部大動脈」「左右の大腿動脈」 の6箇所をエコー(超音波)画像で診る事で ほぼ100%脳梗塞、心筋梗塞は予知できる!』と言い切るのは真島消化器クリニック(久留米市) 院長 真島康雄 です。真島医師は専門は肝臓ですが、卓越したエコー(超音波)画像解析技能の持ち主だったことから脳、心疾患の患者も見ることが多く、その中で、従来のエコーでのプラーク検査では左右の頚動脈を診るのが一般的でしたが左右の頚動脈にプラークがないのに心筋梗塞、脳梗塞になる人がしばしば見られた事に疑問を感じ、さまざまなプラーク発見ポイントを探しました。頚動脈より太くカーブもしており、また分岐していることからプラークが出来やすい鎖骨下動脈の中でも最もプラークが溜まりやすい箇所がピンポイントで明らかになったのです。なぜこの箇所が今まで注目されなかったかというと、もともとその場所が身体の奥深い場所にあるため通常のエコー検査では見つけるのが難しかったのです。これに加え、「腹部大動脈」「左右の大腿動脈」も診ることで、右鎖骨下動脈にもプラークが溜まっていない極少数な症例でも発見することが可能になり『今まさに100%に近い確率で脳梗塞や心筋梗塞の 危険度の判定が可能になったのです』プラークが原因で起きる 心筋梗塞、脳梗塞、失明、尿蛋白から始まる 腎不全、欠陥性認知症、手足の指の壊死、 大動脈瘤などを真島医師は「プラーク病」と命名しています。(注) プラークの説明多くは50歳代頃から発症しますが、初期症状は20歳から始まっているそうです。右鎖骨下動脈のエコー検査をやると20代、30代でプラークが溜まっているケースが増えているそうです。ところがこれらは自覚症状は一切ないとのこと。『私の研究では、コレステロールや中性脂肪が正常でも 肥満でなくても血管プラークが異常な数値を 示しているケースがいくらでもありました。 逆に太っていても問題ない人も多くいました。』ではこのプラークはどうしてできるのか、またこれを改善する方法があるのかということですがこの点も真島医師のすばらしい研究成果が発表されています。(2008年9月日本超短波医学会誌)この原因並びに改善策については次回に紹介させていただきます。
2012年03月09日
コメント(0)
-
脳梗塞心筋梗塞が気になる方に
メタボ検診や人間ドックなどさまざまな健康診断で血液検査、X線、エコー検査、MRIなどが行われており『脳梗塞や心筋梗塞の恐れあり』という漠然とした診断は多く出されますが、その発症の危険度や安全度は把握できないと言われております。そこで、より簡単に安く尚且つ危険も伴わない方法を2つほど紹介させていただきます。一つ目は家庭で出来る方法です。1.脈拍体温健康法 お年寄りの多くは毎日血圧を測っておりますが 病院の薬の販売に協力している程度の ものです。 ここで、福山中央病院 大森隆史 医師が 主張している方法を紹介いたします。 毎日記録をとるなら、体温、血圧、脈拍を あわせて記録すると重要なシグナルが見えるといいます。● 体温 体温が36度を下回っている人は何らかの形で 血流が悪く細胞へ酸素や栄養が行き渡らず 病的症状にあるといって過言ではありません。●脈拍 血流が悪く細胞に酸素が不足すると乳酸が出来て 脈拍が速くなる●血圧 血流が悪くなると身体は血流を高め細胞に 酸素や栄養を充足させようと血圧を上げます。大森隆史医師の方法のポイント1. 体温、脈拍、血圧を継続的に記録することで 自らの標準的な脈拍、血圧の幅を確認する 2. 安静時に測定した脈拍が頻繁に通常の幅を 越えて変動する場合心筋梗塞、狭心症、脳梗塞の 危険性があると見て精密検査等を実施し 予防に努める。詳細は「病気にならない脈拍体温健康法」大森隆史著 (中継文庫)560円(税込み)をお読みください。二つ目はエコー検査での血管のプラーク確認の新技法で尚且つ、プラークを解消するための食事療法にもふれている真島康雄医師の実証理論です。次回に詳しく紹介させていただきます。
2012年03月08日
コメント(0)
-
医療に関する間違った思い込み(特集)
中村純一著「大往生したけりゃ医療に関わるな」をご紹介しましたがネットにより詳しい記事がありましたのでご覧ください。http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1202/22/news005.html
2012年03月01日
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1