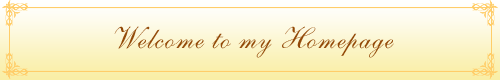2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003年12月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
「なんちゃってSOHO」を使ったから悪いのか?
前回も書いた、私の正体を知っているある同業者が、 この日記が始まってしばらくしてから、自らのホームページ(楽天日記)に、次のような「批判」を認めた。「外注を使って仕事をするのはムシがよすぎる。社員を雇用して育てればいい」 フリーランスの力を借りて仕事をすることを否定したら、編プロは成り立たない。ブローカーになりかねない微妙な問題も含んでいるが、編プロは人材派遣業的側面を自らの業務のうちに必然的にもっている。固定費のかさむマンパワーの常時維持を最小限に抑えることで、コスト的メリットをクライアントに提案できることこそがその真骨頂だからだ。 それとも、「なんちゃってSOHO」は、社員として採用すれば人が変わったようにいい仕事をするとでもいうのか。 ふふ。その理屈は、小学生にたくさんの小遣いを与えたら、大学生になれると言っているようなものではないか。 女性(とくに主婦)にチャンスを与えたい、という弊社の方針自体が気にくわないというのなら、それはもう、外注だの正社員だのといった、採用の仕方の問題ではないだろう。 何よりも、その同業者は、かつてフリーランス時代の弊社の社長を外注で使ってきた事実をどう考えているのだろうか。 話を戻そう。 私の日記を読み、「なんちゃってSOHO」なんか使うからだ、という感想を持たれること自体は、その限りで間違っていない。 問題を起こすのは、たしかに「なんちゃって」ということなのだろう。 ただ、ではどこからが被害を与える「なんちゃって」で、どこからがそうでないのか、その「しきい値」というのを考えると、実は案外難しい。 私がこの日記を始めた頃に書いたような一部の例は文句なしの「なんちゃって」だが、そういうわかりやすい人は、さすがに弊社でも門前払いをさせていただいている。 なにがしかの経歴や実績をもって仕事をしている「プロ」を名乗る人でも、いざ使ってみると「なんちゃって」になってしまう場合があるから厄介なのだ。 そう。今、これを読んでいる「売れっこ」で自信満々のアナタも、いつ「なんちゃって」に転落してしまうかもしれない可能性がある。(もちろん私も含めて……) 人間は間違いうるものだからだ。「なんちゃってSOHO」というのは、きわめて演繹的な概念であり、これからもその定義は「進化」する。その意味で、私たちは、つねに「なんちゃって」になりうる危うさを抱えながら仕事をしているのではないだろうか。結論 これをやったら「なんちゃってSOHO」になるという指摘はできるが、「なんちゃってではないSOHO」という定義は不可能である。 よって、「『なんちゃって』でないSOHOを使うべし」という指摘は、論理的でない。 今年はこのへんで……。 来年もよろしくお願いします。
2003年12月31日
コメント(5)
-
書くことは暴露である、アナタにそういう覚悟はあるか?
「身近な人をモデルにものを書くと傷つく人がいることもある」 私の正体を知っているある同業者が、ホームページでそう書いている。「なんちゃってSOHO」ばかりでなく、理不尽な版元やプロダクションも叩くことを怖がらない私に対して、牽制やあてつけでそう書いているかどうかの詮索は、この際、措くとしよう。 どちらであろうが、私の意見が揺らぐことはないからだ。 私は、「身近な人をモデルにものを書」くことを悪いと思っていない。むしろ、その勇気を持てるかどうかが、いい書き屋になれるかどうかの分かれ目だと思っている。 弊社の社長とは多少なりとも関わりのある人で、萩原遼さんという朝鮮問題研究家がいる。“ハギさん”は、文藝春秋社から上梓した「朝鮮戦争―金日成とマッカーサーの陰謀」という本の中で、「書くことは暴露することである」と明言している。 これ、一見過激だが、至極当たり前のことを言っていると思う。 永年勤めた新聞記者としての退職金をつぎ込んでアメリカに滞在し、図書館に通い詰めて探し当てた資料をもとに、朝鮮戦争の真実を書き上げたジャーナリストの鏡であるハギさんならではの至言だ。 もちろん、どんな「暴露」でもいいとは言わない。その基準は、・公益性ある主張であること・名誉毀損に該当しないこと この2点にある。言い方をかえれば、これらを満たしたものなら、暴露は法的にも道義的にも論理的にも責められるべきものではない、と私は考える。「傷つく」人がいたとしても、上記の点さえ守られたものなら、外部的名誉を傷つけたものにはなっていないはずだ。たんに「感じ方の問題」である。だから書くかどうかは、言論の自由というやつだ。それに対して、書かれた者は反論するなり、シカトするなりしていればいい。 いずれにしても、「言論の自由」というのは、お題目として唱えるのはたやすいが、実際の運用についてはそうした厳しい本質を持っている。 少なくとも書くことを生業とする人なら、この厳しさを認識すべきではないか。受け止められないのなら、表現活動は諦めた方がいい。 ところが、悪口を言わない人がいい人、などという日本的な評価方法を口実に、他者批判・相互批判から逃げるばかりでなく、それを行う人を悪者にするムキもある。それはいかがなものか。 卑屈なまでに「いい人」でいたい人は、書き屋としての基本的な資質に欠けるばかりでなく、他人との(適度な緊張を含んだ)距離をうまくとれない弱い人ではないかと私などは勘ぐってしまう。 筋を通し、人を裏切らない生き方をしていれば、口うるさいとは思われても、人間としての信頼を失うことはないだろう。それだけで十分ではないか。他者に期待し、利用しようという腹黒い野心があるから、「いい人」でいなければならないのではないか。 なお、たぶん、こんな誤解はないだろうとは思うが、バイブル本は、そうした覚悟も責任感も必要ない世界なので、この稿の指す「書く」ことの対象にははじめっから入っていない。 そういう仕事しかしていない人が、その体験の範囲を全てと思いこみ、「私はあなたに賛成しない」などと言われても、次元が違い話が噛み合わないだろうからたぶん無視するので、その点はご容赦を。
2003年12月30日
コメント(3)
-
その他「なんちゃってライター」たちの迷言
前回、インテリ気取りの自爆をご紹介したが、残念ながらこういうケースは、特別なものではない。似たような迷言はほかにもあるのでご紹介しよう。【その1】(原稿を注意されて)「(私が)何を書いたかではなく、何を書きたかったのかをわかって欲しい」 いやぁ、これにはマイッタ。 ちょっと考えて欲しい。 たとえば、ラーメン屋が客に「うまくないラーメンだ」と言われて、「私は美味しいラーメンを作りたいと思ったことをわかって欲しい」などと居直りの弁解をするだろうか。するようなら、そのラーメン屋はすぐに店をたたんだ方がいい。 出した(まずい)ラーメンが全てではないか。料理人が客の好みを忖度することはあっても、客が料理人の脳内を忖度しなければならない義理はどこにもない。 そもそも、忖度して貰おうということ自体、その人には仕事を請け負った者としてのプライドはないのか、と私なら考える。 甘えちゃだめだよ。仕事だろう?【その2】(原稿に朱をいれて戻すと)「版元の編集方針がおかしいから、私の調子が狂ってしまったんです」 ケースにもよるが、原稿そのものが読み物として完成度が高ければ、原稿にそう朱は入らない。具体的に原稿を直すというのは、おおもとの問題ではなく、原稿の書き方それ自体が奇妙なのだ。 私が見たところ、原稿がうまく書けない「なんちゃってSOHO」は、まず、「私だったらここはこうするのに……」などと、自分の原稿の出来は棚に上げて、聞いてもいないのに編集方針に口を挟みだす。 自分がその方針で仕事を請け負っている、という前提を図々しくも忘れ、というより、まるっきりひっくり返して、自分が請けてやってもいい仕事はこういう方針だ、と自分の能力の都合でクライアントの方針を変えてしまいたくなるらしい。あんた何様(笑) 私は、この時点で、「この人は危ない」と判断し、諦める。 そういう人はまもなく、エスカレートしてつまらないことから責任転嫁を始めるからだ。「このときにこう言ってくれれば私はこうしたのだ」 そこで言われることは、たいがいどうでもいい些末なことで、いずれにしても原稿の出来にはあまり影響がないか、もしくは、結果論としての「れば・たら」話である場合が多く、要するに、原稿ができない醜態に対する自己正当化や八つ当たり以上の意味を持たない。 もちろんここまできたら、もうアウトだ。この人は使えない。【その3】(原稿を直されて)「見解の相違ですね。私は自分の原稿でいいと思います」 ライティングの仕事には2通りある。大きく分けて、著作権が自分に残る場合とそうでない場合(業務委託)だ。 前者は、自分の名前で本を出版(企画出版)したり、署名で新聞や雑誌で連載したりする場合を指す。著作権が明確に自分にあるから、当然、書いたものについて責任を負わなければならない。この場合、表記や寄稿規定・要項など、その版元が定めていること以外は、自分の裁量で書ける。 後者は、版元なり制作会社なりが著作者となる仕事を手伝うもので、その法的な是否判断は措くとして、ライターは書いた原稿について、著作権自体を著作者に売り渡すという形になっている。単行本執筆でも、ムックなどはそうした契約形態の場合がある。 主婦SOHOは、おそらくページ建てで後者の仕事を請け負うことが多いだろう。その場合は、最終的にその原稿の権利を持つ人の意向で仕事をしなければならないのは当然である。 そういうときは、一人前にポリシーなど開陳しなくていいから、言われたとおりに原稿を書けばいいのである。その場合、それが仕事なのだから。【その4】(お粗末原稿しか書けなかったとき)「コミュニケーションが足りなかったからうまくできませんでした」 掲示板にも、こんなこと書いている人がいたようだが、脱力してしまった。 少しはちゃんと頭を使って欲しい。【その1】でも書いたが、客は業者を忖度する必要はないが、業者は客のニーズを忖度するのも仕事のうちである。 そう。クライアントが何を喜ぶのか、それを探るのは本来、請け負った側の仕事である。根本的にそこを勘違いしているのではないか。 もちろん、客が、「こんなものを作って欲しい」というオーダーをきちんと行うのは当然だ。 しかし、この日記で書いているのは、そういうことではない。 田貫さんが書かれているように、「その人(SOHO)に能力がなけりゃ、どうしようもない」問題というのがある。私はこの日記で、主にその部分、つまり「その人(SOHO)」の能力に依拠する問題を書いている。 さらに言えば、間抜けな「なんちゃってSOHO」を雇ってしまった後悔やグチを書きたいわけでもない。そういうことなら、最初から主婦SOHOにチャンスなど与えなければいいだけの話だ。 それにしても、白黒を曖昧にした「どっちもどっち」論で片づけないと、気に入らないという、良くない意味での判官贔屓の書き込みが後を絶たないが、これも平和ボケのひとつなのだろうか。 それでは結局、「その人(SOHO)」の側がいつまでたっても現実の課題に気がつかず、よってそこから合理的な進歩や改善の道筋を見いだすこともできないだろう。 それなのにきちんと批判せずに、曖昧な両成敗論を求めることが、責任と道理ある見解といえるのだろうか。「『弱者』の味方」の方々は、そのへんまで考えて書き込んでいるのか、ぜひ伺いたい。
2003年12月27日
コメント(6)
-
つんのめった自称インテリはオノレを捨ててから門を叩け!
以前、東京近郊にある国立大学を出た女性の「ダブルブッキング」を例に出した(2月18日の日記)。そのときに書いたのは、 いくら名門大学や大会社に入ったことがあるといっても、それだけでスキルは保証できない。 ということだ。 これは、採用する側だけでなく、採用される側(つまり本人)もきちんと認識しておいてほしいことである。 根拠のない世間知らずの自信や自負が、仕事を進める上でマイナスになる場合があるからだ。 過日、ある「有名」大卒ライターの女性が、お願いした原稿に、「パラダイム」なる言葉を使っていた。 私は、2つの理由から、別の言葉に置き換えるように命じた。 ひとつは、「言葉の成金」原稿を認めないという私の方針による。 必然性のないカタカナ言葉や独りよがりの新造語を並べた、もっともらしいが中身のない原稿は表現者にとって恥である。「言葉の成金」とは、萩本欽一さんが教えてくれた戒め的な表現である。けだし至言だ。 もうひとつの理由は、(このときはこれがより問題なのだが)「パラダイム」という言葉自体が問題だったからである。 トーマス・S・クーン初出のこの言葉は、科学史上の「一定期間の規範」という意味で使われたが、そもそも科学的な用語として認知されているわけではない。 ところが、それが一人歩きして、今では「物の考え方」「概念」「計画」「潮流」「段落」等々、様々な意味合いで安易に使われ、もはやクーンの意図すら大きく逸脱してしまった正体不明の便利言葉に成り下がっているのだ。 おそらく、この大卒ライターは、「パラダイム」についてそこまで知っていたわけではなく、たんに、「格好いい言葉でまとめたい」という安直な気持ちで使っただけだと思う。 残念ながら、そういう見せかけを私は許さない。そんな「成金」ではなく、もっと地道な原稿を書いて欲しいのだ。 ところが、私の指示に彼女はこう答えてきた。「パラダイムという言葉を知らない読者たちの水準を合わせるという意味で、直すことにします」 負けず嫌いは勝手だが、こちらはそういうことを言ってるんじゃないだろう。 安易に、問題のある言葉を使っているという反省をしようとせず滑稽に突っ張っている彼女に、私は失笑を禁じ得なかった。 また、同じ原稿だったが、ある事実について、認識不足としかいいようのない間違いも見つかった。 そこで、そちらについても、正確な事実関係を説明した上で直すように指示すると、今度はこんな回答が返ってきた。「そのこと(正確な事実関係)は知っていました。ただ、もしもそうじゃなければ、という展開で書いてみても面白いと思ったんです」 さすがにこれには、開いた口がふさがらなかった。 誰も「ドリフのコント(もし……なら)」を書いてくれと頼んではいないのだ。 もちろん、これまたデマカセの言い訳であるろう。要するに、自分が無知であるという理由で突きつけられた直しは、ご自分のプライドが許さないらしい。 しかし、そんな「プライド」にいったい何の意味や説得力があるのか。 少なくとも使う方は、そんな自称インテリとは面倒くさくて金輪際お付き合いはゴメンだ、と思うだけである。 何より本当のインテリになりたかったら、間違いが発覚したところからが大事ではないのかな?「なんちゃってSOHO」は、男社会で勘違いした女性という生き物の象徴かもしれない。無知を恥じずに開き直って甘えるか、もしくは無知を強引に糊塗してつんのめっているのか……。 自分の能力は他人にも自分にもごまかせるものではないし、また何の努力もなく思い通りになれるわけでもない。 ありのままの自分を冷徹にとらえ、そこから地道に頑張るということを考えてみたらどうなんだろうか。学問がそうであるように、仕事にも王道などはないのだ。あったら誰も苦労などしない。
2003年12月23日
コメント(9)
-

岡田可愛さんに見る、観念論と唯物論
以前も書いたように、弊社は何でも屋としていろいろなジャンルの仕事を引き受けている。政治家、財界人、技術者、学者や弁護士・医師などのスペシャリスト、さらには芸能人を含めた有名人へのインタビューもある。もう何百人会ったかわからない。 ある同業者によれば、インタビューという仕事は、ヨイショ仕事だから30過ぎたらやるものではないというが、私はその意見に賛成していない。 それはさておき、これからの日記は、私がインタビューした貴重な体験の一部もご紹介していこう。皮切りは、初期の青春ドラマと、某製薬会社のCMで、60年代後半から70年代まで青春スターとして活躍した岡田可愛さんだ。40代以上なら、いわゆる“カワイスト”だった人も少なくないだろう。 80年代以降は、結婚・出産で一時期芸能界をお休みし、復帰後はコメンテーターやレポーターを「副業」にして、夢一杯のアパレルメーカーを立ち上げた。曰く「幼稚園に子どもを送り迎えするお母さんたちに、廉価でおしゃれな服を作りたい。子育て中はおしゃれに無頓着でも仕方ない、という先入観を変えたい」 芸能人の事業といっても、岡田さんの場合、知名度を利用した名前貸しではない。自宅を担保に資本金を作り、名刺を持って自ら営業するところからはじめている。 岡田さんは言う。「自分の置かれている環境をデメリットと思わないこと。子供がいるからとか、夫の協力がないからとか、人のせいにしていたら自立はできない」 もちろん、女性だから不遇だとも思わない。「男社会を逆手にとる。女だからこそ入り込める部分もあるから」逆転の発想であるが、理にかなっている。そして「勝ち組を羨んでいる暇があったら、自分が勝ち組になれるよう頑張ればいい」とあっけらかんと笑う。 現状を嘆いたり、成功している人を妬んでも何もならない。自分の手にしたいものに向かって努力するしかないということだ。 といっても、子役出身の芸能界育ちだった「一介の主婦」にとっては、子育てとの両立も含めていろいろ辛いこともあったようだ。「失敗なんて怖くない」(ケイエスエス)という岡田さんの本に、具体的な苦労が書かれている。 中身は、夢をもったものの、世の中は厳しく、それだけではだめだった。挫折の中から、合理的な解決法を見いだしてここまでこれた、というような内容である。 ここにリンクされている只野一生氏も紹介されていたが、「失敗なんて……」には、いろいろな名言が出ており、中でも圧巻なのは、「何とかしなければ何ともならない」という一言だ。 その一言にこそ、岡田さんの世界観があらわれている。 岡田さんの話は、一見、夢に向けての精神論に見えるし、事実それは含まれているが、女性にありがちな、「願っていれば夢は叶う」式の待機主義をはっきり否定している。かといって、ただたんに「がんばれ、がんばれ」と発破をかけるだけの根性主義者でもない。精神的な欲求を大事にしながらも、合理的に解決するという立場をとっている。 そう、岡田さんはクリスチャンだが、人生の考え方は合理的な思考を貫く唯物論者である。「世の中には輪廻転生を信じている人もいますが、それを信じる人も信じない人も、今の自分の人生が1度きりという点では同じ事。1度しかない人生を悔いのないように過ごしましょう」という岡田さんの物言いには、「輪廻転生を信じている人」も反論はあるまい。 岡田さんのこうした考え方は、哲学的にも学ぶところが多い。 物知らずは、合理主義的な考え方と精神論、つまり、理性と感性を区別する。そして、理性的考えを冷たいもの、一方で、観念的な思考を崇高なもののようにとらえがちだが、そうやって理性と感性をバラバラにとらえ、対立するもののように位置づけることは、人間の思考や行動を現実的にとらえていないナンセンスな考え方だ。 人間は夢や希望があるから幸せに生きられる。しかし、脳内に描くだけでそれは獲得できない。実現に向けての課題に噛み合う努力から逃げてはならない。自己実現には、理性・感性、どちらも連関した形で必要なのである。 いずれにしても、私も子持ちの女性労働者という立場から、岡田さんには教わることが少なくなかった。 嫉妬とコンプレックスと猜疑心と他掲示板でのヲチスレ作り(笑)に血道を上げる一部「なんちゃってSOHO」も、消化試合人生に陥らずに少しは岡田さんを見習って欲しい……、といっても無理だろうなあ。ふふ。 ちなみに岡田さんは達筆である。事務所移転の直筆通知を頂いて、ビックリした。文字も、相手に与える印象としては重要なファクターであることを改めて教えていただいた。
2003年12月01日
コメント(2)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- 100円ショップ
- ディズニープリンセス ファスナーケ…
- (2025-11-25 23:00:05)
-
-
-

- handmadeのある暮らし。
- ☆木の紙でつくる箸置き☆
- (2025-10-15 19:03:58)
-
-
-

- DIY
- 子ども部屋DIY|押入れが“おこもりス…
- (2025-11-25 18:00:05)
-