2007年07月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-

7月の「おしゃれ手紙」:2つのサイト集
「日記才人」は、日記、今で言うところのブログ を集めたサイトでした。今では、沢山のサイト集がありますが、「日記才人」はその草分け的なところ。私は、2002年から登録して、いろんな方と知り合いました。「ピコとチロの部屋 」で懐かしい昭和を語る、てんとう虫さん。今も楽天で行き来している、haseppe先生。そのhasepe先生を通して、知ったのは、「教官不定期日誌」。その「日記才人」が7月第2週の週末に閉鎖。「日記才人」の管理人様、長いあいだ、ありがとうございました。m(_ _)m今、私は、 ◎人気blogランキング「環境問題」◎に登録しています。クリックしていただけると、ためになるブログが読めます。ちなみに、私は、今日は、50位中、45位。 _| ̄|○でも、知り合いも出来て楽しいです♪ *イラストは、ガラスのマドラーのつもり。 ■□■今月の書き残し。■□■*冷蔵庫ネタ といっても、チュートリアルの漫才ではありません。( ̄m ̄*)*新しいテレビ*小田実氏死去「なんでも見てやろう」*津山のごんご★7月に見た映画★23■□■ ボルベール 帰郷 ■□■7.1124■□■キサラギ■□■7.11■□■先月までの書き残し。■□■*介護医療。*中国の田舎の風景。*中国のトイレ。*食事のマナー、日本と中国。*格差婚:藤原紀香と陣内の結婚式*松江*大根島*三方よし*須磨*庭園美術館*京都のフレンチ*京都の鯉*根雨*長崎市長のこと*四国(内子、砥部その他)*琴平さんの電車*温泉の憂鬱*田辺聖子「難波のゆうなぎ」*淀屋 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月31日*言葉の謎:まむし/民家:民家は人間の作った最大の民具*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.31
コメント(2)
-

冷蔵庫が壊れた。
質問です。8年前に買った冷蔵庫から水が漏れはじめました。A修理して使う。B新しいのを買う。どちらがエコなんでしょう?A修理して使う。この欠点は、8年前の冷蔵庫の部品があるかどうかということ。一方、利点は、ごみが出ないこと。B新しいのを買う。の欠点は、ごみになること。利点は、新しいものは、省エネタイプ!さあ、どうする・・・。迷った結果、新しいのを買うことに・・・。お互いのいいとこどりで、ハコはそのままで、冷却装置を省エネにするという修理はないのだろうか。ところで、「サステナ・ラボ」さんで知ったのですが、家電量販店で一番、環境への取り組みが進んでいるのは、「コジマ」だそうです。「チャレンジ省エネ50%」ってすごい!! ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月29日*子どもの夏服今昔/うなぎの蒲焼 *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.29
コメント(4)
-

夜上海(よしゃんはい)
5月20日(日)から24日まで、4泊5日の中国旅行の最後は、上海(しゃんはい)だった。上海は揚子江(ようすこう)のほとりの中国第2の街。 街中に車が溢れかえっている。街の景色も決して美しいとはいいがたい。オウヤン・フィフィに似た中国人の添乗員は言う。「上海は『夜上海(よしゃんはい)』といわれ、夜がきれいです。これからも次々に新しいビルが建ってきれいな夜景が見られますよ♪」(夜景写真集)電力を消費する、コテコテの夜景はいらない!美しい街並みが見たい!!夜景を売り物にするのは、昼間の景色が汚いから。パリのように、街全体が統率がとれている街では、夜景をウリにする必要がない!!揚子江をもっとアッピールせんでどうする!!揚子江は、上海のいや、中国の宝なのに・・・。その上海の宝、揚子江は、水不足の首都・北京の水として使うため、もっていかれようとしている。 ◎人気blogランキングへ◎*中国旅行*■1■5月20日(日)大阪から杭州へ。杭州市内観光。中国と日本の時差は日本の方が1時間早い。■2■5月21日(月)安徽省(あんきしょう)南部の古村落世界遺産・西逓(せいてい)宏村(こうそん)。世界遺産・黄山(こうざん)。■3■5月22日(火)世界遺産・黄山杭州踊りショウ(OP)■4■5月23日(水)西湖(さいこ)水郷・鳥鎮(うーちん)上海雑技団OP■5■5月24日(木)豫園(よえん)新天地帰国■旅日記■■旅のエコ ■■環境用語:フードマイレージ ■■中国は今日もうす曇■■世界遺産・中国・宏村(こうそん)と水今昔■■世界遺産・黄山の強力(ごうりき)の憂鬱 ■■水郷の町・鳥鎮(うーちん)■◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月27日*ひのつじ*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.27
コメント(0)
-

昔語り:夏の暮らし
子どもの頃、うちには、クーラーがなかった。クーラーは、おろか扇風機もなかった。あるのは、ただ、店でもらった団扇(うちわ)だけ。夏になると、夏ならではの暮らし方をしていた。まず、家中の障子という障子がすべて、取り外された。南向きの家は、南北に大きなはき出し口があり、風の通り道が出来た。麦わら屋根の深いひさしが強い太陽の日差しを家の中にいれないようにしてくれた。父が祖父と作ったという広い土間は、ひんやりとしていた。家の西側には、竹やぶがあって、季節になると筍が食べられ、竹細工の材料になるばかりか、強烈な西日から家全体を守ってくれた。外には、たらいを置いて行水用の日向水を作っておいた。夕方になると、スイカを冷やした水や行水の残りの水をカドとよばれる庭にまいた。欄干も手すりもない、土で出来た橋の上はどこよりも涼しいところだった。夜になると、橋の上で花火を楽しんだり蛍を追いかけたりした。夜になっても戸も障子も開け放したままだった。若者が橋の上にで吹く哀愁をおびた口笛が夜の闇に聞こえると私はなぜか悲しくなったが、蚊帳の中でいつの間にか眠った。あの頃、私は夏が大好きだった。50年前の夏・・・。あの頃、朝起きるとラジオ体操に行って、水汲みをし、川で泳いだ。家の前のキュウリやトマトや茄子・・・。父が切ってくれる、サトウキビの甘さ。昼寝の後のスイカ。行水、蚊帳、花火・・・。夏に一回はやった校庭映画会。カワニナをとることも川で洗濯することもカンピョウを剥くことも干すことも・・・。生きるためにやったことがすべての思い出が、今は大事な宝物になっている。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。やっと修復したと思ったら、過去のデータが無くなりました。。・゚(´□`)゚・。★7月26日*下駄の日/籐の乳母車を見た!/父の麦わら帽子 *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.26
コメント(6)
-

マヤ文明に学べ!:戦わない工夫
中央アメリカに広がる熱帯雨林。鬱蒼と密林が茂り、大きな川もないこの過酷な地で古代マヤ文明は誕生・発展した。およそ70あまりの都市が点在し、厳しい自然条件の中で、お互いを滅ぼし合うことなく共存し、文明を支えていたマヤ文明。お互いを滅ぼしあうことのない、さまざまな工夫がされた。■戦いの日を決め、その日しか戦わない。天文学に長けていたマヤでは、戦いの日を決めていた。年にたった一日だけ!!それ以外は戦わない。現代においては、クリスマス休戦というのがある。がしかし、クリスマスににみ休むのではなく、クリスマスにのみ戦うのであれば、戦いの日は圧倒的に減る。■戦うのは、王と貴族のみ。普通の人が戦いには行かない。日本だったら、天皇とその親族、安倍総理と大臣のみ?アメリカだったら、ブッシュとその内閣?■生け捕られたら負け。致命的なことをしない。貴族や王が生け捕りにされた方が負けになるが、その後もその王家は存続する。アフガンのタリバンが拉致した韓国人23人を全員殺害すると警告している。拉致されたのは、全員普通の市民。アフガンには、韓国軍、約200人が駐留している。韓国の兵隊たちも除隊すれば普通の市民。一般市民が戦争に巻き込まれるなんて、まっぴら。それに、そのために、戦闘機が飛ぶなんて、まっぴら。そして、その戦闘機は、CO2を撒き散らし、地球はますます温暖化するなんてまっぴら。■究極の雨水利用:マヤ文明 ■ ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。ただ今、停止しています。m(_ _)m・・・・・・・・・・・・・
2007.07.25
コメント(2)
-

グーグルの環境戦略
新潟県中越沖地震がおこって、柏崎原発からが危機一髪というところだったのに、脱原発の声は聞かれないどころか、節電しましょうという声さえ聞かないのは、どうして?■そんな時、検索最大手グーグルが6月、カリフォルニア州マウンテンビューの本社で1.6メガワットという大規模な太陽光発電を稼動したというニュース!ヽ(゜∀゜)ノこれだけで、本社のピーク時の3割をカバーできるそうです。グーグルは、環境問題に熱心なスタッフが多く、その他いろんなことをやっています。例えば・・・。■社員を送迎する無料のコミューターバスを150台以上運行し、1200人がバス通勤している。しかもガソリンはバイオディーゼルを使っている。■机や椅子などのオフィス用品が壊れたらメーカーが引き取って再利用することになっており、最終処分場に行くことはない。■紙やペンなども環境配慮型製品にしている。■グリーン調達の専任担当を置いている。■ランチ、ディナーにこだわっている。社員食堂ではすべてオーガニック食材を取り入れている。さらに可能な限り、オフィスのある地元で取れた食材を優先的に使うようにしている。トラックで遠くから食材を運ぶより環境負荷が低い。テイクアウト用の食事を入れるトレーはコーンスターチなどでできた「土に帰る」素材にしている。■従業員が学ぶ機会になっている。■その結果、オフィスだけでなく家でも環境に配慮した生活を送れるようにしている。すごいな、グーグル!!太陽発電装置は、シャープなのに、日本の企業は、どうなってるの?日本もグーグルを見習うべし!! ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。・・・・・・・・・・・・・
2007.07.23
コメント(0)
-

「六花(ろっか)」カフェと喫茶の間
ザ京都といった感じの白川巽橋から遡ること約5分。 柳の木が両岸に並び、行者橋という細い石橋のある白川になる。知恩院から平安神宮へ抜ける白川の道の辺りにあるレトロな雰囲気の古川町商店街があり、その商店街のちょっとはずれたところに「六花(ろっか)」はある。大通りにあるのでもなく、商店街の中にあるのでもなく、川のほとりにあるのでもない・・・。隠れ家のようなところに喫茶・六花はある。 去年、初めて行った時に、「あっ、このカフェ・・・」とひらめくものがあった。そこには、ぬまげんこと、*沼田元気*のチラシがあった。持ってかえって、今も大事にとっている。先日、また行って写真を撮ってきた。 看板の字も窓に飾ってある小物も、キャンドルスタンドも、昭和喫茶を思わせるような、ガラスブロックも、青いビロードの布ばりの椅子もどこか、懐かしく、のんびりとして、かわいらしく、このカフェにふさわしい。カフェと喫茶の間のような場所。■喫茶 六花■なんとなく雨の日が似合う喫茶店がある。喫茶六花。何故そう思うのか。きっと一人が似合う喫茶店だからと思う。 喫茶 六花 喫茶・ランチ京都市東区白川筋三条下ル3丁目唐戸鼻町562-1 電話075-541-3631 営業時間9~18時 ※水曜定休 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。・・・・・・・・・・・・・
2007.07.22
コメント(2)
-

究極の雨水利用:マヤ文明
密林が生んだ二千年の王国。失われた文明・インカ・マヤ。中南米の文明ってほんとうに神秘的!!といつも思っていた私が飛びついたのが「NHKスペシャル・失われた文明 インカ・マヤ 密林が生んだ二千年の王国 」その第3回目がマヤ文明。そこには、驚きの水利用があった!!降った水は、残さず、池の集める。そのために、漆喰で舗装をしている!!しかも、ほんのわずかに、傾斜をつけて、流れやすいようにしている。溜めた水は、使い、その使った水さえも、畑に使うなど2次的に使っている。密林に位置するマヤの古代都市・ティカルは、当時、中心部だけでも6~7万人の人口を擁する大都市だった。だが周辺に水源はなく、また大地が石灰岩だったために雨水は地中に吸い込まれ、しかも地下水位が低く井戸を掘ることもできなかった。この過酷な条件のもとで、人々は120日にもおよぶ乾季にどのようにして水を確保していたのか。そこには、ある巧妙な仕掛けがあった。都市の地表は、雨水が浸みこまないように石灰岩を利用した漆喰(しっくい)で塗り固められていた。しかも地面には0.76度という微妙な傾斜がつけられ、雨水はその先にある貯水池に導かれていた。つまり、都市全体を巨大な漏斗(じょうご)のような造りにすることで水を確保していたのである。さらには、高台にある貯水池の水は、使用後にはその下方にある貯水池に流れ、再利用されていたとも推測される。水循環システムまでが盛り込まれた雨水利用システムである。・・・・・すごい!!都市ごと、雨水利用してる!!しかも再利用も!!今の時期、日本は、必ず雨が降る。そのことが分かっていながら、いつも被害が出たといっている。このことを考えると、本当に科学って進歩してるのかと思う。もっと、謙虚に昔の知恵を生かす暮らしをしなければいけないと思う。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月21日*三日三晩の土用干し・梅干/ 土用餅 *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.21
コメント(4)
-

京の始末:にばんや
「よそさんにも教えたい京都のお作法」という本を読んだ。*町家と祭の記憶*ぶぶ漬けと一見さん*ケチと始末*にばんや*包むという美学*ほめ方いろいろ・・・。などなど興味のあることばかりだった。中でも、「にばんや」の項は、面白かった。かいつまんで書くと以下のようになる。***京都の西陣には、にばんやとよばれる店があちこちにあった。文字どうり、「一番屋」ではなくて「二番屋」。昭和30年代には、まだあったと思われるが、いつの間にか姿を消した。にばんやは、残った糸、余った糸をやりくりするところだった。人件費よりも高いといわれたた絹糸。余った糸、残った糸は捨てるものではなかった。いろんなところによみがえる場があった。しかし、運ばれてくる糸は、色も多彩なら、長さもまちまち。これがにばんやにとってありがたかった。規模の大きな織屋なら、どんな色糸もそろうだろうが、自宅に機を一台置いてあるようなところもある。そんな零細な所では、ほんの少ししか使わない色糸に沢山染めなくてもにばんやに行けば、色糸の中からどんな色だった探すことが出来た。ここににばんやの存在意義があった。10センチ、20センチの糸も捨てずに、にばんやに持っていけばよみがえったし、10センチ、20センチだってわずかなお金になった。無駄遣いをせず、ものを大切に使うという「京の始末」は、見事に、にばんやに生きていた。***今は、残った糸はおろか、布さえも、大事にしない世の中。100円ショップに行けば、新しいものが買えるのに、大事にする必要がないからだ。心ある人たちの気持ちだけでは、本当にものを大事にする社会にはならない。まず、社会の構造を変えなければ・・・。ほんの少しのものでも、商売になる社会であってこそ、本当のリサイクル社会はなりたつ。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月19日*食い初め/ブログのチカラ:へんなれぽんなれ*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.19
コメント(0)
-

「菊次郎とさき」*吊り下げ手水(ちょうず)
*「菊次郎とさき」*第2回目。雨でペンキ塗りの仕事が休みとなった父・菊次郎(陣内孝則)が一人酒を飲んで留守番をしていた時、こっそり学校を抜け出した武が、財布から千円を抜き取り、父、菊次郎に罪をなすりつけるという話。父・菊次郎は、縁側で留守番をしていたのだが、縁側の軒下に、バケツのようなブリキのものが吊り下がったいたのを私は見逃さなかった。おお、懐かしい、手水(ちょうず)だ!!武の子どもの頃は、トイレ(というより便所)は縁側の突き当たりにあった。その頃は、便所の後の手洗いは、今のように水道でジャーというわけにはいかなかった。で、便所の近くの縁側に吊ってあったのが、手水(ちょうず)。ブリキで出来た、バケツよりも少し小さめのもので、下を押すと水が、ちょろっと落ちた。(そのわずかな水ででさえ、地面にかえした。)それで手を洗って、そばにぶら下げている手ぬぐいで、拭く。手水(ちょうず)の水は、いつもなくならないように大人が気をつけていたのだろう。だろうというのは、私は田舎で育ったので、手水はなかったからだ。その代わり、外に水がめがあった。この手水のことを書こうとして、はたと困った。本当の名前が分からなかったからだ。で、探したらあった。極東ブログさん。写真ここ。バケツいっぱいで家族が一日は手を洗えたことだろう。いったい今は、一日に昔の何倍、ひょっとしたら何十倍水を使っているのだろう?昭和30年代は、まだ、今のように、ものを浪費する時代ではなかった。そして、その象徴が、この吊り下げ手水だ。**「菊次郎とさき」**不世出のお笑い芸人ビートたけしの父・菊次郎と、母・さき。このふたりの人生を息子のビートたけし自身が描いたドラマ■「菊次郎とさき」:いとしい日々昭和30年代への賛歌■■「純情きらり」と私の昭和■ ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月17日*民具:民家*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.17
コメント(4)
-

「醜い国ニッポン」
かつて美しい自然環境と豊かな文化遺産を誇った日本は、今は見渡す限りのコンクリートと看板、電線に埋め尽くされている。それらの風景を深い知識と審美眼、そしてなによりも、日本への愛情を持って、ユニークに批判するのが、在日歴40年のアメリカ人、アレックス・カーである。「情熱大陸」2007.7.15放送の「情熱大陸」は、醜悪な現代の日本の姿に怒り悲しみしみ、行動するアメリカ人、アレックス・カー氏。カー氏は、醜い日本の看板や街の風景を写真に撮って、公演会などで使う。指摘されて、気がつく日本人。もう、醜悪な景色になれているので、感覚が麻痺してしまったのか・・・。 月に一度、夫と旅行するが、その度に、楽しいことと同じくらい、いや、その倍の嫌な日本の風景を見てしまう。その度に、悲しくなって、腹が立ってくる。今年の3月に四国に行った時もそうだった。はじめて行く、徳島県の秘境、祖谷(いや)。祖谷川にかかる「祖谷の吊り橋」は、国の重要有形民俗文化財に指定されている。その吊橋の正面に、あったのが、この風景・・・。 私は、写真は上手くないし、美しいものを撮りたいと思う。だけど、これだけは、撮っておこうと思った。かつて、平家の落人たちが、ひっそりと暮らしたという、伝説の地、祖谷(いや)に、なんでこのような工事をするのか・・・。これだけではなく、大型バスの駐車場や、道路を作って、もはや、秘境という言葉は、恥ずかしいような所になっていた。「美しい国、ニッポン」なんて、おかしい。醜い国、醜悪な国、ニッポンではないか・・・。かつて、日本には、美しい町や村があった。それら古い家には、瓦の色、高さ、間取り、材料・・・。全てに秩序がある。ところが、新しい家ときたら、3階だてあり、ビルあり、色もバラバラ、形もバラバラ・・・。統一感のない町になる。アレックス・カー氏は言う。「新しいものを作ることが悪いんではない。作った新しいものが、醜いからいけないんだ」と。 ◎人気blogランキングへ◎■醜い国日本■ 街のあちこちに妖怪が・・・。これが、客を呼ぶなんて、悲しすぎる・・・。。・゚(´□`)゚・。 木の幹にぐるぐるを電線?を巻いていた。豆ランプでもつけるのか? 京都の市街地を流れる高瀬川。普通は、左のように石で出来た、護岸ですが、一部、コンクリート丸出しのところが・・・。 日本中どこでも、ルミナリエって、欧米か! _| ̄|○ 野仏に花ってステキだけど、花入れが、プラスチック・・・。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月16日*里山の歌:われは海の子 *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.16
コメント(4)
-

「太田総理・・・」:車に乗らない人が得をする
オワライ芸人、太田光を「内閣総理大臣」に、現職国会議員やタレントゲストを「議員」に見立てて、テレビ内で討論する、番組「太田光の私が総理大臣になったら・・・秘書田中」(略)「太田総理・・・」)を見ている。先日は、「全ての買い物に環境税を!」という「マニュフェスト」での討論。残念ながら、「全ての商品に環境税を導入します」法案は、「可決」しなかったものの、視聴者の投票では、賛成が多い!。 私は当然賛成だけれど、今ギリギリの線で生きている人も多い世の中。で思うのだけれど、環境に優しい人が優遇されるという世の中にしたらどうだろう。例えば、日本が1年間に排出するCO2のうち、クルマによるものが、全体の約20%におよぶという事実。車の方が便利、安いから車が増える。これを、車に乗ると高くつく、車に乗らない人が得をするという社会に変えないかぎりいつまでたっても車は減らない。そこで「車に乗らない人が得をする法案」。車の免許を持っていない人は、毎年、一定金額の無料乗車券を配布。その上、公共運賃が、激安。50キロ圏内だとどこに行っても、何回乗り換えても100円。遠くへ行くのも今の半分以下。新幹線運賃は、無料。町のどこにでも、乗り放題の自転車を置いておく。などなど・・・。もちろん、この費用は、国が負担。高速道路を日本中に作ったり、それを管理したり、はたまた、お役人の天下りで使うお金を回せばいいだけのこと。 「車に乗らない人が得をする法案」に清き一票を!!m(_ _)m ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月15日*なめすじ/子どもの夏服今昔 *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.15
コメント(4)
-

「キサラギ」★小栗旬
■「キサラギ」公式サイト■ (音が出ます)を見てきました。■あらすじ■2006年2月4日夜、C級アイドルの如月ミキは自宅のアパートで焼身自殺(警察の見解)。2007年、その1周忌に、とあるビルの一室に集まった5人の男たちがいた。思い出話は次第にヒートアップしてゆく。そんなとき、誰かが呟いた「彼女は殺されたんだ……自殺なんかするわけがない」と。この発言が引き金となり、怒涛の議論へ。二転三転する推理。果たして彼らは真相にたどり着けるのか?そして彼らの正体は?「インターネットで知り合ったオタクたち」というところにひかれて、見に行ったのだけれど、これが面白いのなんのって。次々に謎が出てきて、それが解けたと思ったとたんに次の謎が現れるという、息つく暇もない展開。家元:小栗旬 オダ・ユージ:ユースケ・サンタマリア スネーク:小出恵介 安男:塚地武雅 イチゴ娘:香川照之 という5人のオタクたちのなかで、私がいいなと思っているのが小栗旬。「花より男子2」で華麗なる男の子達、F4の花沢類を演じていたのを見て以来、ファンに。「花より男子(だんご)2(リターンズ)」では、飄々とした、クールな彼が、「キサラギ」では、如月ミキに夢中のオタクを演じていた。「キサラギ」で思ったのだけど、小栗旬君の声っていいわ。萌え~♪( ̄▽ ̄) 。「キサラギ」の舞台は、一周忌のオフ会の部屋だけ。これをワンシュチュエーションドラマというそうです。ラストのオタクダンス、すごくいい♪超オススメの密室サスペンス・コメディ。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月14日*なめすじ*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.14
コメント(2)
-

「菊次郎とさき」*印半纏(しるしばんてん)
不世出のお笑い芸人ビートたけしの父・菊次郎と、母・さき。このふたりの人生を息子のビートたけし自身が描いたドラマ『菊次郎とさき』の第3作目が先週の木曜日から始まりました。2003年、2005年とほぼ同じ顔ぶれ。■あらすじ■ 舞台は昭和30年頃。昭和のノスタルジーが色濃く残る、狭い長屋の生活が背景です。まるで落語の登場人物のように、破天荒な生き様の菊次郎。異常なまでに教育熱心なさき。そして貧乏な家族たち。時にはちゃぶ台が倒され、言いつけを守らない子どもは両親に引っ叩かれるかもしれません。でもそれをただの暴力と言ったら、北野夫婦に怒られることでしょう。そこには、今の日本人が忘れかけた“家族の絆”があるのです。 ・・・・・・・・・・昭和30年代といえば、私の子ども時代。私は去年、「純情きらり」と「私の昭和」というタイトルで、昭和な懐かしいものを取り上げてきました。今回もまた、懐かしいものがいっぱい!!!+++第一回目は、◆印半纏(しるしばんてん)◆父の日に子どもたちが、菊次郎に感謝する会をもうける。菊次郎は、張り切って、紋付であらわれる。がしかし、子どもたちは、「父ちゃんは、これが一番だよ」と印半纏を着せる。◆印半纏(しるしばんてん)◆襟・背・腰回りなどに屋号・氏名などの印を染め抜いた腰丈の半纏。主に木綿製。江戸後期から職人の間で用い、また、雇主が使用人や出入りの者 に支給して着用させる。胸紐がないので、手拭いを帯代わりに結んだりする。 法被(はっぴ)。印半纏は、ペンキ屋を営む、菊次郎のユニホームのようなもの。菊次郎をはじめ、このドラマには、職人がよく出てくる。職人以外にも、母、さきもよく働く。仕事といってもマネーゲームのような今の社会と違って、どの人たちもみな額に汗して働く人ばかり。私の家でも、父は、木綿のズボンと夏でも、木綿の長袖、それに麦わら帽子を被っていた。あの頃の大人たちは、今の私たちよりも堂々としていた。それは、働いているという実感がそうさせたのだろか。菊次郎の印半纏は、働く男の誇りの象徴のように見える。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月13日*買物今昔:やみかごからレジ袋/「全国アホバカ分布考」/命の重み *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.13
コメント(0)
-

子沢山は偉いのか。
最近、気になることがある。それは、子沢山の家庭を褒める風潮。先日、テレビで、某子沢山弁護士に対して、ある毒舌家の女性が言った。「あななたのいいところは、この少子化のご時勢に子供を7人も持ったということですよ」と。また先日の蒜山(ひるぜん)旅行のさいには、こういうことがあった。それは、夜のコンサートの時の自己紹介。「先々月、子供が生まれました。他のメンバーに子供の数を言えと言われました。4人目です」とある女性。拍手がおこった。あるアメリカの学者の試算によると、地球環境を変えずに現在のアメリカ人の平均的生活を維持しようとすれば、地球人口の制限は2億人だという。(大江戸リサイクル事情より)2001年の世界の人口は61億3千万人と推計されている。今年の世界人口は、約66億人。たった5年の間に、日本の人口の3倍の5億人近くが増えたことになる。このままいけば、2050年には世界の人口は93億人になるという。 人口の急激な増加は、食料不足・水不足・環境問題・資源の枯渇・住宅不足・貧困の増加といった問題を引き起こし、世界各地で起こっている様々な紛争の原因にもなっています。子供はかわいいけれど、4人もいなくても、いいではないですか。ましてや、7人もいなくても、いいではないですか。人口問題とは、地球規模で取り組んでいかなければならない課題なのです。今日、7月11日は、世界の人口のことを考える日、「世界人口デー」です。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月10日*民具:筵(むしろ)とかます/ *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.11
コメント(12)
-

ダイエット宣言
1月:伊勢志摩に1泊、2月:淡路島に1泊、3月:四国に2泊(フェリー1泊とホテル2泊)。4月:24日(火)~26日、山陰地方2泊。5月:中国(4泊5日)。6月:30日~7月1日(蒜山、大山)1泊。今年前半、夫と行った旅行。月に一回の割合で行くようになったのは、去年、リストラになった私が、休みがとれるようになったから。泊まる先々の温泉で思う。「みんな働いている時に悪いな・・・」と。でも、私も、かつては、年末など土曜日も日曜日のなしで25日間働いたことがあるし、いいか・・・。もうひとつ思うことは、「みんな肥ってる・・・」 _| ̄|○ぼってりとした、腹や肩や背中・・・。その度に、わが身を振り返って、寒々をするのだけれど、食べる時には、忘れることにする。おかげで、2キロ肥った。(ノД`)お粥とプリンとヨーグルトしか食べられなくなって、7キロ痩せてしまった3年前。あれから、頑張っていたのに・・・。細身のシルエットの服も着られたのに・・・。世界には、飢えで苦しむ人が、飢えで死ぬ人がいるのに・・・。よし、これからは、ダイエットのため、食事をひかえよう。私ひとりが、食事を我慢しても、世界の食物事情は変わるまい。がしかし、飢えた人の気持ちのほんに一部でも共感することが出きるかもしれない。 ◎人気blogランキングへ◎ 2007.1月 2007.2月 2007.3月 2007.4月 2007.5月 2007.6月●上の写真は島根県・大根島の牡丹園の牡丹。◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月9日*遊び歌:子とろ*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.09
コメント(2)
-

植物観察はトリビアの泉
私たち夫婦は、よく国民休暇村を利用する。全国36箇所の国立公園、国定公園の中にあって、値段も手ごろ。ほとんどの所が朝7時半から30分、職員と一緒に、近くを散歩する。今年もすでに5泊していて、その度に参加。がしかし、休暇村の職員は、揃いも揃って、植物オンチ。 _| ̄|○がしかし、6泊目の今回は違いました。植物や鳥の名前を熟知している、人が先導してくれての、朝の散歩。双眼鏡とガイドブックをを貸してくれるサービス付き。以下、散歩道で聞いた、トリビア!★前回と同じようにコブシの木を見て、木の名前の質問にも「♪コブシ咲くあの丘北国の北国の春~・・・。のコブシです」と歌付きでの説明。ついでに、「コブシは実の大きさが人の拳くらいあるというところからつけられました」という語源も。へぇ~、へぇ~!!★イタドリを見つけると、「イタドリは、痛みをとる、イタミドリから名前がついたといいます。」へぇ~、へぇ~!!★ナナカマドという名前はは、七回竈にくべても燃えないというくらい燃えにくいところからきた。へぇ~、へぇ~!!★白い総苞が白いずきんをかぶった山法師を連想することから名づけられた「ヤマボウシ」。街路樹に植えられているのは、「アメリカヤマボウシ」。へぇ~、へぇ~!!★エゴノキの実をとって、小豆と混ぜて、お手玉に入れた。へぇ~、へぇ~!!★岡山県下には2500種の植物がるが、蒜山にはそのうち2000種がある。外来種が多いこと。それは、牧草として海外から、種を仕入れたから。(クローバ、ブタナ、ヘラオオバコなど。)欧米か!へぇ~、へぇ~!!おまけに、「あれはなんですか?」と参加者の指差すところにあるものを見て 「あれはスイトンといいます。この地方の精霊です。スイ~と飛んできて、トンと降り立つんです。」とのこと。へぇ~、へぇ~!!蒜山に来るたびに、気になっていたので、謎がとけて、ああすっきりした。この他にも★ハシブトガラスの語源。★ヒバリはなぜ、ピーチクと鳴くのか・・・など興味深い話がいっぱい。いつもは、朝7時半から30分の散歩が今回は、スタートは6時。同じコースが1時間を大幅にオーバーした。自然観察、自然体験などの活動を通して、自然を保護する心を育て、自然にやさしい生活の実践を促すため、自然が発する様々な言葉を人間の言葉に翻訳して伝える人をインタープリターという(interpret=通訳)。彼は素晴らしい、インタープリターだった。センス・オブ・ワンダー(神秘さや不思議さに目を見張る感性)をはぐくんだ人は、人生に疲れることはない。(レイチェル・カーソンのことば)**インタープリター**自然観察、自然体験などの活動を通して、自然を保護する心を育て、自然にやさしい生活の実践を促すため、自然が発する様々な言葉を人間の言葉に翻訳して伝える人をいう(interpret=通訳)。一般的には植生や野生動物などの自然物だけでなく、地域の文化や歴史などを含めた対象の背後に潜む意味や関係性を読み解き、伝える活動を行なう人を総称していう。一般には、自然観察インストラクターなどと同義に用いられることも多い。なお、インタープリターの行なう活動をインタープリテーション(自然解説と訳されることも多い)という。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月8日*「胡同(フートン)のひまわり」*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.08
コメント(2)
-

おしゃれはメッセージ
先週の土曜日、蒜山(ひるぜん)高原の国民休暇村に泊まった。ホテルのロビーで、夜7時半から地元の女性3人によるピアノとチェロのコンサートがあった。月に1回のペースでやっているとのこと。ラッキー♪さっそく、私たち夫婦も参加した。曲は、「花」、「上を向いて歩こう」、「蘇州夜曲」、「鳥の歌」、「メヌエット」、「川の流れのように」などなじみのある曲ばかり8つ。しみじみとしていて、どの年齢にも受け入れやすいし、いい選曲だと思った。がしかし、残念なことがあった。それは、服装。演奏する3人のうち2人は、ズボンだったし、頭もいかにもかまわないといったもの。アクセサリーも化粧もしていなかった。。 _| ̄|○演奏する人たちは、せめてワンピースくらい着てはどうかと思う。あるいは、白いブラウスに黒いパンツかスカートに統一するとか・・・。頭も、まとめて首筋がきれいに見えるようにするといいと思う。ピアノの演奏って案外、後姿が気になるから、頭の後ろにアクセントをつけるとか・・・。以前、オーストリアを旅した時、何回かコンサートに出会った。それは、野外コンサートだったり、場内だったりしたが、演奏家は、それぞれドレスアップしていた。聞く方も女性は、ワンピースにショールをはおっていた。夜が更けていくと、野外では、夏でも肌寒く感じられて、ショールは、実用とアクセントを兼ねたものなのかと、感心した。スイス・サンモリッツの小さなホテルでも、夕食後、ホテルのラウンジで、ピアノ演奏会があったが、客は、夕食の時の少し改まった服装で楽しんでいた。蒜山のホテルでは、聞く方も浴衣姿。もちろん、ホテル内では、リラックスできるように浴衣でもいいと思う。でも、こういう時は、少しおしゃれした方がいいのではないかと思う。私は、たまたま、今回はワンピースを着ていたが、いつもは、綿パンにTシャツ。次回からは、ワンピースを必ず持っていこうと思う。おしゃれは大事だと思う。改まった服装は、「私は、この場所を、この機会を特別に楽しもうとしています」というメッセージだから・・・。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月7日*「純情きらり」と私の昭和:方言/籐の乳母車 *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.07
コメント(4)
-

拝啓、大山(だいせん)のブナ林様
拝啓、大山のブナ林さま。6月30日、私は、初めて、あなたを知りました。もちろん、それまでにも、名前も知っていましたし、お会いしていたのかも知れません。でも、あなたについて、詳しく知ったのは、今回が初めて。大山(だいせん)一帯のブナ林は、西日本最大であること。ブナの大木1本には、50~60万枚の葉がついていて、秋になると落葉し、分厚い腐葉土になること。それは、降った雨を溜める、「緑のダム」ということ。ブナは、水分を多く含むため、かつては材木の価値がないと、乱伐さてた時代がありました。また、価値がないからと伐採を免れたことも・・・。ブナは漢字で木偏に無。木で無いと・・・。失礼ですよね。あなたこそ、男の中の男、じゃなかった、木の中に木なのに・・・。樹齢200年、幹の直径が、胸の高さで、75~80cmのブナは、木一本で8トンの水を貯える。8トンの水とは、500mlのペットボトルで16000本。家の平均的な浴槽で26~27杯分。25mプール2杯分だそうです。この水量で一反の水田がまかなえるというから、どんなすごい量か、私にも分かります。この保水力で、大山に降った雨を一気に流さないで、葉に溜め、幹に溜め、地中に溜めてくれていたのですね。そして、そっと、静かに湧き水として、かえしてくれていたのですね。ブナ林の地名に「一の沢」など沢のつくのがありました。それは、あなたが返してくれた、湧き水が沢となったものなのでしょう。もし、人間が、ゴルフ場など目先の利益のために、あなたたちを伐ってしまったら・・・。考えただけでも恐ろしいことです。今、地球では砂漠化が進んでいます。日本では、降った雨がいっきに川に流れ込んで、川の氾濫や、道路の冠水をよく聞きます。これは、木を伐り、地面をアスファルトで覆い、川の三面をコンクリートで覆った人間が受けた罰。それに懲りずに、今もまた「開発」という名の自然破壊が行われています。何百年という時代を生きたあなたたちは、そんな私たち人間をどんなおもいで見ているのでしょうか・・・。これからも、私たち愚かな人間をを見つめて欲しいと願わずにはいれれません。大山(だいせん)のブナ林さま。 天地 はるなより ◎人気blogランキングへ◎●デジカメを忘れて行ったので、写真は「大山の壁紙写真」をお借りしました。m(_ _)m◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月5日*天気のことわざ/旭川今昔*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.05
コメント(0)
-
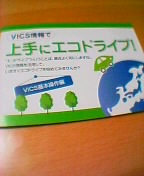
17.4%
日本が1年間に排出するCO2のうち、クルマによるものが、全体の17.4%におよびます。たとえば、最短ルートを選択することや、道路状況を先取りすることなどほんの少しの意識でエコドライブが実現できます。あらためて見直したいのが、渋滞回避。スムーズに走行できれば、無駄なエネルギー消費をカットしCO2の排出量も軽減されます。あなたも思いやりのあるエコドライブを。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月30日から7月1日にかけて、蒜山高原にある国民休暇村に泊まってきた。4月にも行ったばかりなのに・・・。 _| ̄|○写真のチラシは、途中、高速道路のサービスエリアでもらったもの。「エコドライブ」って、ドライブは、エコじゃないから、いくらがんばっても、「エコドライブ」という言葉はおかしい。車によるCO2の排出量は、17.4%というけれど、車を作る時にもいるから、本当はもっと高いのかもしれない。みんなが車に乗るのを半分にすれば、ただそれだけで、「チームマイナス6」どころか、「チームマイナス8.7」!!!本気で取り組めば、簡単なことだと思う。例えば、公務員の交通手段は、自転車か公共交通に限るなんていかがだろうか。公務員以外にも、市会議員や国会議員などもその例外ではない。もらったチラシは、コピーして、会社の近くで、アイドリングしている車のワーパーに貼ろうと思う。◎地球を救う127の方法:交通機関◎81.それでも、どうしても車が必要なら、出来るだけ燃費のよい車を選ぶ。82.気楽な相乗りが出来るように、日頃から地域に友人をつくる。83.車はマメに点検する。84.幅の広いラジアルタイヤはやめ、燃費を考慮した細目のラジアルタイヤを使う。85.空気の抜けたタイヤは、燃費を喰うので、タイヤの空気圧を少なくとも週一回は点検する。86.カー・クーラーはこまめに切る。郊外は窓を開けて走る。87.スピードは出さない。適度な速度を保つ。 ゆっくり加速し、なめらかに走行し、ゆっくりと減速する。88.ドライブプランをしっかりたてる。89.土、日曜、祭日、年末年始、盆休みは渋滞を思い出し、車を使うのを考え直してみる。+++今回は、6時に家を出たのですが、前回は5時でした。これは、渋滞する前に、大阪を出たかったから。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月2日*半夏生(はげしょう)のポチ団子/植物物語・ハゲショウと半生夏餅(はげしょうもち)*UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.03
コメント(0)
-

「昭和恋々」:麦わら帽子
昭和のはじめごろ、夏の子供たちは麦わら帽子か、白いピケの帽子をかならずかぶっていたものだ。このごろでは盛夏でも無帽の子が多いが、私たちが小さかったころは、日射病を恐れ、戸外(そと)へ出るとき帽子を忘れないように口うるさく言われたのを憶えている。「うたを忘れたカナリヤ」の西条八十(やそ)の詩に若かったころの母親を慕う「麦稈むぎわら)」帽子というのがある。”母さん、僕のあの麦稈帽子、どうしたんでしょうね?ええ夏、碓氷峠(うすいとうげ)から霧積(きりづみ)へ行くみちで渓谷へ落としたあ麦稈の帽子ですよ・・・”ここでは「麦藁」ではなく、「麦稈」という字が使われている。最近は、「麦稈真田(ばっかんさなだ)」といっても誰も何のことかわからなくなってしまったが、昔は子供だって知っていた。麦わらを真田紐のように編んだもので、これが麦わら帽子の原料だった。岡山、広島、香川が産地として有名だったが、いまはどうなのだろう。このごろは「日射病」という言葉さえ、あまりきかなくなった。「昭和恋々」久世光彦子どもの頃の遊び友達に、お祖母さんと暮らす子がいた。彼女の家には、台の上に乗った丸い木の型が何個かあった。当時は、何気なく思っていたのだが、あれは、頭の型だ。あの型を使って麦わら帽子を編んでいたのだ!麦稈真田は、岡山県南部地方で女性の副業として盛に作られたこと。私がその友人と一緒に遊んだのが、昭和30年代の前半だったこと・・・。友人の祖母は、間違いなく、麦稈真田で帽子を作って現金を稼いでいたのだろう。しかし、その頃、私たち子どもは、もう誰も、麦わら帽子をかぶっていなかった。けれども、父たち大人は、毎日、麦わら帽子をかぶって、山や田んぼに行っていた。思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ 俵 万智『サラダ記念日』より 今は、日射病よりも、紫外線が怖い。幼稚園の帽子も襟足を日光から防ぐものになっている。 ◎人気blogランキングへ◎◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★7月1日*トリビアの井戸:はかどるの語源 /六月捨(す)てえ *UP・・・・・・・・・・・・・
2007.07.01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 全ショップ2倍もきた!🤩楽天BF6日目…
- (2025-11-28 16:47:43)
-
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 国の予算と世界のお金の流れ!税金・…
- (2025-11-29 00:00:15)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 【1日限定】お肉の福袋‼️メガ盛り1.3…
- (2025-11-29 07:12:59)
-






