2025年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
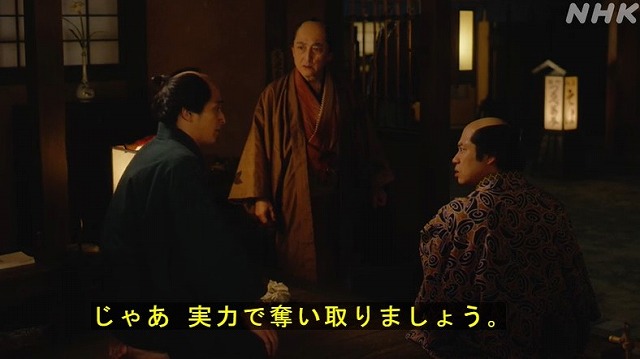
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第12回~「俄なる『明月余情』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。俄祭りをテーマにしたこの回はなんといっても、後半30分からの大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)率いる大文字屋と、若木屋与八(本宮泰風さん)率いる若木屋との、両者の踊りの対決が見物でした。あのシーンがスゴイと思ったのは私だけではなかったようで、放送終了後にはSNS各所で “ダンスバトル” と話題になりました。どこかの記事にありましたが、このダンスバトルを撮るために、俳優さんたちは稽古がとてもキツかったとか。でもこれだけ視聴者の注目を集め感動を与えられたら、厳しかった稽古も報われたでしょうか。ちなみにこの俄祭りに関する特別映像が、3月28日金曜日の午後10時から、「100カメ」の番組の中で紹介されるそうです。⇒ ⇒ こちら さて、もう一つ話題になったのが、筆名では「朋誠堂喜三二」を名乗り、実は秋田佐竹家の留守居役という平沢常富を演じる尾美としのりさんです。尾美さんは毎回クレジットに名前が出てくるのだけど、いったいどこで出演しているのか、第9回あたりまで毎回わかりませんでした。でもそれは私だけでなく、ネットの皆さんも同じ思いだったようで「尾美さんを探せ」になってました。出るのはほとんど一瞬で、尾美さんほどの役者さんがセリフもない通行人とは考えられませんでした。でも逆に、それが視聴者の関心の一つになり、そしてドラマの中では主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)に「あー、あの時の!?」と思い出させるネタになり、こういう方法もあるのかという感じでした。ドラマ製作側もそれをわかっていたようで「これまでの 尾美としのりさん出演シーンをまとめました」と出ています。 ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永6年(1777)年明け、馬面太夫は富本豊志太夫を襲名し、蔦屋重三郎(横浜流星さん)が権利を得た直伝の本は飛ぶように売れていました。ただ富本本と同時に青本も巷では人気となっていて、青本の作家の恋川春町と朋誠堂喜三二は鱗形屋が抱え込んでいました。一方、吉原のほうでは8月に行われる祭りをどうしようかと親父衆の中で話が出ていた時に、何かと対立する若木屋与八から廻状がきて、それは今まさに親父衆が話し合っている俄祭りのことでした。若木屋は昨夏に大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)が言いだしたことをそっくりそのまま自分の名で提案し、またこの時に西村屋は錦絵で『青楼俄狂伝』を出すと言い、これに賛同する者は金2両を添えて申し出を、とのことでした。自分の仕切りで祭りをやりたかったのに、若木屋に持っていかれて怒り心頭の市兵衛に、重三郎は「実力で奪い取ろう」と進言しました。吉原の馴染みの客の平沢常富は実は秋田佐竹家の留守居役で、平沢は重三郎の才能を買ってくれていました。その平沢が重三郎の後ろ盾になると言ってくれたことで市兵衛は強気になり、廻状の趣旨に賛同した、自分たちも参加するとして、金を持って若木屋与八(本宮泰風さん)のところに行きました。とはいえ対立したまま市兵衛と与八はどちらも譲らず双方が優位に立とうとし、互いに悪口を言い合い、果ては喧嘩になるところでした。重三郎は平沢常富から、町が割れるのも悪くない、対立して張り合えば祭りがどんどん盛り上がるとは教わりましたが、それどころではありませんでした。芸事にも詳しい平沢は早速、吉原で祭りの相談役となりました。市兵衛と与八の間では踊りの師匠の争奪戦をしたりと対立は相変わらずであり、また西村屋は吉原に偵察を送りこみ、重三郎の行動を見張らせていました。そんな頃、重三郎が平賀源内を訪ねると源内は不在で、小田新之助(井之脇海さん)が急遽注文が入ったエレキテル作りで忙しそうでした。重三郎は源内がいる千賀道有の屋敷に行き、源内の用事が済んだ後で重三郎が祭りで人を呼び込むものを書いて欲しいと頼むと、自分は今忙しいから朋誠堂喜三二に頼むといい、と言ってくれました。重三郎は最初「朋誠堂喜三二」と言われても誰のことかわかりませんでしたが、源内から言われていろいろ思い出し「朋誠堂喜三二=平沢」だと理解しました。重三郎が平沢のところに行って「朋誠堂喜三二先生!」と呼びかけると、平沢は慌てて重三郎を口止めしました。平沢は、自分が喜三二だと世間にばれると武士として上からお叱りを受けるし、扶持の他の稼ぎは建前では禁じられている、とのことでした。重三郎が平沢にうちで青本を書いてもらえないかと頼むと、青本は去年もうたくさん書いたし、ネタがないからやりたくないと。そこで重三郎が、この祭りの裏側をネタにしたらどうかと提案すると、平沢は次々と物語が思い浮かんできました。でも書くのは気が進まないと言うと重三郎は、本ができた暁には吉原をあげて平沢をもてなすと約束し、平沢もその気になってきました。平沢は実は朋誠堂喜三二として、恋川春町(小島松平家、内用人の倉橋格)と共に、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が出している青本の作者でした。平沢が最近、重三郎と親しく話をしていると聞きつけた孫兵衛はなんとしても平沢を重三郎に取られまいと、妻のりん(蜂谷眞未さん)以下子供たちも含め、家族総出で、青本を出すのは自分のところだけにして欲しい、これで鱗形屋が持ち直さなければ一家離散で後がない、どうか我らを救って欲しい、と土下座して平沢に頼み込みました。平沢は重三郎とも仕事をしたいと思いましたが、迷ったあげく今回は鱗形屋の頼みを受け入れることにしました。平沢は「勤めが忙しいからしばらくは吉原には行かない。でも祭りは楽しみにしている。」と重三郎に文を送り、重三郎も鱗形屋とのことを察しました。そこへ市兵衛が血相を変えて店に来て、ちょうどふらりと現れた富本豊志太夫(寛一郎さん)に助けを求めました。話によると若木屋は祭りの踊りで市兵衛の大文字屋と同じ演目の「雀踊り」を選び、さらに振り付けを藤間勘之助に頼んだ、とのことでした。そう聞いた太夫は、ならばこちらは西川扇蔵に頼むと言ってくれました。一方、重三郎は留四郎も気になるほどこの祭りの宣伝に積極的ではありませんでしたが、西村屋が錦絵で客を呼んでくれている、その上で来た客が耕書堂を覚えて帰ってもらう方法を考えている、と留四郎に返しました。(引いた目で見るーー重三郎は須原屋市兵衛の教えを取り入れていますね)吉原での祭りの準備は着々と進み、若木屋与八と大文字屋市兵衛相変わらず顔を合わせると互いに牽制の応酬でした。そしていよいよ祭り開きとなり、複数の演目に出る次郎兵衛(中村蒼さん)は張りきっていました。祭りはひと月続き、この間は切手は不要で女性客も大歓迎であり、さまざまな出し物が仲ノ町を埋め尽くします。訪れた人々は芝居を見物したり、一緒に歌って踊って楽しんだりしていました。さてこの日のために稽古を重ねた市兵衛たちの大文字屋が登場しました。しかし踊り出してすぐに向かい側から、与八が率いる若木屋が踊りながら現れ、2つの組が正面からぶつかることになりました。与八たちがほぼ同時に出てきたことに市兵衛は抗議しましたが、与八がそれを受け入れるはずがなく、2つの組は左右に分かれて進みました。しかし市兵衛と与八のにらみ合いは続き、他の踊り手たちはその場にいるのも居づらくなり次々と脇へ。どちらも負けたくない二人はしまいには、互いにガンを飛ばし合いながら二人だけで踊るという展開になりました。祭り見物に来ていた勝川春章(前野朋哉さん)は重三郎の茶屋で、湖龍斎が描いた錦絵を悔しそうに見つめていました。重三郎が春章に、錦絵は無理だけどひと月続く祭りの様子を墨摺りで俄の絵を描いてはどうかと提案、春章も描いてみたくて気持ちがのってきました。そんなところに平沢が訪れ、平沢は重三郎との約束を反故にしたと頭を下げて謝ってくれました。平沢の事情を理解している重三郎は自分のほうが無理を言ったと詫びました。平沢が安心し、そして祭りを楽しんでいる様子を見て重三郎は、急ぎで祭りの絵本を出すことになったから序だけ書いて欲しいと改めて伺いました。皆の期待を感じた平沢は快諾し、春章の絵と共に『名月余情』と名付けられた祭りの興奮が伝わる素晴らしい冊子ができました。『名月余情』は俄の土産にと飛ぶように売れていきました。大文字屋市兵衛と若木屋与八の張り合いは祭りの間じゅうずっと続き、日を追うごとに激しくなっていきました。はじめは市兵衛と与八だけの張り合いだったのがだんだんと大文字屋と若木屋との張り合いになっていき、より人々の目を引くように着物を脱いで踊ったりなど、互いに趣向を凝らしていました。祭り見物に来た人々はこの張り合いを見て楽しみ、あるいは鳴り物に合わせて集団の外で一緒に踊ったりして楽しむようになっていました。そんなこんなで連日盛況のまま、祭りもいよいよ最終日を迎えました。雀踊りは人々の間では「喧嘩雀」と名付けられどんな形で終わるのか、人々はその登場を待ちわびていました。どちらの踊りがより人々を楽しませるかの戦いは、双方もう手を尽くした感じとなり、30日間よくやったと市兵衛と与八は互いに思うところは同じでした。そこで最後の一手として、二人は手に持っていた花傘と扇子を互いに交換して、二つの組が並んで踊ることになりました。見物の人々はその姿に粋を感じ、誰もが心地よい感動を覚えました。やがて踊りは大文字屋と若木屋が入り乱れた形になり、見物していた人々も自然と踊りの輪の中に入っていきました。客に促されてその踊りの輪に入るつもりで外に出たうつせみは、人混みの中にかつて足抜けまで図った思い人の新之助を見つけました。松の井から「祭りに神隠しは付き物。お幸せに。」と言われ、新之助の元へ駆け寄り、人混みに紛れて二人はそのまま門の外に出ていきました。
March 26, 2025
-
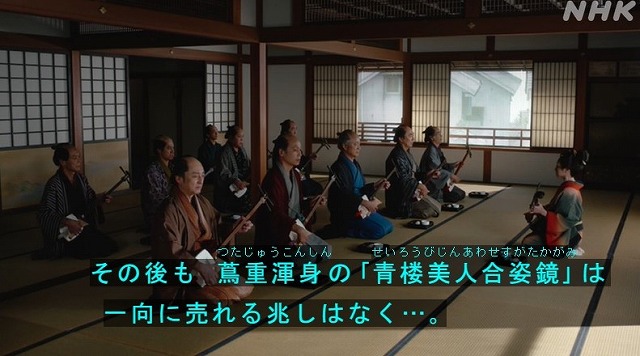
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第11回~「富本、仁義の馬面」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の話の中で全体を通して感じられたキーワードは「男なら」だと思いました。𠮷原からは絶対に外に出られない女郎たちの涙を見た富本豊志太夫(寛一郎さん)は「男なら断れない」と。主家の家老が鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)に酷いことをしたのを「忘れるのは男ではない」と、その埋め合わせを心に決めた倉橋格(岡山天音さん)。でも私はがいちばんグッときたのは、身請けした瀬以(小芝風花さん)を心から愛する鳥山検校(市原隼人さん)の言葉と行動でした。たとえ自分の気の進まないことでも、瀬以が望むことならば、少し時を置いて考えて、自分なりに納得できるとなったら行動しているのです。「そなたの望むことは全て叶えると決めた。」これはもう感動のセリフでした。周囲から大事にされるのが当たり前の人には、あるいは幸せに常に満たされている人には、この言葉の重大さがわからないと思います。でも女郎だった瀬以には、何より有難い言葉でしょう。地位が低い女郎は男に金でいいように扱われ、血のにじむ努力をして花魁になっても、自分は男の名誉欲を満たして話のネタになるだけでした。でも鳥山は、心から自分を大事にしてくれて、何かあればそれが言葉や行動となっているのがわかります。心の中にはまだ蔦屋重三郎(横浜流星さん)がいて思いを消すことはできないけど、自分のために鳥山に無理をさせたくない、鳥山を悲しませたくない、旦那様として仕えたい、そういった思いは瀬以の中にあると思います。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 花魁・瀬川の身請けの旅立ちと共に蔦屋重三郎(横浜流星さん)が大々的に売り出した女郎の絵本の『青楼美人合姿鏡』。しかしこれは鶴屋喜右衛門が予想したとおり、高価で庶民に売れるようなものではなく、本の製作のために重三郎に金を貸している女郎屋の親父衆は、本が売れないことに苛立っていました。そんな折に若木屋の与八は、先日この親父衆と決別した鱗形屋と組むと宣言し、吉原の中に対立ができてしまいました。そして重三郎はというと、『青楼美人』が売れない代わりにこの本を馴染みの客に配って返済金代わりにして欲しいなんて言うものだから、親父衆は怒りの三味線かき鳴らし。(今で言うブーイングか・笑)重三郎はその後は主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)から、毎度の怒りの階段落としをくらいました。安永5年(1776)4月、江戸城では8代将軍・吉宗公以来48年ぶりとなる日光社参が出立、出立だけで12時間もかかる大掛かりなものでした。𠮷原から出られる大文字屋市兵衛やりつらは道中の見学に出ていて、彼はその長い長い行列と人々の歓声から何かをひらめいたようでした。一方、重三郎は市中の本屋で唯一自分と関わりを持ってくれる須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)に、『青楼美人』が思うように売れなくて親父衆への借金だけが残ったと愚痴をこぼしていました。須原屋市兵衛はそんな重三郎を「𠮷原を昔のように憧れの場所に戻したいなら、一度くらいのつまづきでしょげることはない。」と励ましていました。重三郎が親父衆に呼ばれて行ってみると、そこでは𠮷原に人を呼ぶために“俄”の祭りを開いてはどうかと話し合われていました。そしてその祭りに世間で人気の馬面太夫を呼びたい、でも親父衆の中には太夫への伝手がない、平賀源内や勝川春章(『青楼美人』を描いた絵師)なら伝手があるかもしれないから重三郎から当たってくれないか?ということでした。りつ(安達祐実さん)は重三郎が豊志太夫のことを全く知らないので、次郎兵衛(中村蒼さん)も連れて浄瑠璃を見に行くことにしました。重三郎は芝居の前に立ち寄った本屋で浄瑠璃の正本を見て、「直伝」の文字があるものとないものに気がつき、直伝があるものは浄瑠璃の本元の太夫の許しを得ているものだ、とりつから教わりました。芝居小屋に入ると中は豊志太夫と役者の門之助を贔屓する主に女性の客であふれ、浄瑠璃が始まるとその世界に重三郎も思わず引き込まれてしまいました。これは何としてでも豊志太夫を𠮷原の祭りに呼びたいと思った重三郎は、太夫が外に出てくるのを待ち、自己紹介して交渉しました。しかし太夫はなぜか𠮷原を嫌い、そして太夫には鱗形屋孫兵衛がぴったりと付き添い、太夫をどこかに連れて行ってしまいました。鱗形屋の行動と、太夫は間もなく「富本豊志太夫」を襲名する予定という話からりつは、鱗形屋は太夫からの直伝の正本を狙っていると考えました。そう聞いた重三郎の頭の中には、自分が太夫から直伝を取りつければ𠮷原が繁盛するに違いないと空想が浮かびました。ただ太夫の襲名の話は、実はこの時また白紙に戻されていたのでした。𠮷原を嫌う豊志太夫をなんとか𠮷原の祭りに呼びたい重三郎は、伝手を頼って平賀源内(安田顕さん)の元を訪れていました。しかし源内は何かの実験に夢中で(たぶんエレキテル)で重三郎のことは眼中にないので、後で小田新之助(井之脇海さん)から伝えてもらうことにしました。その新之助はというと、本気で惚れた女郎のうつせみをいつか身請けするときのために、今は少しずつ金を貯めているとのことでした。またうつせみの方も、いつか𠮷原を出られた時のために近頃は和算の本を借りて読んでいると重三郎から聞かされ、新之助は安堵しました。(高校の歴史の教科書に「平賀源内、エレキテル=摩擦発電機」とキーワードが欄外の注釈で出ていました)重三郎が吉原に戻ると店にはりつが待っていて、豊志太夫が𠮷原を嫌う理由がわかったと、教えてくれました。太夫はまだ売れてなかった頃、門之助と一緒に役者の素性を偽って𠮷原に遊びに来たものの身上がばれてしまい、その時に若木屋から酷いことを言われたあげく門外に叩き出された、という過去がありました。その話を聞いた重三郎は、なぜ役者が𠮷原の出入りを禁じられているのだろうと思ったのですが、次郎兵衛は「役者の分は四民の外だから」と、りつは「放っておいたら人気で稼げる役者に皆が憧れ、まともに働くやつがいなくなる。だからお上は役者の身分を下げている。」と説明しました。ならばどうやって太夫を説得しようかと思ったとき、大文字屋の市兵衛が慌てて駆けつけ、重三郎に「いい手がある!」と言いました。市兵衛が考えたのは、浄瑠璃の元締めは当道座であり、それはつまり鳥山検校(市原隼人さん)、鳥山は花魁の瀬川を身請けしているからそれを伝手にすればいいのでは、ということでした。市兵衛と一緒に鳥山を訪ねると、すっかり良家の奥方らしくなった瀬川が先に顔を出し、久しぶりの再会となりました。「瀬以」と名を改めた瀬川は重三郎と会って昔に戻った気がして嬉しかったのか、軽口を叩き合いながら声を上げて笑っていました。廊下まで響く瀬以の笑い声は、瀬以が花魁だった時も妻となった今でも、鳥山が聞いたことのない楽しそうな声でした。鳥山が現れ市兵衛と重三郎が挨拶をすると、鳥山は重三郎の声で瀬川を𠮷原まで迎えに行ったときの記憶をたどっていました。市兵衛は豊志太夫の当道座襲名の許しを乞いましたが、鳥山は気が進みません。そこで重三郎は一度太夫の声を聴いて欲しいと進言、重三郎の願いを叶えてやりたい瀬以(小芝風花さん)は自分も浄瑠璃に行きたいと鳥山に願い出ました。鳥山は人が多い所は苦手だとやんわり断りつつ、それでも瀬以が望むのなら行くと応えました。鳥山の意にそぐわぬことはしたくないと困った瀬以を見た重三郎は、突然無理なお願いをしたことを鳥山と瀬以に詫び、渋る市兵衛を連れて帰っていきました。鳥山は重三郎と瀬以の言葉から、どちらも相手の立場を思いやっていて、二人が互いに特別な感情を持っているのだと感づきました。𠮷原に戻った重三郎は、自分に甘えてくる女郎のかをり(稲垣来泉さん)とのやりとりの中で、豊志太夫(寛一郎さん)を呼び出す方法を思いつきました。重三郎はりつと大文字屋市兵衛と共にで偽りの理由で太夫と市川門之助(濱尾ノリタカさん)を向島の座敷に呼び出し、かつての無礼を代わりに詫びた後に、特別に連れ出した女郎たちに会ってやって欲しいと懇願しました。女郎たちは喜んで太夫と門之助をもてなし、もてなされる二人も楽しんでいたのですが、思いの他早くお開きを命じられ、女郎たちはがっかりでした。名残惜しそうな女郎たちの様子を見計らって重三郎は、ほんの少しでいいので富本を女郎たちに聞かせてやって欲しいと太夫に頼み、太夫も快諾しました。りつと市兵衛が奏でる三味線で太夫が歌い、門之助が舞い、本物の浄瑠璃を目にすることができた女郎たちは感動で涙が止まりませんでした。ほんの座興程度の歌と舞いで涙する女郎たちに二人は驚きましたが、女郎たちは𠮷原からは出られないから芝居も観たことがなく慣れていないと重三郎から聞かされ、二人は言葉を失いました。重三郎は二人の前に進み出て姿勢を正し、𠮷原には太夫の声を聞きたい女郎が千も二千もいる、それで救われる女がいる、どうか女郎たちのためにも祭りでその声を聞かせて欲しい、と重三郎は懇願しました。すると太夫は重三郎が言い終わるのを待たず「やろうじゃないか。」と。「こんな涙見せられて、断れる男がどこにいる。」と快諾し、門之助も太夫と同じ気持ちでいました。そんな話をしていたら留四郎が突然入室し、手には鳥山の文を持っていました。その文には「検校率いる当道座は太夫に『富本豊志太夫』の襲名を認める」とあり、さらには「太夫の声を聞いて決めた」とありました。盲ゆえ、たくさんの音が出る場所を嫌う鳥山でしたが、密かに芝居に出向いて太夫の声を確かめていたのでした。瀬以が鳥山に礼を言うと「そなたの望むことは全て叶えると決めた」と。その言葉を有難く感じた瀬以は鳥山に「瀬以は、ほんに幸せ者にございます」と礼を言いましたが、その表情は喜びにあふれたものではありませんでした。重三郎は太夫に直伝を是非自分にと強く願い出て、了承をもらいました。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)も太夫に強く訴え、重三郎に任せれば市中に売ることはできないと念を押しました。しかし太夫は、だったらなおさら重三郎を助けてやりたいと言い、「それが男ってもんだろ?」と謎めいた言葉を残して去っていきました。孫兵衛が帰宅すると小島松平家の内用人の倉橋格(岡山天音さん;『金々先生栄花夢』の作者)が来ていて、次男の万次郎と遊んでくれていました。万次郎に座を外させ孫兵衛が倉橋に挨拶をすると、倉橋は姿勢を正しました。「当家の家老がそなたにまことに酷いことをした。それを忘れるなど男のすることではない。」と言い、孫兵衛は胸が熱くなりました。これより重三郎は富本正本に、孫兵衛は青本にそれぞれ力を入れていくことになりました。
March 19, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第10回~「『青楼美人』の見る夢は」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)が吉原の絵本を作ることでまた一回り大きな人間になっていくのが話の筋なのですが、私はそれよりもドラマの登場人物がいったいどんな人なのかが気になりました。時代劇の大御所、里見浩太朗さん演じる須原屋市兵衛は平賀源内(安田顕さん)と親しく交わり、源内が老中の田沼意次(渡辺謙さん)とつながっていて、意次に重用されていることも知っています。また鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)の事件のときには、世間にはわからない武家が絡んだ裏の真相も知っていて、悪者にされた重三郎を安心させてやってました。須原屋市兵衛はこのドラマではどういう人物なのでしょう。さて、それとは別に今回から登場した若木屋与八を演じるのが本宮泰風さんで、ちょっと感激していました。その昔、里見浩太朗さんが主演の『水戸黄門』を見ていた私は、助さん役で本宮さんの実兄の原田龍二さんを長年見ていたので、ホント兄弟そっくりだと。若い頃はマイルドな顔立ちの兄に比べて、本宮さんはやや恐い感じがしました。でも年齢が上がった本宮さん、風格が出てカッコイイですね。今回は女郎屋の主人の役ですが、長身で腕っぷしも強いので、どこかで殺陣や乱闘を見てみたいものです。話がそれてスミマセン。番組ラストの瀬川(小芝風花さん)の花魁道中。白無垢姿はいつになく美しいものでした。昨年の『光る君へ』では平安貴族の雅な美しさを堪能でき、今年はそういったシーンは望めないかなと思ってましたが、今回の小芝風花さんの身請け(嫁入りと同等)のシーンは格別なものでした。またどこかでこんなシーンがあったらなと思ってます。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 妹・種姫との会話から「江戸城に田安の種を撒こう」と思いついた田安賢丸(寺田心さん)は、母・宝蓮院(花總まりさん)と共に江戸城に行き、10代将軍・徳川家治の嫡男の徳川家基(奥智哉さん)を訪ねていました。将棋の盤を囲む家基と賢丸の姿を見て宝蓮院は、賢丸は8代将軍・吉宗公の同じ血を引く者として家基を支えるつもりでいたのに、年の暮れには陸奥に行かなければいけない、家基の傍にはゆくゆくは出自が低いと嫌うあの田沼意次の息子がつくのか、と嘆いていました。知保の方(高梨臨さん)は老中首座の松平武元(石坂浩二さん)にどうにかならぬのかと相談、武元は一つだけ手があると答えました。一方、𠮷原では女郎屋の親父衆が集まって𠮷原細見をどう売りさばこうかなどいろいろ話し合っていて、身請けされる瀬川の最後の花魁道中となる暮れに女郎の錦絵も出すよう、重三郎に命じていました。親父衆は対立する市中の本屋を潰してやりたいと考えているのですが、𠮷原には親父衆とは別の女郎屋の主人の集まりもあり、その主導者の若木屋与八(本宮泰風さん)は親父衆が吉原への出入り禁止とした本屋の一人の西村屋与八(西村まさ彦さん)を密かに引き入れていました。若木屋与八は親父衆が吉原を勝手に仕切っていると反発し、ここの集まりの皆はこれからも市中の本屋たちと付き合っていくと決めました。女郎の錦絵をどうやって出そうかと悩んだ蔦屋重三郎(横浜流星さん)市中に出てあれこれ考えていたら、自分が作ってあの時には飛ぶように売れた細見が一斉に捨てられているのに遭遇しました。市中では対立する𠮷原の本は取り扱わないとなり、さらにそのいきさつ話には尾ひれがついて完全に𠮷原が悪者になっていました。この先どうしたものかと重三郎が悩んでいたら平賀源内とばったり会い、その源内は須原屋市兵衛と待ち合わせしていたので、重三郎は源内と市兵衛と歩きながら本のことで相談を持ち掛けました。源内と市兵衛の用事が済むのを待つ間、重三郎は店の見物をして歩き、そこで役者絵が売られているのが目に留まりました。その絵は今人気の春章の画風に似せた絵でしたが、役者絵には役者のふだんの姿がなぜないのか、重三郎はふと気になりました。そうこうしていると用事を済ませた平賀源内(安田顕さん)と須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)と合流できたので、重三郎は小料理屋で二人に話を聞いてもらいました。市兵衛は、事を収めるなら重三郎が改めに徹すればいい、と言いました。でもそれは重三郎にとって元の木阿弥になるだけだと言うと、話を聞いていた源内が「もう自分のやりたいことをやったら?」と意見しました。重三郎のやりたいこと、それは𠮷原を江戸っ子が憧れる場所にすることでした。𠮷原を一流の遊び場にする、花魁は男にとって高値の花、女郎たちも辛いことより楽しいことが多い、そんな場所にしたいと夢を語りました。そして話の流れから、作った𠮷原の絵を将軍に献上できないか?せめて将軍が目にしたという噂だけでもあれば𠮷原の格が上がる、と考えました。重三郎の夢の話に二人も乗ってきて、源内を通じて老中の田沼意次までは届くので、源内も協力することにしました。重三郎が吉原に戻って女郎の絵本を将軍に献上するという話を親父衆に相談すると、だれもが驚きそんなことはできるわけがないと反対しました。そこを重三郎が、源内を通せば田沼までは届く、将軍に献上したと箔がつけば本は間違いなく売れる、と説明すると親父衆たちもいろいろ気づき始めました。𠮷原の格が上がる、客筋も良くなり落ちる金も増える、豪気な身請けが増える、その絵本を瀬川の最後の花魁道中に合わせて売れば皆が買い求める、という展開が親父衆の頭の中にも描かれ始めました。しかしそのためには上等な本にしなければいけないから百両かかると重三郎が言うと皆は一斉に手の平を返しましたが、駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が自分が五十両もつから残りを皆にお願いしろと助け舟を出してくれました。ただしこの金は貸し付けだと言い、重三郎も売ってみせると宣言しました。女郎の絵を描くにあたり重三郎が『一目千本』の時に描いてもらった北尾重政(橋本淳さん)に頼んだら、近所だからと絵師の勝川春章(前野朋哉さん)も一緒に連れてきてくれました。絵本には女郎たちのふだんの姿も載せたい重三郎は、親父衆に許可をもらって二人をあちらこちらに案内していました。*番組HPの【べらぼうナビ】に、北尾重政と勝川春章について載ってます。 ⇒ ⇒ こちら 北尾重政と勝川春章による吉原絵本が完成したので、重三郎は平賀源内の力で老中の田沼意次(渡辺謙さん)に会いに行きました。重三郎が説明を始めると意次は意外にも重三郎のことを覚えていて、同行した駿河屋市右衛門と扇屋宇右衛門(山路和弘さん)は苦虫を嚙み潰したようでしたが、重三郎は調子にのったいつもの物言いで、意次も愉快そうでした。そして瀬川の話になると意次は、瀬川の道中の話で自分たちも「社参」を見直すきっかけになった、恩を返すと言い、絵本の将軍への献上を快諾してくれました。意次が吉原絵本の献上に参上すると将軍・徳川家治(眞島秀和さん)から想定してなかった話を聞かされました。田安家の種姫を家治の養女にし、いずれは家基の正室にするということでした。先日、田安賢丸の白川行きを無しにするよう嫡男の家基が言いだし、意次を重用する件でも家基は将軍である父を批判、賢丸の件が無理なら種姫をということで、老中首座の松平武元の進言もあり、家治それを受け入れたのでした。これで賢丸は次期将軍の義兄となり、種姫が子を産めば田安家は盤石に。賢丸が江戸城に田安の種を撒いて芽を出させると考えたのはこのことでした。意次の嫡男・意知は、まだ先の話だから案じなくてもと考えましたが、意次はこの話を聞いた者たちは先の明るい田安のほうになびいていく、田沼から人が離れていってしまう、と危機感を持っていました。そしていよいよ瀬川(小芝風花さん)が身請けされて吉原を出ていく日がきて、新しくできた女郎絵本を手に親父衆も準備に取り掛かりました。今日みたいな日に瀬川と会うのは良くないと思った重三郎は、松葉屋の主人の半左衛門に、絵本を瀬川に渡してもらうよう頼みました。でも半左衛門は二人は互いに気持ちにケリをつけていると考え、自分で渡してくればいいと、瀬川に会うことを重三郎に許可しました。これから着ていく白無垢の前でたたずむ瀬川に重三郎は声をかけ、餞別として絵本を瀬川に渡しました。本を開くと自分が載っていることに驚く瀬川。そして頁をめくっていくとそこには女郎の日常が描かれ、ここでこんな楽しい時間もあったのだと気がつき、思わず涙しました。重三郎は吉原を女郎たちが堂々と生きる場所にしたいと夢を語り、そしてその夢は瀬川も同じで二人で見た夢だっただろ?と贈る言葉にしました。安永4年(1775)12月、七つ刻になり、白無垢姿となった瀬川の最後の花魁道中が始まりました。親代わりの松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)といね(水野美紀さん)、瀬川の付き人だった若い女郎や禿が付き添い、仲ノ町通りの端から端まで練り歩いてその美しい姿を披露しました。通りに並ぶ大勢の見物客からは次々と瀬川への掛け声がかかり、その旅立ちを皆が祝福していました。また松の井や常盤木ら数多くの花魁が道中に加わり、道中に花を添えました。大門の前に立つ重三郎を見たとき、瀬川は最後に二人で語り合った吉原への夢と、重三郎がこの夢をずっと追いかけることと、この夢が自分と重三郎をつなぐ唯一のものであることを思い出していました。大門のところで瀬川は吉原の皆に別れを告げ、かすかに微笑み合った重三郎とはそのまますれ違い、門の外で待つ鳥山検校の元に行きました。そして瀬川が門を出て間もなく、重三郎らによる絵本の売り出しが呼び声と太鼓の音で賑やかに始まりました。幼なじみの花魁で、一緒にはなれない運命だったけど、瀬川は自分にとって誰よりも大事な女なんだと気がついた重三郎は、瀬川へのはなむけになるよう精一杯本を売り込み、人々は先を争うように女郎絵本を買い求めました。しかしその喧噪を聞いていた鳥山は、重三郎の声に何かを感じたようでした。そしてこの絵本は市中でも須原屋の市兵衛は取り扱ってくれて、市兵衛の店では人気の本になっていました。
March 12, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第9回~「玉菊燈籠 恋の地獄」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は、話の中心は蔦屋重三郎(横浜流星さん)と瀬川(小芝風花さん)の恋物語でしたが、𠮷原では許されないそれを、他者には知られないように収めた松葉屋の主人・半左衛門(正名僕蔵さん)と女将のいね(水野美紀さん)の手腕に見入ってしまいました。「亀の甲より年の功」でしょうか。もちろん松葉屋としての利益もあったでしょう。でも若い二人が一時の激情に流されて𠮷原の御法度を破って互いに人生を台無しにしないよう、精神的には一番キツイやり方でそれぞれの立場を自覚させ、恋の炎を消してやりました。やり方は鬼かもしれないけど、もし半左衛門といねが若い二人に対して憎さが先立ったら、二人のやりそうなことはお見通しだからわざと逃亡させ、後で捕まえて激しく折檻をしたでしょう。でもそれはせず、それぞれに現実を思い知らせ、二人に考えさせたのです。またちょうどというか、うつせみの逃亡が先にあったので、二人が考えを改める要因にもなったのですが。甘いゆるいことを言っていたら統制がとれない𠮷原の世界では「忘八」にならざるを得ないと女郎屋の主人たちですが、幼い頃から見守ってきた重三郎と瀬川は、やはり情がわく部分があるのでしょう。親のいない女たちや男たちの親代わりなのでしょうね。*上記番組HPの【べらぼうナビ】に「玉菊燈籠」と「通行切手」についての説明があります。 ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 先日、いつものお稲荷さまのところで瀬川(小芝風花さん)となんとも歯切れの悪い別れ方をした蔦屋重三郎(横浜流星さん)。ある日、小田新之助(井之脇海さん)が茶屋に来て自分と互いに思い合う女郎・うつせみのことについて重三郎に話をしていました。その時、瀬川が花魁道中で現れたのでその行方を追っていくと、盲の客の鳥山検校(市原隼人さん)を出迎えて座敷に案内するところでした。瀬川が客の鳥山と触れ合うのは花魁としてふつうのことなのに、今日の重三郎はそれを目の当たりにしたときに今までとは違う複雑な思いがしました。重三郎は製本の仕事をしようと思ってもなぜか瀬川のことが頭をよぎって全く身に入らず、眠れぬ夜を過ごしていました。翌朝、女郎屋の親父衆のところに打ち合わせに行ったとき、重三郎は瀬川に鳥山から身請けの話が出ていることを知りました。そう聞いて気持ちが乱れた重三郎は、その場は笑ってごまかして出直すことに。店に戻ったら新之助がいて、重三郎に相談があるとのことで外に出ました。新之助は自分のために辛い思いに耐えているうつせみを身請けしたいと思ったのですが、重三郎からその額を300両と聞いて自分には無理だと悟りました。新之助は「金のない男の懸想は花魁にとって幸せになる邪魔でしかない」と言い、重三郎もそれに相槌を打つしかありませんでした。瀬川は重三郎にとって幼なじみの花魁で今まではただそれだけだったのだけど、瀬川が身請けされると聞き、重三郎はこのまま瀬川が吉原から去ってしまうのに耐えられなくなりました。重三郎は瀬川をいつものお稲荷さまに呼び出し、はじめは照れ隠しで仕事の話と鳥山を卑下することで瀬川を引き留めようとしました。でも瀬川から私を利用するなと怒られて、重三郎はようやく「行かないでくれ。俺がお前を幸せにしたい。」と己の本心を打ち明けました。重三郎は瀬川の年季明けには請け出すと言い、重三郎の自分への気持ちに嘘がないとわかった瀬川は重三郎に心変わりをしないことを約束させました。互いに思い合っていることを確信できた二人は心から笑い合いました。重三郎と一緒になるために𠮷原に残る決心をした瀬川は花魁の特権を使って、松葉屋の主人の半左衛門(正名僕蔵さん)と女将のいね(水野美紀さん)に、鳥山からの身請けを断りたいと申し出ました。しかし話は身請け証文にまで進んでいて、今さら断れないといねは激怒です。半左衛門が穏やかにその理由を尋ねると、瀬川は用意してあった理由をよどみなく語り、いねは「よ~くわかったよ」と嫌味っぽくその場は認めました。いねは瀬川にマブができた、相手は重三郎だと見抜いていて「正面きっての掟破りだ。バキバキに折檻してやる。」と厳しい表情になりました。そしてまさを呼び、瀬川の行動を監視するよう命じました。まさの尾行に感づいた瀬川は、当分は会わないよう重三郎に伝えました。二人は周囲を欺き続け、また鳥山が来ても瀬川は座敷に出なくなりました。いねが鳥山に瀬川はひどい風邪で来られないと伝えると鳥山はその嘘を感じ、自分は振られたのかとつぶやきました。破格の条件を示す鳥山を絶対に逃がしたくない半左衛門といねは、なんとかその場を取り繕うのに必死でした。重三郎の主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)は、もしかしたらこの件に重三郎が絡んでいるのではと思い半左衛門に訊ねました。半左衛門は否定はせずに、でも大ごとにならぬよう、まだうちに任せてくれと言って出ていきました。鳥山に限らずこの先だれが身請け話を持ってきても瀬川は断る、と見抜いているいねは、二人をあきらめさせるのにはあの方法しかないと決めました。いねはまず瀬川に次から次へと客を取らせました。瀬川の襲名披露や瀬川になってからの着物や調度品に恐ろしく金がかかった、身請けを断ったからにはガンガン稼いでもらう、瀬川のためならいくらでも金を出す客がいる、外に出ないよう離れで客を取ればいい、と。過酷ないねのやり方に瀬川は、先代の悲劇をもう一度繰り返すのかと言ったのですが、いねは先代の瀬川が可哀想だなんて毛筋も思ってないと言います。さらに「あれは松葉屋の大名跡を潰してくれた迷惑千万な馬鹿女。」とまで言い、瀬川に仕事を言い渡して出ていきました。一方、半左衛門は瀬川と3人で話をするからと重三郎を呼びつけていました。重三郎が松葉屋に来ると離れの座敷に案内され、障子の向こうで人の声がするので昼見世だとは思ったのですが、半左衛門がわざと障子を少し開けた向こうにいたのは、客を取っている最中の瀬川でした。好きな男にはこの姿は見られたくなかった瀬川、惚れた女のおつとめの姿は見たくなかった重三郎。半左衛門はお前らのことはわかっているとばかりに、重三郎に畳みかけます。「これが瀬川のつとめ。年に2日の休みを除いては。お前はこれを瀬川に年季明けまでずっとやらせるのか?」そして半左衛門は重三郎の肩をポンと叩き、「今、お前にできるのは何もしないってことだけだ。」と諭すように念押ししました。重三郎は何も言い返すことができず、ただ立ち去るのみでした。重三郎がやりきれぬ気持ちを抱えて茶屋に戻ると新之助が来ていて、連れの女に玉菊燈籠を見せてやりたいらしく重三郎に通行切手を求めました。その夜、重三郎は通行切手があれば瀬川と二人で𠮷原から逃げられるとふと思いつき、ニセの通行切手を作って瀬川に渡す本にはさみました。しかし重三郎が思い描いていた逃亡を、その夜に新之助とうつせみがすでに実行し、二人は少しでも遠くにと急ぎ逃げていきました。翌日、重三郎が松葉屋に貸本を勧めに行ったとき、ちょうど瀬川が出てきたので重三郎は声をかけ、通行切手を挟んだ本を瀬川に渡しました。本に挟まれた物を見て瀬川が驚いていると、女将のいねがうつせみの名を叫びながら出てきました。うつせみがここにもいないとわかるといねは足抜け(逃亡)だと断定して、男衆にすぐに追うよう命じました。夜通し逃げた新之助とうつせみ(小野花梨さん)でしたが、二人とも追っ手にすぐに捕まってしまいました。𠮷原に連れ戻されていねに折檻されるうつせみは、ただ幸せになりたくてと自分の思いを訴えましたが、いねに一蹴されました。「幸せ?こんなやり方でなれるわけないだろ。追われる身になってどこに住むのか。人別(戸籍みたいなもの)や食い扶持はどうするのか。仕事がなくて男は博打、女は夜鷹、ろくな暮らしができなくて、それが幸せか?!」重三郎から足抜けを提案されている瀬川は、いねのうつせみへの言葉を殊の外、重く受け止めていました。一方、重三郎は新之助から「自分が弱くて、己の不甲斐なさに耐えられず、うつせみに逃げようと誘った。」と聞かされ、自分を振り返っていました。そしてどんなに思い合っていたとしても、自分たちが一緒になろうとすると互いに不幸になるだけで幸せはないのだと、重三郎と瀬川はそれぞれに思うようになりました。瀬川は女将のいねに、先代の瀬川のことを訊ねました。「あの妓があんな死に方をしなければ、きっと何人もの女郎が瀬川になって、豪儀な身請けを決めて大門を出ていった。あの妓のせいで女郎たちは瀬川になれなくなり松葉屋は身代金を失った。だからあんたが瀬川を幸運の名跡にしたいと言ったときは嬉しかった。これでみんな救われると。」いねは瀬川を諭すようにさらに続けました。「𠮷原は不幸なところだけど、人生をがらりと変えるようなことが起きないわけじゃない。そういう背中を女郎に見せる務めが瀬川にはあるのでは?」重三郎と瀬川はそれぞれに、もう自分たちが一緒になるのは無理であると悟り、瀬川は他の女郎たちのためにもと鳥山からの身請け話を決めました。瀬川は重三郎から渡された本にあったニセの通行切手を破って密かに返し、そして馬鹿らしいけど夢を見て面白かった、とびきりの思い出になったと、本の感想を言うふりをして礼を言い、重三郎も瀬川の意思を悟りました。程なくして瀬川の身請けが身代金1400両で正式に決まりました。(女郎にとって身請けは嫁入りと同じなのですね。婚礼の白無垢を用意し、身代金は結納として納め、部屋の主人と女将は親代わりとして正装をして挨拶をするのですね。)
March 5, 2025
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- うさ飼いさん集まろ~
- コナモ (U^ω^U)7歳3か月 YOUTUBE動…
- (2024-11-14 15:13:45)
-
-
-

- トイプードル大好き
- トイプードルLove癒されます🐶💕
- (2025-11-20 12:36:37)
-








