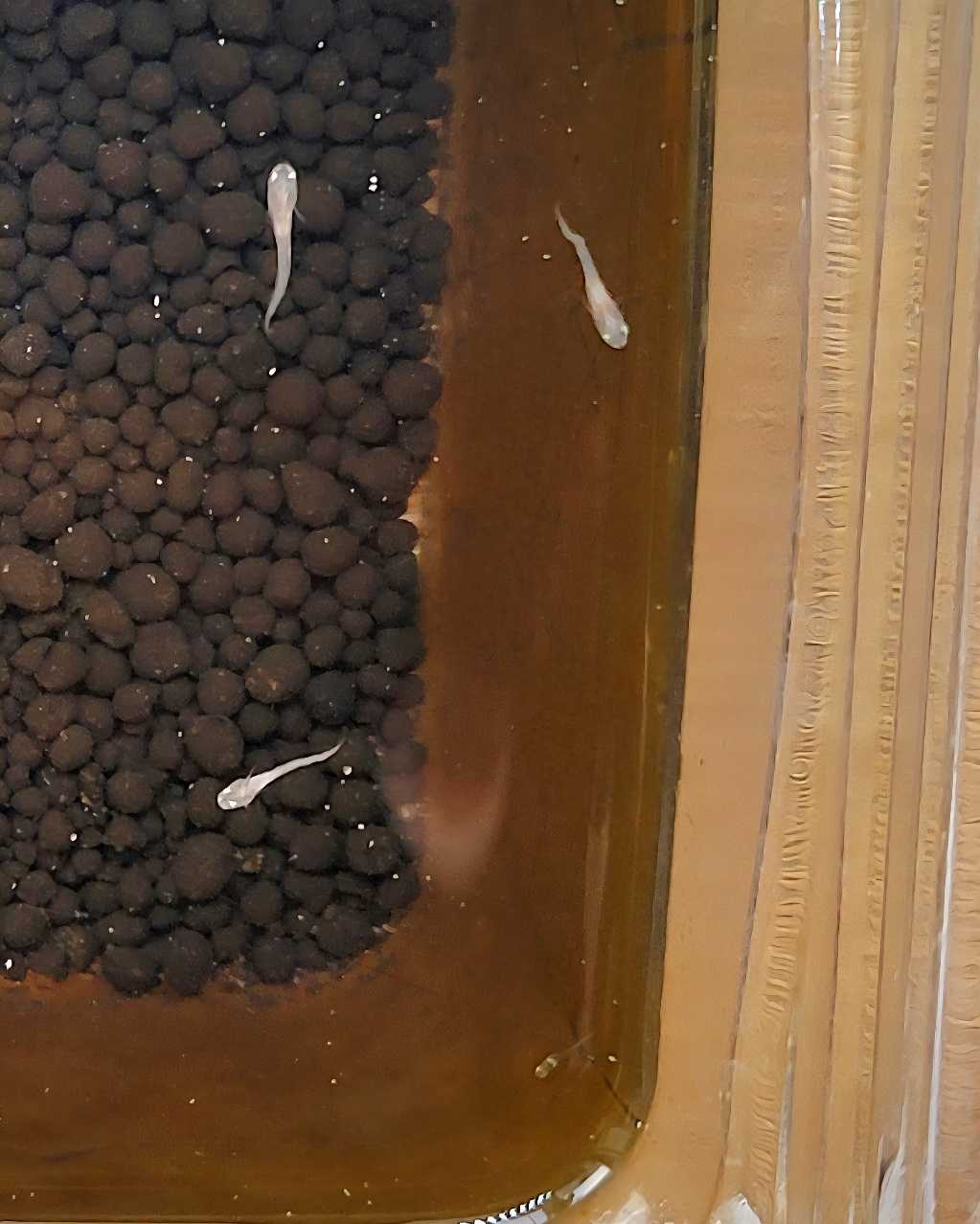2025年11月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第43回~「裏切りの恋歌」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政5年(1793)、喜多川歌麿(染谷将太さん)は義兄・蔦屋重三郎(横浜流星さん)の吉原への借金100両の返済代わりとして女郎の大首絵を50枚描くことになり、吉原で女郎たちの絵を描いていました。しかし吉原では、倹約令のために流行るのは安い女郎ばかりで、高級な花魁たちには声がかからなくて景気が悪い、と親父衆は愚痴ばかりこぼしていました。また江戸市中では、錦絵に描かれた看板娘がいる店では割高な料金を取って商売をしていましたが、奉行所からお叱りを受けて元の値に戻していました。一方、江戸城では老中首座の松平定信(井上祐貴さん)が将軍・徳川家斉(城桧吏さん)にオロシャの来航に伴う海防について報告をしていていました。話の後で家斉は、そろそろ政を定信に頼らず自分で指図すべき、と父・一橋治済(生田斗真さん)から話があったと言いました。しかし家斉は、自分は難しいことはわからないし政に興もわかぬと言い、定信が将軍補佐を外れても政に指図するしくみを作って欲しいとのことでした。定信はそのためにも自分が大老になればいいと考え、徳川御三家尾張の徳川宗睦(榎木孝明さん)に相談しました。宗睦は、大老は「井伊」「酒井」「土井」「堀田」の四家からしか出さぬしきたりがあるから無理だと答えました。しかし定信は、家斉が自分を頼っているからなんとか後押しして欲しい、と本気の覚悟を見せていました。宗睦は、家斉が今まで定信を避けていたのに急接近してきて変だとは感じていました。定信は、オロシャのラクスマンが漂流民を引き渡した後も日本に留まって将軍への目通りを願っていて、開国を要求していると目付の村上義礼(大迫一平さん)より報告を受けました。老中の本多忠籌(矢島健一さん)らはオロシャの要求をのんだほうがいいと考えましたが、定信は彼らを早く帰国させるためにも信牌(鎖国中の日本での長崎の入港許可証)を持たせればよいと考え、幕府の公式の返書をしたためて目付に渡しました。信牌を受け取ったラクスマンはエカテリーナ二世に見せるため、すぐに日本を出てオロシャに戻っていきました。この件を定信は将軍・家斉に報告し、その後で定信はある書状を家斉に渡していました。さて吉原では、歌麿が描いた女郎絵ができあがってきて親父衆たちは喜んでいました。親父衆は昔のにぎやかだった頃の昔話に花が咲き、次の企画は何かないかと盛り上がっていました。重三郎は歌麿が吉原を立て直すと皆に宣言し、親父衆もそれを期待していました。ただ当の歌麿は実は気乗りしていなくて、勝手に安請け合いをする重三郎からますます心が離れていきました。そんな話をしていたらふじ(飯島直子さん)たちが、重三郎の身重の妻のてい(橋本愛さん)のために、赤子の着物やおもちゃなどのおさがりをたくさん運んできました。商売も(歌麿頼みで)上向きになりそうだし、まもなく赤子も産まれてと、重三郎は楽しい未来を想像して笑っていました。しかし大量の仕事を持ってこられるだけで重三郎にいいように使われているようにしか思えない歌麿は、まったく笑う気にもなれませんでした。ある日、重三郎の店に鱗形屋孫兵衛の長男の長兵衛(三浦獠太さん)が『金々先生』の大量の版木を譲るといって持ってきてくれて、重三郎はありがたく譲り受けました。話の流れで長兵衛は弟の万次郎(孫兵衛の次男で西村屋の養子;中村莟玉さん)が歌麿はと組んで仕事ができると喜んでいたと重三郎に伝えました。そんなこと初耳だった重三郎は急ぎ歌麿のところに行きました。歌麿は女たちの「恋心」の大首絵を描き終えて重三郎に渡すと、重三郎は歌麿に好きな女がいるのかと喜びました。やっぱり重三郎には人の微妙な気持ちはわからないなと歌麿は自分の思いをわかってもらう気持ちも失せ、淡々と重三郎には本心は言わない、重三郎とはもう仕事をしない、と伝えました。そして歌麿は看板娘の絵を取り出して重三郎に見せ、これまで重三郎が自分に対していかに軽んじてきたかを訴えました。反省する重三郎ですが歌麿の心はもうすっかり離れていました。歌麿は、西村屋の仕事が面白そうだからやりたい、吉原への恩返しは自分なりにやる、と言いました。重三郎が土下座して「なんでもやるから考え直して欲しい」と懇願すると、歌麿は「蔦屋の店を俺にくれ」と言いました。さすがにそれは無理だと重三郎が断ると、歌麿は「結局はそうだろ?俺の欲しいものはなに一つくれない。妻子を大事にしてやれ。」と言って家を出ていきました。重三郎は、今まで気づかず歌麿に嫌な思いをさせてきたことを詫び、これまでずっと自分についてきてくれたことに礼を言い、歌麿は当代一の絵師だと改めて認め、体は大事にしろ、と文をしたためて歌麿の家に置いてきました。店に戻った重三郎は皆に、歌麿はもう自分の仕事しないと伝え、歌麿が描いた女絵を見せました。それを見たていは歌麿の秘めた恋心に気づきました。しかしこのとき急に産気づいてしまい、急いで産婆(榊原郁恵さん)に来てもらい、重三郎もていと子の無事を必死に神棚に祈りましたが、子は流れてしまいました。さて松平定信ですが、将軍補佐と大老を辞する代わりに大老を拝命する日をいよいよ迎えていました。田安家として将軍を出す夢は叶わなかったが国の舵取りをする役目になれた、と側近の水野為長(園田祥太さん)と共に喜び、江戸城に入りました。将軍・家斉は、定信の早く下城したいという願いについて今も心変わりはないかと念押しし、定信も同意しました。すると家斉は大老を命ずるどころか、ならばこのまま引退せよ、政に関わることなくゆるりと休め、と言い渡しました。一橋治済も、徳川のため、将軍(我が息子)のため、ご苦労であったと、早く下城を促すものでした。定信が茫然自失となって退室したら、襖の向こうから廊下まで皆が揃って高笑いする声が響いてきました。家斉が自分を頼りにしてくれたあの様子も、老中の本多忠籌や松平信明(福山翔大さん)が急に自分に服従するようになったあの様子も、全ては自分を失脚させるためのことだったのか。老中首座となってからは、人々から嫌われても煙たがられても、自分が正しい・やるべきだと思ったことをやり通してきたのだ。それなのに最後はこの有り様。ぶざまでみじめで怒りしかなくて、定信は一人布団部屋であの部屋の皆を呪いながら涙しました。この出来事は、町の瓦版では定信が自ら引退を願い出たとして触れ回られ、人々はこの失脚劇の大喜びでした。そんな折、かつて大奥総取締だった高岳(冨永愛さん)が突然、定信を訪ねてきました。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇前回とこの回で抱いた歌麿の思い。相手が好きな人に限らず、仕事での会社の上司とか、家族間で平気できょうだい差別をする親とか、思いつくまま好き勝手をやってこっちにシワ寄せをかける配偶者や友人とか、etc... 何かにつけて自分が我慢をしてしまう・させられる人の場合、歌麿の気持ちに自分も覚えがあると思った方は多かったのではないでしょうか。この人のために頑張ろう!と思うその相手は、悪い人ではないけれど、独りよがりで、いつも自分に対して勝手な思いこみをして、こちらの気持ちや事情なんかおかまいなしで、あれこれ何かを頼んでくる。言いつけてくる。物事が順調に動いて一人幸せに浮かれていて、こっちは報われない思いを抱えながらも、気持ちに折り合いをつけながら一人引き受けたことを淡々とこなしている。面倒なことや苦労なことは当たり前のように自分に回してきて、楽していい思いをするのはその人が大事に思う他の誰か。私/俺って、便利で都合のいい人なだけ?ずっと我慢を重ねてきたけど、ある日そう気がついたら、心がぶちっと切れるようにその人から心が離れ、その人が目の前で何かやってても何も感じなくなるのですよね。 まあ重三郎の場合はここまで酷くはなくて悪気もなく、まさか歌麿が自分に?という状況もあったでしょう。それでも自分の思い描いたことの実現のために歌麿をさんざん利用し、その分大切にすればまだよかったけど、ないがしろにしてきたことには変わりないですからね。史実でも重三郎と歌麿は一時疎遠になったようですが、脚本の森下佳子氏、こうきたか!と思いました。
November 13, 2025
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第42回~「招かれざる客」
いったい何が起こっていたのか、全くわからないのですが、昨日からずっとパソコンから楽天ブログに入れませんでした。パソコンからは他のサイトには問題なく入れるのに、楽天ブログの管理画面に入れず、今ようやく入れました。では、2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政4年(1792)9月、老中首座の松平定信(井上祐貴さん)のもとにオロシャの船が根室に来航したと報が入りました。オロシャは漂流して助けた日本人(大黒屋光太夫)を送り返しに来ていて、江戸への来航も希望していました。さらにオロシャは王(エカテリーナ二世)からの勅書を持ち、日本との通商を望んでいました。老中の本多忠籌(矢島健一さん)や松平信明(福山翔大さん)は交易を認めようとしますが、定信はオロシャは日本を襲撃しようとしているのでは?と大反対。少し前までは、オロシャの船が江戸の海に入ってきたら国が滅びてしまうと危惧していたのは本多らで、定信は人心がいたずらに混乱すると林子平の『海国兵談』を絶版にしたほうでした。しかし誰よりもオロシャの動向を警戒していたのは定信でした。そんな中、別件で帝(光格天皇)が父・閑院宮に「太上天皇」の尊号を与えるようだと、定信に報が入りました。再び激怒した定信は武家伝奏の正親町公明(三谷昌登さん)を呼び、どうしても尊号を贈るなら向後一切の禁裏御料を打ち切ると公明に伝えました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、尾張に行商に行っている間に母・つよ(高岡早紀さん)が他界していました。それでも商売のほうは少しずつ回復していって、寛政5年(1793)年明けには身上半減が返上できたことを町の人に報告していました。新年にあたり蔦屋の店先には新作の黄表紙や狂歌集がたくさん並び、中でも歌麿(染谷将太さん)の錦絵は相変わらず人気でした。商売がようやく波に乗り出した重三郎は歌麿に仕事をどんどん頼むつもりでいて、ただそれは歌麿の想定以上の量になるので、歌麿は内心困惑していました。2月になり、武家伝奏の正親町公明を江戸城に呼びつけた定信は尊号の件をしつこく問い質していました。公明は帝はもうあきらめたからと釈明するのですが、その態度に苛立った定信は公明らをお役御免のうえ閉門にすると言いました。老中の本多忠籌と松平信明は、武家が公家を処罰するのは良くないと進言しますが定信は、今はオロシャが日本を狙っている非常時、ご公儀と朝廷の不和はオロシャに付け込まれる、何が何でも自分の考えを通そうとします。忠籌と信明は、やり方が強引過ぎて国の中に敵ばかり作っている定信のことを、一橋治済(生田斗真さん)に相談しました。ただ治済は二人の話を聞いているのかいないのか、定信のこととは全く関係ない美人絵を二人に見せて、あることを問いました。この頃、江戸市中では錦絵の題材となった看板娘が世の男たちの関心を集め、男たちが娘たちのいる店に押しかけていました。店側も娘たちの人気を利用して驚くほど値を吊り上げて商売していましたが、それでも人気は衰えませんでした。この状況を見た他の商人たちは自分の娘の絵を描いてもらうよう、こぞって重三郎の店に押しかけました。歌麿はこんなにたくさん描けないと重三郎に訴えます。しかし重三郎は、弟子にあらかた描いてもらって少し手直しして歌麿の名入れをして出せばいい、と聞く耳を持ちません。歌麿がそれは入銀先や客をだますことになるから嫌だと言っても、この流れに乗れば江戸の町全体の経済が回る、そのためのちょっとした方便くらい許される、とどこまでも強引です。歌麿は北尾重政(橋本淳さん)に相談しました。重政は、忙しいと弟子たちに手伝ってもらうことも多いし彼らも喜ぶと言いました。歌麿は、自分は絵を一点一点ちゃんと描きたい、適当になんとかするのではなく本屋にも向き合ってもらいたいと考えていました。でもそんなこだわりを持つのは自分だけなのか?と悩みました。重三郎と歌麿は絵に対して考え方が全く違うのだと、妻のてい(橋本愛さん)は感じていました。重三郎にとって絵は商いの品(道具)であり、歌麿にとって絵は作品であり子のようなものだと。そんな話の流れでていは、子ができたと重三郎に報告しました。絵を弟子に手伝ってもらうのも有りかと思い直した歌麿は、菊麿(久保田武人さん)に下絵を頼み、菊麿も張りきっていました。そんなところに西村屋与八(西村まさ彦さん)が二代目の万次郎(鱗形屋孫兵衛の次男で西村屋の養子;中村莟玉さん)を伴ってやってきました。万次郎は歌麿の『画本虫撰』を見てすっかり心を奪われ、自分が出す新作の絵を是非、歌麿に頼みたいと強く訴えました。万次郎は『当世美男揃え』などの案を持っていて、歌麿もそれは面白そうだと興味をそそられました。歌麿は結局は今は重三郎の仕事で多忙だからと断ったのですが、与八は看板娘の絵を出し、歌麿は重三郎に都合よく使われているのでは?と言い、歌麿の胸に不満の楔を打ち込んでいきました。さて幕閣ですが、本多忠籌や松平信明ら老中が一斉に松平定信に手をついて今までの無礼を深く詫びていました。将軍・家斉からお叱りを受けた、これからは定信に従うと宣言し、その後で市中で流行る看板娘の錦絵を出しました。忠籌は、市中ではこの絵の娘たちを目当てにした男たちが節約を忘れて金を惜しげもなく使い、それにつられて市中の物の値が上がっている、これは「田沼病」では?と報告しました。錦絵を見た定信はなぜか歌麿の名に目が留まりました。一橋治済から何か指令を受けているのか、その様子を見た忠籌は信明に目配せをしました。ところで仕事が順調に動き出したと思った重三郎ですが、人相見からは絵の出し方で苦情が入り、さらに奉行所からは一枚絵には女郎以外の名を書かないよう、お達しがありました。このお達しのために重三郎は仕事をもらっている吉原に大きな迷惑をかけることになりました。駿河屋市右衛門(高橋克実さん)ら吉原の親父たちも不景気で重三郎を助けてやるどころではなく、むしろ重三郎から吉原に借金を早く返して欲しいくらいでした。そこで重三郎が「女郎の大首絵」を提案すると、扇屋宇右衛門(山路和弘さん)は入銀無しならと条件をつけました。どちらも金がなくて話が進まないので、市右衛門は代替案として入銀無しで錦絵を作り、その分は借金を返済したことにしてはどうかと言いました。この話は結局それでまとまってしまい、歌麿の女郎絵50枚を重三郎の100両の返済とすることになりました。しかし自分に相談なしで、ものすごい負担となる事を勝手に決められてしまった歌麿はたまったものではありません。借金のカタに自分を売ったと歌麿は重三郎に激しく怒りました。それでも重三郎は、これで皆が助かり歌麿の名も上がるからいい話だろ?と一方的に繰り返すだけです。歌麿の気持ちを無視して、ひたすら頼み込むだけです。じきにていに子が産まれると聞いたとき、重三郎はどこまでも身勝手で、重三郎にとって自分は無理難題も頼めばやってくれる都合のいい人ぐらいにしか考えていないのだと気が付きました。歌麿は「仕方がないからやってやる。」と返事しましたが、心は冷えきり重三郎からすっかり離れていました。歌麿との話も押し通して思い通りになり、さらにていのおなかの子も元気で喜び浮かれる重三郎。でも歌麿は、後日訪ねてきた西村屋の万次郎に、今やってる揃い物が終わったら西村屋の仕事を引き受ける、蔦屋の仕事はこれで終わりにする、と伝えました。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
November 7, 2025
全2件 (2件中 1-2件目)
1