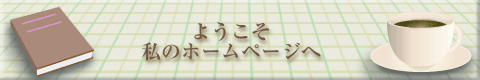2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年04月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
一青窈「一思案」風 米国からの牛肉輸入意見
私の考えは「20ヶ月未満は解除して、早急に米国からの輸入を再開 することに賛成。」ですが、説明が結構難しいのです。反対は「危な い」の一言で済みます。安全の証明はほぼ不可能です。 一青窈(ひととようの「一思案」に「柴犬を飼ったのは 生まれ変わりだと思い込みたい少女、のごっこ遊び」「えんじの日焼けた大きすぎたつっかけと・・・・」 こういう文体で意見を書くとわかりやすくなるのかなぁ 「一思案」を聞いてから読んでもらうとうれしいのですが。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー BSEは牛の病気。かわいそうに牛16頭。 人の病気はvCJD。 昔、イギリスで牛の脳みそ入りのハンバーグを食べた人(たぶん)1人。 肉骨粉、危険部位対策で良いのでは どうして危険?。 マスコミが危ないというから。 マスコミが言わない(言えない)カキは大丈夫。 でも、私の周りでも3人に1人は当たっています。 ノロウイルでは死なないから。 でも、今年の正月6人も7人も亡くなった。 世界一安全な筈の列車事故。 安全地帯と思っていた福岡の地震 絶対安全は無理。 より安全。バランス感覚。優先順序 脅威の最大は戦争。国と国とのバランス。 ビーフの問題だけで来たわけじゃないと。名前がライスだからね 冗談きついね。トップの談話。 ブッシュさんの地元はテキサス。 テポドンが飛来した時、誰に頼むの。 BSEは牛の病気です。日本では16頭。 人の病気はvCJD。患者は1人。 交通事故は7,358人、自殺者32,109人
2005年04月29日
コメント(0)
-
ミツバツツジが咲いていた
湯本温泉のホテルでの研修の帰り、ミツバツツジが咲いているのを見つけました。山口県に多く自生います。高速でも藪の中に咲いているのを良く見かけました。 亡くなった父が山取りして盆栽に仕立てていました。懐かしい木です。九州ではあまり見ません。 夜、メールで西日本厨房機器展でのHACCPプレゼンテーションの話が中村学園大学小田隆弘先生からきました。この所良く話がきます。
2005年04月27日
コメント(0)
-
大学から夏期集中講義依頼
昨日、ある東京の大学(旧国立)から夏期集中講義依頼で1日「食品事故の現場」というテーマで講義して欲しいと依頼がきました。 すごいと少し興奮しています。 WEBで見たということですので、多分「FOOD SCIENCE」でしょう。 月刊HACCPの連載は6月からになりました。6000字は結構書きごたえがありますね。 2回分は提出しましたので、後1回分です。 役所を退職して、食品衛生コンサルタントを目指して、こつこつと書き続けたのが良かったのでしょうね。視界が広がってきた気分。 これから、山口の湯田温泉です。レジャーなら良いのでしょうが、講演です。
2005年04月26日
コメント(0)
-
BSE問題について
我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会プリオン専門調査会にコメントを出そうと考えていました。 私の考えは「は20ヶ月未満は解除して、早急に米国からの輸入を再開することに賛成です。」 一青窈(ひととようの「一思案」を聞いていて、こういう文体もいいなぁと思いました。 BSEは牛のやまいです。かわいそうに16頭見つかりました。 人の病気はvCJDです。日本人はイギリスで牛の脳みそ入りのハンバーグを食べた人1人。 どうして危険なの。マスコミが危ないというから。 マスコミが言わない(言えない)カキは大丈夫なの。 私の周りでも過去に3分の1の人が当たっていますよ。だけどだれも騒がない。 ノロウイルでは死なないはず。でも今年の正月6人も7人も亡くなりました。 私は牛さんの健康より、国の安全の方が大事です。 ライス国務長官が来日した時、アメリカの要求を蹴飛ばして、「ビーフの問題だけで来たわけじゃないと。名前がライスだからね」は冗談きつい。 ブッシュの地元はテキサスですよ。 常任理事国入りに反対してますよ アメリカも テポドンが飛んで来たとき、何とブッシュに頼むのでしょうか。 アメリカの牛肉を食ってもvCJDにはかかりませんよ。 どうしてもvCJDが怖いなら、オージビーフが安全です。 全て、肉骨粉を与えていないとの証明付きですから。 日本のトレーサービリティは肉骨粉を与えていないとは書いてない。 エイジングという昔肉屋さんが使っていた手法を使えば 柔らかい赤みのおいしいお肉が食べられます。
2005年04月25日
コメント(0)
-
花みづきが満開
花みづきが満開でした。板櫃川の散歩の途中に妻がせりを摘んできました。今日はせりごはんです。 「FOOD SCIENCE」4月29日(金)が祭日で5月6日UPの原稿を書いていました。今回は従業員教育について書きます。
2005年04月23日
コメント(0)
-
もう鯉のぼり
散歩に出たら、板櫃川に鯉のぼりが多数泳いでいました。 月刊HACCP5月号が届きました。私の原稿実用講座「食監が見た食品製造現場」は6月号から3回と延期になりました。 HPを更新しました。 従事者教育はどうしてますか? ノロウイルス食中毒患者が平成16年食中毒患者総数の43%を占めています。1番多い感染ルートは従事者の手指からです。昔から「食品衛生の基本は手洗い」と言っていました。トイレ後に手を洗わない人は少ないでしょうが、はたして、きちんと洗えているのでしょうか。「食品衛生管理への道」衛生管理運営基準教育プログラム用平成17年度FAX通信が始まりました。
2005年04月22日
コメント(0)
-
松浦鮮魚市場を見学しました。
また地震がありました。朝早く、松浦市の西日本魚市(株)さんの案内で魚市場におじゃましている時でした。私は外に立っていましたので、気が付きませんでした。 、漁場に近い関係で鯵、鯖が多く、相場をネットに流したり、衛生管理も充実しようと、がんばっています。西日本魚市(株)はドーム型のパック工場を作っていました。魚の洗浄を人工海水を使い、オゾン水で仕上げており、鯖も日持ちが伸びたそうです。腸炎ビブリオの食中毒が激減したのも漁港の腸炎ビブリオが一杯の海水を使わない事が効果を上げているのでしょうか。
2005年04月20日
コメント(0)
-
松浦市に行ってきます
今日は午後から松浦市に行ってきます。 魚関係の工場に東京の加藤先生のお供で見学に行ってきます。 水産関係のHACCP 多分、対米、対EUだと思います。むかし、松浦は歴史をひもとくと日本文化にとって重要な地点だったそうです。海のシルクロードといい、このルートは松浦党がしきっていたそうです。 中国の反日デモが連日報道されている中 こういう文を見つけまいた。中国の人も分かっている人はいるのです。ほっとしました。◆中国はどうして日本に後れを取ってしまったのか 林 思雲
2005年04月19日
コメント(0)
-
●バイキングが明太子の偽装表示に加担?
日本経済新聞系列の日経BP社「FOOD SCIENCE」 に下記の記事をあげました。保健所OB便り●バイキングが明太子の偽装表示に加担? ロンドン在住の友人からメールが届きました。「当方のパートナーであるバイキングの末裔エリック君が、アイスランドでタラコ、明太子の製造をしたいというので協力してくれないか」という話です。
2005年04月17日
コメント(0)
-
亀さんのひなたぼっこ
昨日は、、雑誌、新聞からの取材が続きました。食材の危険について(日経レストラン)異物混入(産経新聞)。 月刊HACCPは20日過ぎに実用講座 食監が見た食品製造現場 第1回HACCPの考えで食中毒予防 を掲載します。 連載の2回目の締め切りが迫ってます。 今日は、板櫃川にいる亀さんのひなたぼっこの写真で。
2005年04月16日
コメント(0)
-
食中毒の質問にお答え願えませんか(結び)
シンガポールの食中毒事件は、3月4日にメールが来ました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 突然ですが,今ごろになって今回の食中毒事件は、業者側に責任がある という記事が新聞にでましたこれまでも、レストラン側と話をしたり、大 使館経由でシンガポール保健省に聞いてみたりしたのですがどうもラチが あかないなと思っていたら、突如、シンガポール保健省の発表という記事 がでました。 記事を読んだ限りでは、どの菌が検出されたというようなことは一切でて おらず、何を今まで調査した上での結論なのかさっぱりわかりません。レ ストランも通常営業しており、私たちも、あきらめ気分が漂っていたとき の記事なものですから、驚いています いずれにしろ、自分たちの言い分が認められたということでとりあえずホ ットしております ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 疫学調査や細菌検査の結果を大使館経由でシンガポール保健省に求めた 結果、業者の責任となったようです。ひと安心ですね。 今回の事件は、国及び国民の食中毒に対する考え方や食文化の違いが影 響しているように感じます。タイに毎年のようにボランティアで行って見 て食文化の違いは、その国の衛生状況から出来上がっている事がわかりま す。 河川が短く急勾配の水清き日本は、生食文化で、蕩々と流れる大河の水 を使用する食文化は、油で揚げる、じっくり煮込む文化です。東南アジア は人口も多く、飲食業に携わっている人も多く、豊富な食材が手近にあり ますので、保存するより、料理して直ぐ食べる文化です。つまり、食堂は どこでもあり、安くおいしい食事が提供されていて、数時間後に食べる弁 当という形態は少なく、外食、中食(テイクアウト)文化でそれほどシビ アな衛生管理をしなくても安全なのでは。気温が高く冷蔵施設が不足の国 では、十分火を入れる、作ったらすぐ食べるから、以外に食中毒は少ない のでは。食中毒統計もなく、あっても調査体制が不十分では日本と比較で きません。
2005年04月15日
コメント(0)
-
お弁当、おにぎりを提供したレストランについて
シンガポールの飲食店営業の許可の状況はよく知りませんが、「衛生 度のランクをしめすA,B,C表示」があるとのことですから、かなり厳格 にされていることと推測されます。また、このレストランのランクはわ かりませんが、たぶんそこそこなのでしょうが、レストランの構造とし て3チーム60~100名分のお弁当を通常の業務に加えて調製する能 力があったかどうかです。店で出す料理と作ってから喫食時間迄の時間 がかかる弁当では衛生管理のレベルが違います。 お昼の弁当を何時から作り始めて、配達迄の時間とその間の温度状況 が問題です。気温が30℃以上の地区で食中毒菌の増殖を押さえるのは かなり厳しい状況です。 もし、黄色ブドウ球菌の食中毒としたら、私の今までの経験からの判 定から言えば残念ながら見た目のランクは別に最低の不潔な店と評価し ます。手洗いをしっかりして、清潔な消毒された器具を使って調製し、 温度管理をしっかりすれば防ぐ事ができる食中毒ですから。日本では発 生件数が減りました。 設備、人的能力が無かったら注文を受けないことです。 つづく
2005年04月14日
コメント(0)
-
山陰長門 みちの駅おふく
今日は湯本温泉に行って来ました。温泉に行ったのなら良いのですが、ホテルの衛生指導で仕事でした。福岡はうば桜ですが、こちらは満開でした。途中の「道の駅」の裏は見事な菜の花畑でした。
2005年04月13日
コメント(0)
-
見た目の清潔さと細菌学的な衛生的とは違います。
次に、 「状況は、日本人中心のソフトボ-ル大会で、同じレストランに注文 した弁当を食べた人が,激しく嘔吐下痢に見舞われ、計40人に症状がでて 15人ほどが入院しました。状況からみれば明らかにその弁当が原因とい うことですがどうも地元の新聞、および厚生省の調査では、レストラン 側は問題なし、弁当が届けられた後の保管の仕方が問題という風潮にな っています。」 その後のシンガポール在住の人からの追加メールで 「症状が出たのは,早い人で、2~3時間後です。私たちのチーム内でこ の弁当を38個注文しましたうち、まったく手をつけなかったのが3個ほど で、10人ほどに症状があらわれて5人が入院しております他のチーム (計3チームで発生)も同様の状況だと思います 弁当は、おにぎり、ポテト,から揚げで,おにぎりは、さけと、オキアミ (小さなエビ)を揚げたもの1個ずつで症状が出た子はみんなおにぎりを 食べています。食べたときに、変な味がしたという人もいるし、おいしく いただいたという人もいます。ただ、おにぎりにしてはやたら、ボロボロ していたという意見がおおくありました シンガポールは、東南アジア周辺各国に比較すれば衛生状態ははるかに よく、また、各レストランには、衛生度のランクをしめすA,B,C表示がし めされ、進んでいるなとは思っていた」 厚生省の調査では、レストラン側は問題なしとして、弁当が届けられた 後の保管の仕方が問題としています。 潜伏時間、症状から考えておにぎりによる黄色ブドウ球菌による食中毒 の疑いが強いようです。 私は、レストランの衛生状況を調査したわけでも何という名前のレスト ランか知りませんが、多分衛生度のランクも高く、厚生省の調査の印象は 良かったのでしょう。ただ、細菌検査の結果や従事者の傷の有無、受け渡 し時間、弁当の調製時間から喫食までの保管状況がなのもしめされていま せんので断定的な事は言えませんし、患者側に説明がないまま、患者側の 責任にするのは少し酷ではないかと私は思います。 日本での解釈は、病因物質を付けた所が(製造者)が責任を持ちます。 食中毒は菌やウイルスが存在しなければ発症しません。環境中にたくさん 存在している腐敗菌とは違います。 見た目の清潔さと細菌学的な衛生的とは違います。 私たちは毎年のようにタイに行き、屋台には行きますが、日本人観光客 の多いレストランは食中毒のリスクがあると思い行きません。屋台ではそ の場で加熱(消毒)した料理をいただきます。旨いし、安いし安全です。 現地のタイ人に案内してもらうと旨い店を知っています。一方、日本人グ ループは生食を注文し、テーブルに付いたら直ぐ料理が出ないといけませ んので、作り置きをしている事が多いのでは。現地のタイ人は「おいしく ないよ」と言ってそんな店は私たちを案内しません。 東南アジアでは見た目の清潔さは信用していません。おにぎりは生食で はありませんが、手でにぎる。喫食までの時間を考えるとリスクの高い食 品です。その意味で気温の高い屋外の行事におにぎりという選択は関心し ません。だからと言って患者側の責任と言うことにはならないでしょう。 つづく
2005年04月12日
コメント(0)
-
疫学的手法で食中毒調査の方向性を定める。
疫学的手法を使えば、メールの文だけでこれだけの事が推定できます。食中毒調査の方向性を定め、黄色ブドウ球菌食中毒特有の検体である検便、吐物、その時に使ったタオルやテッシュ、弁当の残物を集め、施設調査では、聞き取り調査、従事者の手指、鼻孔の異常はないか、施設のふき取り、手指のふき取り検査を行うなどきっちりポイントを押さえる事ができます。もちろん推定ですので、他の食中毒菌やウイルスの事を頭に置いておくのは当然です。 平成9年の堺市のO157食中毒事件では、私はテレビ、新聞からの情報は持っていませんでしたが、共通食という考えを取っていたら、ずいぶん違っていたのではと思っています。最初の段階で多数の小学校から同時に食中毒が発生していて、給食は自校方式なら、給食室での2次汚染の可能性は無く、未加熱の共通食材が疑わしいと推理しました。当初食材はマスコミ報道は無かったのですが、担当部局は食材リストは手にしていた筈です。給食室に保存されていなかっても参考品でも近い日付の食材を確保し、農場の検査をすれば早く判明したのではないでしょうか。福祉施設で同じ農場のカイワレで起こしていますので、食材のカイワレから菌の検出はできたのではないでしょうか。 当時パソコン通信の生活衛生フォーラムでこの事件が話し合われていましたが、共通性のある食材ということでカイワレ説を書いたら、菌が検出されないから違うとの反対意見がほとんどでした。 ドクターも多く参加していましたが、細菌検査、化学検査結果を重視し、疫学は全くと言って良いほど評価されませんでした。そのころ、CDC(アメリカ防疫センター)の疫学の専門家が応援に来ましたが、よく意見を聞かず京都見物をさせて帰っていただいたというニュースもありました。 つづく
2005年04月11日
コメント(0)
-
桜は満開です。散歩コースの板櫃川の風景
福岡地方は桜は満開です。我が家も庭でバーベキューをしながら家の前の公園の桜を借景として花見としゃれ込みました。と言うことで、今日は食中毒調査はお休みします。 散歩コースの板櫃川の風景を上げて置きます
2005年04月10日
コメント(0)
-
食中毒調査で共通食という疫学は重要です。
食中毒調査で、押さえるポイントの第2は、原因施設と原因食を確定させることです。昨日はオッズ比を紹介しましたが、それよりずっと分かりやすいのが共通施設、共通食を探ることです。特に原因施設を探す時は有効です。 「発症した人は食べた人。食べてない人は発症しない。」と言うことで絞っていきます。複数の患者が食べた施設や食事の共通性にに注目しています。ただし、逆の同じ物を食べても体調や菌量により発症しない人もいます。他の原因で体調を壊した人もいます。このような人がいると、オッズ比で押さえる必要があります。 患者 1/20 1/21 1/22 朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 A 自 外 自 自 外 自 自 弁当 B 自 外 自 自 外 自 自 弁当 C 自 外 自 自 外 自 自 弁当 自(自宅) 外(外食) シンガポールの事件の場合、患者が発生した3チームのメンバーは当日の朝まで違う食事をしており、共通しているのは弁当だけです。また、発症時間が集中している単一暴露でので、当該弁当による食中毒と判断します。 原因施設まではほとんど共通食で搾り込みが出来ますが、結婚式の披露宴など全員の聞き取り調査をしても個々の料理を食べたかどうかの記憶が不正確になり、原因食が判明出来ないときがあります。 簡単なことなのですが、精密機械を使った検査結果を重視し、足と耳と鉛筆でまとめた疫学は信用して貰えない傾向があります。この手法が有効なのは、検査結果を待たずに調査、指導の方向性が見えることです。食中毒調査において、食品衛生監視員は常に飲食による危害を防止する目的があり、進行中の事件では拡大防止を図らなければいけません。そのため出来るだけ早く判断し営業を自主的にストップさせたり回収をお願いします。拡大防止は当該営業者のためでもありますから。 ただし、病因物質不明で行政処分伺いで上司のOKは難しいかもしれません。ですから、私は検体確保には努めました。患者の市民から苦情が来るのは食品衛生監視員としては辛いことですから。 つづく
2005年04月09日
コメント(1)
-
疫学検査で食中毒を推定する
家の前の公園の桜が満開です。 昨日はおにぎりによる食中毒との連想でテレビの救命病棟24時の話になりました。話を「食中毒の質問」に戻します。 食品衛生監視員だった頃の私だったらどう考え、行動するかを書いてみます。もちろん日本とシンガポールは、法律も体制も違います。 症候学的観察で黄色ブドウ菌食中毒ではないかと推定しました。それを確定するのは細菌検査が必要です。そのため食中毒調査では必ず採便管と滅菌コップを持って行き、便とあれば吐物、残物を採取します。このように検体確保が重要ですので、探知したら直ぐ動きます。ここを疎かにしますと、原因不明となったり、不満が出たりとトラブルの素となるケースが多いようです。 食中毒調査で、押さえるポイントの第1は、食中毒かどうかの確認です。下痢、嘔吐と言っても風邪も胃腸障害、他の病気の事もあります。食中毒は食に起因した疾病ですから、食事で感染した赤痢、コレラ、ノロウイルスでも食中毒ですし、老人福祉施設や保育園で人から人で感染すれば感染症となります。検査は病院でもしますが、日本では行政機関が検査機関を持っていますので直ぐに採取して検査します。病院で検査されることもあります。 「食中毒の質問」の場合、病因物質が知らされていませんので、これだけですと食中毒かどうかの判定はできません。病因物質が分からないと食中毒ではないかと言うとそうではなく、食が原因と判断できれば病因物質が分からなくても食中毒です。 細菌検査がなされなかったり、検査が遅れて菌が検出されなくても、統計を使った疫学で原因を見つける事ができます。 ソフトボール大会で昼食を食べた人全員に協力していただいて、4つのグループに分けます。仮に1チーム応援も入れて20人として、10チームで200人参加。レストランの弁当は3チーム60人分、患者が40人とします。 オッズ比で見ることもできます。ある事象のオッズ odds とは、その事象が起こりそうもないと思われる回数に対する起こそうだと思われる回数の比と定義され、通常は比や分数で表されます。表5 食中毒における原因食品推定の例 患者群 対照群(健康)食品名 食べた 食べない 食べた 食べない オッズ比 a b c d ad/bcRの弁当 40 1 20 140 280Aの弁当 0 140 70 60 0Cの弁当 0 140 70 60 0 ごく簡単に言えば「弁当を食べて患者」×「食べなくて健康」のグループは弁当が影響しているます(その事象が起こりそうな回数)。体調とか弁当の菌量等により食べても健康な人も、別な要因で症状のある人もいますので、「食べないで患者」×「食べて健康」はレストラン弁当は影響ないとするグループ(その事象が起こりそうもない回数)でこのオッズ比が高い弁当が食中毒の原因食品と推定できます。 食中毒菌により、潜伏期間といって発症までの時間が異なります。そこで、発症時間をグラフに書くことも有効です。 ピークが1峰性であれば、単一暴露と言い食事時間が一緒と判断されます。ピークが一定してないようなら、水の汚染や人から人の感染症、保存食、加工食品のように同じ時間に食べない時にでます。「食中毒の質問」の場合、発症時間が集中しているようで、単一暴露でレストランの弁当が原因と推定できますので、このような調査結果を要求するようにアドバイスしました。 疫学は、1854年まだ病原菌の正体が分かっていない時代に、ロンドンでコレラ死亡者の発病月日を地図にプロットするとある地域に集中していることが見つかり、この地域とほかの地域の水や食べ物を統計処理してコレラの感染源が1つの水源であることを見つけた事例が有名です。 「疫とは人民に大規模な災いをなすもの」という意味があり、この災いを解明する学問が疫学です。疫学を使う目的は、あるデータの集合体の統計処理でその疫を予防することです。つまり、将来を見る学問です。 記述疫学は、ストーリーを見つけ、原因を追求していきますので、推理小説の人間関係、動機、アリバイ等の状況から追う調査に似ていて、細菌検査、化学的検査で見つけた物証で補強、確定していきます。疫学はこうなったら事件が発生する等将来の予防に役立つ学問です。つづく
2005年04月08日
コメント(0)
-
救命病棟24時最終回の食中毒について
少し脱線します。先日私の地元福岡で大きな地震がありました。家は北九州でしたから被害はありませんでした。元の勤め先福岡市役所では、実験用のガラス器具が割れたとか、書棚が倒れたと被害があったそうです。被害の大きかった玄海島の皆様にお見舞い申しあげます。 地震の少し前にフジテレビ系列で震災後の救急医療を描いたドラマ「救命病棟24時」を放送していました。最終回で誤って消費期限切れのおにぎりを食べて看護師とドクターたちが食中毒に罹ったという筋書きでした。 そこで、私が少し違和感を覚えた事をかきます。「あの状況で食中毒に罹るかなぁ」という疑問です。作者は5日も経った消費期限切れのおにぎりなら食中毒になるという常識で書いたものです。 しかし、映像では、コンビニで売られているおにぎりのようでした。食中毒予防の3原則に「付けない」「増やさない」「殺す」があります。聞くところによるとコンビニ業界の弁当は、無添加をうたい保存料を使わない方向に行っています。保存料を使わずに消費期限を延ばすには、食中毒菌を付けない、増やさない事に最大限努力している筈です。その結果初発菌量(できたての弁当の生菌数)が低くなってきています。コンビニ関係の弁当は虐待試験といって、30℃の条件で保存し、生菌数が一定数以下にするという規定を設けている所が多くあります。 特におにぎりはロボットで人が触れない状況で作りますので、黄色ブドウ球菌は付いてないでしょう。しかし、腐敗菌は空気中にもいますので、消費期限が切れれば腐敗を始めます。ドラマでは看護師とドクターが食べていますので、そんなに腐敗が進行してない状態です。その状態では、私は、黄色ブドウ球菌による食中毒を起こす可能性は低いのではないかと思ったのです。 私はコンビニ関係の仕事もしてませんし、実験する気もありませんし、おすすめするわけでも安全を保証するわけでは決してありません。 一方シンガポールのレストランは、お店に来るお客さんに提供するのが仕事ですので、衛生管理のレベルはコンビニのおにぎりとは全然違います。配達するという時間と気温条件も加味しますと、黄色ブドウ球菌による食中毒を起こす可能性は非常に高いと思われます。 同じおにぎり、弁当であっても製造過程の衛生管理によってリスクは違うということ。温食弁当、駅弁、コンビニ弁当はお客さんが食べる迄の時間が違いますので、衛生管理のレベルが違う。新鮮であれば安全という日付表示過信をしないということです。
2005年04月07日
コメント(2)
-
食中毒の質問にお答え願えませんか 2
このような状況の場合、日本の保健所ではどのような対応を取 るかという質問に、私なりに考えて見ました。 食中毒調査は 「食中毒処理要領」というマニュアルに定められており、原則的にそのマニュアルに沿って調査を行います。 趣旨に、食品衛生の究極の目的は、飲食に起因する衛生上の危 害を防止することにあるが、もし万一食中毒事故の発生をみた 場合には、直ちにその拡大防止に努めなければならない。その ためには、事故発生を早期に探知もしくは発見し、その事故の 原因を追求し、できるだけ迅速に原因となつた食品や発生の機 序を排除するための適切な措置を講じなければならない。とあ ります。 食中毒事故を探知したら、直ちに調査を開始します。食中毒調 査というと直ぐ細菌検査をイメージしますが、食品衛生監視員 として調査にタッチしていくと、食中毒事件全体の構成を調べ る事が重要で、細菌検査も調査の中の1つの検査に過ぎないこ とがわかります。疫学とか事件の状況で見ていく事が多いです。 病原微生物の性質、症状や潜伏時間等から、様々な状況を当て はめて推理していきます。人は同じ様な間違いや勘違いを起こ しますので、同様の事件から見たり、その裏付けを取って行く 等刑事ドラマや推理小説とよく似ているのです。相手は食中毒 菌ですから、人為的なアリバイ工作をしませんので、推理しや すく、細菌検査や理化学検査結果が決め手になるだけです。 原因の追求のトップに、「症候学的観察」があり、食中毒は、 原因食品摂取後、数時間からおそくとも3日以内におこるもの であり、その症状も、微生物性のものは急性胃腸炎の形をとる ものが多く、病因物質によって独特な症状があります。嘔吐を 主症状とするのは、黄色ブドウ球菌、ノロウイルス、セレウス 位です。 質問の状況は、「日本人中心のソフトボ-ル大会で、同じレス トランに注文した弁当を食べた人が,激しく嘔吐下痢に見舞われ、 計40人に症状がでて15人ほどが入院しました。」 患者さんの発症は食べてから早いようで、「激しく嘔吐下痢」 から判断して、黄色ブドウ球菌による食中毒と推理しました。 昔は同じ様な食中毒がおにぎり(福岡地方はかしわのおにぎり が多かった)で起こしていました。 この「症候学的観察」は基本で、第1報が電話で入っても、記 者発表用の資料でも必須です。過去の和歌山のカレーヒ素事件 では、最初の症候学的観察が不十分でヒ素中毒を黄色ブドウ球 菌食中毒と間違え、当時の中学生がこれに気づき、文藝春秋に 詳細に書いて間違いを指摘したのを読んだ事があり、スタート を間違えると大変です。 取りあえず今日はここまで。
2005年04月06日
コメント(0)
-
食中毒の質問にお答え願えませんか
今は海外にもたくさんの人が住んでいます。そして、食中毒に罹るリスクは高いわけです。症状の治療は病院で受けられますが、食中毒か否か、責任はという問題が起こります。そのようなケースでインターネットとメールで解決に向かったケースを紹介します。皆様から意見をいただきたいし、意見を書き込みたいので、数回の連載にします。ーーーー2月3日受信ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーはじめまして。わらにもすがる思い出ホ-ムペ-ジを探しましたところ、このHPにめぐりあいました。私たちは、現在、シンガポ-ルに在住しております、実は現在、シンガポ-ル在住の日本人で集団食中毒が発生しております。状況は、日本人中心のソフトボ-ル大会で、同じレストランに注文した弁当を食べた人が,激しく嘔吐下痢に見舞われ、計40人に症状がでて15人ほどが入院しました。状況からみれば明らかにその弁当が原因ということですがどうも地元の新聞、および厚生省の調査では、レストラン側は問題なし、弁当が届けられた後の保管の仕方が問題という風潮になっています。しかし、以上の点から省みれば、私たちはどう考えても、レストラン側の調理過程に問題があるのではないかと思っています1)こういったソフトボ-ル大会は、たびたび行われており、当たり前で すが、日本人は保管の仕方には充分気をつけている これまでに事故なし。現地の新聞のでたように、ひなたで保管してい るような人はだれもいない。2)入院した患者の中には弁当到着後、すぐ食べた子供もいる。3) 今回、ソフトボ-ルチ-ムには10チ-ムが参加。3チ-ムから患者 が発生しており、この3チ-ムは同じレストランに注文しており他のチ -ム(別の業者に発注)からは一切患者がでていない.仮に保管の仕方が 悪かったら、他のチ-ム(業者に関係なく)でも発生するはずである。4)問題のレストランに2種類の弁当をオ-ダ-したが、患者は,すべて1 種類の弁当を食べたものに集中している ただ、厚生省の検査ではどうも菌が検出されないようです(明確な返事はない)ただ、この検査も、食中毒発生が1月22日。食堂への立ち入り検査が24日,25日で業者調理関係者の検便が25日で実施。 まだその結果がでなくて結果待ちの状況です。検便等が実施されたのも発生後3日後、しかも現時点で(2月2日)でまだ結果がでていないなど、ちょっとこちらの厚生省の対応を遅い気がします。また病院での検査も、検便検査させられた患者はわずかでそれも抗生剤投与で菌を放出させた後の検査とこれでは菌がでないの当たり前という状況で行っています以上のような状況で、厚生省の判断がたとえシロであろうともどうも私たちとしては納得できませんそこでお聞きしたいのは、日本での状況です1)たとえば、立ち入り検査は、事件が発生してから2日後に行われてい ます。日本ではどのような対応をとるのでしょ-か2)従業員の検便が3日後に行われていますが、これは意味があるのでし ょ-か3)病院での初期検査体制は日本と比べてどうでしょ-か4)最終的に業者に責任ありという判断がされるにはどのような条件が必要 ですか。現在は上記の状況証拠だけで、菌が検出 されたいう情報は確 認できていません ながながと申し訳ありません。もちろん,日本の厳格さをあてはめる無理は承知の上で質問ですが、どうもこちらの行政、病院の対応含めて非常に不満があり、質問した次第です。また,今回患者がでた、3チ-ムは優勝,準優勝,3位ノチ-ムであり、特に決勝は、最初からでれない選手、試合中に具合が悪くなる選手、親御さんが続出しました。せっかく,一生懸命練習したのに,晴れ舞台にでられず、あげくのはてに保管に問題ありでは、ふんだりけったりです。お忙しいとは存じますがどうかご回答よろしくお願いします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 私も毎年のようにボランティアでタイに行きますが、現地の人はタイ語でマイペンライ(どうにかなるさ)で、この状況で意見を通して行くのは大変ですし、黙っとけばそれでお終いになります。私の回答は明日のblogで。
2005年04月05日
コメント(0)
-
「堀江さん批判」講演会で北尾さん
我が家の前の公園のさくらがやっと3分咲きです。昨日発行予定のメルマガ「食中毒2001」がまぐまぐの都合で今日になってしまいました。今回は「●HACCPが何なのかピンとこない 読者から質問」です。 堀江氏の手法を強く批判 SBI北尾氏、講演会で フジテレビジョンの筆頭株主になったソフトバンク・インベストメント(SBI)の北尾吉孝最高経営責任者(CEO)は3日、名古屋市内で講演し、ライブドアの堀江貴文社長について「(ニッポン放送の)役員から社員までライブドアが嫌だと言っている。株を50%持ったから、もうわたしの支配下だと。わたしはそういうことが嫌いだ」と強く批判した。 北尾氏は「相手のことを思いやることを堀江君も考えてほしい。わたしが買収するときは、相手にとっても良い状況をどう実現するかを真剣に考えている」と述べ、敵対的買収はすべきでないとの考えを強調した。(共同通信) これに対し、みのもんた朝ズバッでみのさんはかなり批判的な意見を言っていました。ライブドアの美人広報を呼んでいるからでしょう。 高裁の判決以降、会社は誰のものかという議論では、一応株主のものとなっていますが、その会社の価値を決めるのは、会社の形態にもよりますが、社員が価値を決めているケースが多いのではないでしょうか。 日本放送を買収できても、ライブドア支配下の日本放送で投資に見合う利益が得られるでしょうか。もし、仮にフジを買収できても(私は堀江さんはできないと思っていますが)フジの持っているコンテンツ製作能力はかなりの部分は社員やチームに起因していますので、同じように製作出来るのか疑問です。 最初から、ライブドアの堀江さんの勝算は無かったのでは。だから敵対的買収は間尺に合わないよと、北尾さんが言っているのに、みのさんは「買収と結婚を同じと考えている」と批判しています。何を聞いているのでしょう。 何か堀江さんを時代のヒーローのように放送しているテレビ局は半年か1年後、なんと言うのでしょうかね。多分知らぬ顔で批判しているのでしょうね。
2005年04月04日
コメント(0)
-
営業マンは断ることを
明日、顧問をしているシー・アール・シー食品環境情報 (食品環境衛生研究所)で営業に関するお話をすることになり、「営業マンは断ることを覚えなさい」経営コンサルタントの石原明さんの本を引っ張り出してきて読んでいます。 役人生活から外郭団体の試験研究機関に行き、そこを辞めて、ハローワークでも59才、求人はありませんよと言われ、取りあえずバックアップ無しに食品衛生コンサルタントを始めたころ、どうやって飯を食っていこうかと考えたころ良く読んでいました。 食品衛生関係もふきとり検査や製品検査が非常に重要になると同時に競争が激化する事を考え、売れる仕組みは、興味ある役に立つ記事が多かったです。
2005年04月03日
コメント(0)
-
BSE対策意見募集
全頭検査緩和で意見募集 BSE対策、食品安全委 牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しで、内閣府の食品安全委員会は31日、プリオン専門調査会がまとめた全頭検査緩和を容認する答申案について、一般から意見を募集することを決めた。 食品衛生監視の現役のころから、BSE問題を私なりに考えていました。私は危険部位をきちんと除去することで安全性に問題がないのなら、出来るだけ早く、輸入を再開すべきです。安全性の問題は国際基準に合わせるべきと考えています。 全頭検査。「全部検査するから良いじゃないの」「しないよりした方が安全・安心でしょう」多くの人の意見です。 このような「One-word Politics」という1言で決めることでは無いと思います。 この全頭検査「One-word Politics」を越えて考えるには、意見を発表すべきと考えています。日本経済新聞系列の日経BP社「FOOD SCIENCE」に書きました。是非読んでみてください。保健所OB便り●分析検査は過去の記録、将来予測は疫学から
2005年04月02日
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
-
-

- 癌
- 最後の納骨 総持寺へお出かけ
- (2025-10-08 21:00:05)
-
-
-

- ダイエット!健康!美容!
- 🐟11月の最旬!脂のり最高潮「寒サワ…
- (2025-11-17 08:50:20)
-