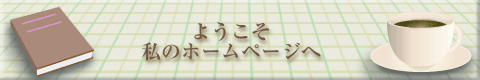2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年05月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
食の安全を考えるつどい
麦秋 福岡県久留米JRから 関東から関西の食品衛生監視員有志によって、毎年監視員の勉強会が開催されています。28日日、29日と以下のテーマで千葉で開催されます。「第10回食の安全を考えるつどい」 シンポジウム「リスクコミュニケーションはどこまで可能か(理念と実態を通して考える)」 私は、はじめて参加します。 また、「週刊SPA!」の「事故・災害から身を守る[不幸の確率]の取材をうけます。6月14日発売号カラー特集ページだそうです。
2005年05月28日
コメント(65)
-
メールマガジン★ 食中毒2001 ★発行
メールマガジン★ 食中毒2001 ★を発行しました。 5月、6月は行政の食品衛生講習会や各種セミナーが開催され、従業員の教育を考える時期です。私も東京海洋大学(旧東京水産)で「食品事故の現場」からというテーマで1日講義する事になりました。また、ある生協からのHACCPのアドバイザーの依頼、月刊HACCPの連載、セミナー講師依頼も来ています。改正された食品衛生管理運営基準も教育を重視しています。 JR西日本の列車事故も従業員教育のあり方が問題となっています。従業員教育をどうしたら良いか連続して考えていきましょう。
2005年05月22日
コメント(0)
-
JR事故と衛生教育
日経BP社「FOOD SCIENCE」にJR事故と衛生教育を書きました。保健所OB便り●JR事故と衛生教育 JR西日本福知山線で多数の死者を出すという大きな列車事故が起こりました。会社の対応やその後のマスコミ報道を見ていると、私には、雪印の黄色ブドウ球菌食中毒事件がダブって見えてきます。今回は、JR事故と衛生事故について考え、ここから衛生教育のあるべき姿を探ります。 マスコミ報道から判断すると、JR西日本のシステムは、精密なダイヤ、厳格なマニュアル、作業手順書、それを守らせるための教育手法として、日勤教育(再教育)という恐怖教育を含む強制的な手法のように見えます。このような上からの命令型方法はそれなりに効果はあるのでしょうが、職員を思考停止状態にする恐れがあり、職場が暗くなり、事が起こると責任追及型になります。事故直後に責任逃れと見られるような置石説を発表したり、事故が発生しているのにボーリングやゴルフに行ったり、それがまた内部告発的に報道されてしまいます。
2005年05月20日
コメント(0)
-
団塊の世代の退職問題を考える
団塊の世代の退職問題を考える 食品衛生コンサルタント 西村雅宏 人生80年です。定年後はまだ20年あります。20年学んで行けば専門家になれます。勝負時を定年後に置けば見方がかわります。色々と自分で計画を立てるのは楽しいものです。 そこで、健康生きがいづくりアドバイザーやシニアライフアドバイザーの資格を取り、仲間をつくり、研究をしてきました。目標としては、75歳まで働く、クリエイティブな仕事、何かお役に立つ仕事。妻と2人3脚になるような仕事をあげ、20年近く考え続けてきました。結局起業するしか、この条件を達成することは出来ない。それには、何が必要か。出来れば、それまでの経験を生かせる事をと考えてきました。 市役所では保健所の食品衛生監視員として、飲食店や食品製造業の指導を行っていましたので、食品衛生講習会を数多く行います。その業界の人達との付き合いもあります。大きな食品事故を続発し「食の安全」についても関心がたかまってきました。 また、ABCキルトJAPANというエイズの赤ちゃんにベビーキルトを送るボランティアでホームページを任されていましたので、インターネット関係の取り組みも早く、情報の発信にも慣れていました。 定年後の青写真を早めに作り、そのための能力開発を心がけていました。こう書くとすごく計画的なようですが、そうでは無く、最初は漠然とした目標であっても常に頭に置いて行くと選別できるようになってきました。 平成13年に58歳で役所を早期退職し、食品衛生の検査機関に就職しましたが、目標とのギャップが大き過ぎると思い、9ヶ月で退職し思い切って「食品衛生コンサルタント」として平成15年独立しました。 これから、退職して起業を目指す人へのアドバイスとして1 ユニークさを目ざし類似問題を探し回るな 団塊の世代が退職して働こうと再就職を考えている人は多いと思います。私 も、食品衛生の検査機関を辞めてからハローワークに行きましたが、60歳前後 の求職はありません。あっても不本意な仕事ばかりです。経験もない飲食業を 開業して失敗して退職金を使い果たした人をたくさん見ています。 みんなが考える先でなく、視点を変えて見ましょう。団塊の世代が退職すると いうことは、勤務していた会社にとっても人材がいなくなることを意味します。 その業務を誰かがする事になります。リストラの時代ですから、安易に人を増や せません。経験知識を要する1部業務を高いレベルの外注でまかなおうと考えて います。また、退職者がフリーになるということは雇用契約の会社だけでなく、 他社も含めて幅広く仕事が可能となる事を意味しています。仕事の開拓が可能な 時代となりました。2 目的展開で考えていこう! 定年後どういう目的で生きていくか、何をしたいかを考えていこう。「好きこ そものの上手なれ」ということわざもあります。3 先の先から見た「あるべき姿」という、夢を語りましょう! 目的展開で導き出された「あるべき姿」(夢、理想など)を思い浮かべる方法 です。未来の“あるべき姿”を決めることで現在を未来から“引っ張る”考え 方です。なお、制約などマイナス面は、ここでは考えないでください4 必要情報(限定)収集。目的に適応した最小限の知識を得よう! あるべき姿に向かって必要なスキルを磨いておく。私の場合は「ネットー人と インターネット」「話すこと」「書くこと」「専門知識」です。 準備段階では以上の4つに事を考えてきました。食品衛生コンサルタントと言ってもたくさん同業者がいるわけでもありません。バックがあるわけではありません。決して安易な道ではありません。当初、定期的な収入がありませんので、飛び出す勇気が必要です。個人営業ですから、妻の協力も必要です。 現代は個人で情報を発信することができます。 パソコン通信の時代から、会議室に意見を発信していました。ホームページ、メールマガジンも立ち上げて10年になります。メーリングリストにも参加しています。著書は2冊出しました。専門雑誌にも記事を書くようになりましたし。非常勤ですが大学で講義をすることになりました。当初予想していた通り、この分野は人材が少なかったのです。ホームページ食中毒を防ぐ知恵 (検索key:食中毒を防ぐ) http://www32.ocn.ne.jp/~abcq日本経済新聞系列の日経BP社「FOOD SCIENCE」(検索key:FOOD SCIENCE)
2005年05月18日
コメント(0)
-
米国からの牛肉輸入を再開すること
「米国からの牛肉輸入を再開すること」というテーマで2005年4月29日に書いた同じ詩をあるメーリングリストに上げていたら色々と論争になっていました。 医薬品と食品の違いのような意見があり取り上げてみます。 > もともと食品には、ある程度の危険性が存在するものであり、いわゆるゼロリ> スク、100%の安全というものはあり得ません。> これに対して、医薬品については、それが人為的に製造されるものであり、な> おかつ、医師による医療行為として、意図的に投与されるものであることから、> 限りなくゼロに近いリスク、ほぼ100%の安全が求められます。> > 例えば、アセトアルデヒドはシックハウス症候群の原因になるなど、人体への> 毒性が知られている物質ではありますが、果実等にも自然に含まれている物質で> す。> アセトアルデヒトが有害物質だからと言って、直ちに果実の流通を禁止したり、> 果実を食べることを禁止したりする訳ではありません。アセトアルデヒドのリス> クを評価し、ある一定の限度内であれば、許容できるという範囲を定め、その範> 囲内で摂取するようにすると言うことで、リスクを管理します。> > しかし、もしも、医薬品からアセトアルデヒトが検出されたら、たとえ微量で> あって健康への被害がないと予想されても、回収されることでしょう。> > 食品のリスク管理と、医薬品のリスク管理とは、当然、分けて考えるべきと思> います。> > また、BSEのプリオンについて言えば、経口摂取した場合と、血中へ直接投与> した場合とでは、リスクが異なることが知られています。> 例えば、豚にBSEのプリオンを注射すれば、BSEと同様の症状を引き起こすこと> ができますが、豚にBSEのプリオンを食べさせても、豚は発病しません。このこ> とから、豚肉は安全とされています。> > 食品として牛肉を食べる場合のリスクと、vCJD感染者の血液を輸血する場合の> リスクとは、分けて評価すべきと考えます。> > > 》残念ながら、プリオンを持たない人間はおりません。> 》体内に入れば、水銀やフグ毒などと違い、異常プリオン蛋白質は、体内のあちこ> 》ちで、 > 》増殖いたします。(増えます。)> 私の意見 わかり易い説明ありがとうございます。 食品においても、他の多くの食品にもリスクが存在し、残念ながら実際に数として危害が発生しています。その数が多い方に対策の重点を進めて行くことのほうが良いのかと私は考えています。 BSE対策は肉骨粉と危険部位をしっかり除くが重要です。また、不安感が強い食品添加物は認定から使用、表示と対策が出来てますし、最近は大きな危害も発生していません。イメージと違って健康食品の方が健康被害が出ており問題が多いものがあります。 健康食品の規制見直しも始まっていますので、健康食品について注目していくも必要ではないでしょうか。
2005年05月11日
コメント(0)
-
日経レストラン6月号に「食中毒に勝つ」
日経レストラン6月号に私の取材をもとにした記事があります。 今月の日経レストラン第2特集です。うまくまとまっています。特集 食中毒に勝つ! すぐできる現場の知恵25「付けない、増やさない、生かさない、選ぶ」 防止策はひと手間でOK
2005年05月10日
コメント(0)
-
従業員教育のあり方を変えよう
散歩コースの板櫃川の水鳥達です。 JR西日本の事故で、社員がボーリングや飲み会に行っていたことをマスコミは大きく取り上げていますが、よろしくはないでしょうが、マスコミの方にも「いいかげんにしたら、ボーリングに行くことがそんなに大きな事件か、北朝鮮をめぐる情勢が緊迫しているのに」と言いたいですね。。 それにしても、従業員教育のあり方を変えないと、ここぞとばかりに、たれ込みのようなネタが噴出してきますね。押さえつける教育は駄目です。 文藝春秋5月号に 立国の基は「ものづくり」にあり 松下電器産業社長中村邦夫氏が書かれています。 「私は社長就任以来、組織改革、人材育成にも力を入れてきた。ここで大切なのは、大胆な権限委譲。以前は社長の決裁が必要だったものを各事業のトップに任せるのは勿論のこと、現場のことはその担当者の判断に委ねるようにしている。その結果、若手社員は明らかに変わってきた。若い技術者は、かつては上司からの「指示待ち組」が多かったが、今では自ら発想して行動するケースが増えているのである。「プラン・ドゥ・チェック・アクション」(発想せよ、行動せよ、検証せよ、実現せよ)を任されれば、人は総じて意欲的になるものである。」 仕事に生きがいを見いだすような、教育ならば、何が大切なのか各自がわかってくるのかな。 私の本「食品事故で会社を倒産させないためのリスクマネージメント」が参考になるのでは。
2005年05月08日
コメント(0)
-
国産牛の安全性について
散歩コースの板櫃川岸で見つけました。メーリングリストに質問が来ました。> 西村さまは、国産牛の安全性を心配されており、米国のほうが> 安心とよくいわれますが、国産牛の安全性について、何か情報を> お持ちでしたら、ぜひお教えください。 特別情報は持ちませんが、自分で考えて判断しています。 牛がなぜBSEに感染するか言うと、BSEに感染した肉骨粉を食べた からと言われており、その感染源のプリオンは脳や脊髄等のいわ ゆる危険部位にあり、肉の部位には無いと言われています。 昔の英国では、わからないまま、牛の脳みそを食べてvCJDを 発症しました。最初は牛のBSEと人のvCJDの因果関係はわから なかったのですが、疫学調査でプリオンと推定されたのです。 BSE対策で1番重要なのは、感染原因である肉骨粉対策と危険部位 の除去です。そこがしっかりしておけば、牛肉は安全なのではない でしょうか。 日本でBSE牛が発見された時、肉骨粉の使用状況が不明であったた め、BSEの全頭検査が始まったのです。それ以降に生まれた牛は肉骨粉の不使用がはっきりしており、若い牛は安全なのではないでしょうか。 BSEに限らず畜産動物の感染症は、餌と飼育環境、年齢に関係する 事が多いのです。高齢になれば乳も出さなくなりますし病気にもか かります。様々な感染症を持っている可能性が高くなります。危険 なのは、vCJDだけではありません。牛肉由来の感染症は、O157, サルモネラ、キャンピロバクター、抗生物質、農薬とあります。 と場では、獣医のと畜検査員が昔から今後もずっと全頭検査していま す。BSE検査で人が取られ検査が手薄になった可能性さえあります。 牛の餌を含む飼育方法、と殺方法を確認できれば、肉用として育て た米国の若い牛の方が安全だと考えています。 1番安全なのは豪州産です。トレーサービリティがしっかりして 、肉骨粉を使用してない事の証明がないとと場に入れません。 (食肉にはならない)牧場から加工センターまでHACCPで管理され ています。 食の安全はvCJDだけではありませんので、総合的に対策を必要と しているのでは。クレームや健康被害が出ている健康食品の方が問題 ありと思います。
2005年05月07日
コメント(3)
-
ファンを失わないようにするための衛生管理
日経BP社「FOOD SCIENCE」に以下の記事をあげました。今回は外食関係の人には参考になると思います。なにせ儲ける話ですから。保健所OB便り●ファンを失わないようにするための衛生管理 スーパーマケットや飲食店の経営者に「パートさんに食品衛生の教育をしてますか」と聞くと、「この不景気な時に時給を払って研修は出来ない」と返ってきます。研修をやりたいのはやまやま、でもなかなかできないというのが実態のようです。 私はFAX通信「食品衛生管理への道」を会員制で行っています。日常業務の中でより良い衛生管理が出来るような教育プログラムを構築できるようにします。 朝礼で3分間お話しする。資料を掲示する。その後質問をするなどして必ず読むようにし向ける。1週間同じテーマで全員で学ぶ事が効果があります。 詳しくは食中毒を防ぐ知恵(旧保健所の片隅)
2005年05月06日
コメント(0)
-
福岡市は「どんたく」です。
今日から福岡市は「どんたく」です。昔1,2回私も、しゃもじを持って町を歩いたこともあります。同じ行進でも先日の中国の反日デモとは全く違い、沿道の観衆に手を振って、そこそこにあるステージで踊ったりするわけです。 保健所時代、仕事で監視に行ってました。パレードの沿道にたこ焼きやはし巻き、東京ケーキ等をつくって売る屋台がでます。主に露天商(テキヤさん)が営業していますが、調理行為や製造の場合、許可が必要ですので、祭日出勤していました。若い兄ちゃんが多く結構気をつかいます。最近の保健所は祭日までは監視してないようです。 私が回った保健所は1月の十日恵比寿、五月のどんたく、七月の山笠、十月の放生会とテキヤさんと縁がありました。親分格の人とも話を付けることもありました。 なお、博多で名物の屋台はテキヤさんの露天とは違い、酒ありラーメン、天ぷらありで椅子に座って酒を飲むところです。
2005年05月04日
コメント(0)
-
東京都のHPに改正される衛生措置の基準が掲載
東京都のHPに改正される衛生措置の基準が掲載されています。平成17年10月1日施行です。食品営業施設における衛生措置の基準が改正されます。1 すべての食品関係営業者が対象です。 2 条例で規定する製造業者等(食料品等販売業(自動販売機)を除く)3 食料品等販売業(自動販売機)4 条例で規定する給食供給者が対象です。 いずれ「食中毒を防ぐ知恵」マガジンで解説します。
2005年05月03日
コメント(0)
-
分析検査は過去の記録、将来予測は疫学から
メールマガジンの記事を「食中毒を防ぐ知恵」にUPしました。分析検査は過去の記録、将来予測は疫学から 公衆衛生の分野では、統計を使った疫学があります。「疫とは人民に大 規模な災いをなすもの」という意味があり、この災いを解明する学問が 疫学です。疫学を使う目的は、あるデータの集合体の統計処理でその疫 を予防することです。つまり、将来を見る学問です。
2005年05月02日
コメント(0)
-
北朝鮮がミサイル発射か
うそ! という感じです。でもやるかもしれませんね。FIFAの裁定で頭に来ているのでしょか。サッカーは棄権かも。北朝鮮がミサイル発射か 米情報、政府は「確認中」 BSEは牛の病気。かわいそうに牛16頭。 人の病気はvCJD。 昔、イギリスで牛の脳みそ入りのハンバーグを食べた人(たぶん)1人。 肉骨粉、危険部位対策で良いのでは どうして危険?。 マスコミが危ないというから。 マスコミが言わない(言えない)カキは大丈夫。 でも、私の周りでも3人に1人は当たっています。 ノロウイルでは死なないから。 でも、今年の正月6人も7人も亡くなった。 世界一安全な筈の列車事故。 安全地帯と思っていた福岡の地震 絶対安全は無理。 より安全。バランス感覚。優先順序 脅威の最大は戦争。国と国とのバランス。 ビーフの問題だけで来たわけじゃないと。名前がライスだからね 冗談きついね。トップの談話。 ブッシュさんの地元はテキサス。 テポドンが飛来した時、誰に頼むの。 BSEは牛の病気です。日本では16頭。 人の病気はvCJD。患者は1人。 交通事故は7,358人、自殺者32,109人
2005年05月01日
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- スピリチュアル・ライフ
- 物理次元で管理人に起きてきた変化に…
- (2025-11-16 07:00:05)
-
-
-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…
- おじさんの青い鳥
- (2025-11-17 05:30:04)
-