全95件 (95件中 1-50件目)
-
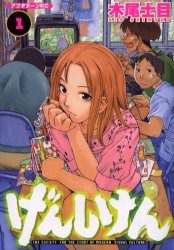
理想郷「げんしけん」!
げんしけん 1 アフタヌーンKC 著者/訳者名 木尾 士目 出版社名 講談社 (ISBN:4-06-321144-4) 発行年月 2002年12月 価格 530円(税込)<感想>とうとう読みました、話題の「げんしけん」。で、想像以上の面白さに、また買っちまった・・・。某大学の「現代視覚文化研究会」に集うオタク達の日常生活を描いた漫画。いや~ 良いな~。自分の学生時代を思い出します。というかマジで入りたいよ「げんしけん」。部室でゲームやったり、ガンプラ作ったり、ダベッたり・・・。自分も実際、そういう学生生活を送っていたのだが・・。私は某国立大学で「ガンダム研究会」または「プロレス研究会」を作ろうと思って、結局「プロレス研究会」を作ってました。一応同人誌も作ったし(笑)。でも結局は「げんしけん」みたいなことをやってたな~。懐かしい。唯一の後悔は女性部員がいなかったこと・・・「プロレス」じゃしょーがないけど、まあ漫画みたいにはうまくいかないよね。社会人になってから、こういう漫画を読むと一種の「癒し」になる。ツライ現実から逃避したいんだな。やっぱ。だから「げんしけん」達の部員が就職活動を始めたりすると、ちょっとゲンナリする・・。初期の頃のダラダラした感じが良いんだよね。主人公、笹原が会長になってからは、やたらコミケ参加に頑張ったりして。まあ漫画のストーリーとしてはしょうがないんだけど、コミケ参加に頑張ったり、ちょっとラブコメみたいになるまでが好きです。秀逸なのが、オタク的視点と一般人の視点の両方が描かれている点かな。一方的にオタクの話だけじゃないのが面白い。作者のバランスの良さが伺えます。漫画中漫画として描かれた「くじびきアンバランス」も本当にアニメ化してしまうとか、今のヲタ文化は本当にすごいんだな~。思わず「くじアン」も観たくなっちまったよ。というわけで今回の日記は「げんしけん」を読んでない人にはまったく理解不能の日記になってしまいました。でも今、イチオシの漫画「げんしけん」。オタクに興味がある人は是非、漫画喫茶ででも一読を!
2006.11.11
コメント(13)
-
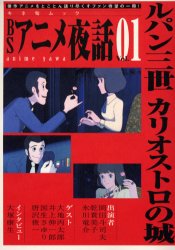
BSアニメ夜話1「ルパン三世カリオストロの城」
キネ旬ムック 出版社名 キネマ旬報社 (ISBN:4-87376-623-0) 発行年月 2006年04月 価格 1,575円(税込)<感想> か、買っちまった・・・。 こういうヲタ系の本はなるべく買わないようにしようと思っていたのだが、あまりの内容の濃さに、本屋をぐるっと一周してから結局買っちまった・・・イタいのは同時に「BSアニメ夜話2 機動戦士ガンダム」も買ってしまったことだ(笑)。 でもこの手のムック本みたいなのはすぐ絶版になるし、内容を見ると資料的価値もありそうなので「まあいいか」ということで。 実は「BSアニメ夜話3 機動警察パトレイバー」の発売も決まっており、そちらも購入予定。このラインナップじゃー買わないわけにはいかん。 で、この本は一体何なのかというと、NHKBSに「BSアニメ夜話」という番組があるらしく、その番組内容を活字化したものなのだ。番組自体その存在をまったく知らなかったのだが、名作アニメをファン代表とか評論家とか数人がアツく語るという討論番組だ。 今回のゲストは岡田斗司夫,乾貴美子,氷川竜介,大地丙太郎,井上伸一郎,国生さゆり,唐沢俊一といった面々。アニメ関係者というか、かなり濃い~メンバーだ。 この本は、番組で討論された内容を活字化した上に、専門用語等の脚注が異常に詳しいので、本として保存版的なものがある。 しかしこの番組、見たことないけどスゴいよなー。いい大人達が公然とアニメを熱く語って成立する番組ってスゴい。 いいオッサンが「カリ城が~」なんて真面目な顔で語ってる姿はスゴいというか嬉しくなってしまう。 いかに好きでもアニメを公然と語れる場って、一般のオトナには意外とないからな~。居酒屋とかで普通のサラリーマンが「あそこでクラリスが~」なんて盛りあがってたら不気味だ(笑)。 そういう意味で「何かを破った」というか、一枚突き抜けた感じする番組だな。「あのあと、主要産業である偽札製造を潰されたカリオストロに残ったクラリスがいかに苦労するか(笑)」だの「カリオストロ公国って伯爵が意外に良い政治をしてることが、酒場や街の雰囲気からわかる」だの「そもそも偽札に興味を無くしたルパンが、カリオストロに潜入する目的は一体何だったのか?」だのマニアックな話が連発。「ああ~そういう見方もあったんだな~」などと、討論内容には感心してしまう。 あと、相当語られたのが監督である宮崎駿の天才性。 関係者に言わせると、仕事量も半端でなくこなすらしいけど、アニメーターとしての才能がズバ抜けてスゴいらしい。 「あ~いいアニメだな~」という感想の裏側にはやはり大量の努力と才能が眠っているのだ。 しかしまた語られるのが、「実はカリオストロが宮崎駿、最初にして最高の傑作だったのではないか?」ということ。 私個人も、「もののけ」以降の宮崎アニメはどうも好きになれないな~という感じがあって、大作になればなるほど、いろんなしがらみが出てきて、監督の才能がシンプルに前面に出てくることはなくなるのかなという気はする。 カネも期間もなかったけど、思う存分作れた「カリオストロ」が最高傑作というのは、ある意味正しいんじゃないだろうか。 「カリ城」は小学生の頃に初めて観て「奥が深いな~」と思ったけど、それから30年くらいたった今でも同じ感想を持てるアニメってのはやはりスゴいな。
2006.11.05
コメント(0)
-
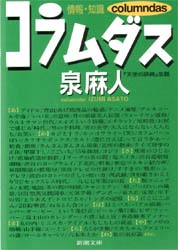
1990年代的なモノ 泉麻人「コラムダス」
コラムダス 新潮文庫 著者/訳者名 泉麻人/著 出版社名 新潮社 (ISBN:4-10-107624-3) 発行年月 1997年09月 価格 580円(税込) <感想> 泉麻人は好きでよく読むほうだ。 ただこれまで会った友人の中に「泉麻人が好き」という人に会ったことはないので、いささか世間の認知度にギモンを持ったりすることが多いのだが、いわゆる「作家」ではないので、あえて「コラムニストの泉麻人が好き」とは普通言わないのかもしれない。 そういうわけで「コラムニスト」というのはどうも「作家」の肩書きに比べるとソンな役回りのことが多いような気がするが、雑誌とか新聞で目にすることが多いのは圧倒的にコラムニストのほうが多いはず。 特に私の場合「トレンド風俗ウォッチャー」みたいな人の文章が好きなので、あえて単行本を買って読むことになる。 というわけで本書「コラムダス」なのだが、泉氏の本の中で「特にこれがオススメ」とかいうわけではなく、たまたま今読んでる最中なので、日記に書いてみた次第だ。 この本には1990年くらいの文章がまとめてあるのだが、この「1990年頃」についてちょっと書いてみたい。 1990年といえば、今年が2006年だから、普通に考えれば16年前のことになる。 ところが私の場合、1990年頃なんてほんの数年前のことのような気がするのだ。 自分が20歳前後の頃のことだったから、妙に当時の「空気のすり込み」が激しく、気分的にはその時代から進んでいないのかもしれない。 正直、とても16年前のことだなんて信じられない。「カウントダウンTV」みたいなテレビ番組で、「1991年のヒット曲ベストテンはこうでした~」なんてモノをみても「懐かしいな~」というよりも「ちょっとウキウキ」してしまう。 よく考えてみれば、どこの世代の人も、青春の熱い時代を過ごした時期を、ずうーっと引きずるものなのかもしれないとも思う。 1960年代後半に20歳くらいだった、いわゆる「団塊の世代」の人なんか、全共闘時代の空気をずーっと引きずってる可能性がある。 「30数年前のことだったなんて、とても信じられない」という風に。 「団塊の世代から人々は大人になることをやめた」と何かの本で読んだが、「歳はとっても心は青春のまま」というのはいいものか悪いものか。 となると団塊ジュニア世代の我々は一生「バブル」ちっくなモノを引きずって生きるのかもしれない。親世代とも話はあわないし、バブルの終わった時代の若者達とも話があわないわけだ。
2006.10.07
コメント(0)
-
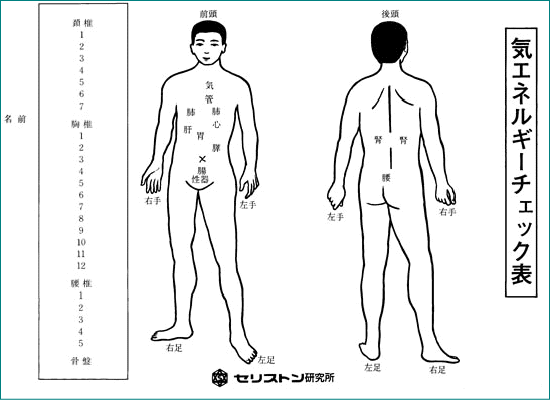
受験体質と人間ドック
↑この絵は特に意味ありません。 先日、35歳を目前にして初めて「人間ドック」というやつを体験してきた。「ドック」というからには、なんか「カラダをバラバラにされて点検される」みたいなものを想像していたのだが、なんのことはない定期健康診断に毛の生えたようなやつだった。 唯一の大きな違いといえば「内視鏡検査」要するに「胃カメラ」があることだったのだが、最新式のやつは鼻の穴から管を通すやつで、精神的なナサケなさは伴うものの、肉体的にはどうということもなく、初の人間ドックは無事に終わった。まあ「無事」かどうかは検査の結果しだいなのだが・・・。 で、後日、送られてきたのが検査結果なのだが、まあ数値的にはほぼ正常であった。ちょっと気になるのが尿酸値と中性脂肪が高めなこと。なんのことはない慢性的な運動不足なのだ。 しかしこの「結果通知」というやつ。どこかで見たことあるような気がしていたら、薄いペラペラの紙といい、印字されたコンピュータ文字といい、中学高校の頃に受けた模擬試験の結果通知とソックリなのだった。ペラペラの紙一枚で「人間の性能」が示されるというのもどうも同じ気分だ。 検診結果なんて前の日に何を食ったかとかで、けっこう変わるような気がするのだが、どうも検査の数値というのは気になる。 正常値からほんの少しオーバーしただけでも「要経過観察」なんて文字が印字されてるのが、なんかコワイ。受験の合格可能性「D判定」みたいな気分になってどうも落ち着かない。 「努力すれば結果はでる」と教え込まれた受験教育の成果なのだろうか、どうもこの「数字」が気になって、深夜にウォーキングを始めてみたり、サウナに通ったりしはじめている。次回検診の「正常値=A判定」を目指して。 どうも私達は「がんばればなんとかなるカラダの数値」に弱いようだ。
2006.09.23
コメント(0)
-
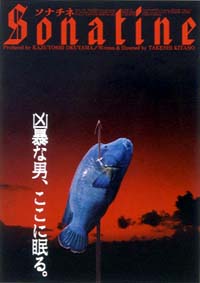
夏になると観たくなる北野武「ソナチネ」
監督 北野武 主な出演者 ビートたけし 、 国舞亜矢 、 渡辺哲 <感想>夏になると観たくなる映画がある。北野武の「ソナチネ」もその一本。ストーリーは典型的なヤクザものなのだが、たけしが撮ると一種哲学的な趣きの作品になる。抗争が膠着し、夏の沖縄の海で遊ぶヤクザ達。その合間にも実は抗争は進行しており、一人一人と死んでいく。久石譲が奏でる沖縄音楽の中、淡々と人が死ぬ。そこに涙はない。あるのは沖縄の海と空だけ。たけしの死生観というのは、数々の著書でも現されているが、映像になるとこういう風になるのだなあという気がする。たけしの映画ではたいてい登場人物が死んだりするが、「ソナチネ」は「人の死」を直球で投げてくる作品だ。この作品は1993年の劇場公開時、ガラガラの映画館に一人、足を運んで観た。当時、21歳だった私の死生観にかなり影響を与えた気がする。「沖縄の海で抗争に巻き込まれて死ぬヤクザ」というのはなかなかシュールな死だが、「そのへんの老人が地元の病院で家族に看取られて死ぬ」という死も同じ「死」だ。 同じ「死」に、そこに何の違いがあるのかないのか。 あるとしたら何が違うのか。 「死」という事実は変わらないのではないのか? そこまでの生きた経緯の問題なのか・・・?夏の熱い盛り、特に終戦記念日近くなると、毎年「死」というものを考えたりする。日本の夏は「死」を考える季節なのだ。そんな夏に観たい映画。
2006.09.10
コメント(0)
-

サッカーは好きじゃない「感動禁止! 涙を消費する人びと」
「感動」禁止! 「涙」を消費する人びと 著者/訳者名 八柏龍紀/著 出版社名 ベストセラーズ (ISBN:4-584-12102-8) 発行年月 2006年01月 価格 819円(税込) <本の内容> 「感動をありがとう!」「勇気をもらいました!」。そう言って涙を流すのが正常だといわんばかりに、屈託なく語る人びと…元々「感動」や「勇気」は与えられるものではなく、内発的に抱くものではなかったのか?だからこそ価値があったのではないか?一体、いつから「涙」は軽くなり、「感動」はお安いものになってしまったのだろうか?内実なき熱狂を買い求めるカラッポ人間が、なぜ多数派を占めるようになってしまったのか。「消費」をキーワードにニッポン社会の変遷から解き明かし、いまどきニッポンを社会哲学で鋭く考察する。<感想> 時おりしもワールドカップ直前の盛り上がり最盛期である。これを書いている今日は6月11日。明日は初戦の日本対オーストラリア戦があるらしい。テレビをはじめメディアはサッカーサッカーで大騒ぎの毎日だ。 今の時期、こういうことを言うのは実に心苦しいのだが、私は「サッカーにはまるで興味が無い人間」だ。 しかし、世間の「ワールドカップファシズム」とも言うべき空気の中で、人前で「いやー私はサッカーには興味ないんで」とはなかなか言いがたいものがあるのが実情である。 そういえばオリンピックのときも野球のWBC優勝のときもそんな感じだった。「いやー興味ないんで」とは言えない雰囲気。これは一体何なんだろう? 本書「感動禁止! 涙を消費する人びと」の帯には「オリンピック・小泉劇場・韓流・セカチュー、簡単に熱狂するカラッポ人間は、なぜ生まれたのか? 」の文字が踊る。なかなか挑発的な文句で気持ち良い。こういうブームを真っ向から非難するのはなかなか勇気がいったことだろう。 この本を購入した理由はそのへんの心意気にもある。 しかし、この本はどうも「初めにタイトルありき」の本だったようで、内容としては70年代~現在に至る日本人の文化風俗論みたいな本になっている。 そしてタイトルを「感動禁止!」として、最近の安易な熱狂ブームを批判する作りに仕上げたように見える。なので、なんで「感動禁止!」とまで言わなければならないのかというポイントがいささか弱い。 作者の言いたかったことを色々盛り込んで商品化するには仕方なかったんだろう。 文化風俗史としてはかなり面白いのだが。 で、なんで「いやー興味ないんで」と言えない社会になったかというと、高度に発達した消費社会が「感情」の分野にまで浸透し、そもそも消費社会が併せ持つ空虚さとあいまって「感情」すら消費の対象になってしまったから、ということらしい。 「感動」だけではない「憎悪」や「悪意」も商品化され、メディアの店頭に並ぶ時代なのだ。 今やニュースもワイドショーも中身は全部同じだ。どの局も同じニュースを扱い、同じ論調に仕上げる。スポーツは徹底的に盛り上げる。不祥事を起こした企業や官庁は徹底的に叩く。殺人事件は徹底的に悲しみ、推理ミステリーのごとく徹底的にあばく。そして時期を過ぎれば全部忘れる。その繰り返し。 そういうテレビの前に毎日毎日いたら、洗脳されるのは当然だ。(若者ばかりの話ではない。テレビの前に相当長時間いるであろう老人の方が深刻だ) そんな中で「自分達は情報を「消費」してるんだなー」と言う意識は持っていたいと思う。「感動するな」とは言わないけど、「自分が感動してるのかどうか」「何を憎んでるのかどうか」くらいは自分でわかってたい。と思う。 いや、サッカーで盛り上がってる人達に水をさそうっていうわけじゃないんで・・・。興味のない人もそっとしておいてほしいというか。
2006.06.11
コメント(1)
-

タイトルで売った「千円札は拾うな」
千円札は拾うな。 著者/訳者名 安田佳生/著 出版社名 サンマーク出版 (ISBN:4-7631-9680-4) 発行年月 2006年01月 価格 1,260円(税込) <本の内容> 残業をやめれば、給料は増える。見えてる人には見えている、常識の「半歩先」の考え方。『採用の超プロが教えるできる人できない人』から3年、読者待望の「安田式・人生を劇的に変えるビジネスバイブル」。<感想> 社会人になってすぐの頃、いわゆる「自己啓発系」の本にハマった時期があった。カーネギーだの松下幸之助だの中谷彰宏だの、その他いろいろ。 一通りそういう本を読むとだんだん書いてあることが同じに思えてくる。実際、そういう作者も誰かの影響を受けたりして本を書いてるわけで、同じような本が世にあふれるのは当然とも言える。 で、本書「千円札は拾うな」だが、読んで正直な感想は「あ~こういうコト誰かも言ってたな~」という感じだった。 本書の要点は「短期的に物事を見るな」「捨てるべきものは早く捨てて、いつも新しいものをみつけろ」「変化を恐れるな、自ら変化しろ」というあたりだ。 当然、これらのことは重要な点ではあるのだが、こんなことはすでに誰かが、どこかの本で書いていることなのだ。 そういう意味でこの本は個人的にはイマイチだった。 ただ、「自己啓発系」初心者にはかなりオススメの本であることは確かだ。 すごく読みやすく書いてあり1~2時間程度で読めてしまう。 自己啓発の要点をわかりやすく読めるってのがベストセラーになった秘訣か?比較的、凡庸な内容の本だが、特筆すべきはそのタイトルのインパクトである。「千円札は拾うな」このタイトルのセンスはすばらしい。これが「あなたにもできる自己変化術」なんてタイトルだったら、誰も買わなかったに違いない。 まあ、自己啓発の要点はいつも心に「自己啓発のマインド」を持ち続けることである。こういう本を本棚に置いてたまにパラパラとめくるのもいいのかもしれない。
2006.06.09
コメント(0)
-

80年代コンプレックス「若者殺しの時代」
若者殺しの時代 講談社現代新書 1837 著者/訳者名 堀井憲一郎/著 出版社名 講談社 (ISBN:4-06-149837-1) 発行年月 2006年04月 価格 735円(税込) <本の内容> クリスマスが恋人たちのものになったのは1983年からだ。そしてそれは同時に、若者から金をまきあげようと、日本の社会が動きだす時期でもある。「若者」というカテゴリーを社会が認め、そこに資本を投じ、その資本を回収するために「若者はこうすべきだ」という情報を流し、若い人の行動を誘導しはじめる時期なのである。若い人たちにとって、大きな曲がり角が1983年にあった―80年代に謎あり!ずんずん調べてつきとめた。<感想> 1980年代には愛憎入り混じった不思議な感情がある。 私は1972年生まれのいわゆる「団塊ジュニア世代」。80年代は8歳~18歳として過ごしたことになる。ちょうど物心ついたときには80年代であり、それは高校卒業までの10年間だったわけだ。 80年代の「大消費時代」の風をビンビンに感じながら成長したものの、自分である程度のカネを稼げるようになって、いよいよ消費の客体となった頃には「昭和と共に時代は終わっていた」そんな感じだ。 そして私の大学時代は1991年の「東京ラブストーリー」と共に始まる。90年代のフワフワした感じもそれなりに楽しかったが、どうしても「時代に乗り遅れた」感じがして仕方なかった。 80年代のギラギラした空気を感じながら、深く吸い込めなかったところに、コンプレックスの根っこがあるような気がする。 最近、80年代論を扱った本をちらほら見かけるようになったが、本屋で思わず手が延びてしまうのは、あのとき吸い込めなかった熱い風が忘れられないからなのかもしれない。 この本、「若者殺しの時代」はタイトルが堅苦しいが、80~90年代を通して変わってしまった文化風俗の検証みたいな本である。「クリスマスはいつから、どのようにして恋人達のものになったか?」とか「トレンディードラマにおける携帯電話の扱われ方の変遷」とか、「いつから大晦日のディズニーランドは殺人的混雑になったか?」とか言ってみればとるに足らない事柄の分析なのだが、その向こう側に見えるのは「若者」がいかに資本主義社会に巻き込まれていくかの過程である。 要するに「イマの若者」を生きるには「カネが必要になった」ということだ。 私の20代もそうだった。カネも使ったし、充分社会に踊らされた。でもそれはそれで、まあ良かったし楽しかった。80年代の遺恨は晴らしたような気がする。 30代になって妻子持ちになると、ある意味老成してくる。消費も等身大になり、過剰ではなくなった。とりあえず「若者殺しの時代」からは抜けつつあるのかなという気はする。 でもオーバーな言い方をすれば、私の人格形成に大きな影響を与えたのは「軽薄短小」の80年代だったと思う。 私と同年代の「15の夜」は土曜の「ひょうきん族」のエンディングでEPOやユーミンを聞いた夜だった。 あの頃の「これから楽しくなっていく時代」の空気はやはり思い出深いものがある。
2006.05.16
コメント(2)
-

「電車男」と「HERO’S」
私の格闘技系のプチ自慢は「PRIDE」の第1回大会を生で見ていることだったりする。もう10年も昔の話だ。 当時、「PRIDE」は高田延彦とヒクソン・グレイシーの試合を提供するためのただ1回限りの大会だったはずなのに、あれよあれよという間に日本を代表する格闘技イベントになってしまった。 「HERO’S」あたりを見てると、中量級の総合格闘技がゴールデンで放映されてるのがいまだに信じられない。昔は後楽園ホールあたりで細々とやってたのになー。シューティングとか。あんなマイナーな競技がここまで発展するとはなかなか感慨深いものがある。 しかし、最近の選手はずいぶんとカッコよくなったもんだと思う。試合はともかく、その言動やファッションがセンスいいもんな。 スーパーバイザー前田あたりは今の選手の注目のされ方に嫉妬してるかも。リングスはちょっと早すぎたな。 ともかく、今の格闘技興行は、「今の技はどう」とか「マウントポジション」「ガードポジション」なんて格闘技マニアの視点で論ずるものじゃなくなってきたような気がする。 こうローマ帝国のコロッセオみたいに「男同士が戦うのを観る」感じ。そういう意味ではもうプライドでもK-1でもHERO’Sでもなんでもいいのかも。若い女性なんかが多い客層を観てると、観て興奮できればそれでいいんだろうなーと思う。 単に「強靭な男達が見たい」というのは別に悪いわけじゃなくて、たぶん人間の(特に女性の)本能に訴えるところがあるのだろう。 「バカの壁」じゃないけど、肥大しすぎた脳世界に対抗するように、「頑丈なカラダを見たい」という欲求が出るのはのはわかる気がする。 アキバ系メイドカフェなんてのが流行りだけど、そういう一種の脳の不健全さとは対極にあるんだな。 肉体派の男はやっぱカッコいいわけで、「電車男でオタクもOK」なんて思ってるとやっぱり足をすくわれるのだ。
2006.05.10
コメント(0)
-

「プチオヤジ道」と泉麻人
おじさまの法則 光文社文庫 著者/訳者名 泉麻人/著 出版社名 光文社 (ISBN:4-334-73967-9) 発行年月 2005年11月 <本の内容> 巷のファッションやトレンドを独特の視点で掬いあげてきた著者が、身近に観察するいまどきのおじさまの生態とは?病気じまん、少年がえり、サッカー通きどり…などなど。そんな症状に思いあたるあなたは、もう立派な“おじさま”。「BRIO」誌上で大好評を博した連載エッセイをオリジナル文庫化。おじさまもおじさま予備軍もおじさまを知りたい女性もみんな必読。<感想> この4月に転勤になり、バタバタとしてる間にもうゴールデンウィークになってしまった・・・。今回の私の異動はいわゆる「本店→支店」的な異動だったため、仕事的にはより現場に近いポストに着くことになった。 それはそれでいいのだが、現場に近い職場は若い社員が多い。これまで30代半ばにして一番下っ端だった私も晴れて(?)中間管理職的な状況におちいるハメになった。 自分では「まだまだ若い」と思っていても10歳もトシの違う若者と飲んだりすると、どうしても「俺もオヤジかな」とか自覚せざるをえない。(先日、「原田知世を知らない」という世代に出会って愕然としたりする」) そう、客観的に見れば34歳というトシはもうすっかり「プチオヤジ」の領域なのだ。いつまでも若者ぶってもいられない。そろそろ自分なりの「プチオヤジ道」を開拓しなければならない時期にきたのだ。 最近、本屋の雑誌コーナーなどに行くと、やたらと「新興・男性系大人の雑誌」が目に付くようになった。と言ってもエッチ系の話ではなくて、「サライ」「日経おとなのOFF」「男の隠れ家」「BRIO」「LEON」などなどの趣味系の雑誌。「いまどきのオジサン道」にもいろいろあるようで、志向の違いが出てて面白い。 この、泉麻人の「おじさまの法則」は高級コンサバ志向雑誌「BRIO」に連載されたコラムの文庫版。でも「BRIO」らしからぬ大衆さがいい味を出してるんだな。 もともと泉麻人は東京出身で慶応高校→慶応大学という学歴のトレンドバリバリの人なんだろうけど、趣味が地図観賞とか路線バスとか昆虫採集とか地味系なのが面白い。以前からその手のコラムは書いていたけど、「オジサン化」するにつれて、そういう地味系の趣味のことをイキイキと語るようになった気がする。 「オジサン化」とは「自分の趣味に堂々とひたれる現象」なのかもしれないとも思う。若者が同じことをやれば、周囲から「趣味が悪い」だの「いい若いモンが何やってる」だの「オタク」だの言われることでもオジサンになればオールOK。 金のブレスレッドで「ガハハ」と笑う浅黒のゴルフ焼けオヤジも神田の古本屋と喫茶店巡りが好きな色白オジサンも誰にも文句は言われない。それは世間の意見に耳を貸さなくてよくなる楽ちん状態。 若者というのは、就職とか恋愛とか結婚とかを目前に控えて、ある程度社会に迎合しなくてはならない存在だけど、そういうものをすでにクリアしたオジサンはもう「自分全開」。何にも迎合する必要はない。 最近、LEON系「ちょいワルオヤジ」なるものが流行ってるらしいけど、いいトシして今さら若い女に媚び売ってどうするっちゅーんだ。 マニュアル雑誌の真似をした「ちょいワルオヤジ」よりも、ガハハと笑う「自分全開系オヤジ」の方が魅力的だと思うんだがなー。「みのもんた」みたいな。 っていう発想がすでにオレも「オジサン」なんだな。たぶん。
2006.05.06
コメント(0)
-

有栖川有栖「月光ゲーム」
月光ゲーム 創元推理文庫 著者/訳者名 有栖川有栖/著 出版社名 東京創元社 (ISBN:4-488-41401-X) 発行年月 1994年07月 <本の内容> 夏合宿のために矢吹山のキャンプ場へやってきた英都大学推理小説研究会の面々を、予想だにしない事態が待ち構えていた。山が噴火し、偶然一緒になった三グループの学生たちは、陸の孤島と化したキャンプ場に閉じ込められてしまったのだ。その極限状況の中、まるで月の魔力に誘われたように出没する殺人鬼! 有栖川有栖のデビュー長編。<感想> 有栖川有栖を初めて読んだのがこの本。 キャンプ中に起きる噴火の中起きる殺人事件。いわゆる「クローズドサークル(「吹雪の山荘」「嵐の孤島」みたいな)もの」。 クローズドサークルものには、変な社会性や現実性は必要無い。そこに謎解きがあればそれでよい。 その意味でこの「月光ゲーム」は「軽いミステリ」に仕上がっている。(「軽い」というのはもちろん悪いという意味ではなくて、ミステリとしての純度が高いということ) 登場人物が全員大学生で、夏合宿に行った先で他大学のサークルと出会い、男女が出会い、そして事件は起きる・・・。 正直、話が全て「若い」。登場人物も若ければ、犯行も若い、動機も若い。30代半ばの自分が読んでてこっちが恥ずかしくなるような話の流れでもある。 そういえばこの作品は有栖川のデビュー長編でもあった。青春小説的な、この青臭さがこの作者の魅力でもある。 重厚なミステリや社会派のミステリは山ほどある。しかし青春派ミステリというのはあんまりないんじゃないだろうか(よく知らないけど) この「月光ゲーム」の読後感は軽く、決して重いものではないが、何年後かしてこの本のことを思い出したとき、まるで自分の青春時代を思い出すような気分になるような気がする。 そんな小説。
2006.03.18
コメント(0)
-

貫井徳郎「慟哭」
慟哭 創元推理文庫 著者/訳者名 貫井徳郎/著 出版社名 東京創元社 (ISBN:4-488-42501-1) 発行年月 1999年03月 <本の内容>連続する幼女誘拐事件の捜査は行きづまり、捜査一課長は世論と警察内部の批判をうけて懊悩する。異例の昇進をした若手キャリアの課長をめぐり、警察内に不協和音が漂う一方、マスコミは彼の私生活に関心をよせる。こうした緊張下で事態は新しい方向へ!幼女殺人や怪しげな宗教の生態、現代の家族を題材に、人間の内奥の痛切な叫びを、鮮やかな構成と筆力で描破した本格長編。<感想>「一部ネタバレ含む」 貫井徳郎衝撃のデビュー作にして、30版を越えたベストセラー。鮎川哲也賞で受賞は逃すものの、その後ファンの間で話題となりじわじわ広まったという傑作。 北村薫が帯に寄せた言葉は「題は「慟哭」、書き振りは「練達」、読み終えてみれば「仰天」」だった。 この作品は文句無しに面白いのだが、メイントリックがいわゆる「叙述トリック」のため、人によっては「こんなのミステリじゃない」という意見もあるという。 正直私も、クリスティの「アクロイド殺し」以来「叙述トリック」というやつがあんまり好きではない。 作品によっては叙述トリックに凝りすぎるあまり、話がややこしくなったり、作者の独り善がりになったりするケースもあるからだ。「フェアかアンファアか」と言われればアンファアだと思う。ただこれはその人の好みの問題なので、ここでとやかく言うものではないのだが。 しかしこの「慟哭」の場合、叙述トリックがシンプルなため、その切れ味はかなり鋭い。 こういう作品を読みなれた人には通用しないかもしれないが、ミステリ初心者はバッサリ斬られること間違いなしだ。 事件が幼児殺人とリアルでヘヴィなのと驚愕の結末で、読後もなかなか忘れがたい作品。
2006.03.04
コメント(0)
-
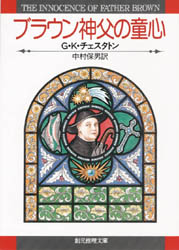
チェスタトン「ブラウン神父の童心」
ブラウン神父の童心 創元推理文庫著者/訳者名 : G・K・チェスタトン/著 中村保男/訳 出版社名 : 東京創元社 (ISBN:4-488-11001-0) 発行年月 : 1992年00月 価格 : 693円(税込)<本の内容> 奇想天外なトリック、痛烈な諷刺とユーモア、独特の逆説と警句、全五冊におよぶ色彩ゆたかなブラウン神父譚は、シャーロック・ホームズものと双璧をなす短編推理小説の宝庫で、作者チェスタトンのトリック創案率は古今随一だ。まんまるい顔、不格好で小柄なからだ、大きな黒い帽子とこうもり傘の神父探偵の推理は常に読者の意表をつく。 <感想> ミステリ初心者にとって至福なのは、これから読むべきミステリの名作が山ほどあることだ。 というわけで「古典」ブラウン神父シリーズをようやく読んでみた。(「30越してからブラウン神父」というのもいささか恥ずかしいが)。 話の構成や展開はさすがに豊富で面白い。短編のお手本のようなシリーズ。「童心」では、「奇妙な足音」「見えない男」が秀逸。 ただ翻訳がどうも古くさく、読みづらいことこのうえない。個人的に翻訳ものが苦手なので「そういうのは自分だけなのかな~?」とも思うけど。 考えてみれば、高校生の頃に、「これは面白い」と言われてクリスティの「アクロイド殺し」を読んで以来、翻訳ものというのは読んでいなかったのだ。エラリークイーンも途中で挫折・・・(確か「ローマ帽子の謎」だったか) 自分の「読み」が足りないのか、翻訳者が悪いのか。名作ミステリは手塚治虫あたりが漫画化しててくれるとありがたかったのだが・・・。 この「翻訳」という作業は一度なされたら、何度もやったりするものではないんだろうか? 願望としては20年に一度くらいは「再翻訳」してほしいもんだが。日本語も変わるし。 少なくとももう少し読みやすいシロモノにはなると思うんだがな~。
2006.02.24
コメント(0)
-
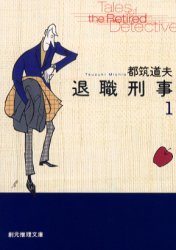
都筑道夫「退職刑事 1」
退職刑事 1 創元推理文庫著者/訳者名 : 都筑道夫/著 出版社名 : 東京創元社 (ISBN:4-488-43402-9) 発行年月 : 2002年09月 価格 : 630円(税込) <本の内容> かつては硬骨の刑事、今や恍惚の境に入りかけた父親に、現職刑事の息子が捜査中の事件を語ると、父親はたちまち真相を引き出す。国産《安楽椅子探偵小説》定番中の定番として揺るぎない地位を占める、名シリーズ第一集。収録作品 写真うつりのよい女/妻妾同居/狂い小町/ジャケット背広スーツ/昨日の敵/理想的犯人像/壜づめの密室<感想> たまたま見かけたブログに「一番好きな作家は都筑道夫」というフレーズがあって読んでみた作品。 恥ずかしながら都筑道夫という作家を全く知らずにいたのだが、「こんな作家もいたのか」という感想を持った。 「安楽椅子探偵」(アームチェア・ディテクティブ、Armchair-Detectiveとは、ミステリの分野で用いられる呼称で、もともとは安楽椅子に腰をおろしたままで、人から事件に関する話を聞き、それに基づいた推理で事件の謎を解く探偵のことをいう)というジャンルはなかなか興味をそそるものがあり、国産でもこういう作品があったのか~と再発見。 退職した刑事の父と現職刑事の息子の会話のみで繰り広げられるストーリー。不可解な事件を、いろんな角度から推理する老父の発想が面白い。 事件はリアルな犯罪さながらの下世話なネタが多いのだが、「父と息子の会話」で話が展開するため、読後感は上品な感じに仕上がる。(ただ、事件がホントに下世話なので、「こんな会話をする親子がホントにいるのか?」という違うギモンもあるが。まあだから「刑事」という設定なんだろうが) 「安楽椅子探偵」の面白さはロジックのみで話が展開し、解決するというところにあるのだが、ややもすれば作者の独りよがり的な展開になることもあり、難しいところではある。 「おいおい、人の話だけでそこまでわかるか?普通」みたいな。 ただこういう作品を連発するのは相当難しいであろうことはわかる。こういう作品は小説雑誌かなにかで、月イチくらいで読むのが良いのかもしれない。 文庫でまとめてガーッと読むにはややもったいない本。 文庫カバーイラストがポップでシャレた仕上がりになっているのも○。
2006.02.23
コメント(1)
-

松本清張「ゼロの焦点」
ゼロの焦点 新潮文庫著者/訳者名 : 松本清張/著 出版社名 : 新潮社 (ISBN:4-10-110916-8) 発行年月 : 1988年01月 価格 : 620円(税込)<本の内容> 新婚一週間で失踪した夫の行方を求めて、北陸の灰色の空の下を尋ね歩く禎子がまき込まれた連続殺人! 『点と線』と並ぶ代表作品。 <感想> 中高校生の頃の話だが「社会派推理小説」というものに憧れた時代があった。ちょうどパソコン(当時はマイコンともいったが)ゲームの「アドベンチャーゲーム」というものが隆盛を極めた頃だった。後に「ドラゴンクエスト」で一世を風靡する堀井雄二が作った三部作「軽井沢誘拐案内」「ポートピア連続殺人事件」「オホーツクに消ゆ」は「社会派」という意味で、ちょっと背伸びしたい年頃の男子に大ヒットしたものだ。同じ感じで「軽い社会派」の赤川次郎なんかもよく読んだ気がする。 「社会派推理小説の重鎮」松本清張という名前はもちろん昔から知っていたが、恥ずかしながら読んでみたのは最近の話で、「砂の器」に続いて読んでみたのが本作品。 「旅情」「サスペンス」「もつれる人間関係」と今で言う2時間ドラマの要素がてんこもりなのだが、その原型となったのが本作「ゼロの焦点」だという。 読んでみてなるほど「これは原型である」と思った。証拠品である2枚の写真を片手に、北陸金沢をさまよう新妻。次々と明らかになる事実。登場人物の思わぬ殺人。謎が謎を呼ぶ展開。そして犯罪の背景にあった社会的事件とは・・・。 2時間ドラマの原型であることもさながら、昔ハマったアドベンチャーゲームの原型がここにあったのだ。証拠品を関係者に見せながら証言をとり、行ける場所が徐々に増え、思わぬ人が意外なことを言い出したりする展開。 宮部みゆきの「火車」を読んだときも「こりゃー昔のアドベンチャーゲームみたいだなー」なんて思ったけど、さらに原型は松本清張なのであった。 それにしてもこの「ゼロの焦点」は面白い。最後までぐいぐい読者を引っ張る語り口のうまさは絶妙だ。松本清張とか横溝正史とか、終戦直後ころの時代を描いた、いわゆる「ミステリの古典」と呼ばれるものが、意外と読みやすいのはやはり名作ということなのか。 「ゼロ~」の舞台となる昭和30年代は確かに遠い時代となってしまったのだが、細かな描写や言葉づかい、出てくる小道具などに「古き良き日本」を感じさせ、独特の良い味を出していると思う。 新幹線も携帯電話もパソコンもなかった時代だが、そこに生きた人達は現代よりももっと品があったのではないかという気がする。 少なくとも「ゼロの焦点」を読むかぎりそんな気がしてくるのだ。
2006.02.12
コメント(2)
-

島田荘司「斜め屋敷の犯罪」
斜め屋敷の犯罪 講談社文庫著者/訳者名 : 島田荘司/〔著〕 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-185189-6) 発行年月 : 1992年07月 <感想> 正月に「古畑任三郎」を見たからというわけではないのだが、今ミステリーがマイブームとなっている。特に「本格物」というジャンルが読みたくなって読んだのがこの本。「占星術殺人事件」と並び表される島田荘司の初期代表作とあって、前評判はなかなかだったのだが、読んでみて「驚愕」の一言だった・・・。 推理小説は皆トリックのための物語であるというのは確かにそうなんだろうが、ここまで大胆に、ダイナミックにトリックのためのストーリーを考えた作者はスゴイ。 なんというか読者を「ズバッ」と一刀両断するようなトリックなんだな。「うわ~やられた!」という感じ。「リアリティがない」という批判もあるようだが、このトリックの前にはリアリティなんて必要ない。多少、社会的背景のある動機すら無くてもいいくらいだ。 ミステリ好きにはもちろん、「あっ」と驚きたい人向けの一冊。 蛇足だが、この「斜め屋敷」の主は「ハマーディーゼル」という農機具会社の社長である。この「農機具会社」が絶対謎解きに関係あると思ってたら全然関係ないのであった・・・。 なぜ作者は「農機具会社」にした?謎だ。(笑)
2006.02.08
コメント(3)
-

さよなら「古畑任三郎」
<感想>いやー、古畑任三郎良かったなー。シナリオとかゲストうんぬんの前に、古畑が画面に登場するのが嬉しい。独特の演技は思わず真似しちゃったりして。「んふふふ・・・」とか(笑)正直、シナリオ的には過剰な期待はしていなかったが、そこそこ面白かった。2ちゃんねるなんかを見ると、「本格ミステリにはほど遠い」だの「どこかのミステリのパクリだ」なんて意見があったが、三谷幸喜に2時間ものを3本書かせて、そんなに斬新なトリックを期待するほうが間違いだろう。推理作家じゃないんだからさ。むしろ古典的トリックでもいいから、ミステリ初心者にもわかりやすいように、ドラマ流にアレンジできてればそれでOKだと思う。イチローの回は、イチローがどんな演技をするのかこっちがドキドキしたけど、けっこう普通だったな。でもスポーツ選手はやっぱりドラマには出てほしくないような気がするな。やっぱ。(イチローは古畑任三郎の大ファンとのこと。自称「日本で一番、古畑ドラマを見ている男」らしい。すげー意外)やっぱり松嶋菜々子の最終回が一番良かったかな。古畑らしいスマートさが一番良くでてた。最終回だからってそんなに大舞台じゃないのも良かった気がする。まだまだ続編を期待したいところだが、田村正和もさすがにトシなので(なんと62歳!)さすがにそろそろ無理かな~。今回のドラマも「ちょっと老けたなー」という場面もあったし。ここはやはりさくっと最終回にして、「あとはDVDで楽しんで」ってのが正解かも。最後に今回どーしても腑に落ちない点・・・「今、甦る死」:ちと偶然が重なりすぎ?「フェアな殺人者」:イチローが飲ませた二つのカプセルはほんとに確率1/2だったの?「ラストダンス」:20分のところを10分でどーやってできた?(管理人の点とか)面白かったから、まーいいか。
2006.01.11
コメント(0)
-
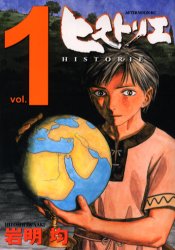
傑作の香り「ヒストリエ」
ヒストリエ 1 アフタヌーンKC著者/訳者名 : 岩明 均 著 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-314358-9) 発行年月 : 2004年10月 価格 : 560円(税込) <内容>「寄生獣」「七夕の国」の岩明均の最新作。紀元前のオリエントを舞台に、アレクサンダー大王の書記官・エウメネスの生涯を描く。<感想> 新年1発目なので壮大なテーマのこの一作。 「アレキサンダー大王の書記官エウメネスの波乱に満ちた生涯を描く」という本作は3巻目にしてすでに傑作の香りがしてきます。 「世界史」というのは日本ではなかなかマイナーなジャンルで、「アレキサンダー大王」とかいっても、普通の人には(゜Д゜) ハア??という感じは否めません。 正直こんなテーマで漫画を描く作者も、GOサインを出した出版社もよく決断したな~と思います。 しかし、最初のとっつきづらさはあるものの、一旦その世界に入り込めれば話は流れるように進みます。この作者特有の「セリフの間」が良い味を出してます。 「歴史」という史実を描く作業の中で、まるで「寄生獣」のようなSFチックなものを感じてしまうのはどうしてなんでしょうか。 人の歴史、異民族との出会い、戦争。 今でこそ安定したかに見える「世界」の歴史には、多くの出会い、謎と発見、繁栄と崩壊があったのでしょう。まさにSF。 現代人とはいっても、その本質は紀元前の世界からそんなに変わっていないような気もします。そんな人の歴史は面白くないはずはないんです。なんていっても実話ですし。 受験でさんざんやった歴史は面白くなかったし、実際さっぱり覚えていません。それは、そこに「人の生々しさ」がなかったのが理由ではないかと思います。歴史は記号ではなく「そこに人がいた事実」そのものと言えます。同じ歴史を扱っていながら、人の歴史の長さ、偉大さ、愚かさを伝えられない受験の歴史は致命的とも言えます。 「ヒストリエ」はぜひその重厚さを保ちながら連載を続けていってほしいものです。 「読みやすさ」「わかりやすさ」よりも作者の思うままに描かせてやりたい。 エウメネスの歴史を描き切って欲しい。 アフタヌーンにならその度胸がありそうで頼もしい限りです。
2006.01.02
コメント(2)
-
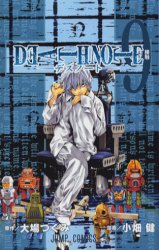
そろそろキツいぞ「デスノート9巻」
DEATH NOTE 9 ジャンプコミックス著者/訳者名 : 小畑 健 画 大場 つぐみ 原作 出版社名 : 集英社 (ISBN:4-08-873887-X) 発行年月 : 2005年12月 価格 : 410円(税込) <本の内容> メロの手に渡ってしまったデスノート・・・。メロはその頭脳・推理力と、死神・シドウの言動から、ノートにかかれたルールの真意に近づいていく!!メロとの対決のために夜神次長はついにリュークと目の取引を・・・。父の死の覚悟により、ノートを取り返せるのか!?じわじわと月に迫ってくるニアと、突然切り込んでくるメロ。Lの二人の後継者を相手に、月はどう出る!?第2部も緊迫の展開です!!<感想> うーむ「デスノート」、読むのがけっこうキツくなってきたぞ。 正直な話、事実関係を本当に吟味して読んでる読者なんているのか?って感じになってきた。(いたら申し訳ないけど) 今さらだけど「犯人がだれか?」なんて話じゃないしなー。 月(ライト)が断念しないでどこまでやるか?って話になってきた。 原作者付きの漫画だけど、本当にラストまで話考えてるのかナー? 米国政府まで巻き込んじゃう展開は話広げすぎだろ。いくらなんでも。 「ドラゴンボール」みたいな話だったら「ある程度の敵を倒して終わり」ってできるけど、 この「デスノート」みたいな展開じゃそれもできないし。 ロジックと弁論の話なんだから、ある程度整合性のあるラストにならないと読者が怒るぞ。(でもジャンプはけっこう平気でそういうコトするからな~) 今ごろ原作者は痛む胃をかかえて必死だったりして・・・。 なんかこのブログは「漫画の適切な終焉を願う日記」みたいになってきた(笑) でも、好きな漫画には「適切に」終わってほしいんだよな。 何事ももほどほどが肝心なのだ・・・と自分にも言い聞かせてみる。
2005.12.25
コメント(2)
-

佐々木倫子&綾辻行人コラボ「月館の殺人」
月館の殺人 上 IKKI COMIX著者/訳者名 : 佐々木 倫子 画 綾辻 行人 原作 出版社名 : 小学館 (ISBN:4-09-188581-0) 発行年月 : 2005年08月 価格 : 1,050円(税込) <本の内容> まだ見ぬ祖父に会うため、生まれて初めて鉄道に乗車する沖縄の女子高生・雁ヶ谷空海。雪の北海道を行く特別急行〈幻夜〉で、彼女を待ち受ける運命とは…?未曾有のタッグで贈る、至極の鉄道ミステリ。<感想> 12月25日。 クリスマスの夜、北海道の原野を走る蒸気機関車「幻夜」の中で第1の殺人は起きた・・・。 「Heaven?」「おたんこナース」の佐々木倫子と「十角館の殺人」「水車館の殺人」等「館シリーズ」の綾辻行人のコラボ作品。 「月刊IKKI」という雑誌に連載中らしいです。コミックスは今のところ上巻のみ。(しかし、最近やたら漫画雑誌が多いような気がするけど、やっぱ買う人が多いんだろうな) 正直「こういうコラボはいかがなものか?」と思いましたが、 佐々木倫子の繊細なタッチと、綾辻の舞台装置作りが上品な感じのミステリに仕上がってます。やや「テツちゃん(鉄道オタク)」に迎合してるような感はありますがギリギリセーフ。 ただ心配なのが「ミステリとしての結末」。 佐々木倫子のキャラで「のほほん」と展開していって、どこでシリアスに転じるか? なんか「劇中劇でした」みたいなオチになりそうでイヤなんだよな~。 こう「どこまでこの作品を信じていっていいの?」みたいな感覚。「ミステリとしてはどこまで本格を期待していいの?」「どこまで佐々木漫画として読んでいいの?」みたいな心配(笑)をしながらハラハラ読むのはけっこう疲れます。 上巻のラストもかなり「これってミステリ上のフェアなの?」ってのがあるんだよな~。「漫画でやるミステリ」としてどこまで考えてるのか?佐々木漫画ってことは考慮にいれているのか?冗長にならない程度にまとめられるのか? たのむ綾辻!ちゃんと考えていてくれ!もし「上中下の3巻セット」なんてことになったら3000円かかるんだからさ!(↓こんな雑誌あったのね)
2005.12.23
コメント(0)
-

クリスマスに「完全自殺マニュアル」
完全自殺マニュアル 著者/訳者名 : 鶴見済/著 出版社名 : 太田出版 (ISBN:4-87233-126-5) 発行年月 : 1993年07月 価格 : 1,223円(税込)<感想> クリスマスを前に「自殺マニュアル」もどうかとおもうんだけど、今日の一冊はこれ。 「完全自殺マニュアル」が出版されて早10年。有害図書指定などで、一時は散々騒がれた本だが結局は100万部売ったという大ベストセラーになった。 この本は実は友人からプレゼントされた本だったりする(この本をプレゼントというのもなかなかシュールな話だが(笑))。プレゼントされなければ、この名著には出会えなかっただろうと思うと、その友人には感謝している。 マスコミでは散々こきおろされた本だが、その内容は実に「救い」に満ちていると思う。淡々と自殺の手段が書かれているだけの内容なのだが、読んでいると「ああ、やっぱり生きていたいな」としみじみ思う。 誰しも「あーもう死んでしまいたい」と思う瞬間があったりするわけで、潜在的な自殺願望というのはみんな持ってるんと思うんだけど、この本はその代替作用があると思うのだ。 「あーもうヤダ」と思った夜には、この本を読んで酒でも飲んで寝れば、なんとなく「自殺したような」気になれたりする。 「自殺」というコトバに異常に反感を示す人がいるけど、「リセット」とでもいえばいいのかもしれない。 テレビゲームみたいに、みんな「リセット」したくなる夜があるんだ。たぶん。その極論が「自殺」というわけ。 この本の魅力は淡々とした描写の中にある自殺のリアリティで、気持ち悪いのでここには書かないけど、自殺した後、どういう状態になるかがけっこう克明に描かれてたりするわけだ。「やっぱ、こうはなりたくないよナ~ とりあえずカップラーメンでも食ってテレビでも見て寝るか」という健全さに戻してくれる。 不健全なものを隠すより、オモテに出した方がよりその不健全さがよりわかるという好例。 馬鹿なマスコミに惑わされずに版を重ねていってほしい。「自殺の仕方」なんてほんとは子供だってわかってるんだからさ。
2005.12.23
コメント(3)
-
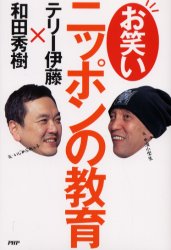
テリー伊藤・和田秀樹「お笑いニッポンの教育 」
お笑いニッポンの教育 著者/訳者名 : テリー伊藤/著 和田秀樹/著 出版社名 : PHP研究所 (ISBN:4-569-63561-X) 発行年月 : 2004年08月 価格 : 1,470円(税込) <本の内容> いまの子どもたちに何を教えたらいいのかわからない大人たちへ贈る元・中流小学生と元・いじめられっ子の本音激アツ人生論。<目次> 第1章 日本の子どもはほんとうに「バカ」になっているの?第2章 なぜ日本の子どもは無気力になったの?第3章 いまこそ学校で「お金儲け」を教えよう!第4章 学校は「本妻」で塾は「愛人」と心得よ!第5章 テリー理事長+和田学長で学校をつくろう!第6章 子どもの価値観は変わって当たり前なんだよ!第7章 「人生いろいろ」を教えよう!第8章 迷える教育の現場に直言!第9章 ほんとうの意味で「笑える」教育をつくろうよ!<感想> この本はテリー伊藤と和田秀樹の教育談義みたいな本ですが、話しの内容が良くも悪くも、そこらへんの居酒屋で話してるオッサンの会話みたいで面白いです。 一応、教育問題の基本用語などの脚注も豊富なので、今の教育問題の基本は押さえられます。 「公教育で何を教えるべきか?」というのは一見明白なようで、実は難しい問題です。 「読み書きそろばん」だけでいいのか。マナーやしつけはどこまでやるのか。子供の個性というものをどこまで考えるか。塾との相違はどこにあるのか。 「公教育とはなにか?」って問題は実はみんなそれぞれ捉え方が違うんだと思います。この本の中で、テリー伊藤は「場の空気を読むという能力は学校で教えられるか?」なんてことを言い出します。これはかなり面白い発想です。おそらくテレビ業界に長くいて、テリーに一番大事なことは「場の空気を読む」ということなんでしょう。 一方、和田先生はエリート教育の方に関心があり、公教育では「必要最低限のことをやればいい」という考えが見え隠れしています。富裕層はエリート教育をすればいい、そうでない層には最低限のことを保証すべきという考え。これはこれでスッキリした意見です。 私個人の意見としては「子供にリアルな社会を見せろ」ってことを言いたいです。 よくいわれる話ですが、大学を出てそのまま社会経験のない教師が「リアルな社会」なんてものを教えられるはずないんですよ。 「読み書きそろばん」はそういう教師に任せるとしても、「社会科」の一部あたりは実社会の経験者に教師をやってもらいたいもんです。 定年退職した実社会の経験豊富な人材なんてたくさんいるはずですから。 海外赴任経験豊富な商社OBとか、トップセールスマンだった営業マンとか、タクシーの運転手とか、リストラにあったサラリーマンとか・・・。 ちょっと考えただけでそういう人の話は実に面白そうです。 「子供の個性の尊重」というのもいいんですが、実社会の現実を教えて感性を磨くというものもありかと。 「社会ってそういうもんなんだ」と薄々感じることのできる授業って良いと思うなー。
2005.12.18
コメント(2)
-

猫も働くんです「ユキポンのお仕事」
ユキポンのお仕事 ヤングマガジンKC著者/訳者名 : 東 和広 著 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-361383-6) <感想> この「ユキポンのお仕事」という漫画はなかなかシュールな漫画です。 フリーターの「あけみちゃん」の飼い猫の「ユキポン」が、だらしない主人の代わりにバイトで生活費を稼いでくる話。 それが「猫のCMモデル」といった猫らしい仕事ではなくて、いわゆるガデン系の仕事、建設現場や引越しセンター、海洋調査等といった肉体派の普通のバイトをこなすのが笑える。 ユキポンは猫なのに言葉を話し、2本足で歩き、飼い主より性格もしっかりしているというまるで「ドラえもん」のぷちリアル版みたいな話です。 ユキポンのするバイトは作者が実際に体験したバイトなのかどうか、やたらいろんなバイトが出てくるんですが、その描写のリアルさがスゴイです。 リアルなバイトの話なのに、なぜか働いてるのがネコというシュールさ。 絵柄もトーンを使わずに手書で描いてるのでなかなか味のある絵に仕上がってます。 作者のメッセージらしきものがちらほら出てくるのも魅力。「勝てる相手としか戦わない80年間無敗の格闘家」というギャグみたいなキャラが意外に面白いことを言ったりします。「アホが、戦争なんかしおって。 世の中アホばっかりや。 戦争で勝ったとしても、ホンマの勝ちと違うんや。 闘いはそんな短い時間軸でやるもんやない。 闘いとはもっとトータルなもんや。 目先の勝負でコトが決まると思ったら大間違いや。 まず勝とうと思うトコがシロートなんや。 勝とうとするから負ける。わかるか?この深い意味が・・・。 オツムの小さいやつはカーッとなったらすぐやっちまえとか思うんやろ。 その時点で負けとるんや。 世の中は非ゼロサム。 なんでもかんでもプラマイゼロなんてことはない。 勝った負けたの二者択一ではないんや。」 一見、ギャグ漫画かと思いきやこんなセリフがでてくるのがまたシュール。正直、とても面白い作品なのでオススメです。
2005.12.09
コメント(0)
-

親と子の「新世紀エヴァンゲリオン」
新世紀エヴァンゲリオン 角川コミックス・エース著者/訳者名 : 貞本義行/漫画 Gainax/原作 出版社名 : 角川書店 (ISBN:4-04-713115-6) 発行年月 : 1995年09月 <感想> かつての「エヴァブーム」からもうすぐ10年が経とうとしている。10年か~。10年。 「10年一昔」とはよく言ったもので、個人的には、現在30代半ばの私のこの10年は、たぶん人生の中でも最も激動の10年だったかもしれない。 10年経っても連載が終わっていないエヴァの漫画版というのもスゴイが、10年経っても熱が冷めない自分もけっこうスゴイ。 ガンダムの話をするときにもしばしば言っているが、こういう「楔(くさび)」を打ち込まれた場合、一生その楔は消えないのかもしれない。私の楔は「ガンダム」「押井守」「エヴァ」・・・あたりか。 たぶん一生背負っていくんだろうなァ。 それにしても、そういう「グッとくる作品」を観てても、自分の観る年代によって、けっこう感想というのは変わっていくものだ。 同じエヴァを観ても、妻子持ちとなった今、感情移入するのは圧倒的に「碇ゲンドウ」になってしまった。 ゲンドウと息子シンジの関係のありかた。ゲンドウがシンジに語る言葉は少ないが、その数少ない言葉の重みを考える。「自分だったら息子に何を言うべきか?」なんてことを考えてしまうのだ。 私にも息子がいるが、もし碇シンジと同じ環境に自分の息子がいたら、何を言うべきか? 「エヴァに乗って使徒と戦う」なんて状況は現実にはありえないとはいうものの、「成長して実社会に出る」というのは「使徒と戦う」くらいにわけのわからない困難な作業だ。 「営業マンになって、クルマ売ってこい」というのと「エヴァに乗って正体不明の敵と戦え」というのはその意味のなさにおいてたいして違わない。 同じ「生きる」ということ。「使徒」は「リアル社会」のメタファーに思えるのだ。 エヴァから10年経って、「ニート」などという言葉が流行りだした。碇シンジはなんだかんだいってけっこう精神的に強い子供だった。今のリアルな普通の14歳はシンジよりさらに脆弱なのではないか? 我が息子の行く末を考えるとき、自分とゲンドウを照らし合わせて、エヴァのことを考える日がまたきっとくるに違いないと思う。(エヴァの話は次回に続く)
2005.12.05
コメント(2)
-

幸福的終末感「ヨコハマ買い出し紀行」
ヨコハマ買い出し紀行アフタヌーンKC著者/訳者名 : 芦奈野 ひとし 著 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-321050-2) 発行年月 : 1995年08月 価格 : 520円(税込) <本の内容> 温暖化が進み水位の上昇で滅びが迫る近未来の日本・・・。大都市ヨコハマもまた高台を残し海中に没した。慌ただしかった時代は過去のものとなり、時間がゆっくりと流れる黄昏の時代。 三浦海岸の西の岬でコーヒーショップ「カフェアルファ」を営むアルファさんは、とても人間的で素敵なA7M2型ロボット。ふらり出かけたままのオーナーを待ちながら、マイペースに喫茶店をやりくりしている。もっとも、店のコーヒーの8割方は自分で飲んでいるような感じだけれど。 <感想> ゆうなぎ ゆふ― 0 【夕▼凪】 海岸地方で夕方、海風から陸風に替わるときの無風状態。[季]夏。⇔朝凪 とあるブログのオススメとして紹介されていたので読んでみた作品。一見、地味な感じのする本作ですが「名作」の評価も納得の内容なのでした。 タイトルからすると「最近、ハヤリの漫画エッセイか?」などと誤解されそうですが、立派なSFです。 「文明が崩壊した近未来」というと大友克洋「AKIRA」か「風の谷のナウシカ」を連想しますが、世界は退廃的な感じではなく、その世界観はむしろ「未来少年コナン」を思い出します。 滅びが迫っているにも関わらず、焦りもなくただ安らぎに満ちた緩やかで穏やかな時間が流れる世界。 道路や建物などの人工物は自然に飲み込まれつつあり、地球本来の姿に戻りつつある世界。 人口は減少し、競争もなくなり、かつての文明社会の「祭り」は終わった時代。そこはまるで「理想郷(ユートピア)」のようです。 作中、この時代は「夕凪の時代」と呼ばれます。大きな時代から時代へと移り変わる間の、ほんの少しの無風状態という意味でしょうか。 その無風状態の中、永遠の時間を持つロボットであるアルファは、変わり行く世界の姿を見ようとします。その自然の中にいる主人公の描き方が実に良いんです。まるでページからその世界の風が吹いてくるような・・・。 21世紀の飽和した日本に住んでいながら、リセットされた世界に憧れるというのは、健全なんだか不健全なんだか。 ただ「心穏やかな時代」への憧憬はどうにも消えそうにないです。
2005.11.27
コメント(4)
-

伝奇SF「七夕の国」
七夕の国 ビッグスピリッツコミックススペシャル著者/訳者名 : 岩明 均 出版社名 : 小学館 (ISBN:4-09-187731-1) 発行年月 : 2003年09月 価格 : 1,000円(税込) <内容>就職問題で悩む大学生“南丸洋二”が主人公。空間に丸い穴を穿ける超能力を持っている彼は、“丸神”教授のゼミで超能力者の家系のルーツが丸川町にあることを知る。教授の謎の失踪と時を同じくして、体を球型に抉り取られる殺人事件が発生、主人公と“丸神”ゼミの面々は丸川町を取り巻く陰謀に巻き込まれていく。<感想> 「寄生獣」の岩明均のSF伝奇漫画。全4巻とコンパクトな作りのうえ、プロットがわかりやすいため好感のもてる一作。 話のつかみがうまいのであっという間に全巻読破すること必至。謎ときのカタルシスもあり、思わず「あっ」という結末も待っている。 ここからはチト厳しい批評。 正直、SFと伝奇の融合という試みは小説では珍しくない。そういうことを考えると「このストーリーがなぜ漫画で語られる必要があったのか?」がいささか疑問に思える。 前作「寄生獣」は漫画でしかなしえない表現に舌をまいたが、「七夕の国」には絵的に漫画である必要はないのではないかと思える。 (一部、図案のトリック的なものも登場するが、小説の挿絵で充分な程度)。 むしろ日本の地方を舞台にした伝奇SFであれば、小説のほうが表現には向いているのではないかという気さえする。 漫画の致命傷は読者が「絵」以上のイメージを膨らませるのが難しい点だが、小説であれば読者が勝手にその場面の表情、空気、広がりを想像できる。 伝奇SFは多分に読者の想像に頼ったほうが良いことが多いような気がするのだ。 話は変わるが、この作者の「時代性の無さ」というのは意図的なものなのだろうか? 登場人物のファッション、髪型、行動様式。主人公の大学の風景など、正直、とても平成の世に描かれた漫画とは思えない古さだ。「昭和の漫画」といってもそのまま信じてしまうだろう。 別に古いから悪いといってるわけではない。ストーリー重視の漫画なのだと言ってしまえばそうだし、20年前みたいな今の漫画なら20年後にも通用する可能性があるということだ。 しかし、漫画である以上「絵的なイメージ」って必要ないんだろうか?別に矢沢あいみたくなれとは言わないが、「七夕の国」のキャラクターを思い出せと言われたら、けっこう難しい(異形の人達はすぐ思い出せるが)。「異形のモノ達を扱ってるから人間は普通でいいのか?」「結局、人間の個性なんて限界のあるものだと言いたいのか?」「もしかして登場人物は忘れられてもいい存在のか?」いろいろ考える。「漫画を読んだ」というより、「小説を読んだ」ような気になる作品だったな。
2005.11.24
コメント(0)
-

堕落論「闇金ウシジマくん」
闇金ウシジマくん 1 ビッグコミックス著者/訳者名 : 真鍋 昌平 著 出版社名 : 小学館 (ISBN:4-09-187341-3) 発行年月 : 2004年07月 価格 : 530円(税込) <感想>おちる[墜ちる] 望みや救いのない所にはまり込んで身動きできなくなる。「地獄に―・ちる」 「墜ちる」というのはコワイ。ブログを書いたり読んだりしている今の私やあなたはきっと平和に違いないが、日常生活のけっこうすぐわきには深くて暗い穴があいてたりするようだ。 街の駅前あたりにはサラ金の看板と店舗があふれるようにある。「たくさんある」ということは、それを必要としている人がたくさんいるということであり、「ご利用は計画的に」できる人はサラ金なんか利用するはずないから、返済しきれない人も数多くいるのだろう。 で、「多重債務者」「カード破産」という類のニュースがテレビから毎日のようにあふれでることになる。 調べてみると自己破産の件数は約20万件(10年前の5倍!)自殺者は年間3万人。 どこか遠い世界の話ではないのだ。 この漫画「闇金ウシジマくん」はコワい。 初めて読んだとき夜眠れなかったよ(いやマジで)。 この漫画の怖さは、闇金業者ウシジマの取立てもあるのだが、なんといっても「普通の人が闇金の客になりえる」という事実だ。 コンビニで隣にいる客が借金地獄であがいているかもしれない、そしてそれは自分にも降りかかる出来事かもしれないという恐怖。 ギャンブルにハマるサラリーマンや主婦、買い物にハマるOL。 どこにでもよくある話だが、ちょっとその収支バランスが崩れるとあっという間に「ウシジマくん」の常客になりえる。 不況下の現在、経済的にも精神的にも、そのバランスを崩して墜ちていくケースは多いに違いない。 本屋に行けば「あなたも成功できる」みたいな本が山ほど売られているが、可能性から行けば「あなたはこうすれば墜ちないですむ」とか「借金しないですむ」という本を読んだほうが良い人が多いに決まっている。 墜ちたくない。 成功なんてしなくていいから、せめて、いつまでも平和にブログの更新とかやってられる日々が続く程度に努力していこう。と思う。
2005.11.19
コメント(1)
-
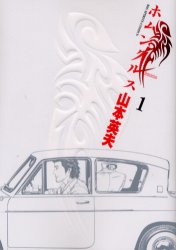
定点の失敗「ホムンクルス」
<本の内容>高層ビルとホームレスの住む公園の間に車を停め、カー(車)ホームレスをしている名越。ある日70万円で頭蓋骨に穴をあける手術をしないかと奇妙な男に声をかけられる。金に困った名越は手術をすることになったが手術後、名越に異変が起きて・・・。<感想> 漫画を読むときにはある程度の「定点観測」が必要です。主人公のキャラクター、職業、性格、おかれた環境等、読者はなにがしかの確認を持ってその世界に入っていきます。 漫画の世界は荒唐無稽な世界であるため、その「足場」がないと読者はファンタジーな世界で迷子になってしまうことになります。 この「ホムンクルス」はいささか読者を路頭に迷わせてしまう作品。 導入部の「トレパネーション」手術のあたりは、話の持って行き方が実にうまく、世界にぐいぐい引き込んでいくのですが、話を引っ張っていくはずの医大生伊藤が途中から登場しなくなり、現実社会と主人公の接点が消えてしまいます。 主人公はなぜ手術を受けるのか?なぜ車の中で生活しているのか?なぜかつて一流ホテルの常連だったのか?職業は何なのか?方言は何なのか?なぜ人のトラウマが見えるのか? こういう読者の疑問はほっとかれて、話はどんどん進んでいきます。5~6巻くらいでおぼろげながら主人公の職業などわかってきますが、5~6巻でやっと主人公のキャラがわかるのってちょっと遅くない? 「砂の女子高生」編のあたりで話がかなりグダグダするので、連載を読んでた人はさぞかしツラかったことでしょう(休載も多かったらしいし)。 主人公が街の人のトラウマを解消していくのが話の軸になるのか、もとの職業に戻るのか、それとも新しい能力をまた身につけるのか、話の方向性もイマイチ見えません。 東京の繁華街のリアルな町並みが舞台のため、その不透明さがいっそう読み手を苛立たせます。 前作「殺し屋イチ」が名作だったため、ある程度ガマンして読んでる読者も多いかもしれないんですが、そろそろ限界。 「第1部 完」でもいいので、はやいとこ軌道修正してほしいもんです。 話の導入はうまいんですよ、ホント。でも続きをサクッと仕上げないと「20世紀少年」の浦沢直樹みたくなっちゃいます。
2005.11.18
コメント(0)
-
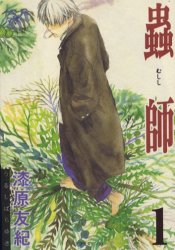
生命を見よ「蟲師」
蟲師 1 アフタヌーンKC著者/訳者名 : 漆原 友紀 著 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-314255-8) 発行年月 : 2000年11月 価格 : 590円(税込)<本の内容>ヒトと蟲との世が重なる時、蟲師・ギンコが現れる。およそ遠しとされしもの――見慣れた動植物とはまるで違うとおぼしきモノ達それら異形の一群をヒトは古くから畏れを含みいつしか総じて「蟲」と呼んだ<感想> 養老孟司が何かの本で「人間は自分達に関わりのないモノは見えない その辺の野原には無数の小さな生き物がいるのに、それが見えないから平気で野原をつぶす」というようなことを言っていた。 人間は自然に対して傲慢になったのだ。 「蟲師」は、人がまだ自然を恐れ、自然と共に暮らしていた頃の物語。民話伝承のようであり、おとぎ話のようでもあり、怪談のようでもある。 山を崇拝し、夜を恐れ、蟲がそばにいた時代。人はそういう時代を経て今に至る。 電飾の網が星を覆うにつれ、人は恐れるものを失っていった。より大きなものしか見えなくなった。 「蟲師」はそんな私達に生命の起源を教える。身近な自然の中の小さな命、私達の体の中に秘めた生命力を教える。小さなものを見る方法を教えるのだ。
2005.11.14
コメント(0)
-

イマイチ香山リカ「いまどきの「常識」」
いまどきの「常識」 岩波新書 新赤版 969著者/訳者名 : 香山リカ/著 出版社名 : 岩波書店 (ISBN:4-00-430969-7) 発行年月 : 2005年09月 価格 : 735円(税込) <本の内容> 「反戦・平和は野暮」「お金は万能」「世の中すべて自己責任」…。身も蓋もない「現実主義」が横行し、理想を語ることは忌避される。心の余裕が失われ、どこか息苦しい現代のなかで、世間の「常識」が大きく変わりつつある。さまざまな事象や言説から、いまどきの「常識」を浮き彫りにし、日本社会に何が起きているのかを鋭く考察する。<目次> 1 自分の周りはバカばかり―人間関係・コミュニケーション篇2 お金は万能―仕事・経済篇3 男女平等が国を滅ぼす―男女・家族篇4 痛い目にあうのは「自己責任」―社会篇5 テレビで言っていたから正しい―メディア篇6 国を愛さなければ国民にあらず―国家・政治篇<感想> 精神科医として、または大学教員として、若者の生態や思考に関してなかなか面白いことを言うなーと思っている香山リカの最新刊。 「いまどきの常識」というタイトルが実にうまい。 こういうタイトルつけられたら「ほほうー。今どきの常識って何なの?」って興味を持ってしまいます。 で購入してみたこの本。香山リカが「右傾化」「全体主義化」していく日本を憂う内容になってます。とはいっても、薄い本に30ものテーマが扱われており、一つ一つの議論が丁寧であるとはお世辞にもいえません。 作者の独断的な反論、なんとなくの言い分もけっこう見受けられるので、そんなに真面目に読む本ではないという気もします。 「ははー、最近はこういう考え方がハヤリなのかー」くらいで正解。 先日の自民党圧勝に顕著であるように、今の日本はどうも「白か黒か」みたいな極端な単純な思考に行きつく傾向にあるようです。 本著にもふれられているとおり、テレビ他メディアの影響が非常に大きく、あきらかな情報操作があっても「自力思考」ができない人が増えてるのかもしれません(自分を含めて)。 ただ、そういう社会で現実に生きている以上、「そういう社会の選択」に従うことも「オトナの生き方」。 要はバランスの問題で、そういう馬鹿な社会を冷静に見つつも受け入れるというワザが必要になってきます。 最近よくマスコミに登場する精神科医の存在を大事だと思うのは、「さすがに精神科医は思考のバランスがとれているんじゃないか」ということ。 和田秀樹にしても斎藤環にしても独自の視点から社会をみつめる冷静さを持っているのが心強い。理論構築だけでなく、「現実社会を生きぬく知恵」を持っている。やはり「ナマの人間」を診ている臨床の賜物なんでしょうか。 「とりあえずみんなを納得させる意見を言うコメンテーター」もいいんですが、こういう時代だからこそ、科学者として「ウマい生き方」を提案する精神科医師に大いに期待してます。
2005.11.09
コメント(0)
-

ファーストとZの間「機動戦士ガンダムC.D.A.若き彗星の肖像」
機動戦士ガンダムC.D.A.若き彗星の肖像 1 角川コミックス・エース著者/訳者名 : 北爪宏幸/著 出版社名 : 角川書店 (ISBN:4-04-713511-9) 発行年月 : 2002年11月 <本の内容>『ガンダム』の人気敵役、シャア・アズナブル。その謎とされてきた『Z』にいたるまでの「空白の7年間」を北爪宏幸が独自の解釈を交え描く。<感想> 「ファーストガンダムとZの間の空白の7年間を描く」ってのは、けっこうな重責です。 なにしろガンダム世代といわれる人達が初めて「Zガンダム」を観たときの「(゚Д゚)ハァ?」の感じをすべて消化させなきゃならないわけですから。 「ファースト」→「Z」の間の裏設定が多すぎるわけですよ。どー考えても。 今にして思えば、ものすごい不親切なアニメでした、「Z」は。順番としては「0080」か「0083」が時代としては順序なわけで、なんでいきなり「Z」に行ったのか今でも疑問です。 あれで、幾人のファーストガンダムファンが脱落していったことか・・・。 当時、中学生の私などはアニメ雑誌などから情報を得て、必死に「Z」についていったものでした。 で、この「機動戦士ガンダムC.D.A.若き彗星の肖像」は「Z」から約20年の後に登場したわけですが、その存在価値は貴重です。 しかし、この北爪宏幸さんという作家は、どーもアニメの人らしく、「漫画家」ではないんですよね。 この作品は確かに読みやすいんですが、描写に深みがないというか、絵もストーリーもいささか淡白すぎる気がします。 そもそも「アクシズ」という宇宙の辺境の話で、派手な戦争の話もなく、要は「つなぎ」の話なわけですから、漫画として盛り上げる苦労もわかる気はしますが。 一番のツッコミどころは「ハマーン、別人じゃん!」というあたりでしょうか。「独裁者」のイメージとはかけ離れた「萌えキャラ」で描かれるハマーンが、今後どのように変貌していくのかは見物です。 しかし、シャアがイメージのままでほんと良かった・・・。おかしく描かれたらどーしようかと思ったよ。
2005.11.04
コメント(3)
-
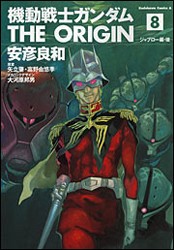
伝説は甦る「機動戦士ガンダムTHE ORIGIN」
機動戦士ガンダムTHE ORIGIN 角川コミックス・エース著者/訳者名 : 安彦良和/著 矢立肇/原案 富野由悠季/原案 出版社名 : 角川書店 (ISBN:4-04-713453-8) 発行年月 : 2002年06月 <感想> この作品、連載当初は「テレビ版の焼き直しか?」と正直思ったものですが、話が進むにつれ、それは大きな間違いであったことに気付きました。 この作品は正統なガンダムの歴史を綴った、いわば「新たな金字塔」です。 基本的にはファーストガンダムのストーリーを追って、話は進んでいきますが、テレビアニメでは描けなかった世界観、人物描写、新解釈を独自に加えているところが大きなポイントです。 新キャラも登場し、モビルスーツデザインもけっこう違っているのですが、「ファーストガンダムの世界」を壊さない程度にうまくリアライズしています。 TV版では描かれていなかったいわゆる「裏設定」が丁寧に描かれていく様は感涙モノです。 特にジオン公国の世界はテレビ版ではほとんど描かれることがなかったため、「ジオン・ダイクンとその思想」「独立戦争の意義」というあたりがよく理解できませんでしたが、この作品はそのへんを丁寧に描いていきます。 また単なる「敵役」だったザビ家四兄弟やランバ・ラル達のジオン政変をめぐる若かりし頃のエピソードや、キャスバルとセイラの生い立ちなどはそれだけで一作品ができてしまうほどの濃密さです。 作者の安彦さんはやはり「キャラの人」で、メカもいいんですが、人間ドラマを描かせたらこれほどの作家はなかなかいません。 どうも作画を絵筆一本でしているらしいのですが、その柔らかなタッチで描かれる人物の微妙な表情が実にいいんです。 これほどの人がジオン軍人達の激動の生き様を描くのですから面白くないはずがありません。 TV版ガンダムを観て育った世代ももう大人。 そういう大人に対して「ガンダムとはこういう話だったんだ」と直球を投げつけた本作品は、「ガンダムサーガの補完」というよりも「新たなガンダムサーガ(伝説)」というにふさわしい一作です。 昔の地位に安住せず、この作品の連載をやろうときめた安彦良和は本当に本当に凄い人だと思います。
2005.10.28
コメント(1)
-

漫画のみに許される表現「寄生獣」
完全版 寄生獣 1 アフタヌーンKCDX著者/訳者名 : 岩明 均 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-334664-1) <本の内容> 「人生、2度目の衝撃でした」――鶴見俊輔氏(哲学者)、驚愕!!累計部数1000万部の大ベストセラー!カラー原稿を完全カラー収録の完全版!シンイチ…『悪魔』というのを本で調べたが…いちばんそれに近い生物はやはり人間だと思うぞ…他の動物の頭に寄生して神経を支配する寄生生物。高校生・新一と誤って彼の右手に寄生したミギーは互いの命を守るため、人間を食べる他の寄生生物と戦い始めた。<感想> ちょっと古い漫画になってしまいましたが、衝撃作であることには変わりありません。 「右手のみが」寄生生物に乗っ取られるという奇想天外な物語。「乗っ取られた右手」=「ミギー」が、異形の生物ながらだんだん可愛く見えてきて、別れのときには涙するほど悲しくなってしまうのは我ながら意外です。 人間が人間を食べたりするシーンが連発なのでホラー漫画と思いきや、ラストの方までいくと「人間とはなんぞや?」という深い哲学的な思考に行きつきます。 異生物「ミギー」は偏見や先入観のない発想をするので、いわゆる「普通の発想」をぶち壊してくれるのもなかなか痛快です(死んだ牛や豚は食べてもなぜ死んだ人を食ってはいけないのか?等) この作品が漫画としてすばらしいのは、このストーリーが漫画という手段以外では語れないところにあると思います。当然、実写化なんて絶対無理だし、アニメもおそらく難しいでしょう(あまりにグロくて)。小説では異生物の動きの描写がこれほどリアルにできるかどうか。 この作家は特に絵がうまいというわけではないんですが、異生物に乗っ取られた無表情な人間の顔を描かせたらすごいです。これは漫画以外じゃ表現できません。一度読み始めると続きがすごーく気になるし、じっくり読むタイプの漫画じゃないので、漫画喫茶などでイッキ読みをオススメします。
2005.10.26
コメント(4)
-

世界を目指せる「鋼の錬金術師」
鋼の錬金術師 ガンガンコミックス著者/訳者名 : 荒川 弘 / 著 出版社名 : スクウェア・エニックス (ISBN:4-7575-1230-9) <感想> 読んでみた最初の感想は「最近の漫画だなー」ってこと。 専門的なことは詳しくわかりませんが、タッチというか動きというか、最近の漫画は昔と違ってだいぶ進化してきた気がします。 一昔前のジャンプ系の漫画は静止画としては美しいものの、絵の「流れ」にはやや欠けたものでしたが、最近の漫画の絵は「流れ」重視になってきてる気がします。 この「鋼の錬金術師」もまるでアニメのような絵の流れと、シリアスとギャグを織り交ぜながらのストーリーのテンポが絶妙で、ここまで登りつめたのも納得の感があります。 正直、第1巻あたりは独特の世界観がつかめていないこともあり、「凡庸な少年漫画か?」と思ったのも事実ですが、話が進むにつれ世界は広がり、10巻を越えた現在でも、テンションと話の深みは全く落ちていません。 特筆すべきは「錬金術」と「機械鎧(オートメイル)」という独自の世界観を創り出したことで、劇中の世界に深みを出していることです。この作者のメカを描くセンスは卓越したものがあり、とても女性作家とは思えないものがあります。 漫画は世に数あれど、このように新しい独特の作風を作り出しながら、かつ商業的にも成功を納めることができる作家が登場することにまったく驚きます。 この作家は「鋼の~」が初連載というのも驚きなんですが、これからも良作を創り出してくれそうで嬉しい限りです。 この漫画は、おそらく世界に通用するものとして現段階でトップクラスの「少年マンガ」ではないでしょうか。 こういう「職人」チックな作家を産み出す日本はやっぱスゴイです。
2005.10.22
コメント(5)
-

ガンダムは癒しである「ガンダムウエポンズ」
ガンダムウェポンズ ホビージャパンMOOK 出版社名 : ホビージャパン (ISBN:4-89425-308-9) 価格 : 1,500円 <雑感> ガンダム世代って今の30代くらいの人達を指すんでしょうか。ガンプラブームに小中学生だったくらいの人達。小中学生時代にガンダムにハマった人達が大人になって、購買力を持ちここまでの一大マーケットになるとは、さすがに予想してた人はいないでしょう。 昔、やはり流行った「仮面ライダー」「宇宙戦艦ヤマト」「超時空要塞マクロス」なんてのは現在はそんなにメジャーなマーケットになっていないことを考えると、ガンダムが当時の私達に打ち込んだ「楔」は相当なものであったと考えられます。恐るべし大河原邦男。 それにしても30代半ばを迎えた今、ガンダム関連商品はあふれんばかりに増え、ガンプラも異常な盛りあがりをみせています。(マスターグレード「アッガイ」とか、そこまでしなくていいだろと思う(笑)) うーん、欲しいガンプラ。でもでも「30代の妻子持ちの男が購入して作ってしまっていいのか?」というジレンマがどーしてもあります。 造型レベルも価格も、今や完全に「大人の玩具」と化したガンプラですから、別に購入してもいいんでしょうけど、買ってしまったら「何か一線を越してしまう」気がするんですよ。(まあ個人的な問題なんだけど) で、登場したのがこの「ガンダムウエポンズ」シリーズ。簡単に言うと、プロのモデラーが作ったガンプラやジオラマの写真集なんですが、これが実に良い! 最新のテクでつくったマスターグレードとその装飾にシビれます。 自分で作ってもこれだけのものは作れないし、写真集ならお手軽にパラパラ見れる。ってわけで、今の最大の私の「癒し」はこの写真集です。
2005.10.20
コメント(0)
-
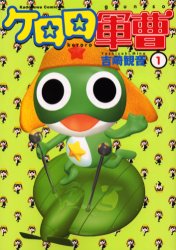
ガンダムヲタ萌える「ケロロ軍曹」
ケロロ軍曹 1 角川コミックス・エース著者/訳者名 : 吉崎観音/著 出版社名 : 角川書店 (ISBN:4-04-713307-8) 発行年月 : 1999年12月<感想> 「ヲタ」系に人気の漫画という感じでパラパラとめくってみたものの、あまりの面白さに引き込まれました・・・というか自分も充分「ヲタ系」であることを再認識。 「地球を侵略しにやってきたものの、とある家族とその仲間達と仲良くなってしまうケロロ星人(?)のドタバタの日常を描いた漫画」って内容で、設定は「ドラえもん」とか「うる星やつら」みたいな感じになってます。 「ヲタ系に人気」というだけあって、他漫画やアニメのパロディが満載。特に「ドラえもん」「ガンダム」のパロディが濃厚。主人公の趣味がガンプラ(ガンダムのプラモ)製作だったりするし。元ネタがわからない人には意味不明でも、わかる人のツボにはもろハマるという代物です。それもかなりマニアック。 漫画中に平気で「ラルグフ」とかいう単語が出てくる。まさかと思ったら、やはり「ランバ・ラル専用グフMS-07B」のことだった(笑)。ちなみに先行量産タイプを「MS-07A」というらしい(興味のある方は検索を) その他ウケた主人公達のセリフ。「(ガンプラの)量産型は数作らなきゃね」「ドムは3体作らなきゃね」「軍人は「専用」が好き」うーむ、笑える。 ところがヲタ系と馬鹿にするなかれ、そのキャラクターが子供に大ヒット。すでに映画化が決まったようで、アニメや関連グッズもかなり好調の様子。 この調子だと、「ドラえもん」「ピカチュウ」クラスのキャラにまで伸びるのかもしれません。 どうやら「電車男」がこのキャラ好きだったらしく、ブレイクの一要因とか。 「電車男」にしろ「ケロロ軍曹」にしろ、これらのブレイクというのは「オタクのカミングアウトOK」という流れで解釈していいんでしょうか?調子に乗って、「オタクOK」みたいな顔をしてると、どこかでハシゴをはずされそうでかなりコワイ気もします。 オタク話ついでに「軍隊の階級」の話など。「軍曹」という階級がどれくらいエライのか?ってよくわからなかったので調べてみると、軍隊の階級って元帥・大将・中将・少将・准将・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・少尉・准尉・曹長・軍曹・伍長・兵長・上等兵・一等兵・二等兵。という序列だったんですね。 「軍曹」というのは士官と兵卒の中間。小隊(10~20人)の隊長クラスらしいです。 普通、漫画とかアニメで活躍する階級って「大佐」とか「少佐」とかの偉いクラスであることが多いような気がしますが、小隊で「軍曹」とか「伍長」が活躍するという「ケロロ軍曹」はけっこうリアルな作りになってるかもしれません。 ファーストガンダム第1話でサイド7に潜入し、アムロに返り討ちにあった「ジーン」と「スレンダー」は軍曹だったらしいです。この階級にぴったりの任務だったのでは?という気がします。(というかケロロ軍曹ってこの二人のパロディなのか?) ガンダムの軍曹といえば「セイラ・マス」とか「ファ・ユイリイ」も実は軍曹なのでした。 「軍曹」といえば「鬼軍曹」とかのイメージだったので、「昨日まで民間人だった女の子が軍曹ってどうなのよ?」って思ったもんでした。 っていうかなんでミライがいきなり「少尉」なの?・・・ヲタ話が長くなるので今日はここまで。
2005.10.09
コメント(5)
-

そんな社会を生きろ「ブラックジャックによろしく」
ブラックジャックによろしく 1 モーニングKC著者/訳者名 : 佐藤 秀峰 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-328825-0) 発行年月 : 2002年06月 価格 : 560円(税込) <本の内容> 超一流の永禄大学付属病院の研修医・斉藤英二郎、月収わずか3万8千円。理想とかけ離れた日本の医療の矛盾に苦悩しつつも、懸命に日々を送る。衝撃の医療ドラマ!<感想> 私が小学3年のとき、同級生がガンで亡くなった。 真面目で優しい子で、ナカムラくんといった。お父さんは確か医者だったと思う。 大人になってから、いとこがガンで亡くなった。結婚したばかりの若い女性だった。その親父さんもガンで亡くなった。 就職してからも職場の人が3人ほど亡くなった。 まわりの人達の死というものが、私の死生観にどこまで影響を与えているのかはわからない。 正直言って「亡くなった人達の身になって考える」ということは難しい。 なぜなら所詮は他人のことであって、その人達の死後も私達は普通に食事をして買い物をしてテレビを見て生活しているからだ。 ただ「亡くなった人達のことを考える」ということはできる。この世の不条理。この世の不公平。 みんな「なぜ私が死ななきゃならないの?」って考えたと思う。「何も悪いことをしていないのに」 そう、この世はおそろしく残酷で不条理で不平等でナンセンスな世界なのだ。「ブラックジャックによろしく」を読んで、感じるのはそういう世界。 生と死を扱う「病院」という、一見理想のシステム化されたかに見える世界で繰り広げられる矛盾と苦悩の連続。 読んでて胸が重苦しくなってくるような話だが、これは病院の中に限った話ではないんだと思う。 高度に情報化され、発達したかに見える今の社会。テレビのバラエティなんか何気なく見ていると、一見理想的なユートピアなったかのように感じてしまうこの社会だが、一皮剥けば当然ながらかかえきれない矛盾と不条理を多く抱えているのだ。 私達はこの残酷で不条理でおかしな社会に今日を生きなきゃならない。みんな隣にいるはずなのに、他人の苦しみ、悲しみを理解できずに。 そしてわかっていながら、私も死ぬときには「なんで私だけが」と思うのだろう。「みんな必ず死ぬ」という事実だけは、真実であるのに。 私が死んだらナカムラくんに会いに行こう。 「いやーまいったまいった。まさか小学3年で死ぬとは思わなかったよ」と言って彼が笑ってくれたら嬉しい。
2005.10.07
コメント(0)
-

終わりなき日常「ハチミツとクローバー」
ハチミツとクローバー 1 クイーンズコミックス著者/訳者名 : 羽海野 チカ 出版社名 : 集英社 (ISBN:4-08-865079-4) 発行年月 : 2002年08月 価格 : 420円(税込) <本の内容> 6畳+台所3畳フロなしというアパートで貧乏ながら結構楽しい生活を送る美大生、森田、真山、竹本の3人。そんな彼らが、花本はぐみと出会い……!? 大ヒットシリーズ第1巻!!<感想> この漫画は「ユルイ」。絵もどこかユルければ、ストーリーもユルい。 でもそれが良い。 漫画の舞台は美大。同じアパートで貧乏暮らしをする男子学生を中心に繰り広げられる「ちょっと面白い日常」の物語。 大学生活というのは人生の中でもかなり自由で縛られない時間であるうえ、美大という舞台の「非実務性」がまずファンタジー色濃厚です。 さらにはけっこうな頻度で留年してみたり、卒業制作を放棄してみたり、助教授と友達みたいだったり・・・というユルさ。 作者もけっこう暴走ぎみで、主人公「はぐ」をめぐる森山と竹本の話がストーリーの軸になるかと思いきや、話がそれるそれる。山田を巡る恋模様あたりはそのときのテンションで描いてるんじゃないかという感じすらします。 しかしそのユルさこそゆえの「ほのぼの感」がこの漫画の最大の魅力です。恋愛話のメインが山田になっていく様も、あきらかに作者の「熱が入っている」ので、主人公の話よりはるかにアツい。 話の展開がまったく読めないあたりがまた面白い(というか作者も読めてない気もする)。 でも「話の展開」などと言っても、たいした話の展開は必要ないような気もします。なんとなく「この状態が良い」というか、就職とか結婚などというシビアな現実を前にした「学生最後の祭り」的な日々がずーっと続いていくのが理想なのかもしれません。 この漫画を読んでてふと高橋留美子「めぞん一刻」を思い出しました。 劇中のキャラも読んでる読者も「ユルい日常がずーっと続いていくのが理想」という不思議な状態です。 「めぞん~」の最終回では「管理人さんや楽しいみんなと一緒に同じアパートで住んでいく」という最も平凡かつ最高の終わり方をしました。 そういう意味で「ハチミツとクローバー」は「2000年代のめぞん一刻」「さらにユルいめぞん一刻」を目指してほしいと思います。自分の本棚にこの漫画があるとちょっと幸せな感じになる一冊。
2005.09.25
コメント(1)
-

ニートは読め!「働きマン」
働きマン 1 モーニングKC著者/訳者名 : 安野 モヨコ 著 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-328999-0) 発行年月 : 2004年11月 価格 : 540円(税込)<感想> 週刊誌編集部の編集者・松方弘子が、働いて働いて、働きまくる!作品。 彼女は仕事モードが最高に達すると「働きマン」になる(といっても変身するわけではなく、男モードでバリバリと仕事することを示す)。 編集部と一口に言っても、いろんな部署、いろんな人材が多様にいて、仕事バリバリの松方はその中でいかに働くか・・・?みたいなストーリーです。 人が100人いれば100通りの仕事があって、100通りの仕事感があると思います。 でも日頃、「自分の仕事感とは」なんて話は同僚とはまずしないのが普通。 そんな話もしないので 、なかなか「自分の仕事感」が自分でもわからなかったりしますが、この漫画を読むとそこらへんがけっこう明確になる気がします。「仕事しかない人生だった、そう思って死ぬのはごめんですね」「あたしは仕事したなーって思って死にたい」ストーリー冒頭、ソコソコに仕事をこなす後輩と仕事バリバリの主人公との会話。ここで読者はすでに「俺はどっちだ!?」なんて選択肢をつきつけられます。 「仕事」というのも不思議なもので、日々のストレスの原因となる一方、それなりに出来上がるとけっこうストレス解消になったりして、(過労死とか)死ぬ原因にもなる一方で、「生きがい」にもなりえるというシロモノです。 「仕事」というステージから降りられれば話は簡単なんですが、大多数の人が生活の必要上、降りるわけにもいかないので、いろんな「仕事感」を持ちつつ働かざるをえない。では「仕事」とは何か? うーむ深い。「仕事しかない人生だった、そう思って死ぬのはごめんですね」「あたしは仕事したなーって思って死にたい」 この二つのセリフの間によこたわる大きく深い溝。 一見かみ合ってるようでかみ合ってないこの会話。「単なる金銭獲得の手段」と「自己実現の手段」の違いとでも言うんでしょうか。(「自己実現」というのもベタな表現だが・・・) 現時点での私の結論・・・。「仕事しかない人生だった、そう思って死ぬのはごめんですね」と言う人でも、じゃ「仕事以外の何か」があるわけで、そういうものも含めて「仕事」でいいんじゃないのかなー。 「良き生を送るのが仕事」みたいな(笑)。 金を稼ぐ作業は片手間でいいと思います。それが面白かったらそれはそれでいいんだし。 本読んで漫画読んで、いろいろ考えて、ブログを更新するのも、今の私のささやかな楽しい仕事だから。
2005.09.23
コメント(1)
-

非日常レストラン「Heaven?」佐々木倫子
Heaven? 1 ビッグコミックス著者/訳者名 : 佐々木 倫子 著 出版社名 : 小学館 (ISBN:4-09-187501-7) 発行年月 : 2004年12月 価格 : 530円(税込) <感想> 「緊張する瞬間」というのは、人が一皮むけるけっこう大事な体験のような気がしますが、日々の単調な生活の中で意外と出会うことはありません。 「仕事で緊張する瞬間」というのは確かにあるにしろ、あんまり体験したくないようなシロモノ。ではプライベートでは?と考えたときに、一番てっとり早いのは高級寿司屋かフレンチレストランに入ることのような気がします(笑)。 この「フレンチレストラン」というのは、けっこう不思議な場所で、「たかだか食事になぜ数万円払ったりするのか?」とか「なぜ異常に緊張するのか?」とか「高い金だす割にはメニューが理解できてないことが多い」とか「そのくせけっこう小さな町にもたいてい存在するのはなぜか?」などという疑問が次々出てきます。 それらの解答は、おそらくフレンチレストランの意義=「非日常空間の演出」といったあたりにありそうです。 つまりみんな「あえて」緊張しに行くわけです。当然、料理はおいしくなきゃならないわけですが、料理だけを楽しむわけでははく、その雰囲気を楽しみに行くところなのかもしれません。だから値段は高いし、メニューはよくわからんし、やたら格式ばったりしていると。 実は個人的に「フレンチレストラン進出計画」というのを練ってまして、地方→東京、庶民的→高級店という風に、食事をするフレンチの店を年々レベルアップさせていき、人生のクライマックスで東京一の高級レストランで食事をすると(笑)。おそらくそのころにはどんな高級店でも緊張しない肝っ玉と財布を持ってるはず(という目標)。 まあ個人的な目標はいいとして、この漫画は「非日常的な空間」であるフレンチレストランの「日常的な舞台裏」を描いた傑作です。 華やかなメニューの裏には厳密な原価計算があり、エスカレートするお客さまの要望はどこまで聞くべきか悩む。ライバル店ができれば偵察に行き、グルメ雑誌の取材に一喜一憂する・・・。 あたりまえの話なんですが、非日常空間を演出している店というのは、ごく普通の人達の努力によって支えられているわけで、そのギャップが楽しい漫画になっています。劇中ではレストランのスタッフがひとくせある人間ばっかなので、話はさらに面白い。 「動物のお医者さん」「おたんこナース」に続く職業モノなんですが、繊細なタッチと綿密な取材による抜群のストーリーセンスは、さすがは佐々木倫子って感じです。
2005.09.13
コメント(0)
-

漫画って良いなー「よつばと!」
よつばと! 1 電撃コミックス著者/訳者名 : あずま きよひこ 出版社名 : メディアワーク (ISBN:4-8402-2466-8) 発行年月 : 2003年08月 価格 : 630円(税込) <感想> 「良い漫画・悪い漫画」という区分けが存在するわけではないのですが、「あ~これは良い漫画だなー」という一作。 アマゾンのコミックランキングに入っていたので読んでみましたが、そんなに期待してなかったぶん、感動と衝撃が大きかったのです。 「こういう漫画もあるんだなー」と素直に驚いた作品。 もうすぐ夏休みという時期に、普通にありふれた町に引っ越してきたお父さんと娘よつば(6歳)、そしてそのお隣さんの物語。(タイトル「よつばと!」とは「よつばと一緒に・・・」の意味) 特段、なんの事件が起きるわけではありません。 普通の夏休みの日々。普通の子供の物語。でもこれが不思議と感動するんだな。 でも子供にとってみれば、夏休みに起きるすべてのことが事件であり、毎日がニュースみたいなもんでした。「自分にもいつの日にかあった物語」という感じで郷愁を誘います。 その反面、「あー自分もつまんない大人になっちゃたなー」と少し反省。 この漫画の雰囲気はどこかで出会ったナーと思ったら、日常の生活の中の「間」の面白い感じが、「究極超人あ~る」の頃のゆうきまさみの雰囲気に似た感じがしたのでした。 しかしこの漫画「月刊コミック電撃大王」というちょっとオタクちっく(?)な雑誌に連載しているものらしく、どの程度メジャーになれるのか不明ですが、老若男女を問わず、多くの人に読んでほしいなーと思う一作です。 ホント、文部省はこういうのを夏休みの推薦図書にしてほしいよ(しなくてもいいけど)。 ↑べつにHな漫画ではないよ(一応)。
2005.09.11
コメント(4)
-

期待と心配「PLUTO(プルートウ)」
PLUTO ビッグコミックス著者/訳者名 : 浦沢 直樹 画 手塚 治虫 原作 出版社名 : 小学館 (ISBN:4-09-187432-0) 発行年月 : 2005年04月 価格 : 550円(税込) 本の内容 人間の痕跡がない殺人事件、残された謎のメッセージ…その先にあるものとは!? 漫画界の2大巨匠がタッグを組んだ、近未来SFサスペンス!!巨匠・手塚治虫の代表作に、現代を代表するコミック作家・浦沢直樹が挑む! 『鉄腕アトム』の名作エピソード「地上最大のロボット」をモチーフにした話題作が、満を持して単行本化!!<感想> けっこう話題作だったんですが、やっと最近読みました。率直な感想は「うーむ、さすがは浦沢直樹」という感じ。 アトムというキャラを用いながら、手塚治虫とは全く異質の浦沢ワールドを作り上げています。 雰囲気は「MONSTER」に近く、伏線はりまくりの短編構成で、全体の謎解きをしていくという浦沢直樹お得意のパターンです。 「世界最強の7体のロボット」をそれぞれテーマにした話で構成されていく中で、「ノース2号」の話が秀逸。 かつて従軍した戦争を忘れるためにピアノを覚え始めたロボット「ノース2号」。ピアノの師である主人の危機を救うべく、あれほど忌み嫌っていた戦闘用ロボットとしての異形の姿に変身するシーンは涙を誘います。 その他、ロボットであるがゆえの悲しみ、戸惑い、悲劇を描いたドラマの数々は一つ一つが輝きを持っています。 是非ともこの漫画には「きちんと完結」してもらいたいもんです。・・・というのも、この作者、風呂敷を広げるのはうまいんですが、たたむのはどうも苦手のようで、「起承転結」が「起承転転転々・・・」となって収拾がつかなくなる事態が非常に多い。 「20世紀少年」とか「MONSTER」とか、正直途中で読むの挫折しました。これは作家にとってけっこう致命的だと思うんですが・・・。 この「PLUTO」はそんなに長い話にはならないと思うのですが、ちょっと心配。天国から手塚治虫も見てることだし、最後はピシッと締めてほしいもんです。
2005.08.29
コメント(4)
-

靖国イノセンス「ゴーマニズム靖国論」「靖国問題」
新ゴーマニズム宣言SPECIAL靖国論 著者/訳者名 : 小林よしのり/著 出版社名 : 幻冬舎 (ISBN:4-344-01023-X) 発行年月 : 2005年08月 価格 : 1,260円(税込) 靖国問題 ちくま新書 532著者/訳者名 : 高橋哲哉/著 出版社名 : 筑摩書房 (ISBN:4-480-06232-7) 発行年月 : 2005年04月 <感想> この種の問題は、それに関わる情報がたいてい強いバイアスがかかったものであることが多いため、正直考えるのがうっとうしくなります。 今年は戦後60年ということで、この2冊がだいぶ売れてるらしいとのこと。30代も半ばを迎えようとしている自分があんまり無知なのもどうかと思って読んでみました。 結果からいうと、「やっぱりそうか」という感じ。 何が「やはりそうか」というと、この2冊、左派と右派に真っ向から意見が対立してますが、双方、自身に都合の良い事実だけを抜粋して論陣をしくという形になっているため、やはり「公平な立場から」考えることができる内容になっていないのでした。 戦争という事実は無数の事件、事故、事実関係から成り立つものであり、「どこで何が起きたのか」という客観的事実を証明するのだけでも膨大な作業になります。 というか全ての事実を客観的に割り出すというのはほぼ不可能。まして戦死した軍人が皆何を考えていたか、送り出した遺族の本音なんてわかろうはずがありません。 今そこらへんの町で起きてる小さな交通事故だって、双方の事実が食い違ってたりして、客観的事実を明らかにするなんてことが難しいのに、国と国が何年にも渡って行った60年前の戦争とそれに参加した人達の全事実なんて、もはや霧の中。断片的な事実のカケラを集めて「おそらくこうだったはず」という複製を試みることができるに過ぎません。 要は、その復元の作業をする人の仕事や思想や思惑、その時代の流行、恣意的技術等によるわけで、こういう意見の食い違う本が共に存在するのもやむをえないという気はします。(小林よしのりは、自分が遺族でも何でもない、まして戦中派でもないのになぜあんなにテンションが高いかといえば、それが仕事だからなんだろうと思う) 作家も読者も結局はその人の思想(思想というのが大げさなら「センス」)によって、過去の事実を解釈してるわけで、時の政権により政治的には何らかの決着がついても、このての問題が実質解決するということはありえないでしょう。 ただ時代の流れで、その時々の「流行り」みたいなものは確実にあります。70年代の安保闘争以降はずっと、左派の意見がもてはやされました。日教組もあり、教科書の問題もあり、みんな自虐的史観をずーっと持ちつづけてきたのに、戦後50年たったら石原慎太郎や小林よしのりみたいのが登場して、右派の勢力が伸びたりする。 結局、双方の意見というのはいつの時代も存在したわけです。時代に乗ったもの勝ちという現実。 おそらく靖国問題をはじめ、戦後の色んな問題を、風化させながらも日本はずーっと引きずるのでしょう。で、その時代の趨勢で各論派の勢力図か変わると。 重要なのは後世への事実の伝達なのですが、時代のバイアスが強くかかりすぎると消滅したりする論派もいそうです。そういう意味で、対照的な2冊が共にベストセラーになったりする今の社会は、ある程度健全なのかなーという気はします。
2005.08.28
コメント(1)
-

花は、散る。「いま、会いにゆきます」
いま、会いにゆきます 監督 : 土井裕泰 主な出演者 : 竹内結子 、 中村獅童 、 武井証 <感想> 最近の日本映画にはファンタジー色の強い作品が多いですが、この映画もなかなか良いです。 信州ロケの美しい舞台で繰り広げられる、幻想的で、不思議で、素敵な物語。 人の死による単純なお涙ちょうだいものとは違って、「人の死」の向こう側にあるもの、死の裏側にある「生」の温かさを自然に感じられるドラマです。 観終わった後にじわじわ感動が来る感じかな。 「人は誰しも死ぬ」という絶対的な宿命の中で、いかに「出会う」か。そして「別れる」か。 人と出会い、家族と出会い、経験と出会い、そしていつかは別れる。そんな当たり前のような日々に、新しい輝きをもたらしてくれる映画でした。劇中「いま、会いにゆきます」の言葉の意味を知った瞬間が感動です。 この映画、竹内結子に注目が集まりそうですが、中村獅童がなかなか良い味を出しています。将来、味のあるいい役者になりそうな感じですね。 オレンジレンジの主題歌は正直「ちょっと会わないかなー」とも思うのですが、映画の内容に合わせてつくってあるので、歌詞は良いです。「花びらのように散っていくことこの世界で全て受け入れていこう君が僕に残したもの「今」という現実の宝物だから僕は精一杯生きて花になろう」みんな「花びらのように」散っていくのです。悲しいけど、それが「花」だから。
2005.08.25
コメント(2)
-

ニートと常人の間「「負けた」教の信者たち ニート・ひきこもり社会論」
「負けた」教の信者たち ニート・ひきこもり社会論 中公新書ラクレ 174著者/訳者名 : 斎藤環/著 出版社名 : 中央公論新社 (ISBN:4-12-150174-8) 発行年月 : 2005年04月 本の内容 増大するニート、高齢化するひきこもり―コミュニケーションの格差化傾向が進んでいる。ネット時代の少年犯罪など、メディアを騒がせた社会事象の本質を、気鋭の精神科医が読み解く。<感想> 「ニート」というものに興味があります。 「働かないで生きるには?」という命題は、恥ずかしながら昔から自分が持っていたものであり、ちょっと前に流行った「だめ連」の著作なんてけっこう読んだりしたものでした。(今にして思えば「だめ連」の人たちは実は全然ダメじゃなくて、左翼的文化活動みたいのを盛んにやっていたのですが) ところで、NEET(ニート、無業者、Not in Employment, Education or Training)とは、英国で社会問題になり労働政策の中で用いられた「職に就いておらず、学校等の教育機関に所属せず、就労に向けた活動をしていない15~34歳の未婚の者」を言うそうです。(なお、英国では”NEET”と言う単語は日本のように普及しなかったようで、英国の新聞記者が日本に来て初めて”NEET”と言う単語を知った、という話もあるらしい。) 日本では、厚生労働省の『平成16年版労働経済の分析』によると、就労対象人口の15-34歳の男女のうち2003年で52万人がニートであるとのこと。 しかしこの52万人(もっと多いとの説もあり)ってすごい数だよなー。大学入試センター試験の受験者数とほぼ同じなんだもの。 大学入ろうとしてる受験生の数だけ、働かないでぶらぶらしたりひきこもったりしてる若者がいるという事実。意外と自分の近所にもそれらしい人がいたりするので「けっこう身近な問題?」などと思うこともある今日この頃です。 「働かないで生きるには?」ってのはたぶん多くの人(というか全員?)が持ってるテーマかもしれませんが、結局はバランスの問題ですよね。 過労死するくらい働いちゃったりするのは論外として、そこそこのストレスというのは、人が生きてくうえで大事らしいです。 月曜から金曜まで働くから土日が楽しいんであって、毎日が日曜だったらたぶん苦痛でしょう。仕事と遊び、労働と休暇、収入と消費、節約と浪費といったバランスが大事なんであって、そのバランスを欠くと社会の歯車にかみ合えない事態になりそうです(実際そういう人が多いから問題なんだけど) しかし考えてみれば、社会の大多数の人はちゃんと仕事を持って、日々平和に、それこそバランス良く「社会にかみ合って」暮らしてるわけですよね? これってけっこうスゴイことだと思うのは私だけでしょうか?
2005.08.24
コメント(4)
-
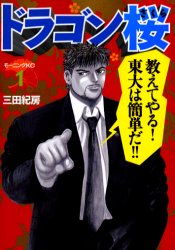
今なぜ東大?「ドラゴン桜」
ドラゴン桜 1 モーニングKC著者/訳者名 : 三田 紀房 出版社名 : 講談社 (ISBN:4-06-328909-5) 発行年月 : 2003年10月 <感想> 今、やたら売れまくっているマンガです。 コミックスは今9巻までありますが、amazonのベストセラーランキング(コミック部門)で9巻ともすべて20位以内に入っている(!)という快挙を成し遂げています。好調らしい阿部寛主演のドラマ効果? 内容は受験のハウツー物ともいえる「受験王道漫画」になってます。昔、小林よしのりが描いた「東大一直線」は受験のパロディでしたが、これはマジで東大を目指す劣等生を描いた漫画です。 以下、主人公の教師、桜木の台詞。「社会にはルールがある。そのルールは全て頭のいいやつが自分の都合のいいように作っている。逆に、都合の悪い事はわからないようにうまく隠している。ルールに従うやつでも賢いやつらはうまく利用するが、頭を使わない奴らは一生騙されて高い金払わされ続けている!」「賢いやつは騙されず、得して勝つ!バカは騙されて、損して負け続ける!負けたくなかったら勉強しろ!」「個性を生かして他人と違う人生送れるなんて間違いだ!社会はそういうシステムになっている。そういう世の中が気に入らないのならルールを作る側の人間になれ!騙されず生きていきたいのなら、勉強しろ。」 今は亡き「ナニワ金融道」の青木雄二がこれとまったく同じことを言ってました。実社会で職を転々とし、散々、辛苦を舐めた青木さんの言葉は実に重く、感動的でした。 そういうマインドを残した漫画としてこの「ドラゴン桜」は高く評価できます。 しかし「今なぜ東大なのか?」という疑問はやや残ります。「頭がいい=東大」というステレオタイプの図式に古さはないのか?まあこれは漫画だから「東大」というインパクトを使わざるをえないんでしょうけど。「早稲田、慶応、上智、一橋その他大学で何が悪いのか?」もっと言えば「大学に行かなくても頭の良い田中角栄(古い・・)みたいなタイプの人間じゃ悪いのか?」という疑問。 むしろ「東大卒」という肩書きとプレッシャーを背負って一生、生きる方がシンドイみたいな気もします。「踊る大捜査線」のキャリア警視同士にもそんな話がありました。東大卒の新城が、仕事でしくじった東北大卒の室井に対して「東北大でしたね・・・。良かった死ぬほど勉強して」とかいうシーンがあります。そんな会話絶対したくねー(できないケド)。 漫画解説に登場するライブドアの堀江社長はこう言います。「日本人はみんなブランド好き。だから大学もブランドを求める。そこに東大卒とそうでない人がいたら会社に採用されるのは東大卒」 ホントにそうなのかなー。ちと古くない?俺ァーどうも納得できんよ。
2005.08.11
コメント(6)
-

世界を創造する「スターウォーズ」
「スターウォーズ」とイマジネーションの世界<感想> 今さらスターウォーズのすごさを語ることはしませんが、 28年という時間と莫大な予算をかけて6本の映画を作ってしまったジョージルーカスは本当にすごく、製作者としてほんとに幸せな人だなーと思います。 一つの世界を描ききったという意味で、これだけのスケールで展開する映画はもう今後もあらわれないかもしれません。 世界中に作家、製作者、表現者、アーティスト等、イマジネーションを商売にしている人は数あれ、ジョージルーカスほど、そのイメージを完璧に映像化し、かつ興行的にも成功している人というのは、世界を探してもいないのではないでしょうか。 「なぜスターウォーズが成功したか」というのは、じっくり研究するに充分な価値がありそうですが、単純に羨ましい! なにが羨ましいかって、自分のイマジネーションを莫大な予算と優秀なスタッフをかけて映像化できるって素敵じゃないですか。 スターウォーズの設定資料みたいのを見てても、そのイメージの豊富さと斬新さ、デザインの良さには惚れ惚れします。 登場する様々なキャラクター、キャラの装い、いろんな星系のイメージ、戦闘機や武器、メカのデザイン、それらの中で縦横無尽に駆け巡るストーリー・・・。 小さいころは皆、SFみたいな世界を想像したものです。それをそのまま大人になっても持ちつづけ、かつそれを仕事にし、世界中の人達に観てもらうという贅沢さ。 「映画監督」という職業をこれまでそんなに意識したことはなかったのですが、「スターウォーズ」シリーズを観て、映画監督という仕事のすばらしさを再認識した次第です。 「世界の創造主」になりたいとは思いませんか?
2005.08.10
コメント(0)
-

仲間に入りたい「THE3名様」
THE3名様 1 ビッグスピリッツコミックススペシャル著者/訳者名 : 石原 まこちん 出版社名 : 小学館 (ISBN:4-09-186701-4) 発行年月 : 2001年03月<感想> この漫画は内容がスゴイ。 だって、「深夜のファミレスで延々とダベるフリーター3人」ってたったそれだけの話だから。 「昼寝て夕方起きて、深夜までバイトして、午前2時頃ファミレスに毎日集まってくるいつもの3人」が織り成す、クダラナイ話と時間つぶしの連続。 することなくて集まってくる3人だから、話の内容はけっして面白くはないんだけど、その様子がやたらと面白い。 いいよなーこういうの。学生だったらできるけど、まっとうな社会人になったらできないもんな。こんな生活。 「スピリッツ」でこの漫画を読んだとき「なんじゃコリャ?」って思ったけど、ハマっちゃってコミックスまで購入してしまいました(笑) 3人は空虚さを埋めようとして、いろんな話題とかゲームみたいのを持ちこんで、なんとか盛り上げようとするわけ。で、盛り上がる夜もあれば盛り上がらない夜もあると。その盛り上がり盛り下がり加減が面白い。 でもよく考えてみると、「空虚さを埋めようと頑張る」ってのはみんな普通に持ってる因子で、けっしてファミレスの3人だけのものじゃないんだよね。 会社や家庭や学校に行けば、みーんな単調な日々なわけで、その中でなんらかの盛り上げがないとやってられない。生活の「強度」という言い方もあるが。 ファミレスっていう超人工的な快適空間のなかで、日々の強度を求めて生きる3人と、超成熟した社会で目標とか生きがいをやたらと探したがる現代人を重ね合わせるのは考えすぎ? って、やっぱ考えすぎだな(笑)
2005.08.06
コメント(0)
-

心の原点「NANA」「のだめカンタービレ」
<雑感> 「売れてる漫画はやっぱり面白い」というわけで、読んでみたこの二つの漫画。やっぱり「こりゃ久々に面白い漫画だなー」と思わせるに充分な内容なのでした。 ところで「なぜみんな漫画を読むか?」などということを考えてみたりするのですが、「面白いから」という答えの向こうには、やはりいろいろな感情があると思います。 自分の理想像を見出したり、感情を共有したり、その世界感に酔ったり・・・。自分の好きな漫画に対するそういう感情を分析していくと、「今なぜその漫画が好きなのか」という話から、「自分が求めているもの(テーマ)」がなんとなくわかってくるような気がします。 「NANA」「のだめカンタービレ」に共通して思ったのは、「若い時代の温かな共同体」ってやっぱ良いなーということ。 当然それだけの漫画じゃないんだけど、個人的にはテーマはそれでした。 「NANA」ではバンド、「のだめ」ではオーケストラという仲間があって(正確には主人公は属していないのだが)、そこに共同体があって、ちゃんとした目標に向かって頑張る、ときに悩む、ときに誰かの部屋に集まって飯食ってバカ話もする・・・みたいな。 ここでいう「共同体」というのは「組織に属する」ということじゃなくて、「気持ちの問題」。 まあサークルでも部活でもゼミでも何の中でもいいんですが、そういう既成の組織の中でも、特に仲の良いメンバーで作る「擬似家族」みたいなもののことです。 それは実際かつて自分も経験したものなので、懐かしい気持ちがすごく強いのと、改めてそういう時代の大切さ、価値を思ったりしたのでした。「自分の生まれ育った家庭」→「就職」→「結婚」→「自分が作る家庭」というパターンの人生の中で自分が果たすポジション・役割・責任というのは、ある程度決まっています。 でも「若い時代の温かな共同体」の時代には役割も責任も最初はありません。まさに「素の自分達」が出会う場です。その中でだんだんと自分のポジションが見えてくる。 30代の今にして思えば、「心の原点」はそういう時代にあるような気がしてなりません。 いずれ皆、大人になって、いろんなしがらみや責任が出てくるわけですが、「心の原点」がある人は寂しくならないと思うわけです。 「NANA」「のだめカンタービレ」を読んでそんなことをふと考えてしまったのでした。
2005.08.05
コメント(0)
-

「機動警察パトレイバー」は「携帯電話」の夢を見るか?
機動警察パトレイバー<雑感> 「機動警察パトレイバー」について調べてみると、週刊少年サンデーでの連載期間は1988年~1994年。ストーリーの舞台は1998年からの数年間であったことがわかります。 つまり今となっては過去となりましたが、80年代に想像した「10年後の未来像」がそこに描かれているわけです。 「OSによるレイバーの制御」とか「東京湾全体を干拓と埋め立てで土地に変える国家的な巨大土木事業「バビロンプロジェクト」」など、リアルな近未来感があふれた作品でした。 現在は2005年。そう考えるとパトレイバーの連載を読んでた時代からはかなり遠くまで来てしまいました(もう少しで連載開始から20年だもんな・・・)。 ロボット工学はかなり進展したとはいえ、今のところレイバーなるものは存在していません。しかし「事実は小説より奇なり」というか、現実が想像を追い越したというか、「携帯電話の登場」はさすがの「パトレイバー」も想像していなかったのでした。 これまた調べてみると、パトレイバーの連載終了が1994年、携帯電話の「端末売り切り制導入と他社参入」によって、契約台数が爆発的に増加したのがやはり94年と、くしくも原作の終了と携帯の普及が同時期であったことがわかります。 もしパトレイバーに携帯電話が登場していたら・・・と思うと想像が膨らみます(「シャフト襲撃による特車2課孤立」の話もだいぶ違った展開だったはず)。 「パトレイバー」ですら想像しえなかった今の携帯電話はホントすごくなりました。インターネット通信機能、写真撮影機能の充実もさることながら、テレビ電話や「ドラクエ」等のゲーム、動画(ムービー撮影)、GPSナビ、電子マネーなど、機能の拡張には際限がありません。 「ケータイ」などと普通の単語になってる今ですが、もはや「携帯電話」というより「携帯情報端末」とでも言うべきシロモノです。これを日本国民のほとんどが一人一台持つ時代など一体誰が想像しえたでしょう。 自分が子供の頃にそんな話を聞いたら「まるでマンガかアニメの話」。到底信じられる話じゃありませんでした。 普通にみんな持ってる「ケータイ」に、「未来がここまで来たか!」と感動と驚愕を覚える自分がいます。 今、私の携帯は「talby(タルビー)」(コレ↑)の緑です。「talby」は「au design project」の第3弾モデルとなる三洋製CDMA2000 1x端末。未来っぽいデザインと機能美が気に入ってます。 「パトレイバー」にもし携帯が登場していたら、こんなデザインだったかも・・・などと勝手に想像している今日この頃です。
2005.07.24
コメント(4)
全95件 (95件中 1-50件目)
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- 税金・地方交付税から行政法まで!国…
- (2025-11-19 09:04:40)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月5日分)
- (2025-11-19 00:45:45)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 薬屋のひとりごと 9 日向夏
- (2025-11-19 15:40:42)
-








