全188件 (188件中 1-50件目)
-
ご無沙汰しておりました・・・生きていましたよ
生きていましたよ。 突然の中止・・・(いや中断のつもりでしたが)から早1年半。 先日久しぶりに懐かしもうと思いこのブログを見たところ・・・ゲゲッ。 中断したのが2011年3月1日とは・・・。 そんなつもりはなかったのですが、これでは東日本大震災により何らかの影響で中断・・・もしかして死んだ?のでは・・・と思われても仕方がない状況。 確かにこの地域は震度6弱で(最大余震も同様の震度6弱)被災したことに変わりはありませんが無事に生きており、仕事も何とかしてきました。 そのとき3日くらいは電気水道共に止まり夜は極寒で漆黒の闇の中・・・思い出すだけでも辛い日々ではありましたが、それは自分たちが置かれている立場があまりにも幸運だったことを電気が通ったときにそう思いました。 3月14日朝方の4時過ぎに電気が復旧したとき突然TVに映されていた映像があの大津波の悲惨な光景。 私は絶句してしばらくは茫然自失。 何日か前に行った陸前高田や大船渡があんな姿になろうとは・・・。 それから2~3日後、ガソリンの供給もままならない中で行列する無駄な時間を費やすこともなく地理上の好条件もあり、郵便局の年金相談会は予定通りこなし、その週末の年金事務所の相談員は朝タクシーで帰りは約1時間徒歩で何とかこなしました。 このときの徒歩で何十年振りかで花粉症にかかってしまいました。 それから6月以降は労働局の仕事で近くの労働基準監督署で勤務するようになりました。 震災の影響による一時的な採用でしたが、今年度は総合労働相談員として月7日ですが継続して採用され何とか生き延びております。 こんなブログを見ていただいている方は少ないと思いますが、それでももしかして心配されている方がいたとしたら大変申し訳ございませんでした。 私は何とか生きています。シブトイです。今後ともよろしくお願いします。 でも更新するのに少し勇気が要りました。
September 25, 2012
コメント(0)
-
ねんきんネット
日本年金機構は、2月28日から新サービスとして登録すればいつでもご自分の年金記録等(ねんきん定期便の最新情報)が確認できる「ねんきんネット」のサービスを開始しました。 初めてご利用される方は、初回にご自分の情報を登録すると約5日くらいでIDが郵送されご利用ができるようになります。 開始早々、システムトラブル?でログインせずアクセスしにくい状況となったことや一部の不具合に対応するため昨夜一時停止してメンテナンスを行い現在は問題なくご利用できる状態となっているようです。 私も先程、登録を行いました。 「ねんきんネット」のご利用について(PDF) ⇒ こちらから 日本年金機構HP ⇒ ねんきんネットサービス
March 1, 2011
コメント(0)
-
平成22年度能力開発基本調査結果の概要
厚生労働省が平成18年度から毎年度実施している能力開発基本調査は、今回で5回目となります。 これは企業や事業所で行われている従業員への能力開発方針や取組み状況などを把握して今後の職業能力開発合成に活用することを目的とするものです。 その調査結果の概要が発表されました。 調査項目として大きく分けると 1.企業での従業員に対する能力開発の方針 2.事業所での教育訓練の実施状況 3.従業員個人による教育訓練受講状況 となっており、結果としてはOFF-JTを重視する事業所、実際に実施した企業の比率は前回よりも減少しており、又、自己啓発支援なども減少傾向にあるようです。 又、従業員個人による教育訓練は、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」や「費用がかかりすぎる」の割合が高いようです。 厚生労働省HPによる詳細 ⇒ こちらから
February 23, 2011
コメント(0)
-
平成23年3月分からの健康保険料率について
全国健康保険協会(協会けんぽ)によると平成23年3月分から適用になる健康保険料率は、すべての都道府県が引上げになります。 都道府県別では、岩手県他3県が最低0.13%の引上げとなっており、最高では佐賀県と大分県0.19%、平均0.16%の大幅な引上げとなりました。 詳細と都道府県別保険料額表については ⇒ こちらから 因みに平成23年度の雇用保険料率は、昨年度の保険料率を据え置くことが既に決定しております。 平成23年度の雇用保険料率を告示 ⇒ こちらから
February 15, 2011
コメント(0)
-
平成23年度の年金額引下げ
先般(1月28日)に総務省より平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨の発表を受け、厚生労働省は平成23年度の年金額を0.4%引下げることを発表しました。 現在支給されている年金は、直近の年金額引下げの年(平成17年の物価基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額を改定することとしており、平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことで改定されます。 又、平成23年度の国民年金保険料額は15,020円(月額)となり、平成22年度から80円の引下げになります。 詳細についてはこちらから ↓ 厚生労働省報道発表資料
February 7, 2011
コメント(0)
-
平成23年度雇用保険法改正の法案要綱
先日、厚生労働省は「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」を元に同法律案要綱を労働政策審議会に諮問し、この度「妥当」との答申を得たとの発表がありました。 今回の改正内容は主に「失業等給付の充実」、「失業等給付に係る雇用保険料率」、「失業等給付に係る国庫負担」の3点についてまとめられています1.失業等給付の充実(1)賃金日額の引上げ 失業者に対する「基本手当」の算出基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布等をもとに法定の下限額等を引上げ(2)安定した再就職へのインセンティブ強化 ア 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」について、給付率の更なる引上げ ・給付日数を1/3以上残して就職した場合:給付率30%→40%(現在暫定措置)→50%(恒久化(改正後)) ・給付日数を2/3以上残して就職した場合:給付率30%→50%( 同 上 )→60%( 同 上 ) イ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「乗用就職支度手当」について、給付率の暫定的な引上げ(30%→40%)の恒久化2.保険料の改定(労働保険徴収法) 失業等給付に係る法定の保険料率を「1.6%」から「1.4%」に引下げ※平成23年度の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.2%」と酷似で規定予定 ※平成24年以降の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.0%」とすることが可能3.国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、出来るだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。施行日:平成23年8月1日(2は平成24年4月1日、3は公布日) 厚生労働省報道発表 ⇒ こちらから
February 3, 2011
コメント(0)
-
次世代育成支援対策取組状況
以前も取り上げましたが、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)が改正されて、これまでは従業員301人以上の規模の事業主に策定・届出義務がありました「一般事業主行動計画」が平成23年4月以降は、101人以上の規模の中小事業主にも策定・届出が生じます。 届出義務が生じる期限まであと約2ヵ月と迫ってきましたが、届出状況は非常に低い届出率となっているのが現状のようです。 これまで届出義務のある301人以上の企業の届出率93.6%に対し、今回届出が義務化される101人以上規模の届出率は何と15.2%と低調の状況にあります。 我が県では、我々委託を受けている社労士の活動の成果も多少あり、42.5%という状況で全国的には高水準の方ですが、逆に言うとまだ半分以下ということになります。 これから2ヵ月間(実質1ヶ月間の活動に制限されますが)でラストスパートですが、最後まで諦めないで活動するつもりです。 ⇒ 厚生労働省「次世代育成支援対策取組状況」
January 28, 2011
コメント(0)
-
適格退職年金の移行手続きはお済みですか?
企業が退職金制度などで、金融機関を通じて年金資産を積み立てるしくみの一つに税制適格退職年金制度がありますが、これは法人税法の規定によって平成24年3月末での廃止が既に決定しているところです。 税制適格年金は、事業主の掛金を損金算入できるという点で税制での優遇措置により比較的規模の大きい中小企業から大企業に至るところで広く利用されておりましたが、反面受給権の保護という従業員の老後の所得保障の面においてやや脆弱な部分を併せ持っていた制度であることから、廃止されることが決定しており、代わりに厚生年金基金、確定給付型企業年金、確定拠出年金、中退共などに移行することを勧めているところです。 しかし、その期限もいよいよあと1年2ヶ月となってきました。 これから移行に関して準備を始める企業の方は、制度設計、労使合意、行政の認可・承認などを経なければなりませんから時間的な猶予はありませんので、すぐにでも取り掛らなければ間に合わなくなります。 厚生労働省のホームページ ⇒ こちらから
January 25, 2011
コメント(0)
-
平成23年4月以降の出産育児一時金制度
平成21年10月1日より、医療保険各法に基づく出産育児一時金等の支給額および支払方法が変わりました。 しかし、支払方法において直接支払制度に対応していない医療機関などは当初平成21年度に限り適用猶予されましたが、これが1年間延長されて平成23年3月31日までとなっておりました。 この度(12日)、厚生労働省は「重要なお知らせ」として出産育児一時金についてお知らせしています。 これによると ・出産育児一時金の支給額は引き続き42万円とする ・直接支払制度の改善や小規模施設等における「受取代理」を制度化 などの改善が図られます。 詳しくは ⇒ こちらから
January 18, 2011
コメント(0)
-
事業仕分けで廃止となったジョブ・カード制度は継続されます!
昨年10月に実施された行政刷新会議による事業仕分け第3弾前半では、ジョブ・カード制度の関連事業である「ジョブ・カード制度普及促進事業」及び「キャリア形成促進助成金(ジョブ・カード制度関連)」が事業廃止との評価結果が示されました。 これを踏まえ、ジョブ・カード制度の関連事業については、現行の手法による事業は廃止し、見直しを行った上で、新たな別の枠組みへ移行するなどとし、平成23年度以降も、引き続き「ジョブ・カード制度」を推進されるようです。 党内決定事項は党内でまとまらない・・・とても違和感がありますが、求職者には少しでも何らかの支援があった方がよいとは思いますが、この事業仕分けで「ジョブ・カード制度」を知った方も多いと思います。 まずは、普及に努めるべきです。 そして、効果があるものなのかを検証すべきと思います。 制度あれど利用者なしでは・・・・。 ⇒ 厚生労働省「ジョブ・カード制度」のご案内
January 11, 2011
コメント(0)
-
2011年 仕事始め
あけましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 早いもので今年で開業3年目を迎えることとなります。 そして個人事業主なので1月より第3期となるわけですが、2月の確定申告まではすぐですが、日頃からコマ目に記帳等を行っているので大して苦になりません。 今年の目標は絵馬に書き入れました。 何とかまずは食えるようにならなければ・・・と焦る気持ちもありますが、こればかりは。 昨日は、仕事始めでしたが、私は昨年同様、年金事務所での相談員を行ってきました。 昨年は、日本年金機構のスタートの日だったことから冷やかし半分、叱咤激励するおせっかい?なお客もおり、正月から罵声を浴びせる客(こうなるとお客様なんて言えない)もいたため、朝行くのがとても嫌でしたが仕方がありません。 事務所に着くと受付時間約15分前だというのにもう3人おりました。 しかし、何とかこなして平穏無事に終了しました。 さて、年金と言えば昨年の年末近くに企業年金(厚生年金基金)における年金支払い未請求者状況の発表がありましたが、未請求者数が約14万3千人おり、年金額累計では1,008億円になっているそうです。 若い頃、短期間勤務していた会社で厚生年金基金に加入していたことを知らなかったり、忘れていたり、加入員証を失くしてしまいは問い合わせもせず諦めてしまうことで未請求になっている方も多いと思います。 又、本来ならば基金の方から連絡するはず・・・請求主義なんておかしい?といつまでも自己中心的に物事を捉えている方もおりますが、住所が変わったり、結婚などで名字が変わっている場合もあります。 年金は老後働けなくなったときの所得保障なのですから、自分のものは自分で守りましょう。 因みに私は年金事務所での相談員のときは、窓口装置を使用して、年金手続きのお客様には企業年金に加入歴を確認してご案内しています。 ⇒ 厚生年金基金における年金支払い未請求者状況まとめ
January 5, 2011
コメント(0)
-
残業月200時間まで可能とした労使協定!
既に報道されている東証一部上場の建設会社の千葉事業所に勤務する男性が自殺し、労災認定を受けていた事件についてですが何とも常識では考えられないことが実際に起きていることがとても悲しいのであります。 景気低迷によって非正規社員が増加し、それにより労働時間の長短2極化が進展する中でこのような悲惨なことが起きています。 法定時間を超えて時間外労働させる場合、又は、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結して、行政官庁(労働基準監督署長)に届出が必要となります。 法定労働時間とは a.週40時間(特例あり)、b.1日8時間以内というa,bの2段階のしばりがあります。法定休日とは週に1日の休日(4週4休の場合を除く)です。 これは労働基準法第36条に規定されていることから通称「サブロク協定」と呼ばれています。(常識中の常識ですが) しかし、このサブロク協定があれば無制限で残業を命じられるかというと・・・まず労働者は当然のことながら機械ではなく人間です。 人間は働き過ぎると過労となり、病気となってしまうことは誰でも知っていることですが、実態として長時間労働を強いられている人がいるということで以前は労働大臣が定める時間外労働時間の目安時間というものがありましたが、現在は厚生労働省の告示として一定の限度時間の基準として定められています。(ここでは労働時間の延長ができる時間を更に延長できる「特別条項付きの労使協定」のことは割愛させて貰います) しかし、この基準にも例外があり適用除外になる業務があります。 1.工作物の建設等の事業 2.自動車の運転の業務 3.新技術、新商品等の研究開発の業務 4.厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)(具体的な指定事業又は業務は、労働基準監督署にお問い合わせください。) 今回は、1の建設の事業ということで適用除外であるとして、何と時間外労働を月200時間までできるとした労使協定を労働組合との間で締結したとのこと。 小さな会社ならいざ知れず、東証一部上場で労働組合との協定がこのような常識を著しく欠いた内容は考えられないものです。 会社も会社なら労働組合も全く機能していないと言っていいでしょう。 2.の自動車の運転などは拘束時間で一定のしばりがあり長時間労働を抑えようとする狙いがありますが、医療現場などはどうでしょうか? 医師不足で勤務医師などは、時間外労働の規制などは一切ないのですから・・・。 その病院で先日、岩手の県立病院で何とサブロク協定を22年間締結しないで時間外労働をさせていたことが明るみにされました。 これはもう何というか・・・お話しになりませんね。
December 20, 2010
コメント(0)
-
平成22年労働組合基礎調査
厚生労働省は、14日平成22年労働組合基礎調査を発表しました。 この調査は、労働組合及び労働組合員の産業、企業規模、加盟上部組合別の分布等、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的に、昭和22年以降毎年実施しているものです。 概要として 1.労働組合員数は、前年から約2万4千人減少(10,053,624人) 2.推定組織率 18.5%(前年と変わらず) 3.女性の組合員が5年連続で増加 4.パートタイム労働者の組合員数が増加(全体の7.3%) パートの推定組織率が5.6%で過去最高。 詳細は ⇒ こちらから
December 15, 2010
コメント(0)
-
次世代法と「両立支援のひろば」について
私は、現在次世代法(次世代育成支援対策推進法)による一般事業主行動計画策定支援のコンサルタントをしておりますが、次世代法の改正によって来年4月より策定届出が義務化される企業規模が101人以上(改正前は301人以上)と拡大されることになりましたが、いよいよあと約3ヶ月と迫ってきました。 次世代法の改正、一般事業主行動計画の概要については ⇒ こちらから 本来ならば自社の現状把握、社員のニーズ等を調査の上、自社の実情に合った行動計画として目標を決めて活動していただきたいのですが、どうしていいかわからないということで策定が進んでいない会社担当者の方もいるかと思われます。 そこで他社の取組事例を紹介しているサイトがありますので、是非ご利用下さい。 又、就活されている方にも希望する会社が公表されているか・・・どのような取組みをしているのか?・・・参考になるかも知れません。 ⇒ 両立支援のひろば
December 10, 2010
コメント(0)
-
雇用調整助成金の生産量要件緩和
厚生労働省は、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の生産量要件を緩和します。 対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日の間にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。 ?円高の影響により生産量等の回復が遅れていること ?最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少 ?直近の決算等の経常損益が赤字 詳しくは、こちらから
December 7, 2010
コメント(0)
-
年末に向けた中小企業金融対策について
経済産業省は、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」(平成22年10月8日閣議決定)を受け、具体的な施策を発表しました。 これによると中小企業庁では、資金需要が高まる年末に向けて、総額15兆円規模の資金繰り支援策を実施するための平成22年度補正予算(5653億円)が成立したことを踏まえ、以下の施策を実施することとしました。 1.借換え・条件変更の推進 2.既存の資金繰り対策の積極的な利用(新規資金ニーズへの対応) 3.金融機関に対する中小企業金融の円滑化に向けた配慮要請 4.相談窓口の拡充 5.全国各地での意見交換の実施 詳しくは、こちらから
December 6, 2010
コメント(0)
-
第4回「イクメンの星」を選定
厚生労働省では、育児を積極的にする男性「イクメン」(2010年流行語大賞にも選ばれました)を広めるため、今年の6月より「イクメンプロジェクト」なるものをスタートさせました。 そして今般「イクメンプロジェクト」において、公式サイトで「イクメン宣言」をし、「育児休業・育児体験談」を投稿した方の中から、第4回「イクメンの星」が選ばれました。 厚生労働省 第4回「イクメンの星」を選定 ⇒ こちらから
December 2, 2010
コメント(0)
-
「雇用・能力開発機構」は来年4月で廃止へ
衆議院の厚生労働委員会は、独立行政法人「雇用・能力開発機構」を廃止する法案について、与党、自民・公明両党の賛成多数により可決しました(共産、社民両党は反対)。 これにより来年の2011年4月に廃止となる予定で、業務は厚生労働省所管の他の独立行政法人に移管される見通しです。 雇用・能力開発機構とは、雇用保険法で定められている雇用保険二事業を主に行われており、「能力開発に関する業務」、「雇用開発に関する業務」や「勤労者財産形成促進に関する業務」などを行っております。 以前は、雇用保険三事業として雇用福祉事業がありましたが、平成19年の法改正で廃止されました。 この雇用福祉事業には、皆さんもご存知の「雇用促進住宅」などが含まれていました。(平成33年度までに地方公共団体や民間等への譲渡等を完了させることとされた。) 実は、平成20年まだ自民党政権下に、厚生労働省では「雇用・能力開発機構のあり方検討会」、行政改革推進本部では「行政減量・効率化有識者会議」において検討され、当時の厚生労働大臣の舛添大臣と甘利行革担当大臣が、機構を廃止して職業訓練業務を高齢・障害雇用支援機構や都道府県に移管することに合意していました。 このときに「私のしごと館」の廃止・売却にも合意していました。(2010年3月31日に廃止、売却はまだ) 独立行政法人「雇用・能力開発機構」のHP ⇒ こちらから
November 25, 2010
コメント(0)
-
平成22年度「労働時間相談ダイヤル」の相談結果
少し古い情報ですが、11月6日(土)に各都道府県労働局で一斉に行った「労働時間相談ダイヤル」の相談結果が厚生労働省のHPで公表されています。 これは、長時間労働やこれに伴う問題の解消を促す「労働時間適正化キャンペーン」(毎年11月に実施)の一環として行われているものです。 平成22年度の相談件数 787件(昨年度比 114件の減)(主な相談内容) 賃金不払残業 438件(昨年度比 42件の減) 長時間労働 247件(昨年度比 35件の減) そのうちの賃金不払い残業に関しては昨年度より114件も減少しているとは言え、全体の56%を占めています。 この内、本人が勝手にしている生活残業(これを黙認していれば会社側の責任)はどれくらいあるかはわかりませんが、依然高水準で推移しています。 上記賃金不払残業の438件中、194件が残業手当が一切支払われていないというかまさに「驚愕の事実」です。 大概このような会社の経営者は、十分な給料を支払っているから文句はでないだろう・・・と本気で思っているか?又は、違法と知っていて文句ある奴は辞めてもらって結構・・・今辞めてもこの不況下、どこも行くところがないから・・・」とタカをくくっているのでしょう。 このような経営者はこれまでも何とか逃れてきたので、大丈夫・・・と、これからも安心と思っている方も多いかと思われます。 とかく日本人は、「事なかれ主義」なので・・・。これ以上は言いません。もし、「やばいなぁ」と思っていたのなら、即刻是正しましょう。 平成22年度「労働時間相談ダイヤル」の相談結果 ⇒ こちらから
November 22, 2010
コメント(0)
-
下請取引適正化推進月間
今月は、下請取引適正化推進月間です。 下請取引の適正化を一層推進するため、親事業者の下請取引担当者を対象に下請取引適正化推進講習会を開催し、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底することになっております。 下請法とは 下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための法律です。 つまり親事業者が優越的な立場を利用して下請事業者に対する不公正な取引を強いることがあるため、弱者である下請企業の保護が目的でつくられた法律です。 もともと独占禁止法で規制されていたものですが、経済的弱者である下請企業には即効性がない独占禁止法では保護が困難であるため、下請法として分離独立したものです。 中小企業庁は15日に親事業者代表取締役(34,583社)及び関係事業者団体代表者(651団体)あてに「下請取引の適正化及び下請事業者への配慮等に係る通達」を発出しました。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2010/101115ShitaukeConsiderationTsuutatsu.htmhttp://www.meti.go.jp/press/20101115005/20101115005.htmlhttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/10.november/10111501.pdf実際の相談窓口については以下です。 下請かけこみ寺 ⇒ こちらから
November 16, 2010
コメント(0)
-
平成22年分年末調整
今年も年末調整の時期がやってきました。 国税庁では年末調整についてわかりやすく解説をするサイトを準備しました。 そのサイトは「平成22年分年末調整がよくわかるページ」という名称です。 内容は動画で「年末調整のしかた」や「法定調書の作成と提出」が見ることができます。 又、冊子も見ることができますし、各種申請書様式もダウンロードが可能です。 年末調整に関するQ&Aもあります。 総務・経理部門の担当者の方は必見?それ以外でも新たに社会人になった方への教育にも使用できると思います。「平成22年分年末調整がよくわかるページ」⇒ こちらから
November 8, 2010
コメント(0)
-
第42回(平成22年度)社会保険労務士試験合格発表について
本日、11月5日は第42回(平成22年度)社会保険労務士試験合格発表日です。 又、正答の発表も同時に行われます。 本年の試験日は、8月22日に実施されました。 それから約2ヶ月半という時間が経過しましたが、毎年この時期に合格発表が行われます。 それにしても何故この時代にこれだけの時間がかかるのか全く理解に苦しむのは私だけではないでしょうが、私も受験生時代にはこの合格発表日がとても長く遠い感じがしました。 合格発表の概要は 19都道府県32会場で行われ申込数70,648人に対して実際に受験したのは55,445人。 合格者数 4,790人 合格率は8.6%(前年7.6%)でした。 私の地域は宮城会場でしたので受験者数2,249人、合格者が170人、合格率が7.6%と全国平均より1%低い結果となっています。 合格基準に関しては 選択式が総得点23点以上1科目3点以上 但し、健康保険法、厚生年金保険法及び社会保険に関する一般常識は2点以上、国民年金法に至っては1点以上という救済措置がありました。 1点救済の問題・・・?。問題自体がもんだい? 選択式の救済措置によりその分択一式は総得点48点以上、救済措置なしとやや厳しい基準となりました。 社会保険労務士試験オフィシャルサイト ⇒ こちらから
November 5, 2010
コメント(0)
-
第3回「イクメンの星」を選定
厚生労働省では、育児を積極的にする男性「イクメン」を広めるため、今年の6月より「イクメンプロジェクト」なるものをスタートさせました。 そして今般「イクメンプロジェクト」において、公式サイトで「イクメン宣言」をし、「育児休業・育児体験談」を投稿した方の中から、第3回「イクメンの星」が選ばれました。 厚生労働省 第3回「イクメンの星」を選定 ⇒ こちらから
November 1, 2010
コメント(0)
-
モデル行動計画
いやぁ~昨日取り上げた「ねんきんネット」ばかりではなくまさかの「ねんきん定期便」も事業仕分けの対象となってしまいました。 長妻前厚生労働大臣の肝いり事業にメスが入れられました。 でも驚いたのは、枝野さんのねんきん定期便でのコメント「何だこれ・・・で即ゴミ箱行きでしょう」と言ってから少し言い過ぎたと思ったのか「少なくともウチはそうだ」と言った。 これは年金に興味がないと言っているようなもの。 せっかく国民が年金に興味をもつようになったのに・・・。 まぁ、議員年金をいっぱい貰える人には定期便などは、なくてもよいのでしょうね。 さて、少子化対策の改正された次世代育成支援対策推進法で一般事業主行動計画策定・届出が義務付けられる範囲が拡大されたことは先日も本ブログで紹介したところですが、東京労働局よりモデル行動計画をウエブで入手できるようです。 9つのモデルがありますのでこれから自社の策定・届出を考えている企業担当者は参考にしてみて下さい。 モデル行動計画 ⇒ こちらから
October 29, 2010
コメント(0)
-
ねんきんネット(仮称)について
昨日取り上げた「ジョブカード制度」は事業仕分けで廃止にされてしまいました。 今日の事業仕分けは「年金」が含まれているそうですので今日は年金についての情報です。 でも事業仕分けの対象のものではないと思います。 日本年金機構は22日の総務省・年金業務監視委員会で、来年2月から稼働する「ねんきんネット」(仮称)の概要を明らかにしました。来春に発送する「ねんきん定期便」の中に個人用の番号を案内するようです。 この個人識別番号を基礎年金番号などと一緒にパソコンに入力すれば、ウェブ上で自分の年金情報が確認できるようになるそうです。 未納状態になっている月が目立つ色で表示されるため、納付確認等の年金記録の確認や訂正などに役立つということです。 現在においてもインターネットを通して各自の年金の加入状況等の年金記録の照会は可能ですが、利用するためのID番号の取得に2週間程度かかることからあまり利用されていないようです。 しかし、利用できるのはインターネットを利用できる環境又はパソコンができる人に限定されてしまうわけですから・・・片手落ちなのか? 今回のこのシステムでは、それらの人たちに年金事務所や郵便局、市町村の窓口で利用することになります。(来年2月ごろに開設予定) 市町村の窓口で対応可能でしょうか?疑問です。 ねんきんネット(仮称)の構築 ⇒ こちらから ねんきんネット(仮称)の画面構成等 ⇒ こちらから
October 28, 2010
コメント(0)
-
事業仕分けで話題となっているジョブカード制度とは
本日の事業仕分けで対象となっているジョブカード制度についてご存知でしたか? おそらく知らない人の方が圧倒的に多いのではないかと思います。 PR不足なのか、ただ単に厚労省の自己満足なのかいずれにせよあまり活用されていないのが実態です。 ジョブカード制度とは、正社員経験の少ない人を対象として、対象者の職務経歴や学習歴、職業訓練の経験、免許・資格などを「ジョブ・カード」と呼ばれる書類にとりまとめ、企業における実習と教育訓練機関における学習を組み合わせた職業訓練の受けることにより、その後の就職活動やキャリア形成に活用する制度です。(ウィキペディアより引用) ジョブカードは6つの書類によって構成されています。 (1)総括表 (2)職務経歴 (3)学習歴・訓練歴 (4)免許・資格 (5)キャリアシート (6)職業能力証明 表現の仕方が適切ではありませんが、自己の売り込みのためのカタログといったところでしょうか? このジョブカードの作成には、ハローワークやジョブカフェなどで面談を行いながら、現状の能力や課題などを整理して、目標を決め、教育プログラムによって能力の向上を図りプログラム修了後に職業能力証明書を教育機関(企業・学校)が発行し、再びハローワーク・ジョブカフェなどで、キャリアコンサルタントとの面談を行いながら職業選択を行います。 そのジョブカードを就職活動に活用します。 ジョブカード制度について詳しくは ⇒ こちらから
October 27, 2010
コメント(0)
-
未払い残業代1221社に是正指導
厚生労働省が21日発表した「賃金未払残業(サービス残業)是正の結果まとめ」によると、2009年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の未払い残業代を支払った企業数は1221社、割増賃金の合計額は116億298万円。 1社当たり平均支払い額は950万円、労働者1人当たりの平均額は10万円だったそうです。 関連リンク ⇒ こちらから 本当に信じられないかも知れませんが、中小零細企業には何を基に賃金を支払えばよいのか分からない事業主が現実にいるということ。 「うちはよそと比べてもそんなに遜色ない給料を支払っているはずだ」とおっしゃる事業主さん。 こういう事業主さんに次の質問をすると明確に答えられない方が多いのです。 労働時間は多い方ですか?残業時間は?何時間ですか? 多いか?少ない方か?なら答えられるのですが、何時間ですか?と訊いてもちろん即答はできないことはわかりますが、その労働時間を把握していない会社が結構あります。 こういうところは、地域の同業種の賃金相場と比較して言っているのでしょうが、賃金を算出する根拠となる肝心の労働時間を把握していないようです。 タイムカードはあるが、形式だけ。賃金台帳には労働時間が記載されていない。記載していないだけだったらまだ話はわかるが、集計すらしていない。つまり、賃金の計算の基礎となるはずの労働時間は無視されているケースが結構あります。 基本給20万円、営業手当 3万円、家族手当 1万円、通勤手当 1万円 総支給額 25万円 「うちのような中小零細でこのくらい払う所なんてない筈だ。文句あるか・・・あるなら他所へ行け」ってな具合。 休みは日曜日だけで1日平均12時間は働いている・・・そういうところは週40時間、1日8時間を超えると割増賃金を支払うことなんて気にしてはいない。 まして変形労働時間制なんて分かるはずもないため、下手をすると最賃割れしている場合も考えられます。 厚生労働省は平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定しております。 ⇒ こちらから 又、前出の場合は、営業社員だから時間外手当は営業手当3万円の中に含まれている・・・なんて言い訳はできません。 計算の根拠を説明できますか? それから最近では、タイムカードを早めに打刻し居残るケースにはパソコンのログの記録を突合させることで確認するそうですので不正はバレバレです。 労働時間の適正な把握と管理、そして賃金の適正な支払いは、事業の存続の上でも重要な管理項目の一つです。
October 24, 2010
コメント(0)
-
最低賃金が変わります!
岩手県最低賃金が、平成22年10月30日より時間額631円から644円となります。 ところで最低賃金とは?と訊かれて誰もが「読んで字の如く、最低限支払わなければならない賃金」と答えるでしょう。そうです、つまり賃金の下限額のことです。 これは憲法で認められている賃金労働者に対する基本的な権利(労働基本権)の一つです。 もう一歩踏み込んでみましょう。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 最低賃金には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。 なお、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 (2) 試の使用期間中の方 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 (4) 軽易な業務に従事する方 (5) 断続的労働に従事する方 尚、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・ 深夜手当等は含まれません。平成22年度地域別最低賃金改定状況 都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日北海道 691 (678) 平成22年10月15日青森 645 (633) 平成22年10月29日岩手 644 (631) 平成22年10月30日宮城 674 (662) 平成22年10月24日秋田 645 (632) 平成22年11月 3日山形 645 (631) 平成22年10月29日福島 657 (644) 平成22年10月24日茨城 690 (678) 平成22年10月16日栃木 697 (685) 平成22年10月 7日群馬 688 (676) 平成22年10月 9日埼玉 750 (735) 平成22年10月16日千葉 744 (728) 平成22年10月24日東京 821 (791) 平成22年10月24日神奈川 818 (789) 平成22年10月21日新潟 681 (669) 平成22年10月21日富山 691 (679) 平成22年10月27日石川 686 (674) 平成22年10月30日福井 683 (671) 平成22年10月21日山梨 689 (677) 平成22年10月17日長野 693 (681) 平成22年10月29日岐阜 706 (696) 平成22年10月17日静岡 725 (713) 平成22年10月14日愛知 745 (732) 平成22年10月24日三重 714 (702) 平成22年10月22日滋賀 706 (693) 平成22年10月21日京都 749 (729) 平成22年10月17日大阪 779 (762) 平成22年10月15日兵庫 734 (721) 平成22年10月17日奈良 691 (679) 平成22年10月24日和歌山 684 (674) 平成22年10月29日鳥取 642 (630) 平成22年10月31日島根 642 (630) 平成22年10月24日岡山 683 (670) 平成22年11月 5日広島 704 (692) 平成22年10月30日山口 681 (669) 平成22年10月29日徳島 645 (633) 平成22年10月16日香川 664 (652) 平成22年10月16日愛媛 644 (632) 平成22年10月27日高知 642 (631) 平成22年10月27日福岡 692 (680) 平成22年10月22日佐賀 642 (629) 平成22年10月29日長崎 642 (629) 平成22年11月 4日熊本 643 (630) 平成22年11月 5日大分 643 (631) 平成22年10月24日宮崎 642 (629) 平成22年11月 4日鹿児島 642 (630) 平成22年10月28日沖縄 642 (629) 平成22年11月 5日全国加重平均額 730 (713) ※ 括弧書きは、平成21年度地域別最低賃金額
October 20, 2010
コメント(0)
-
建設現場における作業主任者の配置が必要な作業
先日、岐阜市で工場を解体中に外壁が倒壊し、女子高生が下敷きになって死亡した悲惨な事故がありました。 事故当時、鉄骨入りの建築物の解体に必要な資格を持つ社員が現場を離れていたことが警察の調べで分かりました。 これは恐らく労働安全衛生法のことを示すものですが、有資格者を現場に配置し作業者に適切な指示をしなければなりません。 特に事故の多い建設業においては人手が足りない・・・では理由になりません。 今回の事故は、労働安全衛生法で定められている高さ5メートル以上の建物の骨組みなどを解体する際、必要な技能講習を受けた「建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者」が現場を指揮するよう規定されています。 それでは建設現場で作業主任者の配置が義務付けられているものはどのようなものがあるのでしょうか。 以下に記載します。 1.足場の組立て等作業主任者(足場) つり足場、張り出し又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 2.型枠支保工の組立て等作業主任者(型枠) 型枠支保工の組立て又は解体の作業 3.地山の掘削作業主任者(地山) 掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業 4.土止め支保工作業主任者(土止め) 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 5.鋼橋架設等作業主任者(鋼橋) 上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上の鋼橋の架設、解体又は変更の作業 6.コンクリート橋架設等作業主任者(コン橋) 上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上のコンクリート橋の架設又は変更の作業 7.建築物等の鉄骨の組立て作業主任者(鉄骨) 建築物の骨組み等で金属製の部材により構成されているもの(高さが5m以上)の組立て、解体 又は変更の作業 8.木造建築物の組立て等作業主任者(木建) 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付け作業 9.コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(コン解体) 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業10.ずい道等の掘削等作業主任者(ずい道掘削) 水道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付け作業11.ずい道等の覆工作業主任者(ずい道等覆工) ずい道等の型枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリート打設等の作業12.酸素欠乏危険作業主任者(酸欠) 第一種、又は第二種酸素欠乏危険場所での作業作業主任者の配置が必要な作業 ⇒ こちらから これ以外にも危険が伴う建設現場では、取り扱う重機は免許制となっていたり、技能講習を行わなければならないものもあります。 しかし、悲惨な事故現場にはこれら監督を行う者や作業主任者が不在であることが多いと聞きます。 これは、体裁を整えるため、工事とは関係のない人(社長やその奥さん等)が講習会に行って資格は得るが現場には行かないことが多くなっていて形骸化していることが現状のようです。 今回の事故では、ワイヤや重機で壁を固定しないまま、壁のすぐ横にあったエレベーター外枠を倒そうとしたところ壁が倒壊したそうです。 「基本に徹してゼロ災害」 建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置 ⇒ こちらから
October 19, 2010
コメント(0)
-
うつの労災認定迅速化
精神疾患にかかる労災認定を迅速化へ(厚生労働省) 厚生労働省は、業務上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患になった人の労災認定を迅速化するため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を示しました。 これまで(昨年度平均で)「8.7カ月」かかっていましたが、申請者から「治療や職場復帰が遅れる」との声が出ていました。 これにより同省では6か月以内の認定を目指すこととしました。 15日から始まった専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指すようです。 因みに現指針は、ストレスの原因となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブル」「長時間労働」などと例示した一覧表を基に、ストレスの強度を3段階で評価。その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断されれば原則として労災認定されます。 当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について ⇒ こちらから
October 18, 2010
コメント(0)
-
母性健康管理支援サイト(携帯版)
母性健康管理支援サイト「女性にやさしい職場づくりナビMOBILE」 厚生労働省はこの度、働く女性が妊娠・出産期を安心して過ごすための携帯版の母性健康管理支援サイト「女性にやさしい職場づくりナビMOBILE」を開設しました。 妊娠中・出産後における職場での注意事項や、母性健康管理措置に関する情報を手軽に入手できるようになりました。 ⇒ こちらから ※母性健康管理に関する法制度など、さらに詳しい情報は、「女性にやさしい職場づくりナビ(PCサイト)をご覧下さい。 ⇒ こちらから
October 14, 2010
コメント(1)
-

中小企業の一般事業主行動計画策定届出義務化
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)の改正によって、従業員数が101人以上の規模の中小企業にも平成23年4月1日までに一般事業主行動計画を策定し届出が義務付けられました。 これまでは300人以下の規模の企業は、努力義務でしたが改正により適用範囲が拡大されました。これにより100人以下の規模の企業は努力義務となります。 この次世代法は、我が国の急速に進行した少子化により経済社会に深刻な影響を与えることから、政府・地方公共団体・企業等が一体となって進めていかなければならない少子化対策の重要な一つです。 平成15年7月に成立・公布されて平成17年4月に施行した10年間の時限立法です。 企業は、少子化対策のための自社でできることの取り組みを考え、目標を設定しその目標を達成するための対策を一般事業主行動計画にして届出を行い、それを実施することになります。 実施した結果、目標未達成だったとしても何も処罰されたりしません。 但し、「認定」を希望する企業の場合は、一定の要件をクリアしなければならず、この目標達成も要件の一つになります。 認定されると以下のポスターにあるような「くるみん」マークを自社の宣伝活動(イメージアップ)に活用することができるようになります。 中小企業のための一般事業主行動計画策定・認定取得マニュアル ⇒ こちらから 他社ではどんな取り組みをしているのだろうか? 参考にしたいということであれば財団法人21世紀職業財団のHPに「両立支援のひろば」というサイトがあります。 このサイトにアクセスすると他社の取り組みが閲覧できます。 又、同業他社、同規模の・・・等検索条件も設定できるのでとても便利です。 実は、来年度以降の届出については、周知、公表も義務化されるので、自社のHPがない企業はこのサイトに登録すれば公表したことになります。 両立支援のひろば ⇒ こちらから 又、100人以下の規模の企業は努力義務ですが、建設業などは県の入札に有利なポイントが与えられるようですので、努力義務という緩い段階での策定・届出を推奨します。 岩手県では、財団法人岩手県長寿社会振興財団が相談窓口となっており、我々社会保険労務士(私は県南地域担当)が指導致します。(もちろん無料です) 財団法人岩手県長寿社会振興財団(企業子育て応援サイト) ⇒ こちらから 財団法人岩手県長寿社会振興財団では、「子育てにやさしい職場づくり助成金」を新設していますのでお問い合わせやお申込みは上記サイトまで。 101人以上規模の届け出が義務付けられる企業の担当者は、もう10月なので早めに対応しなければ後で辛い思いをしなければならなくなります。(年度末なので何かと・・・)
October 11, 2010
コメント(0)
-
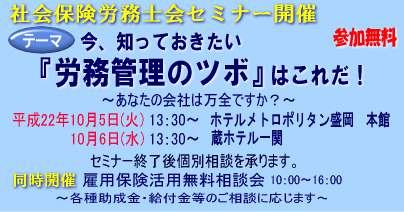
10月は社会保険労務士制度推進月間です
今月10月は社会保険労務士制度推進月間となっており、各都道府県の社会保険労務士会において様々な行事が行われます。 我が県会においてもセミナー、無料相談会等県内各地区において実施されます。お申込みは ⇒ こちらから 岩手県社会保険労務士会HP
October 2, 2010
コメント(0)
-
第61回全国労働衛生週間
今日から7日までは「労働衛生週間」です。 昭和25年に第1回が実施されてから本年で61回目を迎えるそうです。 昨年の業務上疾病による被災者は、過去最少となりましたが、一般健康診断の結果の有所見者の割合は約5割を超えています。 そして我が国が抱えている問題の一つとして自殺者数が3万人を超えており、そのうちの約2,500人が勤務問題を原因・動機の一つとしています。 仕事や職業生活に関して強い不安や悩み、ストレスを感じる労働者の割合が約6割にも上っていることやメンタルヘルス上の理由による休業者や退職者は増加傾向にあり、制渉外等の労災認定件数も多くなってきていることから近年では企業のメンタルヘルス対策が労務管理の重要なファクターにの一つになりつつあります。 そこでこれを機に各企業でメンタルヘルス対策として疲労蓄積度のチェックなどを行ってみては如何でしょうか? ただし、これを行っただけでは対策ではありません。 あとは各企業でメンタルヘルスについて真剣に取り組んで下さい。 参考⇒ 中央労働災害防止協会:「平成22年度 全国労働衛生週間」
October 1, 2010
コメント(0)
-
純粋な開業日記としてはここまで
今週は、火・水・金の3日間だけが営業日。 火曜日は、数少ない顧問先への定期訪問を行い水曜日には年金事務所での当番で2人客から謂れのない不条理かつ理不尽なことを言われ、今日はフリーデイで午前中は歯医者に行ってきてテンションがガタ落ちしており、とても業務が効率よくできないと思い今週は終了します。 明日は、今週の営業日が少ないのですが甥の結婚式のためお休みです。 さて、本ブログについて日記というよりは、週報のようになってしまっています。 当初は、開業以降の足取りを記録しあとで懐かしむことが目的の一つで投稿してきました。 開業するときは散々悩んだ末に決断しました。 本ブログはそんな悩まれている方々へ少しでも参考になれば・・・という思いもあり書いてきましたが、内容が顧問先のこととなると名は出さずとも何か不適切のような気がしてきたこと、上記のような理不尽な者たちへの口(攻)撃も投稿することを辞さないこと等、事務所から発信する情報の一つとしてはいささか不適切な表現も含まれる虞があることを考慮し、 今後は開業日記というよりは事務所からのお知らせのような内容とさせていただきます。 これまでの出来事などは、本ブログとは別に本ブログよりも以前から発信している個人的なブログに投稿しますので、よろしくお願いします。(特にリンクは貼りませんのでご了承願います)
September 24, 2010
コメント(1)
-
さし歯が・・・
今週は、今日は午前中久しぶりに顧問先のS社さんに訪問し社長と面会し、問題社員についての相談。 午後は、さし歯が取れたため歯医者に・・・。昨日も言ったのですがヘタクソな助手がしたため、敢え無く即行でポロリ・・・。 そして今日は、S者の訪問だったので何とか誤魔化しながら・・・。 明日は、沿岸地域のOF市まで。一般事業主行動計画策定等支援事業での業務です。 1社しかアポが取れず、効率が悪いのですが仕方がありません。 約1日が取られてしまいますが、1日分の報酬の請求は困難・・・。 水曜日は、県の方の子育て支援事業で小規模の事業所に出向き、相談・助言・支援をします。 木曜日の予定は現在ありませんが、午前中には顧問先の訪問をして午後から新しいさし歯の金属の土台が完成しますので装着に行ってきます。 そして金曜日が年金事務所での当番です。 諸外国との社会保障協定状況 ⇒ こちらから
September 13, 2010
コメント(0)
-
次世代法の認定企業が・・・
今週の年金事務所での当番は水曜日のみであとはフリーです。 今日は、顧問先の適正賃金設定のためのシュミレーションをしていましたが、あまりうまくいっていません。 そろそろ一般事業主行動計画策定支援のための企業訪問をしなくてはなりませんが、あまり気乗りしません。 皆さんお忙しいのか・・・やる気がないのか・・・定かではありませんが、訪問というと構えられてしまい先に進みません。 電話だけでは埒が明きませんから厄介です。 そんなこんなでグズグズしていたら厚生労働省から「次世代法の認定状況」について報道発表がありました。 ⇒ 次世代法の認定企業が920社に達しました 同時に101人以上規模の企業の届出(一般事業主行動計画)が来年の4月より義務付けられるのですが、まだ届出率が10%未満です。 行政目標はあくまでも100%ですから早期の計画策定並びに届出が今後積極的に行わなければなりません。 頑張らないと・・・。
September 6, 2010
コメント(0)
-
平成22年版厚生労働白書
今週は、昨日と木曜日が年金事務所での年金相談でそれ以外は、事務所内業務の予定となっております。 今日の午前中は月次処理でほぼ終わり、午後は雷が激しかった時間帯が2時間近くあったので、PCの電源を切り学習時間としました。 明日は、顧問先の賃金体系の見直しのため、先週データをメモリスティックで持ち帰ったものを加工して分析したいと思っていますが、雷がないようにお祈りして・・・。「平成22年版厚生労働白書」について <厚生労働省改革元年> ~生活者の立場に立つ信頼される厚生労働省~ ~参加型社会保障の確立に向けて~ 平成22年版厚生労働白書の特徴 今年の白書では「厚生労働省改革元年」と位置付け、年金記録問題や薬害肝炎問題の反省を踏まえた「役所文化を変える」取組を記述。 その上で、今後日本が進むべき方向として新たに「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」の考え方を提起、現時点の検討状況を記載。第1部の構成 第1章 厚生労働省の反省点 第1節旧社会保険庁等をめぐる問題 第2節薬害肝炎事件 第2章厚生労働省改革への取組み 第1節日本年金機構の設立と年金記録問題等への対応 第2節薬害肝炎事件等への対応 第3節内部改革への取組み第2部の構成<現下の政策課題への対応>第2部では、年次行政報告として、厚生労働省が現下の様々な政策課題に対応している状況を図表やグラフ等を用いて分かりやすく示すようにした。 第1章国家の危機管理への対応 ~新型インフルエンザ(A/H1N1)を中心に~ →生活の安心・安全を確保することは重要課題。2009年から流行した新型インフルエンザへの対応を中心とした危機管理対策について記述する。 第2章参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)の確立に向けて →新たに「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」という概念を定義し、そのあり方に関する現時点での検討の成果を示した上で、個々の政策課題への対応状況について記述する。 興味のある方や社労士試験受験生は ⇒ こちらから
August 31, 2010
コメント(0)
-
家内労働法について
今週は、明日火曜日が年金事務所での当番、木、金曜日の半日は顧問先で賃金についての打ち合わせがあります。 空きの日もありますので、一般事業主行動計画策定支援業務のため対象企業の訪問をしなければならないのですが、盆休みの関係で前後の担当者が忙しいなどで日程の調整が取れない状況となっています。 さて、皆さん「家内労働法」って知っていますか? 要するに内職をお願いしている会社に適用される法律なのですが、そのような法律があるのも知らないで、内職を依頼している会社が非常に多いこと。 私がこれまで知っている会社のほとんどは不知でした。 ただし、最低工賃だけは知っていることが多いため、最低工賃さえ守ればよいと考えているのでしょうか? 家内労働法は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家内労働手帳、工賃支払いの確保、最低工賃、安全衛生の措置などについて定められているものです。 そしてこの法律は、家内労働者の労働条件の最低基準を定めているものであるため、この基準より低下させてはならないことはもとより、向上を図るように努めなければなりません。 ですから、最低工賃さえ守っていればよいというものではありません。 通常の商取引では、まず仕事を依頼する際には、まず基本的な取引条件を決定するのがセオリーです。 会社対会社ならば「基本契約書」でしょうか。 これが対個人だと何も発しないでいきなり仕事を依頼する・・・そうですね、オーケストラの指揮者がお辞儀をしないでいきなりタクトを振るようなものです。 これには、家内労働手帳というモデル様式があり、基本委託条件の通知を行います。 そして原材料などの受け渡しの際には、必ず「注文伝票」(これも家内労働手帳に様式があります)を発行します。 この基本的なことを行っていない会社が非常に多いようです。 ISO9000を認証登録されている会社でもしかり・・・。(ISO認証企業・・・あまり参考にはなりませんね) 詳細はこちらからどうぞ ⇒ 家内労働のしおり(厚生労働省HP)
August 23, 2010
コメント(0)
-
イクメンプロジェクト
今週は、昨日からリスタートで9月号の事務所便りを今日まで作成を行い、明日金曜日が年金事務所での当番、明後日はお客様(スポット業務で将来顧問先候補)にお伺いする予定となっています。 最近、「イクメン」ブームとなっておりますが、この度「イクメン・プロジェクト」なるサイトが開設されました。 イクメンプロジェクト ⇒ こちらから
August 19, 2010
コメント(0)
-
職場における熱中症予防対策について
職場における熱中症予防対策について~岩手労働局~ この夏の暑さは異常の一言に尽きますが、県内で犠牲者(死亡)が10人となりました。 そのほとんどが高齢者なのですが、労働者も毎年熱中症による労働災害が発生しております。 職場においても熱中症の対策は必至であり、万全な対策を行うことで労働災害発生のリスクを回避したいものです。 (事業主には、安全配慮義務があります。) そこでどのように行えばよいのか? 岩手労働局HP(参考) ⇒ こちらから
August 12, 2010
コメント(0)
-
平成22年版労働経済の分析(通称:労働経済白書)
先日、私と同じ年金事務所で日替わりで交替で当番をしているST先生から電話があり諸般の事情により今週の金曜日ともしかしたら来週お盆明けにも当番があるが出来ないかもしれないとの連絡がありました。 今週の金曜日はもうお盆に突入するため他の先生にお願いするのは遠慮なので、自分がやることにしました。 平成22年度労働経済白書が発表されました。 「平成22年版労働経済の分析」について ~産業社会の変化と雇用・賃金の動向~ 「平成22年版労働経済の分析」(通称「労働経済白書」)では、我が国経済の現状や課題を踏まえつつ、経済、雇用情勢の短期的な分析に加え、「産業社会の変化と雇用・賃金の動向」について長期的、歴史的に分析。 【白書のあらまし】 ○我が国経済は輸出と生産が持ち直し、個人消費についても経済対策の効果。しかし、外需と経済対策に依存した経済の拡大は、自律性を備えた景気回復とは言い難く、今後は、所得や雇用の増加、国内消費の拡大などを中心に自律的な経済循環を創り出すことが課題。 ○白書は3章構成で、第1章「労働経済の推移と特徴」では、景気と雇用情勢について分析、第2章「産業社会の変化と勤労者生活」では、競争力を備えた産業構造と労働生産性向上の関係を分析、第3章「雇用・賃金の動向と勤労者生活」では、非正規雇用の増加と賃金格差の拡大について分析。 ○分析のポイントとしては、 ・人員削減を通じて労働生産性を引き上げようとする動きが強まり、生産力の持続的な発展に課題が生じていること、 ・人件費コストの抑制傾向により、技能蓄積の乏しい不安定就業者が増加し、平均賃金の低下や格差の拡大がみられること、など。 ○これらの分析をもとに、今後の着実な経済成長に向け、すそ野広く、より多くの人々に支えられた労働生産性の上昇を目指すとともに、成長の成果を適切に分配していくことが課題、とまとめ。 詳細はこちらから ⇒ 「平成22年版労働経済の分析」
August 10, 2010
コメント(0)
-
閑散期・・・海にでもいきましょうか
今日も猛暑日となるのでしょうか?毎日暑い日が続きます。 先週盛岡での会議で県北の先生が今年は「やませ」がないので暑いそうです。 例年であればエアコンは全く要らないそうで、扇風機でさえも一家に1台らしいのですが、今年は寝る時も暑いので家族で扇風機の争奪戦だそうです。 今年1年だけのためにエアコンを買うのも・・・と言っておられました。 今シーズンまだ海に行っていないので今週中にでも行ってみたいと思っておりますが、その今週の予定は、水曜日の年金相談だけで寂しいことに特に予定はないので行けそうです。 閑散期というか夏休みでもとりましょうか? いやいや・・・しかし、先週の会議でそろそろ企業を訪問して行動計画の策定を推進しなければなりませんので、電話でのアポ取りを開始しなければ・・・。 先月7月26日に厚生労働省より発表されました平成21年簡易生命表は ⇒ こちらから
August 2, 2010
コメント(0)
-
思考力ほぼゼロ
今週は、月曜日が年金事務所での相談員の当番で、木曜日が次世代法一般事業主行動計画策定支援事業の会議で盛岡に行く以外には決まった業務はありません。 昨日は先日顧問先にお伺いした際に依頼された賃金規程の原案の作成・・・と思っていましたが、朝うちの奥さんがハチに刺されて病院に連れて行かなければならない事態になってほぼ半日はそれでパーに。 まあ、それでも大事に至らなくてよかったのですが、午後は猛暑日ということもありやる気が起きずついついダラダラと過して夕方に。 そして今日も暑い日でした。 こう暑いと日中は思考力がほぼゼロに近くなってきて・・・今日は、請求書とか領収書とかの事務だけで終わってしまいました。 明日はこの暑い中、盛岡まで行かなければなりません。 平成22年度全国労働衛生週間の実施について ~10月1日から7日まで~ 平成22年度スローガン「心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス」 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善等の労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康の確保等を図ることを目的に行われています。昭和25年の実施以来、本年で61回目です。 毎年10月1日から10月7日までを本週間、9月1日から9月30日までを準備期間とし、それぞれの職場でさまざまな取り組みを展開することとしています。 平成22年度全国労働衛生週間実施要綱
July 28, 2010
コメント(0)
-
熱中症にご注意!
今週の営業日は、今日から土曜日までの5日間。 明日の年金事務所での当番以外は特に決まった業務はないため、依頼されている就業規則等を優先に行う予定です。 木曜日は、クルマの点検なので外出は極力控えて業務に専念する予定です。 梅雨明け早々、毎日暑い日が続いています。 この時期は、急な暑さに慣れていない体の最大の天敵である「熱中症」には十分注意しなければなりません。(梅雨明け直後が大変多いそうです) 職場においても熱中症対策は必須です。 熱中症対策に参考として ⇒ 「職場における熱中症の予防について」 (厚生労働省HP)
July 20, 2010
コメント(0)
-
講師デビュー戦はタイムオーバー
月曜日は無事講師を務めてきました。 雇用保険関連の就業支援講座の一つで主に定年退職される人たちが対象になるようです。 (シルバー人材センター連合会の事業) デビュー戦ということもあって多少不安でしたが、始まってしまうとあっという間に時間が経過して、予定より結局15分以上オーバーしました。 会場は、半日借りているということもあり、無償で急遽個別相談を行いました。 (みんないるときに質疑応答で手を上げる方はいないと思いましたので・・年金のことですから) それにしてもテーマが「年金のしくみと雇用について」ということなので午後の眠くなる時間帯だったのですが、皆さん真剣に聴いていました。 資料の作成も行ったため、今回の1回だけでは何か物足りません。 事業としては完全に不採算ではありますが、知名度と経験値は少し得られたということでよしとしましょう。<年金記録に係る苦情のあっせん等について>-総務省- 総務大臣は、年金記録確認第三者委員会の判断を踏まえ、7月13日に、厚生労働大臣に対し、次のとおり年金記録に係る苦情のあっせん及び年金記録の訂正は必要でないとする通知を実施しました。詳細については ⇒ こちらから(総務省HP)
July 15, 2010
コメント(0)
-
今日は講師デビュー
今週は、今日午後に市内の会場で就業支援講座の講師を務めます。 テーマは、「年金のしくみと雇用について」を90分間の持ち時間でお話しします。 時間配分が難しいですね。これだけ長い時間大勢の前で話をするのは初めてですから少し緊張するかも知れません。 明日は、年金事務所での当番で、明後日は当初一般事業主行動計画策定支援事業で私が担当する区域ではない区域での説明会で他の先生のフォローのため参加する予定でした。 しかし、先週の水曜日に私の担当する区域の説明会でその会場の参加者数が少ないためなくなりましたので、新しい顧問先の就業規則等の作成を行う予定です。 金曜日は健康診断があります。 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の新たな合意について-内閣府- 詳しくは ⇒ こちらから
July 12, 2010
コメント(0)
-
雇用保険の基本手当の日額等が変更になります!
今週は、水曜日に地元のホテルが会場で一般事業主行動計画策定届出についての説明会が行われますが、その説明会で行動計画策定について約1時間の説明を行います。 そして翌日の木曜日は年金事務所での年金相談の当番となっており、その他は、今日の月・火曜日は説明会の準備、週末は来週の月曜日に「年金と雇用」についてのセミナー講師を行うことになっていますのでその準備を行う予定です。 来週のセミナー講師の資料は、ほとんど出来ておりますが、明後日の説明会は資料は作成しなくてもよいのですが、昨年と説明する資料が異なることが先日判明したため、これから目を通して1時間の持ち時間をどのように進行していくか考えなければなりません。 資料のボリュームから1時間はあまりにも多すぎると思いますので、より具体的に突っ込んだお話しをしないと尺の関係で時間が余ってしまうおそれがあります。○雇用保険の基本手当の日額等の変更について 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。 詳しくは ⇒ こちらから
July 5, 2010
コメント(0)
-
フリーランスの悩み!?
今週は、月曜日と金曜日が年金事務所での当番で、今日は就業規則等の変更業務を依頼されているお客様へ納品に行ってきました。 前回訪問した際に賃金規程のチェックも依頼されていましたので、一応そのチェック表も作成して説明を行うと、今日納品したものの請求書と併せてその見積書も依頼されたので、昼食後に別の顧問先に健康保険の傷病手当金の説明をした後に事務所に戻り早速請求書と見積書の作成に取り掛かりFAXを送信して今日の業務は終了しました。 当たり前のことですが、会社勤めしていたときは、請求書なんて自分で作ったこともなく、まして明日は月末なので経理業務もしなければなりません。事務所の経営(一応経営者)、経理、営業、業務と一人何役もこなさなければなりません。(これまで同じことを何回か書いたかも知れませんが・・・。) 会社勤めしていたときは、考えたこともありませんでしたが、今は「3か月先の収入はどうだろうか?」・・・と心配になってきて夜突然に目を覚ますこともあります。 安定した収入があるサラリーマンが如何に恵まれているか・・・これは会社を辞めた人でなければ分からない思います。 経営者ってホント大変なんだなぁ・・・と思いました。 まだ私は従業員を使っていないので責任はないのでその点気楽です。 そんなまだ気楽な身分なのにやはり不安なのです。 でもこれは自分で選んだ道だから・・・なぁ~。 そして明日(6/30)から改正育児介護休業法が施行されます!!
June 29, 2010
コメント(0)
-
障害者雇用に関する制度が7月より変わります
今週は、今日は午後に見込み客に見積書を提出に行ってきます。 経営状況が厳しいようですので、どのような契約内容となるかは行ってみなければ分かりません。 明日は、金融機関での年金相談会、木曜日は年金事務所での当番となっております。 そろそろ来月のセミナーの資料を作らねば・・・。 その前に、昨年も行いました次世代法の一般事業主行動計画説明会の方も1時間の持ち時間がありますから説明はかなりのヴォリュームがあります。 寄りによって時期が重なるなんて・・・。 改正障害者雇用促進法の一部が昨年4月より施行されていますが、今年7月より施行される部分があります。 この度の変更点は、 1.障害者雇用納付金制度の対象企業の拡大 200人超300人以下の事業主 2.短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も対象 常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5としてカウント 3.除外率一律10%ポイント引き下げ 詳しくは ⇒ こちらから
June 21, 2010
コメント(0)
全188件 (188件中 1-50件目)
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】寒い日々に、母の整えポチ◎
- (2025-11-21 10:10:04)
-
-
-

- ニュース
- Google検索の "隠れ機能-2"「3分タイ…
- (2025-11-21 10:15:35)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-








