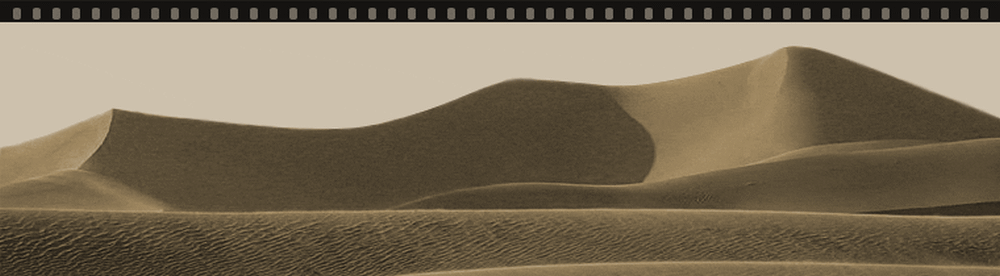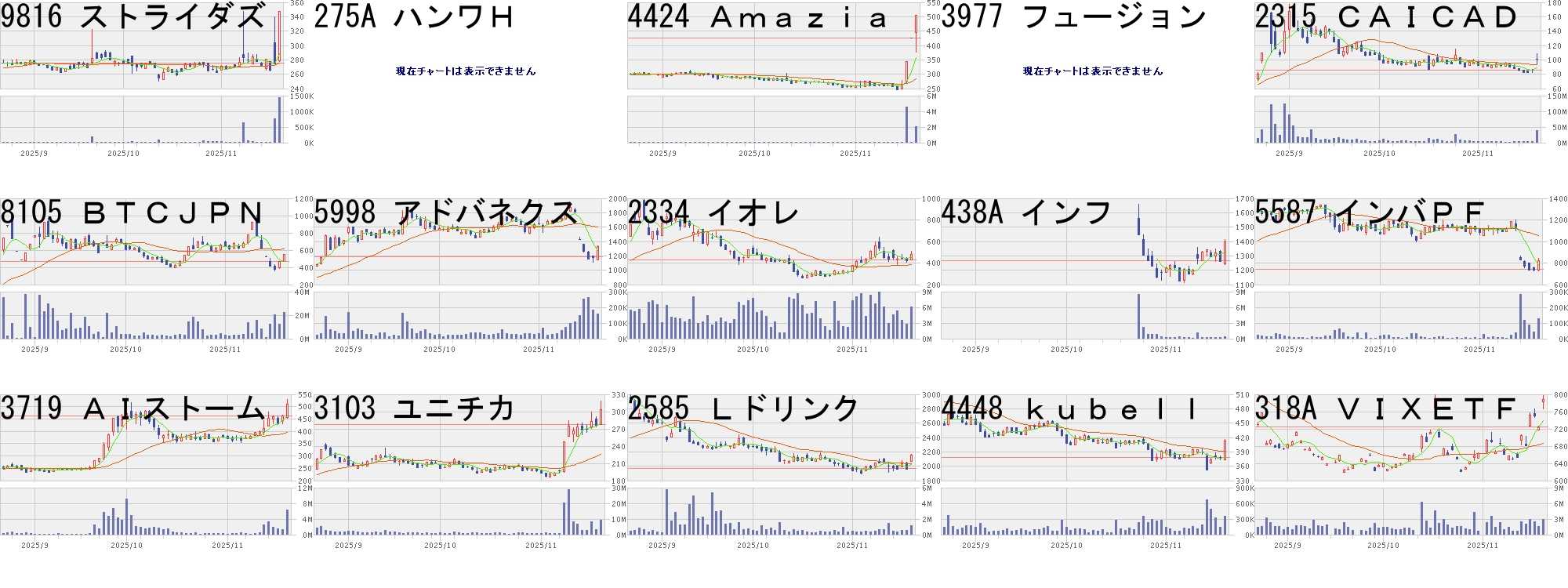2007年08月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
きょう(8/29)は、池袋演芸場下席昼の部・馬桜、小朝、三三、正蔵を楽しみました。
下席の昼の部は14:00開演。10分前に着いて、入場券売り場で「まだ座れますか?」と確認してからチケットを買いました。最近かなりの腰痛で立ち見は辛いのです。もう前座が始まっていましたが、ほぼ満員。空席は補助席も含めて10席程度でしたが、運良く、右端補助イスの最前列に着席できました。小朝さんが、「今回は正蔵と三三さんが交互でトリを取っていますが、まぁ正蔵が三三さんの胸を借りているようなものです」みたいなことを言っていました。「でも、きょう正蔵は、凄いネタに取り組みますからね」と前フリがありました。最近の三三さんは「最近は客席に浴衣の女性が増えました、その浴衣の女性めがけてしゃべるようにしています」と言うようにしています。確かにそうなのですが、きょうは客席には浴衣の女性は見かけなかったような・・・・・・中入りの時に、若い男性に「飯能の席亭さんですよね。これからも行かせてもらいます」と声をかけられました。ちょっと嬉しい気分です。きょうのトリは正蔵さん。ネタは「唐茄子屋政談」。45分たっぷりでした。(やっぱり三三さんの胸を借りるという表現は適切でした)落語の間に、かなりの雨が降ったようですが、池袋演芸場は地下2階なのでまったく気づきませんでした。
2007.08.29
コメント(0)
-
地元の人の出演も地域寄席ならではのコトではないでしょうか?
きょう(8/22)は、隣の入間市で平成5年8月から続けられている「いるま二八(にっぱち)落語会」に行ってきました。案内サイトこの地域寄席は「二八」というタイトルから推測できるように、毎年2月と8月の年2回開催されています。会場は入間市公営の入間市産業文化センター。客席は445席のホールですので、地域寄席の会場としてはかなり大きいほうでしょう。二月の落語会はホールを運営している(財)入間市振興公社が主催し、八月は市民団体の主催だそうです。この市民団体の代表者は私の知人ですが、彼女の話によると、2月は公社主催で予算が有るから出演料の高い噺家さんを呼べるから毎回満員になるが、八月は市民団体主催なので出演料の高い噺家さんを呼べないので、満員にするのは困難だ、とのことでした。きょうの落語会で特筆すべきことは、その主催者の娘さんが邦楽演奏で30分出演したことです。東京芸大の邦楽科卒業で大学院まで修了しているのでアマチュアというわけではありません。胡弓と三線、三味線、長唄を披露し、最後は桂文生さんも高座に一緒に並んでその都々逸の伴奏をしてくれました。寄席の定席の色物として出演できるレベルかどうかの判断は私にはできませんが、当人にその意欲が有るのであれば、その可能性は大きい人ではないかという期待は持てました。私も、「有望若手応援寄席」では、地元の津軽三味線や創作日舞の師匠に「色物」として出演してもらったこともありました。プロの噺家さんに混じって、地元のプロもしくはプロ級の方にも出演してもらうというのも地域寄席の特色として重要視してもいいのではないでしょうか。<蛇足の告白>神田ひまわりさんを初めて最前列で聴きましたが、あらためて写真よりも実物のほうが美人だと感じました。
2007.08.26
コメント(0)
-
その9・やっと、出演して欲しい噺家さんへ「出演を打診する」ことになります。
自分が地域寄席を主催する<本当の目的>を明確にして、<開催する頻度><毎回の公演時間と出演者数><使用する会場><入場料><一定の開催曜日と時間帯>のすべてを明確に決めてから、やっと出演して欲しい噺家さんに出演を打診することになります。日時は、当然のことですが、出演して欲しい噺家さんがその会場に来られる日時」でなければなりません。こちらで会場を確保した「○月○日○時」に、その噺家さんが空いているとは限りませんので、噺家さんに打診する前に、「会場が使用できる日時」の余裕を確認して、幾日分か仮予約で押さえておかなければなりません。もちろん、「開催曜日を決めている」のであれば、仮押さえも同じ曜日でなければなりません。「○月の○曜日はA日、B日、C日のいつがいいでしょうか?」と訊いて噺家さんに都合の良い日を選んでもらうことになります。ここで、その日程の中に、その噺家さんの都合の良い日があれば問題はありません。しかし、時にはどうしても、「会場の空き」と「噺家さんの日程」が合わないことも生じます。そんな時、主催者には下記のような迷いが生じてきます。A.どうしてもこの噺家さんに出演して欲しいので噺家さんの都合に合う日時の会場を探そうか?それともB.日時と会場は変えたくないので、出演してもらう噺家さんを変えて、日時が合う噺家さんに出演を打診してみようか?そんな事態になった時に狼狽しないように、予め地域寄席の運営方針としては<会場優先><曜日優先>か、それとも<噺家優先>のどちらかに決めておく必要があります。「有望若手応援寄席」では、会場として<飯能駅そば久下稲荷神社境内の一丁目倶楽部>、開催曜日としては<土日休日の18:30~>が定着していますから、当初予定していた噺家さんの日程が合わない場合は、ローテーションを変えて、別の噺家さんに登場してもらうことに決めています。例えば、柳家三三師匠の場合は、年4回と予定しているのですが、どうしても日程が合わなかったので、昨年は3回でしたし、今年は5回になります。古今亭菊之丞師匠の場合も予定では年4回でしたが、今年は3回です。1月の出演から7月の出演まで6ヶ月も間が空いてしまいました。それでも毎月きちんと同じ会場で開催出来ているのは、出演して頂く噺家さんを「いつも定めた4人の中の一人」と定めているからです。
2007.08.25
コメント(0)
-
きょう(8/22)は、上野鈴本下席夜の部・柳家三三がトリで「怪談・乳房榎」をたっぷり聴かせてもらいました。
夜の部は17時開場ですから、炎天下で1時間も2時間も行列して待つのは辛いので、昨夜の20時頃、鈴本演芸場に電話してみました。 私「明日、夜の部を聴きに行きたいのですが、 開場時刻まで外で並ぶのでしょうか? それとも整理券が出るのでしょうか?」 係「整理券は出していませんが、並ぶほどのことはないですよ」 私「えっ!? だって三三さんですよ!」 (言外には、当然満員でしょうという意味が込められています) 係「きょうも開場前に並んでいたのは20人も居ませんでしたから」 私「そうなんですか・・・・・」 係「平日ですから、並ばれなくても大丈夫ですよ」こんなやりとりがあったのと、停電でJR各線が止まったために、鈴本に着いたのは開演5分前でしたが、場内に入っていたお客は30人もいませんでした。職場から鈴本に直行していた奥さんは最前列の真ん中で席を確保していました。三三さんにとっては、(知り合いの人がすぐ目の前の席に居られると話しにくいのでは・・・)と思って席を後ろのほうに移動しようと思ったのですが、そのまま三三さんの出番まで最前列に居続けました。地域寄席の主催者として三三さんの噺を何十回も聴いていますが、いつも会場の最後尾の席なのです。だから、どうしても寄席や他の会場ではできるだけ前の席で聴きたくなってしまうのです。三三さんの今夜の演目は予告通り「怪談・乳房榎」この噺は、飯能では2005年5月29日の「柳家三三飯能独演会第18回で聴いたので今日は2回目。50分たっぷり聴かせてもらいました。<追記>三三さんのブログ「三三のひとりごと」にも、この日のことが書かれていますので、ぜひお読み下さい。http://blogs.yahoo.co.jp/yanagiya_sanza/35876724.html
2007.08.22
コメント(0)
-

今夜(8/19)の第5回好二郎独演会の入場者数も記録更新でした。
前回の第81回有望若手応援寄席の会場は、参院選投票日と重なったために大川学園高校体育館でしたが、きょうの第82回は、またいつもの一丁目倶楽部です。開始直前に雷鳴があって弱い夕立になりましたが傘が必要なほどではなく、終了時も稲光は見えましたが、どうにか振られずにすみました。好二郎独演会は年2回のペースで開催しています。前回(3/25)の来場者は65人でしたが、今回は79人。約2割増えました。増えた理由は、7月3日に市内の中学校でやった好二郎さんの落語会のお陰です。そこで好二郎さんの落語を聴いた生徒さんが保護者と一緒に聴きに来てくれたからです。こうして、中学生の落語好きが増えてくれるのは嬉しいことです。きょうは早朝から飯能市全体の防災訓練があって、町内会長さんたちはお疲れなのですが、我々世話人が住んでいる町内会の会長さんも聴きにきてくれました。きょうの演目は「兵庫舟」と「お化け長屋」でした。
2007.08.19
コメント(2)
-
映画『怪談』を観てきましたが・・・・冒頭の導入部分は「講談」ではなく「落語」で語って欲しかったですね。
きょう(8/16)奥さんと隣の市に有るシネコンで『怪談』を観てきましたが、やや「??」と「不満」が残る作品でした。映画評サイトでの評価も高いものではありませんでした。映画の冒頭で三遊亭円朝作『真景累ヶ淵』と書いてあるのに、物語への導入を講談で語るのは納得がいきません。これでは、この映画で初めて『真景累ヶ淵』という怪談を知った人は、作者の三遊亭円朝は講談師で、『真景累ヶ淵』は講談で作られ、講談で語り継がれていると思ってしまうのではないでしょうか?田中秀夫監督には「怪談は講談」という思い込みが有るのでしょうか?私は三遊亭円生師匠の『真景累ヶ淵』全巻をCDで聴いたことがありますし、いまの若手では古今亭菊之丞さんの「豊志賀」を生で聴いたことがあります。今回の映画が、落語にも「聴かせる怪談」は有るのだ、ということを知ってもらう良い機会だと思っていたのに、それが残念です。もし、この映画の冒頭での導入部分を講談ではなく、歌丸師匠の落語で演ったら、「笑点しか知らない多くの人が落語に興味を持つようになった」のではないかと思っています。もちろん、演者は歌丸師匠に限りません。若手の花禄さんや喬太郎さんがやっても「落語への関心」はさらに高まったであろうと思っています。 <参考>映画『怪談』公式サイト 映画評サイト
2007.08.16
コメント(0)
-
その8・「曜日」と「時間帯」も決めておく
会場と出演する噺家さんが決まって、初めて「第1回目の開催日時」を決めることになるのですが、その前に決めておくべきことがあります。それは開催日の曜日と開催日の時間帯の基本を決めておくことです。<開催日の曜日>とは、「休日か?平日か?」 ということもありますが、「曜日を一定にするのかしないのか?」ということです。曜日を決めると「月曜寄席」とか「火曜寄席」というような名称を表記して、お客さんに覚えてもらいやすくなるというメリットがあります。しかし、その反面、「曜日を固定してしまうと出演者がなかなか決められない」というデメリットもあります。特に出演者を固定している場合は、なかなか日程が確保できない場合が生じてきます。<開催の時間帯>は、午後、夜間が多いでしょうが、意外にも午前中の開催も可能なのが落語会の特徴でもあるでしょう。有望若手応援寄席では、「休日の夜間」と決めてスタートしましたが、結果的にはほとんど「日曜日」になっています。これは会場の一丁目倶楽部が地元町内会の集会所であるため「日曜日の夜間」は他の曜日と夜間と比べて「使用されない時間帯」でもあるため、確保しやすいからです。
2007.08.05
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1