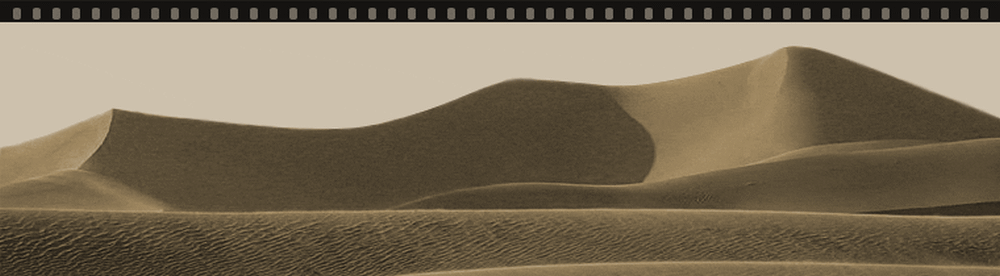2007年02月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
きょう(2/28)の日本経済新聞夕刊コラムで「地域寄席の事例」として紹介されました。
日本経済新聞夕刊の第二社会面(22頁)に『広角鋭角』というテーマ別の連載コラムがあります。いまのテーマは「笑いの風景」。医療や介護、学校現場、仕事場で「笑い」を活用している事例を紹介しています。きょう(2/28)は、「町の寄席」「地域寄席」の事例として、7年前から続けている「有望若手応援寄席飯能」が紹介されました。その記事の切り抜きをスキャナーして、『飯能これから大事典』に掲載したいのですが、しばらく使用しなかったスキャナーが不調で、残念ながらそれができません。日本経済新聞の担当記者から連絡があったのは、昨年の暮れです。インターネットで「地域寄席」を検索して、有望若手応援寄席を知ったとのことでした。 試しに 地域寄席 でGoogle検索してみたら「531,000件」で、「有望若手応援寄席」は、上位7番目に表示されていました。 「マスメディアの取材を受けるための発信手段」としては、この「有望若手応援寄席」サイトは、効果があったようです。 10年続いた川越の地域寄席が無くなってしまいましたが、有望若手応援寄席は、最低でも10年はなんとか続けていきたいと思っています。あと3年ですから、それくらいは何とか続けられると思います。実は、「地域寄席研究所というBlogを開設しよう」と思ったのは、この日経の取材を受けた時だったのです。
2007.02.28
コメント(0)
-
地域寄席の<目的>は一つではない
地域寄席の「目的」とは、誰の目的なのでしょうか?もちろん<主催者>の目的です。<主催者>が地域寄席を主催する本当の目的のことです。言うまでもなく、目的には<建て前の目的>と<本当の目的>があります。まず、<建て前の目的>には、下記のようなものが挙げられます。 1.落語を知らない若い人や子供に「本物の落語」を知って欲しい 2.地域の人に「生の落語」に触れてもらいたい 3.自分の住んでいる地域に「落語好き」を増やしたい 4.都内の寄席に行かなくても近くで落語が聴ける場所が欲しい 5.マイク不要の小さな会場で身近に落語を聴きたい 6.若い噺家さんに「高座で話す」機会を提供したい 7.若い噺家さんを応援したい<本当の目的>としては、下記のようなものが挙げられます。 1.自分の好きな噺家さんの落語だけを聴きたい 2.噺家さんと個人的に親しくなるキッカケにしたい 3.特定の噺家さんに影響力を発揮できるようになりたい 4.地域の人たちに認知されるイベント主催者になりたい 5.楽しみながら「儲かる」ことをしたいおそらく、地域寄席の主催者の「本当の目的」に触れた文章は極めて少ないのではないでしょうか。なぜ、私が「主催者の本当の目的」を書けるのでしょうか?もちろん、上記のすべてが「私自身の中に有る」からなのです。
2007.02.27
コメント(0)
-
昨日に続いて、今日(2/24)は奥さんと「所沢寄席」で蕎太郎、正蔵を聴いてきました。
「所沢寄席」と銘打っていますが、主催者は(財)所沢市文化振興事業団ですから、「地域寄席」ではなく「ホール落語」です。 開演は18:30からですが、先に私一人で15:00に会場に行って、ロビーで{有望若手応援寄席}のチラシの挟み込みをさせてもらいました。 既に主催者がセットしてあるパンフレットとチラシのセットの最後に{有望若手応援寄席}のチラシを追加する作業です。700セットに1枚ずつ追加する作業にかかった時間は60分。それでも、挟み込みのほうが、会場の外で来場者に手渡しするよりも、大勢の人に、一人残らず全員に手に取って見てもらえます。<きょうの演目> 林家正蔵「一文笛」 三増紋之助・曲独楽 柳家喬太郎「うどんや」 桂つく枝「ちりとてちん」 林家たこ平「つる」 会場:所沢市民文化センター・ミューズ マーキーホール(定員798席) S席3000円 A席2000円 「完売」とのことでしたが9割の入りでした。
2007.02.24
コメント(0)
-
きょう(2/23)は「桂三枝創作落語会」に
きょう(2/23)は奥さんと、自宅から徒歩5分にある飯能市民会館で開催された『桂三枝の爆笑創作落語独演会2007』に行ってきました。主催者は地域の朝日新聞専売店なので「地域寄席」というわけではありません。いわゆる「ホール落語」の範疇だと思います。自由席なので開場の90分前に行きましたが、それでも整理番号は255番。しかし、最前列に座る人は意外に少なく、ラッキーにも最前列の中央に二人分を陣取れました。大きな会場での落語会では初めての体験です。誰でも入場できる落語会でしたが、『東京かわら版』のイベント情報欄には載っていなかったので???でした。 桂三枝「読書の時間」「良心」「涙をこらえてカラオケを」 桂三弥「にぎやか寿司」 桂三枝「青い瞳をした会長さん」 休憩入れて2時間10分 前売り券3000円。 定員1000人の大ホールで8割の入り桂三枝の創作落語が、東京の落語と違うところは、扇子と手ぬぐい以外に「小道具」を使うことです。「涙をこらえてカラオケを」は、とうぜん、落語会としてのマイクの他に、小道具としてカラオケマイクが使われました。この演目をCDで聴いた人は理解できると思いますが、そのカラオケマイクには、違和感が無いだけではなく、使用するだけの必然性を強く納得できました。
2007.02.23
コメント(0)
-
「変更」への対処は、「日程」を変えずに「出演者の交代」で!
一昨日(2/19)の夜、古今亭菊之丞さんから私の携帯に着信が。 (こういうときの連絡はたいてい日程の変更の予感です)「4/22の出演を変更できませんか」というものでした。 (やっぱり・・・でした) 私は、有望若手応援寄席に出演してもらっている噺家さんには「こちらは安い出演料しか払えないので、他にギャラのいい仕事や、義理で断れない仕事が後から入ったときは、事前に連絡してくれれば調整しますから」と伝えてあるのです。 4/22なら2ヶ月前の日程のことですから、どのようにでも対処できる余裕があります。 菊之丞さんは、「日程をずらして貰えれば」ということですが、主催者としては、地域寄席を始めた当初から、「出演者の変更はしても日程変更はしない」という方針を決めています。(実は、そのほうが楽なのです・・・・) 既にチラシやwebサイトで6月までの日程と出演者をお知らせしていますので、常連さんは「4/22は飯能の有望若手応援寄席」を予定に入れておられます。 もし、日程を変更して、その変更後の日時に他の予定が入っていて、その日は聴きに行けないような場合は、常連さんには、どうしても「勝手に変えるなよ」という不満が生じてしまいます。 その点、出演者の変更でも、お客さんに喜んで頂ける人に替わって来て貰えるなら、「菊之丞さんの話を聴きに来たんだけど、この噺家さんだったらいいよ」と許して頂けます。 幸い、次の日(2/20)の昼に柳家三三と連絡が取れ「4/22は出演できます」とのことでした。三三さんなら、「菊之丞さんを聴こう」と思って来たお客さんでも、喜んで頂けると思います。 出演者の都合が悪くなった時は「日程の変更」よりも「出演者の交代」で対処できるところが、固定したメンバーで続けていく地域寄席の強みだと思います。
2007.02.21
コメント(0)
-
昨日(2/18)は<有望若手応援寄席>の第75回目でした。
出演者は柳家三三師匠。飯能独演会としては24回目。出し物は「味噌豆」と「大岡政談・五貫裁き」「悋気の独楽」の三席。 昨日は、特筆すべきことがありました。 来場者が90人だったのですが、それは来場者数のいままでの記録を大幅に更新したのです。 それまで、最近の三三さんの独演会の時の来場者の推移は下記の通りでした。 2006年9月17日(日)70人 2006年6月18日(日)70人 2006年2月26日(日)57人 着実に伸びていますので次回も楽しみです。
2007.02.19
コメント(0)
-
「学校寄席」とは違うタイプの「中高生向け落語教室」!
実は、この度、飯能市内の中学生、高校生を対象にした<落語入門教室>を企画しました。 噺家が中学校や高校から呼ばれて体育館で全校生徒の前で落語を聞かせる「学校寄席」とは違います。 落語が好きで、希望する生徒だけに会場に来てもらってじっくり、落語と「落語に関する初歩的な解説」を聞いてもらおうというのが「落語教室」です。 といっても、単に地元で地域寄席を主催しているだけのオジサンが企画しても、それだけで対象にした中学生や高校生が聴きに来てくれるわけではありません。 一番効果的なPR方法は市の広報誌の「イベント案内頁」に載せてもらうことですが、残念ながら、飯能市では、市や県が主催するイベント以外は広報誌に掲載してくれないのです。 そこで、公民館に働きかけました。 公民館が主催する講座やセミナーなら広報誌に案内が載るからです。 厳密に言えば、「落語教室の開催を公民館にはたらきかけた」のではありませ。 公民館が募集した「講座企画委員」に私が応募して、そこで開かれた「公民館主催講座企画委員会」で、「中高生のための落語教室」を提案したら採用された、というのがその真相です。 開催日は2007年3月10日(土) 講師は柳家三三師匠。会場は飯能市中央公民館の和室。 定員は40人 受講料は無料です。 さあ、果たして、何人の中学生、高校生が来てくれるでしょうか。
2007.02.16
コメント(2)
-
<主催者>によるスタイル分類・その3「同好会タイプ」
<主催者>によるスタイル分類きょう(2/12)は3.「落語好き」が数人グループで主催する地域寄席について書いてみました。 このタイプの地域寄席は、「特定の噺家さんを応援する」ということよりも、とにかく「落語そのものが好き」だから、「自分たちでも噺家さんを呼んで落語会を開催したい」ということが始める動機になっています。 だから、主演する噺家さんは、いつも顔ぶれを変えるようにしているので、いつも落語以外に、音曲や曲芸、マジック、物真似、漫才などの色物の芸人さんも出演します。あたかも、鈴本や末広亭なので定席の「ミニ版」のようなものです。 主催者たちが、地域で「いろいろなタイプの芸人さんを呼んで楽しもう」というので、私はこれを<同好会タイプの地域寄席>と読んでいます。 主催者のスタイル分類による4タイプの中では、このタイプが一番多いのではないでしょうか。
2007.02.12
コメント(0)
-
<主催者>によるスタイル分類・その2「後援会タイプ」
<主催者>によるスタイル分類きょう(2/10)は2.「あの噺家が好き」という個人的なフアンが主催する地域寄席について書いてみました。 このタイプの地域寄席は、そもそも主催者が「自分の好きな噺家さんの落語だけを聞きたい」ということが始める動機になっています。 いつも「主催者が自分の好きな落語家さんだけに出演してもらう」ので、その噺家さんの、その地域での後援会のようなものです。 なので、私はこれを<後援会タイプの地域寄席>と読んでいます。 その落語家さんの出身地などで開催されている地域寄席は、大部分がこのタイプかもしれません。 ちなみに、私が主催している<有望若手応援寄席>も、この<後援会タイプ>です。
2007.02.10
コメント(0)
-
<主催者>によるスタイル分類・その1「個人席亭タイプ」
<主催者>によるスタイル分類きょう(2/9)は1.会場所有者や管理者が主催する地域寄席について書いてみました。 地域寄席の会場には、よく神社仏閣、飲食店、事業所のホール(社員食堂)などが使われています。それは、その会場の所有者や管理者が主催者になっていることが多いからです。 寺院の住職、神社の神主や氏子代表、店のオーナーや店長、事業所の責任者で「落語好き」であれば、多くの人が「いつか自分の所でも落語会をやりたいなぁ」と思うようになるからです。 これは数ある<地域寄席の始め方>の中では、一番始めやすいスタイルです。 なにしろ、会場の確保はすぐできるし、落語会場だけでなく周囲の場所までかなり自由に使えます。それに会場使用料が不要です。 私は、これを<個人席亭タイプの地域寄席>と読んでいます。 個人の住宅でも、30人以上が入れるくらいの大広間や集会室が有るような家であるなら、そこで地域寄席を開催することは可能です。
2007.02.09
コメント(0)
-
地域寄席は、<主催者の違い>で、4つのタイプに分類できます。
〈地域寄席って何?〉というカテゴリーでは、地域寄席を<主催者><目的><出演者><会場><来場者><入場料><開催回数>の7項目で定義付けのようなことをしています。 この〈地域寄席のスタイル〉というカテゴリーでは、同じ7つの項目で、地域寄席を「開催のスタイル」から分類してみました。<主催者>によるスタイル分類 日本で唯一の演芸情報誌『東京かわら版』の【毎月の演芸会情報】頁には、「会の名称」「会場」「連絡先」が記載されている欄がありますが、そこに必ずしも<主催者名>が書かれているわけではありません。 まず、地域寄席には<主催者の違い>によって下記の4つのタイプがあります。1.会場所有者や管理者が主催(個人席亭系)2.「あの噺家が好き」という個人的なフアンが主催(後援会系)3.「落語好き」が数人グループを結成して主催(同好会系)4.「イベント好き」がたまには落語会にしようと主催(イベント系) 次回からは、この1~4の違いについて書いてみます。
2007.02.05
コメント(0)
-
菊之丞さん、三三さんに弟子ができたら、まっさきに出演してもらい、毎回前座で来てもらう。
私が<有望若手応援寄席>で描いている三番目の夢は、定期的に出演して貰っている噺家さんに、一番弟子ができたら、まっさきに飯能で前座さんとして出てもらうことです。 まず前座さんに15~20分ほど話してもらい、続いて師匠(菊之丞独・三三)が1席話して中入り、その後また師匠が1席、という「構成」になるのをいまから待ち望んでいます。 地域寄席では、毎回、噺家さんと世話人で「打ち上げ」と称して、近くの居酒屋で呑んでいますが、この時にも前座さんが居てくれたら、さらに楽しいでしょうね。 私は、菊之丞さんも、三三さんも、柳朝を継ぐ朝之助さんも、その存在を知ったのはもう「二つ目」になっていて、残念なことに彼らの「前座時代」を知りません。 「落語の楽しみ方」の一つに、前座のときから成長するのを見続けていく」ということがありますが、やはり、私もそれを体験していきたいですね。
2007.02.03
コメント(0)
-
地元の子供が落語家に弟子入りする → 地元で独演会を始める → 後援会長は市長に
私がいま埼玉県飯能市で毎月開催している<有望若手応援寄席>で描いている二番目の夢は、子供の常連客の中から、出演している噺家さんに弟子入りする子が出てくることです。 古今亭菊之丞さんも、柳家三三さんも、3月に襲名する春風亭柳朝さんも、やがて「弟子」をとる時が来ます。「一番弟子」とはいいませんが、その弟子の中に、「飯能で聴いて師匠が好きになったから」という子供が何人か出てくることをいまから楽しみにしています。 もちろん、前座になる前の「見習い」の時から、師匠の飯能独演会のときには高座をつとめてもらいます。そのときは、その子の親戚や同級生たちも来場するでしょう。 やがて、その子自身の飯能独演会を定期的に開催するようになれば、こんな嬉しいことはありません。 市内で開催されるイベントの司会の仕事も来るでしょう。 その子の後援会長には市長になってもらいましょう。 地元企業がTVCMを製作するときはもちろん専属契約です。・・・・夢というか私の妄想はどこまでも広がっていきます。
2007.02.01
コメント(3)
全13件 (13件中 1-13件目)
1