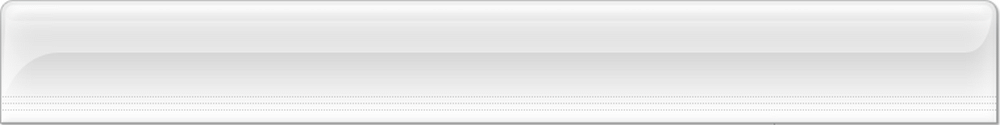2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年02月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
おいでやす
この土日は奈良に出張でした。久々に新幹線に乗りました。やっぱり窓の外の景色を楽しめるのはいいですね。(2週間前の飛行機の出張と比較してしみじみ思いました)さて、関西は5年振りくらいです。京都駅構内のにしんそば屋に入ったとたん「おいでやす」と言われて一気に京都ワールドにトリップ。お国言葉は本当にいいです。その地域独特のよそ者には入り込むことができない豊かに醸成された文化を感じます。東京生まれの私にとって密かに、だけど強烈に惹かれる存在です。地方出身者が私の周りに多いからなのか歴史を遺していこうという活動をしているからなのかそれとも単に歳のせいなのか年を追うごとに「お国言葉」を持つ人たちへの羨望が強まっています。「おいでやす」あー、私も楚々として言ってみたい。^^
February 28, 2006
コメント(0)
-
「聴く力」と「器」
「聴き書き」という仕事をしていると嫌でも自分の「聴く力」に敏感になります。そして毎回自己反省の日々です。先日、とある方の紹介で素敵な活動を長いこと行っている老紳士にお会いしました。気持ちいいまでに私の言うことに「傾聴」して下さる方でした。私は話し終わって大きな充実感を味わいました。でも、反面自分の話した量と先方の話した量とではあきらかに私の方が多くそのことに自分の未熟さも痛感。素晴らしい聴き手に出会うといつも頭をガツンとやられます。人間としての器の大きさは「聴く力」と比例している気がします。もっと前にお会いした「聴き書き職人」の方も素敵でした。どんどん人の話を聞きだします。こちらは調子にのってぺらぺらぺらぺら話します。そしてふと冷静になって「あー、またやられた」と頭をかかえ、先方の素晴らしい人間性に敬服します。「きちんと聴く」ことは器の大きな人にしかできません。自分の意見を言わずもちろん反対することも賛成することもせずただありのままを受容して耳を傾ける。そうすることで話し手の心を開けるのです。「聴く」のはそんなに苦手だと思っていなかったから「聴き書き」なぞを仕事にしようとしたのですがいざ、意識してみると自分の「聴く力」のなさに猛省する日々です。つい口をはさんでそれに関連する自分の経験や意見を述べたくなってしまいます。その課題にいかに取り組むかと考えていたらそれにはうってつけのお仕事の話が舞い込みました。とにかく「聞き役」に徹するお仕事です。自分の一番のウィークポイントの強化方法を考えていたら抜群のタイミングでお仕事がくるなんて今年は運気がいいらしいのですがちゃっかりこういうところでもいいチャンスがいいタイミングで舞い込んでくるものなのですね。^^器を大きくするきっかけに感謝してきちんと生かしたいと思います。毎日経験、毎日反省、毎日進歩・・・で頑張ります。
February 26, 2006
コメント(2)
-
退屈のススメ
昨日、とある方とのお話しの中で「退屈がエネルギーの源」という言葉を頂戴しました。いやはやごもっともだと思いました。人は退屈したときにはじめて「こんなことして遊んでみようかな」とか「宇宙の果てってどうなっているんだろう」とか、そんなとりとめのない制限のない思考がはじめて踊り出します。無意味にテレビを見てしまったりゲームに興じてしまったりゴシップ雑誌を暇つぶしに読んでしまったり・・・そんなことが気軽にできる環境が周囲にあると思考が停止してしまうしはたまた何か考えたような気になっていても人が作った思考や娯楽の枠を超えずに小さくまとまってしまって私たちに備わった無限の想像力/創造力を活用するにいたらずに終わってしまう。子供の頃空を見上げて雲が色々な形に見えてきたそんな時間を大人になった私たちは悲しいかな意識的に作り出さなければいけない。今の子供達だって勉強だ塾だゲームだと毎日することが溢れすぎていて「退屈」する暇がないんじゃないだろうか。何もない自然の中で退屈したとき無限の想像力を発揮してはじめて新しい遊びを思いつくように私たちも「退屈」を楽しんで未知なる可能性を開拓していきたい。考えてみれば私のこの事業の全ての発端も時間からもお金からも全て開放されたニュージーランドでの一人旅で思考の流れに身をまかせて考えたことからはじまっている。毎日、何をしてもよかった。毎日、何もしなくてもよかった。ちょっと立ち止まって退屈してみよう。本とか音楽とかとりあえずそんなものも全部置いて自然の中にぽつんと身を置いてみよう。私たちは何を考えるだろう。何を想像/創造するだろう。。。思考を解き放って、退屈してみよう。たった半日でもいや、たった2時間でも何もない時間から何かが生まれるかもしれないから。。。
February 22, 2006
コメント(0)
-
本能的感覚
私の周りでは妊娠ラッシュです。この一週間で四人の妊婦さんに遭遇です。産婦人科勤務並かな。笑子供が・・・時代が・・・繋がっていく。本当に嬉しい。きっと本能的な嬉しさなのだと思う。ここ最近は本能が研ぎ澄まされたのかなんなのかわからないけれど出産シーンがテレビの画面に出るとそれがたとえ1秒であってもパブロフの犬のように涙が出てくる。もちろん友人が妊娠だなどと聞くとお腹の中に芽生えたいのちが小さく光って見えるようでこれまた涙が出てしまいそうになる。後世に何かを遺したい、繋げたい、という感覚はとてもとても「本能的な」感覚なのだと思う。近代文明の中でのめくるめく刺激やストレスで私たちが「種を保存」しなければいけないと組み込まれているはずの「本能」がかき消されている。その象徴が少子化であり環境破壊であり凄惨な事件であり・・・私が自然が大好きなのは自然の中に身を置くとその「本能的感覚」がよみがえってくるから。どう進めばいいのかどう生きればいいのか自然が教えてくれるから。私たちは自然の一部でしかないことそんな「本能的感覚」への気づきをウィルウィンドでは提供できればと思う。その先、社会をどうしていくかはみんなで考えればいいこと。まずはちょっと立ち返ろう。いのちの繋がり自然への感謝私たちの心の中に眠る道しるべを見つけるために。日本って古来からそういう感覚に長けている気がするのです。だからこの国からなら世界に発信できるかななどと思っているのです。みんなの力を合わせれば。--------「聴き書き冊子」おじいさまの歴史おばあさまの歴史--------
February 20, 2006
コメント(0)
-
下関駅焼失の寸前で・・・
乗り換え検索サイトの駅前探検倶楽部で「駅の記憶」の連載が始まりました。「昭和の記憶」との共同企画です。第一回目は先日焼失した「下関駅」。下関駅が焼失してしまったのは記憶に新しい今年の1月7日。1942年、つまり戦時中に建てられた三角屋根の駅舎でした。そしてだからこそ「駅の記憶」として建物とともに多くの思い出がつまった駅であり「昭和の記憶」の活動の一環で、取材をしていたのでした。そのような中、焼失の1週間前の年末に「昭和の記憶」の事務局長が下関を訪ね駅の昔の写真や資料をお借りして帰ってきていました。もし、それをしていなかったらそれらの写真や資料もみんな今回の火災で灰になっているところでした。一週間前に「昭和の記憶」がそれら貴重な資料を”救い出した”格好になりました。なんという「不幸中の幸い」なのでしょう。今はなき「下関駅舎」。でも、「記憶」は人々の中で生き続けてます。「駅の記憶」、どうぞお楽しみください。
February 19, 2006
コメント(0)
-
元軍人さん
昨日は元軍人さんに来し方を伺いにいきました。軍人さんとのお話しは初めての体験でした。93歳になられていましたがその矍鑠とした振る舞いそして発言の数々今の人々の中にはない何かを感じました。終戦によって価値観が180度転換されたその中で常に大きな命題を抱えられながら生きてこられた方なのだと思いました。歴史を知るということはそういった過去の事実があったということよりもその中で人がどいういった普遍的なことを学び生きる道を切り開いてこられたのかその点を知ることこそが先人の知恵に学ぶところであり一番価値を感じるところです。個人の心のプライベートな部分もちろんそれにずけずけと土足で踏み込む失礼があってはなりませんが全てをお話にならなくてもその行間から読み取れる多くの思いはやはり目の前でお話しを聴かずに知ることはできません。とてもとても大切なお仕事をさせていただけていると心から感謝しています。======「おじいさまの歴史」「おばあさまの歴史」という聴き書き冊子を作らせていただいています。
February 18, 2006
コメント(0)
-
みんなサバイバー
昔「サバイバー」というテレビ番組がありましたが今日はそんな疑似体験ゲームの話ではなくて本当の「サバイバー」のお話し。私たちは全員が「サバイバー」つまり「生き残り」です。みんな当たり前にそうなのですが戦争の話を聞くと特にそれを痛感します。昨日は神風特攻隊だった方の息子さんから8月16日に特攻予定だったものがその前日の戦争終結によって救われたお父様のお話を伺いました。東京大空襲で逃げるみんなと正反対の方つまり爆弾が既に落ちた火の街の中にさらにそこに爆弾が落とされることはないだろうと読んで逃げ、一命を取りとめたお父様を持つ方も友人にいます。朝鮮戦線にいて終戦を知ったと同時にソ連の捕虜になることを真っ先に恐れて大多数がそこに残ったにもかかわらずすぐに戦線離脱をして命のとりとめた人の本も先日読みました。つい一代、二代前の方、つまり私たちの両親や祖父母の世代がその中を危機一髪で生き残った。そして私たちはその「生き残り」として今、この世に生きています。まぎれもない「サバイバー」なのです。その前の数々の戦争大震災大噴火大飢饉疫病・・・それを生き残った人たちだけが次に子供を残しそしてその子供達である私たちも病気、地震、事故、テロ・・・それらを生き残ってこうしてここで確かに生きています。・・・なんていのちは大切なのだろう。なんていのちはかけがえがないのだろう。私たちの想像を遥かに超えた人と人が殺しあう死と隣合わせの戦争を生き残った方たちが手をのばせばすぐそこにまだ沢山お元気でいらっしゃいます。偉人や歴史上の人物ではなくてあなたのご両親、そしてあなたのおじいさまやおばあさまです。とはいえ、戦争をきちんと意識して乗り越えた当時成人していた方々は戦後61年目に入った今、すでに80代。なにを学ばれたのだろう。なにを考えながらゼロから立ち上がったのだろう。聴きたいことは山積みです。「おじいさまの歴史」「おばあさまの歴史」という聴き書き冊子を作るサービスを始めました。みなさまのお話を伺わせていただきながら小説や映画などとは比べ物にならない目の前に座っていらっしゃる生き証人からの直接のエネルギーを頂戴するこんな素敵なお仕事にたずさわれることの感動にそして今日もいのちがあることの感動に毎日毎日感謝しています。
February 12, 2006
コメント(2)
-
2歳5ヶ月の女の子から学んだこと
ロスで宿泊していた友人宅には2歳5ヶ月の子供がいる。こんな天使のように愛嬌があってかわいらしい子供は見たことがないようなほんと、こちらの顔がとろけてしまうようなそんなウルトラスーパースウィートな女の子。どこにいってもみんなの人気者。子供がいない私にとって3泊5日もの連続した期間その年頃の子供と過ごしたことがなくてたった5日の間に彼女がどれだけの新しい言葉を覚えたのかどれだけの新しいフレーズを覚えたのかもう鳥肌が立つような吸収力なのである。初日に言えなかったことが帰るころには言えるようになっていてなんとなく口走ったフレーズも知らないうちに真似されて自分のものにしている。本当に驚異的。・・・でもよくよく考えてみた。0が1になったり、1が2になるとその差に驚くけれど私たちの毎日だって10が11になったり、20が21になったりしながら日々色々なことを学んでいる。本を読んで、テレビを見て、会話を通じてよく新しい言葉は覚えているし新しい概念だって理解している。最初はその女の子に感心ひとしおだったけれどそのうち、そうか、自分も気づかないうちに成長しているのかもと思った。自分たちの力だって見直したい。2歳半の女の子が私たち人間の凄さをわかりやすく見せてくれた。可能性に蓋をしないで自信を持って毎日毎日成長していきたい。この脳みそには、最新鋭のコンピューターだってまだまだ追いつけないのだから。
February 8, 2006
コメント(0)
-
アメリカより帰国しました
皆様、しばらく日記が空いてしまいました。と、いいますのは、昨日までアメリカに出張していました。訪問地はフロリダの西海岸、及び、ロサンジェルスです。とにかく実り多い充実した旅でした。フロリダでは、次回のメールマガジンのテーマ「えっ、私が消え行くサンゴ礁に!?」について取材もしてきました!結構面白いお話しができると思いますのでご興味のある方は是非メルマガ登録してみてください!ロサンジェルスでは、戦争花嫁の方に、彼女の一生をうかがってきました。後世に絶対的に遺していきたい、貴重なお話です。同時に、とても興味を持っていた「信仰」というのものに深く触れるきっかけを頂戴いたしました。彼女からしていただいた無心のお祈りが今でも耳に、そして心に残っています。さて、今週もまた起点を日本に戻して頑張ります。それにしても、こちらの寒さが骨身にしみます。フロリダもロスも連日20度前後のポカポカ陽気でした。でも、四季がある日本が、やっぱり好きかな。
February 6, 2006
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天お買い物マラソンは“買い方”で決…
- (2025-11-19 12:00:07)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- プレッシャーに打ち勝つ方法
- (2025-11-19 07:37:30)
-
-
-

- 楽天写真館
- おやまへゴ~(*^o^)/\(^-^*)
- (2025-11-19 06:38:54)
-