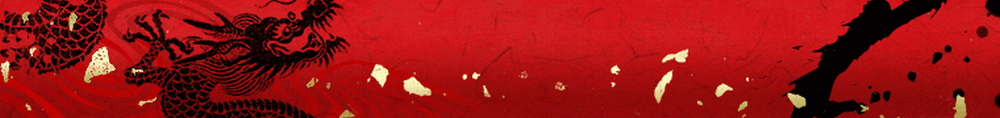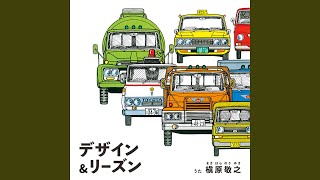2008年03月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
蝶の熱情。
野草園のある大年寺山近辺を仕事で巡った。野草園の入口から仙台放送の方にのびる坂道を歩いていると、ふと、原阿佐緒の碑に出逢った。歌人・原阿佐緒。天与の才能と美貌に恵まれ、情熱的な短歌で歌壇の注目を集めた、そんな女流歌人が仙台に由縁があったんだね~。美貌と言われると気になってネットで調べて見る。う~ん、確かに薄幸の美人という感じ。歌碑には家ごとにすもも花咲くみちのくの 春べをこもり病みてひさしもという一首が刻まれていた。与謝野晶子に認められアララギに入った。官能的とも言える叙情歌が多いが、とにかく、恋多き、波瀾万丈の人生を送ったようだ。東北帝国大学教授石原純との恋愛事件では世の厳しい非難を浴びせられた。傷心と淋しさから逃れるため歌舞伎座近くのバー「ラパン」にマネキンガールとして働いた。市村座の舞台「歎きの天使」に出演、昭和七年には映画「佳人いずこへ」にも主演している。そんな阿佐緒は二冊の日記を遺している。なかに、狂おしいくらい美しい歌が残されていた。生きながら針に貫かれし蝶のごと 悶えつつなほ飛ばむとぞする春の芽生え。一匹の蝶が、野草園の香りの方へ飛んでいった。
2008年03月31日
コメント(0)
-
顔のない愛国心。
縁談好きのおばちゃんが見合いの写真を持ってくる。「あんたも、そろそろ結婚を考える年やろ。いい人がいるで、写真持ってきたわ。」写真を見る。顔の部分がのっぺらぼうだ。「顔が映ってないやん。」「顔? 顔なんかどうでもいいわ。いい人やて。おばちゃん保証するわ。」「え~、顔がわからんのに~。そんなのいややわ。」「あんたそんなに面食いやったん。人間顔やないで~。もう、誰でもいいから、見合いして、とっとと、結婚して!」とうとう本音が出る。いま、新たに、子どもの教育方針に「愛国心」なるものが植え付けられようとしている。いったい、どんな国を愛せばいいのか。そんなわけわからず一方的に愛国心を言う前に、日本がどんな国であるかをしっかり教えるべきではないのか。やちまた道、もともと日本という国が好きではなかったが、最近、やっぱ日本の伝統文化は世界に誇れる素晴らしいものだ!と思うようには、なってきている。日本がどんな表情を持っていたのか。いま、どんな表情をしているのか。これから、どんな表情をしようとしているのか。どんなものにも face to faceで向き合うのが、教育なのではないのだろうか。それとももう日本は、顔のない「のっぺらぼう」になってしまっているのだろうか。
2008年03月28日
コメント(0)
-
返り血を浴びない犯罪。
「誰でも良かった。」最近の犯罪の常套句だ。「誰でも良かった」んじゃない、「誰でもないのが良かった」んだろう。誰?と聞いたら誰々だ!と、レスポンスの返ってこない場所。被害者の顔を見たくない。被害者を生身の人間にしたくない。殺す前に論理的に殺しておきたい。非人称の自分。非人称の相手。非人称の犯罪。非人称の傷口。非人称の叫び。非人称のナイフ。非人称の血痕。そこでは、人間への憎悪も、殺意も、吐き気も、そして悔恨も、すべてきれいに捨象されている。殺される人間から返り血を浴びない、そんな「卑怯」な場所に、現代人はうごめいている。
2008年03月27日
コメント(0)
-
自由のために。
大杉栄は、言った。「…読者諸君とともに、われわれ自身の生活している人類社会の生活を反省したい。(略)この今日の社会においても、われわれがわれわれ自身の生活に顧みて、相互闘争によって得るところよりも相互扶助によって得るところの遥かに多いことがすぐに分る。」「…社会主義も大嫌いだ。無政府主義もどうかすると少々いやになる。僕の一番好きなのは人間の盲目的行為だ。精神そのままの爆発だ。思想に自由あれ。しかしまた行為にも自由あれ。そしてさらにはまた動機にも自由あれ。」現代の人間がどれくらい、「大杉栄」のことを知っているだろう。歴史の教科書には載っていた。クロポトキンや幸徳秋水に影響を受けた「アナキスト(無政府主義者)」。関東大震災のごたごたの中、有名な甘粕事件によって妻の伊藤野枝と甥とともに殺害された人物。まあ、これくらいは知っているだろう。が、その人となりはあまり知られていない。何度も獄中に入るたびに、新たな外国語を覚えたというインターナショナルなやつ。ダーウィンやファーブルを訳したという生物学や進化論にも精通していた。文章もめっちゃくちゃうまい。まあ、とにかく、あの時代の(といっても100年ほど前のことなんだが…)日本人はすこぶるすごいやつがいっぱいいた。アナキストとひとことで言うが、単に国家嫌いとか、政治嫌いという、現代の何も考えていない「ノンポリ族」とは違い、壮大な「生命哲学」を持って権力や体制と戦う自由個人解放戦士だった。平民の自由のために戦った。そして、夢半ばに、権力によってその生命を奪われていった。そんな、革命戦士たちが、日本にもついこの前までいたんだ、という事実に驚く。そして、この時代は大杉栄たちが夢見たような世の中になっているだろうかと思うたびに、ちょっとやりきれない気持ちになる。「…僕らは、この専制君主たる資本家に対しての絶対的服従の生活、奴隷の生活から、僕ら自身を解放したいのだ。自分自身の生活、自主自治の生活を得たいのだ。自分で自分の運命を決定したいのだ。」
2008年03月26日
コメント(0)
-
あるマンションのモデルルームにて。
バリバリの完璧主義で、ちょっと切れキャラで有名な女性インテリアコーディネーターが叫んでいる。「私がたのんだ、赤い椅子がない!」下請けの業者さんが、おろおろしながら言う。「ですから、こちらの椅子なんですが。」「何言ってんのよ、これは茶色の椅子でしょ。私が言ってるのは、赤い椅子。深紅の燃えるような赤い椅子よ。」みんなあきれ顔で見ている。どう見ても赤い椅子だ。ただ、インテリアコーディネーターの「満足のいく赤」ではないようだ。今からだと、新しい椅子を持ち込むのはオープンに間に合わない。で、機転を利かせた女性スタッフが、赤い布を何種類か買ってきた。満足のいく赤を選ばせて椅子にかける。女性インテリアコーディネーターの怒りがおさまり、この場は一件落着となった。やちまた道、すべての不幸の奥に「ない」という感覚があると思う。赤い椅子が「ない」。毛が「ない」。貯金が「ない」。夢も希望も「ない」。丈夫な肝臓が「ない」。彼氏が「いない」。子どもが「いない」。今日着ていく服が「ない」。…みんなそれぞれ満足いかない「ない」に悩んでいる。じゃあ、どうするか。道はいくつかある。「諦める」。あるいは、「絶対に探し出す」。でも、「ある」んだったら、最初から、不幸になっていないし、「諦める」のも、どんどん人間が小さくなるようで寂しい。やちまた道、モデルルームでの教訓から次の提言をしたい。「代わり」を探すこと。求めている「満足の本質」を見極めて「代替」を探すこと。「ない」ものを「カバー」できるものを探すこと。これが、新しい処世術だ。安易な対処法のように思えるが、意外と人間が生きるとは、不断の「ない」に対して、智慧を絞って、努力して、自分だけが満足できる「りっぱな代替物」を探すことのような気がする。なぜなら、人間誰しもなんかかんか「不具者」なのだから…。
2008年03月25日
コメント(0)
-
宴の時は過ぎぬ。
週末、三線の会の宴会。沖縄料理屋にでも、とも思うが、なかなか仙台あたりだと、唄って、踊って、ということができる店がない。それにも、かかわらずみんな酒が入ると、唄うの好きでね~。ということで、思いっきり唄える、いつもの練習場が宴の席となった。やっぱり、みんな唄うの好きだね。八重山民謡という、かなりマイナーだけど、しっかりとした「共通言語」を持っているというのは、すごく幸せなことだ。久しぶりに会っても、どこで会っても、三線があれば、唄がはじまる。沖縄の人とはもちろん、東京の人とでも、大阪の人とでも、八重山民謡つながりで、飲み屋で輪を広げることができる。これが、メジャーな音楽だと、なかなかこうは、いかないんだろうね~。でも、それにつけても、仙台にも、もっと自由に、三線を奏でながら「うたげ」のできる店ができるといいのにね~。
2008年03月24日
コメント(0)
-
いい詩。
いい詩に出逢うことは、いい酒に出逢った幸せがある。最近好きな、小熊秀雄の詩を贈りたい。(声を出して読んだら、きっと、元気が出ますぜ。)「蹄鉄屋の歌」泣くな、驚ろくな、わが馬よ。私は蹄鉄屋。私はお前の蹄から生々しい煙をたてる、私の仕事は残酷だらうか、若い馬よ。少年よ、私はお前の爪に真赤にやけた鉄の靴をはかせやう。そしてわたしは働き歌をうたひながら、――辛抱しておくれ、 すぐその鉄は冷へて お前の足のものになるだらう、 お前の爪の鎧になるだらう、 お前はもうどんな茨の上でも 石ころ路でも どんどん駈け廻れるだらうと―― 私はお前を慰めながらトツテンカンと蹄鉄うち。あゝ、わが馬よ、友達よ、私の歌をよつく耳傾けてきいてくれ。私の歌はぞんざいだらう、私の歌は甘くないだらう、お前の苦痛に答へるために、私の歌は苦しみの歌だ。焼けた蹄鉄をお前の生きた爪に当てがつた瞬間の煙のやうにも、私の歌は灰色に立ちあがる歌だ。強くなつてくれよ、私の友よ、青年よ、私の赤い焔を君の四つ足は受取れ、そして君は、けはしい岩山をその強い足をもつて砕いてのぼれ、トツテンカンの蹄鉄うち、うたれるもの、うつもの、お前と私とは兄弟だ、共に同じ現実の苦しみにある。
2008年03月21日
コメント(0)
-
内なる熱情、津軽手踊り。
津軽手踊りをやられている方のお話を聞いた。津軽手踊り。津軽の五大民謡(津軽じょんから節・ よされ節・小原節・あいや節・三下り)とともに演じられる。じょんがら節などは旧節・中節の2種類に踊りが付けられるらしいが、基本的にはこれだけの数の民謡。いろんな唄に舞踊が付く八重山民謡とはちがい、かなりストイックに伝統を守っているという感じ。見たことはあった。印象は手踊りというだけに、パラパラのような自在な手の動きが印象的。三味線の情熱的な響きに、手の動きで対峙しようというのだから、これは大変だ。…という安易な印象を持っていたが、実は足踊りとも言われるぐらいに足の動きも大切ということを知った。(どんな踊りでも足の運びはとても大切なんだね~。)例えば、常に腰を低く構える。この姿勢を保つだけで大変だ。そして、手が左右交互に動かすのに、足は右、右、左、左、というように手足違う動きをしなくてはいけない、らしい。また、しゃがんだ時も、お尻をかかとにつけず、そしてそこから斜めうしろに起き上がるという、話を聞いているだけでつってしまいそうに、全身の筋肉を酷使する踊りだ。青森の厳しい風土に相まって、激しいリズムを奏でる津軽三味線。その内に秘めた熱情を自分の身体をストイックに酷使することによって表現する手踊り。荒々しく燃えたぎるものを、内に向けて凝縮・昇華していく。踊りひとつにも、北東北の風土や人間味がにじみ出ているようで、面白い。いや~いろんなところに奥深い伝統芸能があるものだ。
2008年03月19日
コメント(0)
-
復讐するは…。
人間は、昔、大きな動物たちに喰われていた。新しい化石調査や霊長類研究により、一般に思われている「人類=狩猟者」のイメージを打ち破る世界観が生まれているらしい。まあ、確かに、走りが速いわけでもない、飛べるわけでもない、力が強いわけでもない。丸腰で戦ったら、負けるわな。現代だったら、想像できないことだけど、普通に、人間どもがいっぱい喰われるシーンがそこかしこにあったわけだ。そんでもって、大きな動物たちに仕返しをしてやろうと、「頭」を使ったわけだ。「知は力なり」と近代哲学の祖ベーコン先生は言った。しかし、知というものが、こんな血なまぐさいところから生まれたとしたら、そんなきれいごとではすまないだろう。やちまた道、もっとシビアに「知は復讐の力なり」と言ってしまおう。(北村透谷は「人間の心界に、頭は神にして脚は鬼なる怪物棲(す)めり。之を名(なづ)けて復讐と云ふ。」と書いた。天才北村透谷、実に素晴らしい洞察力。)まさに、DNAの記憶の中に、この復讐の香りが漂っている。人間どもは復讐すべき敵がをいるときに、頭が冴え、狂気のような力を持つ。復讐は新たな復讐を生み、そして復讐の連鎖が生まれることになる。人類の歴史は、そんな復讐の歴史だとしたら、寂しいものだ。
2008年03月18日
コメント(0)
-
お江戸帰り。
4時半起き。6時に神田駅を探して彷徨っていたのが昨日のことのように、杜の都・仙台にて定刻どおり会社出勤。月曜、東京からの出勤は、いや~、眠い。昨日の酒が残ってる~。東京での1日目。特にすることもなく、浅草・浅草寺あたりをぶらぶら。(やちまた家、東京に行くといつも浅草や上野あたりになってしまうな…)街の細部まで、いろんな顔がある。そんな襞のある街は歩いていて面白い。江戸の資料館みたいなところに行く。(あすの八重山民謡の会場も江戸資料館。江戸づいてますな~)東京に江戸文化。当たり前なんだけど、やっぱり、ひとつの都市が、何百年もの時代を席巻したというのは、良く考えるとすごいことかも知れない。で、2日目。八重山民謡の東京での発表会に仙台からも何人か参加させてもらった。唄だけで、2時間。仙台だったら、踊りを入れないとお客さん寝ちゃうんじゃないか、と思うが、そこは、花のお江戸。皆さん、八重山民謡のこともよ~く知っていて、始まる前から、この唄はどうだ、あの唄も聞きたかった…、とか言っている。仙台だと、とりあえず沖縄民謡を聞きました~というお客さんが殆どだから、この違いは、やっぱりうらやましく思ってしまう。普通は座開きである「赤馬」を最後に。目からうろこ。みんな気持ち良さそうで、これは新鮮。う~ん、良かった。唄に聞かせる力があれば、唄だけで演奏会が成立する、ということを教えられた、お江戸の旅であった。
2008年03月17日
コメント(0)
-
心ここにあらず。
やちまた道、たまに人の話を聞いていないらしい。ほんじつ朝、「心ここにあらずね」とカミさんにつっこまれた。自分の方こそ、聞いてないことが多いのに…、と思ったが、ちょっと面白いので「そうなんだよ、心ってここになくてもいいんだよ」とわけのわからんことを言い返してやった。鳩が豆鉄砲をくらっていた。しかし、きっと、たまに、ほんとうに、心はここになくてもいいと、思う。だからこそ、肉体がどんなに離れていても、心と心は、出逢うことができる、のではないでしょうか。出逢いと、そして旅立ちの春に、乾杯!
2008年03月14日
コメント(0)
-
3つの嫌いなもの。
良寛さんは言った。自分には3つの嫌いなものがあると。「詩人の詩、書家の書、料理人の料理。」そして、「誰か我が詩を詩と謂う 我が詩は是れ詩に非ず」と書いた。自然に即し、素朴でまっすぐなることを愛した良寛さんは、いわゆる「プロ」の技巧に走ったものが嫌いだったんだろう、か。敬愛する良寛さんにならって、3つ嫌いなものあげてみよう。愛犬家の愛犬。(犬にゃ罪はなかろうが…)日本メジャー系ミュージシャンたちのメジャー系ミュージック。(誰?)そして、政治家の政治。小田実は、ガンに侵された身でありながら、病床からも、ずっとかわらない信念で、「市民の市民による市民のための政治」を訴えて、そして散っていった。 うらを見せ、おもてを見せて、散るもみじ 良寛さんの辞世の句は、小田実にも美しく共鳴する。
2008年03月13日
コメント(0)
-
春、田植え踊り。
週末、田植え踊りを見に行った。昨年獅子踊りや剣舞を見たのと同じ、民俗芸能のつどいだ。田植え踊りも、素朴ではあるが、民俗芸能を形づくる重要な芸能のひとつ。ここ宮城県も各地で伝承・継承されている。いくつかの保存会の方が披露されていたが、共通している部分は、「弥十郎」という男衆と「早乙女」という女衆が出てくること、かな。「弥十郎」は道化の役なのか、ひょうきんに踊っている。「早乙女」は田植え踊りらしい、華やかな衣装で優雅に踊っている。…が、どうもみんな身体がごつい。パンフレットを見ると女装と書いてある。そうか男か…。だまされた気分だが、まあ、これはこれでユニークだ。八重山舞踊だと、男が女装して踊るなんてことはめったにないが、この女装は昔からなんだろうか…。ひばりの鳴き声が聞こえてきそうな、のんびりした空気が流れている。田植えの季節には普通にあった光景なんだろうな~。芸能と言われるものの中で、一番「芸能」っぽくない素朴なものなのかもね~。芸能を見ているというよりは、郷愁を誘うような田園風景が目に浮かんでくる。観客を見てみると実に年齢層が高い。まあ、民俗芸能だからしょうがないとも思うが、昨年の獅子踊りや剣舞の時は若い人も含め満席という感じだったので、「芸能好き」な若者にも田植え踊りはちょっと不人気なのかも知れない。田植え踊りのような、素朴なものこそ、大切に受け継がれなくてはいけないように思うのだが…。
2008年03月12日
コメント(2)
-
国民詩人。
昔、日本文学を勉強しに来ているロシア人の女性に聞かれたことがある。「日本ノ国民的詩人ハ、ダレデスカ? ワタシの国には『プーシキン』ガイマス。」「国民詩人」か。考えたこともなかった。ギリシアではホメーロス、ローマではヴェルギリウス、イタリアではダンテ、イギリスはシェークスピア、ドイツはゲーテかヘルダーリンか、アメリカではホイットマン…か。みんな誇るべき「国民詩人」を持っているわけやね。ただ、あのころは、「国」なんて言葉が嫌いだったし(今も嫌いだが)、一人の声が国を代表するなんてことも嫌いだった。「いや~、日本には、国民詩人ってのはいないような…」と曖昧に答えると、「いない、デスカ?」といぶかしげに見ていた。もちろん、日本にはいっぱい世界に誇る詩人がいると言いたい。芭蕉とか藤村とか白秋とか…。でも、「国民詩人」というと違うような気がする。あれから、何年か過ぎて、いろいろ考えた結果、「とりあえず」いまのやちまた道の結論。「どうしても答えろというなら、やっぱ万葉集かな~。」柿本人麻呂とかヒーローはいるけど、やっぱ庶民的な東歌だったり、防人の歌だったり、「読み人しらず」も入った、あの万葉集全体が「国民詩人」なのだ。一人の詩人の声が代表するのではなく、あまたの声が創り上げる世界。まさに、ポリフォニー(多声)的な森羅万象の詩の世界。そこにあるのは「編纂・編集」という方法論だ。編纂詩・編集詩が日本の詩の伝統なのだ。複数の人間で和歌の上句と下句を繋げていく連歌などもそうだ。その象徴として万葉集がある。ただ、しっくりしない部分もある。「そこには編纂・編集によって抹殺された声もいっぱいあったはずだ」ということ。ここまで来ると「国」とは何か、ということになる。残された言葉から、その声たちを思い描くしかない、のかな…。
2008年03月11日
コメント(0)
-
ころびすぎで、本末転倒。
やちまた道、若いころ、友達に誘われて、いやいや(?)サーフィンをしたことがある。道具を一式揃えて、湘南の海に出かけたものさ。一度、台風が来ているとき、「よし行くべ!」という友達の言葉に「え~」といやいや(?)出かけた。浜に着くと地元のにいちゃんたちが、「こら、素人が、こんな日に海に出るな!」と怒ってくれて、そのまま帰ることができた。(ありがとう。にいちゃんたち!)とにかく、一度も立てなかった。波にさらわれ、水中でぐるぐると回ること何度も。苦しくて上に出ようとするのだが、どっちが上か分からない。死ぬかと思ったこと何度も。この時得た教訓が、人間あまりにくるくる回っていると、どっちが上か、方向が全くわからなくなってしまうということだ。(ありがとう、サーフィン。ありがとう、湘南の海。)この前、ニュースでこんなことを言っていた。地球温暖化のせいで、山中湖の氷が張らなくて、自慢のワカサギ釣りができなくて困っているとか。そこで登場したのが、屋形船。船の上からワカサギ釣るんだね~。「船内は暖房が効いていて、温かくて、快適ですよ~」とリポーターが言っていた。暖房付きかよ。地球温暖化でワカサギ釣りできなくなってるのにね~。現代日本人は、あまりにくるくる回り過ぎて、どっちが上なのか、どっちが頭なのか、どっちが正しいのか、どっちが向かうべき方向なのか、分からなくなっているのかも。
2008年03月10日
コメント(0)
-
ゴキブリを見たら。
ゴキブリを1匹見たら30匹はいると思え、と昔から言われる。確かに、0匹と1匹の差はめちゃくちゃ大きいけど、1匹も2匹も30匹もそうかわりゃーしない。1匹いた時点で1匹しかいない可能性の方が低くなるだろうな~。同じことが生命体全体にも言える。人間が1匹いた時点で、宇宙人が30匹はいると思った方がいい。宇宙中に人間のような生命体がうじゃうじゃいるなんて愉快だ。この論理を広げれば、この世に人間が1匹いたら、あの世にも人間がうじゃうじゃいてもおかしくないような気がする。いつか、宇宙人と、そしてあっちの世界にいった人たちと、宇宙的大宴会で飲み明かせたらおもろいのにな~、と思う。逢魔が時、みんな集まれ、今夜だけは…♪ by ソウル・フラワー・ユニオンでも、最近、ゴキブリ見ないね~。
2008年03月07日
コメント(0)
-
おっ、いっぱいあるやん。
キーワードを入れると、全世界の調べたいことが出てくるインターネットは便利なものだ。便利な分、怖い部分もある。例えばこんなことはないだろうか。普通に考えたら関係のないような、AとBとCを入れて複合検索する。と、だいたい何かしら出てきて「おっ、いっぱいあるやん」となってしまう。そうすると、何かしらAとBとCに関係があるように思えてきてしまう。(本当はすっご~い偶然のような件数しかないにもかかわらず…)そんなことを何回かしているうちに、AとBとCの関係性は誰もが認めることとして、自分の中で「常識」としてまかり通るようになってしまう。これはもしかしたら面白い発想が生まれるかも知れないが、反面、何の因果関係もないことが真実だと思うようになってしまう危険性もあるわけだ。気を付けたし。
2008年03月06日
コメント(0)
-
夢の論理。
わけのわからない夢を見る人がいる。うちの義理の姉は、石になった夢を見た、とか。ずっと、石になって、じっと何かを待っていたそうだ。夢の世界ははちゃめちゃだ。いわゆる論理から逸脱している。普通の論理だとこうだ。動物は動く。人間は動物だ。だから、人間は動く。主語の同一性から導く一般的な主語論理だ。でも、義理の姉の論理はきっとこうなのだろう。私は動きたくない。石は動かない。だから、私は石だ。いわゆる、述語論理。述語側の同一性を「願望」して論理が進む。論理の中に「願い」や「祈り」が入ってくるのが、述語的世界の面白いところだ。夢というのは「私」という主語の同一性から解き放たれ、「私」のいない「無」という豊穣な述語の海の中に浸ることのできる希有の時間なのかも知れない…。こういった論理は神話的世界や原始社会などでもよくあることだ。例えば、ライオンは獲物をとるのがうまい。私は獲物をうまくとりたい。だから、私はライオンだ。こんな感じでトーテミズムが生まれるのかも知れない。はちゃめちゃだけど、がんじがらめの現代の論理社会よりは、とても夢があって面白い世界像だ。
2008年03月05日
コメント(0)
-
わかり合うということ。
古来から、比喩で使っている言葉には、実は深い本質を突いているものがある。「波長が合う」という言葉。その人と気があったり、趣味があったり、考えに共感を持てたりして、「わかり合えた」状態を示す言葉だか、社会におけるコミュニケーションを考える上で実に示唆のある言葉である。とりあえず人間で考えよう。人間にそれぞれ、生体を貫く「波」というか「振動」というか「リズム」みたいなものがある。これは固有の「波長」があるのであり、出会った瞬間は、波長があわずとまどう。ただ、そえぞれが歩み寄り、聞き耳を立て「チューニング」することにより、波長があうようになると、心地よいハーモニーというか「共鳴」「共振」「反響」を生み出す。これが「わかり合えた」状態だ。ここで重要なのは、決してそれは言葉だけの「比喩」ではないということだ。そして、これは、人間だけでなく、動物や植物、もっと言えば芸術作品、石ころ、風、社会や機械やシステムなどにも言えることではないか、と思っている。街にいて、心地よいと思う。これは、街の波長とぴったり合っている状態を示すのではないだろうか。いま仙台の街はケヤキが切られて、なんか街の風景としっくりこない。(仙台弁でいうと「いづい」感じがする?)なんか今まで合っていた街の波長がズレてきているように思えて仕方ない。街が破調をきたしているのか、あるいは意気消沈して(?)リズムを奏でなくなっているのでは、とも思ったりする。街と、森と、自然と、わかり合えなくなりつつある。
2008年03月04日
コメント(0)
-
着々と。
週末、市の用地課の人が家に訪ねてきた。アパートの立ち退き料の提示のため。着々と事が進んでいるようだ。提示のあった金額は、まあ、この金額以下だったら文句言おうと思っていた額はなんとかクリアしていた。(ただ、今のアパートの敷金が戻ってくるかどうかは、市としては何とも言えないとのこと。このあたりは不動産屋さんや大家さんとの交渉が今後必要になるので、万事問題ないかどうかは今後の動き次第か…。)とりあえず、ほっとした感じだが、冷静に考えてみるとやちまた家だけにこれだけの金額がかかるとなると、アパート全体を立ち退かせるのにいくらお金がかかるんだろうね~と思ってしまう。このアパートだけじゃないから、全体の道路用地取得には、相当にお金がかかることは予想がつく。この前、ドイツの道路建設費に対し、日本の道路建設費が何倍もかかることが問題にされていた。詳細はわからないが、こんな狭い国に道路を造ろうとすると、いろんなものを「どかす」ことをが必要になるので、お金も莫大にかかるんだろうね~。街の方では地下鉄工事のための青葉通りのケヤキの伐採と移植がすべて終わったみたいだ。さすがに、出勤途中の人たちもちょっと驚いたような顔で通りを見ている。街路樹を伐採すると、やちまた道的には、自然破壊の一端だと思ってしまうのだが、街を創るときに「人工的に」植えた街路樹なんだから、自然破壊ではない、という意見もあるのかも知れない。言ったとして「第二の自然」・「第三の自然」というもので、人間が自由に制御できるもの、というわけか…。街にはもう「第一の自然」はないのかも知れない。
2008年03月03日
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1