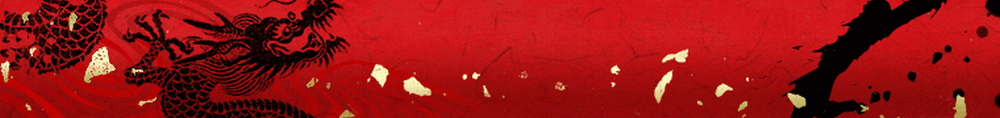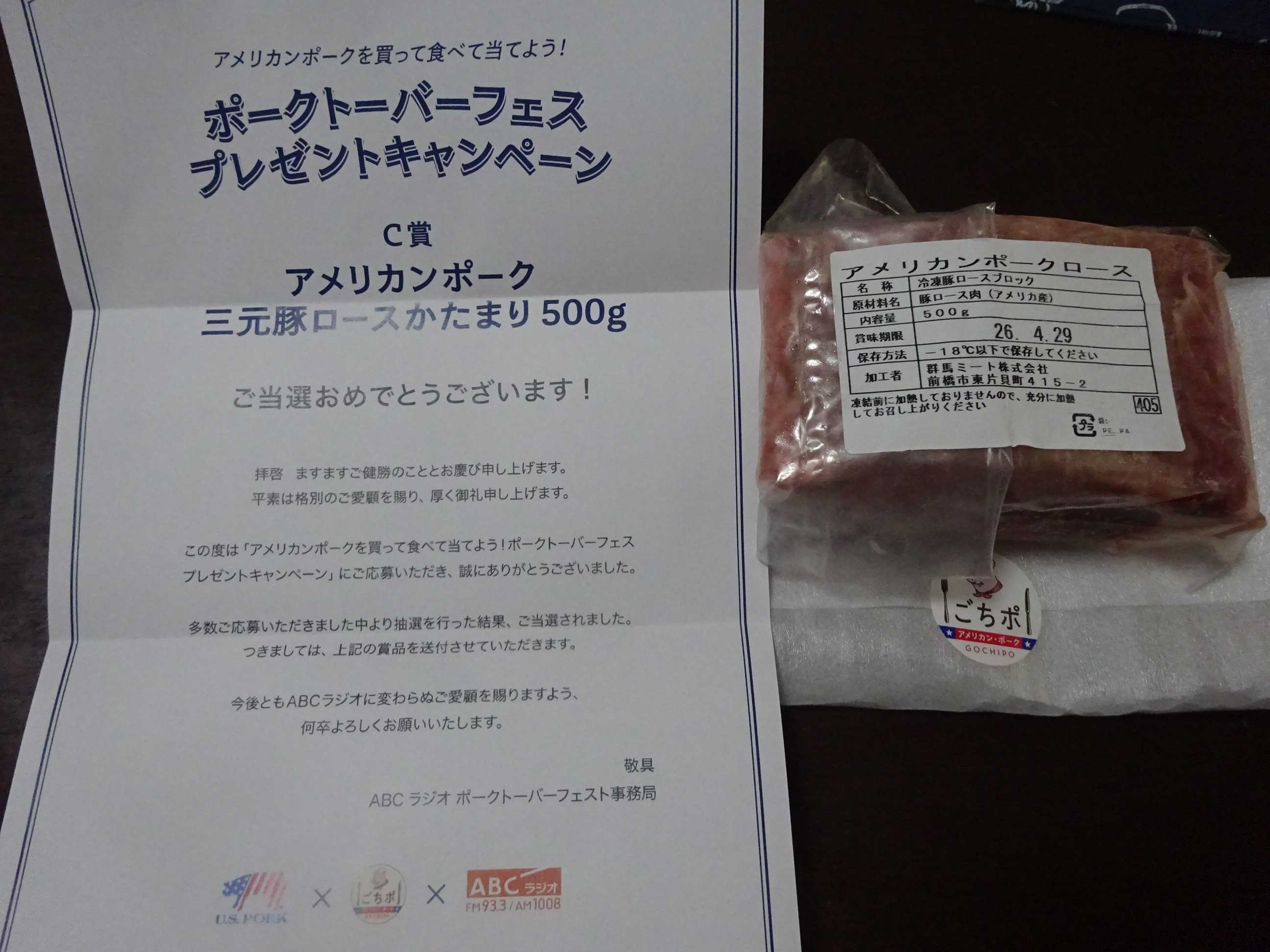2008年09月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
記憶の観覧車。
う~っ、寒くなってきた。寒くなると、脳裏に浮かぶのが、北の町。八戸も懐かしい町のひとつだ。八戸という一番に想い出すのが、八食センター。東北一じゃないか、というぐらいのでかい魚市場があった。威勢のいいかけ声。新鮮な海の幸が安い値段で出ていた。最近、八戸に転勤になっている人と話をした。八食センターの話をするとすぐに話が盛り上がった。やっぱり今でも八戸の台所として機能しているんだ。しかし、ある言葉で、急に行き詰まった。「八食センターに観覧車があるよね?」「観覧車?そんなのありません。」「いや、あるよね、でかいの?」「それいつの話です?いまありませんよ。」話を聞いていたみんなも、魚市場に観覧車なんかないでしょう~、という顔。いや、いや確かにあったんだが…。ということで、自信がなくなってきたので、本当にあったかどうか、ホームページで調べてみる。しかし、調べても調べても昔八食センターに観覧車があったなんて記事は載っていない。う~ん、どうなったんだろう。いよいよ気になる。八戸全体にある観覧車を探す。でも、現時点で観覧車があるなんてどこにもない。夢だったんだろうか。それとも、北上のカミさんの実家のすぐそばにある観覧車とごちゃごちゃになったのだろうか。もしかしたらと思い「八戸 観覧車 廃止」で調べてみる。おっ、あった。あった。イオンモール下田というところに、昔大観覧車があったみたいだ。そのイオンモールから八食センターは近い。これで記憶がごちゃごちゃになったんだね~。でかいイオンモールとでかい八食センターで、ごちゃごちゃになったんだね~、ってみんなになんて言えばいいんだろう…。とても、みんなには言えないので、みんなには八食センターに昔、大観覧車があったと思い続けてもらおう。昔、よく行った町がどんどん記憶の遠くに行ってしまう。観覧車のように、また戻ってくればいいのに…。
2008年09月30日
コメント(0)
-
切なき秋の恋模様。
突然、名古屋の兄貴が、仕事の関係で本日静岡へ引っ越すこととなった。(今年1年で兄弟そろって引越しか…)さすがに、何年も住んでいた場所から出るのは、感慨もあるだろう。まあ、そうは言っても、後ろ向きに考えてもアレだし、自分の経験から言っても、新しい場所には新しい場所の良さがあり、楽しむ気があれば、結構充実した生活も送れるはずだ。本人も意外とサバサバしていた。ただ、若干心配なのは親父だ。「お義父さんが、恋をしました」事件以来、なんか電話する気になれず、話をしていなかった。昨日めずらしく夜遅く、向こうからかかってきた。やちまた道、電話に変わる気がしない。カミさんがずっと話を聞いている。ようは本人自体は籍を入れたい感じだ。というか、養子になって向こうの家に入ってもいいなどと…。(別に苗字が変わってもええわ、などと…) そして何よりも驚きが、やちまた道と10才しか違わないということ…。(う~ん、ここまで来ると、常人のやちまた道には、ついていけない。)1周忌を前にして…。兄貴が引っ越すことも関係しているのか…。この先、小栗印伯人には、喜劇が待っているのか、悲劇が待っているのか。どうしたらいいんだろうね~。なんか、切なくなってきた…。
2008年09月29日
コメント(0)
-
泡の宇宙。
意図せず、この世に吹き出されるシャボン玉。それでも、希望のような虹の光に包まれ、様々なものを映しながら、空へと向かう。しかし、その夢ははじけ、美しくも、儚く、消えていく。まさに泡沫(うたかた)の夢。泡は、気体なのか、液体なのか、固体なのか。きっとどれでもなく、まさに幻なんだろうね~。宇宙は、重なり合ったシャボン玉の泡のような構造になっているらしい。宇宙にひろがる銀河の空間分布を数億光年以上のスケールで眺めると泡のような構造がみられ、銀河は泡の膜にあたる部分に分布していると言う。「泡宇宙」と呼ばれる宇宙の大規模構造だ。銀河は、神様が吹いたシャボン玉ということか…。今宵、宇宙の泡たちは、ビールの泡とまみれながら、泡沫の夢を見るとしよう。「愛を総動員して、声あげろ。」 by ソウル・フラワー・ユニオン
2008年09月26日
コメント(0)
-
わかもの、ばかもの…。
新しいビジネスを生み出す!みたいなセミナーに出席した。仙台あたりも、不景気を吹き飛ばして頑張っていかなくちゃ! …という企業が増えているのだろうか。こういうセミナーも盛況をみせている。面白いと思った一言。新規企業をつくったり、新しいまちおこしをしたり、何か新しいプロジェクトを成功させるには「3つの人材が必要だ!」というくだり。「わかもの」に、「ばかもの」に、「よそもの」の3つだそう。なるほどね~。若い発想が必要だ。奇想天外な意見も必要だ。第三者的な視点も必要だ、ということか。確かに安易にプロジェクトを成功させようとすると、どしても、同年代で、常識的な人を揃えてしまって、「同化」してしまう。うまくコトは運ぶが、結局のところ、なんの面白くないできあがりになってしまうことが多々あるものだ。(そして「同化」は「風化」を呼ぶ…。)そこで、わかもの、ばかものと言った、異質な人材の登用。人材に幅がでると、自然と面白い発想が生まれてくるものかも知れない。…となると、一番大事なのは、「わかもの」「ばかもの」「よそもの」をうまくとりまとめる、求心力のあるリーダーがやっぱり必要だということかも知れない。
2008年09月25日
コメント(0)
-
しょうげき!昌益。
反逆のレジスタンス。江戸時代の北東北にあって、これほど、炎の言葉を吐き続けられた人間がいたとは驚きだ。「安藤昌益」。在日カナダ大使・ハーバート・ノーマンによって「忘れられた思想家」として世界にも紹介された。すべての既成の体制や思想や宗教を罵倒しまくった。昌益は大いなる「否定」の人だった。社会制度、身分、宗教、道徳、為政者、商業、貨幣、文学、芸術、学問、その他ありとあらゆる現存秩序を「私作」なものとし、罵倒しまくった。すべては聖人つまり支配者層にとってのみ都合の良いものだ。君主は盗人だ。聖人と言われる人間も盗人だ。老子も孔子も仏陀もみんなウソぱちだ。聖人たちによって形成された社会を「法世」とし、自らが目標とした万民が農業に従事する平等社会を「自然世」とした。マルクスに先んじて何百年。これだけ、封建社会の中にありながら、反逆の言葉を投げつけられたという事実に圧倒される。それだけじゃない。宇宙観もいい。自然を「ひとりする」と読む。宇宙を「転定(てんち)」とする。そして転定宇宙は活き活きとした真である「活真」の直耕であるとする。「自然による直耕」と「人間による直耕」。廻る天(転)と、動かぬ海(定)。その間にあって、そこに人間が生息し、その大地を耕して穀を食んでいる。活真が通横逆としてこの転定を廻るとき、そこに穀物、男女(ひと)、四類(鳥獣虫魚)を生み出す。う~ん。とにかく圧倒される、思想であり、文体だ。こんな人を生み出した東北大地。あらためてすごいと思う。
2008年09月24日
コメント(0)
-
おいしい学園祭。
日曜、近所を歩いていると、人だかりができている。調理師専門学校の学園祭。学園祭と言っても、調理師学校だけあって、本格的なレストランやカフェの模擬店がでている。お昼時に、こんな場所に出逢えるなんて、ラッキーだ。やちまた家、さっそく学園祭に行ってみる。そとのオープンレストランはいっぱいだ。本格的な窯でピッツァなんか焼いているから、目を引くだろうな~。中のビュッフェに行く。こちらは立食形式。好きなもの取って、最後に精算するという感じ。一般のおじさん、おばさんも含め、こちらも大盛況。やちまた家、子羊のソテー(?)みたいなのに、ちまき、肉まん、さんまのつみれなどを選ぶ。なかなか、どうしておいしいではないか。さらに上階に行くと、蕎麦なんかも出している。伊達家の殿様の料理を再現したコーナーもある。ケーキもある。(こちらも、手作り感満載で、おいしかった!)ふつうの学園祭のように、ちょっと名の通ったバンドやタレントを呼んで、やきそばなんかを出している学園祭に比べると、勉強していることと、学園祭で出す内容がうまくリンクしていて、これは身のある勉強をしているな~と思う。減価計算から、買い出し、飾り付け、調理から、サーブ、皿洗いまで、ふつうのレストランでやることを学生たちだけでやっているんだから、エライ。食の安全が叫ばれ、自給の必要性が叫ばれる昨今。いわゆる「食育」というのは、どんな学問よりも一番重要にされるべきじゃないか。こんな調理師学校みたいなところから、次の時代の「食」を支える若者が出てきてほしいもんです。そのためにも、ウソと自分勝手と偽装に包まれた大人たちの「汚食文化」をキレイに浄化しないとだめなんだろうね~。
2008年09月22日
コメント(0)
-
共生と共死。
秋田の人にあうと秋田のことを想い出す。とくにこの季節、頭の奥の方に残っている暗く深い森の映像が、もの悲しいような郷愁をさそう。熊谷達也のマタギの本を読んだ。阿仁のことなどが克明に書かれていて、なつかしい。印象に残った言葉。現在の「共生」という思想の根底に「共死」の思想がないのがいけない、という。確かにそうだ。限られた地球、資源の中で、生きるものもいて、死ぬものもいるからバランスがとれている。「共生」というひとつの方向性だけでいっしょにやっていこうなんていうのは、キレイごとでひとりよがりすぎるのでは…。共に生き、共に死ぬ。いただける時はありがたくいただくが、譲る時が来たら潔く譲る。そんな覚悟みたいなものが我々現代人にあるかどうか…。
2008年09月19日
コメント(0)
-
余韻3。
…わが三線の会、伝説のクライマックスが始まった。八重山の芸能の定番、まみどーま。鎌、鍬、ヘラを持ったメンバーが舞台袖から列を組んで歩きだす。(おしゃれなアーケード街を鎌、鍬をもって踊るオモシロサよ…)知っているお客さんから手拍子も出る。…と突然、「あっ間違えた!」という大声。先頭のカミさん、何を考えたのか、波を押し戻すように引き返す。なに? 他のメンバーもえっ!という顔。どうした? どうした? …そうか、種まきが先に出なくてはいけないのに、先に鎌、鍬、ヘラがでてしまったんだ。(種まいてないのに、収穫できまへん。) 会場から笑いが起こる。気を取り直して、種まきが出て踊る。その種まきに呼ばれて、再度、そしてなにもなかったようにすまし顔で鎌、鍬、ヘラが出てくる。会場はもう笑いの渦だ。間違えた張本人のカミさんは、なぜか「おっす!」とばかりに会場に鎌で挨拶している。(いかりや長介か!)もうこうなると八重山民謡というよりは、吉本新喜劇だ。全員集合だ。種まきが恒例の飴を巻くサービス。どよめきが起こる。鎌、鍬、ヘラの踊りが終わり、最後種まきが閉めの踊り。会場からあたたかい拍手。(不幸中の幸いで大いにもりあがったね~。)…とここで、ポツリとくる。う、雨だ。(アメまいちゃったからね~)次の演目はクイチャー(巻踊り)。いやな予感。前にも書いたが、「クイチャー」は、みんなで輪になって踊る、雨乞いの踊りだ。クイチャーが雨を呼んだんだね~。雨はどんどんひどくなる。(だって雨乞いしてますもん!) もう土砂降り状態。観客はアーケードの方に避難。こちらは、やめるわけにもいかず、踊りをつづける。そしてカチャーシーへ。ずぶ濡れ、もうやけくそ状態で踊りまくる。ウッドストックばりの伝説のライブとなった。最後、しっとり雨音を聞きながら、みるく節。映画のエンドロールのように心に沁みいる唄。雨乞いで雨が降るように、種まきで芽が出るように(?)、きっとなにかしら「願ったことは叶う」と昔の人と同じように唄い、信じ、そしてへこたれずに生きていきたいもんです。そして、わが三線の会のジャズフェスは終わった。万難を排し、わざわざ、来てくれた人、観てくれた人に、そして、観れなかった人にも、幸多かれ、と思う。
2008年09月18日
コメント(2)
-
余韻2。
そして、わが三線の会の伝説のライブがはじまった…。最初は、「赤馬」。う~ん、しぶい。アーケード街をめっちゃしぶい八重山民謡の斉唱で制覇する快感。そして、「じっちゅ」。ほんとうは10人で踊るが、今回は4人。一人2.5人分の笑顔。片袖を出した白い襦袢が、天女のような(笑)みやびな印象を醸し出す。終わった後、「ほお~」みたいな感嘆の声があがったのは、長いわが三線の会の歴史の中でもあまりない経験!「川良山(かーらやま)」。男だけの演奏。今までだと、ちょっと渋すぎるか、と思っていただが、なかなか心地よいうねり。手拍子も自然にあがったのが、うれしい。まわりの子どもたちも唄に合わせて踊ってくれている。唄と踊りが「同じ根っ子」でつながっていることを、大人より子どもたちの方がよ~く知っている証だ。ゆんた。メンバーのかけ声もよく出ている。一様でないかけ声。それぞれ思い思いのかけ声が重なる。ポリフォニー(多声的)で、とてもアジアの海人(?)な感じが出ている、と勝手に感心。そして、「しょんかね」、「安里屋ゆんた」、「月ぬかいしゃ」、と続く。唄と踊りの切り替えもスムーズ。40分の中でこれだけ場面転換があるのもわが三線の会の特徴だろう。MCも気負いがないゆるい感じで心地よい。10月に行われる発表会の告知までしちゃったりして…。みんな笑顔で聞いてくれている。ジャズフェスはあったか~いお客様に囲まれてほんとうにありがたい限り。そして、いよいよフェナーレへ突入。定番中の定番、「まみどーま」。常連のお客さんたちも「まみどーま」がお好きなよう。うれしそうだ。鎌、鍬、ヘラを持ったメンバーが歩きだす。ここから、わが三線の会の伝説のライブ(?)が伝説のクライマックス(??)を迎える…。 (そして余韻は、さらに新たな余韻へ。(えっ~!?))
2008年09月17日
コメント(2)
-
余韻1。
余韻と言う言葉は、秋にぴったりだ。夏のざわめきの残響。心地よくもあり、心寂しくもある。やっぱり、いまやジャズフェスは、仙台一番の祭りになっているような気がする。3連休もあって他県からも来ているのか、かなりの人手になっている。ジャズフェス1日目、知り合いが出している純米酒BARに顔をだす。というか、開店前の一番乗り。先着30名様に500円のきき酒3種類が4種類というサービス。その時点でカミさんノリノリ。朝からつまみもなく日本酒だけで飲めるのかと思ったが、意外ときりりとして飲み口がいい。特にスパークリングな「すず音」というのが異様に美味しかった。みんな頑張って売り子に徹していて、う~んすごい、と思ってしまった。次にこれまた秋田時代の知り合いが出るウクレレを観に行く。いつ聞いても心地よい音色。新曲(?)にもかなりチャレンジしていてこちらもまた、すごいと思ってしまった。そして、毎年恒例のアイリッシュを2組立て続けに聞く。同じアイリッシュでも編成によってかなり曲調や雰囲気が違う。こちらもまた、秋の風にぴったりのハーモニーを奏でていた。どうも、やちまた家にとってのジャズフェスはアイランドミュージックフェスになっているよう。島の音楽の素晴らしさを堪能できる2日間となっている。夕方から、わが三線の会の練習。明日の出番に向けていい雰囲気に盛り上がってきている。そして、夜。秋田のウクレレチームの飲み会に途中参加。仙台にもハワイアンのバーがあるんだね~。秋田のメンバーの演奏に、店のマスターの演奏、そして踊りなど、ウクレレを楽しませてもらった。(沖縄民謡にも唄えて、踊れる店があればいいのにね~。そういう意味ではまだまだ、沖縄民謡は仙台には浸透していないのかも知れないね~。)そして、2日目。一時は100%まであがった雨の心配もなさそう。よしっという感じで練習場に向かう。メンバーもかなり場慣れしてきているのか、とくにキンチョーした風もない。良い感じだ。いよいよ、演奏ステージの方に向かう。人が賑わうアーケード街で、10人もバサーを来ていれば、目立つ目立つ。何時からですか?といろいろ声をかけられる。良い感じだ。風も吹いてきた。そして、わが三線の会の伝説のライブ(?)がはじまった…。 (そして余韻は、さらに続く。(え?))
2008年09月16日
コメント(0)
-
ユーリー・スコット教授。
今、20世紀少年で名をなしている浦沢直樹の漫画「マスターキートン」。考古学者でありながら、普段は保険調査員として働いている主人公のキートンが様々な国で起こる事件を解決する。想い出深いシーンがある。恩師である考古学のユーリー・スコット教授。焼け野原になった戦場で言う一言。「どんな所でも勉強はできる。さあ、授業をはじめよう。」強い意志さえあれば、どんな所でも、生きる価値は見つけ出すことはできる。
2008年09月12日
コメント(0)
-
自己複製への意志。
生命とはなにか。ずっといろんな思想家や科学者を悩ませてきた問題。ずばっと、正面切ってひとことで言い表せないけど、生命あるものと生命のないものとの違いはいくつかあげられるらしい。自己複製をするということ。いろいろ新陳代謝するけど、個体として同一性を保持していること。時間とともに成長するということ、など。人間は1年ですべての分子は入れ変わるんだってね~。1年前のやちまた道と、今のやちまた道はまったく違う素材でできているということだ。それでも、同じようにスーツを着てしがないサラリーマンをしている。これは生命のないものではありえないことだ。「自己複製」というのはなんとなくわかるね~。生命の設計図であるゲノムとしてのDNAはまさに自己複製の名手。生命維持に必要な物質を作り出し環境に適応しながら自己維持や自己複製、増殖などを行う。そして自分というものを子孫まで伝えていく。しかし、ここでひとつ疑問もある。自己複製は、目に見えるカタチあるものだけのことだろうか。「個体の自己複製」だけが生命活動だろうか。日々日常の営み全体がある意味で自己複製への意志の現れではないだろうか。カタチだけでない、想いや思想やクセなどの自己複製もあるのでは。例えば何かを教えるという行為。これは、他の人に自分の技能や知能を自己複製していると言っていいのでは。目に見えない、個体を超えた「自己複製」というものも生命の大切な営みとしてあると思うのだが…。
2008年09月11日
コメント(0)
-
しょーぎ革命。
将棋というのは、実に人生を教えてくれる、すぐれもんのゲームだ。取られた駒も、復活する。まるで東洋的な輪廻転生を示しているよう。本質的に敵も味方もない。誰しも、敵にもなれば味方にもなる。歩も香車も敵陣に入れば、成金になれる。成金になっちゃえば、前の職がなんだろうといっしょ。絶対的平等精神に則っている。…と、人生教訓にあふれた遊びだが、一点気に入らないことがある。王様がいること。王様だけは別格だ。王様さえ無事だったらいいみたいな感じ。みんな王様のために働いている。これは、良くない。ということで、やちまた道、将棋革命をしてみた。王様を王様でなくしてしまう。そして、それぞれが「この駒がとられたら負け」というのを自由に決めれるようにする。(ようは、ババヌキに対するジジヌキやね。) そして、自分だけがそれを知っている。どの駒にしてもいい。歩だっていい。桂馬だっていい。もちろん、裏の裏でをかいて王様のままでもいい。どんな駒にしたらいいだろう。普通に考えるとどこでも逃げれるよう、前後左右斜めに動ける駒がいいかな。銀か、金か、狙われやすいけど飛車角あたりが逃げ足がはやいか。いや待てよ。意外と歩というのもありかも。だれも歩が王様なんて気づかないもんな。相手の陣地に入って成金になって、隠者のようにこっそり生き延びるという手もあるな。この将棋の面白いのは、見ている第三者が、どっちが優勢がさっぱりわかんないこと。(もちろん、やっている当人たちもわかんないけど…)こんな話をカミさんにしたら、「なんかつまんないな~。何を攻めたらいいか、目的がよくわかんないじゃん」という。何を言っているんです。何が目的かわかんない。これこそが人生ではないか。あてもなく運に身をまかせる、まさに人生将棋。(そのかわりちゃんと「どの駒にしたか」は覚えておきましょう。当人が忘れちゃうと、もうわけわかんなくなります。)ぜひ、一局お試しあれ。
2008年09月10日
コメント(0)
-
ひと花。
植物を育てていると面白いことに気づく。思わぬところから枝が出たり、葉がであり、花が咲いたり。見た目には他の部分と変わらないのに、枝や葉や花になって現れるのはなぜだろう。始めから決まっていたのか、偶然の産物なのか。予想外の動きをするのが、自然であり、この世のすべてかも。名古屋の義理の姉から突然メールが来た。「お義父さんが、恋をしました。」 …とカミさんが読み上げる。コイ? 鯉? 来い? 濃い? 故意? 頭の中でぐるぐる変換ミスを繰り返し、そして…えっ「恋」。いやな予感はしていた。この前の電話の最後で、「ひと花咲かすわ~」と言っていた。カミさん「競馬のことじゃない?」と言ったが、そこは実の息子、なんかザワッとするようないや~な感じは残っていた。恋ね~。70過ぎて恋か~。さすがは小栗印伯人、インパクトのあることをしてくれる。…と感心している場合ではない。その後どんな展開を生んでしまうか…。相手さんだっていることだ。「電話で聞いてみたら?」とカミさんは言うが、「誰に恋したの? いいから言ってごらん」って自分の親父に言いたくないぞ。どこから、芽を出すか、花を咲かすか…。「人生って、素敵!」と義理の姉のメールは絞めていたが、そんなもんでしょうか。手綱を引く人のいない、小栗印伯人の疾走。今後の展開はいかに…。
2008年09月09日
コメント(0)
-
お寺のお祭り。
やちまた家の家の廻り散歩が続いている。土曜日に輪王寺あたりまで行ってみる。庭園で有名なお寺。五重塔があったりする。明日の日曜日に街のお祭りがあると書いてある。何もすることがないので、明日も来てみることにした。日曜朝、雨がパラパラする中、輪王寺へ散歩する。出店が出ている。雨が強くなってきたが、ビールの魅力が勝る。焼き鳥と、もう一品、そして秋味2本を買って、雨をしのげる「あずまや」みたいなところで乾杯。そうすると他にもおじさんやおばさんが同じようにビールを持って集まってくる。みんなで席をわけあう。人情あるちょっとした一杯居酒屋みたいになった。お寺の境内で朝っぱらから、雨の音を聞きながら飲むビールもおつなもの。お墓参りの人もいる。人形供養で大きな人形をもってやってくる人もいる。お寺のネコもやってくる。ゆる~い、日本映画をみているみたい。う~ん、雑多な感じがおもしろい。漱石の「我が輩は猫である」の世界である。他の作品はテーマが集中していて完成度が高い分、なんか雑多な生命力に欠ける部分がある。その点「猫」は日本の庶民文化の生命力をそのまま映し出したような漱石文学のある意味での最高峰だと言える。そんな世界がまがりなりにもお寺の祭りには残っていると思い、楽しくなった。来週は、ジャズフェスだ。いい雰囲気でお祭り気分を演出できるかな。
2008年09月08日
コメント(0)
-
想い。
いろいろ、人の書いた文章を見ていると、その人のクセみたいなのがわかる。やちまた道、いつか、文章鑑定士になってみようと思っている。やちまた道、自分が書いた文章を見ていると、あることに気づく。「想い」という言葉が結構多いということ。確かに好きな言葉だし、漢字も好きだ。木に目がある。それが心だ。なんか宮沢賢治の世界だ。イマジネーションがふつふつと湧いてくる。あと語感もいい。「オモイ」。そう、重いんだ。重力がある。リルケは、大切なものは、すべて重いと言っていたっけ…だから、心の奥の方にずんずん沈んでいってしまう。自分でも取り出すことが難しいほど。今宵、ひとりグラスを傾け、心の奥の「想い」に出逢ってみてください。(やちまた道は、しないけど…、というかできないけど…)
2008年09月05日
コメント(0)
-
みやぎの酒。
あんまり、日本酒は飲まないけど。やっぱり飲んだ時は、「日本酒が一番うまい」とも思ってしまう。いま、結構山形のお酒が、ブランドらしい。新潟のより、一部の飲み屋では重宝されているとか。たしかに、昔「十四代」を飲んだときは「水みたい」という形容詞の意味が初めてわかったような気がした。宮城にはそんなにすごい酒はない、と思っていた。でもはじめて美味しいと思う酒に出逢った。「乾坤一」。宮城県柴田郡、村田の大沼酒造店でつくられている。まあ、酒にそんなに味を求めていないやちまた道にとって、魅力的に映ったのは、その名前なのかも知れない。乾坤って「天地」のことなんだね~。宇宙一おいしいお酒という意味か。あるいは、天と地の恵みがひとつにつまっている酒という意味か。どちらにしてもスケールの大きいネーミングだ。中国には「乾坤一擲」という故事成語がある。天地をさいころの一振りに賭ける意。のるかそるかの勝負をすることらしい。もしかしたら、この酒に宇宙のすべてをかけた蔵の意気込みを示しているのかも。まあ、どっちにしても、自分の全宇宙をかけるようなことしてないね~。なんか、もっと、大きいことをしてみたいもんです。ここで宣伝。知り合いが定禅寺ジャズフェスの時に、「純米酒BAR」なるブースを出すとか。もし、仙台でジャズフェスを見られる方、こちらの方もよろしくです。(乾坤一はないと思うけど…)http://blogs.yahoo.co.jp/miyagijunmai
2008年09月04日
コメント(2)
-
りーだー。
一国の主が、辞任する。すごいことなのに、「まあ、しかたないよね~。誰がなっても同じだし…」みたいな雰囲気になっている。首相の話ではない。わが会社の社長の話。(同じ日に辞任のあいさつがあった。そんな季節なのかね~)最初に社長が変わった時は、さすがにヤバイと思った。でも、大して、何事もなかった。この時代、リーダーが変わったぐらいで、良くも悪くもならない。リーダーも言葉とはうらはらに、組織を「引っ張ろう」なんて考えていない。リーダーなんて、所詮組織の「顔」でしかない。「象徴」でしかない。…とまあ、こんな感じの雰囲気が広まると、次にリーダーになる人の「心持ち」にも影響が出るんだろうな。「オレがリーダーになったところで、変わりはしない。下の人間もさして期待してないだろうしね~。まあ、当分、リーダー気分を味わせてもらって、時期が来たらやめればいいし…。」こんなゆる~い感じが、日本中にひしめいてきている。リーダー不在の世の中。だって、「引っ張る」必要がないんだから。むしろ、世の中は、悪いところに「引っ張られる」より「じっと動かない」でいた方がいいと思っているのだから。
2008年09月03日
コメント(0)
-
打って出る。
仙台には、結構、小説家という人がいる。映画化になる作品もある。まがりなりにも、杜の都・仙台。けっこう文化的なんである。ある在仙の小説家さんと話をした。地元で書いている人は、やっぱり、なんかしら「野心」みたいなものを持っているんだね~。いろんな場面で、東京からの「借り物」みたいなものに侵されすぎていると嘆いていた。たしかにね~。例えば、仙台に限ったって、素晴らしい文化がある。全国区の哲学者だっていた。阿部次郎。「三太郎の日記」で有名になった人。西田幾太郎の「善の研究」、倉田百三の「出家とその弟子」と並んで、大学生の「三種の神本」と言われたもの。こんなに有名だった人も今となっては、仙台の若者がどれくらい知っているのかな~。こんなケースはいっぱいある。東北までエリアをのばせば、日本のマルクスと言われた安藤昌益がいる。ユニークな国学を打ち立てた平田篤胤だっている。東北の風土が作りあげたりっぱな思想群があるわけだ。その小説家の人と、もっと東北の文化を掘り起こせば、外に「打って出れるんじゃないか」と話した。酒の勢いとは言え、確かに東北からもっともっと埋もれている「北の叡智」を発信できたら、面白いんじゃないかと思った。
2008年09月02日
コメント(0)
-
詰まりは…。
秋になろうとしているのに、ジメジメとした季節。いろいろ困ることがある。鼻づまり。もともと鼻の通りが良い方ではないが、この季節になると完全に片鼻が詰まってしまって口呼吸になる。鼻が詰まれば、口で呼吸すればいい、なんてことはない。鼻呼吸と口呼吸は同じ呼吸でも酸素の摂取量が違うらしい。だから、口呼吸の人は血液中の酸素不足を引き起こす。血中の酸素濃度は98-99%が理想とされ、93%で酸素不足顔となり、87%は肺の悪い人、85%ともなれば頭はボーっとしてくるという。たしかに、鼻が通らないと頭がボーっとしてくる。でも、問題はそれだけじゃない。・口呼吸の人は、ウィルスを吸い込んだり、喉を乾燥させ、調子悪くさせたりする。・唾液が不足することで口臭、歯周病、虫歯の原因ともなる。・顔もたるみやすくなり美容にも影響がある。・眠りが浅くなり睡眠不足が続いたりして睡眠障害を起こす。……口呼吸全然いいことないじゃん。本来通るべきところを通らないと結果が同じでも、いろいろと支障が出てくる、ということだ。これはもう、鼻を通すしかない。鼻炎スプレーは一時的にスッキリするが、なんかだんだんクセになるような気がする。鼻うがいもそこそこ気持ちいいが、そもそも鼻が通っていないとうがいできやしない。なんか鼻を通す良い方法はないか。ちょっと、この秋のやちまたやぶ医者道のテーマにしたい題材だ。
2008年09月01日
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1