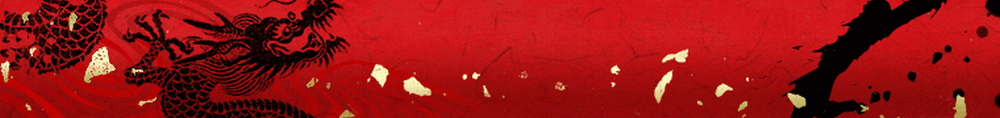2008年07月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
野性と分析。
もうすぐ、オリンピック?あまりスポーツに興味のないやちまた道だが、気になる選手がいる。野口みずき。いいね~。あの野性の走り。サバンナを獲物を追って走る、古代人の様相。きっとあの走りはO型の走りだ!と予想したら、案の条。(う~ん、やちまた血液道、「走り」で血液型が当てれるレベルになってきた。)で、当然、ハイエナのように小賢しい、現代マスコミ分析集団が、野性のスプリンターを狙う。腕の振りを分析する。歩幅を分析する。持久力を分析する。そんな分析の集積で、あの野性の走りが再構成できるように。怖いのは、彼女自身に、その分析癖がつくことだ。分析をし始めると、走る自分ではない「自分」が生まれ、併走することになる。もはやそこには、野性の瞬発力・爆発力はなくなるんじゃないか。マスコミの餌食なった高橋尚子も、走る自分じゃない「自分」がたくさん生まれすぎた。それが、あの悲劇になったような気がする。野口みずきには、いつまでも野性のサバンナを走っていてもらいたい。
2008年07月31日
コメント(0)
-
道連れ。
「誰でもよかった。」流行語になりそうなぐらい、通り魔事件のアイコトバになっている。「道連れが欲しかったんでしょうか」とニュースキャスター。なるほど…、道連れか…と思っていると、うちのカミさん「なぜ生きる道連れを探さない!」とビールを飲みながら、突然吠えた。たしかにね~。昔は、「旅は道連れ、世は情け」なんていったもんだ。決して、死への道連れだけではなかったし、「死なば、もろとも」的な「カタストロフィー」への強引な道連れでもなかった。いつから、「道連れ」の意味合いが、こんなネガティブになったんだろう。ぱっと浮かんだのが、奥田民生の「さすらい」。みんなさすらわなくなった…、みたいな歌詞でなかったっけ。(間違ってたらごめんなさい…)「家に自分の居場所がなかった」と、ある容疑者は言ったとか。「居場所がない」なら外に出ればいい。「居場所がない」んじゃなくて「行き場がない」んじゃないのか。(「行き場がない」んじゃなくて、「行き場が見つけられない」の方が正確か…。「行き場が見つけられない」なら、さすらえばいい、と奥田民生なら歌うかな…。)日常に「旅」がなくなった。日常に「道」がなくなった。日常に「孤独」がなくなった。(旅を棲処とす、みたいな芭蕉さんの時代は、遠い昔となったんだね~)旅の途上で「本当の孤独」になった時はじめて、「道連れ」というものが意味をなし、「本当の道連れ」に出逢うことができる、のかも。「生きる」という日常の中で、現代ではもはや道連れが必要なくなったんじゃないだろうか。(道連れを探せなくなった、というのが本当か…)旅なき、さすらいなき、行き場なき、やり場なき、がんじがらめの、そして莫大な情報だけが行き交う小市民的な「ちっぽけな定住民族時代」の中で、「本当の孤独」になれない現代人。そんな現代人が、唯一はじめて、遅ればせながら旅に出るのが、自暴自棄になって死を意識した時だ。(あくまで、「自暴自棄」な死。「自分の死」ではないところが現代人らしい。)初めての旅路。まっすぐ伸びる、孤独な死への道。どうしようもなく寂しくて、手当たり次第に「道連れ」を探す。まあどっちにしても、そんな身勝手な旅路の「道連れ」にされた人はたまったもんじゃないが…。(しかも、道連れを探していた本人は、旅に出ず生き延びているという世にも不可解な矛盾…)
2008年07月30日
コメント(2)
-
かなかな。
夕闇の中で、ビール。そして、外から聞こえるせみの声。風流だね~。「夏」かしい、夏がやってきたという感じ。セミの声というと、みーん、みーんという声。暑い熱帯夜をさらに寝苦しくする。やちまた道の名古屋の記憶の中の夏には、そんな元気なミンミンゼミがいる。しかしここで、カミさんと意見が分かれる。カミさんにとって、夏かしいセミと言えば、カナカナらしい。カナカナか…八木重吉の遺作の詩集「貧しき信徒」にこんな印象的な詩があったっけ。「かなかな」かなかなが 鳴くこころはむらがりおこりやがて すべられてひたすらに 幼(おさな)く 澄むカナカナ。ヒグラシの別名。晩夏のセミという感じがするが、北仙台の新居ではまうすでに夕暮れに鳴いている。異次元に誘うような、実に哀愁を帯びた神秘的な鳴き声。う~ん、間違ってたら許してください、名古屋ではこんな「カナカナ」って鳴き声、あんまり聞かなかったと思うけど…。NHKの「どんど晴れ」で印象的に使われていたので、なんか東北とかに生息するセミだ、なんて勝手に思っていた。でも、ホームページとかで調べると、やっぱりカナカナの生息エリアはほとんど日本全国らしい。…でさらに調べると、関東以西では山に生息し、東北では平地にいるらしい。つまりは、名古屋あたりだと、山奥にしかいないのに、東北だと、民家のある平地に平気でいるということか。あまりにも日常の中にカナカナがいるから、東北人にとって夏かしい音になっているのかな。そうか~。だから、東北の夏の夕暮れは、ちょっぴりもの悲しく、センチな感じなのかな~。カナカナ。きっと、悲悲と泣いているんだろうね~。
2008年07月29日
コメント(0)
-
地域ぶらんど。
愛知県は三河で、「三河武士」というもので地域ブランドをしているらしい。5人の武士ーと鷹をキャラクターにして、仮想の「三河国」なるものを作ってホームページでも大々的に情報発信している。三河国でだけでなく、加賀国、安芸国、尾張国と連携しているらしい。サムライ日本プロジェクトと称して、表参道にも進出している。サングラスに革ジャンに褌のサムライキャラクターが、世界へ向けて、地域のこだわりのモノ作りを発信していて、話題になっている。う~ん、おもしろい。愛知県出身者としてちょっぴり自慢したくなる。ひるがえって、仙台でもこんなのをやったらいいのに、と思う。仙台には、正直名古屋なんかかなわないぐらいの文化があると思う。その代表がやっぱり「伊達文化」だ。愛知県にも、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という名だたる戦国武将がいるが、それが、地域文化として根付いているとはなかなか言えない。それに引き換え、政宗さんの伊達文化は、今も仙台の中心的な「ぶらんど」と言える。このあたりを核にして、全国に向けて、世界に向けて地域ブランド発信をしたら、面白いと思うけど…。(サムライに対して、トノサマかな?)地方が地方なりに地方独自のものをどんどん発信していくべきだ。国になんか頼ってられない。なによりも、石原TOKYOには負けてられない。
2008年07月28日
コメント(0)
-
スロー・トレイン・カミング。
暮らしを明るくするのも、暑い夏を吹き飛ばすのも、伝えたいことを発信するのも、行きたいところへ飛んで行くのも、街を元気にするのも、化石燃料だけじゃない。人類は、石炭を燃やして機関車を動かした産業革命以来、まだ、化石燃料の呪縛から抜け出せていない。もっと、他にも燃やすものがあるはずだ。…ということで、本日も魂の燃料を!
2008年07月25日
コメント(0)
-
飾りとしての祭り。
仙台に一番最初に遊びに来たとき、やっぱり観たのは、七夕祭りだった。アーケードにいっぱい竹が並べられ、賑やかな飾りが飾られる。「動きのない祭り」として地元では不評だが、まあ観光客にとってはきらびやかでそこそこ見応えもある。七夕飾りが飾られるのはアーケードの中だけでない。地域の小さな商店街も自前で七夕飾りをだして、街全体がキラキラとなる。ただ、最近、不景気の影響で、竹飾りを出すことを見送る商店が増えているとか。「不景気で祭りどころじゃない」というところらしい。う~ん。しょうがないんでしょうね~。燃料費も高いし、原材料費も高いし、消費者の財布の口も固くなっているだろうし、地震もあるし(関係ないか)…。でも、しかし、BUT!「不景気で祭りどころじゃない」というのは寂しい限りだ。本来、祭りって、五穀豊穣を願ったり、商売繁盛を願ったりするものじゃないのかな~。それが、「祭りは所詮、飾りにすぎない!」なんて発想になってきちゃっうのは、寂しい。苦しい時だからこそ、みんなを鼓舞するような祭りであるべきなんじゃないのかな~。(キレイごとかも知れないけど…)大きな竹飾りが無理だったら、小さな竹飾りでもいいではないか。小さな竹飾りでも無理なら、…唄と踊りだけでもいいではないか。(金かかりませんぜ!)…ということで、八重山民謡から繁昌節を、仙台の商店街の皆さんに贈ります。「繁昌節」だんじゅ豊まりる崎枝ぬ島や ヨーウネ(ダンジュトゥユマリル サキーダヌ スマヨウ ウネ)黄金岡ぃくさでぃ スリ(クガニムルィ クサディ)田ぶく前なし(タブクマイナーシ)(囃子)イヤマシ ウヤキ ハンジョウマサル ハンジョウカツィ マタ イヤマシ
2008年07月24日
コメント(2)
-
穴。
今朝、ヒゲを剃りながら、あることに気づいた。目に目ん玉があること。他の五感と言われる耳や鼻は穴があいているだけなのに。目には穴だけでなく、中から目ん玉が剥きだしている。(埴輪の目は穴ぼこだけだけど…)アリストテレス先生は、「全ての人間は、生まれつき、知ることを欲する」と言っていた。なるほど。目ん玉の剥きだしは、知ることの「欲望」の表れなのかも知れない。他の五感で考えてみよう。味覚である口はどうか。口自体は穴に過ぎないが、そこにはベロという欲望が出ている。触覚はどうか。手が伸びた。足が伸びた。まだ足りなくて指まで伸びた。目ー手足ー口は、人間の欲望の体系を作り出した。獲物を見つけ、捕獲し、むしゃぶり喰らう。この欲望は肥大化し、地球の生態系を壊し、現代の「危機の時代」を作りだした。進化した目ー手足ー口は、欲望の赴くままに一線を越えた。その傍ら、耳と鼻の穴ぼこは欲望の身体の進化からこぼれ落ちたようだ、昔ながらの、ただ向こうから来たものを摂取するのみ。そこには古代の叡智への「従順」がある。聞くべきものを聞き、嗅ぐべきものを嗅ぐ。「過不足のなさ」が古代の叡智の特徴だ。他の五感との一番の違いは、「危機」や「危険」を感知する能力があるということだ。自分にふさわしくないものは、ものすごく臭い。腐ったモノは酸っぱい匂いがする。逆に自分にふさわしいものは甘い匂いがする。敵の気配を感じるのも、耳であり、鼻である。そして、生きるための叡智である音や匂いをもたらしてくれるのは「風」だ。風という媒体が古代の五感には大切な役割を果たした。風に従順だった時代は、人間はもっと叡智を身に付けていた。それ以外の五感は、風に逆らい、外に獲物を獲りに出かけた。手に入るものは何でも欲しい。あまりに欲望に支配されたため、そこにある「危機」や「危険」を認識できなくなってしまった。耳と鼻。この穴たちは、古代の叡智に従順だったころの記憶を残している。ただ最近、耳も欲望を持ち始めている。iPodに何万曲、何十万曲も入れ、持ち出す時代。もうすぐしたら、耳の穴から、悪魔の舌のような欲望の食指が伸びて来るかも知れないね~。
2008年07月23日
コメント(0)
-
夏到来。
毎年恒例となった、3連休のジャズフェスミーティング。この頃になると、ああ夏が来るんだな~と実感する。去年も雨の中のジャズフェスミーティング。雨の匂いが夏の到来を告げているようだ。気になる演奏場所。今年は、久しぶりにアーケードの中だ。ストリートジャズらしくなった。(ジャズではないけれど…)なんだかんだ言って、買い物なんかで通りを行く人に自由に見てもらえるのが、仙台のジャズフェスの良さだ。八重山民謡の唄も踊りも、すごく身近に「人の体温」を感じながら演奏できるのが、一番楽しいものだ。はじめて耳にする人には、ああ八重山民謡って楽しんだなって思ってもらえるような、そんなあったかい演奏がしたいね~。遅まきながら、夏到来のわが三線の会だ。
2008年07月22日
コメント(0)
-
うぐいすとカラス。
引越してきて3週間。毎日、感動していることがある。うぐいすだ。雨の日でも、風の日でも、ひとりで鳴き続けている。仲間がいるわけではない。ただ、鳴いているだけだ。生ゴミの日、6時くらいに、突如、カラスがやってくる。「カーカー」「あーあー」どう見ても、お互いにコミュニケーションを交わしている様子。人間のようにコミュニケーションをするカラスはエライ、あったまいい~と思っていた。ただ、最近その想いが違ってきた。コミュニケーションには、聞いてくれる人がいるという安心感がある。双方向が前提だ。相手がいる。そこには、安心と安定と安易がある。それに引き換え、孤独なうぐいすの鳴きは基本的に一方通行だ。片思いのコミュニケーション。失恋したコミュニケーション。知らない場所に産み落とされた赤子の泣き叫び。「自分はここにいる」という存在誇示の「表現欲」だ。そこには、命がけの真剣さがある。片割れのいない絶望と孤独がある。誰が聞くわけでもないのに、バカのひとつ覚えのように「ホ~ホケチョ」と鳴くうぐいすに、胸がきゅーんとなる。見てくれる人がいなくても道端に咲く花のように…。「表現」。それは、自分の存在を見て欲しいという根源的な欲望だ。この小さな存在を認めて欲しいという切なる血の滲むような願いだ。すべての生きとし生けるものが根源的に持つ「表現欲」には、聞いてくれる人がいなくても表現せざるを得ない、そんなギリギリの愛おしさがある。それは例えば、元ちとせが、聞いてくれる人がいなくても、声が出なくて伝わらなくても、歌わざるを得ない。そんなシーンとリンクする。
2008年07月18日
コメント(0)
-
全体史ー部分史。
歴史に最近興味を持ってきた。学生の頃は、歴史がキライだった。(やちまた道、固有名詞を覚える能力が著しくない。外国の長いカタカナの用語なんか覚えれるわけがなく、これが歴史ギライの大きな要因になった。小さい頃、頭をぶつけすぎたためであるという勝手な理由づけをしている。)どんな本がいいか。世界の歴史がいいか。日本の歴史がいいか。もっと、特定した時期・場所の本がいいか。いろいろ調べていて、ふと気づいた。別に世界史だから、日本史よりページ数が多いわけではない。日本だって、そうだ。仙台市の一番町の国分町の歴史書が、世界史より分厚いことだってありうる。まあ、こんなことは当たり前のことだけど…。歴史というものが、その場所、その期間に蓄えられた情報の表現だとすれば、どんな部分的な歴史の情報量も、世界という全体的な歴史の情報量を超えることだってできるわけだ。極端な話をすれば、一番町1丁目1番地の昭和元年1月1日の歴史書だって、世界史に匹敵することだってできるわけだ。現代歴史家の代表的存在と言えるブローデルは、地中海という限られた領域に、その背景となる自然環境、政治、社会、経済、文明の多角的な歴史を丹念に描き<全体史>を作り上げた。地中海の中に、人間、駄馬、車、商品、船、思想、生き方まで、一つの文明ではなく互いに層をなしているいくつもの文明を描き出した。すべてのものが混り合い、そこから再び独特の統一体に構成されてゆく一つの組織体としての姿。地中海から、全世界を見つめていたと言っていい。部分と全体の関係。あるいは一と多との関係。この関係の中で見る歴史が面白いような気がする。
2008年07月17日
コメント(0)
-
人間の発見。
朝、ヒゲを剃りながら、ふと不思議な感覚になった。「鏡」。鏡って、不思議な存在だ。実体があるわけじゃない。モノとしては、単なる金属の板でしかない。鏡が鏡になるのは、そこにモノを写し、それを映しているという認識が働いた時だ。鏡はモノを写す。いや正確に言うと、写すという<関係性>が「鏡」だと言える。本体と写された像との関係性、その関係性を発見したときに、初めて鏡は生まれた、と言っていいのでは。つまり、実体が「ある」のではなく、関係性が「ある」という発見。この驚愕の発見で、人間は人間になったのかも知れない。同じような発見は「火」に対してもあったのでは…。火は実体がない。火だけを掴まえようとしても、その実体を掴めない。あるのは燃えているモノの<働き>だけだ。この「火」を発見した時にも人間は驚愕しただろう。実体なきものとしての「鏡」と「火」。人間が人間になった驚愕の「発見」の象徴としての「鏡」と「火」。この2つが神的なモノとして、祭壇なんかに飾られるのは、なんとなく頷けることだ。
2008年07月16日
コメント(0)
-
敵なきストライキ。
燃料費が高いということで、漁業団体が休漁するって。燃料費で打撃を受けている業種は他にもあるだろうが、獲れるか獲れないかわからない「リスクの大きい商売」にとって、黙っていてもかかってしまう燃料費の高騰はきついだろうな。う~ん、気持ちはわかる…でも、誰に対して抗議するストライキなんだろう、という疑問はある。このストライキをして誰が困るんだろう。誰が困って誰が問題解決に向けて譲歩するんだろう。カギを握るひとにぎりの人間たちは、ストライキは痛くも痒くもないのではないか。従来までの需要ー供給などの市場原理の枠組みから外れたものに、従来のようなストライキは有効だろうか。同じようにストライキをする業界が増えれば、結果的に傷口に塩を塗り合うだけのストライキにならないか。抗議する本当の相手がどこにいるか分からない、対象なきストライキ。世界は今までのような、「型どおりの経済学」がなりたたないところに来てしまっている…。もっと、違う形の「抗議行動」ってないのかな…。
2008年07月15日
コメント(0)
-
車ぎらい加速。
引越先の街は、いたる所で気に入っている。お寺もある。公園もある。そこそこ街でもある。いろいろ表情があるので、いまの所週末は探検だけであきない。(まあ、あきっぽいやちまた家だから、この先どうなるかはわからないが…)しかし、唯一困るのが、住宅街だけに道が狭いところ。通常だったら、一方通行になりそうな道だ。運悪く対向車が来ようものなら、運転が苦手なやちまた道、もうキンチョーが走る。週末もいやな予感で細い道を走っていると、前の車が対向車にクラクションを浴びせられている。ごつい感じの高級車。あんな車にクラクションならされたらビビるだろうな。前の車、あわててバックをしてくる。「おいおい…」「あぶない!」と思っている間もなく、電柱に激突した。車ってあんなに簡単にへこむんだね。ぐっしゃとへこみ、さらに、上に盛り上がっていた。クラクションを鳴らした対向車は知らん顔して通っていく。かわいそう、と思いつつ、なぐさめる言葉もなく、やちまた道も通り過ぎた。なんか、いやだね~、車って。必要のない限り、これからは街は歩いていこう。
2008年07月14日
コメント(0)
-
花と実。
人間の活動(例えば文化活動など…)をよく花にたとえることがある。耕し、種をまき、芽が出て、根を張り、花が咲き、実を結び、また種となる。なかなか詩的だし、意外と本質的な比喩だ。ただ、あまり表だっていわれないステップがある。「受粉」ということ。やちまた道、今回のブルーベリー事件により、ちょっと勉強した。(というか、当たり前のことを思い知らされただけだけど…)花が咲いても、必ずしも実にはならない。ちゃんと受粉していないとダメだ。受粉には、自家受粉と他家受粉がある。それぞれに良い面と悪い面がある。自家受粉は近いから粉がつきやすい。でも遺伝子の組み合わせの多様性が減って、種としての適応度が低下する。他家受粉は雨風にさらされ粉がつく可能性が低くなるが、うまく付けば遺伝子の組合せのバリエーションが広がり、種として強くなる。キレイな花が咲いても、自分の外に出て雨風にさらされ他流試合(?)をしないと、いい実はつかないということか…。いま花ざかりの諸君、外に出て受粉しましょう。
2008年07月11日
コメント(0)
-
数字の怖さ。
数字には顔がない。数字だけを見ていると、その中身の違いが分からなくなる、という危険性がある。洞爺湖では、各国のお偉いさんたちが、CO2削減の数値目標づくりでシックハックしていた。同じC02を削減するにも各国で思惑がちがう。原子力産業を発展させようとするフランスは、CO2削減策として積極的に新興国に原子力を売り込んでいるようだ。かたや、エコ最先端のドイツは、太陽光エネルギーを次世代の代替エネルギーと考え、太陽光でつくった電気を電力会社が買い取ることを義務づけるなど、国ぐるみで普及策に取り組んでいる。おなじCO2を削減するにも、まったく手法が違うわけだ。それぞれに問題点があるだろう。原子力にした時、その安全性は疑問だし、太陽光にすれば多大な設置費用がかかるし、天候にも左右されるという問題点がある。だから、エネルギーの代替の問題は、社会全体の犠牲や苦難や不具合をどこに切り替えるかの問題に帰着するように思う。(エネルギーは天から降ってこない!)少なくとも、これが数字だけがクローズアップされると、本質的な論議が見えなくなる。一番大事なのは、どのような形で次世代のエネルギーを考え、結果としてCO2の削減に結びつけるかということのはずだ。その是非の議論がないまま、数値目標だけで右往左往しているのでは、…どうなんだろう。
2008年07月10日
コメント(0)
-
頭がジャム。
ブルーベリーはジャムでしか知らなかった。簡単に栽培できることも。カミさんがパート先からブルーベリーを持ってきた。ブルーベリー用土を園芸店で買ってきた。酸性の土らしい。鉢に植えて、たっぷり水やりをする。しばらくすると、いくつか実らしいものが出てきた。ブルーベリーは、寒冷地に育つハイブッシュ系(この中でノーザンハイブッシュ系とサザンハイブッシュ系がある)と暖地に育つラビットアイ系、野生種のローブッシュ系に分かれるらしい。うちのは何かな。見た目は、ハイブッシュ系。寒冷地というのもうなずける。ふつうに見るものより、かなり小さい。しばらくすると若干紫がかってきた。う~ん、確かにブルーベリーだ。ただ、このペースでいくと本格的に収穫できそうなのは5~6粒だ。しかもかなり小粒。…で、ホームページで調べる。1品種ではなりにくいので2品種以上植える必要がある…と書いてある。さらに同じ系統でないとダメらしい。なるほどね~。ということはハイブッシュ系のうちの違う品種を一緒に植えないとダメってことか?ジャージー、ディクシー、ブルーレイ…などいっぱいある。でも、そもそも、うちのブルーベリーはどれなんだ???う~ん、ジャムになるには、まだまだ道は遠いね~。
2008年07月09日
コメント(0)
-
世界遺産と痕跡。
平泉、だめだったか~。世界遺産。まあ、別に世界遺産でなくてもいいけど…。できれば、カミさんの実家に帰る時、世界遺産の中を通るなんて醍醐味を味わいたかった。まあそもそも、平泉には、本質的な部分は残っていないしね~。なんと言っても平泉の凄さは、100年続いた浄土宗一色で染まった平安な街づくり。世界的にも珍しい宗教国家。こんな文化遺産というか、思想資産は世界でも類を見ないのでは?でも今となっては、日本のどこにも、世界のどこにもその「痕跡」すら残っていないものね~。「普遍的価値」か。平泉は、東北の地に生まれた「奇跡」とも言える「つかの間の夢」だった。それは確かに「普遍的価値」ではないかも。でも、普遍でなかったものにも、抹殺されたものにも、その微かな「痕跡」に価値ってないのかね~。(芭蕉は、その痕跡に泪を流した…) 夏草や兵どもが夢の跡 五月雨の降りのこしてや光堂
2008年07月08日
コメント(0)
-
街あるき。
久々にゆったりとした休日。せっかく新しい街に引っ越したということで、街を遊んでみよう、となった。まずは、体育館。ジムが入っていて、1回300円で利用できる。決して体育会系ではないやちまた家だが、なんか久しぶりに運動してみるかな…とジムに行く。最初は機械の使い方の講習がある。10名ぐらいが参加している。いや~、なんかこんな感じで朝からスポーティなのも気持ちいいもんだ。でも、ストレッチにはまいった。やちまた道一人が全然曲がっていない。ストレッチで筋肉痛になってしまった。…で、体育館を出て、神社巡りに出かける。とにかくいっぱいある。ざっと10寺ぐらいが並んでいる。お目当ては、アジサイの花で有名な「資福寺」。梅雨の時期にぴったり、と思っていたのだが、全然ピーカンの天気にあじさいの色も冴えない。それ以上に筋肉痛で、もうこれ以上階段をあがりたくない。とりあえず今日のところは街の探索ということで、すべて門の前で帰ってきた。輪王寺では無料で座禅とかできるみたいなので、ざひやってみたいな…。…で、飲み屋にも行った。飲み屋が多くてこれも気に入った。ただ、若干ビールが高い。すでに3・4軒巡ったが全体的に高い。これはやちまた妻にはなっとく行かないよう。とくに中ジョッキを頼んだときに、取っ手のないグラスで出てきたときは、カミさん店員にかみついた。「すいません、これ中ジョッキですか?」「ええ、中ジョッキです。」「えっ、取っ手がないのに中ジョッキ?」「…ええ、まあ、量的にはいっしょぐらいだと思いますが…」「量的にいっしょ『ぐらい』? ぐらいって何よ。ビールに「ぐらい」なんてないよね。勝つか負けるかじゃん~、やるかやられるかじゃん」。もう、若い店員は泣きそうだ。次に同じ中ジョッキを頼むと、さすがに取っ手のついた中ジョッキが出てくる。「そうだよ、これが中ジョッキだよ」と勝ち誇ったように言い放った。ちょっとビール受難の街か。いろいろ巡っているうちにやちまた家にぴったりの店に出逢うことを祈りたい。
2008年07月07日
コメント(0)
-
守る力。
シルク(絹)屋さんと話をした。シルクには天然素材ならではパワーがあるそう。シルクの下着を着ていると、例えば肝臓が悪いとそのあたりが黒ずんでくるらしい。何か毒素でも吸収しているのか…。シルクというと、よく「傷みやすい」と言われる。確かに、例えば太陽のもとで繊維は傷みやすい。しかし、これは人間の代わりに紫外線を吸収しているために起こるとか。他のために自らが「傷み」そして「守る」わけだ。絹というのはマユから紡がれる。マユは一匹の蚕(カイコ)がなんと1500メートルの絹糸を吐いてできるとか。子孫を残すために自らが犠牲になって生命のエネルギーのすべてをつぎ込むかのように。中のカイコを守るためにあるマユ。すべての外敵や不具合を自分の中に吸収する力を持っている。だから、そこから紡がれる絹はどこまでも受容的で、どこまでも強い。これは、プロポリス(プロ(守る)+ポリス(都市))が、蜂の巣を守るために生まれ、優れた抗菌作用と生理活性作用などのエネルギーを持つのと似ている。この宇宙は、何かを守る時に、何か守るべきものがある時に、人知を超えたパワーを発揮するのかも知れない。
2008年07月04日
コメント(0)
-
プランB。
最近よく聞く「プランB」というお言葉。一筋縄ではいかないことが多すぎるこの世の中。今まで通りのやり方では、状況を打破することが難しいことも多々出てくる。そんな時のために、従来どおりの戦略「プランA」の代替案として「プランB」を用意しといた方がいいですぜ、ということらしい。レスター・ブラウンさんという人が、同じ題名で本を書いている過剰な資源消費の上に成り立つ既存の経済のあり方(プランA)を脱して、環境を考慮した新しい経済を構築(プランB)していかなければ、数年のうちに食糧不足をはじめとする深刻な影響が出てくる…ということらしい。「何事も従来通り」とする「プランA」は何でもありの「イケイケゴーゴー」のバブル経済を生んだ経済体質。全てがマヒして破綻に向かう。それに対して「プランB」は「ちょっと待てよ」という精神。経済のバブル体質を改め、持続可能な社会政策へ転換する。これは、日常でも使える。奥さんから「豪勢にホテルでコースランチに行こう」と誘われたとする。プランAだ。でもプランAだけだと心許ないんでプランBを考えようと言おう。中華屋さんでラーメン定食だ。例えば「豪華に海外旅行に行こう」なんて言われても、いちおう「松島あたりで観光」というプランBを逆提案する。そして、「なんかプランBの方が大人だよね」と言って、結果的に、プランBで落ち着かせることができる。日本は今、プランAのままなんだろうか。プランBを用意できているのだろうか。
2008年07月03日
コメント(0)
-
カラオケはフォークだ。
聞くのは、そうでもないが、歌うならフォークだ。中でも最近、頭の中を巡る歌がある。千賀かほるが歌ったフォーク。(ソウル・フラワー・ユニオンの「満月の夕べ」にも匹敵(?)するフォーク魂のある名曲だと思うが…。)知っている人も、知らない人も、今度のカラオケで熱唱をどうぞ。(メロディを知らない人は、音の出るホームページがありますぞ。)http://www.biwa.ne.jp/~kebuta/MIDI/MIDI-htm/Mayonaka_no_Guitar.htm「真夜中のギター」吉岡 治 作詞河村利夫 作曲街のどこかに 淋しがり屋がひとりいまにも泣きそうに ギターを弾いている愛を失くして なにかを求めてさまよう 似たもの同志なのね此処へおいでよ 夜はつめたく永い黙って夜明けまで ギターを弾こうよ空をごらんよ 淋しがり屋の星がなみだの尾をひいて どこかへ旅に発つ*)愛を失くして なにかを求めてさまよう 似たもの同志なのねそっとしときよ みんな孤独でつらい黙って夜明けまで ギターを弾こうよ*)繰り返しギターを弾こうよ ギターを弾こうよギターを弾こうよ
2008年07月02日
コメント(0)
-
女難の相。
引っ越し先が決まったので、親父に電話する。言われた通り連絡先を書き留めているようだが、あまり興味ない御様子。こちらの用件が済むと、早々にゲートボールの話になる。毎日早朝から元気よくやっているようだ。昔から近所づきあい、町内会つながりなんかが大キライだったくせに、今は結構コミュニケーションをとっているよう。その中でも、本人の弁によると、かなり女性からもてる(?)よう。「中の一人なんか、結構強烈なモーションをかけてくるで、まいったわー。」と言う。モーション? なんのこっちゃ。「今年は何か女難の相が出とるな~。まあ、何かあったら相談するわ。」女難の相??? なんのこっちゃ。70のおじいちゃん、おばちゃんたちの強烈なモーションって何なんだろう。女難の相とは? 何かあったらとは…?う~ん、自由人B型はどこまでも自由気ままだ。(おふくろが泣いてなければいいが…)
2008年07月01日
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
-

- 政治について
- 中国EC大手 「アリババグループ」…
- (2025-11-20 21:20:58)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- まち楽ブログ
- 山城ガールむつみさんの「北条五代特…
- (2025-11-20 23:23:43)
-