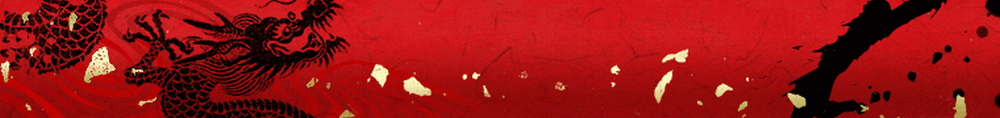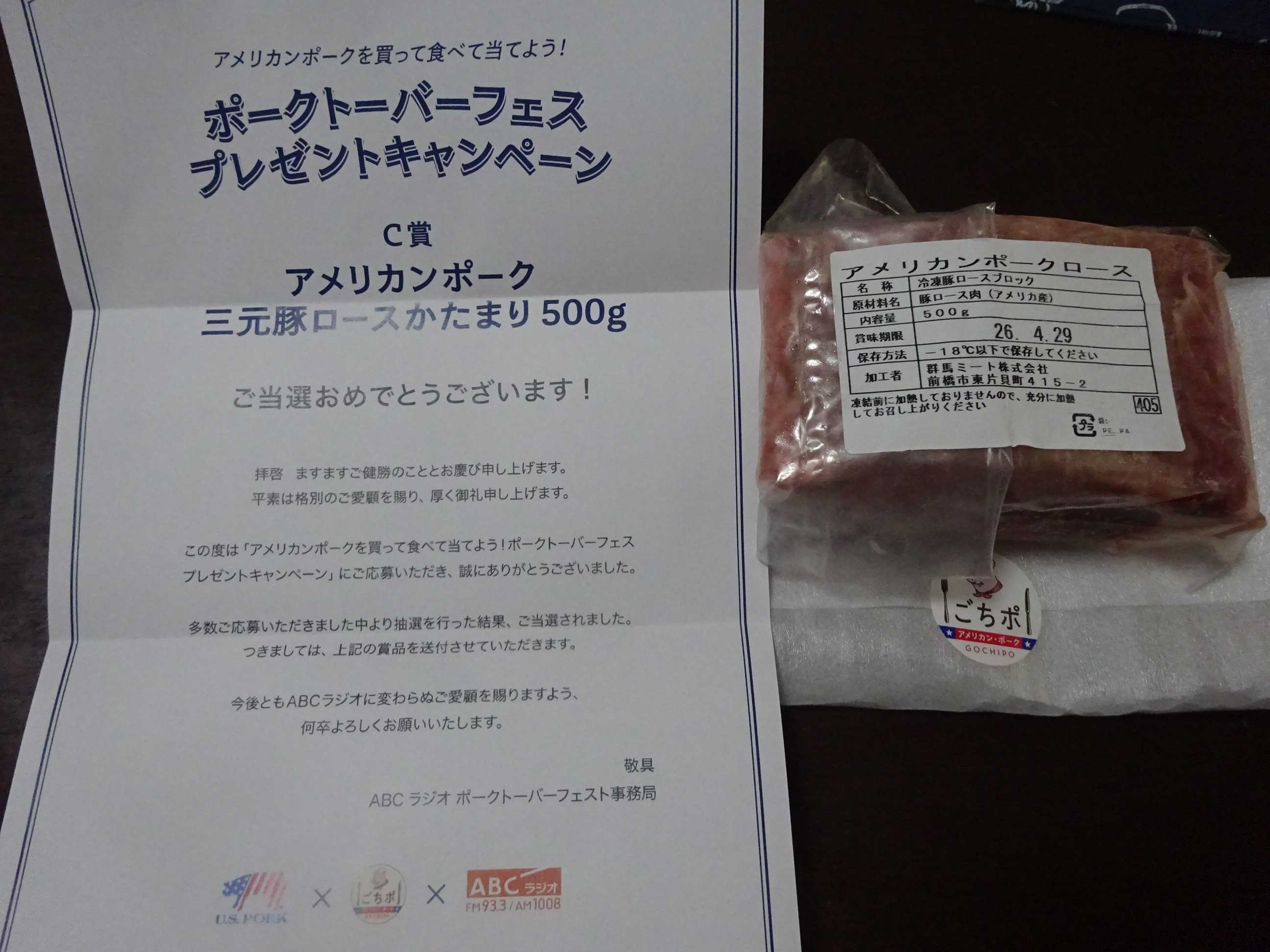2008年04月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-
日本三景より出勤。
飛び石連休の飛び石の日。親父、カミさんとで松島へ1泊旅行。運転は親父。せっかくカーフェリーで来て運転したそう。自慢のカーナビに任せ、朝早く出発。カーナビがいい道を選んだからか、全然渋滞もなく、かなり早く松島到着。施設関係はどこもやっていないので、奥松島まで足を伸ばす。ハアハアいいながら、小高い山の頂上に登る。松島全貌が見渡せる。う~ん、はじめて松島が美しいと思った。芭蕉さんはこんな松島を見たんやろうね~。松島に戻り、島めぐり。親父は奇岩が好きなようで、巡っている間、ずっと甲板に出て、望遠カメラでバシバシ撮っていた。(やちまた夫婦は寒いので船内でぬくぬくしておりました。)その後、瑞巌寺、五大堂などいわゆる定番コースをめぐる。最後に、お茶屋さんに。渋い抹茶を飲みながら、松島を眺めるのもおつである。…と、その庭に俳句募集の箱が置いてある。さすがは、芭蕉さんゆかりの地。優秀なものには景品がもらえるそうで、親父興味津々。カミさんは、当然パス。しかたがないのでやちまた道が参加。即興で一句ひねってやった。 洞窟の 闇より深し 姥桜「なんかよくわかんない~」というカミさん評。親父を見ると一生懸命書いている。 島めぐり うみねこせかる 春の風「こっちの方がいい」とさすがにお世辞を言うんだね~カミさん。親父まんざらではない。そうこうしているうちにホテルチェックインの時間。チェーンの飲み屋さんが経営するという変わったホテル。夜は1階の居酒屋で飲むことができる。(カミさんそこに惹かれたらしい…)ビールと焼酎をダマで持ち込み、居酒屋前にもうすでにほろ酔い状態。マッサージチェアが各室に装備されていて無料使い放題。松島の夕景をみながら酔っぱらいながらマッサージするという贅沢を満喫する。で居酒屋へ。日本酒を気を失うまで飲む。やちまた道、いい気分になって、「親父、俳句のセンスがあるから、これから俳句やれば」と調子のいいことを言ってやる。親父もさらに調子に乗って、「俳号がほしいな~」とぬかす。しょうがないので親父が尊敬する馬の名前をくっつけてやった。命名!「小栗印伯人(おぐりいんぱくと)」。馬鹿三人、やんや、やんやでよく覚えていないうちに、部屋で仲良く川の字状態で寝ていた。そして、翌日、というか本日。やちまた道、親父とカミさんを残して、日本三景より出勤。「休んじゃえば!」というカミさんの悪のささやきに後ろ髪を引かれながら。 松風に うしろ髪ひく ライオン島ライオン島は、親父が気に入って命名した奇岩である。やちまた家の芭蕉と曽良。珍道中は続いているはずである。
2008年04月30日
コメント(0)
-
フェリー来仙。
ゴールデンウィーク前半、親父が名古屋から仙台にやってきた。最初は新幹線でくると言っていたが、ぽろっとフェリーのことを口にすると、みょーに興味を持ってしまい「自分もフェリーに乗る!」と言いだした。しかも、車で。まあ、カーフェリーなので車で来るのが普通ではあるが、70を超えた老人が一人でしかも始めてで車でくることにはちょっと不安だった。ただ、本人はケロッとした感じで車に乗ってやってきた。さすが新しいもの好きのB型である。2日は、カミさんの実家のある岩手へ挨拶に。最初は始めてくるところで借りてきたネコのようになっていたが、酒をどんどんつがれるうちに気分よく独壇場で自分の話ばかりをリピートしはじめた。カミさんの母親も、負けていない。最初はおとなしく聞いていたが、酔いが回ってくると、親父の話を聞かず大あくびをしはじめた。この辺はカミさんとまったく同じ性格で、いたずらっ子である。かわいそうなのは、お父さん。誰も協力しない中、まじめに親父の話をヒトリで聞いてあげている。結局、挨拶といいながらも親父の競馬武勇伝(?)をぶちまけに来た感じになっていた。今日は、ひとりで仙台観光。青葉城や野草園あたりを「るーぷる」という周遊バスでまわっているはずだ。明日は、松島にでも行くとするかな。なんかすごーく絵に描いたようなベーシックなゆるーい仙台観光ゴールデンウィークになっているね~。
2008年04月28日
コメント(0)
-
ヒノキ舞台?
花粉の季節が終わったと思ったら、急にまたくしゃみがとまらなくなった。こんなことは初めてだ。通常の花粉の症状だと、鼻がムズ痒い感じなんだが、ここ最近の症状はむしろ鼻の奥がイタイという感じだ。「スギ花粉が終わってからも、別の花粉が飛ぶんじゃなかったけ?」とカミさん。ネットで調べてみる。ぶたくさもあるけど、ちょっと時期にははやいかな。ヒノキ花粉というのもあるんだね~。時期も4月末ピークと書いてあるし、ヒノキの方が粒子が小さくて、症状もちくちくイタイ感じらしい。お~!これはまさに「ヒノキ花粉症」に違いない!!やちまた道、新しい花粉症ステージに突入か!?(でも、理由が分かったら、なんか急に楽になりやした。)それでは、よいゴールデンウィークを!
2008年04月25日
コメント(0)
-
災い転じて…。
災いに取り囲まれている。自然環境の不調和によって、大雨や嵐や極端な天候が続いている。地震への恐怖もある。とにかく、日本は、いろんな天災に見舞われている。(週刊誌の見出しに、次ぎの大地震は宮城県だという不吉なものがあったな…)天災だけじゃない。人の不注意や過失によって人災もふえている。公務員が酒を飲んで交通事故なんて許せるんだろうか。まだまだある。それ以外にも、災いがふってくる。年金問題や、医療問題。これを災いと言わずしてなんとしよう。やちまた道、これを人災でも天災でもない「国災」と言いたい。とにかく、災害の多い国だ。小田実は、こんなに災害の多い国だから、自衛隊を「国際災害援助隊」みたいなのにすればいい。日の丸の旗をつけて誇り高く世界の各地で災害援助したらいい、と言っていた。名案だと思う。じり貧の日本、戦っている場合じゃない。人と人、国と国とが戦う前に、災害という戦わなくてはならない相手がある。
2008年04月24日
コメント(0)
-
東か西か、北か南か。
「東日本は、雨」。こんな天気予報を聞くとやちまた道、東北も雨か、と思ってしまう。でもカミさん「仙台はどうなんだろうね?」と言う。この若干のずれを結婚10何年目にしてやっと最近理解した。アイヌの末裔(!)のカミさんにとっては東北は「北日本」なんだ。名古屋生まれのやちまた道、東に東京、西に大阪に挟まれている。だから、東西の意識が強く、東京より先は東日本、大阪より先は西日本という感覚が自然とできてしまっていた。せいぜいあって、東北、西南という意識だが、あくまで中心は東と西。東が北を含み、西が南を含むという暗黙にして強引な意識がある。これは、日本が東北から西南という「ななめ」の国土になっていることにも起因しているのかも知れない。どちらにしても、純粋なる北、純粋なる南という「方位」が日本人には大きく欠けているような気がする。この国土意識が、文化意識にも大きく影を落としている。東西対抗はあっても、南北対抗なんてないよね。相撲も東の横綱、西の横綱だし。北の北海道や、南の沖縄は、バカンスの時にしかいかない、「異境の地」なんだ。この東西偏狭意識のため、東京・関西という2極分化した、狭くてちっぽけな文化しか生まなかったと言えないだろうか。(こう思いだしたのが、最近近代詩をいろいろ読んでいて、いいな~と思った詩人たち、例えば、小熊秀雄や吉田一穂や鷲巣繁男などが、偶然にも北海道生まれだったり、北海道で住んでいたりした「北の詩人」たちだったからだ。そこには日本人の魂の奥底を揺さぶるような、荒魂の乱舞、広大な大地のうねりみたいなものが息づいていると思う。この豊穣なる「北の文化」を意識してかせずにか、日本は取りこぼし抹殺してきた。)日本文化に「北の文化」と「南の文化」を復権すること。これは、環太平洋からロシアの大地に連なる、本来の「日本の原文化」を取り戻すことにつながるような気がするのだが…。
2008年04月23日
コメント(6)
-
ねじれ好き。
ねじれがあるだけで、美味しくなる。麺をねじることによって食感もタレのからみもよくなる。麺だけでなく、餅にも、おかきにもねじれがある。ねじりはちまきに、ねじれ大根、…日本人はねじれ好きだ。ねじれが面白いのは、表と裏が、どっちだかはっきりしないこと。表だと思っていたら知らないうちに裏になっている。日本文化にねじれ模様がいっぱい出てくるのも、そんな、イージーな、なんでもあり風土のあらわれなのかも知れない。ねじれ国会も、白黒つけたがらない日本人の精神構造の象徴と言えるかも。最近最たるねじれ現象を見た。自衛隊のイラク派遣は違憲だという判断がくだされた。(この辺までは、名古屋高裁えらかった。)でも、結局原告はなんら損害を受けていないから、請求は棄却するって。(う~ん、損得勘定の名古屋っぽい。)こんなねじれが許されるのだろうか。原告たちは「画期的裁判」と抱き合って喜んでいたけど…。違憲でも誰も「損」しなければ許されるという前例を作った「画期的裁判」だった!なんてことにならないことを祈る。
2008年04月22日
コメント(0)
-
天気には勝てぬ。
やっぱり、わが三線の会には雨男か雨女がいるんだろうな。ただ、今回はあまりに気持ちよく一日降り続けたので、あきらめもついた。ここ何年間か続けた花見ライブも今年は中止。唄わずに一日を過ごすにはさすがに気持ちが収まらないので、カラオケ屋で練習会。カラオケ屋でカラオケもせず、八重山民謡を粛々と練習するのはいいことなのか、悪いことなのか。ジュースをもってくる店員が、ちょっと恐ろしいものを見るようにしているのを感じる。で、その後飲み屋に。何も演奏会をしていないのに反省会になる。わいわい飲みながらも、自然と話は八重山民謡の話に。正統な伝統芸能を受け継ぐことと、広く一般の人に広めることの矛盾というか難しさみたいなことに話が及ぶ。みんな何となく感じているんだろうね~。で、これで終わりかと思いきやまだまだ唄いたりないようで、またカラオケ屋に。カラオケのはしごか~。今度は、普通に(?)カラオケになる。思いっきり、飲んで、唄って、騒いで…。で、気持ちよく帰った。が、やっぱりライブしたかった~、というのがみんなの本音かな。ぜひ、次の機会を。
2008年04月21日
コメント(0)
-
息切れと息漏れ。
今の日本人、息切れ状態です。年金も、医療費も、地方財政も、みんな息切れ状態です。でも、息切れの原因のひとつには、息漏れもあるのです。心地よい音の響きを乗せない息。ようは、ムダに息を使っているのです。肺活量の少ない日本ですから、息漏れぐらいはなくしたいものです。息切れも息漏れもない、息の長い人生を!
2008年04月18日
コメント(0)
-
古畑中学生。
ヤフーニュースを見て、初めてニヤリとしてしまった。(いつも暗いニュースか、残虐なニュースか、アホらしいニュースばかりだものね~)ドラマ「古畑中学生」放送へ。古畑任三郎の少年時代を描く。オトナ古畑が何であんな風になったのか、その謎もわかるらしい。なんか見る前から、笑えてくる。ふざけてるな~、三谷幸喜。でも、天性の「おふざけ感」が、三谷ドラマの持ち味なんだろうね~。やちまた道も、謎解きが大好きだ。少年時代の愛読書は、怪盗ルパンに、ホームズに、江戸川乱歩シリーズ。この少年時代の推理好きがたたって、とにかく完全犯罪がないように、すべての現象には理由や隠れた意図があると思ってしまい、すべてのことに理由がわからないと落ち着かないようになってしまった。…で、「古畑中学生」。どんなストーリーになるか気になる。推理してみたい。古畑の特長をあげてみる。○何かに執着するオトナになりきれない、子どもじみた性格○有名人好きのミーハー○自転車好き○血を見るのがきらい○完全犯罪ぎらい○母親が出るらしいこの幼児的な執着癖は、小さいころトラウマになるような事件がおきたに違いない。しかも、殺人事件。きっと肉親の犯罪に巻き込まれたに違いない。たぶん尊敬していた有名人の父親が殺された。車に乗らず自転車に乗っているのは、きっと、車による殺害だったにちがいない。その父親を殺したのが、母親だ。母親の秘密を暴くうちに、犯罪者への怒りと、犯罪者への悲しいいとおしさみたいなものが同居してしまった。だから、犯罪者から自発的に告白させるようにもっていく。そうなると、今回のドラマは、その父親殺人の問題解決を少年古畑がするに違いない。で、きっと今と同じようにできの悪い少年今泉君が出てくるに違いない。あたっているかどうか。皆さんもお考え下さい。正解はドラマで。
2008年04月17日
コメント(0)
-
名もなき地方の時代。
いろんなものが金になる。施設の名前も金になる。でもクリスタはいかがなものか…。家から歩いて5分のところに楽天イーグルスの本拠地がある。週末看板を見てずっこけた。去年のフルスタの看板はドリームランドみたいで格好良かったけどね~。でも、クリネックスはどうだろうか。「うそだろう~」ぐらいの、ちっちゃな看板が申し訳程度についている。(これじゃ、ポケットティッシュやね。せめて箱ティッシュぐらいにはしてほしかった。)でも、しょうがないんだろうね~。いろいろ協賛を集めないと地方球団は運営できんだろうから。他にも、県民会館も「東京エレクトロンホール宮城」になったし。(東京なのか宮城なのか…)地方が貧乏な時代。いろんな施設が東京資本のナショナルカンパニーの名前になっていくかも知れないね~。いっそのこと、貧乏な県は県の名前自体を売ったらどうだろう。どんなのがいいか…。杜の都の爽やかなイメージをいかして「ブルーレットみやぎ」とか。濃そうな感じで「リーブ21おきなわ」。りんごのほっぺの赤ちゃんのイメージで「パンパースあおもり」…。なかなか楽しい地方の時代がやってくる、かも。
2008年04月16日
コメント(0)
-
香りと音楽。
日本近代には、またひとり隠された詩人がいた。大手拓次。萩原朔太郎より先に、口語象徴詩を完成させた。しかし、そんなことは一般的な詩史では認められていない。なぜなら、彼は生前詩集のひとつさえ出していない一介のサラリーマンだったから。ただその言葉の妖しいぬめり感、震えるように息づく微細な感覚と色彩、フラジャイルな壊れやすい透明美など、やちまた道的には、朔太郎より本物に感じる。ライオン歯磨本舗・広告部に就職し、今で言えばコピーライターとして働いていた。日本文壇から忘れられた孤高の詩人が書いた商業コピーなんてどんなものだろう、と興味をそそる。ライオンらしく『「香水の表情」に就いて』という文章がある。彼は言う。香りには表情がある。その表情を捉えることによってその奥にある美を捉えることができる、らしい。「香水の表情把握は香水に対する単なる嗅覚的見地から一歩深入りして、香水のかもしだす幻想美をひきだすからだ。」では、具体的に香りにはどんな表情があるのか。1速度感、2重量感、3形態感、4音響感、5時刻感、6季節感、7言語感、8年齢感、9韻律感、10方位感、11振幅感、12色彩感、13金属感、14性別感、15硬度感、16角度感、17容貌感、18性格感、19生物感、20光度感、21触感、22粘着感、23湿度感、24運命感、25生長感……とこんな感じに無限に表情があるという。「さうして、この「感じ」が一つ一つ認められるとともに、また全体が共鳴(ともな)りして、絶えまない水の流れゆくやうな交響楽を奏するのである。で、この綜合感と個々の感じとは、即(つ)き、離れ、即き、離れつつ諧調をなし、破調をなして旋回するのだ。」香りの表情のコレスポンダンス(交感・照応・呼応・調和)。素晴らしい香りの表情への洞察。ブラボー!と言いたい。やちまた道、これが面白いと思ったのは、香りについて言えることが音楽にも言えるのでは、と思いいたったからだ。「香水は、音楽と等しく幻想の芸術だ。次から次へと移りながら、消えてゆく音(おん)を捉へると同様に、散りゆく香気の翅を捉へて動きゆく、重なりゆく、高まりゆく、流れゆく幻想の画像をゑがくのだ。」唄における方位感とはどんなものだろう。(たとえば、島のはるか南の方へ。パイパティローマを夢見た…)唄における光度感とはどんなものだろう。(たとえば、月の真昼間のような幻想的な光の淡さ…)唄における運命感とはどんなものだろう。(たとえば、しょんかねのような、儚い運命に捧げる想い…)香りの表情がそれぞれ共鳴するように、音の表情たちもそれぞれが美しく共鳴するべきだ。どんな音の表情の交感(コレスポンダンス)が、どんな深く香気のある幻想美を描くことができるのだろうか。
2008年04月15日
コメント(0)
-
お花見前哨戦。
仙台もいよいよお花見シーズン。だいたい、2回の週末で満開を楽しめる。その1週目が今回の土日だったんだけど、あいかわらず寒い。名古屋生まれには、なんでこんなに東北の花見は寒いのだろうと思ってしまう。もっと、暖かくなってから咲けばいいのに、と思うが、もしかしたら、春を待ち焦がれている北の人々に少しでも早くお花見気分になってもらおうと桜たちも頑張って咲いているのかも知れない。こう思ったら、東北の桜たちがいとおしくなる。わが三線の会。今年の花見ライブも花見も来週。だから今週はなしのはずだったが、やっぱり、桜見のニュースが流れると、ちょっと様子を見に行きたくなる。練習の後に、お花見前哨戦を行った。立ち飲み、立ち見のつもりが、キレイな花と、周りの盛り上がりを見ると、やっぱり、ちょっと座りたくなる。ブルーシートをゴミ場から取ってきて、なんとど真ん中に陣取る。静かに飲むだけのつもりが、やっぱり、三線を弾きたくなる。月ぬまぴろーまあたりの静かな曲だけかと思ったら、踊りもしたくなる。前哨戦は、本戦へと突入してしまった。ど真ん中で踊り騒いでいるから、周りから文句が出ないかと、内心ハラハラしていたが、なんと、日本舞踊をやっているというお年をめした方も、ちょっと怖い感じの若者たちも、「ちょーカッコイー」「イヤササ、イヤササ」とはやし立てくれた。最後にカチャーシー。みんなで踊りまくった後、みるく節を唄いながらそそくさと撤収。周りが「なんだこの集団」という感じで見ているのを快感に感じながら…。みょーに宴会なれしているわが三線の会、みょーに手際が良くて笑ってしまった。なぞの芸能集団は、来週もきっと踊りまくるに違いない。天気がいいことをみるく様に願う。
2008年04月14日
コメント(0)
-
魂はどこにあるかゲーム。
コーヒーを飲みながら、数人で魂はどこにあるか、という話になった。50%くらいが胸というか心臓あたりを指す。30%くらいが頭を指す。まあ、どちらも無難ではあるが、面白みにかける。ある女性が、「目にあると思う」といった。みんな「おー」と声をあげる。女性は顔を赤らめる。ちょっと、インテリっぽいにいちゃんが「最近の学説に魂はDNAにあるってのがありますよね」と言う。フランシス・クリックか。『あなたの喜怒哀楽や記憶や希望、自己意識と自由意志などは、無数の神経細胞の集まりと、それに関連する分子の働き以外の何ものでもない』ふ~ん。科学者らしい、発想。ここでやちまた道、最近気に入っている説を披露した。ミッシェル・セールの「五感」からパクった説。彼は「魂は皮膚の合わさる場所にある」と言っている。例えば、悔しくて唇を噛みしめる時には、魂は唇にある。ダメだと思って目を閉じたら魂はまぶたに移動する。チクショーと思って拳を握ると手のひらにある。なかなか、美しい詩的な説ではないか。この説でいけば、若者カップルが、手を握ったとき、その手の温もりにドキドキしてしまうのがよ~くわかるよね。唇と唇にいたっては、もう、…。…と、意気揚々と説をぶちまける。気づくと、女性陣がどん引きしていた。それでは、魂の週末を。
2008年04月11日
コメント(0)
-
地獄の沙汰も取引次第。
この時代は、取引の時代だ。どんなものでも取引できる。取引の仕方で人生が決まる。取引しないやつはバカだ。自分に科せられた義務だって取引できる。今話題の「CO2排出量取引」。CO2排出削減目標を上回って削減した企業の分を、目標達成が困難な企業が買い取る。で最終的にみんなで目標達成を実現しよう、という仕組み。う~ん。説明を聞くと、みんなで目標を達成しようなんて、すごく前向きな仕組みに聞こえる。でも、最終的には、自分の義務さえも金で解決しようというものだ。このしくみだと、結局は、「頑張る人はより頑張るようになるし、頑張らない人はさらに頑張らなくなる」のではないか。本来であれば、排出量という目標は、すべての国や企業がクリアしなくてはいけない、そういった最低限のボーダーラインだったはずなのに…。まあ、いっか。姑息な現代人らしいし。どうせなら、この仕組みを使って、いろいろ社会の問題を解決するのもいいかも。例えば、少子化問題。一家に2人の子育てを義務づける。これに足りない家庭は、2人以上育てている家庭に、1人いくらという計算でお金を払わなくてはいけない。(うっ、やばい…)もっと日常でも使えるな~。ボランティア取引、メタボ削減取引、桜の枝を大切にしよう取引、DV削減取引、少年犯罪削減取引など…。さあ、いっぱい取引して、良い社会をつくりましょう。
2008年04月10日
コメント(0)
-
香りと味で、疑似旅行。
臭覚、そして味覚。この2つは、直接記憶と結びついているのかも知れない。あの時の香り、あの時の味を味わうと、一挙に身体全体が昔懐かしいあの場所にワープしてしまう。やちまた道、図らずも、そんなワープを昨日の夜に行った。普通に夕食を食べていた。その中の一品に、いつもとは違う薄目の味噌汁というか吸い物にショウガをのせたものがある。中にモツが入っている。ふーんと、この吸い物を口に含むと、一気に石垣の食堂にワープした。赤い瓦の屋根に、三線の音に、ハイビスカスの花…。パッと、八重山の風景が眼の前に広がった。最初は、理由が分からなかった。ただ、このモツの吸い物の味が、まさに、沖縄でいただく「なかみ汁」の味であることに気づいた。そうか。なかみ汁か。「なかみ」とは、豚の胃,小腸,大腸のこと。まさに、「中身」なわけやね。こちらの「白モツ」を使えば、まあ殆どいっしょなわけだ。カミさんは、ただ、昨日のモツ鍋で残ったモツとキャベツともやしをうすい味噌汁に入れただけ。別に「なかみ汁」を意識したわけではない。ただ(野性のカンなのか)、結果して同じ味になったわけやね~。ほんの数秒だったけど、沖縄の風、八重山の風景を楽しむことができた。と、ここで、やちまた道、いいことに気づいた。このせちがらい世の中、なかなか、沖縄や海外には行けない。でせっかく旅行したら、その土地ならではの香りや、味をいっぱい吸収して記憶中枢の中にたたきこんでこよう。そして、どうしても旅行に行きたくなった時、その時の香りや味を味わおう。こうすれば、忙しくて旅行に行けなくても、擬似的にバカンスを楽しむことができるわけだ。忙しくて貧乏な日本の皆さん。是非、今年の連休や夏休みは、旅先で鼻がいたくなるほど匂いと味をかぎまくってきてください。
2008年04月09日
コメント(0)
-
危うし、カメラ小僧。
やばい。ほんとうにやばい。ネガフィルムの現像をずっと格安のクリーニング屋のDPEサービスを使っていたが、とうとう、安いところは、どこも受け付けてくれなくなった。こういったことは、一気にやってくるみたいだ。ほんの2・3ヶ月前にある店が受け付けてくれなくなったら、バタバタど仙台市内のどこでも受付てくれなくなった。今までは、36枚撮りのネガフィルム(枚数関係ないので36枚撮りを利用していた)で500~600円ぐらいだった。年間かなりの本数を撮るので、とても助かっていた。これが、もう格安DPEがなくなってしまったから、さあ大変。仙台で現在でも対応してくれるところをいろいろ調べてみた。一番安そうな、ホワイト急便のDPEサービスで、現像費300円で同時プリント1枚につき22円。36枚撮りで計算すると1,092円。ヨドバシカメラで、現像費460円で同時プリント1枚につき26円。36枚撮りで計算すると1,396円。他の仙台にあるカメララボを調べてみても、だいたい、ヨドバシ並みかそれ以上だ。コンビニでも、そこそこ安いところがあるみたいだけど、プリントのできが心配だし、いつまでサービスがあるかも心もとない。う~ん、ことごとく1,000円超えか~。しょうがいないのかな~。なんか、もう、フィルムカメラ、やめようかな~。と、やけになってきたとき、ネットで探せば、全国の安いところを探せるのでは、と思いついた。さっそくネットで探してみる。プリントが安い!と思うところは、ネット対応のデジタルプリントだ。やっぱり、フィルムの現像&プリントなんてもう時代遅れなのか?と、あった、あった。埼玉の「デジカメプリント.com46」というお店がフィルムも大歓迎と書いてある。よし、とばかりにメールで値段を聞いて見る。36枚撮りでも、1本690円という丁寧な返事メールが来た。さらに調べると、36枚撮り630円という「超!プリ」「GEKIPRI.COM」というのもある。同時にデータにしてCDにしてくれるサービスもある。(調べればもっと安いところがあるかも…)これなら今までとそんなに変わらんな~。ただ、これに加えて、フィルムの送り賃がかかる。店からの発送は5本までなら標準発送で200円ということ。あと、郵便振り込み手数料で80円か。まあ、5本分一気に送れば、なんとか1本あたり、800円ぐらいには収まりそうだ。ふ~。しかし、こうまでして、撮らなくてはいけないものを、撮っているのだろうか? と自嘲気味になる。…なんか、カメラ小僧にとっては、厳しい逆風の世の中になってきた。
2008年04月08日
コメント(0)
-
人恋しさの映画。
開花宣言の仙台。でも、花見をするにはまだ肌寒い。何もすることがない週末も久しぶりなので、のんびりと、映画でも見に行くことに。観た映画は、迷子の警察音楽隊。2007年のカンヌ映画祭でも絶賛された作品。物語は、文化交流のためにイスラエルにやってきたエジプトのアレキサンドリア警察音楽隊が、空港に出迎えもなく、自分たちで目的地にたどりつこうとして、ホテルすらない辺境の町に迷い込んでしまった、というお話。食堂の女主人に助けられ、地元民の家で一泊させてもらう。そこで、音楽を軸にして、心温まるストーリーが繰り広げられる。もともと、アラブ人とユダヤ人は長い対立してきた。言葉も違うし、考えも違う。突然の訪問で、気まずい雰囲気が流れる中、誰かが「サマータイム」を口ずさむと、急に場が和み、心を解きほぐしていく。音楽があれば、人々は対話をすることができるし、平和への希望をつなぐことができる。そんなメッセージが込められているのだろうか。まあ、そんなメッセージはともかく、やちまた道的には、楽団が真夜中に悲しく奏でていた大正琴のような楽器の音色が気になった。なんという楽器だったんだろう。映画が終わってカミさんに感想を聞いてみる。「もっと、音楽が流れると思った…。」 確かにストーリーに絡めて、もっと楽団の音楽を聴きたかったような気もする。ただ言えることは、人はピュアに人が恋しくなるほど、迷子になることもあるし、人は迷子になった時、はじめてほんとうの音楽恋しさをピュアに感じることができる、という事なのかも知れない。奇をてらわず、抑制のとれた、静かで美しい映画だった。
2008年04月07日
コメント(4)
-
健康レジスタンス。
年金もあてにならない。医療費・保険費も負担があがる。もう、すこぶる健康であることだけが、これからの日本人の唯一の生きる道だ。ということで、やちまた家のスーパー健康類人猿たち(親父とカミさん)から、健康になるためのお智慧を賜ることにする。2人の共通点。とにかく、よく噛む。もうずっと、もぐもぐ食べてる。「いい加減、飲み込めよ!」とつっこみたくなるほど一生懸命噛んでいる。3人でご飯を食べていると、ステレオ状態の「もぐもぐ」がうるさくて、テレビの音が聞こえやしない。もう、なんか、悲しくて笑うしかない。とにかく、最後まで食べる。キャベツの芯や魚のはらわたまで、人があまり食べないものを、むしろ美味しそうにさらうように食べる。とにかく、寝付きも、寝起きもいい。というか、酒がなくなるとすぐ寝てしまう。寝付きの悪い2人を見たことがない。とにかく、楽しい夢を見る。カミさんたまに自分の夢に笑って、その笑い声で目が覚める。天童よしみがバサー(沖縄の民俗衣装)の着方がわからないんです~とやって来たとか。とにかく、よく動く。起きてから、寝るまで、基本的によくちょこちょこ動く。これは、エライ。親父にいたっては、飲んでベロベロでも、よく働く。とにかく、脳天気。悩みがないのか。悩みを忘れちゃうのか。他人のことなんか知ったことか、という感じ。何があっても、ケロッとしているのは、すごい。まあ、とにもかくにも、健康になることだけが、この時代、この日本政府に対する唯一最大のレジスタンスだ。負けるな、日本人!
2008年04月04日
コメント(0)
-
さくら、さくら。
さくらになった。と言っても、桜ではなく、さくら(偽客)だ。仕事上、いろんなイベントで、さくら(偽客)をさせられることがある。(私生活でも、いろんなところでさくら(偽客)をしているから、公私ともにさくら(偽客)人です。)さくらになりながら、桜の季節だけに、なぜ、偽客を「さくら」というのか、気になった。一説では、江戸時代の芝居小屋で、ワッとかけ声を掛けて、お客を盛り上げるのが、パッと咲き散っていく桜の花のようだ、ということでこの名がついたらしい。あと、人を寄せ付けるとか、宴や集いに華を添えるとか、そんなところから、きているのかも知れないな…。偽物だけど、本物ではないけれど、パッと咲いて、パッと盛り上げて、人知れずすっと散っていく。やちまた道、さくら(偽客)人生、まっさかり。
2008年04月03日
コメント(0)
-
ルービック・キューブ。
やちまた道の、家の前まで、道ができている、といった。だが、突然、そのスペースが、壁で囲われた。「なにができるんだ?」「なんか、撤去された自転車の一時置き場になるみたいよ。」と、カミさん。なるほど、道がつながるまで、そのスペースは有効活用できるわけだ。でも、なんかこういう、その場しのぎの都合のいい移動のしかたを見てると、ルービック・キューブでガチャガチャされているみたいで悲しくなるね~。やちまた家の「立ち退き」も、所詮、お役人さんにとっては、ルービック・キューブのよけいな色なんだろうね~。(近代都市は、ルービック・キューブだ。雑多な色は悪。同じ面は、一様に同じ色であることが正義だ。)まあ、やちまた家の話はどうでもいいけど、都合良く撤去される400頭のカンガルーは、とてもかわいそうだ。
2008年04月02日
コメント(0)
-
言葉が生まれた時。
鎖国が終わり、明治になると、西洋の思想が入ってきた。その時に、今では普通の言葉が、造語としてたくさん作られた、と言う。例えば、「情熱」という言葉は北村透谷が造ったとか。ふ~ん。江戸時代には、情熱という言葉はなかったわけやね。(なんかこう「情熱だ~!」みたいな時に、どんな風に言っていたんだろうね~?)情熱以外だと、高山樗牛が「憧憬」、福沢諭吉が「西洋」、漱石が「非人情」、尾崎行雄が「趣味」などを造っているらしい。明治の偉人たちが、このような概念を造ってくれたおかげで、今の日常がゆたかになっている、といっても過言ではないのかも…。「平和」という言葉。この言葉自体は、もともと漢詩などにも使われているみたいだけど、日本語として意味を持って使われだしたのも、明治以降らしい。北村透谷は「平和」という機関誌を出して、その発刊のあいさつの冒頭で「平和の文字甚だ新(あらた)なり…」と意気揚々と語っている。明治以前には、この日本に「平和」という概念自体なかったのかも知れないね~。この言葉のおかげで、まがりなりにも、我々は平和の時代に生きて居られるのかも知れない。ただ、安穏とはしていられない。山本夏彦は次のように言っている。「言葉は乱用されると、内容を失う。敗戦このかた、平和と民主主義については言われすぎた。おかげで内容を失った…」言葉が生命を失ったとき、その場に生きる人間の思想も生活も、死に絶えることになる。
2008年04月01日
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1