2007年10月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
日経の相反する二つの記事について
今日の日経で興味深い記事を二つ見つけたので以下引用します。その1成長企業の軌跡(6)トヨタ自動車(株価上昇率22位)(ブラックマンデー20年) 成長企業の軌跡(6)トヨタ自動車(株価上昇率22位)(ブラックマンデー20年)2007/10/29 日経金融新聞 P 5 トヨタ自動車(7203)にとってブラックマンデー以降の二十年は、「三河の田舎企業」から自動車メーカーとして時価総額世界一の巨大企業へと変貌(へんぼう)を遂げる道のりだった。 一九八七年六月期の連結業績は、売上高六兆六千七百五十四億円に対し経常利益五千十八億円。全国上場企業の経常利益ランキングでは、野村証券や東京電力に次ぐ三位だった。 それが二〇〇七年三月期(米国会計基準)の売上高は二十三兆九千四百八十億円と三・六倍に、税引き前利益は二兆三千八百二十五億円と四・七倍に増加した。税引き前利益が二兆円を超える日本企業は、トヨタのほかに見あたらない。 日産1社分相当 成長の原動力は海外販売の増加だ。八七年の世界販売実績は約三百八十三万台だったが、今年は子会社のダイハツ工業や日野自動車を含まないトヨタ単独で八百四十万台の見込み。この二十年間の世界販売の伸びは四百万台強と、日産自動車の全世界販売を上回る成長を遂げた。 とりわけBRICsをはじめとする新興諸国でモータリゼーションが加速した二〇〇〇年以降は、販売ペースが急上昇。直近五年間で世界販売は約三百万台増加した。一年あたりでは六十万台の増加で、富士重工業一社分の成長が続いてきた計算になる。 もっとも国内販売は八七年の百八十七万台から減少傾向にある。今年は前年実績を上回る百七十二万台の販売計画を打ち出していたが、国内市場の低迷で「百六十万台半ばまで落ち込む」(渡辺捷昭社長)見通しだ。 業績が低迷した時期もあった。一ドル=一〇〇円まで円高・ドル安が進んだ九四年六月期には、売上高営業利益率が一・五%まで低下。自動車輸出を巡る日米自動車交渉を経て、自動車の海外生産に拍車がかかった。 現地生産を強化 トヨタの海外生産拠点は、八七年時点では米ゼネラル・モーターズ(GM)との合弁工場など十数カ所だったが、その後は欧米や中国に工場を相次いで建設。現時点で世界二十六の国と地域に、計五十二の生産事業体が海外各地で現地生産にあたっている。 そして当時のトップだった奥田碩相談役が「二十世紀中に実現すべきプロジェクト」と号令をかけた、世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」の発売と、ニューヨーク・ロンドン市場への株式上場を九九年までに達成。企業イメージの一新と、投資家のすそ野拡大を推し進めた。 近年、力を入れているのは株主配分の拡充だ。公的機関のトヨタ株放出に対応するために、九七年三月期から自社株買いを開始。これまでに二兆五千億円を投じ六億八千万株を取得。うち二億七千万株の自社株を消却してきた。 また二〇〇五年には、配当性向三〇%を目標として設定。〇七年三月期には百二十円の年配当を実施し、連結配当性向は二三・四%まで上昇している。 ただグループ戦略には課題も残る。トヨタは九八年にダイハツ工業を、〇一年には日野自動車の株式を追加取得し子会社化している。だがダイハツの時価総額はスズキの四分の一、日野はいすゞの半分と振るわない。ダイハツ、日野ともに売上高に占める海外比率は三割弱にとどまり、海外展開で後れを取っている。 「商用車と低コスト車の開発は今年度の重要テーマ」(渡辺社長)。先進各国で成功を収めてきたトヨタも、新興諸国では再びチャレンジャーとなる。ダイハツ、日野を含めて新興諸国で確かなシェアを築けるかどうかが、トヨタが輝き続けるための条件といえそうだ。 (名古屋支社 北沢宏之)この記事には秀逸な所とそうでない所(こっちは本当にたいしたことないですが)が一つずつあります。秀逸な点は自動車産業を成長産業とみなしている所です。これは国土交通省のサイトを見れば一目瞭然です。逆にそうでないところは最後の「先進各国で成功を収めてきたトヨタも、新興諸国では再びチャレンジャーとなる。」のくだりで、商圏を拡大するという意味では合っているのですが車の開発、生産という意味ではチャレンジャーじゃなくてリーダーの方が実態に即していると思います。まあ、これはたいした問題でもないのであまり気にしていません…。しかし、次の馬鹿記事を読むとやはり指摘せざるを得ないのかな?と思います。その2環境と少子化が問う車の未来(社説) 環境と少子化が問う車の未来(社説)2007/10/28 日本経済新聞 朝刊 P 2 東京モーターショーが始まった。その直前に、トヨタグループのセントラル自動車が仙台市郊外に車両組み立ての新工場を建設すると発表した。日本車の競争力は強く、自動車メーカー各社は総じて収益が好調な今、新たな供給体制構築を進めている。だが、現在の成功が明日の成功を保証するわけではない。 今日の自動車産業の競争の焦点は環境対応だ。これまで日本車の独壇場だったハイブリッド車でも、欧米勢の追い上げが始まった。燃料電池を含めた電気自動車の開発では、新興の米テスラ・モーターズなど新たな挑戦者が次々に登場している。 トヨタ自動車は、航空機で使われ始めた軽くて強い炭素繊維を導入したコンセプト車を披露した。ホンダの目玉は、指で押すとへこむほど柔らかいシリコン素材を使った燃料電池車だ。いずれも素材の領域まで踏み込んで環境性能の向上を目指す。 過去百年間「化石燃料でエンジンを動かす」という自動車の基本は変わらなかった。二酸化炭素の排出削減が地球規模の課題になる中で、二十一世紀のクルマは大きく変身するだろう。とりわけ電池技術の進化は急で、将来「エンジンのない車」が主流になってもおかしくはない。 日本メーカーの伝統的な強みは、品質改善や効率的な生産体制だ。今後は環境をめぐるイノベーション(技術革新)競争でも、ライバルをリードし続ける必要がある。東京モーターショーは、その意気込みを世界に発信する舞台である。 自動車産業のもう一つの課題は国内市場の低迷だ。日本の景気が緩やかながらも回復しているのに、新車販売台数は下げ止まらない。ある自動車メーカーの首脳は(1)少子高齢化に伴う需要層の減少(2)低所得層の増加による購買力の低下(3)若年層のクルマ離れ――などを指摘し、いずれも構造的な要因だと認めている。 欧米の自動車メーカー首脳が東京より上海など新興市場のモーターショーに関心を示すのも、日本市場の魅力が低下した証左といえる。日本市場の底上げに即効薬はない。消費者の選択のポイントは燃費や維持費の経済性だ。そうした要請に応えるクルマづくりを地道に追求することが、自動車産業の道だろう。この新聞社に限らずどうも新聞社はピント外れな馬鹿記事を堂々と社説にしたがる傾向があるようです。どういう神経しているのでしょうか?売国奴にも程があります。大きな問題箇所は赤字の部分です。自動車産業のもう一つの課題は国内市場の低迷だ。日本の景気が緩やかながらも回復しているのに、新車販売台数は下げ止まらない。再三繰り返すのですが、販売台数では現時点日本はアメリカの次の世界第二位のとても大きな市場なのです。もうすぐ支那とインドに抜かれる運命にありますがそれでも巨大市場には変わりないのです。それがさも衰退市場の代表格であるような書き方をするのはどうかと思います。それに次の部分もおかしいです。日本の景気が緩やかながらも回復しているのに、新車販売台数は下げ止まらない。ある自動車メーカーの首脳は(1)少子高齢化に伴う需要層の減少(2)低所得層の増加による購買力の低下(3)若年層のクルマ離れ――などを指摘し、いずれも構造的な要因だと認めている。一方で景気回復していると書いておきながら、文章の後半部分はどう考えても景気回復と関係ないとしか思えない事象ばかり羅列しています。一体どっちやねんと言いたくなります。しかもこれが社説なんだから笑わせてくれます。あと、いつもどおりというか後半部分も最悪です。欧米の自動車メーカー首脳が東京より上海など新興市場のモーターショーに関心を示すのも、日本市場の魅力が低下した証左といえる。これ、主語誰やねん?、そして証拠どこにあるねん?この内容は全くでたらめです。これは、世界第二位の市場である日本で欧米の自動車が全く売れないのが実態であってその原因は欧米製品の商品力が極めて脆弱だからなのですが、何故そのことに触れないのでしょうか?そして、欧米自動車会社が上海に興味があるのは、競合相手が殆ど勝ち目のない日本製品ではなく欧米の製品よりも数ランク商品力の劣る支那製品(こっちであればかなり勝ち目がある)だからなのと、市場拡大余地が望めるからという理由であって日本市場が魅力的でない(ある意味合ってるのか?)というのとはニュアンス以上に違うと思うのですが、どうなんでしょうか?トリの部分も笑わせます。日本市場の底上げに即効薬はない。消費者の選択のポイントは燃費や維持費の経済性だ。そうした要請に応えるクルマづくりを地道に追求することが、自動車産業の道だろう。燃費や維持費の経済性において日本製品はまだまだ劣っているんでしょうか?おしそうであればそれらに勝る外国の会社を具体的に書いて欲しいです。まあ、日本市場の底上げに即効薬がないのは認めますが(移民という手はありますが現実的ではないと思います。)そもそもこの記事は日本市場が低迷であるということの定義を間違えているからいつものように構成がぐだぐだになるのです。あと基本的な数値を把握していないんじゃないでしょうか?もし把握していてこの記事を書くのであれば相当な確信犯だと思います。しかし、よくこんなの社説に載せるよな…。
2007.10.29
コメント(4)
-
また発な状況…
予想通りアメリカや日本の金融機関の決算がイマイチなようです…。多分この数字は判明分だけなので今まだ抱えている負債の損は計上されてないと思います。また個人投資家には買いたくなる場面が近々きそうです…。のんびり待つのが吉だと思います。
2007.10.25
コメント(0)
-
がちょーん…
なんとドイツ証券武者氏が日本株に死刑宣告が…。日本株は力強い上昇トレンドに入る=ロイターセミナーで武者ドイツ証券副会長2007年 10月 23日 20:42 JST 記事を印刷する[-] 文字サイズ [+] [東京 23日 ロイター] ドイツ証券副会長兼CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)の武者陵司氏は23日、ロイターセミナー「今日の市況における投資戦略」のパネル・ディスカッションに出席し、米国経済が2008年に加速することがポジティブサプライズとなり、日本株はいずれ力強い上昇トレンドに入ると語った。 クレディ・スイス証券チーフ・ストラテジストの市川眞一氏も、米国景気が改善するなら日本株のパフォーマンスは来年に向けて改善すると予想、ここから日本株に弱気になる必要はないと述べた。 一方、JPモルガン証券チーフエコノミストの菅野雅明氏は、円安水準がしばらく続くことから、輸出企業の収益性が相対的に高くなるとの見通しを示した。 武者氏はサブプライム問題に苦しむ米国経済について、住宅価格上昇による景気けん引効果の反動が大きかったのは過去1年であり「最悪の時期は過ぎつつある」と指摘。景気循環的にもリセッションに入る条件は整っておらず、金融政策の効果やエマージング諸国の経済成長もあって米国景気に強気の見方を示し「マーケットのサプライズ(になるの)は2008年に米国経済が加速することだ」と語った。 このため、日本株を考えるにあたっては「グローバル・グロースに焦点を絞り、1年先をみて運用を考えるべきだ。日本株はいずれ、力強い上昇トレンドに入る」としている。 市川氏も、日本株に対しては「ここから弱気になる必要はない」とみている。2002年末を起点に考えると日米欧の株式を比較しても日本株のパフォーマンスは悪くなく、過去16カ月間の日本株のアンダーパフォームは、2005年後半以降日本株が強かったことで生じた過剰な期待感の調整によるものとしている。 サブプライム問題で世界経済は難しい局面に入っているが、日米金融当局の政策運営に加え、世界の市場に流動性を供給してきた石油系マネーや中国などのソブリンマネーの動きも続いていることから「米国景気が改善するなら、日本株のパフォーマンスも来年に向けて改善する」と予想している。 日本の企業業績についても2008年3月期は7─8%、2009年3月期は13─14%の増益を見込んでいる。 一方、菅野氏は、日銀の金融政策に関連して「(日銀は)上げる上げると言いながら、なかなか金利は上がらないと思う。その結果として円安の時代がしばらく続き、輸出企業は相対的に収益性が高い形になる」との見通しを示した。サブプライム問題については「10─12月期の米銀の決算が出れば、全体の損失額もある程度わかって、収束に向かうと思っている」と語った。私の強気は許されても彼の強気は許されないと思うのは私だけでしょうか?(笑)ていうか、証券会社の社員が市況を語るなんて胡散臭いこと極まりないですよね。自社で抱えている証券を個人投資家に高値で買い取らせる以外の理由が思いつきません。(更には売り叩き安値で買い戻す可能性も高いと思います。)しかし、何度も書くように郵便局の買い増し攻勢もあるので案外彼の言う事は当たるかも(但し理由は違いますが)とも思っています。そう考えると極端に悲観する場面じゃないかもしれないです。しかし、このニュースはいただけないですね。(苦笑)
2007.10.23
コメント(5)
-
インターネットエクスプローラー7
先日インターネットエクスプローラー7にバージョンアップしたんですが、やたら止まるし文字は入力できなくなるしでどうしようもありませんでした。ネットで調べたら案の定不具合が多いとの情報があり、アンインストールすれば元のバージョンに戻せるということだったので早速アンインストールしました。信頼性は非常に重要だと感じた数日でした。
2007.10.22
コメント(0)
-
しぶといですね…。
今日大型株は災難でしたが小型株や低位株は結構堅調でした。サラ金やIT銘柄が結構上がっている所を見ると、中長期的には買いの場面かな?と改めて思います。今回のサブプライム問題は根が深いと思うのですが、8/17よりも下げることはないような気がしています。これは妄想なのですが、郵便局が低位株を買ってるんじゃないでしょうか?別に低位株でなくてもいいのですが郵便局はかなり大きな資金を持っているので個人投資家にとっては強い見方になりうると思います。ちょっと明日明後日から色々買いたくなります。
2007.10.22
コメント(0)
-
20日の日記
最近日本株が好調だった矢先にアメリカ市場がやっとこさ下がりました。今幸いにも株券は持っていないので今度はちゃんと下がったところを狙おうと思います。 場中見れたら空売りしたい場面だと思います。 そこそこ下げると思うのですが多分8/17よりも酷くならないような気がします。 需給面では今回は郵便局が強い味方についてくれると思っています。
2007.10.20
コメント(0)
-
読み飛ばし推奨
10/12の日記の続きです。結局亀田選手が謝罪する方向で落ち着きそうですが、(そもそもしらけているんで個人的にはどっちでもいいですが。)あの試合の後に気づいたのですが、あの試合の後にこんなパフォーマンスをしていたらどうだったでしょう…。試合後いきなり土下座して大声で「あんた(内藤選手)には家族ぐるみで反則してでも勝とうと思ってたけど歯が立たんかった。あんたは最強や!!完敗や!!せやけど、今度はめっちゃトレーニングして普通に勝ったるで!!」個人的には、その後のワイドショーの扱いも大分違っていたのではないかと思います。あいかし、亀田選手を褒めちぎっていた番組までも手のひらを返したような態度を取るのはちょっと納得しにくいです…。テレビ局も商売している以上仕方がないのでしょうが、本来の彼等を知っているテレビ局までもそういう態度を取るのはいただけないですね。今回一番株を下げたのはTBSだと思います。
2007.10.20
コメント(0)
-
最近の状況
最近忙しくて寝不足気味で集中力や判断力が低下気味です…。ちょっとゆっくりしたい今日この頃です。
2007.10.18
コメント(2)
-
日本株について
ちょっと気になって世界株価指数改めて見てみたんですが、支那や香港の指数えらいことになってますね。2006年初頭に買っておけば放置しちえて株価が3倍から4倍です。こんなん見ると日本株はあほらしすぎてやってられない気持ちになるのは私だけでしょうか?こっちのチャート見るともっともっとあほらしくなること請け合いなしです。はぁ…ため息出てきた…。
2007.10.17
コメント(0)
-
16日の日記
明日の夜にアメリカの住宅販売戸数が発表されるんで明日の朝手仕舞いするつもりだったのですが野村證券の件もあって今日大半を手仕舞いしました。あのローンの性格上被害額が少なくなることは考えにくいので寧ろ空売り仕掛けるべき場面だったかと思いました。場が見れたら積極的に仕掛けるのですがいつものように様子見です。しこしこスクリーニングでもして過ごすつもりです。 まあ暴騰したらしたで諦めます。(苦笑) 今日も海運株強かったのでそっちにくら替えするのもいいかもと思ったりもします。
2007.10.16
コメント(0)
-
いきなりベアモード
野村證券の決算すごいのが出ましたね。明日以降サブブライムの影響が不安なので大半を手仕舞いしました。これで明日爆上げしたらまた置いていかれますがしょうがないと思います。
2007.10.16
コメント(0)
-
無題
今日はある銘柄群のパフォーマンス等を書こうと思ったんいたのですが時間が取れず書けませんでした。しかし気になる事をいくつか見つけたので近日中にアップしようと思います。しかしいろんな方々が既に書かれていますが、売られすぎの時にいかに我慢強く買いに行けるかというのも重要な投資法の一つかもしれないと思い始めています。ただし必ずしもそれは正解だとは思いませんが…。ベストなのは早いうちに損切りして底値まで空売るか底値付近で買い戻す事だと思いますし粉飾決算や下方修正でリリバウンドが取れない場合もあるので゙。しかし来週以降も個人的には強気です。株券買って損する気がしません。(苦笑)ちょっとこれはまずいかなとも思っています。
2007.10.14
コメント(0)
-
銘柄探し等
四季報等を見て安い銘柄を探しています。最近DAIBOUCHOUさんの著書「サイクル投資法」を読み直しているのですが、定量分析、定性分析について大変勉強になります。その本に刺激されたのもありますが市場そのものが莫大に拡大している業界、及び異様に評価の低い業界の銘柄を探しています。業界ではないのですが会社であればダイエー、日本航空辺りかなという気がしています。見つけ次第blogにアップしようと思います。
2007.10.13
コメント(0)
-
読み飛ばし推奨
昨日の内藤大介と亀田大穀の試合をさっきyoutubeで見たのですが、点数ほど差のついた試合じゃなかった感じですね。個人的には大穀君見直してしまいました。個人的には、「八百長やらんでもちゃんとボクシングできるやんけ。ジャブの練習さえちゃんとやればまあまあいけるんちゃう?」と思いました。まあ、次はアックスボンバー~16文キック~ブレーンバスターを決めたら仮に反則取られても観客は強者だと評価すると思います。(笑)まあ、ボクシングには負けましたが、タイマンでは勝ってたんちゃうの?という感じですね。TBSも八百長組む暇あったらちゃんとトレーニングさせとけば視聴者の支持取れるかもと気づいたかもですね。再戦があるかどうか分かりませんが個人的にはちょっと楽しみです。
2007.10.12
コメント(4)
-
いい感じですね
今日もいい感じで推移した印象があります。まだもう一回暴落あると予想しているのですが外れたかも…。(汗)金融機関の損失額によると思うのですがまだ不安感があります…。今から買っても十二分に儲け代あるんでしこしこ押し目買いするんがいいかもと思ったりしています。
2007.10.11
コメント(0)
-
多分ですが…
今日も小型株は強烈でした…。大分置いていかれてしまいましたが、個人的にはこれから小型株が注目されるんじゃないかという気がします。また半年以内に一回は買い時が来るのではないかとも思っていますのでそう焦っていません。しかしもう少し下がると思っていたのでこの時期の反転?は意外でした…。
2007.10.09
コメント(2)
-
さて
そろそろ個人投資家が息を吹き返す時期にさしかかってきたようです。これから数年は日本株に投資する個人投資家にとっていい状況になるような気がします。
2007.10.05
コメント(2)
-
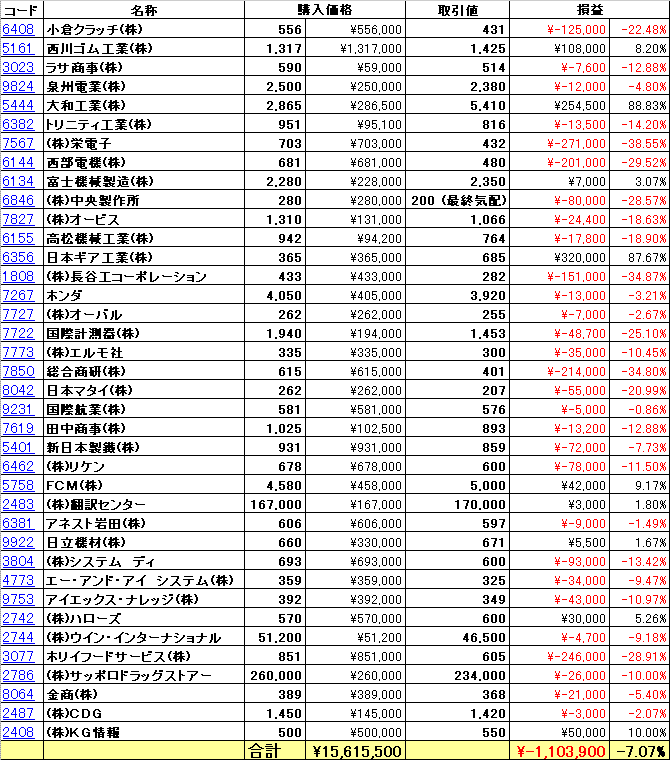
たらればファンドの状況
夕方の日記の続きです。私が独自に見つけた「たらればファンド」のパフォーマンスです。銘柄は最新のを織り込んでいます。本来損切り銘柄や入れ替え銘柄があるのですが、計算が面倒なのでそのまま載せています。(基本的に下方修正、及び購入後-15%で損切りとしています。)これも残念ながら元本割れしています…。投資商品としては不合格ですね…。(別にこれを情報商材で売ってはいませんが…。)因みに下方修正、及び減益理由でたらればファンドから外す予定の銘柄は、6408 小倉クラッチ7567 栄電子1808 長谷工8042 日本マタイの4銘柄です。
2007.10.03
コメント(0)
-
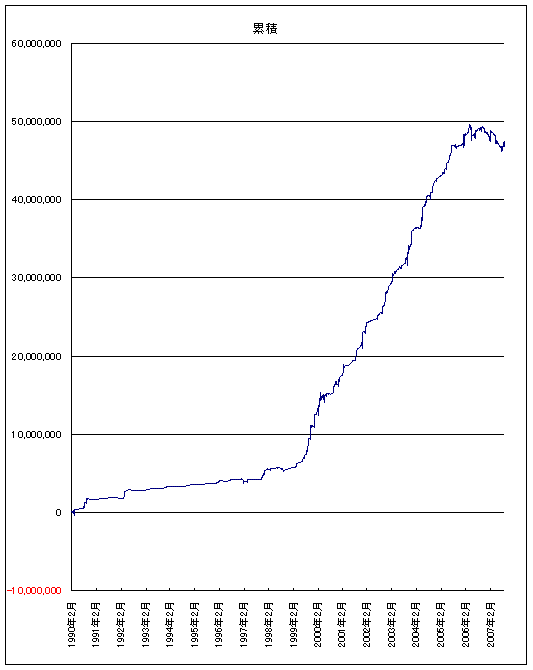
あるシストレのパフォーマンス
夕方の日記の続きです。これはあるシストレ商材のパフォーマンスです。売買手法は伏せておきますが、この商品が販売されたのは2006年でした。ちょっと見づらいのですが、損益グラフもその頃を境にして下降の一途を辿っています。それも商品を販売してからずっとマイナストレンドです。これがまさしくシストレの恐怖だと思います。過去長年通用した手法が将来通用必ずしも通用するとは限らないという一例だと思います。この仕組みを解明しない限り、安易なシストレは破産への片道切符だと思います。
2007.10.03
コメント(0)
-
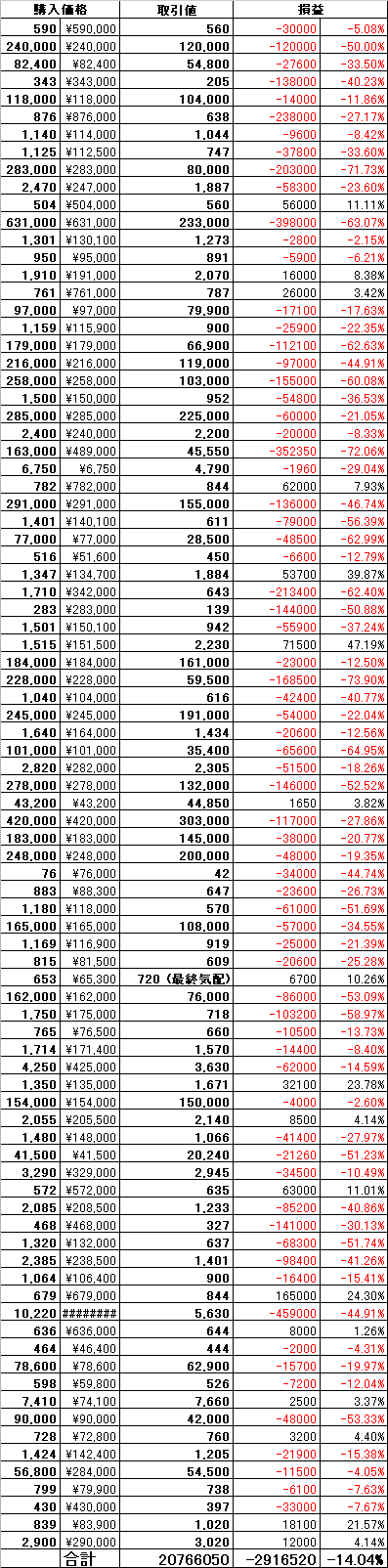
あるファンドのパフォーマンス
夕方の日記の続きです。あるファンドのパフォーマンスです。これは銘柄紹介後に寄り成りで1単位ずつ購入したものを単純計算しています。本当は銘柄名もあるのですがその部分は削除して載せています。
2007.10.03
コメント(0)
-
情報商材
ウィキペディアにも載ってますが、昨今情報商材が流行っているみたいですね。具体的な手口や返金方法等も乗っていて参考になります。今更ですが理由は何であれ元本以下のパフォーマンスしか出せないファンドには何の価値もないですね。さっさと死刑、いやつぶすべきだと思います。今日は気分が優れないのもあるんですが後で某投資商品のパフォーマンスを載せようと思います。これらもバックテストが良かったり過去とんでもないパフォーマンスを出した投資手法というのが触れ込みだったんですが…。いやはや…。
2007.10.03
コメント(0)
-
もう逆張りなんてやらん!!(涙)
8/17の暴落後に買い付けた小型株が最近すごい勢いで吹いています。私が買い付けた銘柄もほぼ元本まで戻りました。しかし今回恐怖感から一割損したところで売却してしまったのでちっともよくありません。しかも売った後に含み損が二割を突破していた時もあったので尚更です。自分で調べた限りその場面は統計上買い増しするべきだったのですが…。しかしリバウンド所要日数が増えていたのもあったので次回も通用するのか不安であります。今回はタイミングもどんぴしゃで完璧だったのですがなかなか上手く行きません。もう当面逆張り禁止しようと思います。ムカつくだけです。
2007.10.03
コメント(0)
-
四季報でスクリーニングしています…。
最近四季報CDスクリーニング機能が使いやすくなったのもあって色々いじってます。誰の目にも明らかな割安銘柄が出てくるので億万長者に簡単になれそうな気がしてしょうがありません(笑)。財務指標や株主構成でも色んな切り口で調べてます。既に禁断の空売りグループ(仮称)も出来てしまいました。(汗)これは財務や業績に関係ない指標で選んでいるのですが密かにちょっと自信があります。(苦笑)その企業群の問題点を強いて上げるなら社風に尽きるのですが、親会社が自分の会社をこかせる社風であるなら子会社もほぼ間違いなく親会社と同じなので四季報使えば簡単に見つかるのです。(笑)衰退する社風というと不思議に聞こえますが、上場企業には結構そういう会社が沢山あります。新聞等ではそういう会社が数年に一度業績が上向くたびに「この企業は過去の失敗から学んで復活した。」とか書いてたりしますがそんな上手く学習して復活を遂げた奇特な会社を見たことがありません。(笑)大体復活する主な理由は、当然市況が味方するというのが大前提ですが、大抵はリストラの効果と会社が倒れ掛かった時だけ本気になる社風を持っているの二つしかないのです。少し考えればわかるのですが無能な経営陣を育て続ける風土を社内で数十年に渡って熟成しているのをたかが数年程度で劇的に変える事なんてほぼ不可能です。という事は、過去十数年間山あり谷ありの会社は今後も山あり谷ありの運命をたどる可能性が高いということがいえると思います。何故なら過去数十年間そうだったからです。(笑)という事から考えると繁栄している業界で過去に会社がこけかけた会社やそのグループ会社は長期間で買い向かうのはあまり賢明ではないと思います。
2007.10.01
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1










