カテゴリ: 鉄道 / Trains
2019年5月26日、小田急ファミリー鉄道展で撮影した、マルチプルタイタンバーです。
線路の下には電車の衝撃を受け止めるため、枕木の下に石が敷いてあり、クッションの役割をしています。一日に何度も電車が通ると石の状態が悪くなり、線路が凸凹になるので、マルチプルタイタンバー(略してマルタイ)が直していきます。以前は社員が手作業で敷石を直し、大変な作業でしたが、この機械を導入することで、作業が軽減されたそうです。
マルタイは、オーストリアのブラッサー&トイラー社製で、1か月の船便で、2017年11月に到着しました。車両の長さは26メートル、重さは80トン、ディーゼルエンジンです。作業量は一般平均800mです。
クランプという機械で線路を持ち上げ、タンピングツールという爪で石を押し込み、つき固めます。騒音やほこりがでないように、扉が下まで動きます。

↑ 小田急のマルタイ(マルチプルタイタンバー)。

↑ マルチプルタイタンバーの説明。
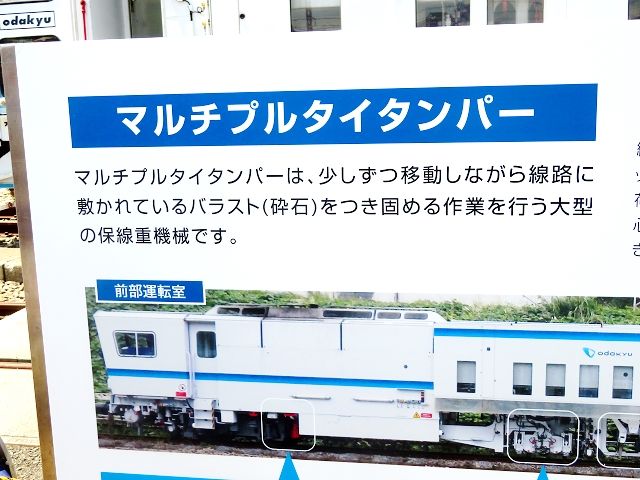
↑ マルチプルタイタンバーは、少しずつ移動しながら線路に敷かれているバラスト(砕石)をつき固める作業を行う大型の保線重機械。
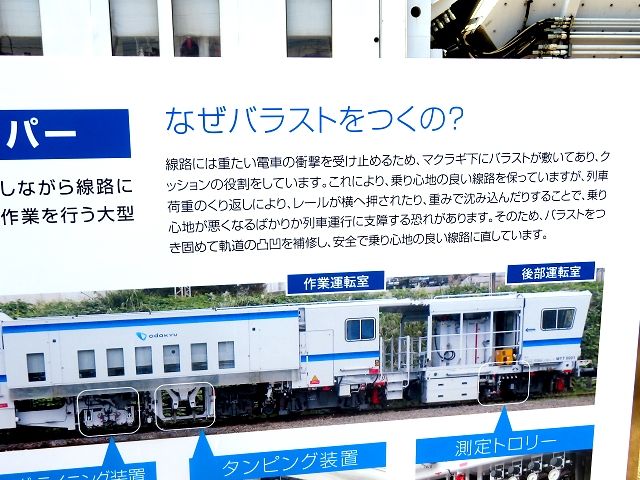
↑ 線路には重たい電車の衝撃を受け止めるため、マクラギの下にバラストが敷いてあり、クッションの役割をしている。これで乗り心地の良い線路を保っているが、列車荷重の繰り返しにより、レールが横へ押されたり、重みで沈んだりすることで、乗り心地が悪くなるばかりか列車運行に支障する恐れがある。そのため、バラストをつき固めて軌道の凸凹を補修し、安全で乗り心地の良い線路に直している。


↑ 脱線復旧装置。


↑ リフティング・ライニング装置。
タンピング装置の動きに合わせてレール及びマクラギを設定した高上量に持ち上げる装置。それと同時にレールを左右へ動かし、横の歪みも補修することができる。
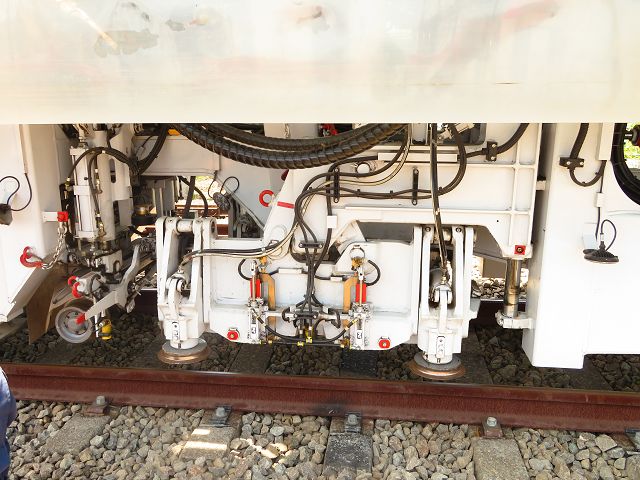



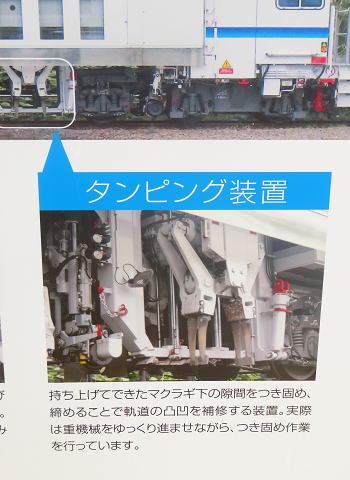
↑ タンピング装置。
持ち上げてできたマクラギ下の隙間をつき固め、締めることで軌道の凹凸を補修する装置。実際は重機械をゆっくり進ませながら、つき固め作業を行っている。

↑ 線路、マクラギとバラスト(砕石)。

↑ タンピングツールという爪。



↑ 爪をバラストの中に突き刺し、振動でつき固める。


↑ 防音扉が下がり始める。

↑ 下がる途中。

↑ 防音扉が下まで下がった。

↑ 測定トロリー。


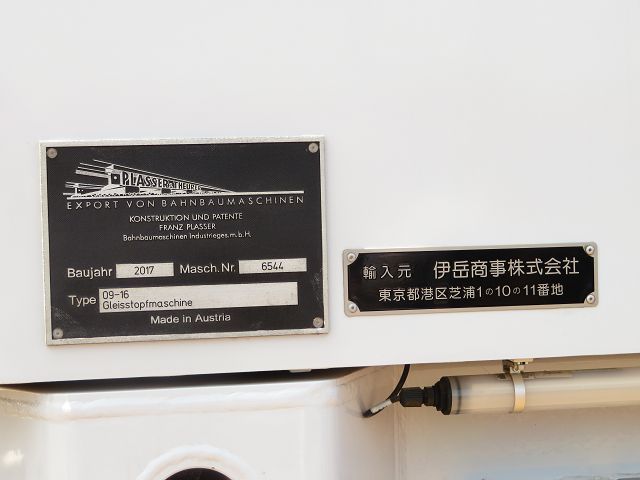

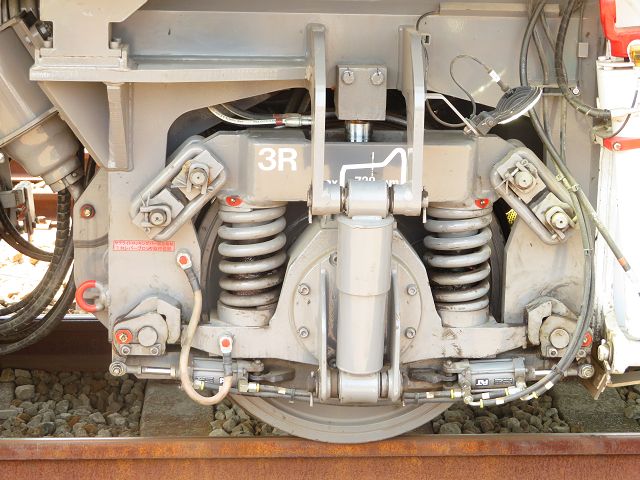
線路の下には電車の衝撃を受け止めるため、枕木の下に石が敷いてあり、クッションの役割をしています。一日に何度も電車が通ると石の状態が悪くなり、線路が凸凹になるので、マルチプルタイタンバー(略してマルタイ)が直していきます。以前は社員が手作業で敷石を直し、大変な作業でしたが、この機械を導入することで、作業が軽減されたそうです。
マルタイは、オーストリアのブラッサー&トイラー社製で、1か月の船便で、2017年11月に到着しました。車両の長さは26メートル、重さは80トン、ディーゼルエンジンです。作業量は一般平均800mです。
クランプという機械で線路を持ち上げ、タンピングツールという爪で石を押し込み、つき固めます。騒音やほこりがでないように、扉が下まで動きます。

↑ 小田急のマルタイ(マルチプルタイタンバー)。

↑ マルチプルタイタンバーの説明。
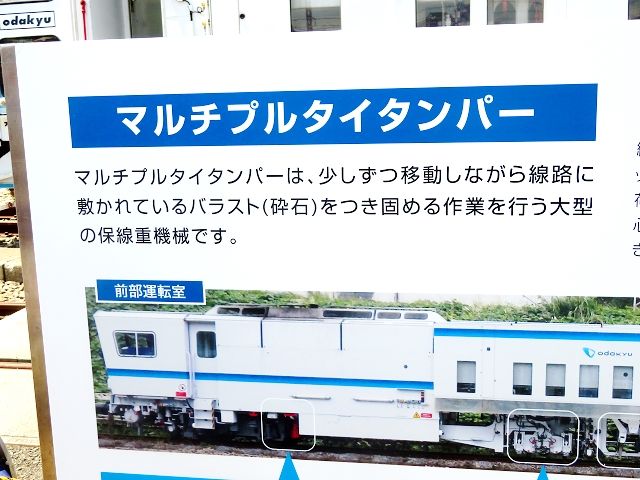
↑ マルチプルタイタンバーは、少しずつ移動しながら線路に敷かれているバラスト(砕石)をつき固める作業を行う大型の保線重機械。
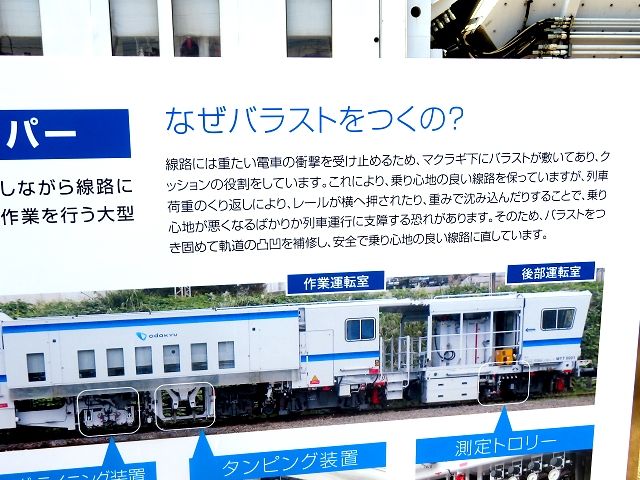
↑ 線路には重たい電車の衝撃を受け止めるため、マクラギの下にバラストが敷いてあり、クッションの役割をしている。これで乗り心地の良い線路を保っているが、列車荷重の繰り返しにより、レールが横へ押されたり、重みで沈んだりすることで、乗り心地が悪くなるばかりか列車運行に支障する恐れがある。そのため、バラストをつき固めて軌道の凸凹を補修し、安全で乗り心地の良い線路に直している。


↑ 脱線復旧装置。


↑ リフティング・ライニング装置。
タンピング装置の動きに合わせてレール及びマクラギを設定した高上量に持ち上げる装置。それと同時にレールを左右へ動かし、横の歪みも補修することができる。
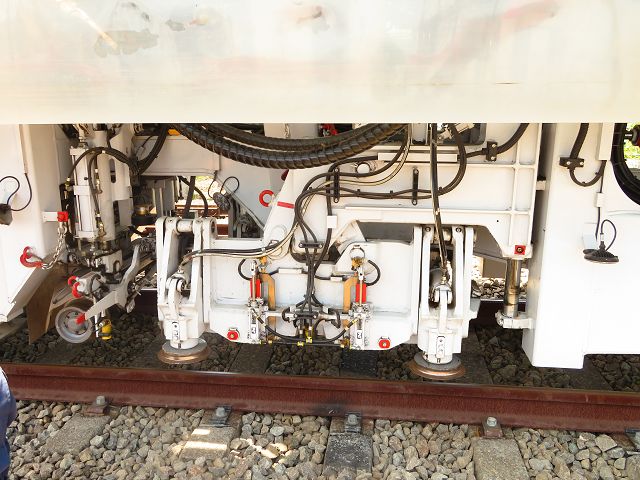



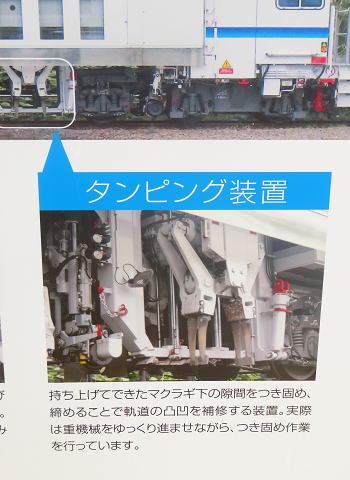
↑ タンピング装置。
持ち上げてできたマクラギ下の隙間をつき固め、締めることで軌道の凹凸を補修する装置。実際は重機械をゆっくり進ませながら、つき固め作業を行っている。

↑ 線路、マクラギとバラスト(砕石)。

↑ タンピングツールという爪。



↑ 爪をバラストの中に突き刺し、振動でつき固める。


↑ 防音扉が下がり始める。

↑ 下がる途中。

↑ 防音扉が下まで下がった。

↑ 測定トロリー。


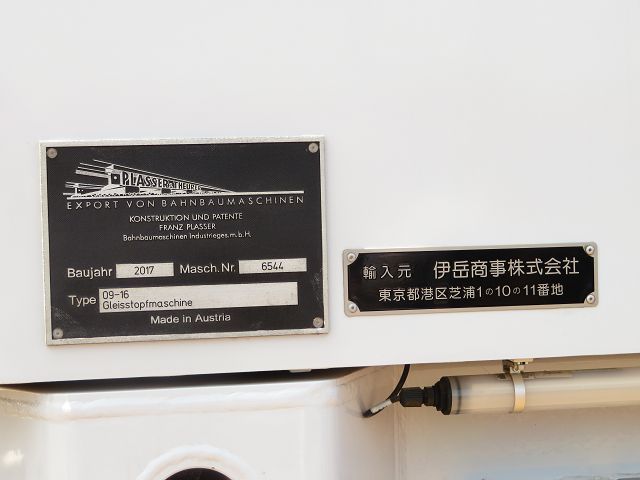

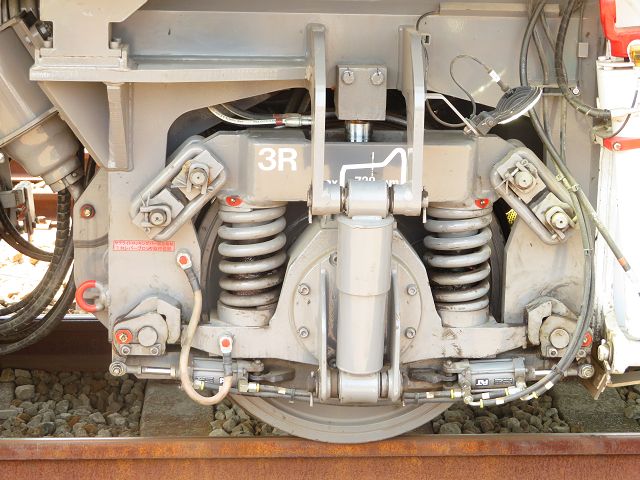
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[鉄道 / Trains] カテゴリの最新記事
-
JR東日本パンフ(銀山温泉・山形県) 2024.05.28 コメント(1)
-
北陸フリーきっぷ(東尋坊・福井県) 2024.05.27 コメント(1)
-
E259とE257・品川駅(2024年5月4日 2024.05.11 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
山歩き / Hiking
(82)河合奈保子さん
(484)歌謡曲/映画/テレビ
(202)ウォーキング
(39)メーテル
(45)美術 / Art
(250)ガンダム・イデオンなどロボット
(13)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー
(30)星 / Stars
(77)カワセミ / Kingfishers
(18)鉄道 / Trains
(195)飛行機の機窓/飛行機
(32)カメラ / Camera
(5)本、雑誌、記録
(89)英語の本
(2)鳥類 / Birds
(31)ペット / Pet
(43)国内旅行(関東・甲州・信州)
(296)国内旅行 (東海・北陸)
(14)国内旅行(関西)
(67)国内旅行(中国地方)
(55)国内旅行(九州)
(70)国内旅行(四国)
(10)国内旅行(東北)
(1)国内旅行(北海道)
(15)城
(52)気象・災害
(22)昆虫/Insects
(5)花・植物
(9)車窓
(10)パンダ
(4)ヨーロッパの曲
(4)オランダ / The Netherlands
(1)オーストリア/Austria
(1)ドイツ/Germany
(2)フランス/FRANCE
(2)イタリア(ITALY)
(7)イギリス(UK)
(4)アメリカ/U.S.A
(6)中国/China
(40)シンガポール/SINGAPORE
(3)台湾
(1)料理
(25)スポーツ
(62)病気
(7)ニュース
(2)© Rakuten Group, Inc.








