PR
X
Calendar
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教
Category
寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)
(64)自由が丘氏寄稿文
(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など
(326)政治・経済(国内統計etc.)
(655)世界、国際比較(国際統計etc.)
(224)生活全般
(125)基本事情(各国)
(114)アジア州
(248)ヨーロッパ州
(275)北米地区
(182)中南米地区
(112)オセアニア州
(95)中東地区
(51)アフリカ州
(126)宇宙の不思議・開発etc.
(71)気候変動など
(7)津波・自然災害
(30)自然の脅威、驚異etc.
(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)
(49)発電・原発事故・放射能事故
(74)金融(事件含む)
(128)PC・家電
(229)スポーツ・余暇・車
(262)栄養・健康
(142)病気・伝染病など
(182)事故・災害
(102)福祉・厚生・年金問題
(59)公害
(15)流通(商品)・廃棄関連
(17)新技術
(30)友人・知人・地縁等
(40)土佐の高知
(63)夢
(49)お墓・葬儀・戸籍
(24)ガーデニング&DIY
(14)TV番組
(15)海外旅行
(6)国防/テロなど
(41)財政・税・電子証明など
(28)自治体、地元、遺産など
(37)店舗
(6)公衆道徳/法律など
(26)裁判/調停
(7)宗教
(21)ブログ
(31)テンプレート(表形式etc.)
(3)DVD収録など
(6)ホームページ、ウエブ会議など
(48)祝い事など
(13)会社時代
(22)学生時代
(7)物語り
(43)経済学研究
(26)思考紀行
(73)作業中マーク(終了次第削除)
(0)カテゴリ: 思考紀行
☆
我々倭人 (?) は北海道というと
昔から日本人が住んでいたように錯覚する。
これは、沖縄が琉球王国の独立体としてよりも、
古来から日本の薩摩に隷属していたと
錯覚するのと同じかもしれない。
////////////
(?)
日本列島は大陸からプレートの力の反動で
日本海に一旦落ち、プレートの力で
東側が持ち上がったようだから、
遅かれ早かれ渡来人の島国である。
海に囲まれた、狭い国土であり
渡来人の国は急速にまとまった
のが国の生い立ちであろう。
///////////
☆
スキーでニセコに行くように、
また、札幌薄野でジンギスカンをつまみ、
生ビールを飲んだり、
十勝バターを食べ、
雪まつりを楽しむように非常に
北海道を身近に感じる。
☆
WIKIPEDIAや、北海道開拓史によると、
しかし、北海道は
それほど古い昔から日本であったわけではない。
日本人が蝦夷地に進出して、
現地のアイヌ人を完全に支配化に治めた のは、
それほど昔ではないのである。
渡島半島周辺を除く現在の北海道を中心に、
樺太と千島を含む蝦夷地
(アイヌ人がアイヌモシリと呼ぶ)には、
15C~16Cにかけて
渡島半島南部の領主に成長していった蠣崎氏
(かきざきうじ)は
豊臣秀吉(関白、太閤)・
徳川家康(征夷大将軍)から蝦夷地の支配権、
交易権を公認された。
江戸時代になると蠣崎氏は
松前氏と改名して大名に列し、
松前藩となる。
北海道太平洋側と千島を東蝦夷と呼び、
北海道日本海側と樺太を西蝦夷地と呼んだ。
ところが寛政から文化期に入ると
幕府は南下政策を強力に推し進めるロシアを警戒し、
1799年(寛政11年)に東蝦夷地を、
1807年(文化4年)に西蝦夷地を天領として、
1809年、カラフト島の呼称を北蝦夷地と
正式に定めた上で
東北諸藩に警備を目的とした出兵を命じた。
緊張が緩和したと思われた1821年(文政4年)には
蝦夷地の大半を松前藩へと返却したが、
諸外国との緊張が再び高まった
1855年(安政2年)には
渡島半島の一部を除いて再び天領とした。
幕府は財政負担軽減のために
仙台、盛岡、弘前、久保田、松前の
東北の大藩に対して沿岸の警備義務を割り当てて、
会津と庄内の2藩もそれに続いた。
1869年6月27日(明治2年5月18日)の箱館戦争終結
をもって戊辰戦争が終わると、
同年9月20日(明治2年8月15日)に
新政府は太政官布告によって
蝦夷地に北海道の名前を与え、
北蝦夷地は樺太と改名した。
ほどなく旧幕府各藩をはじめとし、
諸勢力に対して蝦夷地を分領することで
その開拓を促したが、
命じられた藩が早々に辞退を申し出るなど
成果に乏しく、 困難を極めた。
そこで明治政府は再び蝦夷地を直轄化
開拓使にそれを統括させて現在に至る。
なお、この時最後まで蝦夷地であった地域には
北海道11国86郡のうち下記の令制国が置かれた。
和人地であった 令制国 である。
明治以前までの蝦夷の地はおそらく
有史以来一度も斧を入れたこともない大原始林に
覆われ、 そこに住む人々は鳥獣を狩り、野草を摘み、
川や海の魚を捕って生活していました。
彼らは蝦夷の先住民
(原日本人とも言われている)でしたが、
文字を持ってなかったので
その歴史はよく分かっていません。
明治維新後、国策は一変します。
失業した士族の救済、
ロシアの侵攻に備えた屯田兵の創設、
そして何より、欧米列強に対抗するため
富国強兵の道を 歩み始めた新政府にとって
石炭、木材、硫黄などの
無尽蔵とも思えた天然資源は、
日本近代化の大きな原動力とうつりました。
つまり、北海道開拓のもっとも主要な動機は、
日本近代化のための資源の開発であり、
このことが、北海道開拓の基本的なパターンを
決定しました。
育苗したのではないでしょうか。
北海道の大規模農林業を今一度見直して、
大規模農業にあった土地の再構築、
防風林・道路の再構築などを図り、
防風林の整備、住宅地の再整備などを
計画的に行う必要があるのではないでしょうか。
☆
今、内地で行われている台風災害復旧とは
全く異なる大規模農地・防風林開発計画で
災害復旧を図るべきだと思います。
災害復旧の初期から、
計画的な実装を設計するべきでしょう。
☆
呆け老人・素人の言うことではないでしょうが・・・
高橋はるみ北海道知事に頑張ってほしい!
都市計画なども、熊本県で大人足のような場所に
むやみやたらに住宅地を建設するようなことが、
北海道では行われていたようである。
自由と無計画では大きな違いである。
危機管理が全くない都市計画ではいけないのである!
我々倭人 (?) は北海道というと
昔から日本人が住んでいたように錯覚する。
これは、沖縄が琉球王国の独立体としてよりも、
古来から日本の薩摩に隷属していたと
錯覚するのと同じかもしれない。
////////////
(?)
日本列島は大陸からプレートの力の反動で
日本海に一旦落ち、プレートの力で
東側が持ち上がったようだから、
遅かれ早かれ渡来人の島国である。
海に囲まれた、狭い国土であり
渡来人の国は急速にまとまった
のが国の生い立ちであろう。
///////////
☆
スキーでニセコに行くように、
また、札幌薄野でジンギスカンをつまみ、
生ビールを飲んだり、
十勝バターを食べ、
雪まつりを楽しむように非常に
北海道を身近に感じる。
☆
WIKIPEDIAや、北海道開拓史によると、
しかし、北海道は
それほど古い昔から日本であったわけではない。
日本人が蝦夷地に進出して、
現地のアイヌ人を完全に支配化に治めた のは、
それほど昔ではないのである。
渡島半島周辺を除く現在の北海道を中心に、
樺太と千島を含む蝦夷地
(アイヌ人がアイヌモシリと呼ぶ)には、
15C~16Cにかけて
渡島半島南部の領主に成長していった蠣崎氏
(かきざきうじ)は
豊臣秀吉(関白、太閤)・
徳川家康(征夷大将軍)から蝦夷地の支配権、
交易権を公認された。
江戸時代になると蠣崎氏は
松前氏と改名して大名に列し、
松前藩となる。
北海道太平洋側と千島を東蝦夷と呼び、
北海道日本海側と樺太を西蝦夷地と呼んだ。
ところが寛政から文化期に入ると
幕府は南下政策を強力に推し進めるロシアを警戒し、
1799年(寛政11年)に東蝦夷地を、
1807年(文化4年)に西蝦夷地を天領として、
1809年、カラフト島の呼称を北蝦夷地と
正式に定めた上で
東北諸藩に警備を目的とした出兵を命じた。
緊張が緩和したと思われた1821年(文政4年)には
蝦夷地の大半を松前藩へと返却したが、
諸外国との緊張が再び高まった
1855年(安政2年)には
渡島半島の一部を除いて再び天領とした。
幕府は財政負担軽減のために
仙台、盛岡、弘前、久保田、松前の
東北の大藩に対して沿岸の警備義務を割り当てて、
会津と庄内の2藩もそれに続いた。
1869年6月27日(明治2年5月18日)の箱館戦争終結
をもって戊辰戦争が終わると、
同年9月20日(明治2年8月15日)に
新政府は太政官布告によって
蝦夷地に北海道の名前を与え、
北蝦夷地は樺太と改名した。
ほどなく旧幕府各藩をはじめとし、
諸勢力に対して蝦夷地を分領することで
その開拓を促したが、
命じられた藩が早々に辞退を申し出るなど
成果に乏しく、 困難を極めた。
そこで明治政府は再び蝦夷地を直轄化
開拓使にそれを統括させて現在に至る。
なお、この時最後まで蝦夷地であった地域には
北海道11国86郡のうち下記の令制国が置かれた。
和人地であった 令制国 である。
明治以前までの蝦夷の地はおそらく
有史以来一度も斧を入れたこともない大原始林に
覆われ、 そこに住む人々は鳥獣を狩り、野草を摘み、
川や海の魚を捕って生活していました。
彼らは蝦夷の先住民
(原日本人とも言われている)でしたが、
文字を持ってなかったので
その歴史はよく分かっていません。
明治維新後、国策は一変します。
失業した士族の救済、
ロシアの侵攻に備えた屯田兵の創設、
そして何より、欧米列強に対抗するため
富国強兵の道を 歩み始めた新政府にとって
石炭、木材、硫黄などの
無尽蔵とも思えた天然資源は、
日本近代化の大きな原動力とうつりました。
つまり、北海道開拓のもっとも主要な動機は、
日本近代化のための資源の開発であり、
このことが、北海道開拓の基本的なパターンを
決定しました。
明治維新前後の北海道人口は、
アイヌが2万人前後、和人が10万人前後と
推定されています。
現在では人口562万人余り(平成18年)。
戦後の開拓も効果をあげましたが、
やはり北海道の開拓は明治維新後の約半世紀で
その骨格が出来上がったと見るべきでしょう。
なによりも開拓者の血の滲むような格闘こそが
現在の北海道を築いたといっても
過言ではありません。
・北海道開拓史
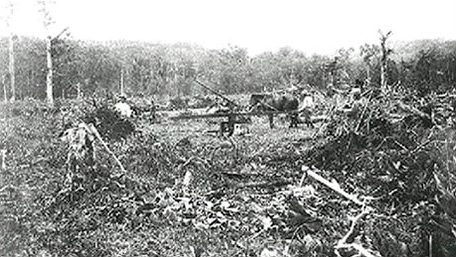
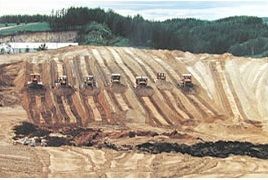

アイヌが2万人前後、和人が10万人前後と
推定されています。
現在では人口562万人余り(平成18年)。
戦後の開拓も効果をあげましたが、
やはり北海道の開拓は明治維新後の約半世紀で
その骨格が出来上がったと見るべきでしょう。
なによりも開拓者の血の滲むような格闘こそが
現在の北海道を築いたといっても
過言ではありません。
・北海道開拓史
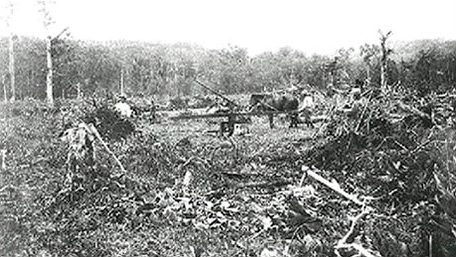
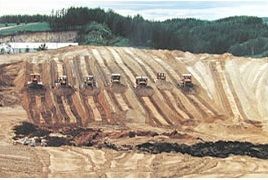

不毛の原野をわずか130年の短期間で
一国にも匹敵する素晴らしい地域に造りあげた ことは
世界的にも例がないとも言われています。
日本が2千年かかつて創りあげてきた農業の歴史を、
わずか百年そこそこで駆け抜けた とも言えます。
圧倒的な自然の営み、
あらゆる辛酸を乗り越えてきた開拓者魂、
そして、農業土木というわが国独自の技術体系。
それらの見事な結実が、生産量日本一の水田とともに
世界に誇るべきこの美しい北海道の田園風景を生んだ
と言えるのではないでしょうか。
☆
このように、明治の屯田兵までは、
米国の西部劇のような狩猟などの生活が
主流であったと思われます。
・米国中西部



ですから、
内地の田畑、山林が台風で被害を受けたような感覚で
広大な開拓地・北海道を見るのは歴史的に正しくなく
開拓史から思い起こしてみるべきだと思います。
・今回の地震による山崩れ

本州の山々が、木材の再生産のために計画的な植林を
続けてきたのに対して、
北海道では軟弱な土壌( 泥炭土、重粘土、火山性土等 )
一国にも匹敵する素晴らしい地域に造りあげた ことは
世界的にも例がないとも言われています。
日本が2千年かかつて創りあげてきた農業の歴史を、
わずか百年そこそこで駆け抜けた とも言えます。
圧倒的な自然の営み、
あらゆる辛酸を乗り越えてきた開拓者魂、
そして、農業土木というわが国独自の技術体系。
それらの見事な結実が、生産量日本一の水田とともに
世界に誇るべきこの美しい北海道の田園風景を生んだ
と言えるのではないでしょうか。
☆
このように、明治の屯田兵までは、
米国の西部劇のような狩猟などの生活が
主流であったと思われます。
・米国中西部



ですから、
内地の田畑、山林が台風で被害を受けたような感覚で
広大な開拓地・北海道を見るのは歴史的に正しくなく
開拓史から思い起こしてみるべきだと思います。
・今回の地震による山崩れ

本州の山々が、木材の再生産のために計画的な植林を
続けてきたのに対して、
北海道では軟弱な土壌( 泥炭土、重粘土、火山性土等 )
育苗したのではないでしょうか。
北海道の大規模農林業を今一度見直して、
大規模農業にあった土地の再構築、
防風林・道路の再構築などを図り、
防風林の整備、住宅地の再整備などを
計画的に行う必要があるのではないでしょうか。
☆
今、内地で行われている台風災害復旧とは
全く異なる大規模農地・防風林開発計画で
災害復旧を図るべきだと思います。
災害復旧の初期から、
計画的な実装を設計するべきでしょう。
☆
呆け老人・素人の言うことではないでしょうが・・・
高橋はるみ北海道知事に頑張ってほしい!
都市計画なども、熊本県で大人足のような場所に
むやみやたらに住宅地を建設するようなことが、
北海道では行われていたようである。
自由と無計画では大きな違いである。
危機管理が全くない都市計画ではいけないのである!
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[思考紀行] カテゴリの最新記事
-
一人当たり可処分所得から故鈴村博士を思… Aug 29, 2023
-
情報の拡散:ウクライナを守るため兵役に… May 27, 2022
-
「人類の造られた歴史」を学んでいない世… May 23, 2022
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









