-
1

555~1963.11.22.
“Stop! in the Name of Love” by The Hollies 1983 (Original: by The Supremes 1965) 2週間ほど先の話になりますが、正確には12月6日、ラジオが通算555回目を迎えます。 2度とない5が三つ並ぶゾロ目の回なので、これにちなんだ特集をと考えていたのですが、特に名案が浮かばず、結局「5=go 」だからと、相変わらずの「駄洒落 (ダジャレ)」頼みの「“go” 特集」をすることにしました。 そこで皆さんには、曲のタイトルに “go” が使われている曲 (“going” や “goes”も可とする) で思いつくオールディーズナンバーをリクエストしていただくことにしました。楽しい番組になることと期待していますので、よろしくお願いします。 オンエアは12月6日なので、リクエストの締め切りは12月4日(木) の午後11時59分です。 リクエスト専用メールアドレス↓です。 anazawageorge@gmail.com 因みに、12月20日は毎年恒例の「クリスマスソング特集 (全曲クリスマス関連曲)」を行いますので、こちらの方のリクエストもよろしくお願いします。 ********** 1963年11月22日はジョン・F・ケネディ大統領が暗殺された日。この時僕は中学生でした。 アメリカからのテレビ中継(=宇宙中継)があるという記念すべき第一声は以下の通りでした。「日米宇宙中継という輝かしい試みの電波に乗せて、悲しいニュースをお伝えしなければならない事を残念に思います。アメリカ合衆国第35代ジョン・F・ケネディ大統領は11月22日、日本時間11月23日午前4時、テキサス州ダラス市において銃弾に撃たれ死亡しました」(Wikipediaより)。 時差があるので、日本時間では23日のことですが、この日のことは鮮明に記憶に残っています。 様々な業績を残しましたが、何より、激しく残っていた人種差別撤廃に向け大きく道筋を付けた大統領として、僕らには実にかっこいいリーダーに見えたものです。 そのケネディが銃弾に倒れたというショックは大きく、さらにその後キング牧師、ロバート・ケネディと続けて銃により暗殺された一連の出来事は、アメリカに多くを期待していた僕らにとって実に悪夢でした。 あれから62年も経って、アメリカでは銃規制など全くする気のない大統領が、すんでのところで銃により暗殺されそうになり、最近ではその大統領熱烈支持者で保守派活動家チャーリー・カークが銃撃され死亡。銃規制など一向に進んでいる様子はありません。 ********** あの極右でタカ派の首相、もし本気で自分が正しいことを言ったと思っていて、あの国会答弁を撤回しようとしないのだとしたら、いや、たぶんそう思っているようなので、今最も危険な世界のリーダー何人衆かの仲間入りですね。思ったとおりですが。 けど、高みの見物などしていられません。このまま改憲まで突っ走られたら、僕らの子や孫たちの世代が普通に戦争に巻き込まれてしまう。いや、その前に沖縄は最初の戦場になる。 昨日も、台湾有事に備えて宮古空港で先島島民を県外に避難させる実地確認=訓練をしれっと行った。飛行機で12万人を6日で九州と山口に避難させるそうです。ずいぶんと悠長なことを言ってますが、戦争になったらそんな時間ありませんよ。昔と違うんだから。戦艦なんて来ませんから。 とにかく戦争にならないように、今からみんなで声を上げるしかないですね。 「愛の名において、止めよ!」← “Stop! in the Name of Love” を直訳してみた。というところで、ホリーズ1983年のカヴァーを聴いてみましょうか。当時のクリップ、音悪いですがYouTubeにあがってました。 “Stop! in the Name of Love” by The Hollies 1983 ********** 11月15日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. Zing! Went the Strings of My Heart 2. Don’t Make Me Over 3. I Couldn’tn Live without Your Love (以上, Petula Clark) 4. The Way We Were (Barbra Streisand) 5. Peace of Mind (Loggins & Messina) 6. Stop! in the Name of Love (The Supremes) 7. Stop! in the Name of Love (The Hollies) 8. Petite Fleur 9. Hello Dolly 10. Downtown (以上, Petula Clark) リクエスト曲は、 4.酋長Kobaさん。ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。1.~3.と8.~10.はこの日がペトゥラ・クラークの誕生日(11/3)で。1.は彼女が歌う「今月の歌」。5.は先週時間が足りず「同名異曲特集」でかけられなかった分。6.&7.は「愛の名において」戦争につながるような発言は「やめて!」欲しいので。 以上。次回もよろしくお願いします。
2025.11.21
閲覧総数 198
-
2

西銘さんの思い出~近頃心がざわつくぞ
“Peace of Mind” by Gene Vincent1958 与那原「コスモス」のオーナー西銘さんが亡くなってからもう三ヶ月ほどになります。 以前、西銘さんの友人の屋良さんと三人でやんばるまでドライブしたことがあって、一緒に出かけたのは後にも先にもこの時だけだったので大変思い出に残っています。 時期がちょうど今頃で、暑くも寒くもない天気の良い日でした。途中カフェに寄ってコーヒーを飲んでから、食堂で昼食をとり、午後は屋我地島でゆっくりのんびり過ごした一日でした。 僕が沖縄に来てしばらくしてから「コスモス」を知り、西銘さんにお会いしてからすぐに「ジョージさん、今度やんばるに行こうね」と何度も言ってくれたんですが、色々都合がつかず、結局行けたのがこの日2019年の11月10日のことになってしまいました。 この時の思い出がお互いとても深く残っていたので、その後も「また行こうね」が二人の口癖になっていましたが、結局はコロナ禍で先送りになり、西銘さんは体調が少しずつ悪くなって、とうとう行けずじまいになってしまったのが心残りです。 できれば、近いうちに同じコースを追悼ドライブしたいと思っています。 ↓途中の食堂に上がる階段にいたミケさん。猫好きだった西銘さんと長いこと一緒に遊びました。 ********** まさかと思っているうちに、絶対に首相になってほしくなかった人物が首相になって、しかも絶対にやってほしくないことを次から次にやろうとしています。 極右であり鷹派であることを隠さず、能ある鷹ならば隠すはずの爪を隠しもせず、「財源が財源が」と言いながら防衛費をすぐに2パーセントにすると公言し、普通なら慎重でなければならない中国との関係を自ら進んで悪化させ、まさに戦争への道をまっしぐら。 こんな恐ろしい人物の発言が毎日いやでも耳に入ってくるのが嫌でたまりません。 心がざわつきます。心の平安が欲しいです。 というようなこともあって、ラジオでは「心の平安」を歌った歌 “Peace of Mind” の「同名異曲」特集をやりました。全部で5曲準備しましたが、時間の都合で4曲お届けして、残りの1曲は次週に回しました。取り上げた曲は下記に記してありますので参照ください。もちろん全部違う曲ですよ。 ジーン・ヴィンセントのやつを聴いてみましょうか。これを聴いて少しは心が落ち着くといいのですが。 “Peace of Mind” by Gene Vincent1958 ********** 11月8日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. Happy Birthday Sweet Sixteen (Neil Sedaka) 2. Happy Birthday (The Wedding Present) 3. Zing! Went the Strings of My Heart (The Coasters) 4. People (Barbra Streisand) 5. You’re So Vain (Carly Simon) 6. Peace of Mind (Nat King Cole) 7. Peace of Mind (Bee Gees) 8. Peace of Mind (Paula Parfitt) 9. Peace of Mind (Gene Vincent) リクエスト曲は、 4.酋長Kobaさん。5.座波ソーメンさん。以上、ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。1.&2.は私の誕生日(11/3)が過ぎて最初の土曜日だったので。2.はジョンピール・ショーのスタジオライブ。3.が「今月の歌」オリジナルのコースターズで。6.~9.は「同名異曲」特集。最近ざわつく心を鎮めたいので “Peace of Mind” を。 以上。次回もよろしくお願いします。
2025.11.14
閲覧総数 201
-
3

写真追加:キンクス『ウォータールー・サンセット』
“Waterloo Sunset” by The Kinks 1967 今回もロンドンに住んでいた時の話を...。 その日僕は本当にきれいな夕日を見た。場所はプリムローズ・ヒル。緑の芝が美しいちょっとした小高い丘の公園で、沈むまでその光景に見とれていたのを覚えている。前景には、犬を散歩させている老人や帰宅途中の近くの住人が、時折シルエットで通り過ぎて、粋な偶然の演出をする。プリムローズ・ヒルはリージェンツ・パークの北側とアルバート・ロードを隔てて接している。つまり London Zoo (動物園)からは通りを渡るだけだ。こんな、いかにもロンドンらしい所で見た夕日だから、余計印象に残っているのだろう。 プリムローズ・ヒルがいかにもロンドンらしいと書いたが、「ロンドンらしい」にも当然いろいろある。キンクスの『ウォータールー・サンセット』の舞台になった Waterloo Station (ウォータールー駅) から、すぐ近くのテムズ川にかかる Waterloo Bridge (橋) にかけても、ロイヤル・フェスティバル・ホールやナショナル・フィルム・シアターなどのあるサウスバンクと呼ばれる一帯で、さすがにロンドンにいる実感が味わえる界隈だ。駅舎の入り口は昔のまま残っていて、実にかっこいい。 ロンドンを知らない人でも、あの有名なビッグ・ベンから見て、テムズ川の対岸わずか左手のところ、ちょうど今評判の大観覧車ロンドン・アイの向こう側といえば、だいたいの光景が想像できよう。ビッグ・ベンから歩いたとしても15分。それ以上はかからない。 (↑15年前に僕が撮ったウォータールー駅) この曲に歌われた「♪ 見つめているかぎり 何も怖くない 天国にいる気分」にさせてくれる夕日は、残念ながら僕には見る機会がなかったが、駅を出て少し歩けば、なるほどここから夕日を見たらきれいかもしれないと思わせる橋だ。よく聞くのは、ウォータールー駅からの夕日が美しく、キンクスは駅から見た夕日を歌ったのだということ...。でも僕はこの歌の夕日は橋からの夕日なんじゃないかと勝手に推測してみる。その根拠は歌詞の一番最後のところにある。「♪ たくさんの人が ハエのように群がる 地下鉄ウォータールー駅」の次ね。♪ でもテリーとジュリーは 川を渡る そこはホッとするところ 二人には友達もいらない ウォータールーの夕日を 見つめている限り 天国にいる気分 人々がひしめいている駅から外に出て、橋を渡りながら眺める夕日だからこういう歌になったんだろうと、僕は思うのだ。この若い男女二人は夕日が沈んだら橋を渡って、コベント・ガーデン方面へ向かうのだろう。金曜の夜だしね。 ただ、昔のままの駅舎の入口は階段になっていて、よく若者たちが腰を下ろしているから、ここからの夕日もいいかもしれないが、方角がどうだったか覚えていない。 改めて感じるのは、この歌は世界に数ある「ご当地ソング」を代表する1曲じゃないだろうかということだ。レイ・デイビスは詩人としても一流だね。冒頭からこれだものね。 ♪ Dirty old river 古く汚い川よ Must you keep rolling とうとうと流れ Flowing into the night 夜に注げ People so busy 忙しい人々を見て Make me feel dizzy 僕はめまいを感じる Taxi lights shine so bright タクシーのライトが まぶしく光る キンクスについては、僕はあまり深く知らないということが、今回よくわかった。でも、実にイギリス的なこのバンドについては、もっと聞かなくてはと思ったのだ。 そういえば、レイ・デイビスとブラー(Blur)のデーモン君が、仲良くデュオでこの歌を歌っているのを衛星放送(スカパー)のミュージックエアで見たが、ビデオに取り損ねた。惜しいことをした。 (文中訳詞は穴沢)
2003.02.24
閲覧総数 220
-
4
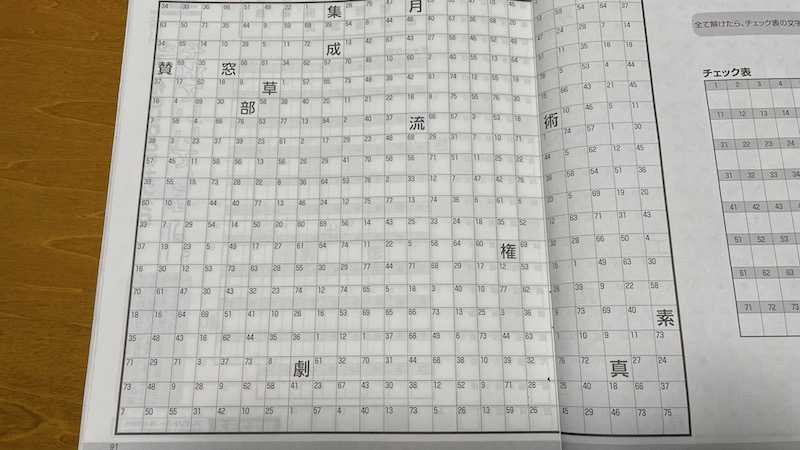
今年も12/8がやって来た~追悼:シェイン・マガウアン
“Fairytale of New York” by The Pogues, featuring: Kirsty MacColl 1987 「番組休止のお知らせ」 誠に申し訳ありませんが、明日、12/9の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」は残念ながら局の都合でお休みとなります。 来週は通常通りに番組をお届けいたしますので、よろしくお願いします。 ********** ポーグスのシェーンが死んでしまった。11月30日。享年65。 以前、1987年のクリスマスシーズンから翌年にかけて流行ったポーグスの “Fairytale of New York” のことについて書いたのがちょうど20年前の12月7日のことだった。 まずは、2003年12月7日の日記「ポーグスのクリスマスソング」を読んでください。 この日記↑で取り上げた “Fairytale of New York” は、プリテンダーズの “2000miles” と並んで80年代クリスマスソングの双璧と言っても過言ではないと、いまでも思っています。 あれこれ言うのもなんですから、まずは聴いてみましょうね。 “Fairytale of New York” by The Pogues, featuring: Kirsty MacColl 1987 ああ、いつ聴いてもいい歌だ。 あの遠い日のロンドンがこのシェーンの声とともにいつでも蘇ってくる。 シェーンが死んでしまうのは時間の問題だったとしても、この歌はいつまでも生きていて、彼はあの声で、クリスティ・マッコールと一緒に、僕をニューヨークではなくロンドンに連れて行ってくれるのだ。 あの年にロンドンにいてこの曲と出会ったのは偶然だったと言えないような錯覚に陥ってしまう。 シェーンくん、どうか安らかに眠ってください。本当にお疲れ様でした。 さて、今年も12月8日がやって来ました。 ウクライナでの戦争はいつ終わるかわからないような状態のまま年を越してしまおうとしているところに、今度はイスラエルがガザで暴れまわっているようで、どうにも仕様がないですわ。 21世紀に入って20年以上も経つのに、こんな状態をジョンもさぞかし天国から呆れて見ていることでしょう。 我が国も、相変わらず核兵器禁止条約を批准する気すら無いようで、二言目には決まって「抑止力」「核の傘の下」といったお題目のような言い回しを使って、ひたすら軍備を増強する道を歩んでいて、困ったもんです。 ********** 近頃またこれ↓に凝ってます。 漢字ナンクロの難しいやつ。 ********** 12月2日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. White Christmas (Otis Redding) 2. 涙くんさよなら (ジョニー・ティロットソン) 3. 風 (はしだのりひことシューベルツ) 4. At Seventeen (Janis Ian) 5. Walk Right in (The Rooftop Singers) 6. Words (The Monkees) 7. Words (Bee Gees) 8. Words (F.R.David) 9. Winter Wonderland (Paul Anka) リクエスト曲は、5.座波ソーメンさん。6.酋長Kobaさん。以上、ありがとうございました。 上記以外穴沢選曲です。1.は、毎年恒例の12月最初の曲。オーティスの『ホワイトクリスマス』です。2.はこの日が作曲家浜口庫之助の命日(1990.12.2.没,享年73)で。3.はこの日がはしだのりひこの命日(2017.12.2.没,享年72)で。6.~8.は以前にもやったことはあるのですが、このところやっていなかった「同名異曲」特集で、今回は “Words”。なお、信州そばさんからも「同名異曲特集」のご提案はいただいておりました。9.は「今月の歌」『ウィンター・ワンダーランド』をポール・アンカで。 以上。次回もよろしくお願いします。なお、12/9は局の都合でお休みです。
2023.12.08
閲覧総数 152
-
5

na Relo (ナレロ) の “Because” を聴きました
“Because” by Dave Clark Five 1964 ネット友達の nonoyamasadao さん (「ゆっくりとまったりと」の著者、野々山貞夫氏) のブログで na Relo (ナレロ) というグループを随分前に紹介してもらったんですが、いつかこちらに感想を書こうと思いつつ、今日になってしまいました。 このグループは YouTube に「na Relo 洋楽チャンネル(na Relo’s English Song Cover Channel)」と「na Relo 邦楽チャンネル(na Relo’s Japanese Song Cover Channel)」を持っていて、実に見事なカヴァー曲の数々をアップしています。 YouTube ではかなり評判のようなので、すでにご存知の方も多いでしょうが、初めての皆さんにはとりあえず見ていただくのがよろしいでしょう。 “Because” Covered by na Relo 2024 “Mamatsu-no Dekigoto” Covered by na Relo 2023 na Relo(ナレロ) としては4年前から活動しているようです。 基本的にこのユニットはフロントに女性ヴォーカル2名、バックにギターとドラムの男性2名の4人組オールディーズバンドで和洋どちらも分け隔てなくやるのがそのスタイルです。 ベースは普段はいないので、ライブではヘルプが入り、キーボード、サイドギターも稀に入るようです。4人でやるアコースティックライブという形もあるようです。YouTube 配信ではベースパートはたぶんギターさんがあとから重ねているのだと思います。コーラスやギターもさらに自分たちで重ねているのでしょう。 そして、何よりも、歌と演奏のレベルが高い。 さらにはどの曲もオリジナルをしっかり踏襲していて、非常に良い。 今年の5月15日に「4周年記念ライブ配信」をしていて、これを見ればどういう4人かは良くわかると思いますよ。ただし、1時間24分37秒の中で、3曲しかやっていなくて残念ですが (笑)。でもその3曲が “Pineapple Princess” “Eight Days a Week” “Be My Baby” ですからね、みなさん。 余計なことかもしれませんが、これは僕には結構大事なことなので書かせてもらいますが、この na Relo の4人の服装などについてです。 制服みたいに同じスーツを着て同じ髪型 (リーゼント) でビシッと決めたつもりのオールディーズバンドが時々ありますが、あれは好きになれない。その方が気持ちが入りやすいかもしれませんが、なんだかちょっと違うんだよなって、冷めた気分になってしまう。 その点、na Relo は普通に自分の趣味の服装髪型で好感が持てます。 現在僕はバンド活動休止状態ですが、次にやるバンドは na Relo みたいなのが良いと勝手に妄想しています。昔やってたスリージョージズみたいなやつね。 ↑家族が楽しんでいる庭の薔薇コレクションの一つ。地面にへばりついているようでなかなかいいです。 ********** 9月28日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. 悲しき片想い (ヘレン・シャピロ) 2. Ecoute Le Temps 3. La Madrague (以上, ブリジット・バルドー) 4. September in the Rain (The Platters) 5. Kiss Me Quick (Elvis Presley) 6. I Neve Loved a Man (The Way I Love You) (Aretha Franklin) 7. Smoke Gets in Your Eyes (J.D. Souther) 8. Faithless Love (Linda Ronstadt & J.D. Souther) 9. You’re Only Lonely (J.D. Souther) 10. Little Miss Lonely 11. Some Time Yesterday (以上, Helen Shapiro) リクエスト曲は、5.酋長Kobaさん。6.座波ソーメンさん。7.信州そばさん。以上、ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。1.と10.&11.は、この日がヘレン・シャピロの誕生日(1946.9.28生.78歳)で。2.&3.は、この日がブリジット・バルドーの誕生日(1934.9.28生.90歳)で。4.は今月の歌『セプテンバー・イン・ザ・レイン』をプラターズで。7.~9.は先日(9/17)亡くなったJ.D. Souther を偲んで。 以上、ありがとうございました。次回もよろしく。
2024.10.04
閲覧総数 405
-
6

ジョン・レイトン『霧の中のジョニー』1961
“Johnny Remember Me” by John Leyton 1961 (日本語版:by 克美しげる 1962) 60年代初期の、リバプールサウンド上陸以前、日本でも流行った英国ポップスといえば、女性ではヘレン・シャピロとアルマ・コーガン、男性シンガーではクリフ・リチャードが有名だろう。あとは、このジョン・レイトンの『霧の中のジョニー』と『霧の中のロンリー・シティ(Lonely City)』が流行った。本国イギリスでも流行ったが、アメリカでは全く流行っていない。このあたりは、クリフ・リチャードのケースとよく似ている。 ジョン・レイトンは、むしろ俳優としての方が知られているかもしれないが、彼の出ている映画で僕が知っているのは、『大脱走』ぐらいだ。やはり僕らには、『霧の...』シリーズでおなじみの歌手だった。 『霧の中のジョニー』『霧の中のロンリー・シティ』ともに、いい曲だと思う。が、個人的には、同じマイナー(短調)の曲でも、僕は『霧の中のロンリー・シティ』の方が好きだ。サビでメジャー(長調)に転調して、「♪ ウォー、ウォ ウォウォ、ウォ ウォ ウォー、ウォ ウォ ウォ~」で、元に戻るところなんか、ポップスの王道を行く鳥肌モノだ。 それに比べれば、この『霧の中のジョニー』は終始マイナー(短調)を貫き、比較的単調な曲に思えるが、こちらの方が流行ったのは歴史的事実なのでどうにも仕方がない。ただ冒頭の詞を読んでみると、このとてもイギリス的な風景がこの曲の UK No 1 ヒットに一役買ったのだろうと、想像できる。♪ When the mist’s arising and the rain is falling And the wind is blowing cold across the moor I hear the voice of my darling The girl I loved and lost a year ago...... 「霧が立ちこめ 雨が降り 風が冷たく荒れ野を吹き抜けてゆくとき 好きだったけれど 1年前に別れた 彼女の声が聞こえてくる...」(穴沢訳) このあと、サビにさしかかるところで、女性の高い声で "♪ Johnny,remember me..." というフレーズが入る。克美しげるの日本語バージョンでも同様で、この曲のいちばん重要な箇所ともいえる。 ところが、この部分、日英で微妙に違うのだ。 英語の方は、"remember" の "mem" と "ber" のところが、半音下がって me につながるのに対して、日本語の方は、「メン」から「バー」に全音使って下がっている。この違いは曲調に大きな差を生んでいるが、皆さんはどう思いますか。 え?そもそも、この歌自体聴いたこともないですって?そうですか。それでは、判断は難しいですね。尤も、今僕の手元には、日本語版がないので、本当は確かめようもなく、曖昧な記憶で書いているだけので、突っ込まれたらそれまでです。 さて、いろいろややこしくなる前に、ちょっと話題を変えよう。 この当時、ジョン・レイトンの LP を友人が持っていて、よく聴かせてもらったので覚えているのだけれど、その中に "Johnny My Johnny" という曲があった。サビを女性が歌っているとても印象的なロッカ・バラード風の名曲だ。しかし残念なことに、この LP も今は友人の手元にはなく、その後いろいろ探してもなかなか見つからない。ああ、もう1度聴きたいなあ。 東京にでも出た折りに、大きなレコード屋で見つけたらあるような気もするけれど、東京に行く機会がほとんどなくなってしまって、どうにもならない。どなたか情報お持ちでしたら、よろしく。 克美しげるは『霧の中のジョニー』がデビュー曲だったと思う。彼はジョン・レイトンのカヴァー曲のほか、『片目のジャック』、伊藤アイ子やザ・ピーナッツと競作の『さいはての慕情』『北京の55日』などをヒットさせたあと、演歌の方に転向したところまでは覚えている。その後、犯罪を犯してしまい、服役して出所したあと、また事件を起こし...というような一生を送った人だった。 演歌の方が似合いそうな人だったけれど、元々いわゆるマイナー(短調)の曲だったせいか、『霧の中のジョニー』の日本語版は彼の独壇場だった。 ******************** さあて、皆さん。いよいよ今日の宿題ですよ。 これは老若男女関係なく、これを読んだすべての皆さんに答えていただきたい。お願いします。 1.「ジョニー(または"Johnny")」といえば、どんな曲を思い浮かべますか? 2.「ジョニー(または"Johnny")」といえば、どの歌手を連想しますか? 星の数ほどあるジョニーの中から、何を(誰を)選ぶか楽しみですぞ~~。
2003.05.14
閲覧総数 1354
-
7

プリテンダーズ『2000 miles』
"2000 miles" by the Pretenders (1983) あれこれ忙しさにかまけて、楽天に集中する時間がないままクリスマスを迎えてしまいそうです。 だれか、時間をくださ~い。 9500万人のクイズファンのみなさま、大変お待たせいたしました。 本日のタイトルは、そのまま先日のクイズの答えです。 つまり、『500マイル』を採り上げたときの日記のタイトルを、マイルをキロに換算して「804.65km」としたのを思い出して、単純に4倍したというだけのことでございました。 楽天仲間の幻泉館主人さん言うところの「姉御率いる偽善者たち」プリテンダーズは、クリッシー・ハインドの少々演技過剰の歌い方のせいで、僕はあまり魅力を感じていなかったんですが、1st は持っていました。"Stop Your Sobbing" が入っていたしね。 でも、レコードをまとめて処分したときに、これも売ってしまったんです。テープに録ったからいいかなって。 その後、メンバー二人(4人のうち二人だから、すごい確率)を亡くして、しばらく活動を停止していたところに、突然のクリスマスソング。まさに、このタイミングしかないなあと、感心せざるを得なかった。 この "2000 miles" は忘れた頃にやってきたクリスマスの贈り物でした。 しかもこれが、心に届く響きをたずさえた珠玉の名編だったから、当時のニューウェーブ少女やパンク少年、はたまたロックおばさんやオールディーズおじさん?まで、思わず涙したものです。 いかにもクリスマスにふさわしいイントロの後、いきなり「♪ He’s gone 2000 miles(あの人は2千マイルの彼方へ行ってしまった)」と始まる。次が「♪ It’s very far...(とても遠い...)」って。そりゃそうだ。500マイルの4倍だもの。 途中もう一度「2千マイル」が出てくるところの歌詞。「♪ 2000 miles is very far through the snow (2千マイルは雪を越え遙か彼方) I’ll think of you wherever you go (たとえあなたがどこへ行っても私の頭からは離れない)」 全体に、クリスマス・ソングの常套句をちりばめ、2千マイルの件(くだり)が引き立つ、とても素敵な歌詞です。クリッシー姉さんの才能見させていただきました、というところですね。 そんなわけで、80年代前半のベスト・クリスマスソングは、クリッシー・ハインド入魂の "2000 miles" で決定ですね。異論のあるのはまったく承知の上ですが、僕にはどうしても83年のこの曲が一番に思えます。 後半には、先日来話題になっている 87年のポーグス with カースティ・マッコールによる "Fairytale of New York" がある。あ、こちらも当然異論はあると思いますけど......。 というわけで、明日はいよいよクリスマスイブ。予告しておいたあの歌の登場ですよ~。 (文中訳:穴沢) *************************** きょう、楽天仲間の isemari さんが、すばらしい歌詞解説の付いた「正解レス」を書いてくださいました。みなさん、読んでくださいね。
2003.12.23
閲覧総数 149
-
8

「Q.いしかわさん」逝く
“When I Grow Too Old to Dream (夢見る頃を過ぎても)” by Q.いしかわカルテット (From the Album: “In My Life” 2007 Original: 1934) テナーサックス吹きの Q.いしかわさんが、今月4日に亡くなったとのこと。SNS仲間に教えてもらいました。1931年の10月生まれなので、もうすぐ89歳になるところでした。 Q.さんには2005年に初めてライブを聴かせてもらってから、6年間ほど毎年のように聴きに行っていました。 初めて聴いたときのことは↓に書きましたので、・・・。 2005年12月4日の日記 2005年12月18日の日記 2005年12月20日の日記 戦後の日本のジャズ界のもう一つの流れの中を飄々と歩んで、音楽の楽しさを多くの人たちに伝えた功績は大きいと思います。 いつでも若いミュージシャンに慕われて、実力のあるプレイヤーを従え、とは言っても、決して親分肌などでなく優しい眼差しで一人一人に目を向けプレイする姿は、まさにカッコよかったです。 沖縄に越してからは一度もライブに行けなかったのが心残りです。 時折歌うその独特の節回しも、今となっては CD で聴くしかないと思うと、やはり残念です。 天国からその優しさで僕らを見ていてもらいたいです。 ご冥福をお祈りします。 YouTube に↓ライブ音源アップしてくださった方がいました。 “夢見る頃を過ぎても” by Q.いしかわカルテット 2006.12.9. at !st Call Club, Karuizawa ********** 『夢みる想い』ジリオラ・チンクエッティと『ほほにかかる涙』ボビー・ソロ 今年、2020年とカレンダーが同じだった1964年。東京オリンピックのあった年の秋は、ビートルズやベンチャーズ、サーフィン・ホットロッド・ミュージックなんかが流行っているところに、カンツォーネ(というよりもイタリアンポップスというべきか)とフレンチポップスの新しい風が吹いて、僕らのようなポピュラー音楽かぶれの少年少女たちは当然これにも飛びついた。 イタリアからは、ご存知ジリオラ・チンクエッティとボビー・ソロが、少し遅れてフランスからはシルビー・バルタンが、親しみやすく軽快なメロディーと魅力的な言語と共に僕らの前に現れた。 この年の1月の終わりに開かれたサンレモ音楽祭の優勝曲『夢みる想い』と入賞曲の『ほほにかかる涙』は、約8ヶ月遅れてヒットした。サンレモの後しばらくしてレコードは出ていたと思うし、ラジオでも聴いていた記憶はあるけれど、なぜか流行ったのは秋だった。 それまでの絶叫型のカンツォーネとは全然違う新鮮さが、ヒットの理由だったと思われるが、「♪ ノノレタ~ ノノレタ~ ペラマルティー ノノレタ~・・・」とか「♪ ダウナラックリマッスルビ~ゾ~・・・」みたいに歌えてしまうところも良かったのかもしれない。 特に「♪ ノノレタ~」の方は、ユーロビジョン・コンテストでも優勝して世界的なヒットとなったが、この歌い出しは、どの言語圏の若者でも間違いなく歌えただろう。 “Non ho l’età” by Gigliola Cinquetti 1964 “Una lacrima sul viso” by Bobby Solo 1964 ********** 9月19日の穴沢ジョージの “Good Old Music” のオンエア曲です。1. 花のサンフランシスコ (スコット・マッケンジー) 2. The White Cliffs of Dover (ライチャッス・ブラザース) 3. Beautiful Dreams (Twiggy) 4. テネシー・ワルツ (David Bromberg) 5. The Wind Cries Mary (The Jimi Hendrix Experience) 6. イザベル (シャルル・アズナブール) 7. Let It Be Me (トム・ジョーンズ) 8. Oh, Pretty Woman (ロイ・オービソン) 9. L’homme en noir (シルビー・バルタン) 10. ほほにかかる涙 (ボビー・ソロ) 11. 夢見る想い (ジリオラ・チンクエッティ) リクエスト曲は、5.座波ソーメンさん。6.酋長kobaさん。7.なんくるタイムの洋子さん。ありがとうございました。 上記以外は、穴沢選曲です。 1.は、アメリカ西海岸の森林火災お見舞い。2.~4.は、この日が誕生日の三人。2.ライチャス・ブラザースの Bill Medley 氏 (1940.9.19生)。3.Twiggy さん (1949.9.11生)。4.David Bromberg 氏 (1945.9.19生)。8.&9.は、本日の聴き比べ。8.が1964年のこの日、Cash Box の #2 になり翌週から #1 に上り詰めたのです。9.は、これのフランス語によるカヴァー。先月もかけましたが。10.&11.は、1964年9月17日放送の「9500万人のポピュラーリクエスト」で #2 #3 になった曲。翌週はそれぞれ #1 #2 になりました。 それでは、また。
2020.09.24
閲覧総数 2192
-
9

60年代のイギリスを代表する女性歌手(1)
ヘレン・シャピロは『子供じゃないの』と『悲しき片想い』の2曲があまりにも有名ですよね。これが流行ったとき、まだ子供だった僕らにはヘレン・シャピロより、圧倒的に弘田三枝子だった。漣健児の訳詞も実にメロディーにピッタリで、よく大声で歌ったものだった。続きはまた明日書きますね。
2002.09.16
閲覧総数 128
-
10

『ブルージーンと皮ジャンパー』アダモ
“En blue jeans et blouson d'cuir”by Adamo 19631.「大いなる誤解」 初めて『ブルージーンと皮ジャンパー』を聴いたとき、僕は絶対女の人が歌っていると思った。もちろん、すぐに男だと知ったわけだが、なかなか納得がゆかなかった。どんな声帯をしているか、ちょっと見てみたい気がしたものだ。 ただ高い声というだけなら、ほかにもたくさん高音の歌い手はいるし、女の人だとは思わなかっただろう。けど、なぜかアダモには「おんな」の声を感じてしまった。ちなみに当時まだ僕は中学生だった。 そしてこの約1年後、ゲール・ガーネットの『太陽に歌って』が登場したときには、全く逆に彼女を「おとこ」と思ってしまった。 アダモがとてもハスキーな声だったのに対し、ゲール・ガーネットはいわゆるドスの利いた声というやつ。高音の方になると少しかすれ気味だけれど、落ち着きのある歌いっぷりと相まって、独自の味を感じさせていた。今手元に『太陽に歌って』の音源が見つからないけれど、覚えている限り、こんな風だったと思う。 で、アダモとゲール・ガーネットの声について正直に言えば、どちらも実に魅力的なのだ。 以前に、ずいぶんここでも話題になったヴォーカリストの「声」だが、美声もいいけれど、やはり個性的な声というのには、つい惹かれてしまうのだ。 ......と、ここまで書いてから、はたと思い出した。ゲール・ガーネットの『太陽に歌って』が、確か、先日義姉にもらった 60年代のヒット曲を集めた CD に入っていたことを。滅多にこのたぐいの CD には入っていないので印象に残っていた(じゃあどうして忘れてた...セルフつっこみ)。 そして今その CD を見つけてきたのだ。久しぶりに聴く歌だが、ホントに素晴らしい。で、やっぱり男声(おとこごえ)...。いつかこの歌のことも書こう。2.「皮ジャン着て粋がって」 『ブルージーンと皮ジャンパー』というタイトルから、「おれはブルージーンと皮ジャンを着て街を歩いているぜ 大人たちがなんと言おうと そんなことはおかまいなしさ やりたいようにやるのさ」というような反抗する若者の姿を、ついイメージしてしまうかもしれない。当時の僕がそう思ってしまったように。 何しろあのイントロの口笛なんて、すれたブルージーンをはいた若者が、セーヌ左岸の裏路地を皮ジャンの襟を立てて歩くときに吹いたら最高じゃないか。......と、勝手に思っちゃったりしたわけ。 ところが当時聴いていたラジオで、「この歌は結構哲学的な内容だ」という意味のことを、誰かが言っていたのだ。 それで、フランス語......、結構大変で、ほとんど「わかる」という域に達していないが、この歌の内容を探ってみたら、「♪ ブルージーンと皮ジャンで 君は仲間に会いに行く もし着ていかなかったら 明日何て言われるかわからないから...」という冒頭から、反抗的な若者を客観的に眺めているのがわかる。 2番は「♪ ブルージーンと皮ジャンで 君は自分が自由だと思い込んでいる 誰も異議を唱えないと それが君を傷つける」って、醒めた目で反抗する若者を批判するのだ。 このあとも、ちょっとお説教めいた内容が続き、サビの終わりでは「♪ ...ごろつきを気取るために生まれてきたんじゃないだろ」と締めくくり、エンディングもこのサビを繰り返す。 ああ、それにしてもフランス語...、久しぶりに読んで、疲れた。3.「皮ジャン初体験」 この歌がはやった頃も、それから何年も、僕は「ブルージーンと皮ジャンパー」というスタイルにはあこがれたものだ。今どき、ブルージーンと皮ジャンパーが、反抗する若者の象徴だなんて言ったら笑われそうだが、アダモがこの歌を歌った頃は、まさにその通りだった。その点においては、確かに時代は変わったのだ。 我が国で、この格好が一般市民の間に定着したのは、70年代も後半になってからだったと思う。理由は単純だ。輸入革製品が安く出回り始めたからだ。 それまでは、革の衣類は高級品で、とても庶民がたやすく手に入れられるものではなかった。友人のイタリア製の皮ジャンはとてもうらやましかったのだ。 70年代も終わる頃、念願の皮ジャンが手に入った。 渋谷の百軒店にあった中古衣料品屋で、3800円だった。たぶんバイク乗りが着た古着で、表面はだいぶすれていて、固い革だったけれど、うれしくて、着て帰った。 バイクに乗り出したこともあって、文字通り、これを皮切りに、皮ジャン・革パンツや革のコートを何着か買うことになる。 この中で一番目立つのが、ハインゲーリック社の真っ赤なライダージャケットだ。ライダージャケットといっても、クリッシー・ハインドがレコードジャケットで着ているようなオーソドックスなスタイルではなくて、両肩のところが白のシャーリングになっていて、かなりおしゃれなものだ。ただ、近頃はバイクに乗る機会がほとんどなく、出番がないのでちょっとかわいそう。久しぶりに着てあげよう。......いつ?(←セルフつっこみ その2) でも、一番思い出に残っているのは、やっぱり初めて古着で買ったあの皮ジャンだ。残念なことにもう手元にはない。表面はどんなに傷んでも、皮ジャンの場合あまり気にならないが、何しろ裏地がかなりボロかったので、最後はどうにもならなかった。4.「皮ジャンは寒い日に着る」 とても暖かい日が続いたと思ったら、一変して昨日は北風がぴゅーぴゅー吹いて、今朝は氷点下5度。三寒四温とはよく言ったものだ。つまり、今日なら皮ジャンの話題が違和感なく書けて、ああ良かった。...、というお話。 ...以上は一昨日書いたもので、昨日今日と暖かく、朝の犬の散歩がずいぶん楽だった。 タウンユースの皮ジャンは、確かに冬のものだが、あまりに寒い日には役に立たない。 東京方面で暮らしていたときには、厚着をした上に大きめの皮ジャンを羽織って、マフラーでも巻けば、十分暖かかったが、信州の冬はこの程度では乗り切れない。東京にいたときに買った、ちょっと長めのフード付きの革コートがずいぶん役に立ったが、ジッパーが壊れてしまった。今はもっぱら、ダウンコートが活躍している。何と言っても軽いし、暖かくて、皮ジャンや革コートより、はるかに実用的だ。 それでも皮ジャンは時々着たくなる。 これからの季節、寒すぎる日はともかく、皮ジャン着るには結構いいかもしれない。 え?ブルージーンの話題はどうしたかって? それは、次回のお楽しみ。5.「謎」 ところで「皮ジャンパー」は、なぜ「革ジャンパー」と表記しないんでしょう。皮革製品には普通、「革鞄」とか「革靴」「革のベルト」のように、「革」を使うと思うんですが、......。
2004.02.26
閲覧総数 1337
-
11

ナンシー・シナトラ『いちごの片想い』
“Tonight You Belong to Me”by Nancy Sinatra 1962 & Patience and Prudence 1956 日本語版:中尾ミエ/ベニ・シスターズほか 1963 Original by Gene Austin 1927「え~?『レモン...』の次は『いちご...』?ホントかよー」と思ったあなた。……おっしゃるとおりです。本当なんです。まだ中学生のわたしには何の違和感もなく、ああ『レモン...』の次は『いちご...』なんだなあと...。当時は素直なモンでした。 日本では、『レモンのキッス』のあと、間髪を入れずに『いちごの片想い』を出してきたんですよ。う~ん、改めて、商売上手だったんだなあ。 でも、この時のナンシー・シナトラも実に良かったです。まさかこれも本国では売れなかったなんて、全く知らずに人生送ってきましたから、スキ(隙)だらけの人生でおます。ほんまに。 日本語翻訳版は『レモンのキッス』ほどの大ヒットではなかったように記憶していますが、やはりそこそこ流行って、とくに中尾ミエのバージョンをよく覚えています。 ♪ ネエ~ネエあたしはここ 誰か早くぅ見つけてよ 甘い~いちごぉー なの... ここまで読んで、ああなるほどね、『レモンのキッス』に続き、『いちごの片想い』でも、みナみカズみは本領を発揮しているなあ…と思ったあなた!Too sweet. だぜ。甘すぎるのよ。 この訳詞はね、何を隠そう、あのミュージックライフの編集長をしていた星加ルミ子さんなのです! あ、ビックリして、シャックリが出てしまいましたか。 ところが、でございます。これはベニ・シスターズでも流行ったんですが、こちらはみナみカズみさんの訳詞なのですよ。 ♪ ある~かぁわぁぁぁいい ちぃいぃさないちぃごが 恋を~知りました... 冷静に読んでもらっても、これは星加ルミ子の勝ちですよね。特に『レモンのキッス』の続編としては、圧倒的に中尾ミエの歌ったバージョンが、すんなりと受け入れられたのは言うまでもありません。あ、誤解のないように。すんなりと受け入れたのはあくまで「僕の中では」ということですから。当然異論もあろうかとは思います。 さて、原題は "Tonight You Belong to Me" ですから、勝手に邦題すると「今夜だけはあなたはわたしのものよ」とか、そういった感じです。 内容は、新しい恋人の元に行ってしまう「あなた」に向かって、「せめて夜が明けるまでは一緒にいたい」という気持ちを歌ったもので、ちょっと『いちごの片想い』ではなさそうです。 このオリジナルは、Patience and Prudence という、まだ子供の姉妹の歌ったものだとずっと思っていたんですが、作られたのはなんと1926 年。Gene Austin (ジーン・オースチン) が1927 年にナンバーワン・ヒットさせています。 う~ん、『砂に書いたラブレター』よりもさらに古い曲だったのかぁ。 Patience and Prudence で1956年に全米でヒットしたので、アメリカ編集のオールディーズのオムニバス盤などでは、ナンシー・シナトラではなく、こちらが採り上げられていますね。 でも、当時レコードは高くて、中学生の僕にはしょっちゅう買えるものではありませんでしたから、こうして中尾ミエやベニ・シスターズ、Patience and Prudence などの音源が CD で聴けるようになったのは、本当にありがたいです。一瞬にしてあの頃に戻れるもんなぁ。 ところで、Patience and Prudence は、パティエンス&プルーデンスと表記するのが普通のようですけど、やっぱり「パティエンス」はまずいんではないでしょうかねえ。 どう考えても、「ペイシェンス」だでや。
2004.09.21
閲覧総数 1114
-
12

ロネッツ『ビー・マイ・ベイビー』
“Be My Baby”by the Ronettes 1963 今日のタイトルを見て、「あ、この曲なら知ってる」「これなら感想書けそうだ」と思った人も多いのではないだろうか。はい、いいですよ。どんどん感想書いて下さいよ。もちろんこの曲に関する思い出なんかあったら、大歓迎ですよ。お待ちしてますよ。 実は11/10 の日記に「どんどこももんちゃん」さんがレスをつけてくれて、その中で「もし、よかったら「be my baby」の解説もして下さいませ」と書いてくれました。僕としても、この曲のことはいずれ書かなければと思っていたので、いつか必ず書くと約束したのです。おーい、約束果たしたぞ~、ハマショー・フリークの「どんどこももんちゃん」さ~ん。とか言ってこのまま終わってはいけない。(笑) “Be My Baby”を初めて聴いたときの印象までは記憶にないが、当時中学生だった僕は、たぶん弘田三枝子の日本語バージョンとロネッツのオリジナルをほぼ同時に聴いているはずだ。その時は「どっちもいいなあ」と思っていた。何しろ僕はとりあえず日本語で覚えたからね。 「♪ 忘れられない ひーとみー 離れられない そのみりょーくー」ってさ。ただ、何度か聴いているうちに、バックコーラスの歌詞の違いが気になりだしたんだよね、これが。 サビの部分のコーラスは "♪ Be my be my baby, my one and only baby" って言ってると思うんだけど、日本語バージョンは、後ろの "♪...my one and only baby" を無視して "♪ Be my be my little baby,..." を繰り返すだけ(littleは余計だし...)。オリジナルを聴いてからこの日本語バージョンを聴くと、どうしてもそこの部分だけは違和感があって気になってしまう。いっそのこと "♪...my one and only baby" の部分も日本語にしてしまった方がよかったんじゃないの。「♪...わたーしだけのものー」とかさ。 「どうせわかりゃしないんだから」と手を抜くと、あとで後悔することになるんだ。などと今さら怒ってみたところで、どうにもならないが、弘田三枝子のバージョンは、訳詞もいいし(またまた漣健児!)、彼女の声と歌い方にとても合った曲なだけに、残念だ。もっとも、アレンジについては比較するのもかわいそうなくらい、初めから勝負にならないけどね。予算の関係とかもあっただろうしね。 プロデューサー、フィル・スペクターが日本でも注目され始めたのは、おそらくこの曲のヒットからだろう。彼の作り上げた厚みのある独特の音の世界は、"Wall of Sound" と呼ばれ、この曲にもそれは遺憾なく発揮されている。 まず、誰もが1発でこの曲だと言い当ててしまうあのイントロのドラム2小節。単純なバスドラとスネアだけの組み合わせだが、これが無いと当然この曲は始まらない。そして、これがないとこの曲は終わらない。なぜなら、エンディングに行く前にもう1度全く同じパターンが入るからだ。この辺の作りは本当に感心してしまう。「ドッ、ドドッ、タン! ドッ、ドドッ、タン! 」って、思わず口ドラムやってしまいますよね。(笑) このドラムに続いてさらに2小節の厚みのある前奏が続くが、ここで聞こえてくるあの楽器の音色には、思わず耳を奪われてしまう。この楽器はエンディングまで響き続けて、実にうまい隠し味になっているのだ。(突然ですが文中クイズです:この楽器とはなんでしょう? ヒント:マラカス[シェーカーかな?]も聞こえるけど...) とはいえ、いつまでも耳を奪われているわけにもゆかない。このあとすぐにあの魅惑にあふれたロニーの声が続くからだ。リードボーカルの彼女の声は、決して澄んだ美しい声ではない。かと言って、ソウルやブルースの黒人歌手にあるようなドスの利いた迫力のある声というのでもない。ちょっとハスキーがかって、あまり大人っぽくないけれど、何とも引き込まれてしまいそうな、実に不思議な魅力を備えた声だ。ロニーの声は誰の声に似ているか考えてみた。そしたら思いついたね。デビュー当時の梓みちよだ。もしもう少し低い声だったら、ロニーにそっくりなように思うけど...。見当違いだったらごめんなさい。 歌は途中からコーラスが絡み、間奏ではストリングスが強調されてますます厚みが加わって、あとは一気に最後まで行ってしまう。ただし、エンディングの前にさっきも書いたあのドラムソロが入るのが、実ににくいアクセントになっている。 歌詞はといえば、タイトルからも想像できるように、例によって「他愛もない愛の歌」なのです。「初めて逢った夜、わたしには分かったの。とってもあなたが必要なんだっていうことがね...」ってな具合に始まりまして、「...だから、わたしを愛してると言って。あなたがわたしを自慢できるようにしてあげる。どこへ行っても、みんなを振り向かせてみせるわ...」という感じ。この最後の "♪ We’ll make them turn their head, every place we go" は、この詞で一番好きかな。あと2番の "♪ For every kiss you give me I’ll give you three(あなたが1回キスしてくれたら、わたしは3回お返しするわ)" っていうのも気に入ってます。 『ビー・マイ・ベイビー』は実に名曲だが、ロネッツのバージョンを越えるのはかなり難しいと思う。それでも後にこれをカヴァーしている勇気ある人がいた。その名はカーマイン・アピス。バニラファッジのドラマー。その後、ベック・ボガード&アピスのあのカーマイン・アピスだ(因みに今日12/15は彼の誕生日!)。彼のバージョンは聴いたことがある人も多いと思う。結構いい味出してはいるが、オリジナルは越えていない。だがこれは無理もない話だ。オリジナルは越えなくていいのだ。問題は、彼がなぜこの曲をあえて取り上げたのかということだと思う。きっと大好きな曲で、いつかは自分でも歌ってみたいと思っていたに違いないんだ。 もう一人、日本でも男性歌手でこの曲を取り上げているのが、浜田省吾だ。しかし困った。僕はまだ彼の歌う『ビー・マイ・ベイビー』を聴いたことがない。しかしこれに関しては「どんどこももんちゃん」さん初め、きっといろんな方が「感想」で書いてくれると思うので、皆さん期待して待ちましょうね。 ところでこの二人とも男性ですよね。でも心配はいりません。タイトルも歌詞も男性女性どちら側からでもおかしくない内容だから、変ではないんだよね。ただし弘田三枝子の日本語盤は、語尾の「・・・のよ」が完全に女性です。 最後に一言。ビーチボーイズの超名曲 "Don’t Worry Baby" が、"Be My Baby" のアンサーソングだという説もあるようだが、確認は取れていない。だが、"Be My Baby" が後に与えた多大な影響を思うとき、この話もまんざら眉唾物だとも思えない気がしてくるのだ。 ああ、長かった。(笑) (文中訳は穴沢です)
2002.12.15
閲覧総数 681
-
13

We all love each other, don't we? (愛し合ってるかい?)
“I've Been Loving You Too Long” by the Otis Redding [Live]1967そろそろ梅雨入りかと思っていたところに、台風6号が駆け足で通り抜けて行きました。今回はこちらは特に被害はなかったんですが、皆さんのところはどうでしたか。今年は観測史上最速のペースで7号まで発生しているようで、ちょっと先が思いやられます。で、梅雨はどうなったんでしょう。もう梅雨入りしたんでしょうかねえ。先週の土曜日、5月9日の “穴沢ジョージの Good Old Music” では、そろそろ雨の季節ということで、リクエストいただいた雨の曲もかけたんですが、まだ「雨特集」をやるタイミングではない感じです。そのかわり、2日が清志郎くんの命日だったのに取り上げられなかったので、一週遅れでちょっと特集しました。お送りした曲は以下のとおりです。 1. Yes It Is (ビートルズ) 2. I've Been Loving You Too Long 3. Satisfaction 4. Try a Little Tenderness (以上、Otis Redding) 5. ラブミー・テンダー (RCサクセション) 6. I Think It's Going to Rain Today 7. Can't Help Falling in Love (以上、UB40) 8. The Sound of Silence (Simon and Garfunkel) 9. 花のささやき (ウィルマ・ゴイク)1. は、前回間違えて頭を出してしまったお詫びに、通してかけました。2. ~5. が、忌野清志郎特集で、2~4. は、清志郎が大いに参考にしたと思われるオーティス・レディングの、モントレー・ポップフェスのライブから。5. は、清志郎の見事な訳詞でね。6. ~ 9. が今週のリクエスト曲。期せずして UB40 を2曲頂きました。6. は、糸満ろまんさん、7. が、杏さん。8. は、アルバムバージョンで、旧友の tougei さん。9. は、サンレモ66年入賞曲で、ミスターコーラさんからでした。以上、通算30回目を迎えた “穴沢ジョージの Good Old Music” でした。 ********** オーティス・レディングは、1967年のモントレー・ポップフェスティバルで圧巻のステージを見せました。この時の映像を僕が初めて見たのは、70年代に入ってからで、テレビで一度放映されたんですが、ウッドストックの映画の方が先でした。 このフェスティバルの模様を納めたレコードは持っていましたが、このレコード、A面がジミヘンでB面がオーティスという大変贅沢な組み合わせで、すり減るほど聴いたものです。 で、オーティスの “I've Been Loving You Too Long” に入るときのMCが印象的でね。 “・・・This is the love crowd. Right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah!・・・” っていう感じかな。正確に聞き取れているとは限らないので、ご了承を。 時は1967年。場所は、約束の地サンフランシスコにほど近いカリフォルニア州モントレー。この歴史的なポップフェスが "Summer of Love" と呼ばれたあの夏の序章となったのです。そこで歌ったオーティスのこの MC の場面に、清志郎くんも大いに感動したに違いない。「愛し合ってるかい!」はこれを訳したんだなと、後に思ったものです。 “I've Been Loving You Too Long (Monterey '67)” by Otis Redding 忌野清志郎くんがブッカー T. & MG's とレコーディングした『オーティスが教えてくれた』っていう歌がありますね。この歌が出来た時の様子を NHK で放送したのを一部見た記憶があるんですけど、きちんと見ていませんでした。 で、この歌の歌詞を見てみると、最後が「♪ 愛し合うこと 戦争をやめること」で締めくくられてます。これこそがあの奇跡的なモンタレー・ポップフェスでのオーティスの言葉と、「愛と平和 (Love & Peace)」を合い言葉にそこに集まった若者の大群衆 (love crowd) を念頭に置いた、清志郎くんの遺言のようにも聞こえてくるんですよね。 『オーティスが教えてくれた』 忌野清志郎
2015.05.13
閲覧総数 1323
-
14

『この素晴らしき世界』(今月の歌)
“What a Wonderful World” by Louis Armstrong 1967 サッチモの『この素晴らしき世界 (What a Wonderful World)』、何度となくラジオで取り上げている曲ですが、この歌と戦争は、僕の頭の中で切り離すことができません。 一番の理由は、何と言っても、あのベトナム戦争に赴く兵士を慰問したときに彼が歌った光景が目に残って忘れられないからだと思います。 テレビのドキュメンタリーで見た記憶があるので、映像はネットで見ることができそうなものですが、検索してもなかなかヒットしませんでした。 辛うじて YouTube で見つけたのがこちら↓。 “Louis Armstrong 1967-12-20 Fort Hood ABC“Operation: Entertainment”” 2曲目に歌っています。 ここに映っている若者の大多数が徴兵で招集されたはずで、どれくらいの人数が生きて帰っただろうか。 この番組のタイトルが “Operation: Entertainment (作戦:娯楽)”。とても笑えない冗談としか思えないが、戦争になるとこういうことが普通に起きてしまう。 1967年といえば、6月にカリフォルニアであの「モンタレー・ポップフェスティバル」が開かれた。集まった若者の多くが長髪で愛と平和を訴える。その半年後に、南部テキサス州の陸軍基地フォート・フッドでは、ベトナムの戦地に向かう軍服を着た短髪の若者が慰問楽団のパフォーマンスを見ている。どちらも大集団だが、正反対というか好対照というか、見事に当時のアメリカの両極を見る思いだ。 あれから54年以上も経つというのに、アメリカがベトナムでやったようなことをロシアがウクライナにやろうとしているんだろうか。 本来なら、平和国家の日本がちゃんと仲裁に入って、とりあえずやめなさいと、進言できるようなら良いのだけれど、アメリカの核の傘の下にいると公言しているような政府では、最早そのような立場にも無く、端からできるはずもない。 それでも僕たち一般市民が、戦争は間違っていると声をあげ続けていないと、結局は軍国主義的な或いは狭量な民族主義的な思想が先行して、この国は間違った方向に向かって行ってしまいそうだ。というより、今まさにそっちに向かっているようで怖い。 それで、今月からラジオの中で「今月の歌」のコーナーを設けようかと思いついて、3月は『この素晴らしき世界 (What a Wonderful World)』を「今月の歌」に決めました。 やり方としては、毎週違う人の歌または演奏で、どの時間帯にかけるかは気分次第で決めるというのがルール。もちろんリクエスト有りです。ただし、「今月の歌」はその月の最初に決めますが、あらかじめ前の月に予告することも有りです。まあ、色々有りです。 ↓息子が釣ってきた、でかいガーラ。食卓が賑やかになりました。 ********** 3月5日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1.にくい貴方 (ナンシーシナトラ) 2. Listen People (ハーマンズ・ハーミッツ) 3. 監獄ロック (ブルース・ブラザーズ) 4. 恋のデュエット (エルトン・ジョン&キキ・ディー) 5. マリリン・モンロー (キキ・ディー) 6. Viva Bobby Joe (The Equals) 7. Gimmie Hope Jo’anna (Eddy Grant) 8. Rescue Me (Lesley Duncan) 9. 渚のデイト (伊東ゆかり) 10. この素晴らしき世界 (ルイ・アームストロング) リクエスト曲は、8.尻焼原人さん。9.酋長Kobaさん。10.座波ソーメンさん。ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲。1.&2.は今年とカレンダーが同じだった1966年の3月5日付 Cash Box Top Single の#2.と#4.の2曲。3.はこの日がジョン・べルーシの命日(1982.3.5.没,享年33)で。4.&5.はこの翌日がキキ・ディーの誕生日(1947.3.6.生)で。日付を間違えてしまいましたが、せっかく選んだ曲なので1日早いおめでとうとなりました。6.&7.はこの日がエディ・グラントの誕生日(1948.3.5.生,75歳)で。Happy Birthday! では、次回もよろしく。
2022.03.11
閲覧総数 576
-
15

大坂なおみさんベスト4進出!~9/6のラジオはお休みです
“Questions 67 & 68” by Chicago 1969 ほとんど決まり文句のようになってしましましたが、テニスの全米オープンがセカンドウィークに入ってしまいました。というより、女子のシングルスはすでにベスト4が出揃って、もう次は準決勝です。 アンドレエワさんはベスト8にも残れず残念でしたが、負けた翌日には楽しそうにダブルスを戦っているのを見て安心しました。まだ若いのだから、これからに期待しましょうね。 さて、大坂なおみさんですが、なんと!ガウフを破って準々決勝に進み、ムチョバも破り明日は準決勝です。そして準決勝の相手はあのアニシモワです。 ウィンブルドンの決勝でシフィオンテクにダブルベーグル(6-0,6-0)喰らってすっかり有名になってしまったアニシモワさんですが、実力があるのは間違いなく、大坂さんの相手としては結構厄介かもしれないので、要注意ですね。 ただ、前回のウィンブルドンから今回の全米オープンに入ってからの試合を見る限り、大坂なおみは見事に復活したと言って良いでしょう。 落ち着いた試合運びのおかげで、簡単に崩れることがなくなっているので、安心して見ていられるというやつです。よほどの実力がある相手でないと今の大坂なおみは倒せないと思うのです。明日が楽しみです。 大坂さんはいつもかなり奇抜なウェアで僕らを驚かせてくれますが、今回はまたびっくりさせてくれましたね。 ↓ちょうちんブルマの二枚重ね?因みにナイキです。 ところで、今沖縄は旧暦のカレンダーでお盆に入っています。 9月4,5,6日が、旧暦の7月13,14.15日にあたり、今日がウンケー、明日はナカヌヒー、そして明後日が最終日ウークイと続きます。 ウークイの日は特別で、要するにお盆に帰ってきたご先祖を送り返す日なので、エーサーなどもこの日に行われることが多いです。 そんなこともあって、9月6日は旧盆ウークイ特番のため、「穴沢ジョージの “Good Old Music”」はお休みさせていただきます。 来週からは通常通りになりますので、どうぞよろしく。 ********** 今年とカレンダーが同じだった過去に遡って、ラジオでは放送当日と同じ日付のヒットチャートを眺めて、その中から何曲かおかけしています。今回は1969年に遡り、8月30日付 Cash Box のシングル盤ヒットチャートからたくさん選んでお届けしました。 ベスト10にはおなじみの曲も多いですが、いつも思うのは、かなりランキングの上位に達しなかった割には有名な曲がいくつかあって、ヒットせずとも後世に残っている曲ってあるんだなあと。 今回でいえば、シカゴの “Questions 67 & 68” は82位。どこまで上昇したんだろうと調べてみたらびっくり。Cash Box ではこの82位が最高位で、Billboard でも71位止まり。 これは実に意外でした。当時ヒットパレードは聴いていなかったとはいえ、この曲は印象的で、あの2枚組のLPの中でも一番の出来だと勝手に思っていただけにね。 まあ、そんなもんかなと、納得しておきましょうね。 “Questions 67 & 68” by Chicago 1969 ********** 8月30日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. Sugar Sugar (The Archies)[#5] 2. Sweet Caroline (Neil Diamond)[#3] 3. Put a Little Love in Your Heart (Jackie DeShannon)[#4] 4. Forget Him (Bobby Rydell) 5. ボーイ・ハント (伊東ゆかり) 6. A Nightingale Sang in Berkeley Square (Michael Buble) 7. It’s Getting Better (Mama Cass)[#37] 8. Easy to be hard (Three Dog Night)[#15] 9. Barabajagal (Donovan)[#29] 10. Rain (Jose Feliciano)[#75] 11. Questions 67 & 68 (Chicago)[#82] リクエスト曲は、5.酋長Kobaさん。ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。5.「今月の歌」伊東ゆかりの日本語版。6.先月の「今月の歌」マイケル・ブーブレで。これ以外は今年とカレンダーの同じだった1969年8月30日付 Cash Box のシングル盤ヒットチャートからお届けしました。#印が順位です。因みにこの日の#1.はローリング・ストーンズの “Honkey Tonk Women” でした。次回お届けします。 以上。次回もよろしくお願いします。
2025.09.05
閲覧総数 191
-
16

“Remembrance for Stan Hays” さよなら、スタンさん!
“When The Saints Go Marchin’ in” by Phil & Guuwa Band 2025 沖縄に来てから世話になった音楽仲間が二人、相次いで亡くなって、少なからず寂しい思いを引きずっています。 7月には「寓話」で長年クラリネットを吹いていたスタンさんが、そして8月には与那原「コスモス」のオーナー西銘さんが。 このお二人には大変良い思い出しかありません。 ぜひ安らかにお眠りください。でも、あと1回でいいから会って話したかった。 ********** ここではまず、スタンさんのことから書いて、西銘さんについては後日改めて書こうと思う。 初めてベースの恵茂さんに誘われて、土曜日の「寓話」のドラムのトラをさせてもらったのが、確か2013年のことだったかと記憶している。 スタンさんは初対面からとても気さくで話しやすく、その後何度か土曜日の「寓話」でお世話になっても、その都度「ジョージ、ジョージ!」と、暖かく僕を迎えてくれたのがとてもうれしかった。 年齢的にはさほど離れてはいなかったけれど、大変頼りになる兄貴的なすばらしいクラリネット吹きだった。 ある日、スタンさんから「なにからやろうか」と言われて、咄嗟に “I’ll Close My Eyes” と僕がいうと、「“I’ll Close My Eyes” か。いいね」と、その日は “I’ll Close My Eyes” からスタートして、なんだかとても気持ちよく演奏したことを今でも思い出すことがある。 なぜ突然 “I’ll Close My Eyes” になったのかは記憶にないが、この曲は思い出の1曲になった。 サックスのフィルくんはいわゆるバンドメンバーではなかったけれど、スタンさんの知り合いということでよく顔を出して仲間に加わり、歌も歌った。やはり土曜日の「寓話」で知り合ったことになる。その後フィルくんはほぼメンバーのようになって、今では第4以外の日曜日の「寓話」のレギュラーになっている模様。 そのフィルくんの主催で、先週の土曜日(6/20)、「寓話」にて “Remembrance for Stan Hays” が盛大に催された。スタンさんゆかりの人たちでお店には入りきらない人ほどの人が詰めかけた。 たくさんの人から、生前のスタンさんとの逸話などを聴くことができたけれど、みなさん「彼の人間性、人柄の良さ」を口々に語っていたのは印象的だった。 ただ、残念ながら僕の英語聞き取り能力の衰え具合がひどく、ナチュラルスピードで話されると、わからないことの方が多い。これは重症だと認識させられた。とにかくユーモア精神たっぷりだったスタンさんの思い出話には、やはりユーモアがふんだんに含まれているのだが、これが聞き取れない。そこで朗報。 当日の模様がYouTubeにアップされました。 これ↓を拝見して勉強するのがよろしかろうと。 Memories of Stan 49分45秒後からは当日の演奏も聴けます。『聖者の行進』からスタートしますが、最後の方でフィルくんの歌が聴けます。しかし “♪ When Stan went marchin’ in” って歌っていたような。Very nice arrangement, Phil! 思えば『聖者の行進』は亡くなった者を陽気に弔おうというジャズの原点の1曲なのだと再認識。 ********** 9月20日放送の「穴沢ジョージの “Good Old Music”」のオンエア曲です。1. September Song (Dion & The Belmonts) 2. I Should Care (Julie London) 3. Day by Day (Astrud Gilberto) 4. Cheek to Cheek 5. Always (以上, Ella Fitzgerald) 6. When You’re Smiling (Dr. John with Dirty Dozen Brass Band) 7. Misty (Johnny Mathis) 8. Heartbreak Hotel (Elvis Presley) 9. 悲しき少年兵 (藤木孝) 10. Summer Symphony (Lesley Gore) 11. A Summer Song (Skeeter Davis) リクエスト曲は、 7.カルロス・イノウエさん。8.酋長Kobaさん。以上、ありがとうございました。 上記以外は穴沢選曲です。1.は毎年恒例?9月に聴く曲。2.~5.はこの日が Paul Weston の命日(1996.9.20没,享年84)で。2.&3.は Paul Weston 作曲、4.&5.はアレンジャーとしての彼の代表作、エラ・フィッツジェラルドの名盤 “The Irving Berlin Songbook” より。6. 「今月の歌」『君ほほえめば』Dr.ジョンで!9.はこの日が藤木孝の命日(2020.9.20没,享年80)で。10.&11.は、秋分が近いのでそろそろ夏も終わり`に近づいているかということで、夏の歌2曲を。 以上。次回もよろしくお願いします。
2025.09.26
閲覧総数 178
-
-
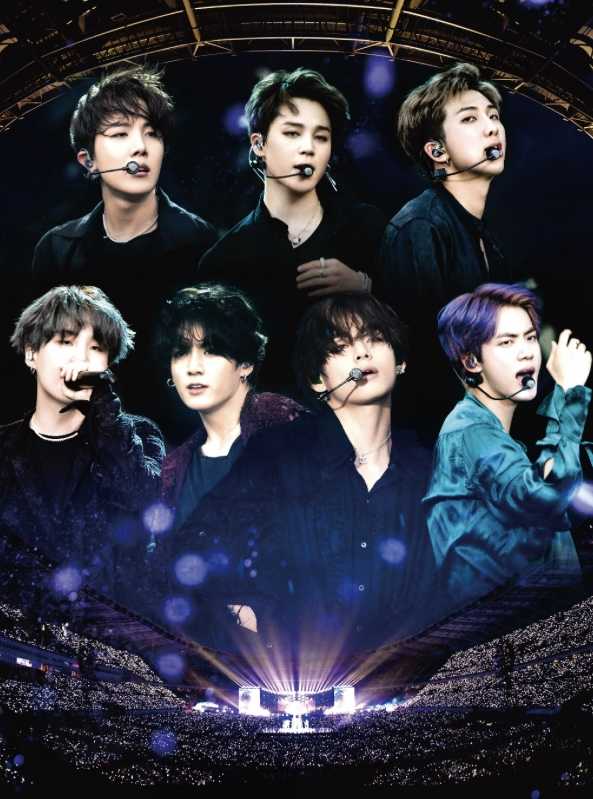
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-

- Jazz
- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…
- (2025-11-02 07:32:37)
-






