2010年11月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
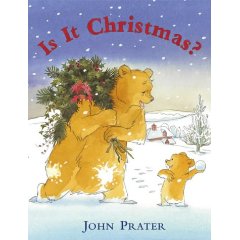
"Is It Christmas?", "Baby Bear's Christmas Kiss" by John Crater
左の"Is It Christmas?"は昨年も紹介しましたがとても好きな絵本ですのでもう再度登場です。Amazonで見るとBaby BearとGrandbearが登場するBaby Bearシリーズと言うのがあるようですが、古書でしか手に入らない物が多いようで残念です。なぜ,冬に熊?というのは置いといて、、熊のふわふわっとしたイメージと雪のイメージは合うような気がします。Little Bearはクリスマスが待ちきれなくて、毎朝目が覚めるとGrandbearに"Is it Chritmas?"と尋ねます。まだだよ、"After two more sleeps, it will be."と答えるところなど、お正月を指折り数えて待っている子どもと親の会話のようです。「もういくつ寝ると,お正月ー」の歌のせりふそのものです。クリスマスの準備に忙しいGrandbear、お手伝い(邪魔?)するLittle Bearのの様子が微笑ましい!やっとやって来たクリスマスの朝、プレゼントと一緒にお客様がやってきます。その続きになっているのが,右側の"Baby Bear's Christmas Kiss"です。Granny Bear, Uncle Bear, Auntie Bear,に4人のCousin Bearが集まりました。ところが,Little BearはGrand Bearに何もプレゼントを用意していない事に気づきます。そこで,すてきな思いつき!Snowberry snowmanです。寒いはずなのに温かい!ほっこりした気分になります。
2010.11.30
-
クリスマス絵本、ど~んとかごにいれました。
今年はちょっと出遅れてしまいました。きのう、どっさりとかごにクリスマス絵本をいれました。昨年よりも増えていて、かごがギューギュー状態です。古い本もあるし、昨年のクリスマスが終わってから届いた本もありますので、古い会員さんも新しい会員さんも、どんどん読んでくださいね。昨日,来た高校1年生、今までこういう絵本はCD付きでないと読めなかった、と言っていました。もうCDなしでも読めるくらいになってきたから、読んでみてね!」とすすめてみました。絵本は子どもが大人に読んでもらうという場合が多いので、けっこう難しい表現もあります。わからない言葉も読めない単語も何度も聞いて、絵と見比べて,子どもは言葉を習得して行くんですね。もう子どもではない私たちもCDがあれば,それと同じ体験ができます。ただ、ちょっとスピードが速すぎると感じるものもあるので、そういう絵本は一度CDと一緒に読んでから、もう一度じっくり絵を見ながら味わいながら読んでほしいな,と思います。1回読んでさっさと次ぎに行くには絵本はもったいない栄養がいっぱいあります。CDなしの絵本はじっくり読むチャンスと思って味わって読んで見てください。
2010.11.30
-

紅葉の散歩でシャドーイング ”Paddington"とI Am Readingシリーズ
今年は例年より,関東の紅葉は遅れているという事で、まだまだ我が家の周辺はこんな奇麗な紅葉が見られます。左は公園の、右はうちのマンションのすぐ前の銀杏並木です。今日はこのすばらしいお天気に誘われて、先週の運動不足を解消しようと思って散歩に出ました。正味歩いたのは1時間半くらい、途中ベンチで休んだり、買い物したり、2時間くらいで帰ってきました。公園内はピクニックを楽しむ人々、ジョギングやウォーキングする人がいっぱい、のどかな1日でした。今日のお散歩のお供のiPodの中身はPaddington Here and NowとI am Reading シリーズのAlbert's RaccoonとBarn Party。しばらくMagic Tree Houseばかり聞いていたのですが、28巻まで聞き終わりましたので、イギリス英語を聞きたくなりました。 Paddington Bearはけっこうスピードがありますが、すばらしい朗読です。なんせ主人公が熊のPaddingtonですから、言葉の間違いがよく出てきます。Stir-fryをStirred Fliesと間違えたPaddingtonはなんと本物のハエを混ぜた料理を隣人のMr Curryにごちそうしてしまいます。本人はLucyおばさんにDon't Swallow fliesと言われたんだ、とMr Curryに言ったのですが、これはあの有名な絵本「I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly」を思い出しました。もちろんMr Curryはカンカンです。でも、Stir-fryを食べたいと言ったのは自分だったのですから,Paddingtonは全く悪気はなかったのです。I am Reading シリーズはちょっとゆっくり目、Magic Tree Houseくらいのスピードです。奇麗なイギリス英語で音響効果もあって聞いてて楽しいし、シャドーイングにはぴったりだと思います。「Albert's Raccoon」はいつも変な贈り物を送ってよこすおじさんが、今回送ってくれたRaccoonのRockyが巻き起こす騒動のお話しです。このraccoonただ者ではありません。とんだトラブルメーカーかと思ったら,ものすごい天才というか魔法使いというかすごい能力の持ち主だったのです。I am Readingは短いのですが、ちょっと学校英語ではお目にかからない単語がいっぱい出て来て,難しく感じますが、聞き読みをすれば内容が分かりやすいと思います。ぜひ、すてきな朗読を聞いてください。
2010.11.28
-
うれしい!高校生からの報告
1週間アメリカ人の女子高校生のホームステイ受け入れを体験した高校生が嬉しい報告をしてくれました。中学校の頃から多読も勉強も熱心にしていたこの高校生は、将来は英語を使った仕事に就きたいとか、留学したいとか,夢を語っていたのですが、その第一歩としてホームステイの受け入れと,その交換として自分もアメリカにホームステイに行くという高校のプログラムに積極的に応募して今回の受け入れとなりました。今日教室に来てその時の様子を語ってくれました。なぜか分からないけれど,相手の言う事がスイスイ分かる!話す事もできた!自分でも不思議なくらい英語が出て来たという事でした。毎日学校に一緒に行って、帰りには寄り道してお店に入ったり,お休みの日にはディズニーシーに家族で出かけたり、英語漬けの毎日だったようです。不自由なく英語を使えたという事が大きな自信になったようです。彼女はこれは絶対多読の成果だ,と話していました。それと,中学校のときの音読だと。中学校の時、教科書の音読をしっかりやって自然に覚えてしまうほど読んでいました。発音も多読の聞き読みやシャドーイングのの成果でしょうか、かなり自然な発音で音のつながりもちゃんとできています。高校生になってからは学校の勉強は自分でするということで、教室では多読が中心で、Totally Trueや最近はSpeech Navigatorをやっています。またQA300もやってますが、スムーズに会話がなりたっています。成果を自分で感じてますます多読がんばるぞう!と今日は張り切ってました。シャドーイングがいいという事も自分で感じたたようで、シャドーイングもがんばるぞ,宣言してました。今日はMagic Tree Houseをまるまる1冊大きな声でシャドーイングしていました。彼女のこれからの成長が楽しみです。
2010.11.23
-
「多読村祭り」に行ってきました。
昨日は朝から調布の電気通信大学で催された「多読村祭り」に行ってきました。お手伝いをする事になっていたのですが、私の仕事はフリーマーケットの店番でした。実際は自分の番の時も他の方もたくさん手伝ってくださって助かりました。出品されたのは1000冊以上ということでした。どれもタドキスト必読の本ばかりでこれから多読を始めようと言う方には絶対お薦めしたい本ばかりでした。ペーパーバックもかなり出ていましたが、有名な本もいっぱいで、目標本として買っておきたいと思いながら、未読本が一杯の状態では我慢我慢。結局私が買ったのは既に持っているけど、もう1冊あってもいいかなと思う本を中心に6冊ほど購入しました。これでも1000もしなかったのですから超買い得です。それにタドキストのタイのおみやげのかわいいリボンがついた50円のバッグ、私の好きな色の花模様ですぐ目がいってしまいました。なんだか買い物ばかりしていたみたいですが、酒井先生の講演会がメインだったのです。買い物客がぼちぼちの段階ではこの会場のいすが全部埋まるかな,とちょっと不安でしたが、いざ始まるとどんどん人が増えてイスが足りないくらいになりました。まさに、5~6歳から70代80代までの方がいらしたのではないでしょうか。多読は今すごいことになってます!午前と午後、2回に分けて行われましたが、どんどん脱線オーケーの講演会ということで、やっぱりかなり脱線してましたね。でも、ちゃんと戻してくれるタドキストがたくさんいるのでいつもの様にちゃんと着地します。数年前から何回も聞いている酒井先生のお話ですが、少しずつ変化しています。それは今回特に感じたののは多読は量だけではない、質もかなり大事ということです。特に簡単な本を読む事の大切さが強調されていました。また、シャドーイングで読む力に繋がってくるという事です。多読の集まりに参加する様になって7年ほどですが、しばらく会っていなかった懐かしい方もたくさん会えて楽しい1日でした。
2010.11.22
-
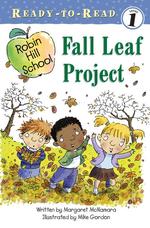
Robin Hill Schoolシリーズの中の秋の絵本
Ready-to-Readの中のRobin Hill Schoolシリーズは24冊出ている事が調べてみて分かりました。教室にあるのは10冊くらいですので、買い足しました。教室ではピンクレベルよりちょっと長めなので赤レベルにしています。YL(読みやすさレベル)は0.7~0.9くらいだと思います。小学校1年生のMrs.Connerのクラスの様子が描かれています。前にご紹介した"Snow Day"ではSnow Dayの意味を初めて知りましが、今日ご紹介する"Happy Thanksgiving"でも、そうだったのか!というような表現に出会いました。先生が大声の男の子を注意する時の言葉が“Use your indoor voice!"です。なるほど!と思いました。"Fall Leaf Project"はたぶん、日本で言ったら社会科のクラスなんでしょうね。アメリカの地図を広げて、アメリカには葉っぱの色が変わらない州もあるんですよ、とMrs. Connerが言います。Robin Hill Schoolの周りにはいっぱい奇麗な葉っぱが落ちています。教室を奇麗に飾り付けています。奇麗な葉っぱを見られない学校に送ってあげようと言う事に!"Happy Thanksgiving"では1年生たちはCosutumeを作って着ています。でも,その真っ最中にFire Drillが始まります。衣装を着たまま整然と列を作って子どもたちは校庭に移動します。衣装を着たままの子どもたちがかわいい!Fire bellがなって、さあ大変と思ったら、Fire Drillだったのですね。どちらも、普段通りの学校の様子です。季節の行事や歴史的な行事などが描かれているシリーズです。易しくて,楽しくて,でも,毎回「勉強になるなあ!」と感心してしまうシリーズです。
2010.11.18
-
秋の絵本 "In November" by Cynthia Rylant
In Novemberもう秋はすっかり深まり、冬の気配も!冬が来る前に秋の絵本をご紹介します。この絵本の秋は関東よりはもっと寒い地方をイメージしてもらった方がぴったり来ます。東京の11月はまだ紅葉が奇麗ですが、この絵本の11月は冬の入り口です。渡り鳥たちが飛び立つ季節、とどまる鳥は一生懸命えさをとる季節です。動物たちには厳しい冬の準備ですが、人間にとってはこの季節はすてきな季節です。遠くから家族が集まっておいしいごちそうがテーブル一杯に並びます。おいしそうなにおいが漂ってきそうです。しーんとした雰囲気と温かい雰囲気が伝わる絵本です。子どもよりきっと大人の人にじっくりと味わっていただきたい絵本です。
2010.11.17
-
「ワイルド・ソウル」 垣根涼介著
友人のお勧めで初めてこの作家の本を読みました。おもしろい、という言葉で言うのははばかられるほどの感激でした。上巻はつらい場面が多くてショックでした。私の世間知らず、物知らずを恥ずかしく思いました。数年前にドミニカ移民の方達が日本政府に対して謝罪を求めて裁判を起こしたというニュースを記憶していますが、それほど注目していませんでした。「ワイルド・ソウル」は南米ブラジルのアマゾンの荒廃した土地に移民した日本人の恨み、怨念が詰まったような作品です。こんな熱帯の奥地、全く耕作に向かない土地に何の保証もなく放り込んだのが、国の政策であったという事が信じられない思います。これがたった50年くらい前の日本の姿だったのです。政府に対して起こした大復讐劇、絶対に成功してほしいと、力を入れて読んでいました。小説の力を感じました。この登場人物たちの心の叫び、ジャングルの中で死んで行った親を思う心、小説だからこそ訴えられる物があると思いました。
2010.11.16
-
中学生の多読と個人レッスン
中学生は全員多読と個人レッスンの組み合わせで行っています。最近、全員にメニューを渡しました。30分以上 自由に多読 自分の好みの本を選んで読む。オレンジレベルを読んでいる人が多い。15分以上 ピンクや赤レベル(CDなしで読める本)をじっくり味わって読む15分以上 シャドーイングする。ここまでで1時間の多読です。30分 個人レッスンを受ける。問題集などの宿題のチェック、教科書の音読、QA100~200~300、Totally Trueなどの副教材、残りの30分で英検のリスニング問題、宿題など、多読など自由にすすめる。10時まで残る事も可能。これを簡潔に書いたメモを多読手帳に貼付けてもらいました。6時半から10時までの間に3~5人の中高生が来ますが、必ずしもこのメニュー通りにすすむわけではないのですが、次に何をしなければならないかをあらかじめわかっているので、以前に比べるとかなりスムーズに進む様になりました。以前は1時間の多読が終わると、先生!終わった、次何したらいい?と聞いてくる生徒が多かったのですが、今は自分で調整して出来る様になってきました。シャドーイングも慣れて来たのか、一応の目安を示してあるので、自分でその順番にすすんで出来る様になってきました。個人レッスンの時はなるべく会話をしっかりするようにしています。QA200や200をすらすら言える様になると他の質問でもかなり答えられる様になります。高校生はSpeech NavigatorとQA300を使っていますが、どんどん会話が広がって行きます。
2010.11.16
-

映画 「冬の小鳥」
冬の小鳥?-?goo?映画冬の小鳥オフィシャルサイト今日、神保町の岩波ホールで「冬の小鳥」を見てきました。この写真に惹かれました。可愛いけれど何かを訴えている目、演技であるはずなのにこれを引き出しているのは映画の力です。父親に捨てられてキリスト教の孤児院に預けられたジニ、必ずパパが迎えに来ると信じて、頑に周りととけ込もうとしません。次々に養女にもらわれて行く孤児たち。自分は迎えが来るから行かないと言い張っています。孤児という言葉、孤独という言葉、親に捨てられたという言葉、1人でも生きて行かなければならないという言葉、私はすべて「言葉」でしか理解していないという事を思い知らされました。映画のエンディングの音楽が流れてから涙が止まらなくなりました。映画の内容は決して涙を誘うような描き方ではないのです。淡々と日常を描いて行きます。静かな映画です。韓国の風景はどこか私が小さい頃に過ごした田園の風景に似ています。
2010.11.14
-
「多読村祭り」に行きましょう!
11月21日(日曜日)に電気通信大学でおいて、多読村祭りが開催されます。この教室での講演会にも2回来ていただき会員のみなさんに楽しい多読のお話をしてくださった酒井邦秀先生ですが、今年で退官を迎えられます。そこで、電気通信大学の調布祭(学園祭)の場をお借りして多読村祭りが行われます。フリーマーケット、多読にまつわる展示など、また、酒井先生の講演会も行われます。まだ酒井先生のお話を聞いた事のない方、ご一緒に出かけませんか。
2010.11.14
-
Saxophoneがこんなにすてきとは!Julian Smithの演奏
歌のレッスンを受けている事は前にも書きました。それで,どんな歌を今度は歌おうか,といろいろYoutubeで見ていたら、こんなすてきな動画にぶつかりました。歌ではないのですが。Youtubeの画像の貼付け方がわからないのでここをクリックしてみてください。↓Julian Smith: Somewhere - Britain's Got Talent 2009昨年のBritain's Got Talent 2009で3位になったJulian Smithさんです。スーザン・ボイルさんの方にばかり注目していてすっかり見落としていました。私のイメージの中のサクソフォンはジャズの楽器をいうイメージでこんなにしっとりと聞かせる演奏は初めてでした。身震いするほど感動しました。演奏中の彼の表情もまたすてきです。いったい今までなぜ注目されなかったのでしょう。ホームページも見つけました。ホームページではほかの曲も聴けます。どれもすばらしい!Julian Smithホームページ
2010.11.14
-
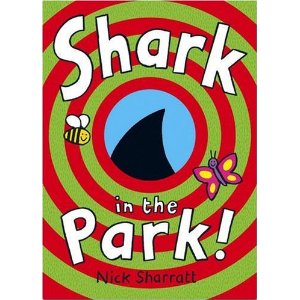
"Shark in the Park " by Nick Sharratt
Jacqueline Wilsonの児童書のイラストレーターとして有名なNick Sharrattさんの届いたばかりの絵本です。独特の鮮やかな色使いが冴えています。仕掛け絵本です。Thimothy Popeくんは新しいTelescopeを買ってもらいました。ちゃんとRhymingしています。早速新しい望遠鏡を持って公園に行って空を見たり、地面をみたり。なんと~!サメが見えました。と思ったら猫でした。それからまたまた,サメだ!と叫ぶと、、という調子で繰り返しの多い展開です。最後の絵を見逃さないでください。ちゃんとオチがありますよ。
2010.11.10
-
"A House for Hermit Crab" by Eric Carle
なぜか,ずっと前からあるのに読んでいなかった絵本。絵本の整理をしていて見つけました。絵がすばらしく奇麗です。同じ作家Eric Carleさんの作品では超有名なSmimmyがありますが、この絵本も海の中が美しく描かれています。やどかりさんは心地よい貝の中で暮らしていましたが、Outgrownしてしまってもうここにはいられません。新しいすみかを見つけなければなりません。不安だけど思い切って外へ出て新しいすみかを見つけます。でもなんだかさびしい!海の中の生き物たちに声をかけて一緒に住みます。すみかの周りを奇麗に賑やかにしてくれた友達と仲良く暮らしていたのに、また1年たって、大きくなってしまいます。また,おうちさがしです。私もよく知らない海の生き物がいっぱい出てきます。Sea Anemones、アネモネですから植物かと思ったらanimalなんだそうです。それからSnails, カタツムリってが海の中にもいたんですね。
2010.11.09
-
Kira-KiraとWeedflower by Cynthia Kadohata
3~4年前に読んだ本ですが、最近Audible.comで音源を買いました。2冊とも買ったのですが、聞いたのはKIra-Kiraだけで,まだWeedflowerは聞いていなかったので、今回「90年の愛~Japanese Americans」を見て聞いてみようと思いました。主人公が10歳くらいの少女の1人称で描かれていますので語り口が素直で分かりやすく描かれています。Weedflowerは日米開戦前から始まり、収容所の生活が描かれています。この中でも何もない砂漠の中で日系人たちが畑を耕し、花を育てる場面が出てきます。Kira-Kiraは戦後の日記人がまだ貧しかった時代が描かれています。まだまだ差別が激しく、主人公の両親が苦しい生活の中でも日本人としての誇りを持って生きる姿に打たれます。海外に移住して差別を受けても毅然として生きていくには”日本人としての誇り”は最後の砦だったのだと思います。どちらも差別、生活の困難さなどがありますが、少女の目からみた小さな日常の喜び,悲しみの方が主題になっていています。涙を流しながらもさわやかさの残るすてきな作品です。
2010.11.09
-
テレビドラマ 「99年の愛 Japanese Americans」
先週の水曜日から5夜連続のドラマ全部見ました。5日間連続というのにまったく飽きも感じず感動しました。仕事が10時までなので,毎回DVDに録画して見ました。橋田壽賀子さんが新聞のコラムで、今書き残しておかなくてはならないテーマであると言っていましたが、確かに忘れてはならない事だと思います。明治時代に貧しさから脱出するために大きな夢を持ってアメリカにわたった日本人、日本人としての誇りを持ち続けながら、アメリカ人として生きる事を選ばなければならなかった人々の苦しみはいかばかりだったかと思います。日系2世ばかりの442部隊の活躍という話は全く知らなかったことでした。児童書の"Kira-Kira"や“Weedflower"も日系二世の物語です。作者のシンシア・カドハラさんの文章のすばらしさから悲惨さよりも日々を精一杯生きた2世の少女が描かれてさわやかな読後感です。
2010.11.08
-
Puppy Mudgeシリーズが入りました。
多読指導をしているNEOさんのブログのご紹介で買ったのですが、是非読んでもらいたいシリーズです。犬のシリーズはみんな大人気、簡単なので小学生にも読んでもらえそうです。Henry & Mudgeシリーズは28冊ありますが、その他にこのPuppy Mudgeが加わりました。一人っ子のHenryがさびしがっていたので両親がMudgeを飼ってくれたのが物語の始まりです。いとこのAnnieのシリーズも加わり、今度はPuppy Mudgeシリーズです。Henry & MedgeはORTを読み進んだ後に、あるいは,平行して読むのにちょうどいいくらいのレベルと長さですが、Puppy Mudgeはぐ~んとレベルが下がります。1ページに1~2センテンス、語数が100語前後のピンクレベル(YLー0.5くらい)です。中学生、高校生にもレベルが上がっても、長い本が読める様になっても、教室内ではピンクレベル、赤レベルも数冊読む様にすすめています。せっかくたくさんある簡単な本を読まずにどんどんレベルが上がって行くのがもったいないという気がします。簡単な本ほど言葉のイメージがつかみやすく、しみ込むと思いますのでこのシリーズも是非読んでもらいたいと思います。Puppy Mudgeとは言いますが、puppyというには大きすぎるほどです。でもやる事が、まだ遊びたい盛りで赤ちゃんっぽいことをするMudgeがかわいいです。眠くなるとお気に入りの毛布を探しまわるMudge、まるで人間の子どもです。このシリーズで初めて知った単語がdroolでした。この単語を見るとMudgeが頭に浮かびます。高校生の女の子はこのシリーズをジュルジュルの犬のシリーズと言ってます。ジュルジュルよだれのMudgeです。
2010.11.07
全17件 (17件中 1-17件目)
1










