2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年06月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
言い過ぎないように注意しているハズが・・・
「君まで一緒にお母さんと言ってたら、生徒さんからすると『言われすぎ』になっちゃうよ。」私が大学生のときに家庭教師をしていた際、友達にこう言われた。私「こんな調子でテスト大丈夫だと思ってんの!」お母様「ほんとよ!これじゃぁ、全くダメじゃないの!」・・・こんな調子でサラウンドのように生徒さんに言っていても、効果はあまり得られない、ということは経験を通して解ってきたので、『あまりいい過ぎないように』日々注意をしていたのだが、さすがに今日は、言ってしまった。ガツンと言わないといけない場合も当然あるので、『言う』ことも大切なのであるが、『言い過ぎる』という点で今日は、ちょっと行き過ぎたな、と思う。ウチでは指導報告が毎回あるので、この指導報告をご覧になると、きっとお家の方は生徒さんに怒るだろう、と思い、お家の方にご連絡をし、状況をご説明した上で、こちらでかなり怒りましたのでとお伝えした。その後、お母様と一緒に今後の対策を立てる。「君は女の子だから、お母さんと一緒にクドクド言っちゃうんだよな。」とはくだんの彼の言葉である。それ以来、クドクドを気をつけることと、誰か講師を教えに行かせる際に、『クドクド系』が良いのか否かは気をつけるようにしている。もし、家庭教師をつける際には、今のお子さんの状況下で「細かく」が必要なのか、「おおらか」が必要なのかを考えて、講師をお選びになると良いです。女の先生は「細かい」場合が多いので、細かくみてもらうと同時にお子さんに『クドクド』言う傾向も強いので、ちょっと『クドクド』が合わなさそうだと思う場合は、男の先生をまずは選択されてみてください。もっとも、性別要素だけでなく、性格要素も入りますので、男の先生でもクドクド言う場合もあります。ご参考まで。
2006/06/21
コメント(0)
-
『まつり縫い』を教える
「よく解らないんです。」と、生徒がいきなりカバンから針と糸を取り出した。は?「まつり縫いのテストがあって、ちょーヤバイ。」どうやら家庭科の授業で実技テストがあるらしく、「本返し縫いはなんとかなるんだけど、まつり縫いが」ということらしい。こういう実技テストって、学校の先生の教えた通りにきっちりやらないとダメなんだけど、縫い方書いてある紙とかもらった?と聞くと、ちゃんと持ってきている。正直、『まつり縫い』より『国語』をやりたいところであるが、気にかかっていることをそのままにする方が結果が悪くなるので、『まつり縫い』を教えることに。はい、じゃぁ、まず玉を作って、、、見本を見せる。ぷしっつ、斜め、ぷしっつと説明し、実際にやってもらう。私が生徒さんに説明している様子をみて、他の生徒が「先生って、家庭科まで教えるの?」ハイ、教えます。過去に、いちょう切りとか教えましたねぇ。っていうか、君達はこの実技試験どうやって突破した?「テキトー」まぁ、適当にこなすぐらい度胸がすわっているならいいんだけど、皆が皆そうじゃないからねぇ。何回か練習しているうちに、だんだん綺麗に縫えるようになったので、じゃぁ、また明日練習してごらん。といって、サブ科目の指導は一旦終了。こういう科目って、私よりお母さんの方が上手いと思うんだけど、と思っていたら、どうやら私に聞く前に、お家の方に聞いたらしく、それでも上手くいかなかったために、私に聞いてきたようであった。針と糸を使って縫うことがうまくできない原因として、・針の向きが上げられる。なので、もし、お子さんが『縫い方』を聞いてきた場合、「針の方向」に注意して、針先をどうやって向けるかをよく教えてあげると上手くいきます。この際に、間違った方向を向いていても、『おしい!』と言うこともポイントです。『ちょっとちょっと違うでしょ!』と言った日には、糸と針を放り投げてそっぽを向きかねない(お子さんからすると『できるぐらいなら聞いてない!』と思うため)ので、ご注意を。
2006/06/19
コメント(0)
-
国語は『当て』にいってるんだけど・・・
「学校の先生が、『この問題、私が教えた内容をきく問題じゃない!』って言ってました!」生徒さんが、私が出した宿題を楽に解けた!と喜びの連絡をしてきた。ん? 学校の先生?「(私が出した)宿題を学校でやってたら、国語の先生がそれを見てて、驚いてました!」あ~、マズイ。国語は完全に学校の出題傾向を『当て』にいってるんだけど、手の内がバレてしまっては、対策を取られる可能性が・・・国語力を伸ばすには、『解き方』をきちんと教えていった方が良いのであるが、定期テストの点数をとにかく上げないとならない場合、『当て』にいきます。「勉強すれば点数が取れるんだな」という実感を持ってもらうのが大切なので、ノートをみて(学校のノートをきちんと取ってこないとダメなのであるが)、こう教えているなら、ここを出すなと対策を立て、生徒さんに演習をしてもらう。これが『今度のテストで点数と取らないと!』という時の黄金パターンなのであるが、今回は手のウチがバレてしまった可能性が・・・ん~、どうするかな。対策立てられた時ように、対策を立てるか。ちょっとひねった問題を用意することにした。本当は、きちんと勉強していればここまでやらなくても良いのであるが、今回は時間の関係もあって、致し方ない。夏に『解き方』をちゃんとやるぞ!あと、学校で(特に先生の前で)宿題を見せないでね(笑
2006/06/16
コメント(2)
-
100円ショップの「森鴎外」
え~!今って文庫本まで100円で売っているんだ~!久々に行った100円ショップ(@ダイソー)にて、森鴎外の文庫本を発見。問題集とかを売っていたのは知っていたのだが、あの問題集はそんなに使い勝手が良いなとは思わないので、文庫本もあまり期待をしないで中を見てみると・・・あっつ、これはかなり良く出来ている!何が良いかと言うと・難しい漢字にはすべて振り仮名が振ってある・解りづらい言葉は、文中で色を変えてあり、その意味を本文のすぐ下の欄に書いてあるという2点。この他にもストーリーのポイントが本文の前に記載がある、登場人物をまとめてあるなど、教科書よりも読みやすく出来ている。森鴎外は、中学ではほとんど国語には出てこない(注:私立の中には教えるところもあります)が、高校では一度はどの作品かは必ず学習する。そして、ものすごく点差がつくのも森鴎外が範囲に入ったときの特徴である。 漢字が読めない ↓ 意味が解らない ↓ 内容がつかめない ↓結果、設問の意図(意味)が解らないという悪循環。教科書を読んでくるように言うよりは、100均のこの文庫本を渡して読んでくるように言った方が、効果があがりそうだな森鴎外は2分冊になっている(内容ではなく収録してある話の量で2つになっている)のだが、両方とも購入する。1か2に載っている話は必ず学校で教えるからなぁ。森鴎外以外にも、夏目漱石や宮沢賢治、芥川龍之介もあった。宮沢賢治は中学生には出てくるので、もし本が好きなお子さんがいたら、小学生のうちに読んでおくと良いです。読みやすく出来ているし、本自体も軽いし、100円なので汚れても気にならない、という点において、『ダイソー文学シリーズ』はオススメです!
2006/06/10
コメント(3)
-
ノートの作り方について
6月5日の日記の「ノートの取り方・・・」のコメントに、質問がありましたので、ポイントを簡単にお伝えします。小学生の場合、ポイントは、おさかなの母さんが書かれているように、・筆算するときは定規を使う・計算式と式の間は隙間をあける・日付を入れるとかですが、多分こういったことはご存知ではないかと思いますので、いかに実行に移すかについて。なんでもそうですが、口頭で伝えて終わり、という形ではなく、こうやって書くと良い、という見本をみせるということが効果があります。もっとも、見本を見せても「ふ~ん」で終る可能性もありますので、薄い字で書いてその上をなぞらせるという『行動』まで踏み込んでやった方が良いです。「ここまでやらないとダメですか?」と聞かれそうですが、今の生徒さんは行動まで踏み込まないと「聞いていない」と同じことになりかねないので、大変だとは思いますが、一度書いてみてなぞらせてはどうでしょうか?なぞらせる、といっても、算数などは計算方法は解っていて、書き方に問題があるだけの場合もありますので、ここに書く、という場所に○などのマークをするといいかと思います。ただし、お子さんによっては、聞いて理解する方を優先するため、『ノートはメモ程度』にしか書かない場合もあります。要は理解できていれば良いので、このタイプのお子さんでしたら、メモ程度の書き込みでもかまいませんが、『解らなくなった場合に見直すベースとなるもの』をきちんと決めておかないと、解らなくなった時に「まぁ、いいか」となりかねないので、注意が必要です。なお、小学生のときは枡目のあるノートを使うことがまずポイントになります。ご参考まで。
2006/06/07
コメント(3)
-
やっぱりノートの取り方から教えないといけなんだな
定期テストの結果が出た。さんさんたる結果の生徒さんがいる。直前、『教えて欲しい』といわれた科目を教えているときに気づいた。あっつ、これはノートの取り方から教えないと厳しいかもしれない。テスト前なので、そのときは応急処置にしたのだが、期末に向けては根本からやり直さないと。ノートの作り方を説明し、実際にやってもらってみたところ、えっつ! と思うぐらい解っていなかった。違う違う、そこに書き込むんじゃない!こうしてこうする、と説明している様子をみて、他の生徒さんが「そのやり方って、クラスで成績の良い人は皆してます。」と言う。やっぱり。。。対策問題の作成に力を入れる前に、ノートの取り方の指導をやった方が効果があった、ということか。『ノートの取り方』か。想像以上に出来ていないものなのね。ここからスタートに切り替えないと。
2006/06/05
コメント(2)
-
都立高もなかなか良いね!
先日、高校説明会に行ってきたのだが、都立高が想像以上に選択肢にとみ、また進学に力を入れていることがよく解った。進学に力を入れている学校の中には、「予備校に頼らない受験」を目指していたり、「速い進度で大学現役合格」を掲げていたり、土曜日に自習室を開放し(今は割りと土曜開校しているところが多いが)、OB・OGが学習支援を行っていたりetc、と学校側で独自にそれぞれ工夫をこらして頑張っているところが多かった。当然、こういった学校は昔で言うところの「学区トップ」高が多いので、中学で内申を上げておかないと・・・となるのであるが、実力さえあれば学校の内申がちょっと、といった場合でも、今は受験が可能。成績は良いのに担当科目との先生との相性が悪くて、結果、内申評価が低いといった生徒さんには良い制度である。これは「特別選考」という枠(定員の1割or2割)になるのであるが、入試のみで選抜する方法をとっている学校として、日比谷、戸山、小石川、上野、両国、西、立川、武蔵、町田、国立、新宿、etcといった学校が採用している。この他には、・理工系・薬学系の大学進学を目指す学校・英語とビジネス教育重視のカリキュラムで文系進学を目指す学校・「アニメーションの基礎」が学べる講座がある学校など、各学校の特色が非常にはっきりしていて、もし、『○○の勉強がしたい!』と思っている生徒さんには、目的をもって進学できるようになっていた。もし、お子さんがまだ小学生で、「公立か私立か」で悩まれている方は、一度、都立高の情報を調べると良いですよ。入試内容がちょっと複雑(学校単位で違うので)ではありますが、最近の都立は非常に頑張っていますし、中学も区によっては進学先を選べたりもしますので。
2006/06/02
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 大学生母の日記
- 美濃吉「京の旬彩 丹波若どりの味噌…
- (2025-11-18 10:44:22)
-
-
-

- 小学生ママの日記
- 派遣元責任者講習を受けてきたよ。
- (2025-11-24 23:00:04)
-
-
-
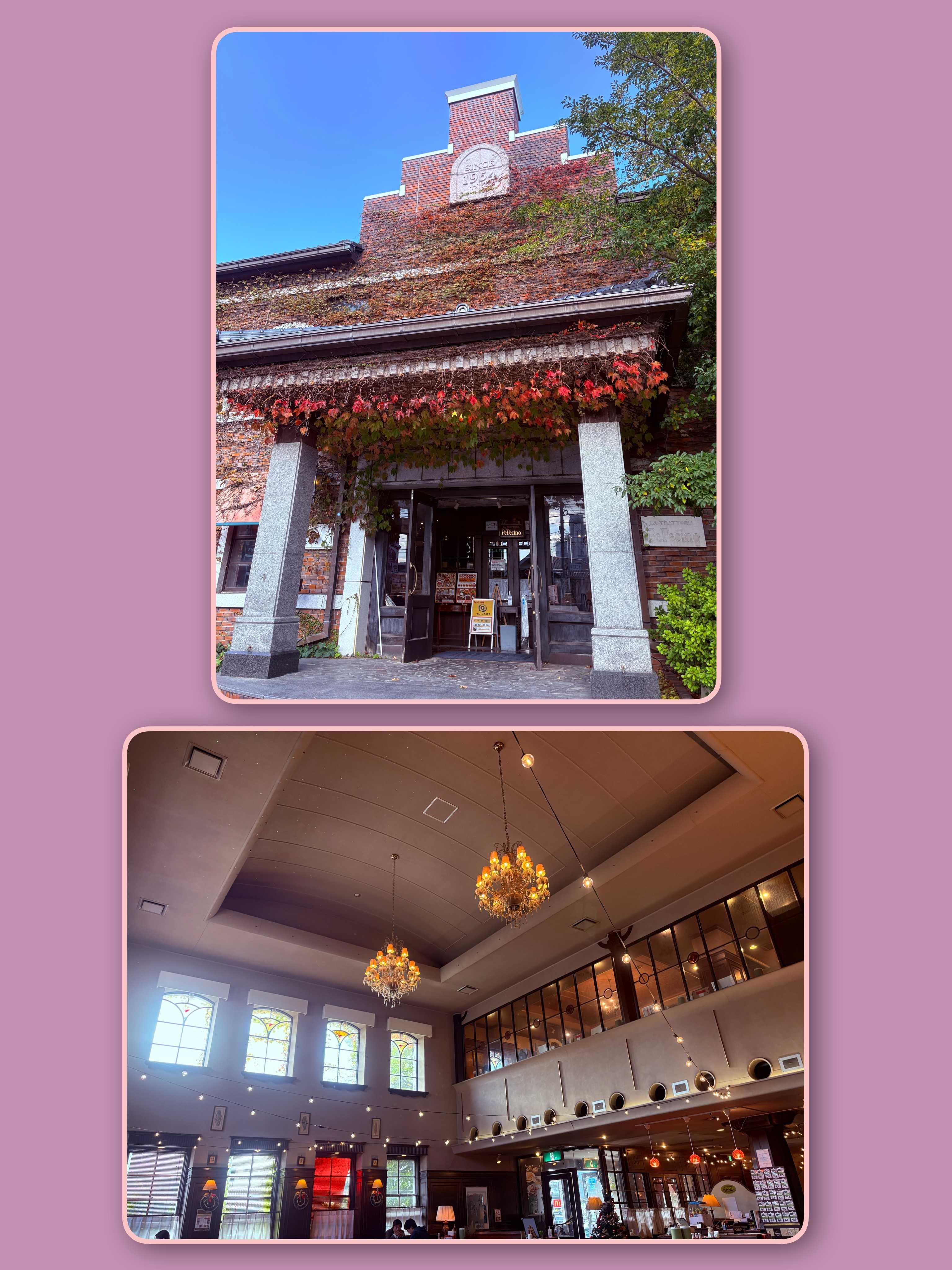
- 高校生ママの日記
- 3連休(ピアノレッスン・夫BD・神社…
- (2025-11-24 23:59:17)
-






