2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年02月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
今、書の良さはどこへ。。。
先日、ハウスメーカーさんやインテリアコーディネータさんが買い付けにいかれるというアートの会社に行ってきました。今、墨を使ったものでどのようなものが出回っているのかを訪ねると想像していた通り、いわゆる書ではなく、墨を使った抽象画的なものとの答えでした。軸ものは人気がなく、フレームまたは、パネル仕上げものをインテリアのスタイルやカラーに合わせて選んでいくそうです。伝統的な書もやってきた私にとっては少し悲しい現状で、私なりにもっとインテリアに取り入れてもらえるよう、また新たな作品を作りたいと思って帰ってきました。
February 28, 2006
-
おもてなしのスリッパとは。。。
お客さまに履いていただくスリッパを買う時にこだわる点が1つ!それは、洗濯可能なものを選ぶようにしていることです。以前は、デザインや質感を優先していましたが、今はコットン素材の洗えるシンプルなものを買い求めています。ネットに入れて洗い、干すときには、内側にチラシをざっくりと包んでスリッパの形が奇麗になるようにつめます。あとは、陰干しにすると、できあがり!お客さまが来られた時にも、自分自身の気持ちも違います。一度、試してみてはいかが?
February 27, 2006
-
中国と日本の違い。。。
また、お気に入りの中国茶のお店『桃花源』に行ってきました。http://www.toukagen.com/店主の方は日本人ですが、奥様は中国出身の奇麗な方です。さっそく、茶葉を試飲させていただき、いつも色々お話を聞かせてもらいます。今日は、中国と日本の書は、名前が伏せてあっても、だいたいどちらの人が書いたのかが、わかるということで意見が一致しました。その理由は、やはり持ち方にあるようです。日本では、筆を鉛筆持ちのような形で柄の真ん中くらいを持ち、少し、角度がついていますが、中国では、紙に垂直になるように、人さし指と薬指はかなり離して持ちます。(文では、わかりにくいですね)かっこいいです。比較すると、より中国の方が直線的なラインと均一な線幅が出てきます。紙を切ったように書くもの中国の持ち方の方が適しているように思えました。また、小学生の時にお手本となる書の古典が違うのも、大人になってからの書体に影響しているようです。その他、中国では、その土地で取れるお茶のみを飲むのが普通で、日本のように色々な銘柄をTPOに合わせて飲む分けるということは少ないとのことでした。文化の違いを知るもの面白いですね。
February 21, 2006
-
21Cのモガ
主人のおばあちゃんは大正生まれ。94歳になっても美容室でセットしてもらい、上品な色合いで素材の良いものを身につけているお洒落なおばあちゃんでした。今年で3回忌になりますが、元気な時は、おじいちゃんとの思い出話やプレゼントしてもらったものを嬉しそうに見せてくれました。本当に女性としても魅力のある人でした。ある時、書家の町春草さんの本を読んでいて、その中にあった『生きた 書いた 恋した』の内容が、あまりにもおばあちゃんにピッタリだったので、その書を背景にしたテーブルコーディネートをしてみようと思いました。生きた(命ある限り、美しく生きる)書いた(自己表現する)恋した(やはり女性はいつまでも恋していたい!)大正生まれのモガ(おばあちゃん)から21Cに生きる『私』が女性としての良さを引き継げたらなぁと思います。現代のスタイリッシュさを表現するシルバーのクロス使い、スプーンやフォークなども洗練されたデザインのものをセットしてみました。八角盆も現代のものですが、大正モダンなデザインです。クッションやランナーも大正時代の古布などをリメイクしています。時代を超えても受け継がれるものを大事にしたいです。
February 21, 2006
-
すべてのことには意味がある。。。
私の好きな言葉です。ある方が物事を説明されるときに言われてた言葉なのですが、それを聞いた瞬間、今まで不消化だったものが、すっと消えていったことを覚えています。意味のないことなんてない。そう考えると、今、自分がしていることや、自分のおかれている環境も大事なんだなと考えるようになりました。また、なにげなく過すのではなく、きちんと物事を見ようと思いました。あと好きな言葉2つ。。。・本物志向(本物には、答えが隠されている)・仲間を大切に(友人に何度も助けられた!)この3つの言葉をOLを辞める時の最後にも話しました。今も、やはりこの言葉が好きかな。。。
February 16, 2006
-
キッチンを安くリフォームするには?
築30年近くのキッチンを安くリフォームしたい!ということで、実行したが、次の通り。。。1)上の棚はそのまま使う(状態が良かったので)2)システムキッチンではなく、単品のキッチン(下部のみ)購入。3)表に厚手のクロス(水場専用)を貼ってもらう。4)仕上げに好きな取っ手を購入し、取り替えると完成!!最初は、ペイントしようと試みましたが、キッチンの油や水をはじく性質の壁面にはうまく塗れず断念。。。リフォームに関わってもらった大工さんの案で、パネルのようなしっかりしたクロスを貼ってもらうことになったのです。ハンズは大きなホームセンターなどに行くと、色んな種類の取ってが売ってて見るだけでも楽しいですよ。1つ注意点は、取っ手のピッチ(間隔)をあらかじめ測っていってくださいね。幅が違うとせっかく買っても付けれないので。。。
February 14, 2006
-
和のセッティングに書を取り入れるには?(2)
昨日の続き。。。さて、実際にランチョンマットを敷いたお盆のコーディネートはこんな感じです。赤とんぼの模様にカットされたオレンジの酒器は石川県のガラス館で買いました。四国にもガラス館はあるようです。食卓のライトが当たると、塗りのお盆にトンボが舞っているように映るのがいいでしょ。(見えないかな?)後ろの書は『好機』(=チャンスの意味)です。学生の頃は、何かと主催できたことも多かったのに、入社してからは上の先輩は切りがないほどいて、本当にチャンスないのかな~なんて思ってた頃の作品です。でもこの書がきっかけでテーブルの世界へ入れたのも不思議です。『念ずれば、花ひらく』というのは、嘘ではないようです。
February 9, 2006
-
和のセッテイングに書を取り入れるには?
先日、東京ドームのテーブルウェア・フェスティバルのトークショウで、洋のテーブルセッティングで一番簡単にイメージ変えるには、カラフルなぺーバーナフキンがお勧めとの話がありました。私は、和食も大好き!以前、私が大阪ドームに和のテーブルを出展したときに、オリジナルランチョンマットをつくりました(写真と同じもの)写真は、11月のサロン風景です。お盆の上にちょうど良い大きさに色画用紙(あずき色)をカットし、アクリル絵の具の白で、秋の詩を散らし書きしています。ポイントは、4人(複数)で順に詠むと1つの詩になるように分けること。また、実際に食事をいただく時に食器やお箸が来る位置をなるべく外して書くことです。サロンに来られた方の中で、後日、そのランチョンマットを使ってお食事会&お茶会を開かれたと伺いました。(お食事会の時は伏せておき、お茶の時に文字が見えるように裏返して驚かせたらしいです。Very Good!)画用紙1枚、絵の具1色あるだけでも、素敵なテーブルになりますよ!
February 8, 2006
-
フォトフレーム『春夏秋冬』
いつも表具をお願いしているT氏とのコラボでこんなフォトフレームを。障子などの枠組みになるところをシルバーに、春夏秋冬に合う言葉1字を書いています。文字も照明の関係でキラキラとシルバーに光ります。春ー霞(春がすみ)夏ー陽(夏の太陽)秋ー月(秋の名月)冬ー星(冬の星空)また、それぞれの1枠には季節に合った和紙を貼って、そこに思い出の写真や小物が貼れます。季節ごとに1枚ずつ飾るのもいいし、広い空間だったら4枚横に高さ違いに飾ってもいいかも。。。ありそうでないフォトフレームでは?
February 6, 2006
-
テーブルウェア・フェスティバル2006に行ってきました!
今年も行われた東京ドームでのテーブルウェア・フェスティバル2006 暮らしを彩る器展に昨日行ってきました。今年もお花を習っている塩貝起志子先生がパンフや有名ブランドのテーブルコーディネートをされるので、見せてもらいに。。。写真は塩貝先生とです。(このテーブルがポスターのメイン写真になりました。3年連続なのは、すごい!)ノリタケの新食器は軽やかなモダンさがあり、お花の演出もとても素敵でした。また、HOYAのクリスタルも迫力があり良かったです。テーブルコーディネートコンテストでは、今年は自然の色(海のブルー、土の茶、植物のグリーン)を取り入れたテーブルが入賞していたように感じました。豪華、モノトーンモダンは姿を消していました。地域の焼き物や漆器も素晴らしいものが多く、特に長崎の器のデザインの良さに感動しました。各ショップの実演の仕方が異なるもの面白く、色んなことに刺激を受けて帰って来た1日でした。
February 5, 2006
-
リビングに合うインテリア書道とは。。。(1)
リビングは、人が集まって、くつろいだり、おしゃべりしたり、楽しむ場所。書が主役ではなく、脇役であるべきだと思います。(主役はもちろん人です。)さて、よく聞くのが『書の作品を創っても飾れない。。。』ということです。そういう方の行程を聞いてみると。。。1)書を書く→ 書に合った仕上げにする→ 飾れる場所を探す→ 飾れない!私の考える行程はこうです。2)インテリアのテーマを決める→ デザイン、言葉を決める→ 書を書く → 決めた仕上げをする→ 飾る写真は、モダンで少し華やかな感じのインテリアに合わせたものです。フレームはつや消しのゴールド2色使いの細めのフレーム、日本画の絵の具で背景柄を書き、『Japan』と言う文字も黒が主張し過ぎないように割り箸で細めに描いています。落款も朱色ではなく、落ち着いたゴールドでトータルコーディネートを。実物は大阪市立美術館 地下展覧会室で見ていただけます。(2月7日~12日、第71回 浪速書道展 随意部に出展予定。)
February 1, 2006
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 今日見た連ドラ。
- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…
- (2022-01-28 23:32:16)
-
-
-
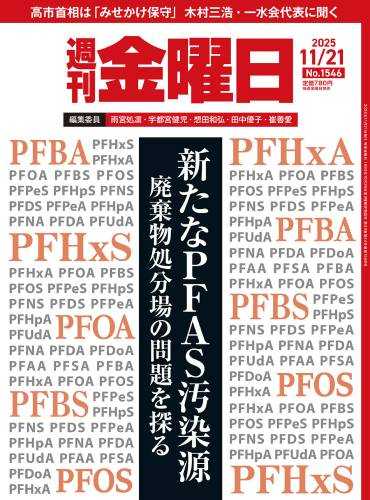
- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…
- 劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとず…
- (2025-11-21 13:22:46)
-








