2011年05月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

黄色のもやもや
昨日はアレイに住む友達の家にお泊まりに行っておりました。アレイ(Alley)とはベイルートから15分(混んでいたら30分)ほどの場所にある地域の名前。高台に位置しているので、ベイルートと比べて涼しくさわやかで、夏はサウジやカタールなどの湾岸族がわんさかと押し寄せる避暑地となっております。アレイには別荘やホテル、貸しアパートが多く、夏の時期にはすべて満室となります。が、冬になるとこうしたアパートなどはことごとく空になり、人口がぐっと減るのがこの地域の特徴。私の友達は別荘としてではなく、年間を通じてこのアレイに住んでいるそれほど多くないアレイ人の一人。といっても、フランス人と日本人のカップルですが(笑)。アレイはベイルートからそれほど遠くないものの、ベイルートとは全く違う風景。緑が生い茂り、花が咲き乱れ、山の間から見下ろす風景はまさに「絵のような」美しさ。その友達の家から撮ったのがこの下の写真。黒で囲んである部分には、実はベイルートが!! ベイルートの向こうには地中海が広がっています。↓ 黒の丸の部分をぐぐっと拡大。ベイルート市がぼんやりと分かりますか?実は首都ベイルートの環境汚染は甚だしく、アレイから見下ろすベイルートは大抵スモッグに覆われているのだそう。2日前に雨が降ったので、今日のスモッグはマシな方で、いつもは黄色のもやもやに覆われているのだそう。そんなベイルートを見下ろしては、2人で「Naokoはあのスモッグの中にいるんだねぇ」と話しているのだそう。そんな環境汚染のベイルートはこの時期からもやもやとした異常な暑さで、夏は息をするのが苦しいほど。夜には海からのクサ~イ臭い(海の近くにゴミ捨て場がある)が漂い、何とも不快。特に6階にはこのニオイが漂いやすいらしく、夜になると漂うこの悪臭にリラックスなんてできません。去年の夏は灼熱のベイルートでカリカリに痩せこけ、散々な思いをしました。今年はアレイに避難してきたら!! と友達は勧めてくれます。そうやな~、黄色いスモッグに覆われたベイルートを見てしまうと、その中に自分が住んでいるのが恐ろしい!! 夏は「脱ベイルート」を図るべきでしょうな。 夏休みはヨルダンへ http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.31
-
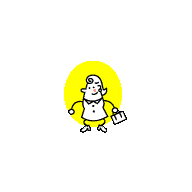
私がアラブと結婚できないわけ
仕事柄というわけでもないのですが、毎日誰かと会っています。毎日毎日毎日誰かと合わなければならないので、一人になる時間を探し求めてしまいます。今日は午前中の予定が急にキャンセルになったので、久しぶりに朝から晩まで一人で家で過ごしました。飛び上るほど嬉しい時間!!! あ~あ、でももう夜になってしもうた。今日は家の掃除をし、洗濯をし、アラビア語の学習をし(し始めたら眠気に襲われ、昼寝をし)、体にいいものを食べてダラリンダラリンと過ごしておりました。そんな私ですから、付き合いが悪くならないようにしながらも、お誘いを断ることも多いです。アラブ世界ですべてのお誘いに応じていたら、身が持ちません。彼らには理解できないようですが、本当に私には一人でゆっくり過ごす時間が必要なんです。アラブ世界では常に人と一緒にいることが求められます。誰かが病気だなんて聞いたら、我先にと訪ねます。病気の人を訪ねないのは「アイーブ」つまり、非常識なんです。私だったら、絶対に放っておいてほしい…実際、風邪で寝込んでいる時に友達が訪ねてきて、居留守を使ったこともあります。パジャマやし、横になってるんやから、わざわざなんで人と会わなあかんの? 会う元気があったら、休んでへんて! と思ってしまう。でも、ここではこんな考え方、理解されもしません。病気の人、退院してきた人、誰かを亡くした人、こうした人たちを集中的に訪ねてダラダラと一緒に時間を過ごすのがアラブ流。実際、ヨルダンにいたときにシリア人の友達からまじめに相談されました。フランス人の友達について。「なぜ Marc は病気の時に誰にも会いたくないっていうんだ? 僕だったら、絶対訪ねてきてほしい。一人にならないように入れ替わり立ち替わり誰かが来てほしい」・・・もうハナシになりません。こんなアラブたちには、私が一人暮らしをしていることも理解不能。一緒に住んだら、と人を紹介されることもあります。誰でもかれでもいいからとにかく人気(ひとけ)が欲しい、一人になりたくない、というアラブなんかと一緒に住んだら自殺行為ですよ。そしてこんなカルチャーを持つアラブなんかと結婚なんてあり得ない!! 頼むから、後生だから、1秒でいいから一人にして~と気が狂い、離婚沙汰になること間違いなし。そんな私の一人っきりの休日はあっという間に終わりまして、明日からまた忙しい日々が始まります。アラブとの付き合いには体力がいるのう… 夏休みはヨルダンへ http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.29
-

レバノン南部の町シドンで起きた爆破事件
シドンで数日過ごして帰ってまいりました。その翌日の今日、シドン付近で爆破事件が起きたというニュースが。あれ~。昨日バスで通ったところやん!! シドンはレバノン南部に位置する海沿いの町です。イスラエルとの国境に近いことと、反欧米・反イスラエル路線を掲げるヒズボラ(政治組織)の活動の拠点であることから、ちょっとしたいざこざが起きやすいといわれている町。とはいえ、通常のシドンは平和そのもので、人懐っこいレバノン人が忙しく行き交う活気のある町。今回の爆破事件は、ベイルートからシドンへ通じる主要道路で起きたもの。平和維持のために駐留しているイタリア兵が乗ったUN(国連)の護送車が爆破され、6名のうち1名が死亡、数名が大けがを負ったようです。 写真はBBCからの転載この爆破事件に誰が関わったかは、まだ分からないということです。犯行声明も出ていないようです。シリアの情勢と何らかの関わりがあるのでは、とも言われていますが、真相は明らかになっていません。爆破事件???!!! レバノン全体が緊急事態と思われるかもしれませんが、そんなことは全くありません。ほとんどのレバノン人はテレビのニュースでこの事件について聞き、「シドンで爆破があったんだって~」「え? そうなん?」と話している状況です。ほとんどのレバノン人は平和を望んでいます。これはヒズボラの人たちも全く同じ。ヒズボラ=過激派組織という風に報道されがちですし、覆面をかぶったテロ組織のようにイメージされる方もおられるかもしれませんが、実はごくごく普通の人々です。靴屋や薬局を営み、英語やフランス語を堪能に話し、「おはよう」「ありがとう」などちょっとした日本語も知っていて、私が日本人と分かるや「日本語知っている!」と披露してくれたりもする人懐っこい人々。ヒズボラについて書きましたが、これはヒズボラが今回の事件に関わっているということではありません。レバノンで何かあればすぐにヒズボラと結び付けられるので、そうではないことを知っていただきたいと思うからです。人々の願いとは裏腹に、なぜかゴタゴタに見舞われる中東です。この時期、美しい花々がレバノンを彩ります。この地に本当の意味での春が訪れるのはいつのことでしょうか。 夏休みはヨルダンへ。http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.28
-

この時期に中東で咲く花
この時期の中東では、きれいなきれいなジャカランダの花があちこちで見られます。この花の特徴は、美しい紫色。花の形は長方形で、ラッパのような形をしています。ぱっと見ると桐の花に似ていますので、キリモドキという別名も付いているのだそうです。が、ジャカランダの木の葉っぱは、桐の木の葉と全然違います。ジャカランダは熱帯に適した木のようで、中東に限らず中南米でも見られます。暑い気候に強いようで、砂、砂、砂のヨルダンのぺトラ遺跡でもきれいに咲いていました。桜と同じように、まず花が咲いて、しばらくしてから緑の葉が生い茂ってきます。ゴツゴツとした木の幹に美しい紫の花がたわわに(?)咲き乱れます。この春の時期はブーゲンビリアもわんさか花をつけますので、ブーゲンビリアの目も覚めるような赤とジャカランダの清涼感のある紫のコントラストがとてもきれいなのです。上の写真は、レバノン南部の町シドンで撮ったもの。首都ベイルートにもジャカランダの木はありますが、古びたビルが連立する街角で居心地悪そうに咲くジャカランダよりも、自然の中で元気いっぱいに咲いているジャカランダのほうがずっときれいです。もうしばらくすると花がパタパタと下に落ちてしまいます。ベイルートのジャカランダはシドンよりも一足先に花が落ち、すでに緑の葉で覆われています。この時期に中東にこられる観光客の皆様は、是非このジャカランダの花も楽しんでくださいね! 夏休みはヨルダンへ http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.26
-

語学習得のコツは「ネイティブ・センス」
先回のブログで、「ネイティブ・センス」とやらについて少し書きました。繰り返しになりますが、ネイティブ・センスとは母国語に対して誰もが持っている感覚 (センス) のことで、母国語を話すときは誰でも感覚的に正しい文法・語順・語彙を選んでいます。 誰もが母国語を完璧に習得していることからして、言語の習得というのは実は何もたいそうなことではないのです。人間の脳の作りから言いますと、誰でも第2、第3言語、さらにはそれ以上を習得できるキャパシティを持っているのです。その証拠に、幼い時 数カ国語に日常的に接していた人は自然にバイリンガル、マルチリンガルになります。別に努力したわけではなく、環境ゆえにそうなります。ほんと、環境って大きいですねぇ~。それで語学学習の時にはネイティブ・センスを養うような学習法を取り入れるのが一番効果的だといえます。では、どうしたらいいのでしょう。赤ちゃんが言語を学ぶときのような環境に身を置くのが一番よいと思います。赤ちゃんは本を開けて勉強したりしません。最初はとにかく聞くだけ。じっと寝かせられていますが、周りでは絶えず誰かの声がし、赤ちゃんに対する働きかけも絶えずあります。また、赤ちゃんに話しかけるのは一人だけではありません。たくさんの人が入れ替わり立ち替わり赤ちゃんを覗き込み、何だか分からないけど抱きあげられたり、頬ずりされたりします。そして、いろんな発音・話し方を聞きます。いつもクリアな発音の人ばかりではありません。歯のないフガフガじいちゃんもいれば、早口の人あり、ゆったりとした話し方の人もあり…。声のトーンも人それぞれ違います。キンキン声を張り上げる人もいれば、穏やかなそよ風のように心地よい声もあります。そのうち、聞いた言葉を真似して言うようになりますが、もちろん初めから正しく発音できるわけではありません。赤ちゃんが声に出すことばに大人が「??」と思ったり、笑いを誘ったりすることもしばしばです。間違いを何度も直されているうちに正しい言葉を習得していきます。つまり言語を学び始める時は、ネイティブの発音を何度も何度も繰り返し聴くことが必要だということです。しかもいろいろな発音や声のトーンに耳を慣れさせることも大切だと思います。それからやはり声に出してみること。相手がいるとなお良いです。相手がいる場合には、すぐにフィードバック (自分の発音や言い方が間違っているか正しいかが相手の反応によって分かること) があるからです。そう考えますと、大人が赤ちゃんと同じような環境で言語を学ぶには、やはり留学が一番よいかと思います。それが難しい場合はCDや映画などをフル活用することができるかもしれません。耳に入るのが自然な会話であればあるほどよいのです。誰もが母国語を完璧に習得していますので、第2言語/第3言語も必ず習得できます!! 大切なのは、ネイティブ・センス養成に重点を置いた学習法!! という私もアラビア語に四苦八苦している身なのでありますが…でも、言語の習得は誰にでもできる! という脳の作りを信じて頑張ってまいります 夏休みはヨルダン散歩。http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.19
-

赤ちゃんみたいに学習してみたら
1か月ほど前に私は晴れて(?)「おばさま」になりました。兄夫婦に赤ちゃんが産まれたのです。 赤ちゃんはすくすくと成長しているようで、最近は目をぱっちり開けて天井をじっと見つめている時間が増えたのだとか。一体何を考えてるんやろねぇ、と母と話しておりました。ほんま、何考えてるんやろ~。ところで、先回・先々回と勝手ながらも語学の学習に関してウンチクを垂れました。語学学習でまず大切なのは、文法うんぬんよりコミュニケーション力と発音だ、ということなんですが… カンのよい方は「え? それって赤ちゃんみたいな学び方?」と気づかれたかもしれません。ここからは私の持論ではなく、実際の学説です。まだ日本にいたときですが、英語教授法といわれる TESOL のコースを受講したことがあります。TESOL とは ″Teaching English to Speakers of Other Languages″ を短くしたもので、英語を母国語としない人に英語を教えるためのテクニックを学ぶコースです。最近では、海外の大学でこのコースを受講する留学生も多いのではないでしょうか。難しいようですが、理論は簡単です。語学はイスに座ってガリガリ勉強するものではない、自然な形で自然な表現を身につけてこそ習得できるものだという理論に基づき、赤ちゃんが言語を吸収するときのように右脳と左脳をフルに活用した教え方を学ぶものです。実際に赤ちゃんは、文法をまず勉強したりしません。最初の1年2年は聞くだけ。ただただ聞きます。そして話し始めます。文法の知識も何もないのですが、聞いたことを真似して口にし始め、簡単な言葉を話し始めます。その後、語学力はグングングンと大人顔負けに上がっていきます。人間の脳が語学を習得する方法としては、赤ちゃんが言語を習得する過程が一番効果的・効率的なのです。そもそも誰もがそうやって母国語を学んできたわけですから、第2言語を学ぶ時も同じ原理が当てはまります。ガリガリと文法を勉強するやり方は、人間の脳の作りに合わないので、最終的には効果的ではありません。これは日本で行われている教育の過程と真っ向から対立するかもしれませんが、だからこそ日本人が英語を話せないという事実は納得がいくことなのです。学習法に問題があるわけですから…。実際にすぐに気づくことですが、ガリガリと机に向かって勉強したきた語学の場合、「生きて」いません。自然な形で語学を勉強していないので、「ネイティブ・センス」が培われていないのです。このネイティブ・センスとは、母国語に対して誰もが持っている感覚のことです。母国語では、誰もが感覚的に正しい文法・語順・語彙を選んでいます。ガリガリ勉強型は、このネイティブ・センスが発達していないので、これまでに遭遇したことがない単語や文章に出くわしたときに応用が利きません。反対に、第2言語に対するネイティブ・センスがある人は、センス(感覚)で乗り切ります。理論では説明できないとしても、自分の中にあるセンス(感覚)が「こうだ!!」ととっさに反応するのです。正しく養われたネイティブ・センスは正しく働きます。実際、母国語ほど文法の説明が難しいのではないでしょうか。これは母国語の場合、「ええと、文法的にはこれが正しくて…」などと考えずに話している、つまり感覚的に語学を習得しているからです。第2言語でも、母国語と同じようなセンス(感覚)が働けばシメたものです。でもネイティブ・センスって言っても…どうやったら身につくの?? ほぼ答えはお分かりかと思いますが、次回はこの話題で行きやしょう。 中東旅行のことなら http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.16
-

コミュニケーション力と発音
先回、「コミュニケーション力」についてのお話を勝手ながらさせていただきました。文法の知識うんぬんより、会話の流れに乗る力、自分を数少ない単語でも表現できる力が「コミュニケーション力」。さてコミュニケーション力に発音は必要か? 私が思うに、発音は絶対に大切です。どの言語を学ぶにしろ、まず入るべきは発音から、だと思います。発音がきれいだったら、その言語のネイティブに「おっ」と思ってもらえる。相手の聞く耳を刺激することができると思います。この点日本の英語教育の現場では、日本人の教師、しかも発音の悪い教師が英語を担当しているケースも多いのではないでしょうか。最近の事情は分かりませんが、少なくとも私が学生の頃は英語の発音にはほとんど重きが置かれていませんでした。かくして、いわゆる「日本人的発音」の英語が出来上がり。発音が悪いと、文法的にいかに正しくてもネイティブには理解されません。それに発音が悪いと、聞く気が殺(そ)がれます。相手を疲れさせてしまう。間違った文法を話すときより、ずっと聞きにくい英語になるのです。海外で日本人の旅行客などが発音の悪い英語を話している現場に遭遇することがあります。この「日本人的英語」を耳にすると、私はタッタカタッタ~、スタコラサッサとその場を逃げ去ります。いやや、まるでコントやで。恥ずかし~い、聞くに堪えない!!コミュニケーション力には、正しい発音が欠かせません。これには、ネイティブの発音をとにかく聞きまくることだと思います。最近では、発音と自然な会話に重きを置いた英語学習本がけっこう売られていると思います。実際にネイティブと接する機会が限られる方は、こうした本をフル活用して何度も何度も聞きまくるとよいと思います。ネイティブの発音を体で覚えるのです。国際化の今、英語は必須ですから、若い人には「相手の聞く耳を刺激する」英語力をぜひとも身につけてほしいと思います。思わず耳を覆いたくなるような発音はもうやめましょうよ~。 中東旅行については http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx まで。 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.14
-
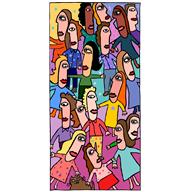
言語力とコミュニケーション力
日本人の中には海外在住の方も多く、海外で活躍されている方も多いことでしょう。それでも一般的に、日本人は第2言語(多くの国では、第2言語は英語になります)を話せないということでよく知られています。 英語教育は学校のカリキュラムにしっかり組み込まれているはずなのに、なぜ日本人は英語が話せないか? これは教育の現場で本当~に何度となく繰り返されてきた議論だと思います。海外で生活して思うのは、日本人は一般的にコミュニケーション力 (りょく) に大いに欠けるのではないかということです。コミュニケーション力 (りょく) とは何ぞや? それは文法をいかによく知っているかということではありません。頭の知識ではないのです。例えばフィリピン人。完璧な英語を話すフィリピン人ももちろんいっぱいいると思いますが、一般的にフィリピン人の英語といえば、「ブロークン」。文法めちゃくちゃ、時制も何もない、しかも簡単な単語を並べているだけ・・・・でも通じている!! 通じさせている!! 英語ネイティブの相手は完全に理解している!対照的に、文法の知識はばっちり!! であるはずの日本人の英語は本当に通じていない…。会話の腰を折り、会話がブチブチ途切れ、相手も聞くことをあきらめてしまう…。この違いはなんでしょう。コミュニケーション力とは、会話の流れに乗ることができ、その場のノリにすっと溶け込み、自分の気持ちを多少なりとも相手に伝えることができる力のことだと思います。文法云々(うんぬん)とはかけ離れた世界です。私自身も若かりし頃、ロンドンに住んでいたときに自分のコミュニケーション力のなさを痛感したことがあります。ネイティブを目の前にすると臆病になって、ごくごく簡単なことも表現できない。英語で楽しく会話なんて夢のまた夢、そんなジレンマに陥っていた時のこと。日本から友達が遊びに来ました。この友達は英語は全くと言っていいほど話せない50代の主婦の方。ところが、臆病で硬くなっている私とは対照的に、あっはっはと笑い、ジェスチャーを交えながら楽しくネイティブと会話しているではありませんか。別に意味ある会話をしているわけではありません。でも、ネイティブと対等に話しています。そんな友達を目の前にして、大切なのはコミュニケーション力なのだと気づかされました。完璧主義は脱ぎ捨てて、コミュニケーションを楽しもう、そんな風に開き直ったのは、それからさらに数年後のことでしたが。開き直りの境地に達してから始めた第3言語はアラビア語。私のアラビア語は文法的にはまだまだ滅茶苦茶。文法は極力あえて勉強しないことにしているからです。でも会話はできます。私の持論は、コミュニケーション力を養うのに文法は障害となる!! というものです。文法の知識が必要でないと言っているわけではありません。文法は絶対に必要!! でも最初に必要なのは「コミュニケーション力」なのではないでしょうか。文法は最初は必要ない? じゃあ発音についてはどうなの?? 発音についても、英語学習者の方から結構質問されます。コミュニケーション力に「発音の良し悪し」は含まれるか? 次回は発音についての私の持論を展開したいと思いま~す。 夏の中東散歩、ヨルダン散歩。http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.14
-

中東にいると受ける珍しいオファー
中東にいると、面白いお問い合わせやオファーを受けることが多いです。まだまだ中東の日本人人口が少ないからでしょう。中東での起業のご相談や土地購入のご相談など、ズブの素人にお問い合わせいただいても…。申し訳ありませんが、お役に立てません、という回答でがっかりされた方も多いことでしょう。ほんまにスミマセン。単に中東に住んでいるだけで、どう頑張っても全くの素人ですから。さてそんな中東生活で、これに勝るオファーはまだ来ておりません。それはまだヨルダンに住んでいた時のこと。ツアーの仕事駆け出しの時で、これで食べていけるかわからない…という頃、並行して就職活動をしておりました。掲載していた履歴書があるサウジの富豪の目に留まったようです。突然電話が。「会いたい、日本人の家庭教師を探している」とのこと。日本人の家庭教師なんて、そんないい話これまでもなかったし、これからも中東ではないであろう、と思いつつ、とりあえず会うことに。アンマン市の Intercontinental Hotel で待ち合わせをいたしました。アラブの白くて長い衣装に身を包んだ、でっぷりと太った浅黒のアラブ男性を想像していましたら、あれ? ほっそり・こじんまりした紳士がこぎれいなスーツに身を包んで待っておりました。サウジのアラブというイメージからは程遠い、ヨーロッパ的な雰囲気も漂う男性でした。しかもお辞儀をして日本語で声をかけられましたので、なおさらびっくり!おっしゃるには、東京で8年ほど勉強していたとのこと(正確な年数は忘れました)。現在はサウジで会社を経営しているのだそう。奥さまはヨルダン人なのですが、離婚し、3人の子供は自分が世話をしているということ。下の子はまだベイビーです。ふむふむ。で、ぜひとも日本人の家庭教師、しかも住み込みの家庭教師を探しているとのこと。自分は日本の文化に非常に感動しており、子供にも日本語と日本の文化を教え込みたい、という強い希望を持っておられました。ベイルートに高級マンションを持っていて、マンションの目の前はビーチ。ロンドンにも家があり、ベイルートとロンドンを行き来する生活になるとのこと。妻ではないけれど、妻のように扱う!! 何でも、何でも好きな物を買ってあげる! お金に糸目はつけない。不自由な思いはさせない。ただ子供と一緒に時間を過ごしてほしい。日本語を教えてほしい。日本のしつけをしてほしい。日本にも行かせてあげる。子供を連れて行ってくれたらいい、などなど…とても親切に熱心にご説明いただきました。結局、その時点で折り合いがつかず(私は通いの家庭教師ならできますと言ったのですが)、この話はなくなりました。が、友達の反応が面白かった。思い込みが時々激しいフランス人の友達(男性)は、すぐに「それは結婚の申し込みだ!! Naoko が気づかないうちに彼の妾(めかけ)になっているはずだ!!!」危険だ、やめろ、やめろ、軟禁されてもう二度と祖国の土を踏めなくなるということが分からないのか、とさんざん言われました。だ、だから、この話はなくなったって言ってるやん…。反対にスペイン人の女友達は「え~、なんて良いオファー!!」好きなもの買ってもらえて、ベイルートの高級マンションで生活? キャーキャーと、無邪気に喜んでおりました。実はこの友達もその時就職活動中で、低賃金・激悪条件のオファーが続いていたので、こうしたオファーにクラリとくる立場だったのです。そして男性と女性では、ここまで差が出るのかという両極端の反応でした。もちろん、どう考えても住み込みの家庭教師なんてできません。私にとって一番大切なのはプライバシーと自由な時間。朝も昼も夜もずっとつきっきりなんて、無理ですよ!!そんな感じで、中東に住んでいると想定外のシチュエーションに出くわすことがあります。とっさの判断が求められることもありますから、浅はかな結論を下さないために、普段からじっくりと物事を考え、周りに振り回されないように自分自身をしっかりと確立することが大事だと感じます。さて、これに勝るオファーが来るか? 受けて立ちますよ~ 中東旅行のことなら何でもご相談ください。http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.09
-

ヤギのチーズにまつわる話
無類の納豆好きです。朝に納豆、昼に納豆、夜に納豆、夜食に納豆を食べても問題なし! というか、食べたい!! 日本からレバノンに帰国する前夜、「最後の夜に何が食べたい?」と母に聞かれ、「納豆と豆腐のお味噌汁と白和え」などとリクエストしまして、母をがっくりさせました。「老人食好み」と家族には言われつつ・・・でも好きなんだから仕方ありません。さて基本的に食事にこだわらない私ですから、中東でも食に関して不自由に感じたことはありません。が、納豆が食べられないことが唯一ご不満。栄養面からしても、納豆は完全食品に近いですね。こんなに優秀な食品を食べられないなんて…(涙)今回の日本一時帰国の時に測った骨密度ですが、思ったより少し悪くなっていました。先生曰く、この2,3年の食生活でぐっと悪くなった可能性がある、と。納豆食べてへんからちゃうん?? またまた先生曰く、「でもこれから意識すれば現状維持できて、問題ない」と。実は私はミルク・プロダクト全般がとても苦手です。つまり、チーズにしろ牛乳にしろヨーグルトにしろ、とにかく苦手。においが嫌だし、独特の酸味もどうも好かん。納豆はカルシウムも豊富に含みますから、ミルク・プロダクトが好きでなくても日本にいた時は問題ありませんでした。が、ここでは納豆が食べられないわけですから、それに代わるものでカルシウムを取り入れねばなりません。いろいろ調べまして、ヤギのミルクは牛のミルクに勝る栄養価があると知りました。ある情報によれば、ヤギのミルクは牛のミルクよりも、カルシウム13%、ビタミンB6 25%、ビタミンA 47%、カリウム134%、ナイアシン350%多く含んでいるそうです。この数字がまったくもって正しいかどうかは賛否両論あると思いますが、いずれにしてもヤギのミルクが牛のミルクに勝る栄養価であることは、どのサイトでも認められています。そうなんか~。苦手なミルク・プロダクトをどうせ食べなアカンのやったら、栄養価の高いヤギ・プロダクトを取り入れて効果的に栄養を吸収しようと計画いたしました。ところがヤギのプロダクトって、臭いんですね!!! 牛にはないさらに独特のニオイがあります。口に入れた瞬間、うえっ。それにいつまでも残るこの野性的な臭み。一体どうしたらいいの~。そこで知恵をまた絞りました。臭みを消してしまう食品と一緒に口に放り込んだらいいのでは...? 登場したのが「ナツメヤシ」です。 ナツメヤシは中東では本当に愛されている果物です。干したナツメヤシはとても甘くて、ねっとりトロリ。砂漠の過酷な条件で育ちますから、栄養価も非常に高い。このこってり甘いナツメヤシと、クサい(が優秀な)ヤギのチーズを同時に口に放り込みます。食べている途中にヤギの臭みが気になったら、さらに1個、2個とナツメヤシを追加。口がはちきれそうになりますが、どうせ一人やし! 毎朝これを続けます。でもこんなに苦しみながらヤギ・プロダクトを食べていると、免疫が下がってかえって体に悪そうやなぁ...と思ってみたり。そんなこんなで2か月が過ぎましたが、だんだんヤギの臭みにも慣れてきました。チーズ1切れに対するナツメヤシの割合が少し少なくなってきたような気がします。ヤギのプロダクトはレバノンでも一般的ではなく、輸入品となり少し割高になります。が、栄養のことを考えると食べないわけにはいかない。現在、ヤギミルクのパウダーを物色中ですが、こちらはまだ見つかりません。海外在住の皆様もそれぞれ工夫されていると思います。美と健康は食品から! 栄養から! 頑張ってまいりましょう。 中東旅行のお問い合わせなら:http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.08
-

シリアのデモ騒動の背後には?
シリアのデモは混迷の度を極めています。戦車投入だとか、無差別発砲だとか…確かに金曜日の礼拝後にデモが起きるようですが、実際のシリアでは国内のほとんどが通常は静まり返っている状態だということです。ニュースだけを聞いているとシリア国内全体が緊急事態という印象を受けることでしょう。が、シリア人の中には政府支持者も多く、反体制派が多数を占めているような報道は誤解を招きます。デモに関しては、当のシリア人が戸惑っているというのが現実かもしれません。実はシリアのデモには、エジプトの民主化デモなどとはまた一味違った怪しげな面も見え隠れします。シリアのアサド大統領は、民衆に向かって演説を行った初めの時から「このデモは外国勢力の工作によるもので、今こそシリア国民の団結と一致が試されている」というようなことを主張しておりました。そんな矢先、アメリカのワシントン・ポスト紙で明らかになった事実があります。それは実際にアメリカがシリアの反体制派を資金援助しているという事実。ブッシュ大統領の時代に始まったこの資金援助、オバマ大統領の代になっても続けられていたとのこと。少なくとも昨年の9月までは。米国務省は2006年から総額6百万ドル(約4億9000万円)規模の資金援助をシリア反体制派にしているということです(記事を一部抜粋)。さて、政治の世界はとことん腐っていて、誰がどんなふうに絡んでいるかは当人と神のみぞ知る世界でしょう。今回のシリアのデモに関しても、どこまでが外国勢力の「工作」で、どこからが民衆の熱き思いか確かなことは分かりません。ただ分かっていることは、反体制派が多額の資金を持ち、一般の民衆にお金を渡して情報工作しデモを拡大しているということです。これは実際に私の友達に起きた経験です。正確に言うと、友達の妹の職場仲間に起きた話。ホムス出身の彼女は、アレッポで教師の仕事をしています。ホムスで大規模なデモが起きたことを知ったある日、家族の安否が心配でバスに乗り、ホムスへ向かっていました。ホムスの手前で、突然バスが止められます。男性の乗客は全て降ろされ、バスには女性だけが残されました。一人の男が乗ってきます。かばんを開けて取り出したのは…マイク。彼女に職業は何か、なぜホムスに向かっているか聞きだします。そして、「アサド大統領に対する不満を何でもいいから話しなさい」と強要しました。「″給料が安い″でもいい、とにかく何でもいい」というのです。彼女が「何もない。何も言いたくない」と拒否すると、この男はマイクのスイッチを切り、「家族のところへ向かっているんだろう? 家族に会いたいだろう? 何も言わなかったら、家族の身の上は保証しないよ」というのです。ショックを受けた彼女は、マイクに向かってアサド大統領を非難する内容のコメントをせざるを得ませんでした。言い終わって泣いていた彼女に、この男は「Good Girl」と言ったということです。情報は明らかに工作されています。純粋な民主化デモと言えるのでしょうか。また反体制派が多額の資金を有していることも明らかです。前にも書いたとおり、シリアの政治事情は特殊で、言論の自由はないし、「圧政」と言うこともできるでしょう。不満を持つ人々がいることは否定できません。そもそも、誰もが満足する政治などというのはあり得ません。また時代の流れには逆らえません。民衆の声がかつてなく強くなっているのは、起こるべくして起きたこと。ただ、反体制派の情報工作や一般民衆の買収について、いったいどこまで報じられているのでしょう。メディアは本当に中立の報道をしているのでしょうか? 「中東の民主化のドミノ現象がシリアにも普及」などとは一言で言えない事情があるのです。シリアのことを本当に知っているジャーナリストでなければ、公平な報道はできないでしょう。この点、日本のメディアも中東から遠くかけ離れているような気がしてなりません。中東旅行のご相談は http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx まで。 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.05
-
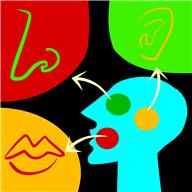
高すぎてもダメ? 大きすぎてもダメ?
アラブの女性、と聞くと皆さまはどんなイメージを持たれるでしょうか? 私のブログでも何度かアラブ女性をテーマにしたことがあります。以前にも触れたとおり、アラブ女性といっても本当に人それぞれ顔も違えば体格も違います。アラブといってもアラブ以外の血が混ざっているケース (つまり、いわゆるハーフやクォーターなど) も多いです。レバノン人女性は一般的にどのアラブよりもきれいだといわれています(出た! レバノン人特有の自負心!!)。これが本当かどうかは疑わしいのですが、一つ確かなことはレバノン人女性はどのアラブ女性よりも beauty concieous (美を意識する、美に関心がある、美志向? などと訳せますでしょうか) であるということです。そんなレバノンで今流行っているのは″美容整形″。何せ外見が全て、若さが全て、という思考ですから、美容整形の流行も当然の成り行きといえるかもしれません。「若くて美しけりゃ、頭は空っぽでもいい」と堂々とのたまうレバノン男性も多いのです。そんな男性を相手に、美しくならねばというプレッシャーは相当のものでしょう。で、ここでの美容整形は、日本とは全く逆のものです。例えば鼻。高すぎるから低くするというケースが多い。高い鼻に憧れる日本人からしたら、もったいない!! と思うかもしれませんが、高い鼻は彼女たちの悩みの種にもなるのです。それから胸。貧弱な胸の人は圧倒的に少なく(というか、ほぼいない)、かなり豊満な人が多いです。大きすぎるから小さくするという手術がほとんど。私なんかからしたら、分けて~という感じですよ(笑)。バストを小さくする手術を受けたという友達の友達は、取り除いた胸の重さが18キロだったということ。ふ~~~~ん。そぉなん。胸だけで18キロなん…2キロくらいやったら欲しいな…こんな風に、高すぎてもダメ、大きすぎてもダメっちゅうわけですね。こうして美の追及には終わりがありません。以前に「キャラメル」というレバノン映画をご紹介しました(http://plaza.rakuten.co.jp/fmtours/diary/200911120000/)。レバノン女性の若さと美に対する熱い思いが可愛く描かれています。映画だから可愛く上品に仕上がっていますが、レバノンに移動して感じるのは、実際のところ女性たちは美の追求にある意味 悪戦苦闘としているのではないかということです。私の顔はレバノン人の美の基準には到底かなっておりませんから、蚊帳の外。美を追求する女性たちを横目に、その胸の大きさに驚いたり、エレファント級のお尻の大きさに圧倒されたり、ギネス級のまつ毛の長さに驚嘆したり…とアラブ世界で新鮮な驚きを体験しています。中東旅行のことなら http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx までどうぞ。 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.04
-

プライドと偏見
レバノンと一言(ひとこと)でいっても、この国に住むのはレバノン人だけではありません。レバノンは多宗教・多人種国家。アルメニア人やクルド人、シリア人など様々な人種が入り乱れて生活しています。観光で来られる日本人のお客様からすればアルメニア人もクルド人もシリア人もレバノン人も見分けがつかないと思います。顔の構造が似ているんですから仕方ないですよね。顔の彫りが深くて、お目めぱっちり、まつ毛がクルン、立派な眉毛に全身を覆うもじゃもじゃの毛…男性を例にとりますと、レバノン人、シリア人、クルド人に関わりなく これが彼らの身体的描写です。が、見慣れてくると、少しずつ違いが分かるようになります。レバノン人は日本人のさらに上 (?) をいっています。日本人と中国人の違いが分からないというのは分かりますが、日本人とインド人・フィリピン人・スリランカ人もみな同じ顔だと主張します。ここまで来ると、「ちょっと、おたくの目に問題あるんちゃうん?」と言いたくもなりますが(笑)。この点、ヨルダン人やシリア人のお目めにはそれほど問題がなく、レバノン人のお目めにとりわけ問題があるようです。そんな風にインド人と日本人との見分けすらつかないレバノン人、特にレバノン人男性にありがちな傾向ですが、レバノン人だということに不必要な誇りを持ち、ともすれば他の民族や人種を見下げる傾向にあります。そんな彼らに「あんた、クルド人?」などと聞くと、顔を真っ赤にして憤慨します。「俺様はレバノン人だ!! なぜそれが分からん? クルド人かなんて聞くな」というわけです。なんたって、俺、俺、俺の世界ですから。人のことはインド人だと決めてかかるくせに、自分が同じこと (というか、それよりずっとレベルの高いこと) をされると憤慨するというのは極めて矛盾しています。が、こうした明らかな矛盾も中東では日常茶飯事。なんたって、俺、俺、俺の世界ですから。ときどき私の中の「イジワル虫」が悪さをし、私はわざと「あんた、クルド人?」「あんた、シリア人?」とレバノン人男性に聞くことがあります。むふっ。どういう対応を相手がするか分かっているんですけど。このイジワル虫がモゾッと動くのは、あまりにも横柄なレバノン人男性に対してだけ。ちょっぴりからかってみたくなるんです。プライドを身にまとってカッコいいと思い込んでいる「裸の王様」には、これくらいの可愛いイジワルしてもいいですよね??レバノン人の持つ「誇り・プライド」が内戦の原因でもあり、経済上の発展を妨げるものであり、レバノンをいまだに第3世界に押しとどめている主な理由でもあります。注) アラブは全体として誇り高き国民と言われますが、レバノン人のそれは他のアラブ諸国をはるかに上回ります。なので、今日のブログの内容は、レバノン人だけに当てはまります。同じアラブでもヨルダンやシリアでは国民性が異なります。小さな小さな国の中で威張り散らしてても、何にもならへんで~。世界は広いんやから。・・・って言っても分からへんやろなぁ。なんせプライドが高いから(笑) ちなみに題名に、有名なジェーン・オースティンの小説名「プライドと偏見」(Pride and Prejedice) を使っていますが、今日の本文とオースティンの素晴らしい名作には何の関係もありません!! オースティン・ファンの方、ごめんなさいね~。 中東旅行のことなら http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx まで。 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.03
-

「正義」とは?
たまたまニュースを見ていましたら、パキスタンに潜伏していたオサマ・ビンラディン氏が米国主導の作戦によって殺害されたというニュースが報道されていました。日本ではこのニュース、どう受け止められているんでしょうか。オバマ大統領は「正義が達成された」という演説を行ったようです。もちろんこれによって、テロ組織が衰退するのは喜ばしいことです。ただし、報復の連鎖が切れるわけではありません。欧米諸国は報復への警戒を強めているとのこと。ビンラディン氏が死んでも、同氏の思いを受け継ぐ次なる人物が現れることでしょう。その人物はビンラディン氏以上に fanatic かもしれません。報復は続きます。ビンラディン氏うんぬんに関係なく、中東諸国での反米感情はかなり高いのです。それには様々な理由があり、反米感情を抱くどの人も「自分たちが正しい」つまり正義だと信じているのです。では、今回アメリカが達成したという「正義」とは一体何でしょうか。そもそも人間が人間を殺すことで本当に「正義が達成」されるのでしょうか。どちらの側も自分たちがしていることを「正義」だと確信しています。「正義」のために戦います。そして沢山の人が死んでいきます。正義とは一体何ぞや? この疑問は続くことでしょう。 中東旅行のことなら何でも http://picturesque-jordan.jp/japanese.aspx まで。 応援してくださる方はクリックしてくださいね。
2011.05.02
全14件 (14件中 1-14件目)
1










