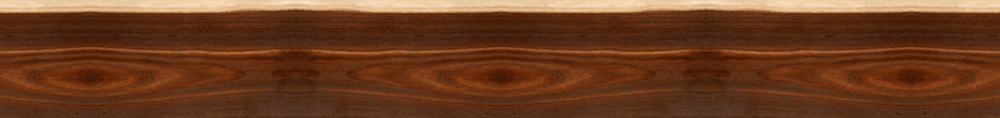2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
消費税引上げ前に購入したい住宅事情
消費税引き上げが徐々に現実的なものになりつつありますが、住宅購入への心理的影響を調査したデータが公開されています。野村不動産アーバンネット(東京都新宿区)は、不動産情報サイト「ノムコム」の会員を対象とした「住宅購入に関する意識調査」を実施。1月27日にその結果が公表されました。不動産情報サイト「ノムコム」住宅購入に関する意識調査(第2回)http://www.nomura-un.co.jp/page/news/pdf/20120127.pdf ■消費税引き上げが「購入計画に影響を受ける」は58%(約6割)、 「できるだけ引き上げ前に購入するようにしたい」と45%が回答。 「予算等の購入計画を見直したい」(35.9%)「購入自体を見送りたい」(16.9%) と続きました。 ■「不動産は買い時」と約半数が回答 不動産については「買い時だと思う」「どちらかと言えば買い時だと思う」を 合わせると 49.7%が「買い時」と回答。 2011 年7月の前回調査と比較して2.1%増加となっています。 一方、「買い時とは思わない」との回答は 19.6%と前回比で 4.1%の減少。 買い時と判断する理由については、前回調査と同様に「住宅ローン金利が 低水準」が 72.8%と最も多く、前回比で 6.0%増。 「今後、消費税が引き上げられる可能性がある」は51.9%と前回比で8.1%の増。 一方、「物件価格が落ち着いている(割安感がある)」は 47.7%と前回比で 3.2% の減少となっています。 なお、買い時だと思わない回答者を対象に「どうなれば買い時になると思うか」 という設問をしたところ、「景気や社会情勢が落ち着いたら」が 52.5%と前回比 と比較して 2.4%の増。 「物件価格が更に安くなったら」が 42.9%と前回比で 4.7%の増加。以上の結果となりました。消費税増税については、もはや規定路線と考えておいたほうが間違いなさそうですが、一方では、1月20日に安住財務大臣が経団連会館の懇談会で発言した「住宅購入は他の消費支出と比べ金額のスケールが異なるため、対応を検討したい」。1月21日に仙台市内で河北新報社のインタビューに応じたときの発言「新たな負担を発生させないくらい思い切った対策を取る」という発言があります。政府・与党でまとめられた「社会保障・税一体改革素案」でも「検討すべき事項」として「住宅の取得」があげられており、その過大な負担と駆け込み需要・その反動減対策については、「緩和化」と「平準化」が求められています。上記の調査は1月13日~18日にノムコムPC会員を対象にインターネットで実施。(有効回答数 2021人)であることから、調査時点では安住大臣の発言は影響しておりませんが、いずれにせよ消費税増税が閣議決定した段階で、駆け込み需要が始まると想定してよさそうです。認定省エネ住宅への税制優遇をはじめ、「断熱材」「窓」「浴槽」を対象としたトップランナー制度の導入(次期通常国会に提出)。そして、国主導による「スマートハウス」への取り組みなど、消費税増税にタイミングをあわせた住宅の省エネ性能向上策の構築とは、つまり、消費税を増税する前にたくさん省エネになる新築・リフォームを勧めていきたいという意図と考えても差し支えなさそうです。(あくまで個人的な見解です)そうなると、家づくり、リフォームにあたり一日も早い計画着手が望ましいのですが、展示場に行ってその場で決めること、言われるがままに土地を購入する、という売り手主導での買い方ではなく、少しでも不安のある方は立ち止まる勇気を持つべき。いくら省エネ住宅になっても、住み心地が悪い家では本末転倒です。住まいの選択肢は、幾とおりもあるのです。もう一度、生涯設計(ライフプラン)を見直し、過剰なリフォームではないか、過剰な新築なのではないか、急ぎながらも要所要所で確認しながら確実な計画を進めていくのが、消費税増税前の家づくり・リフォーム計画の進め方なのです。ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/テクノラティ
2012年01月31日
-
住宅を維持するにはある程度の出費はかかるけど、やっぱりスマートに暮らしたい
マイホームは手に入れてからも、もちろんお金がかかるものです。住宅ローンと税金、保険以外に大きなものは、マイホームを維持するためのメンテナンス費用は想像以上に大きなものがあるのです。その目安とは、どの程度なのでしょうか?一戸建ての場合、持ち主が取得後のメンテナンス計画を立てて実施しなければなりません。その目安金額は10年間で100万円~1,200万円程度。メンテナンスに手を抜いていると後々大がかりな補修が必要になり、修理費がかさんだり、建物の寿命が縮んでしまいます。修繕費を積み立てるにあたってのお薦めは、繰上返済の費用とは別に銀行などに住宅専用の口座をつくって管理すること。毎月、給料から住宅専用の口座に移す際に、ローンの引き落とし額より数千円から1万円程度を余分に口座にいれておくようにするのです。すると、少しづつ余剰金が貯まり無理なく修繕費用を用意することができます。では、その余剰金を無理なく捻出できるおすすめ方法とは?それは、月々の光熱費を下げること。太陽光発電システムや太陽熱給湯システムを導入することで、努力すれば月々の光熱費をいままでの半分近くまで下げることが十分に可能です。なんと、同じようなことを考えている方は、現在では約6世帯に1世帯の割合。住宅金融支援機構が昨年11月に実施した、住宅取得にかかる消費実態調査(平成23年度「新規住宅取得者の耐久消費財購入実態調査」) の結果が公表されています。ここに興味深い結果があらわれています。「太陽熱温水器・太陽光発電システム」の購入世帯比率は10.5%にのぼり、2003年の前回調査時(1.3%)と比べ、約8倍に拡大していることがわかりました。特に新築戸建の方は、約6世帯に1世帯の割合(17.5%)で太陽光発電システムを購入。購入世帯あたりの平均購入額は、太陽光発電システムが177万3100円、太陽熱温水器は26万5100円になったそうです。確かに、太陽光発電システムや太陽熱温水器は、決して安い買い物ではありませんが、発電システムや温水器を導入するコストを何年で回収する、という視点だけではなく、無理なく節電・省エネできる発電システムや設備機器を導入して、節電・省エネに意識した暮らしをしながら、浮かせたお金を将来の住宅メンテナンスにあてる。こんな、スマート(賢い)な暮らし方もあるのです。 ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/テクノラティ
2012年01月24日
-
住みやすさは採光と通風が最大のポイント
国の方向性として、住宅のスマート化や省エネ・節電などの性能向上がクローズアップされていますが、住宅のスマート化や省エネ・節電の効果を大きく左右する要素とは?実は、開口プランと通風の良い間取りです。日当たりのいい家は、それだけで気持ちが良いものですね。日中、光を取り入れるポイントとは、大きな開口。窓が南側にあれば、より多くの光が入ります。ただし、光を多く取り入れようとすると、今度はプライバシーの確保に問題が。大きな開口は魅力的ですが、外からの視線を遮る工夫も必要になってきます。リビングが暗くなりがちで日中でも照明をつけてしまうと、省エネ・節電の点から観て、決してお薦めできることではありません。その場合は吹き抜けにしたり、北向きの暗い場所であれば、天窓や小窓などを多く設けると、日中はかなり明るくなります。中庭や坪庭があると、家の奥まで明るくなりますし、間仕切りをすりガラスにしたり縦長の窓を多く使うことで、光が奥まで届くようになります。暑い夏を快適に過ごすにあたり、もっとも省エネ効果・節電効果が高いのは、通風の確保。確かにエアコンや24時間空調・換気システムによって、室内温度や湿度の管理は精度よくできるようになりましたし、エアコンの省エネ性能も向上したことで10年前の半分程度の消費電力で同じ程度の冷房・暖房能力となっています。また、エアコンの特性として、室内温度や湿度が安定すると時間あたり消費電力は大きく下がります。これも、省エネ・節電には欠かせないこと。よって、室外の温度の影響を受けにくくするための断熱化、ならびに、すきま風をできる限り少なくする気密化は、通風とは別の視点。つまり省エネと節電のためには欠かせないものです。でも、締め切っていた夏の室内が暑いときは、まず窓を全開について自然の風を取り入れ少しでも室内温度を下げたほうが、冷房開始直後のエアコン消費電力を抑えられるほか、朝晩の涼しいときは、むしろ積極的に通風したほうが心地よいことは、みなさま経験していることと思います。新築やリフォームであれば、設計次第でさらに風通しをよくすることができます。住まいのなかに自然の風を通すには、対角線上に窓を設けることが効果的です。特に、南北の対角線上に設けると効果的。また、横に通り抜ける風だけではなく、1階の窓から取り入れた空気を階段や吹き抜けを通して、2階の窓や天窓から抜けるようにする工夫も大切。住まいの気密化・断熱化が進むにつれ、室内の風の流れをおおよそ正確に予測できるようになっています。また24時間換気(2時間に室内空気が入れ替わる)の義務化によって、最低限の換気は確保されています。しかし、『シックハウス症候群』を予防するためにもっとも効果的な方法とは、室内の積極的な換気なのです。決して、締め切った部屋で空気清浄機だけに頼るものではありません。『気密』と『換気』。一見矛盾しているように見えますが、効率よく、狙い通りに換気して、快適に過ごすには、住宅そのものを高性能化して消費エネルギーを確認できるようにする《高気密高断熱》・《スマートハウス》と同じように、《採光》と《通風》も、同じように重要な要素。《高気密高断熱》・《スマートハウス》というコトバが一人歩きしている現在。《採光》と《通風》という、家づくりの基本をないがしろにしてはいけません。ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/テクノラティ
2012年01月17日
-
ゾーニングと動線を考えるときに抑えておきたい4つのポイント
年始から3連休にかけて、住宅展示場や現場見学会へ足を運んで実物を見学された方も多くいらっしゃったかと思います。住宅展示場や現場見学会に行った後、家族で外観イメージやインテリアのイメージを、カタログ片手にいろいろと選んでいきます。次に、敷地の建ぺい率・容積率から家の大きさが定まりますが、敷地や予算などの前提条件から家の大きさがある程度固まっているのであれば、ゾーニングという作業をしてみましょう。ゾーニングとは、家のどのあたりにどの部屋をどの程度の大きさで置くのか、おおよそ決めていく作業です。パソコンで書く方法もありますが、最初は家族総出で「方眼紙」にフリーハンドで書き出すと、あとで家族でモメることも少ないようです。そのゾーニングのポイントですが、まず、最初は大きなくくりで3つの要素を配置してみます。3つの要素とは、リビングやダイニングなど家族が共有するパブリックスペース。寝室や子ども部屋など、家族おのおのが専有するプライベートスペース。そして、水まわりや収納など、その他スペース。それぞれ3分の1づつ配分してみると、きれいにまとまります。意識しなければならない大切なことは、「家は立体である」ということ。最初のうちは、どうしても家を平面とみなして書いてしまいがち。当たり前の話ですが、階段や吹き抜けは1・2階とも同じ位置になります。また、2階の水まわりや子ども部屋は階下への騒音を配慮します。おおよその部屋の配置が決まると、設計担当者が具体的なプランニングに入ります。 ゾーニングと同時に考えるのが、「動線」。動線とは、人の移動経路を線で結んだもので、動線がよくないと人と人がぶつかりやすい、暮らしにくい家になってしまいます。家のなかでの家族の行動や動きを想像してみながら、動線計画とゾーニングを考えてみましょう。□ ゾーニングと動線を考えるときに抑えておきたい4つのポイント 1.主な動線は3種類 家事動線=料理・洗濯・掃除などで動く動線。 生活動線=家族が生活するために動く、通常の動線。 来客動線=来客が動くための動線。 2.動線はなるべく短く 動線は短くするのがポイントです。 家のなかを頻繁に動く家事動線は、一直線の短い動線が理想。 3.動線同士を交わらせないように 住み心地重視であれば、動線が交わることがないようにすることが重要です。 新居でお風呂上がりに来客とバッタリ、という事態は考えたくないですね。 4.動線は複数検討する 動線を回遊型にしたり、目的の部屋に行くための複数の動線を考えておくと 人の動きに柔軟性が。 別の部屋を通らないと目的の部屋にたどり着けない動線は家族のプライバシー を損ねます。 ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/テクノラティ
2012年01月10日
-
住宅展示場や現場見学会に行って住宅会社を絞りこむコツ
あけましておめでとうございます。さて、年末・年始にかけて、住宅展示場や現場見学会へ足を運んで実物を 見学される方も多くいらっしゃったかと思います。 住宅展示場や現場見学会に行った後、実のところ以下のような悩みを抱える方が たくさんいらっしゃいます。 ○住宅展示場を見学したが、想い描いていたイメージ通りの住宅がなかった・・・。 ○すぐに決めてしまっていいものか、なんだか不安・・・。 ○いろいろ見てみたいけど、住宅展示場に行くにも時間も労力もかかるから・・・。そこで、今度の土日から住宅展示場や現場見学会に行って、チェックする住宅会社を絞り込むコツ、ネットでイメージを探すコツなど、この場を借りてご案内しましょう。□ 住宅展示場や現場見学会で住宅会社を絞り込むコツ ■ 住宅展示場の場合 1.見学する会社、棟をあらかじめ決めておきます。 見学は1日あたり3棟までが理想です。 2.見学する目的を絞りましょう。 あらかじめ、家族でどのポイントを重点的に観るか決めておきましょう。 間取り、素材や部材、デザインなどあらかじめ目的を決めておくと、 帰宅後の話し合いもスムーズです。 3.これから開催されるイベントは要チェック。 休日に住宅展示場に行くと、資金計画無料相談・住宅会社の選び方・ 工法の説明・外構(庭づくり)などのセミナーや相談会が開催されています。 このような相談会を活用することで、よりイメージと段取りが明確になります。 ■ 現地見学会の場合 1.質問ができる程度の事前勉強をしておきましょう。 特に基礎や構造の現場を見学する場合は、基礎知識を勉強しておくとスムーズ に質問ができます。 2.施工中の現場では職人さんも観察しましょう。 ゴミが散乱していないか。構造見学会の場合は、道具や機械が作業しやすい 状態になっているか。 施工中の現場では、携わる職人さんたちの仕事ぶりもチェックできます。 3.入居した方の話が直接聞けるOB施主見学会は恰好のチャンスです。 入居後、数年経った家を見学できる『OB施主見学会』『入居後見学会』などを 開催している住宅会社もあります。 実際に住んでみての感想、部材の経年変化、その住宅会社のアフター サービスなど、住んでいる方のホンネが聞ける絶好のチャンス。 住宅会社を選ぶ際、もっとも参考になる見学会のひとつです。 □ 現場見学会に持って行くと良いもの 1.デジタルカメラ 帰宅してから記憶が薄れないので便利。 室内撮影では、一般的にデジカメのほうがケータイで撮影するよりブレにくい 写真が撮れます。 2.巻き尺 スチール製で、できるだけ長いものが良いでしょう。 3.ノート・筆記用具 家づくりの専用ノートを用意して、細かなことでもメモしておきましょう。 4.道路地図 周辺の状況や主要な施設が確認できます。 ケータイやタブレットで観るのではなく、印刷して持って行くと、 その場で気づいたことをすぐにメモできます。 5.方位磁石 部屋の方位が、その場で確認できます。 6.クリアファイル 渡された資料をその場でひとまとめに整理できます。 家に帰ってからの分類が容易になります。 ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/テクノラティ
2012年01月03日
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- ヨックモックXmas🎄ホリデー シーズ…
- (2025-11-25 09:32:56)
-
-
-
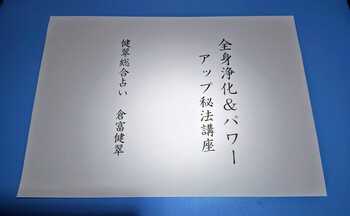
- 運気をアップするには?
- 全身浄化&パワーアップ!が手軽に実…
- (2025-11-24 23:57:10)
-
-
-

- コストコ行こうよ~♪
- コストコでお買い物⭐️
- (2025-11-24 09:21:49)
-