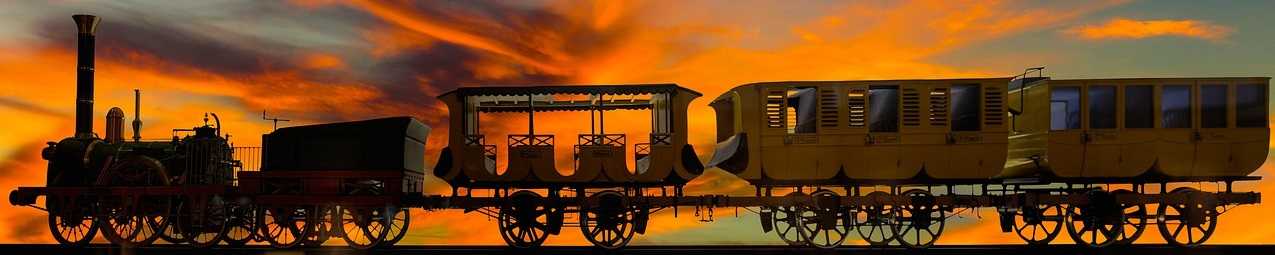2025年09月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その2
にほんブログ村 矢作川橋近傍の推定・高見観音。現地確認で驚いたことがあります。それは「FDG公式さん」撮影のこの写真。(画像提供: FDG公式さん)さすがFDG公式さん、私が観音像背面を見たがるとご存知です。当然、私も背面の撮影を試みようとしました。しかし、この写真をご覧ください。観音像の向こうに見える茶色の箇所は河川敷の道。観音像の背後は崖です。橋脚の水位計から、高さは4~5メートルあるとわかります。私が恐る恐る撮影できたのは次の写真。傘を片手に、濡れた草で足が滑りそうなのもありますが、とてもこれ以上背後には回り込めません。あれはFDG公式さんがアスリートだから撮影できた写真なのです。御覧の皆さんもFDG公式さんの真似はされませんように。さて、頭部には砂利や鉄筋の露出があります。高見彰七作品の特徴があります。現地確認でも私には限界がある。それを再確認した今回の現地確認でした。すみませんが、肝心の見解の修正報告は次回へ順延させて頂きます。【 災害トイレ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.30
コメント(29)
-

【現地確認】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1
にほんブログ村 「FDG公式さん」が発見された矢作川橋近傍の推定・高見観音。現地確認の結果、私の見解の誤りに気づきました。幾つか訂正点が在りますので、現地確認の経緯も含めてご紹介します。私は名古屋鉄道本線 矢作橋駅で下車し、徒歩で現地に向かいました。天気予報が外れ、現地はかなりの雨降り。悪条件での散策となりました。駅から東にしばらく歩きましたが、現地への道にアクセスできません。仕方なく、一旦国道1号線に出て、車道を横断しました。さらに橋の手前で車道沿いに南下すると、目的の小道への入り口に遭遇。入り口には鎖が張られ、徒歩でしか入れません。その道を傘をさして、矢作川沿いに歩きました。しかし観音像は見当たらず、舗装道も終わりました。その奥の鉄橋で土手道も行き止まりのようです。とても不安になりながら、さらに奥に進みました。するとたくさんの花が咲くその奥に、観音像が見えてきました。情報があってもこの難易度。FDG公式さんの新発見にはあらためて驚嘆します。ところでこの場所にたくさん自生しているこの花は「ヤブラン」でしょうか?ご存知の方は教えてください。さて、思っていた以上に綺麗な観音像でした。一目で私の見当違いに気づきました。傘を差しながら、観音像の高さを計ると地面からの高さは65cm。私はこの観音像は高さ120cmクラスと勝手に思い込んでいました。この大きさの認識違いがきっかけで、他の見解の誤りにも気づきました。やはり現地確認は重要ですね。なぜ観音像の寸法が重要で、私がなぜ寸法を計るのか。その理由や、見解の訂正について、次回お話します。【 多機能防災ラジオ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.28
コメント(32)
-

歴史の証人: 成就院の石仏の塔と地蔵尊
にほんブログ村 東京台東区 誓教寺の傍には、成就院という寺院もありました。地下鉄の駅の近くですので、道すがら立ち寄りました。その成就院の境内には珍しいものがありました。石仏を集めて作られた石仏の塔とでも呼ぶべきものです。石仏をピラミッド状に積み重ねた例は、しばしば見かけます。しかし、石仏をセメントで固めた塔を見るのは初めてです。塔には如意輪観音や地蔵が埋め込まれています。これらは江戸時代の石仏ですが、石仏の盗難が相次いだそうです。その対策として、石仏はセメントで固定されました。やや乱暴ですが、苦肉の策の結果です。また成就院には、成就地蔵尊という石仏もありました。やや首を傾けた、やさしいお顔立ちの地蔵菩薩です。しかしよく見ると、首はセメントで補修されています。首はその補修時に傾いたのでしょう。成就院は関東大震災で全焼したそうです。成就地蔵尊もその火災で破損したのかもしれません。盗難という人災、地震という天災。幾たびもの苦難を乗り越え、石仏を守り抜いた成就院。石仏保存の難しさを実感する成就院の歴史でした。【 スイートポテト 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.25
コメント(38)
-

遠い昔の猫の足跡
にほんブログ村 名古屋市科学館で開催されていた特別展「古代DNA」。結局、行きませんでしたが、気になる発掘品の展示がありました。それは「猫の足跡が残された須恵器」です。(画像出典: https://www.takaobakufu.com/2023/09/28/)2007年、兵庫県姫路市の見野古墳群6号墳から発掘された須恵器には猫の足跡が付いています。古墳時代には既に人と猫が共同生活を送っていたことを示す証としてこの須恵器は注目されています。しかし、私はこの須恵器に、別の興味を持っています。それは、「なぜ猫の足跡が付いたのか?」という疑問です。公式見解では、足跡は乾燥中の須恵器を猫が踏んだ跡とされています。しかし、乾燥中の須恵器は粘土の固まり。毛布や布のように、踏み心地が良いものではありません。警戒心の強い猫が、くっきりと足跡が残るほど踏みつけるでしょうか。そもそも踏んだにしては、足跡の向きも不自然です。猫と一緒にお住まいの方、如何思われますか?私は別の理由で足跡が付いたと思っています。見野古墳群6号墳には、石室が2個あります。この2つの石室には、時期がずれて関係の深い被葬者が埋葬されたと考えられます。そのことから、この古墳は「夫婦塚」とも呼ばれています。(画像出典: 見野古墳群保存会H.P.)この古墳の被葬者は、猫を愛した人だったのではないでしょうか。猫の足跡が付いた須恵器は、被葬者への捧げ物だったのではないでしょうか。須恵器の製作者は、自ら猫の手を持ち、須恵器のデザインとして、猫の足跡を付けたのではないかと思います。それは被葬者への、残された家族からの想いだったのかもしれません。そう思うと、猫の足跡がある須恵器から、遠い昔の声が聴こえてきます。「猫を愛した貴方へ。 安心してください。 猫はこれからも、私達が大切に守っていきます。」全ては空想の世界です。猫の足跡の真相はわかりません。ただ、遠い昔の声が聴こえる足跡の世界の方が、よりふさわしい猫と人のあり方だと、私には思えます。【 プレート 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.23
コメント(28)
-

葛飾北斎の墓と北辰信仰
にほんブログ村 東京の宿の近くに誓教寺がありました。誓教寺は浄土宗の寺院です。誓教寺には葛飾北斎の墓があります。墓石には「画狂老人卍墓」と刻まれています。「画狂老人卍」は北斎が75歳から使い始めた、北斎最後の雅号です。刻まれた雅号が見えるでしょうか。「葛飾北斎」の雅号は45歳からの5年間しか使っていません。しかしこの間には「北斎漫画」や「富嶽三十六景」などの代表作が残されました。「北斎胸像」「葛飾北斎」の雅号は、下総国葛飾領(本所割下水,現・墨田区亀沢)で彼が生まれたことから「葛飾」と名乗りました。北斎は日蓮宗信者で、「北辰妙見菩薩」を信仰していました。妙見菩薩は、北辰(北極星)や北斗七星への信仰と菩薩信仰が集合したもの。北斎の雅号は「北斎辰政」の略号で、妙見信仰(北辰 )にちなんだ雅号と言われます。「妙見菩薩」 (画像出典: ウィキペディア)雅号「画狂老人卍」が示す通り、北斎は90歳で大往生するまで、作画活動に没頭しました。臨終に際し、「あと5年生き延びたなら真正の画工となり得たものを」と言い残したと伝わります。まさに芸術家らしい生涯でした。【 葛飾北斎 スマホケース 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.21
コメント(32)
-

東大は観光地?
にほんブログ村 久しぶりに東京大学の本郷地区キャンパスに行きました。東大の他のキャンパスには折々行く機会もありましたが、赤門のある本郷地区キャンパスには久しぶりです。早朝の撮影ですので、人影はあまりありません。何時頃からか、赤門は閉鎖されていました。赤門の耐震強度不足が理由とのことです。歴史のある建築物は、何度見ても良いものです。日中のキャンパスは、海外観光客や一般人の姿も多数見られます。実質、キャンパス立ち入りフリーで、観光地化しています。そのためか、キャンパス内には警備員の姿が目立ちます。写真ではわかりませんが、安田講堂にも警備員がいます。赤門やその他の出入口付近にも警備員。多数の警備員が配置されています。今年の8月には、中国籍の女性が工学部の煙突に登り、落下死亡する事故もありました。この女性は大学とは無関係の部外者でした。大学は開けた場所であるべきとは思います。しかし、これほど多数の警備員を配置してまで、実質入構フリーであるべきでしょうか?本郷地区キャンパスは上野公園の近く。キャンパス内を自由に歩く海外観光客を見ていると、インバウンド対策は見直すべきではないかと思います。【 ジジ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.19
コメント(30)
-

矢作川橋近傍の観音菩薩像 その3(弘化2年の石柱の考察)
にほんブログ村 矢作川橋付近の観音像、続いて「弘化2年の石柱」について考察します。1)石柱は何か?「弘化2年の道標」を検索すると、下記が候補に挙がります。【画像出典】 「足助町 弘化2年の道標」この足助町の道標がある場所は、今回の観音像がある矢作川の上流、その支流の近くです。今回の石柱も弘化2年に同じ街道沿いに建てられたのかもしれません。2)高見彰七と石柱の関連は?コンクリート製ではなく石柱、しかも弘化2年(1845年)となると、高見彰七と石柱の関連はないと思われます。3)観音像と石柱はなぜこの場所にあるのか?発見場所は国道1号線(旧東海道)の近くです。両者は国道1号線沿いにあり、拡張工事などで移設されたと推定します。台座の「交通安全」の文字が、観音像も本来は道路沿いにあったことを示唆します。観音像の周辺には、台座から外れた外れた際の破片がありません。おそらく移設時の観音像の吊り下げで破損したのでしょう。そこで観音像の背面で台座にもたれかけさせた様です。石柱は移設品を一ヶ所に集める意味と、観音像の側方への転倒防止の役目で、この場所に置かれたと思われます。以上が私の推定です。観音像が移設品なのは間違いないと思いますが如何でしょうか?【関連記事1】 「矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1」【関連記事2】 「矢作川橋近傍の観音菩薩像 その2」【 かおなし 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.17
コメント(26)
-

矢作川橋近傍の観音菩薩像 その2(考察)
にほんブログ村 矢作川橋付近で発見された観音像は、表情(目鼻など)や服の装飾など、過去の高見彰七作品にはない特徴があります。それでも今回の観音像を高見観音とする理由。その根拠となる類似点を見ることにしましょう。引き続き画像はFDG公式さんからお借りしています。1)観音像前後の接合部 横から見た観音像は体が異常に折れ曲がっています。 これは観音像の下方後半分が欠損したことを示しているのでしょう。 台座に残された像との接合痕が像よりかなり大きいのも 像下部の欠損を示しています。 注目点は像下部が前後中央で綺麗に割れていること。 これは高見彰七作品の「像を前後で接合」という製法上の 特徴を示していると考えられます。2)観音像背面のモルタルの粗さ 像の後頭部付近では大きな骨材(砂利)が露出しています。 モルタル像でこれほど粗く大きな骨材は通常は使いません。 骨材が表面に露出して、繊細な細工を損なう恐れがあるためです。 高見彰七作品では、像後部には粗い骨材を含むモルタルが しばしば使われます。 これには粗い骨材を配合し、像の強度を高めようとした意図があった と思われます。 「背面のモルタルに粗い骨材を配合している」 今回の観音像にも、この高見彰七作品の特徴があります。3)筆跡の検討 今回の観音像の台座には「南無阿弥陀仏」の文字があります。 (「弥陀仏」の文字は地中にあるため未確認) 作品リンク集3 No.5「釈迦如来像」の台座にも、 「南無阿弥陀仏」の文字がありますので、両者を比較しましょう。 左から、(a)漢字辞典 ON LINE(参考)、 (b)リンク集3 No.5(高見彰七在銘)、(c)今回。 (a) (b) (c) (b)の「南」で「半」となっている誤字は(c)にはありません。 「無」のれんがの4ツ点の向きもやや違います。 その他は類似点もあります。 文字からは高見彰七確率50%程度でしょうか。結果、製作法の類似点から高見彰七作品と判定しました。文字は高見彰七と高見正美の共同製作と考えると納得もできそうです。皆さんは如何思われますか?次回は「弘化2年」の石柱と、この場所に観音像がある理由を考察します。【関連記事】 「矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1」【 英語音声認識ポケットロボット 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.15
コメント(32)
-

【新発見】 矢作川橋近傍の観音菩薩像 その1
にほんブログ村 高見彰七作品候補、新発見の報告がありました。私が遠方に出る所用があり、新発見の掲載が遅れました。発見者は、今回も「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」私は現地未確認ですので、画像はFDG公式さんからお借りしました。観音像は特に発見が困難な場所にありました。矢作川沿いの小道に観音像はあります。少しいつもと違う御顔立ちです。目を開いている点も、印象の違いになっています。鼻の穴まで作っている点も従来とは違います。隣には弘化2年と書かれた石柱があります。観音像は台座から外れてしまっています。台座には「交通安全 南無阿弥陀仏」(推定)の文字があります。謎多き観音像ですが、私は高見彰七作品だと思います。リンク集登録させていただきます。【 リンク集2 (No.35) 観音菩薩像 】 ・所在地: 愛知県岡崎市矢作町 名鉄本線矢作川橋近傍 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・その他: 台座に「交通安全 南無阿弥陀仏」 ・発見者: FDG公式さんこれで確認された高見彰七作品は、117体となりました。消失作品7体や検討中の作品1体もあります。自力では発見は困難な今回の新発見。引き続き情報をお待ちします。私は最近、消失作品にばかり出会っています。特にいつもながら、FDG(フィールド・ティスカバリー・ゲーム)の探索力には驚きます。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。なお、謎多き今回の観音像。その検証の過程は、次回以降の記事でご紹介します。【 ブックマーカー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.13
コメント(30)
-

岐阜駅のステンドグラス
にほんブログ村 以前、何度か名古屋地下鉄の構内にあるモザイク壁画をご紹介しました。モザイク壁画は無機質な駅の構内に彩りを与えてくれます。名古屋に限らず、各地域の駅では構内の装飾にも工夫があります。例えばJR岐阜駅には、大きなステンドグラスがあります。左半分の大きなウと脇の人物の姿から、鵜飼の様子だとわかります。右半分は、岐阜城なのでしょう。各地の駅の装飾も、よく見れば芸術性があるものです。ただ電車ㇸ駆けこむのではなく駅構内を見渡せば、意外な発見があるかもしれません。【 ブルーベリーくりーむチーズ大福 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.06
コメント(60)
-

愛知池の高見観音の管理者・観音寺
にほんブログ村 愛知池にある高見彰七作の観音像。この観音像の管理者は、愛知県東郷町の恵日山清峯院観音寺です。以前にこの観音寺も調査していたのですが、ご紹介できていなかったので、高見彰七との関連で今回掲載します。観音寺は比較的、境内が広く、閑静な寺院です。山門はRC(鉄筋コンクリート)製。鐘楼もRC製。鐘楼に天井画があるのが珍しいと思います。こちらは本堂。地蔵などの石仏もあります。風化していてわかりませんが、馬頭観音でしょうか。観音像はありますが、高見彰七作品ではありません。観音寺の境内に、高見観音は見当たりませんでした。観音寺に高見観音がないということは、愛知池の高見観音は観音寺への奉納ではなかったということかと思います。愛知池の観音像は、所有者の水資源機構への寄贈なのでしょう。愛知池の工事では、工事で命を落とした方もおられます。もともと愛知池には、観音寺の所有地がありました。ただ、愛知池の観音像は、高見彰七が工事の犠牲者の供養のために寄贈したのではないかと思います。【関連記事】 「愛知池の高見観音の詳細」【 おしゃべり猫型ロボット ミーア 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.09.03
コメント(40)
-

スマホ規制条例と二宮尊徳
にほんブログ村 豊田市の鹿島神社。この境内の木陰には、二宮尊徳像があります。近年、二宮尊徳像は撤去され、その数は減りました。その理由のひとつは、姿形が「歩きスマホ」を助長するというものでした。最近話題の愛知県豊明市の「スマホ規制条例案」。スマホなどの使用時間を1日2時間以内とする条例案です。豊明市民全員が対象で、罰則はありません。たしかに長時間のスマホ利用は健康にもよくありません。しかし条例案としては、私には不要に思えます。地方行政では、より重要な審議すべき課題があるでしょう。豊明市では二宮尊徳像も撤去されるのでしょうか?スマホ規制のとばっちりが、二宮尊徳像にも及びませんように。【 二宮尊徳像 】
2025.09.01
コメント(30)
全12件 (12件中 1-12件目)
1