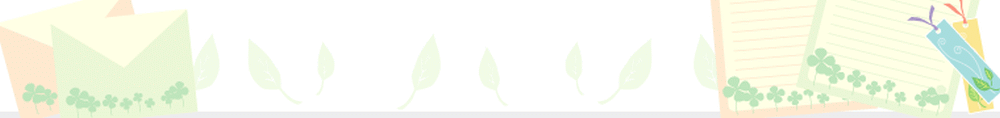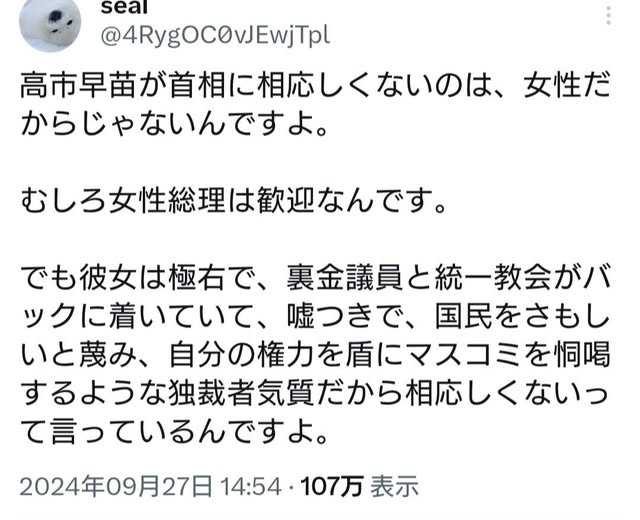2006年08月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
昼下がりの上七軒
外はとてもいい天気で、我が家の窓から東山の大文字もくっきり見えているのですが、さすがに暑くて外を歩き回る元気も出ません。とはいえ、せっかくの日曜日でもあり、運動不足解消のため、ほんの少しだけ近くを散策して過ごしました。国宝建造物である千本釈迦堂を通り抜け、上七軒界隈で少し贅沢なお昼ご飯とお茶をいただき、帰りに北野天満宮に寄るという、ごくごくささやかな休日の楽しみ。「このお天気なら絶対に梅を干しているはず!」という私の予測は的中、境内には梅干の香りが漂っておりました。この梅干は年末にお正月用の大福梅として授与されるものです。
2006年08月20日
-
ブラームス晩年の佳品 作品119第1曲・第2曲
近日中に、標題作を人前で弾く機会があり、先ほど一言コメントを大慌てで作成しました。以下、その原稿です。-*-*-*-*-<第1曲>分散和音中の不協和音の響き、この中に新たな時代の到来を感じさせる何かが潜んでいるような気がします。また、ブラームス晩年の作品よくみられるヘミオラ、こちらも明確に表現できるように努力したいと思っております。短いながらも非常に凝ったつくりになっていて、それでいながら派手さとは無縁の音楽になっているところがいかにもブラームスらしいです。<第2曲>曲想の変化を明確に感じとりながら演奏しなければならない難しい曲です。中間部の美しい旋律は、懐旧の情を想起させるものがありますが、同時に諦念にも似た感情に支配されているところがあって、弾く者の表現力を問われる部分でもあります。
2006年08月19日
-
エリザベート・シュワルツコップの訃報
先日、名ソプラノとして知られたエリザベート・シュワルツコップ女史の訃報が伝えられました。また一人20世紀の偉大な芸術家がこの世を去って行ってしまったという思いを強くしています。正直なところ、シュワルツコップの歌は、あまり好みではありませんでした。上手さはもちろん理解できるのだけれど、でも声質がどうも苦手だと感じていたのです。ですが、訃報に接してみると、やはり亡き人を偲びたくなるもので、先ほどからCDラックから往年の録音を取り出して聴いています。ブラームスの「ドイツ・レクイエム」だの、R=シュトラウスの「四つの最後の歌」だの、「メリー・ウィドウ」だの、「好みではない」などと言いながらも、案外彼女の録音を持っていたことに改めて気づいたのでした。エリザベート・シュワルツコップ、確かに一時代を築いたソプラノ歌手でした。
2006年08月12日
-
『クリスティアン・ツィマーマン ピアノ・リサイタル』放映
昨晩NHK-BS2で放映された標題番組、今朝録画しておいたものを見ながら朝食のひとときを過ごしました。番組では、モーツァルト、ベートーベン、ラヴェル、ガーシュウィンというプログラムでしたが、音色・様式ともにそれぞれの作品の味わいを十二分に表現したすばらしい演奏だったと思います。まだまだ若手だと思っていたツィマーマンも、そろそろ大御所世代にさしかかろうとしているようですね。端正で細部にまで神経が行き届いたスタイルに、余裕と円熟味が加わり、非常に好感度の高い演奏になっていたと思います。多少ピアノを弾く立場の者として、彼の演奏は非常に参考になりますし、何よりも私にとって違和感のない解釈だったのが心地よかったです。
2006年08月12日
-
やはり若い頃に沢山の曲をさらっておくべし
年とともにそれなりの表現力がついてくるものですが、反比例して苦労させられるようになるのが暗譜という作業です。おぼえるのに大層骨が折れるし、しばらく弾かないと見事に忘れてしまう...。年をとるのは悲しいものであります。ところが、不思議なことに、若い頃にさらった曲は、たとえ20年のブランクがあっても、すぐに暗譜できてしまうから不思議です。先日、20年ぶりにショパンのスケルツォを弾いてみた話を書きましたが、本当に数回の練習で暗譜完了、我ながら驚きました。やはり、若い頃に、いろいろな曲にチャレンジしてみるべし、なのでしょうね。表現を深めるのは大人になってからでも十分できることです。逆に、若いうちは、たとえ荒削りであってもいいから、どんどんと難しい曲にチャレンジしておくのが理想的なのではないでしょうか。もっと、いろいろな曲をやっておくのだった、と今頃になって後悔している私でした。
2006年08月06日
-
派手なわりに弾きやすい曲
ピアノ弾きの立場から言わせていただくと、「派手なわりに弾きやすい曲」がある一方で、「聞いた感じよりも数段弾きにくい曲」も存在します。前者の事例としては、例えば多くのショパンのピアノ曲やグリーグのピアノ協奏曲がこれにあたりますし、ブラームスの2つのピアノ協奏曲あたりは明らかに後者に属するものと思われます。映画「ここに泉あり」の感動的な場面で使われていたグリーグのピアノ協奏曲第3楽章あたりは、実は案外譜面も読みやすく、その昔リストが初見で弾き切ったのもむべなるかなという感じがします。
2006年08月06日
全6件 (6件中 1-6件目)
1