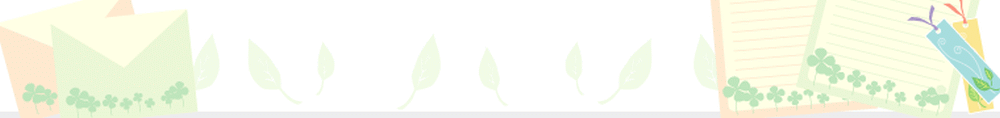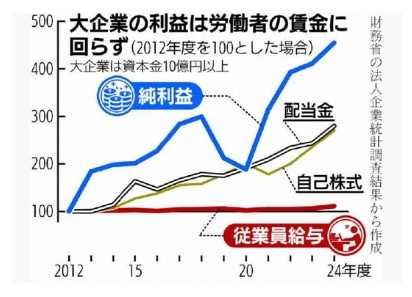2006年11月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
モーツァルト「レクイエム」の思い出
アーノンクールの演奏に触発された私は、久しぶりにモーツァルトの「レクイエム」の譜面を取り出して、ピアノの前に向かいました。弾いているうちに、高校時代この曲を練習していた頃のことをいろいろと思い出しました。その話題を2つほど。(1)伴奏者泣かせ キリエと怒りの日当時の高校合唱部には、ピアノの上手な諸先輩方が沢山いらっしゃったので、私がこの曲の伴奏を正式に担当することはありませんでした。とはいえ、放課後の練習で伴奏者が来なかったりしたときには、その場で誰かが弾かなければならなかったりするわけで、私も何度かピンチヒッターをつとめたことがあります。そんなにわか伴奏担当にとって、「キリエ」と「怒りの日」は、初見で弾くには恐ろしく手強いまさに「伴奏者泣かせ」の難曲でしたね。「キリエ」は細かい指の動きが複雑にからみあった四声の対位法でしたし、「怒りの日」はヴィルトーゾ的運指が要求されるこれまた大変な曲。よく仲間たちと、「バッハやツェルニーでもやっているような気分。毎日練習すると効果的かもね!」と話していたことを思い出します。衝撃の思い出といえば、一学年上だった某先輩のこと。今では世界的な指揮者となられたわけですが(リンクをたどっていけばお分かりでしょうが敢えて伏せておきますね)、この難曲の「キリエ」を、後輩の私たちの前で初見でよどみなく弾いていらっしゃったのでした。(2)某先輩の含蓄の一言某先輩の話題が出てきたところで、高校時代のエピソードを一つ。モーツァルトの「レクイエム」は、確かどこかの文化祭のステージで歌うために練習していたと記憶しておりますが、某先輩が人前(舞台)で指揮棒を振ったほとんど最初の作品だったのではないかと思います。それはさておき。放課後の練習の折だったか、休憩時間だったか、こんなことをおっしゃったのを今でも鮮明におぼえています。「キリエの最後の和音(D-A-D)は、これは長調なんだろうか、短調なんだろうか?」という一言でした。「確かに、どちらともいえるようなニュートラルな響きですよね」と返答したところ、「この曲単体としては、長調の可能性もありうるだろうが、怒りの日との続き具合からすると短調なのかもしれない。他の部分でも、調性の続き具合は考慮されているようだしね。いずれにしても面白い和音だ」というコメントが返ってきました。さすがの一言でしたね。
2006年11月26日
-
再びアーノンクール モーツァルト「レクイエム」
週末の夜中に、アーノンクール/ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスによるモーツァルト「レクイエム」の演奏が放映されました(11月16日・NHKホール収録分)。先日の演奏会の感動さめやらぬうちに、東京公演の模様が放映されたものですから、この週末は、すっかりアーノンクールの音楽の虜になってしまっております。今回の東京公演の演奏ですが、隅々にまで神経が行き届いた緻密な構成と、楽曲の新たな解釈の可能性を提示するものだったと思います。私にとってのモーツァルトの「レクイエム」は、高校の合唱部時代自らも歌い、また数々の録音を聴きこんだなじみの曲、ところが、アーノンクールのような演奏に接すると、よく知ったはずの曲なのに、全く新しいものにでも触れたような驚きがあって、従来自分が抱いていたこの曲に対する既成概念を一旦白紙還元したくなるような衝動にかられるから不思議です。「なるほどそこはそのように表現するのか...確かに理にかなっている気がする...」まさに、この連続でした。
2006年11月26日
-
今年の松磯山荘の紅葉
今年も紅葉の季節がやってまいりました。唯一ご自慢の松磯山荘の実生の紅葉は、今年も見頃を迎えています。年々木々が生い茂ってきて、写真では背後にあるはずの比叡山が完全に隠れてしまっています。松磯山荘の写真をこちらにアップロードしております。
2006年11月25日
-
PDA三台目(三代目?)
数ヶ月前にPHSを手放したとき、同時にPDAの使用を一旦止めたのですが、長年PDAを愛用してきた者にとって、携帯電話だけではどうにも物足りず、結局音声通話機能付&無線LAN内蔵タイプの新しいPDAを買ってしまいました。無線LANエリア内では、高速通信が可能ですし、エリア外でもPHSによる通信が確保されますから、なかなか便利です。目下この高機能なおもちゃに夢中です。もっとも無線LANを常にONにしていると、電池を消耗するようですし(先日半日程度で電池切れに…)、ときどきリセットが必要になることもあったりしますから、使いこなすまでには、しばらく時間が必要かもしれません。この記事も無線LAN経由でPDAを利用して入力したものです。
2006年11月23日
-
アーノンクールのメサイア
11月演奏会の二大目玉のうちのひとつ、アーノンクールのメサイアに出かけてまいりました。アーノンクールは、学生時代から一度生で聴いてみたいと思っていた指揮者の一人でしたが、来日公演の機会に恵まれず(来日はほぼ四半世紀ぶりだそうですね)、ようやく宿願かなった感じです。昨秋には京都賞受賞したというアーノンクール、まさに押しも押されぬ大家の風格が舞台からも伝わってきました。巨匠のオーラがホール空間を支配していた…まさにそんな表現がふさわしいと思います。それにしても、何とすばらしい公演だったことでしょう。合唱もオーケストラもソリストも、巨匠の意図を汲んだ見事な演奏を見せていました。古楽器の音色の幅広さ、合唱のまろやかでとけこむような響き、アルトのソロの自在な表現力、壮大かつ厳粛なオラトリオの世界。最後は感動のあまり涙が出そうになりました。
2006年11月19日
-
庭三題 聖護院・黒谷・天授庵
折角の週末というのにお天気は下り坂、雨が降り出す前にとりあえず散歩に出ることにしました。京都に住んでいて助かるのは、さして目的意識もなくその辺に出かけても、何かしら見てまわることができることでしょうか。来たバスにとりあえず乗って、何となく熊野神社前で降りたところ、聖護院門跡前で秋の非公開文化財特別拝観中であることを知り、早速寄り道をすることにいたしました。聖護院内部の拝観ははじめての経験で、特に御所から移築されたという書院のたたずまいが見事、狩野派の絵画と後水尾天皇の宸筆額が印象的でした。智証大師坐像や胎内におさめられていたという願文等、宝物類も興味深いものが多く、さすがにこの寺院が辿ってきた歴史的変遷の奥深さに驚かされることしきりでした。この聖護院、近世には御所炎上等の影響もあって、たびたび仮御所となることも多かったとのことです。それゆえに書院まわりの庭も、近世期にはおそらく公家風に作られていただろうと推測されるわけですが、書院前庭の作庭については詳しいことは何も伝わっていないのだそうです。お寺の人の話では、度重なる改修で現在の庭の姿はもしかすると当初の形から崩れてしまっているかもしれない、ということでした。聖護院から足を伸ばして、黒谷金戒光明寺にまいりました。慶長年間に再建されたという阿弥陀堂は現在修復中とのことでした(以前に阿弥陀堂前で撮った紅葉の写真はこちらです)。今回は、法然上人八百年遠忌記念で新しく作られたばかりという方丈庭園「紫雲の庭」を鑑賞してまいりました。こちらの庭は、法然の幼少時代(美作国)→修行時代(比叡山延暦寺)→浄土開宗(金戒光明寺興隆)を表現したものだそうで、その明確なストーリー性がいかにも現代的だと感じました。年月を経て、遠い未来の世代の人たちの目には、この庭はどのように映るのでしょうか。聖護院からさらに永観堂前を経て、南禅寺に至る道に歩を進めたわけですが、さすがにこの季節のこの界隈は黒山の人だかり、観光客であふれかえっていました。そんな中、まっしぐらに天授庵へと向かってしまった私でしたが、これにはそれなりのわけがあったのです。以前から、天授庵の紅葉には心ひかれるものがあり、一度中の庭を鑑賞してみたいと思っていたからです(以前に天授庵門前で撮った紅葉の写真はこちらです)。こちらは、書院前庭の林泉と方丈東庭の対比が面白く、特に紅葉する樹木を一列に配した方丈東庭は、まさに今が盛りの錦の美しさでした。上の写真は方丈東庭の紅葉です。本日の散歩の折の写真は、こちらにアップロードしております。よろしければご覧下さい。
2006年11月18日
-
便利な代金引換サービス
仕事を持っていると、せっかく苦労して取った公演類のチケットを泣く泣く手放さなければならないことも結構多いです。大抵は友人知人に声をかけたりすることで何とかなるものですが、どうしても反古にしたくないときには、全く面識のない人にチケットを渡さなければならないような場合もあります。そんな折に便利なのが、郵便局の代金引換サービス。受け取る側も、チケットと代金の同時引換なので安心でしょうが、送る側としても、発送後配達完了までの追跡が可能なこと、送り先に口座番号を教えなくても配達完了後1日程度で郵便局の口座に入金されること等、なかなか便利なシステムだと思います。
2006年11月18日
-
家族の入院 そして 忙中閑あり
家族がアキレス腱を切って急遽入院することになり、今朝から休暇をとって病院との往復を繰り返しておりました。入院の手続き等が終わる頃には、お昼をとうにまわっており、さりとて今さら仕事に行くわけにもいかず、ちょっと時間が出来てしまったのでした。忙中閑ありとはことのこと、少しだけ色づく木々を楽しんでまいりました。車折神社から鹿王院を経て天龍寺付近までをそぞろ歩きしましたが、さすがに天龍寺付近にさしかかると平日でもかなりの人込みなのですね。写真は鹿王院で撮影したものです。また、本日の写真をこちらにアップロードしておりますので、よろしければご覧下さい。
2006年11月13日
-
素晴らしきかな ル・サージュ兄貴とパユ坊や
さて、長い傘を持って出かけた先は、お気に入りアーティスト、エリック・ル・サージュ&エマニュエル・パユの演奏会。彼らの生演奏に接するのは、一昨年の演奏会以来のことです(そのときの記事はこちら)。何が面白いって、ル・サージュ兄貴とパユ坊やの名コンビぶりでしょう。彼らの演奏を一言で表現するなら、多少乱暴かもしれませんが、「兄ちゃんたち、なんだってそんなに上手いんだよぉー、このヤロー、泣けちまったじゃねぇかぁー!」といった感じでしょうか。心憎いことに、自在で華麗なテクニックとともに、絶妙な緩徐楽章ピアニッシモという必殺武器まで突きつけて来るのですから、始末に終えません。今回は、選曲がこれまた渋く、シューベルト、モーツァルト、ウェーバー、ブラームスにアンコールがシューマンという、ドイツ・ロマン派の甘美かつ深遠な世界を見事に体現してくれました。ため息が出るほど美しい旋律の輪郭、多彩で幅広い音色...。そして、何よりも素晴らしいのは、自在でありながら、決して美の法則から逸脱しないこと。兄貴と弟のようなやんちゃコンビから奏でられる音楽は、実は、決して裏切られることのない確かな心地よさに満ちたものなのでした。
2006年11月12日
-
長い傘を持参して後悔する季節
今年も、長い傘を持って出て後悔する季節が到来しました。京都・滋賀在住の人が、大阪・神戸・奈良方面に出かける際には、よくあることなのではないでしょうか。時雨・雨・雪のために自宅を出るときには傘が要る、つい長い傘を使ってしまう、ところが高槻・枚方を通る頃には嘘のような晴天、この長い傘が邪魔で仕方ない…。毎年のことながら、同じ過ちを繰り返している私でした。
2006年11月12日
-
感嘆と不満と
とあるミュージカルの舞台を観に出かけました。抱腹絶倒のコミカルな作品で、主演者たちの絶妙なパフォーマンスに、酔いしれていたわけですが…。残念なことに、主要キャストの中には、「どう考えても芝居も歌も踊りもなっていない!」という方が何人か混じっていて、正直興ざめでした。脚本がいくら面白くても、主演者たちがいくら素晴らしい芸を見せていても、共演者たちのスキルが低レベルでは、結局作品としては台無しになってしまいます。時々こういう興行に出くわすことがありますが、もう少しキャスティング等厳選してもらいたいものだと思ってしまいます。それとも、日本ではまだまだパフォーマー層が厚くないのでしょうか…。
2006年11月11日
-
洛趣会
本日、洛趣会に出かけてまいりました。今年の会場は祇園の歌舞練場ということで、これまた華やいだ雰囲気でよかったです。南禅寺・建仁寺・仁和寺といった具合にお寺で開催されることも多いようですが、歌舞練場も過去に何度か会場になっているのだとか。京の老舗によって構成される洛趣会同人による美しい展示会は、洗練された美意識の結晶とも言うべきもので、他の展示会にはない独特のもの。特に友禅や帯の類は、どれもこれもため息が出るような作品ばかりでした。関係者の方々の和服姿がまた見事で、賑々しくていい感じですね。今日のお茶席は裏千家、その後尾張屋さんの美味なるお蕎麦をいただき、すっかり満足して帰途につきました。
2006年11月04日
全12件 (12件中 1-12件目)
1