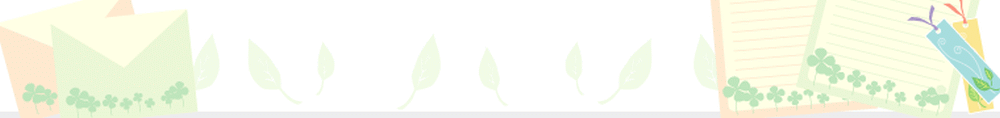2007年04月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
観劇週間第4日 文楽四月公演
お正月に続き、文楽四月公演に出かけてまいりました。文楽に出かけるときは、通し狂言であれみどり狂言であれ、第一部と第二部を続けて鑑賞するようにしております。気がつくと文楽に通い始めて十年以上になりますが、それだけ観客としてのキャリア(?)を積んだからこそできることなのかもしれません。もっとも、終演後は満足感・充実感とともに、かなりの疲労感も味わうものです。疲れているときは、公演中も時々集中力が途切れてしまったり...ということもあります。事実、今回も何度かありました。今回の演目は、文楽の生舞台で接するのははじめてという演目が多く、何か新鮮な発見が出来るのではないかという期待感がありました。以下、上演順に少しずつ。第一部の『玉藻前曦袂』は、玉藻前というからには、謡曲『殺生石』を素材にした作品だろうという予想があったのですが、なるほど『殺生石』を思わせる要素が随所にふんだんに散りばめられており、観ている方としては、そういう要素を発見する楽しさがありました。解説書によれば、近世後期の作であるとのことで、なるほど人形浄瑠璃のスタイルが既に確立されていた時期の作品らしく、作劇上の定石、とりわけ時代物の鉄則を踏まえた凝った作りになっていたと思います。さすがに、鑑賞歴も十年選手になりますと、伏線の段階から「ははーん、どんでん返しはこう来るだろうなぁ」という予想はつくもので、その通りに筋が運ぶと内心なかなか痛快でしたね。続く『心中宵庚申』は、いかにもそのドラマツルギーが近松らしいと感じさせる作品。お正月に続き、ここでも会心の演技を見せたのが勘十郎。この人が演じる世話物の色男には、何というか抗いがたい色気があって、「馬鹿男とはわかっていても、それでも惚れてしまう」のがなぜか納得できてしまいます。そうです、登場人物の女性に共感できてしまうのです。「上田村の段」は、決して大仰に騒ぐことなく、ただ静かに深い情と諦念が表現出来なければ成り立たない難しい演目で、今の住大夫でなければ表現し得なかっただろうと思われます。続く「八百屋の段」における嶋大夫の艶のある声といったら...。第二部は、これまた妖艶な花ますの勘十郎の演技が見ものの『粂仙人吉野花王』。未亡人なのに(?)、いえ未亡人だから(?)こんなにもなまめかしいのでしょうか?最後は、これぞ天下の大物悪役「岩藤」を、これまた憎々しげに演じた十九大夫&富助&玉女トリオの印象が強い『加賀見山旧錦絵』。悪役は悪ければ悪いほど、大物であれば大物であるほど、芝居が楽しくなるというものです。悪役万歳!!!
2007年04月30日
-
観劇週間第3日 座付作者と主演者の不思議な関係(宝塚歌劇星組公演)
観劇週間の第3日目は、宝塚歌劇星組公演『さくら』/『シークレット・ハンター』。宝塚舞踊詩と題された日本物のショーは、明確なメッセージ性を有し、冗長さを排したすっきりとした構成、そして何よりも主演者の持ち味を十二分に引き出す演出が印象に残りました。また、第2部の『シークレット・ハンター』は、コミカルで、ショー的要素も盛り込まれた色彩感あふれる明るい作品、ハッピーエンドなおとぎ話風味ゆえの後味のよさでした。最近疲れ気味で、なかなか評論意欲がわかなかった私ですが、今日は多少元気ですので、座付作者と主演者の不思議な関係について、感じたことを書いてみたいと思います。主演の安蘭けいという人は、歌、芝居、日本舞踊のどの分野をとっても、その豊かな表現力に支えられた総合点の高いパフォーマンスを見せるスターであると思いますが、彼女がいわゆる宝塚の「ステレオタイプの正統派男役」であるかと問われれば、実は「否」と答えざるを得ないような気がしています。男役にしてはあまりにも華奢なその容姿、宝塚の男役にありがちな「スター個人のカリスマ性に役柄を引き寄せて舞台を造形する性向」からはおよそ遠く隔たったアプローチ。彼女は優等生のようでいて、どこか宝塚らしからぬところがあって、それがまた不思議な個性を形成しているように見えるのです。しかし同時に、彼女もまた役者の性として、自らが演じる役柄に独創性を与えずにはいられないわけで、自らの個性をはっきりと自覚し、決して強引ではないけれども、しなやかな強さをもって与えられた役に個性を投影することを忘れない...。しかも、面白いことに、座付作者達は、そういう彼女の個性を知り尽くしていて、結果としてスターシステムを基盤とした宝塚ならではの、主演男役の個性を前面に出した演目構成になってしまっていたところが非常に面白く感じました。今回の『さくら』(作・演出:谷正純)にしても『シークレット・ハンター』(作・演出:児玉明子)にしても、座付作者達の態度は、「はじめに作品ありき」というよりは、明らかに「はじめに安蘭けいありき」からスタートしているように見えました。にもかかわらず、演ずる安蘭けいの側は、座付作者達の意図を十分に自覚しながら、漫然と提供された場に身を委ねることを一旦棚上げにし、スターとしての個存在を白紙還元したうえで、全く異なる性格の二役を一から造形してみせる、しかも彼女のならではの持ち味を十二分に活かして、いかにも「当たり役」であったと観る者に言わせてしまう...。この公演では、こうした座付作者と主演者の実に奇妙な関係が、スリリングでありながらも全く嫌味なくごく自然に共存していて、それがまた不思議な感覚を呼び起こしたのでした。
2007年04月30日
-
観劇週間第2日 演劇空間と字幕(ウィーン版『エリザベート』)
先日、ウィーン版エリザベートの引越公演に出かけてまいりました。テアター・アン・デア・ヴィーン以来二度目のエリザベート(そのときの感想はこちら)、主演も同じ Maya Hakvoort で、座席もこれまたウィーンのときとほぼ同じような場所(前から二列目)での鑑賞でした。オリジナル演出(ハリー・クプファー演出)のままの引越公演ですが、やはり舞台が異なると見える印象がまた微妙に変わってくるものです。小ぶりなオペラハウスであるテアター・アン・デア・ヴィーンのときよりも、大掛かりな舞台装置がより効果的に見えたと思います。そのかわり、ウィーンの劇場で感じる一種の「小屋感」は、多目的大ホールであるがゆえにちょっと薄れていたかもしれませんね。私が観劇した回は、ちょうど Maya Hakvoort さんのエリザベート役通算1千回記念にあたるということで、カーテンコール時に花束やケーキ(エリザベートの扇をかたどった巨大な特製ケーキ!)の贈呈が行われ、観終わった後にも賑やかなお楽しみタイムが続いていました。さて、標題の件につき少しだけ。今回は日本における引越公演ですから、観客用に字幕スーパーが用意されるのは当然のことです。興行の普及促進のためにも、こうした字幕サービスは非常に重要な役割を果たしていると思います。最近では、文楽でも字幕スーパーが出るようになりましたしね。ただ、私個人の感覚では、「字幕の必要性は十分理解しつつも、字幕なしで済ますことができるのであれば、ないにこしたことはない、字幕があるとどうしても違和感を感じてしまう」というのが正直なところです。演劇空間における時間の流れ(台詞や歌が作る独特の時間の流れ)と合わないこと、そして翻訳劇の場合、原語のニュアンスが100%同時に伝えられるわけではないこと、できるだけ字幕を見ないようにしても時々どうしても文字が視界に入ってしまうこと、このあたりが理由でしょうか。文楽鑑賞でもよく経験することですが、字幕が出てしまっているため、客席から笑いが起こったり拍手が起こったりするタイミングが、劇の進行よりも微妙に早くなってしまう現象がしばしば見られます。まだその台詞が語られる前から、舞台上にその部分の字幕が出てしまうと、いくら演じる側が緊張感をもって台詞を口にしていても、すでに観客側がその情報を文字で感知していて、観客がその部分の演技をいわば「待ってしまう」形になってしまうのです。これは、舞台に流れる時間感覚を大いに狂わせることになってしまいます。すなわち、演じる者と観る者の「体験の同時性の阻害」とでも言うべきでしょうか。さらに、翻訳の問題について。『エリザベート』の場合、日本における小池演出で有名になってしまっているため、致し方ないところがあるのも重々承知なのですが、今回の字幕でも「いささかの意訳」が随所に見られ、残念ながら少し違和感を覚えてしまいました。例えば、日本では「闇が広がる」というタイトルで有名になってしまった第二幕のナンバーですが、ここは独語の歌詞を直訳すると、実は「影が次第に長くなっていく」という意味なのですね。独語の「影」という語は、「分身(ドッペルゲンガー)」を想起させる有名なモティーフであり、西洋文学の世界でもしばしば登場する概念です。そもそも、この『エリザベート』という作品の主要なモティーフ自体が、「死=分身」ですから、「影が次第に長くなっていく」というフレーズは、作品の中核をなす要素だといっても過言ではないわけです。この部分で、基本的にルドルフの死がもはや必然となることが予言されているわけですし。もっとも、上演中、この「影」がどんどん長くなっていって12時5分前 - これも日時の境目に対する特殊な時間感覚 - になってしまった狂気じみた状況を説明している時間なんてないわけですから、手っ取り早く観客に感覚的に訴えるには、実は「闇が広がる」方が適切な意訳だったとも言えますが...。いずれにしても、今回「字幕なしですませられるなら、ないにこしたことはない」という思いが強烈に残った公演でした。だとすると、私自身、文楽(近世の主として上方の日本語)や独語オペラはいいとして、他の原語(英・仏・伊語等)はどうしても字幕に頼らなければならないわけで、やはり舞台を楽しむためにも、それなりに語学力を上げる努力が必要だと、今更ながら痛感しているのでありました。
2007年04月30日
-
観劇週間第1日 都をどり - 亡き人を偲びつつ
このところ、仕事が忙しくて普段の睡眠時間も3~4時間、身も心も疲れ果ててはいるのですが、その割にはよく遊んでいるかもしれません。4月に入って、花見に観劇にと、休日もこれまたなかなか忙しい日々を送っています。4月後半は、観劇週間とでも言うべき状況になっております。今日はその第1日目、祇園甲部の都をどりでした。こちらは、実は予定外の出来事で、昨日急に出かけることが決まったのですが...。今日は舞妓さんたちの初々しい芸や、この頃らしい趣向をこらした演出(ゴンドラにドライアイスですから...)を思う存分楽しんでまいりました。彦根屏風の場面も、独創性が感じられて好印象。概して決して層が厚いとは言いがたい芸の分野、若い芸妓さんたちには、これから尚一層の精進に励んでいただきたいものだと感じました。都をどりに出かけるのは、ほとんど20年ぶりでしょうか。その昔、近所に住んでいた祇園甲部関係者の女性と非常に親しくさせていただいた関係で、祇園甲部はもとより、先斗町・上七軒の切符も簡単に手に入ったものでした。ときには、関係者向けのおさらい会を見せていただいたことも - これはこれで出演者全員の緊張が伝わり、とても印象深かったです。花街の風習をいろいろ教えていただいたほか、歌舞伎や演劇・映画も大好きな方で、それこそいろいろと舞台話に花を咲かせたものでした。私の舞台好きは、もしかしたらその方の影響が大きいのかもしれません。大好きだったその方が亡くなられて、もう十数年が経ちます。甲部の歌舞練場へ足を踏み入れると、亡き人の在りし日の姿が懐かしく思い起こされ、感慨深いものがありました。このあと、今月末までの間に、ウィーン版『エリザベート』の引越公演のほか、宝塚星組公演、文楽四月公演を鑑賞する予定です。これから、今朝録画した蜷川演出の『コリオレイナス』も観なければなりませんし、近く京都国立博物館の特別展示も始まります。体力を温存しつつ、毎日を乗り切らなければなりませんね。
2007年04月21日
-
花は気持ちよく楽しみたいもの
遠出をする元気がなかったので、仁和寺と妙心寺退蔵院に花を見に出かけました。仁和寺は今日が本当に見頃だったようです。幸い天気予報がはずれて(!)午後からも青空が広がっていましたので、気持ちのよい休日...になるはずでした。残念だったのは、桜の根元で座り込んで喫煙する人たちを目撃してしまったこと。桜の根はとてもデリケートですから、踏み固めては木が弱ってしまうのです。しかも、今日のように空気が乾燥していて風もあるようなときに煙草とは言語道断。仁和寺のように世界遺産登録された場所には、数々の貴重な文化財があるのですから、火はやはり御法度でしょう。花はやはり気持ちよく楽しみたいものですね。お小言はこの程度にすることにして。本日の写真をこちらにアップロードしておきましたので、よろしければご覧下さい。
2007年04月15日
-
大人気上賀茂神社
先日、松磯山荘に行った帰り道、ちょっと寄り道のつもりで上賀茂神社の前まで出かけたのですが、例年以上の恐ろしい人出にびっくり仰天、境内に入らずにそのまま帰宅してしまいました。後日、この恐ろしい人出の理由が、ローカル番組によって明らかにされました。それは、JR東海のCMの効果だったのですね。先ほどHPでその幻想的で美しい映像を見て、ようやく納得しました。何でも、いつもの10倍の参拝者なのだとか...。JR東海のこのCM、地元民には見る機会がないですものね...いやはや全く...。
2007年04月15日
-
落花に酔う
仕事の関係で桜の季節の休日はわずかに本日一日。なればこそ、はらはらと散る桜のもとで憩いたいと思い、朝は松磯山荘の自分の桜を愛で、午後からは京都御所周辺を散策し、落花の雪に踏み迷うひとときを過ごしました。本日の写真は、こちらで公開しております。
2007年04月08日
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ^-^◆ 浪花節(浪曲)の修行<少年時の…
- (2025-11-25 05:00:06)
-
-
-

- 楽天写真館
- 25 日 ( Tuesday ) の日記 体調…
- (2025-11-25 04:00:04)
-
-
-
- ひとり言・・?
- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…
- (2025-11-22 22:12:52)
-