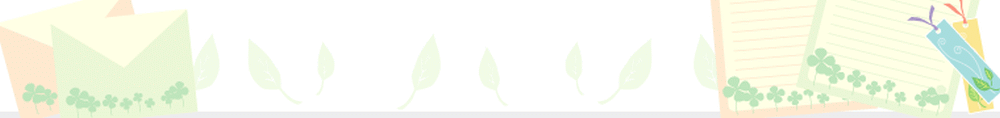2008年05月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐる旅(3)
【唐津】充実感いっぱいではありましたが、とにかく先を急いだため、慌ただしく太宰府を後にして、向かった先は、眺望と唐津焼で知られる城下町唐津でした。唐津に行くことにしたのは、以前何度か出張で福岡へ行った折、唐津へのアクセスが案外簡単であることを知ったからだったのです。地下鉄空港線からそのままJR筑肥線へと続くこの路線、地上を走るようになってからというもの、車窓からは博多湾に能古島、唐津湾に虹の松原と次々と美しい風景が続き、お天気にも恵まれて本当に目で楽しむ旅になりました。夕方4時頃に唐津駅にたどりつきましたが、最終の市内循環バスが5時過ぎであることを知り、これに乗らないと宿のある東唐津に行くのが大変になりそうでしたので、唐津城下を大汗をかきながらまるで競歩のような足取りで歩きまわりました。とはいえ、さして広い城下町でもありませんでしたから、市内循環バスまでの間に、唐津くんちの曳山展示場をはじめ、唐津神社・埋門ノ館・時の太鼓・旧唐津銀行本店・西の浜をチェックする時間はなんとか確保できました。宿へ入ってからも、松浦橋から唐津城を眺めたり(もれなく火力発電所も見えてしまうことには苦笑を禁じえなかったですが)、高島を望む浜辺で貝殻を拾って遊んだりする時間は十分ありました。文政年間以降唐津神社の氏子たちが奉納したという、漆の一閑張で作られた色鮮やかな14台の曳山は、豪壮華麗でありながら、どれもどこかユーモラスな表情が可愛らしかったです。鯛の目も獅子の目も、まるでアニメキャラクターのような親しみやすさにあふれ、心和むものがあります。翌朝、虹の松原を少しだけ散策した後、藤の見事な唐津城へ。唐津城からの眺望は、東西南北どちらもなかなかのもので、特に玄界灘にぽっかり浮かぶ島々が本当に美しかったです。宝当神社があるという高島に渡ることも考えましたが、定期船の便数が案外少なく、旅程の関係もあって今回は天守閣からの眺めを楽しむだけに終わってしまいました。【福岡】出張等で何度かこの町に来る機会があったのですが、観光となると櫛田神社や旧日本生命九州支店(昨年夏の記事はこちら)にちらっと寄った程度で、いわゆる筑前黒田52万石の威容について触れたのは今回がはじめてのことでした。今までの出張では、那珂川の東側にある港湾商業都市「博多」のイメージが強かったですが、巨大な大堀(現在の大濠公園)に、福岡城址のあまりに巨大な城郭に驚いた(むしろ「驚き呆れた」)というのが正直なところです。近代に入って陸軍第12師団が置かれたり、国民体育大会による運動施設が設置されたりと、いろいろな時代を経てきたようですが、ようやくこの史跡が史跡らしく認知されるようになってきたのでしょう、筑紫の鴻臚館跡(平和台球場のあったところ)では着々と発掘が進んでいるようでした。この鴻臚館ですが、他の平安京や難波についてはあまり詳しいことが分かっていないようですし、唯一遺構がはっきりと遺されている史跡なのですから、今後の発掘の成果に大いに期待したいところです。
2008年05月05日
-
下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐる旅(2)
【太宰府】下関を後にした私は、夜博多の町に入り一泊、翌朝ラッシュ・アワーの勤め人達を尻目に(そんな私は有給休暇中!)、念願の太宰府詣でに出かけました。お正月に道明寺天満宮に参拝したわけですが、結局太宰府よりも道明寺詣でが先になったことは、先日ここで書いた通りです(そのときの記事はこちら)。菅原伝授手習鑑でおなじみの天拝山の位置関係も確認でき、すっかり心は菅公伝説の世界に浸りきっておりました。西鉄太宰府駅から天満宮に至る参道は、梅が枝餅を食べさせるお土産屋さんが軒をつらねていて、北野よりも道明寺よりもさらに賑やかな門前と感じました。心字池に架かる太鼓橋・平橋・太鼓橋がこれまた見事で、まだ参拝客の少ない朝の境内でひたすらシャッターを切り続けていた私でした。小早川隆景が造営したという本殿も、北野同様(こちらは豊臣秀頼造営)桃山様式ですが、見慣れた北野の社殿とはまた異なる豪壮華麗な建築がひときわ印象的でした。山に抱かれた緑の多い地域、歩きながら一瞬大和の山の辺の道に入り込んだのかという錯覚にとらわれることもありました。太宰府は、確かに大和の佇まいとどこか通じるものがあるような気がします。特に、観世音寺・戒壇院・太宰府政庁跡の周囲は、古代の息吹に満ち満ちていて、この地に大宰府が置かれたのも頷けると思うことしきりでした。天智天皇の発願によるという観世音寺、東大寺・下野の薬師寺とともに知られている戒壇院、いずれも静寂のなかにときを超えてそこに立つ歴史の重みがあり、はるばるここまで足をのばしてよかったと何度思ったことでしょう。写真は、戒壇院の門前です。我ながら、いかにも春らしい光景が撮れたと思う1枚です。他の写真は、以下にアップロードしています。 ↓http://www.photohighway.co.jp/AlbumTop.asp?key=1861803&un=58318&m=0あと、旅の復習にもってこいのページを見つけました。九州国立博物館(今回こちらに寄る時間はありませんでしたが…)による太宰府紹介のページです。http://www.kyuhaku-db.jp/dazaifu/historic/index.html
2008年05月04日
-
下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐる旅(1)
大型連休も後半に入り、気温もぐんぐん上昇してまいりました。連休前半、2泊3日で下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐってまいりました。今日あたり、博多どんたくで福岡あたりは恐ろしい人出でしょうが、連休前半はさしたる人ごみにも巻き込まれることもなく、ゆったりとした気分で、しかし(捻挫した足首にも頓着せず)旺盛に、ひたすら歩きまわってまいりました。写真を20枚ほどピックアップして、こちらにアップロードいたしましたので、よろしければご覧下さい。http://www.photohighway.co.jp/AlbumTop.asp?key=1861803&un=58318&m=0【下関・門司】まずは、さまざまな表情を持つ下関へ。朝一番落ち着いた佇まいの城下町長府へ寄りました。これほど情緒と清潔感あふれた城下町はなかなかないと思います。長府藩侍屋敷長屋・忌宮神社・菅家長屋門・古江小路・長府毛利邸・功山寺を歩いてひとまわり。人通りもまばらで、どこも訪れる人も少なく、「人だらけの京都から逃れて正解」と実感できたひとときでした。功山寺山門前では美しい新緑の写真を撮ることができてすっかり満足。また、最古の禅寺様式を持つという国宝の功山寺仏殿は、造りがとても面白かったのですが、近くに送電線があったりして、なかなか思うような撮影ができなかったのが少し残念でした。そういえば、世界遺産登録されている宇治上神社も、社殿のすぐ傍に送電鉄塔が立っていますが、文化財と社会インフラ、どちらが大切と一概には言い切れないだけに、複雑なものがありますね。次に訪れたのは、唐戸地区。途中たまたま乗った路線バスが、かつてロンドン市内を走っていたというあの赤い2階建てバス。旧下関英国領事館内では、ロンドンバス路線化記念ということで、英国政府発行の観光ガイドブックが配布されていましたので、そちらもちゃっかりいただいてまいりました(重かったですが…)。向いの唐戸市場だけは、新鮮な海産物めあての家族連れも多く、人また人の賑わい。しかし、人だらけの京都で「百戦錬磨」の私には、その程度の人ごみに物怖じなどいたしません。しっかり美味しいものをたらふくいただきました。唐戸市場の人ごみにひきかえ、日清講和記念館、旧秋田商会ビルあたりは、訪れる人も案外少なく、静かそのもの。落ち着いて史跡めぐりをすることができました。中でも、個人的に興味深かったのは、李鴻章道と赤間神宮内にあった能登守教経の墓所でしょうか。海岸沿いの国道を歩くのは、車の音もうるさく日差しも厳しいと感じたことから、丘沿いのコースを歩いていたところ、偶然見つけてしまったのが李鴻章道。日清戦争の講和条約の清国全権大使であった李鴻章が、危難を避けるために通ったとされるこの道は、徒歩の旅だからこそ見つけられた細い細い小径でした。壇之浦古戦場には、八艘飛びの源義経像とともに、碇をかついだ平知盛像が置かれていますが、赤間神宮の平家一門の墓所の中央に一際大きな墓石で祀られているのは、「見るべきことは見はてつ」と言い残して果てた新中納言知盛ではなく、安芸兄弟を左右の脇にはさんで「おのれら死出の山の供せよ」と入水した猛将能登守教経でした。子供の頃親しんだ平家物語の中で、敦盛最期とともに鮮やかな印象となって残っている能登殿最期のくだりを、しばし思い出しました。義経・知盛像と長州砲展示のある御裳川は、関ヶ原同様歴史上重ねて戦場になった場所のようですが、今は関門トンネル人道の下関側出入口になっているとのこと。ここから、歩いて関門海峡を渡り門司へ入りました。和布刈神社・門司関址・平家一杯水を経て、門司港レトロ地区へとひたすら強烈な日差しの下歩き続けたのでした。門司関は、海峡を往来する人や船を監視したり太宰府と都とを行き来する役人の世話をする拠点だったようで、恐ろしく古い史跡なのにもかかわらず、あまり宣伝もされているようでもなく、その辺の児童公園内にあっけらかんと石碑だけが残されているのが、やや妙な感じでした。むしろ、門司=バナナの叩き売り発祥の地ということなのでしょうか(笑)。旧門司税関・旧門司三井倶楽部・旧大阪商船といった洋館群も、現在では門司港駅以外すべて用途を変え、若者向けのおしゃれなスポットになっているようでしたが、賑やかさの中に、どこか時代の移り変わりを感じ、一抹の寂しさを感じた瞬間でした。門司港桟橋から船で再度唐戸へ渡る頃には、すっかり夕刻となっていました。平家物語に早鞆とうたわれた潮の流れも、頻繁に行き来するタンカー類も何のその、門司⇔唐戸定期船の舵をとるのは、威勢のよさそうなお嬢さん達。時間切れで、満珠・干珠も巌流島も陸からちらっと見るだけに終わりましたが、素晴らしい景観の中に歴史の息吹を感じさせるこの地域は、汲めども尽きぬ魅力にあふれていると思いました。
2008年05月03日
全3件 (3件中 1-3件目)
1