2007年02月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

数がわからない!?
英語を習いたての中学生時代から今に至るまで、私がずっと苦手にしているのが、数字です。英語で数字をすらすら言ったり聞いたりするのって、難しくありませんか?インドに来たばかりの頃は、まず電話番号で苦労しました。聞き取れないのです。いえ、聞こえてはいるのですが、英語のまま記憶できないのです。相手が自分の番号を「ナイン・エイト・・・・・」なんて言い始めると、私の頭の中はパニック状態。「ちょっと待った!」と慌てて紙とペンを取り出します。次に困ったのは買い物の時です。日本の学校で学んだ私は、たとえば850ルピーという価格の読みは、エイト・ハンドレッド・フィフティ・ルピーだという固定観念に縛られているわけです。ところが、こちらの人はこれを簡単に、エイト・フィフティと言います。今でこそこの言い方には慣れましたが、なんど恥をかいたことか。さらに複雑さを増すのが、インド独特の単位の存在です。thousand(千)で少し怪しくなり、million(100万) billion(10億)では完全にお手上げ状態の私。それなのに、lakh(ラク)とcrore(クロー)という、全く未知の単位が、日常会話やテレビ・新聞に頻繁に登場するのです。Wikipedia(ウィキぺディア)で調べたところ、lakhは10万、croreは1千万を意味しているそうです。インドを始め、バングラディシュ、モルジブ、パキスタン、スリランカで使われているとか。数字を聞き間違えると、生活において大きな支障が出るので、固い頭を柔らかくするべく、日々努力するマダムでした (T_T)
2007.02.27
-

NewもあればOldもあります
私が住んでいる所は、インドのニューデリーです。英語で書くと、New Delhi意味はそのものずばり「新しいデリー」。新しいのがあるのなら古いのもあるだろうと、みなさんお思いになりますよね。あるんです、オールドデリーが。かつて北インドは、ムガール王朝などのイスラム勢力に支配されていました。その時代に築かれた城砦や街がある所が、オールドデリーです。その後、インドはイギリス統治時代を迎えます。イギリスによって、1911年からオールドデリーの南側に新しい街が造られ始め、整然とした計画都市が出来上がります。それがニューデリーです。2月14日にご紹介したインド門はニューデリーにあります。ニューデリーとオールドデリーとの境にあるのがこちらです。Delhi Gate (デリー門)昔のオールドデリーは城壁に取り囲まれていましたが、今ではほんの一部が残るのみで、この門もその名残だそうです。街の様子は、古色蒼然という表現をはるかに超えていますね。今にも崩れ落ちそうな建物がひしめいていて、どこからわいて出てきたのかと思うような大勢の人々が通りを埋め尽くしています。オールドデリー駅駅前の混沌ぶりには、ただ目を丸くするしかありません。人・車・サイクルリキシャ・荷馬車・牛車が、おすなおすなの大騒ぎ! オールドデリー及びニューデリーの一部で自転車タイプのリキシャ(簡易タクシー)は、オールドデリー内のみ走行が許されているそうです。欧米系の観光客が嬉しそうに乗っている姿を目撃しました。車から降りて駅舎の写真を撮りたかったのですが、荷車にひかれたら怖いので、諦めざるをえませんでした。普段私が生活しているニューデリーと、オールドデリーでは、同じインドとは思えないほど全く雰囲気が違います。でも、オールドデリーでは、インド人のもつ計り知れない生命力というか生活力というか、ものすごいエネルギーを感じました。恐るべし、インド・パワー! (2月26日 一部修正)
2007.02.26
-

へび使いはどこに?
今日はへびの話題です。苦手な方はスルーしてくださいね。インドに住むことが決まった時、真っ先に頭に浮かんだこと。それは、へび ~>゜)~~~が、街のいたる所に出没するのではないか、という心配でした。基本的に、細長いうねうねした生き物が苦手な私。テレビを見ていて、へびの姿がちらっとでも映ろうものなら、悲鳴を上げるほど大嫌いなんです。そんな私が子供の頃から抱いていたインドに対するイメージは、カレー、ターバン、そしてへびの国。頭にターバンを巻いたへび使いが縦長の笛を吹き鳴らすと、恐ろしいコブラが籠からゆらゆらと顔を出す、あれです。ニューデリーはとっても緑豊かな街で、樹木が生い茂った森のような場所がいくつも点在しています。さすがにコブラはいなくても、他の種類のへびが生息しているとしか思えないんですよね。ですから、ここに到着してから何人ものインド人に訊きまくりました。「ニューデリーにはへびがいますか?」すると、訊かれたインド人は一様に目を丸くし、「ノー!」と答えるのです。私の質問が飛んだ的外れといわんばかりの反応です。でも、言われてみれば、猿使い、熊使い、象使いの姿はたまに見かけますが、へび使いの姿は全くありません。へび使いの本家本元のこの国に、なぜいないのでしょう?そんなはずはありません。「見なくてすんでラッキー」なはずの私が、へび使いの姿を捜し求めることになったわけです。そうしたら、捜すまでもありませんでした。ドライバーに尋ねたら、名所旧跡の近くに出没するとのこと。な~んだ、そんな簡単なことだったのね。インドに到着してからしばらくは、暑くて観光どころではなかったので、だからへび使いの姿を見ることがなかったことがわかりました。さっそくカメラ片手に出かけました。大勢の観光客が出入りする門のわきで、寂しげにしゃがみこむ一人のおじさん。足元には曰くありげな籠があります。私と目が合ったおじさんが嬉しそうに手招きするので、近寄っていくと、案の定、中にへびが入っているとのことです。覚悟をきめて見せてもらうことにしました。コブラなんだか迫力がないコブラなんですよね。笛の音につられて出てきたのはいいのですが、それっきり固まって動かないのです。もっとおどろおどろしいものを想像していたので、拍子抜けでした。がっかりだったのはへび使いのおじさんの姿もです。ターバンはどうしたのよ!?その思いっきり普通の格好はなんなの!
2007.02.24
-

インドの光と影
1月28日~30日にかけて3夜連続で放送されたNHKスペシャル「インドの衝撃」を、みなさんご覧になりましたか?ご存知ない方のために内容を簡単に説明しましょう。第1回 「わき上がる頭脳パワー」 世界のIT産業を支えるインドの頭脳集団が、どのように生み出されているか。第2回 「11億の消費パワー」 今、インドにはかつて存在しなかった「中間層」と呼ばれる人々が急増。 彼らが巻き起こす「消費革命」の実態と影響について。第3回 「台頭する政治大国」 核を巡るアメリカとの政治的駆け引きや、 急発展する都市部との格差が広がる貧しい農村部の実態について。インドで実際に仕事をしている夫は、日本から送られてきたビデオを食い入るように見ていました。ほとんどニューデリーしか知らない私と違って、夫は日々変化していくインドを目の当たりにしていますので、感慨もひとしおだったんだと思います。確かにインドは変わりつつあります。でも、それはまだまだほんの一部のこと。貧しい人々は相変わらず貧しいままなのです。インディラ・マーケット庶民の台所と呼ばれているマーケットです。開店直後ということもあって、屋台にはまだ半分シートがかかったままです。涼しい今の時季ですから私もたまに行きますが、暑い季節にここを訪れることは不可能ですね。というのも、ハエの数がびっくり仰天するくらい多いのです!「これちょうだい」なんて言おうとしたら、口の中にうわっとハエが飛び込んでくるのではないかと思うほどです。野菜コーナーと軒を並べて鶏が売られています。生きているのを指差すと、その場で絞めてくれます(私は買ったことありません)。 マーケット全体に漂う悪臭は半端ではなく、こんな不潔な状態がなぜ許されるのか理解できません。その一方で、テレビで放送された豊かな世界も確かにインドには存在するのです。この矛盾をどのように解決するのか、あるいは永遠に解決されないのか、今後を見守りたいと思います。
2007.02.22
-

優雅なホテルのインドカレー
インド料理レポートをお届けするのも3回目となりました。(第1回→こちら、第2回→こちら)今回は、ニューデリー市内にあるホテルのなかで、最も優雅な雰囲気の The Imperial(インペリアル) 内にある「Daniell’s Tavern」というレストランに出かけました。ホテルの正面に車を乗りつけると、いかめしい顔した背の高いドアマンが恭しく出迎えてくれます。このホテルは、イギリス統治時代に建てられたコロニアルスタイルの建物のため、館内に一歩足を踏み入れると、まるでタイムスリップしたかのような感覚におちいります。でも、けっして古臭い感じではなく、クラシックとモダンが見事に融合していて、独特の雰囲気を醸しだしています。インドレストランで出される飲み物としては、ヨーグルトドリンクのlassi(ラッスィー)が有名ですが、私の最近のお気に入りはスイカジュースです。スイカ本来のほのかな甘さが、スパイスでひりひりした口の中を優しく洗い流してくれるのです。カレー3種Murg Tikka Masala (チキン・カレー)Methi Matar Khumb (マッシュルーム・グリンピース・カレー)Dal Maharani (豆の煮込み)ローティー(パン)2種Pudina Paratha (プディナ・パラタ)Kashimiri Naan (カシミール・ナン)この中で初めて食べた物は、カシミール・ナンです。ドライフルーツ(チェリーとパイナップル)がいっしょに練りこまれていて、ほのかに甘く、やはりカレーとのなじみが良くて、美味しかったです。カレーは、店内の雰囲気に見合ったお味でした。辛すぎなのが苦手な私でも、十分食べられる程好さで、満足でした。でも、こうして改めてみると、カレーはいつも同じものをチョイスしているんですよね。他にもいっぱいあるというのに、変化なし ^_^;次回はいつもと違う物をオーダーしますので、お楽しみに!Daniell’s Tavernの結果は、★ ★ ★
2007.02.20
-

本格カレーに大変身!
以前の記事でご紹介した紅茶ショップ「Mittal Stores」。実は、紅茶以外にも、ブレンドされたスパイスを買うことができるのです。そのうちのひとつがこちら。Mild Curry Powder (マイルド・カリー・パウダー)コリアンダー・ターメリック・マスタード・チリ・ドライジンジャー・クミンシード・フェヌグレク・ガーリックが絶妙にブレンドされています。自宅で作るカレーにこれをほんのちょっと入れるだけで、あ~ら、不思議 \(◎o◎)/!まるで専門店で食べるカレーのような味に大変身するのです。スパイスは種類が多く、私たち外国人が使いこなすのは難しいのですが、これさえあれば手軽に本格カレーが味わえるので、ほんとお役立ちものです。さあ、あなたのカレーにも、一さじ、いかが?
2007.02.18
-

不思議な名前の石鹸
以前は、食料品・日用雑貨などの買い物は、ほとんど使用人にまかせていましたが、ある事情があって、今は私自身ですべて行っています。そんなある日、使用人から石鹸を買ってほしいと言われました。何に使うのかとたずねると、床拭きをした雑巾を洗うために必要、との答えでした。銘柄も指定されました。「ライフボーイ」と聞こえたので、私の頭の中にはすぐさま、life boyというスペルが浮かびました。なんで boy なのかな?男の子は泥んこになって遊ぶから、ばい菌をすぐ退治して生命を守るという意味で、この名前がつけられたのかも、なんて漠然と想像しながら買いにいきました。スーパーマーケットの棚には、品質や値段が様々な石鹸がたくさん並んでいます。でも、すぐに見つけることができました。ほら、あったでしょう?しかも、左上の黄色いパッケージで黒いマスクをつけて写っているのは、私の大好きなインド人俳優 Hrithik Roshan(リティク・ローシャン) です!でも、石鹸の名前をよく見ると、うん? なんか変…。life boy ではなくて Lifebuoy と書かれているではありませんか。buoy って何? ヒンディー英語なのかしら?などと首をかしげて帰宅し、さっそく英和辞典で調べました。そこには、life buoy : 救命用浮き袋、救命ブイと書かれていました。ふ~ん、救命ブイか…って、なぜ? どうして石鹸の名前が救命ブイなの??答えはこの写真をご覧下さい。合成着色料が思いっきり使われています!と、いわんばかりの目立つ色。まさに、海でもはっきりと見えるブイの色そっくりなんですよね。それにしても、この石鹸で毎日手を洗ったら、指紋が消えてなくなりそうで怖いんですけど…。
2007.02.16
-
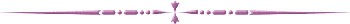
ニューデリー観光 「インド門」
住んでいる所の近くにある名所旧跡には、意外と足が向かないことってありませんか?私の場合、いつでも行けると思ってつい後回しにしがちなんです。突然の夫の転勤で慌ただしく引越しをすることになり、気がついたら、ここにも、あそこにも、行っていな~い!という失敗もありました。日本だったら、また訪れるチャンスがあるかもしれませんが、ここインドに関してはそうもいきません。そこで、後悔しないためにも、少しずついわゆる「観光」なんかをしておこうと、思い立ちました。みなさんにもお付き合いいただければ幸いです。今日ご紹介するのは、ニューデリーのほぼ中心地にそびえ立つ、こちら。India Gate (インド門)一見するとパリの凱旋門に似ていますよね。でも、成り立ちの理由が違うのです。パリの凱旋門は、ナポレオンがフランス軍の栄光を称えるために建てさせた物。一方のインド門は、第1次世界大戦で亡くなった9万人のインド人兵士を弔うために、1929年に建てられた物。当時のインドはイギリスの統治を受けていて、大勢のインド人がイギリス軍の兵士として戦場に赴いたのです。高さ42mの門の壁面には、戦死者の名前が刻まれています。門の周りには緑地が広がり、市民の憩いの場所となっています。ここから道路が放射状にのびているところなんかは、パリといっしょですね。Rajpath (ラジパト通り)そのうちの一本がこの通りです。大統領官邸まで直線道路が3kmも続いていて、それは壮観です。(遠くに小さく見えているのがインド門。)1月26日のRepublic Day(共和国記念日)の軍事パレードは、毎年ここで行われます。この周辺一帯は、イギリス統治時代にイギリス人によって計画的に作られたため、実に美しい街並になっているんですよ。私の一番のお気に入りポイントです。
2007.02.14
-

雷雨続きのニューデリー
ニューデリーは、この1週間というもの天候が悪く、毎日のように激しい雷雨があります。そのため、30℃近くまで上昇していた気温がいっきに下がり、しまいかけていた冬物の服をまたもや引っ張り出してきました。この時季にこんなに雨が降るのは珍しいことだそうです。迫り来る長い夏に向けて、気持ちを切り替えた直後にこの寒さですから、体が全くついていきません。すっかり鼻風邪を引いてしまいました。でも、植物にとっては恵みの雨。今朝の雷雨のあとの庭に出てみたら、乾燥して砂埃をかぶり、元気がなかった鉢植えの植物が、生き生きとした様子に変わっていました。
2007.02.13
-

カラフルなインドの新聞
以前の記事にも書きましたが、インドでは英語が準公用語として広く使われています。そのため、教育を受けた人々の間では、英語で書かれた新聞や雑誌が、当たり前のように読まれています。英字新聞が各社から発行されていて、我が家は、夫用に経済新聞、マダム用に大衆紙、の2種類を毎朝配達してもらっています。経済新聞は、オレンジ色を帯びた用紙に黒のインク1色で刷られた、ごくシンプルな紙面です。一方、私が読んでいる「Hindustan Times」は、ほぼ全面がカラーで印刷されていて、それは派手な作りになっています。新聞が内容ごとに分かれて束になっています。この日は7つに分かれていました。 ● 一般のニュース ● 経済と世界のニュース ● ファッションと芸能関係 ● 商品等の案内と入札の広告 ○ 土地に関するニュースと広告(3部構成)上の4つは毎日入ってきて、あとは曜日ごとに違います(日曜日は結婚紹介が入ります)。ちなみに、この日の「一般のニュース」(上の写真の右下)の一面を飾ったのは、インドのトップ俳優同士の婚約を伝える記事でした。マダムのお気に入りは、もちろん「ファッションと芸能関係」ですね。ビーチリゾートにお薦めのファッションが特集されていました。(派手派手で、とても着られそうもありません (>_
2007.02.12
-

ジョークでみるインド人
「世界の日本人ジョーク集」早坂隆著(中央公論新社)を昨夜読んで、ほんと笑ってしまいました。世界で親しまれている「日本、日本人をネタにしたジョーク」を作者が集め、さらに解説を加えた内容の本です。その中にこんなのが載っていたので、ご紹介したいと思います。●至難の業国際会議において有能な議長とはどういう者か。それはインド人を黙らせ、日本人を喋らせる者である。こんな短いジョークの中に、ふたつの国民性の違いが端的に表現されているのが、可笑しくてたまりません ^m^私は日々、この両極端の人種の中で生活しているので、これを読みながら、数々のエピソードを思い出してしまいました。そのうちのひとつ。インド人の多くは、相手に対して駄目元で言うところがあるんですね。いちいち真剣にとりあっていたら、こちらの身がもちません。たとえば、ある日本人の方から聞いた話です。その人がタイのバンコク空港でインド行きの搭乗手続きをしていたら、年配のサリー姿のインド女性が話しかけてきました。「あなたは私の息子よ。息子は母の荷物を持たなければならないわ。ほら、あそこにあるのはあなたの母の荷物よ」と、指差す方を見ると、カートの上に山と積まれた大量の荷物が!飛行機に預ける荷物には重量制限があって、それを超えて載せるためには料金が別にかかります。どうやらそのインド女性は超過料金を払いたくなくて、日本人に自分の荷物を押し付けようとしたらしいのです。いくらおとなしい日本人でも、そこまでお人好しな訳がありません。彼はきっぱりと言いました。「私の母は日本で暮らしています。残念ながら、あなたは私の母ではありません。さようなら」…お粗末さまでした
2007.02.10
-

お洒落なインドの額飾り☆
まず、この写真をご覧下さい。白黒写真ですみません。この女性のおでこの真ん中に付いている丸い印。これが今日お伝えする Bindi (ビンディ)と呼ばれる額飾りです。みなさんも何かで見て、ご存知かもしれませんね。インド女性のファッションには欠かせない重要なアイテムなんです。うちの使用人に聞いたところ、既婚女性のみ付けることが許されているそうです。でも、若手の女優さん(未婚)が付けているのをテレビで見たことがあるので、今は昔ほど厳密ではなく、気軽に使われているのかもしれません。元々は赤い粉を指先でチョンと付けていたらしいのですが、最近ではシールタイプが普及し、いたる所で売られています。赤い丸ばかりでなく、いろいろなデザインがあるんですよ。サリーやパンジャビドレスの色と合わせるのが、お洒落なんだとか。気恥ずかしいので、まだ私は付けたことがないんです。インド女性の彫りの深い顔立ちだからこそ、映えるっていうこともありますし。まぁ、そのうちインド風のばっちりメークでもして、華麗にきめてみましょうか (^_-)-☆ビンディをつける部分は、インドの考え方で命のパワーが宿る大切な部分とされている。この部分に第三の目を持つ神様もいる。ヒンドゥー教の儀式で僧侶が額の真ん中に色粉や灰をつけてくれるのは、お払いとかお清めのようなものだろう。大切な部分を守る意味もあってか、額に点を置いて飾る化粧法が古代からあったようだ。現在のインドではあまり深い意味はなく、装身具の一つとして普及していると思えばいい。 「インド 魅惑わくわく亜大陸」トラベルジャーナル から引用
2007.02.09
-

牛のお食事タイム
先日、ニューデリー市内のレストランでランチをした時のことです。お腹いっぱい食べて、さ~て車に乗りましょう、と、店の前の通りに出たところ、このような状況に出くわしました。大きな牛がなにやら真剣にゴミを漁っています。日本では、カラスによるゴミ荒らしが社会問題となっていますが、ここインドでは、牛がゴミを撒き散らしていても全くニュースになることもなく、人々は平然と横を通り過ぎていきます。このゴミ箱、まるで牛のエサやりのために設計されたように見えませんか?高さといい、大きさといい、まさにおあつらえ向き♪「不思議の国インド」を日々探索するマダムでした。
2007.02.08
-

インドの車にはドアミラーがない!?
ちょっとビックリでしょう?本来ついているべき所に、ミラーがない!何かにぶつかって壊れたのでもなく、あるいは故意にもぎとったのでもなく、最初からミラーなしで作られたような感じなんです。これはいったいどういうことなのでしょうか。そもそも、インド人ドライバーは前だけを見つめて運転しているふしがあるんです。ハンドルにしがみつくような前傾姿勢で、猛然とクラクションを鳴らしまくりながらの運転は、見ていてハラハラドキドキの連続です。少しでも他の車を追い抜こうとする凄まじいばかりの執念を、彼らから感じますね。ちょっとでも隙間があったら車の頭を突っ込むので、本来、片側2車線の道路が4~5車線になるのなんて、日常茶飯事です。狭い隙間を通過するには、横に張り出したミラーが邪魔をします。だから、せっかくミラーがついているのに、折りたたんだまま走っている車もよく見かけます。さらに、他の車との接触でミラーがもぎとれてそのまんま、なんてこともざらなんです。さて、写真の車の件を、私のドライバーに聞いたところ、インドで製造される車の廉価モデルのみ、オプションで左側のミラーを外すことができるんだそうです。もちろん、外したミラー分、車両価格がほんの少し安くなるので、このクラスの車を買い求めるインド人のほとんどが、そのオプションを行使するんだとか (ー_ー)!!インドの交通法って、どうなっているのでしょうね…。
2007.02.06
-

日本人御用達紅茶ショップ
インドの特産品といえば、真っ先に思い浮かぶのは紅茶でしょう。ダージリン、アッサムなどの名産地があるので、インド国内ではどこでもいいお茶が買えると思われるかもしれませんね。ところが、良質の葉っぱはほとんどが海外へ輸出されてしまうために、美味しい紅茶を普通のお店で買うことは難しいのです。でも、ここニューデリーには品質の良い紅茶を扱うお店がちゃんとあります。Mittal Stores (ミッタル・ストア)季節ごとに、いろいろなダージリンティーやフレーバーティーなどを取り揃えています。物にもよりますが、100g入りダージリンティーを250ルピー(約650円)くらいから買うことができます。このお店で私の一番のお薦めはマンゴーティーです。香りが人口的でなくとても自然で、飲み飽きない爽やかさがあるんです。去年の夏はこればかり飲んでいました。値段もお手ごろで、50g入りで45ルピー(約117円)なんです。実はこのお店の隣に別の紅茶ショップがあるのですが、なぜかそちらはいつもガラガラ状態。日本人ばかりでなく、ほとんどの欧米系の外国人もMittal Storesで買っています。かくいう私も、お隣に入ったことはまだありません。これだけ足繁くMittalに行っていて、いまさら隣のお店に入るのもちょっとためらいが…。たぶん、扱っている紅茶に差はないと思うのです。恐るべし、口コミパワー! といったところでしょうか?
2007.02.05
-

「ボリウッド」ってな~に?
「ハリウッド」の間違いではありません。インドのムンバイ(旧名 ボンベイ)で作られる映画のことをさしていいます。ハリウッドにボンベイをかけ合わせた言葉なんです。1年間に製作する映画の本数が世界一多い国はインドだということを、みなさんご存知でしょうか?年間800本以上も作られているそうです。最も映画産業が盛んな街はムンバイ(旧名 ボンベイ)。次はチェンナイ(旧名 マドラス)。以前の記事でお伝えしたとおり、インドには多くの言語があるため、映画が作られる街によって使用される言葉が違ってきます。ムンバイはヒンディー語映画、チェンナイはタミル語映画となっています。だいぶ前に日本でもヒットした「ムトゥ踊るマハラジャ」という映画は、実はタミル語のものなんです。でも、なんといってもインド映画の主流はムンバイで作られるヒンディー映画!これは一度見るとやみつきになる面白さがあるんですよね。歌ありダンスあり、涙あり笑いあり!主役をつとめるのはなぜか美男美女ばかり☆まさに百花繚乱、マサラいっぱいな一大絵巻となっています。ボリウッド情報誌
2007.02.03
-

ニューデリーの霧
日中の気温が高くなったためなのかどうかはわかりませんが、この1週間ほど、ニューデリーの朝は霧で真っ白です。昼近くなってやっと視界が良くなってきます。でも、晴れてはいても空の色は薄い灰色のまま。こんな霧の朝には、さすがのインド人ドライバーもいつになく慎重に運転します。ほとんどの車がライトを点灯し、スピードを落としています。さらにハザードランプまで点けている車を見かけ、驚きました (@_@)というのも、彼らがハンドルを握ると、まるで命をかけているとしか思えないような危険きまわりない運転をするからなんです。彼らも冷静な判断ができることがわかって、少しホッとしました。霧はほんと困りもので、この時季の航空機の離発着に大きな影響を及ぼします。現在、成田~デリーを結ぶLAL(日本航空)フライトが週4便あります(成田とデリーを4往復)。このフライト、夏と冬とで時間帯が変わるんです(成田発:夏は午後、冬は午前)。原因はみなさんお察しのとおり、「霧」です。霧は朝ばかりでなく、気温が下がる夜間から発生するため、濃霧の場合、いっさいの離発着ができなくなってしまうのです。インド観光には11月~2月がお勧めなんですが、もし、インド国内の移動に航空機の利用をお考えの場合は、霧のせいで予定が狂ってしまう可能性があることを、謹んでお知らせ申し上げます
2007.02.02
全17件 (17件中 1-17件目)
1









