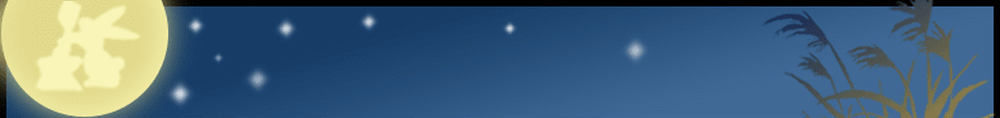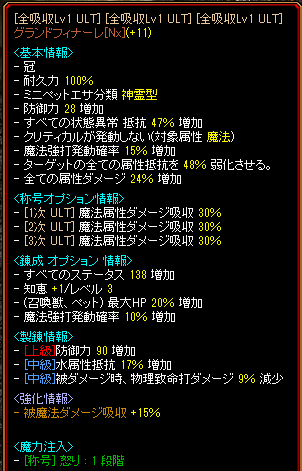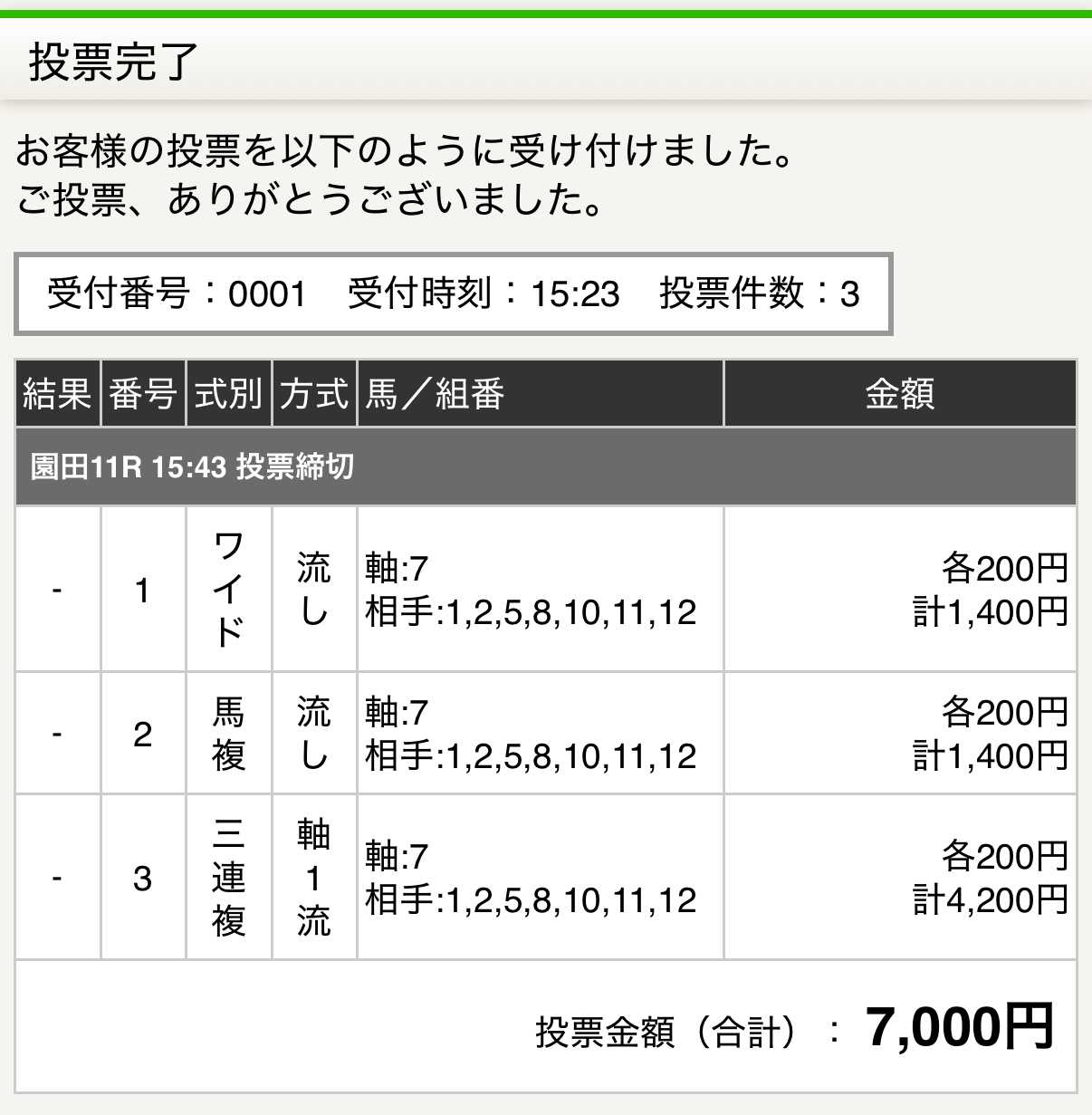2020年12月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

星と鬼
日本の森にはこうした人々の目には触れないまま現れては消えていく微細なきのこたちであふれている。月や惑星の消息には目が行くが、星座に仕立て上げらた星は別にして、星屑にはさほど関心を持たないのとよく似ている。日本書紀で登場する神で、珍しく天神であるにもかかわらず、悪神と名指しされた神がいる。天津香々背男(あまつかかせお)、別名天津甕星(あまつみかぼし)だ。国土平定に最後まで抵抗した天孫族の身内の神とされた。現在常陸の国の大甕神社に祀られている。この星神の抵抗神話は古事記には触れられていないことも覚えておきたい。 日本神話には不思議なことが多々ある。太陽神が女性であること。月神は早々と殺されてしまう。これは月読命(つきよみのみこと)として各地で細々と月読神社としてまつられている。 そして星神はあきらかに国賊と名指されて討伐され磐座に封印されたと創成神話は語る。世界の神話からみてもあきらかに我が国の神話は異常な操作が加えられ、天照大神のみが君臨する神話に書き換えられている。ここには、壬申の乱を平定し、皇親政治をようやく実現した8世紀の王権の思惑がにじんでいる。 カカセオは山田の案山子にむすびつくが、カカとは、天孫が中津国に降臨した折に、猿田彦がちまたに立ち尽くしていたとされ、その目はランランと輝き赤かかち(あかほうずき)のようであったとする描写のカカに通じ、地蔵菩薩ご真言のオム・カカカ・ビサンマエイ・ソワカの赤く輝くさまを言い表わすカカに通じる。このあまつみかぼしくんは全国の星神社、星宮神社に祀られている。このかかせおは一神教世界で堕天使とされた金星のジャスパーになぞらえたり、北極星に比定されたりした。北極星は天一神とされ各地の妙見社に祀られている。この星神にまつわる神社には不思議なことに秦氏が深く関与していることも見逃せない。 かくしてこのような微細で屑に等しい存在は列島の創成神話からも黙殺されていった。 私は、大地に時としてさんざめくきのこは地の星なのだと考えてきた。 井上靖は散文詩集『挽歌』の十一月という詩編の中で、鬼の部首をもつ漢字が多く星と鬼に付せられていることを指摘し、この鬼編の漢字を麻雀牌のようにかきまぜるとどれが星でどれが鬼かより分けるのが難しいとし、所詮、星と鬼とは同族なのであろうと指摘している。そして、一つは天上をうかがって星になり、一つは地上にひそんで鬼となったのである。だから一年中でもっとも夜気の澄み渡る十一月になると、界を異にした二つの鬼たちが互いに呼び合う声が聞こえる。その魂のきしみが聞こえる。と結んでいる。 わたしの<きのこ目の日本史>とは、こうした微細きわまりない命の声を拾い続けることなのである。 2020年の大みそかは、旧暦でいえば霜月十一月の立待月の十七夜に当たる。身近な存在である日・月・惑星の天空ショウを追いながら、ときには天地で呼び交わす星屑と鬼(=隠)の声に耳傾けるひとときをぜひもっていただきたいものだ。 2021年はきのこ歴第四期8年の5年度。そろそろ、星屑も地の鬼も森のきのこにつらなるすべての月のしずくに等しい存在を拾い集めてひそかに厳と小流れをつくる作業をはじめるべき時がきたと考えている。 この一年、皆々様のご厚誼ご交配に深謝申し上げ、以上を以って贈る言葉としたい。
2020年12月31日
コメント(0)
-

月のしずく31号 発送
昨夜、今年最後の望月を望んで帰宅すると月のしずく新年号届いていましたので、そのまま封入作業。 そのきのこさんのコラボで月のしずくの顔も定まり、会員の粒もそろってきましたので、序奏期間も満了、いよいよきのこ暦第4期後半戦のスタート。小冊子ながら、そんな気概が予感できる誌面となっています。マイノリティー、かつマジョリティーのきのこ・菌類に学ぶ文化の力で世界を少しずつ変えていくことを主眼に、偏らざるをえない21世紀の政治主義、経済主義と距離を置き、そのバランス回復に全力を注ぐ中に明日を見出していく。そのためにつねに庶民の立場に身をおき、あらゆる権威や権力からも一線を画してやってきた月のしずく会員の総力戦がしずかに幕を開けていきます。群れるは蒸れる。群れてダンゴになるなかれ。そしてたとえつたなくとも、つねに単独で、自身で考え行動する人財を集める「ちょっと背伸び」のサロン活動も強化していきます。巻 頭 メルヘンのなかのきのこ そのきのこ うれしいコラボが実現。この小冊子のクオリティーがぐんかと上がりました。2ページ 同和教育の罠 村上学 被差別民の固定化という大人の事情をわかりやすく解説していただきました。3ページ U-Boat 寺岡久隆 潜水艦の従軍兵士の日常生活から見事に戦争そのものの悲惨さをじんわりと解説。戦争を知らない世代の次世代、次々世代が中心となりつつある今の列島で、異民族慰霊と併せて、若い世代にNo More 英霊、すなわちこれ以上ただの一人たりとも虚偽の美名を冠された英霊をつくらぬ決意を新たにするためにこうした試みはこれからますます器用化していかねばならないと思っています。4-5ページ 日本史 うそで笑事典-1 さらば 卑弥呼 なつきじろう きのこを通して列島の聖地を巡り我が国の特異な精神風土と向き合うために、これからわたしたちの無意識を規定してきた天皇制度を中心に日本の宗教文化に触れていきます。6ページ ナラタケ 写真と文 なつきじろう なつきくんがナラタケへの熱い思い入れを語ります。7ページ 山本佳世の世界 友人のグループ展でゆくりなくその作品に出会い紹介ページが実現。あわせて紹介する、星野時環くん主宰の天空のドラマと少年愛の静かな主張をこめた月光百貨店は、月のしずくと親和性があり、今後もこの冊子でコラボしていきます。8-10ページ雑煮餅 円か四角か 奥村彪生 御年83歳、年明けには84歳を迎える奥村彪生ちゃんは、なつきくんの30年来のきのこの盟友です。 近年、長年にわたる氏のきのこをはじめ、世界の食文化と列島の食文化の比較研究のすべてのエッセンスを食にからめて本誌で紹介していただき本当にうれしく感謝しています。11ページ 気になるきのこ なつきくんがヘテロソフィア・アートのパイオニア的存在として交流を深めてきたアーティストたちの個展やアトリエ訪問記です。今回は、レザー・クラフト作家の河野甲さんと山口紀子さん。12ページ ひとときのこは似たものどうし だからなかよし 月のしずくのささやかな主張ときのこ探訪会、ラボMのサロンのお知らせです。ムックきのこクラブの探訪会は、これまでの踏査を重層化させるため、日本史うそで笑事典と連動した聖トポロジーのきのこ旅をふたたび辿ります。 列島では庶民救済の地蔵信仰に先駆けて、十一面観音信仰が奈良時代に興りました。その仕掛人は秦氏出身の白山の泰澄であり、東大寺初代別当の良弁と初期王権を支えた倭(和)氏と京都の葛野・若狭小浜の秦氏でした。列島の宗教文化を神道仏教のわけへだてなくまとめあげた人物群像をなつきくんはこれからも追い続けていきますので、うそで笑事典シリーズは、そんな旅のガイドブックとしてご注目のほど。 かくして、2021年はすでに鳴動をはじめています。けっして群れない。つねにちょっと背伸びを。この2点をあらゆる活動の芯に据えて今年も寄り道人生続けましょう。そして、ヘテロソフィアアーティストを目指す人たちは、自身のアートを言語化する必要があります。そのためのレッスンとしてなつきくんは夜の顔不思議な俳句会のオブザーバー、コメンテーターとしても活動していますので、自身の無意識を言語化したい情熱をお持ちのアーティストの皆様はぜひこちらにもご参加くださいませ。 つきのしずくは<きのこの前の一切平等主義>をモットーとする肩書抜きの会員制の文化サロン。年会費4000円です。 ふところ具合で出世払いでも額面割れでもOK。いやでも読んでほしいひとにはお金を出してでもお贈りしていますので、<群れず><ちよっと背伸び>を持続したい向きはぜひ、ご参加くださいませ。
2020年12月30日
コメント(1)
-

仕事納め
2020年の仕事納めの今日、志手原方面を1日車で巡り、定点の冬田の彼方の有馬富士にご挨拶。 思うに志手原とは死出原の転訛で生野や化野と同じく、野辺送りの地であったように思える。令和の今も、羽束山の西北の位置に斎場がちゃんとある。かっての京都賀茂川以東の東山あたりりがすべてそうであったように洛外の地だ。そう思いながら巡るとなお、感慨深いものを覚える。 明日、自宅の窓ふきと、自分も含めて捨て場の無い粗大ごみをなんとか適当にまとめ上げて残りの時間を読書に充てる。この年末年始、次年度の旅のお伴に井上靖を読み返す必要に駆られて彼の小説に没頭する予定。 車を洗車して帰宅する寸前、避雷針の傍らの叢雲に襲われ始めた十五夜月とご対面。刻々と2021年へのカウントダウンは首尾よく進行中。
2020年12月29日
コメント(0)
-
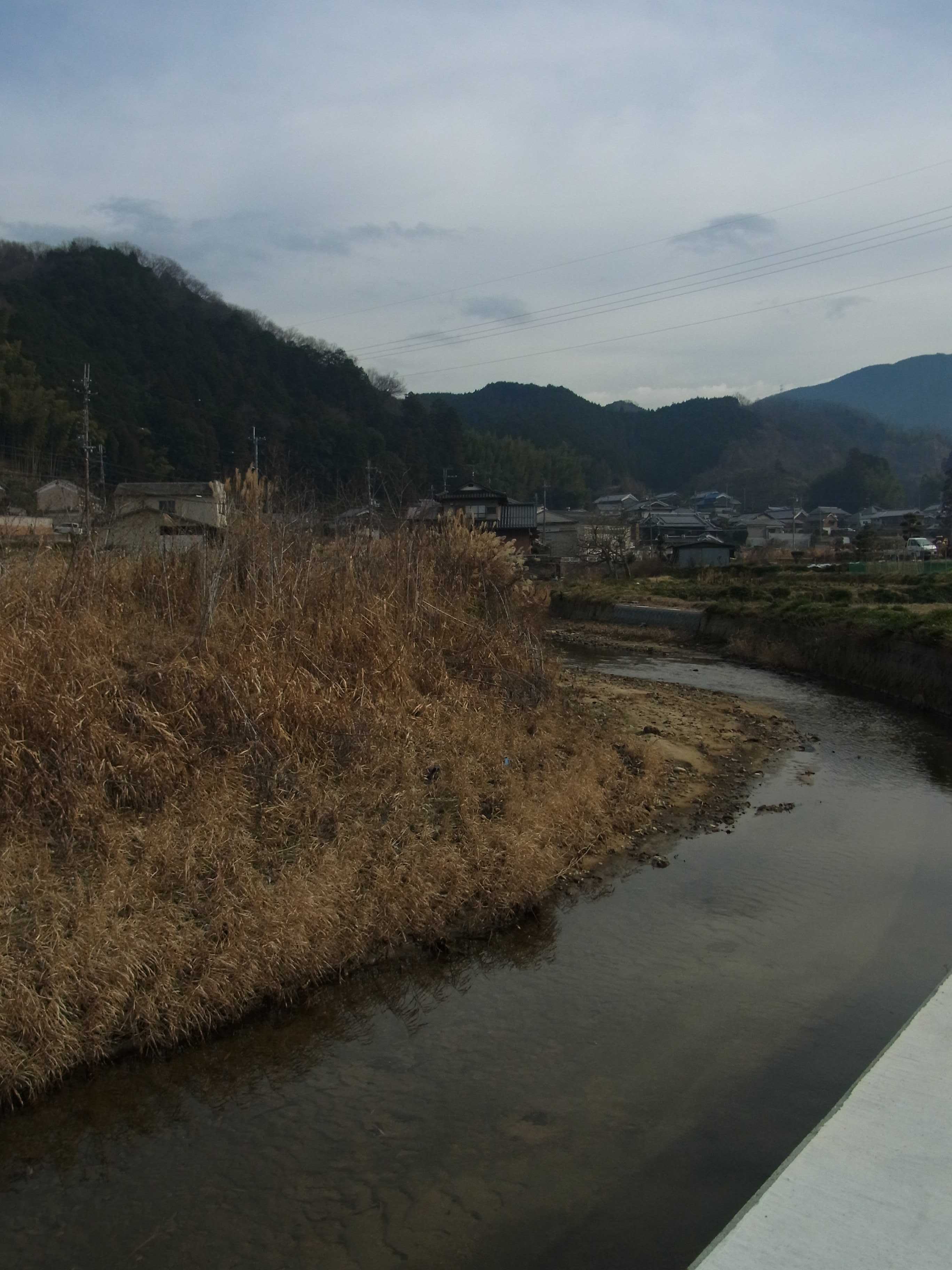
桜井市の鳥見山・等彌神社と宗像神社
久々にSilent Night, Holly Night と歌われた聖夜(きよしこの夜)そのままの、しずかなジーザス・クライスト生誕にふさわしいクリスマスとなりそうで、これもコロナ様のお蔭である。さて、伊那佐山を登場させたからには無視のできないトポスを次々とご紹介することにする。 忍阪と三輪のエリアを分けて南北方向に流れる粟原川(山の辺の道あたりでは寺川となる)を西に越えると、式内社の宗像神社がまもなく見えてくる。宗像氏は初期の王権を支えた古代雄族のひとつで、天武帝と宗像の娘の間に生まれ、壬申の乱で大活躍した高市皇子(たけちのみこ)と深いつながりのある神社である。 延喜式・式内大社の宗像神社の背後の山が鳥見山で、宗像社のある山麓をさらに西へ少し歩くと山の西側にあたるところに等彌(とみ)神社がある。ここから桜井市の鳥見山へ登った。 生駒北端の宝山寺の麓あたりにも同名の富見の地がひろがっており、宇陀にもあり、このあたりの人たちは、奈良県でもひそかにしっかりと富をたくわえているのかもしれない。 書紀によれば、神武大和入りの以前に、もう一人の天孫で物部の祖とされる饒速日命(にぎはやひのみこと)が天降(あも)ったとされる磐船神社があり、そこもとみの地にあるから奈良盆地には方々にトミと呼ばれる地だらけなのだ。そのひとつが桜井の鳥見山でこちらは神武天皇に関連づけられている。 この等彌神社左脇から鳥見山へ参拝できる。標高245mの小山だが、道中のカワラタケや大ぶりのキクラゲらと対話を交わしながら30分も歩くと頂上にいたる。ここが小さいながらも独立峰であることは重要である。 この頂上にある石碑には見慣れぬ文字がきざまれている。霊畤(れいじ)とは、大嘗祭の場所のことをいう。天皇家初代の神武が国家を平定し、橿原市で即位された折にその大嘗祭がここで行われたとされる。 この鳥見山が奈良盆地の内外の方々にあるというのは、天皇家の万世一系が、我々が考えるほど単純なものではなく、まさにその血統が理念上のものであることを示している。 この2020年の歳晩の日々、三輪山の始原の姿を求めてムックきのこクラブで歩いた日々の記憶をお伝えしたい。三輪山参拝が重層化して記憶に刻まれれば幸いである。やがて「月のしずく」でもこれらを参考に、多角的に検討していく。
2020年12月25日
コメント(0)
-

奥三輪の伊那佐山へ
宇陀駅から墨坂神社を更に奥へ行くバスでしばらく走ったところに八咫烏神社がある。現在はサッカーの神様として崇敬を集めているらしく境内にはサッカーボールを頭に載せたコミカルな八咫烏の像が奉納されている。しかし、ここから眺めるいなさ山はなかなかすばらしい。この日は、2014年6月8日、梅雨晴れ間の暑い一日だったと記憶する。 纏向の大和の初期王権の東方の国境は墨坂なので、さらに東のここは東国ということになるが、この奥三輪の人たちの甘南備信仰が三輪山祭祀の原郷と言われている。このいなさ山の麓から忍阪あたりの人たちの祖先が神武あるいは崇神に例えられる初期の大和王権を三輪山麓へ迎え入れ、支えたのではなかったかと私は考えている。 山の口では、木製の鳥居が迎えてくれる。 こうしただらだら坂を詰めれば地元の人が嶽大明神と呼んでいる山頂の明神社につく。この社殿の石垣の脇に三等三角点が置かれてあった。 来春の旧正月に登る三輪山との比較は歴然としている。三輪山はこうした里山のかんなびとは異なり、記紀神話に対応する3つの磐座がつくられており、明らかに人工的な手が加えられているのでそれをぜひ体験してほしいものだ。
2020年12月24日
コメント(0)
-

生駒宝山寺-5 地蔵坂の愉しみ
まどろみ地蔵 寝ているのか起きているのか、その境にあるまどろみの表情を湛えたじぞうさん。これも全国の画一的な地蔵像にはみられないすばらしい逸品である。夢うつつの薄明域にあるとき人は誰でも、ひととき幸せ感にひたられものだ。そんな境地を造形したような地蔵である。 地蔵というのは、日本全国津々浦々、とこででも出会うが、ここでご紹介したものはいずれも普段の生活のどこかできっと出会っている親しみをこめた表情を湛えている。地蔵はそんなちまたで喜怒哀楽を共にしてくれる存在であってほしいものだ。そんな地蔵のようにあなたも僕もなりましょうね。2020年、ムックきのこの旅は閉じ、まもなく2021年、令和3年の旅が新たにはじまる。冬至も過ぎていよいよ一陽来復。日はまた昇り、畳の目のひとつずつ日が長くなる。明日を信じて益々着実に足元をかためながら歩き続けましょう。
2020年12月23日
コメント(0)
-

生駒宝山寺-5 地蔵坂の愉しみ
宝山寺地蔵坂の地蔵像の中でも特に現代的で秀逸な造形は、この忿怒の相をもった地蔵であろう。地蔵は誰もが見向きもしない最底辺で生きる人たちを救済する目的でこの世にあらわれたとすれば、救世主然とした面相でなくとも、「こんな俺にだれがした」と言うようなやり場のない怒りで張り裂けそうになった造形がもっとあってよい。地蔵の字義は「大地を蔵するがごとし」である。遺伝子組み換え、ゲノム編集、核汚染物質の不法投棄、乱開発などで悲鳴をあげつつある大地の声は笑顔だけではすまされないまでになりつつある。 21世紀の地蔵は、もっと現代人のすさんだ心に直接訴えかける造形、ときには怒りの造型があってもよいように思える。ちまたの地蔵さまに飽き飽きしていたのでこの年の暮れは久々にニューウェイブ地蔵に出会ってワクワクしている。
2020年12月22日
コメント(0)
-

生駒宝山寺 地蔵のニューウェイブ-2
冬至の今日は、久々に凍てつく夜明けだった。仕事の後、駅を出るとすでにニアミス状態の土星と木星が歓迎してくれていた。こんなに接近するのは、土星、木星でなくても初めてだ。しかし、つまようじ1本ほどにまで接近したことはわかったが、大空での見かけのニアミスはよくあることだし、激突したわけでもないのになぜこんなに大騒ぎするのだろう。ショーではなく、もっと誰もが気付かない夜空の星たちのささやきを静かに聞きたいものだ。お地蔵さんも笑っている。ということで地蔵坂のつづき。 スマイル地蔵 仏像にはそれぞれ儀軌というものがあって、面相はそれに従ってつくるのでほぼ似通ってくる。しかし、地蔵は庶民の切ない信仰に支えられてそんな制作上の禁じ手はほぼない。しかし、完全に儀軌に自由ではないことからいずれも似通ったものになる。だけど、こんな人間臭い笑顔は公式の地蔵には見られないものだ。この感情過多の造型は仏師以外の人でないと無理だ。こんなところに僕の地蔵に惹かれる理由がある。ハッピースマイル、こんな地蔵にはめったにお目にかかれない。宝山寺ならではの地蔵である。くちべに地蔵ー2 前回お見せした地蔵とは化粧の仕方がいささか異なる。舞妓はんや芸妓はんの紅のさし方に近い。口を突き出してはいないものの、あきらかにキスを求めている面立ちで前回のくちべに地蔵よりも、さわやかなエロスを発散していて男心をくすぐる。これは紅の差し方が違うだけで地蔵の造形からくるものではない。紅一点で月とスッポンほどの差が生じる。この紅を差した人は天性のアーティストだ。
2020年12月21日
コメント(0)
-

生駒宝山寺-3 地蔵坂の愉しみ
生駒宝山寺をくまなく歩いて見つけたもので忘れられないのは、地蔵のニューウェイブである。 日本全国、どこへ行っても、どこを掘っても地蔵が見かけられるが、私は平安以降のみほとけの救済の手からこぼれ落ちた庶民を最後のひとりまで掬いげることを本願とする地蔵にきのこを重ねて、行く先々で地蔵像は撮り続けてきたが、久しぶりに造形的にみても面白いものが居並んでいて留飲を下げた。これからその一部を紹介する。 くちべに地蔵 「お地蔵さんは女性だった」とは、インドで生まれた説話にあるが、地蔵像でもとりわけ女性的なフォルムは、私がもっとも好みとするものである。 京都を中心に高槻から近江まで、地蔵盆に地蔵に化粧を施す習慣が残っているが、これはそんな地蔵像とはいささか趣きを異にし、洗練されている。澤山輝彦画伯(筆名 茶屋町一郎)が目下、くちびるについての考察を練っているのでそのイラストに使いたいと思っている逸品である。
2020年12月20日
コメント(0)
-

生駒宝山寺-2 奥の院の仲間たち
フユワラビ Botrychium ternatum 多宝塔より地蔵坂を上り詰めると不動明王を祭った本堂と開山廟があり、仏足石も古瓢句碑も蘇鉄の葉隠れにある。そこはさすがに冷暗所にふさわしくフユワラビがあり、同行の稲葉さんが目ざとく見つけてくれました。ラテン名のポツリキウムはボツリヌス菌と同じブドウの房状ということで胞子をつけた穂を言い表したものでしょう。触れると胞子のうから胞子を煙草の煙みたいに放散します。 ヤブコウジ Ardisia japonica 南天や千両、万両といった赤い実をたわわにつける冬の季節に、ひっそりと林の隅の光の乏しい場所に息づいているのがヤブコウジです。サクラソウ科ヤブコウジ属の常緑小低木。背の高いものでも20cmどまり。真夏に咲く花も実もつつましやかで万葉集では山たちばな。赤い実をほんの数えるほどつけることから背の高い派手な常緑樹に対して十両と呼ばれています。以前ご紹介した竜のひげの実の碧い玉同様、僕の冬の楽しみの草の実です。 ヒラタケ Pleurotus ostreatus ふつうは春から秋、広葉樹や倒木から多数、層を成して発生するが、この冬の季節に出るヒラタケはカンタケといって雪国ではとりわけ珍重される。商品名「なんとかシメジ」と名をつけられてスーパーなどで売られているものはすべてこのヒラタケの改良種である。ラテン名 Pleurotus は、片方の耳。ostreatus はオイスターのカキのこと。奥の院から生駒山上遊園地へ向かうケーブル脇のルートで見つけました。 そして今回の旅の終着点、石切劔箭神社(いしきりつるぎやじんじゃ)。ここのお百度巡りは有名で四六時中数十人がそれぞれこよりを手に回数を数えながら群れを成して歩いています。しかし、この神社、今でこそでんぼ(できもの)の神様になっていますが、神武東征以前に大和の地で先住民の蝦夷たちと共同統治をしていたと伝えられる物部の祖・饒速日命(にぎはやひのみこと)を祭る神社なのです。次春の旧正月の頃、参拝を予定している三輪山の神様・オオモノヌシや出雲族と深く結びついている神様です。
2020年12月18日
コメント(0)
-

シコンノボタン Tibouchina urvilleana
数年前に大谷美術館の冬ざれの庭でみかけた美しい紫の花は野牡丹だと思ったが、花期は夏で俳句の季語でも夏に充てられている。原産地もブラジルということで熱帯性植物とある。「だったら、あれは何だったのか」と、ずっと心にひっかかっていました。 ところが、昨日ふたたび同じ花木に出会い、思い切って持ち主にたずねたら紫紺野牡丹だとのこと。このノボタンには3品種あり、これはティボウキナ属で、他のノボタンとの差異は、おしべの先端がムラサキ色を呈するとのこと。 シコンノボタンTibouchina urvilleana 花期は夏だが、温度さえ高止まりなら12月でも開花は可能とのこと。そのかわり、葉は低温になると赤く紅葉するとのこと。なるほど紅葉していました。おしべの様子、葉の紅葉とすべて納得。これでようやく長年の疑問が解消しました。
2020年12月17日
コメント(0)
-

生駒宝山寺から石切劔箭神社の巻
近鉄生駒信貴山鉄道は全国でも珍しい踏切のある軌道を走るケーブルカーと画伯が言うので、それはぜひ乗らねばとちんたらちんたら宝山寺駅まで乗りました。なるほど、途中車が通る踏切や人だけが軌道の鋼鉄製の牽引ロープを跨いでそっと抜ける踏切があり面白いものでした。 いつもは通過するだけの宝山寺。今回はみっちり密着取材の旅。ここはインドの象神様、抱き合うガネーシャの歓喜天、つまり聖天さまで有名ですが、本来弥勒浄土兜率天信仰に支えられた山です。本殿を抱くようにそびえる岩屋には役行者が梵字の般若経を納めて修行した般若窟があり、そこには金銅の弥勒菩薩坐像が安置されています。聖天さまの本地仏は十一面観音ですから、ガネーシャは後付け。此の地が奈良時代から続く霊山であることがしのばれます。中興の祖である江戸中期の淡海律師は、本尊を不動明王と定め庶民救済を本願とする寺院再興を目指しました。なかなかの炯眼の持ち主で、遣り手じじぃだったようです。おかげで生駒山の地主神・往馬大社をしのぐ勢いで今日も大阪の底力を支えています。宝山寺の寺紋は笹りんどう。そもそも源氏の源頼朝の家紋が笹りんどうで鎌倉市の市章になっていますので、源氏の武家とのつながりもそこはかとなく匂ってきます。 でも、大阪市民には、この商売繁盛のきんちゃく袋のほうが馴染みがありましょう。これが奥の院にある中興の祖淡海律師の開山廟。 その廟脇には淡海律師の尊像のレプリカが置かれています。 こちらが同じく奥の院に設置された般若窟の弥勒菩薩のレプリカ。マイトレ―ヤーちゃんです。なかなか端正な顔立ちでちょっと胸キュンとなります。そのマイトレーヤーちゃんの前には線刻の仏足石が。 私は奥の院までの地蔵坂のお地蔵さんに見惚れてあっちふらふら、こっちふらふらしていましたら、同行のSさんが蘇鉄の植え込みのそばに山本古瓢さんの句碑を発見。「これってあなたの先生では?」と声をかけてもらって初めて気づきました。…鳥雲に享くるのみなる手を浄む… 古瓢てっきりわすれていましたが、古瓢先生は聖天さんの熱心な信者だったらしく、その縁でここに。ついで堺の大仙陵に、そして龍野の嘴﨑にも句碑が建てられています。そんなバブル期の句碑建立ラッシュの半世紀以上も前のことすっかりさっぱり忘れていました。大学を出て間もない頃、私はこの句碑の除幕式に立ち会ったことを思い出しました。わが生涯唯一の師と定めた古瓢さん。なんとも薄情な弟子であること丸わかり。そういえば宝山寺の信者会館で句会が開かれ「蟻ひとつふたつみつよつ墓域なり」という拙句が物議をかもしたことが思い出されました。当時は奥の院まで句碑以外に何もなく墓地になっていたように思えます。
2020年12月15日
コメント(0)
-

2021年・きのこ暦第Ⅳ期5年目の新春へ
この1週間で、野山から秋の気配はなくなり、一挙に冬景色に。 旧暦・神無月最後の日のムックきのこクラブ納めの会で、生駒宝山寺から石切までをさすらってきた。その足で梅田阪急百貨店で開催中の河野甲さんのレザークラフトアート展をのぞいたが、百貨店の夕刻は、人で溢れていて驚いた。9階だったか?の催し会場は、月光百貨店の時環くんが喜びそうな天空図のもとで、X'mas Treeのシャンデリアが燦然と輝いていた。 霜月朔日の本日、いよいよ「月のしずく」31号編集スタート。宝山寺のさまざまなハプニングは、編集の合間にちらほらお知らせすることにしょう。そして私の頭の中もメリー・クリスマス & ハッピー・ニュー・イヤーモードに切り替えましょう。 来る2021年は、力のかぎりこれまでやってきたことを少しずつかたちにしていく年にしたい。
2020年12月14日
コメント(0)
-

蘇我期のもうひとつの皇統・忍阪
桜井から更に近鉄で宇陀方面へ向かうと三輪山の奥処(おくが)へと入っていく。その奈良盆地との境にあるのが近鉄朝倉駅で、ここは聖徳太子の時代に蘇我の血を引かない古代最大の忍阪王統があったところ。額田王や鏡王女を育てた額田部氏の居住地がここで、地元の人は「おっさか」と呼んでいる。 神籠石の辻を山辺に向かうとこの細流れにそって、ひっそりと、しかし、威厳を放つ舒明天皇陵がある。 春浅き頃たどるとこの細流れに冬いちごがたわわに実っており、それを口に含みながらの逍遥となる。10分も歩くと山里の風景が一変、舒明天皇陵が見えてくる。なかなか見事な眺めだ。当時は成り上がりものの蘇我氏に対し「田舎もんの蘇我氏なにするものぞ」といった気概を持っていたと思われる皇統の姿が浮かび上がってくるのを覚える。 しかし、本当のところは、蘇我氏の系統は、我が国の外交を一手に引き受けた葛城氏につらなる、この時代にはめずらしいずば抜けた都会もんで同じ都会もんの藤原氏のご一統には煙たすぎる存在だったようです。 舒明天皇陵への小径の更に奥には鏡王女と大伴皇女の墓がある。 山畑の脇には水仙がひっそり花をつけていた。 鏡皇女は藤原氏や天智天皇と恋歌を交わしたほどの才女である。大伴皇女は堅塩姫(きたしひめ)の娘で蘇我系の推古天皇、聖徳太子と忍阪王統をつなぐ人材だ。この<つゆおとなうものなき>山里に古代史のドラマが息づいているのを辿るのは、わたしのひそかな愉しみのひとつだ。 ひそかな愉しみといえば、駅からここへ来る途中に見た玉津島明神。誰だったか忘れたが、貴紳の産湯址だとされ、ここには丹生都比売(にふつひめ)と衣通姫(そとおりひめ)が祀られている。衣通姫は、飛びぬけた美貌に恵まれ、黙って坐っているだけでも着物を通して(=そとおり)、たまんないオーラ、今どきの言葉ではフェロモンを放っていたという。そのため、皇后から妬みを受け不遇の人生を送ったという。私にとっては、古代史の中でももっとも会いたい女性の一人である。 私のその折りの目的の中心は、おっさかのたかまどやま・石位寺の必見といわれてきたわが国最古の見事な薬師三尊石仏だった。 飛鳥・奈良初期の頃刻まれたという石仏だが、本当かなと思えるほどの見事な保存状態で驚いた。しかも、本当に無造作に置かれていて、このお堂の鍵を開けていただいた区長さんは、「写真撮影」は基本的にはダメですが、フラッシュを焚かなければ撮ったところで傷むわけでもなし。どうぞどうぞと言われた。この時は区長さんが自宅に居合わせて本当にラッキーだったが、通常は奈良市観光課へ電話を入れて、そこ経由で区長さんが在宅であればこちらに出向いてもらいカギをあけてもらう段取りらしいので、石位寺へ行かれる方は電話予約しておいたほうが安心かも。私にとってはここ忍阪は、おっさかべ=刑部に通じる天皇紀のあけぼの時代の鍵を握るとても重要な地点。さらに駅からすぐの忍阪坐生根神社(おっさかにますいくねじんじゃ)を始め、奥三輪から宇陀にかけては、かんなび山を神体とする神社が目白押しなので目がはなせないところだ。 この区長さんは、そのあと自家用車で額田大王が造立したという草壁皇子慰霊のための粟原寺跡や玄道を潜り抜けて石棺が見れる古墳などを案内してくれた。その折のことは「月のしずく」の墓マイラー編で詳しく述べたので省略する。しかし、何の目的も持たずにふらりと来ても決して後悔しない山里だ。
2020年12月11日
コメント(0)
-

森・杜・盛り・もりの話
神社の杜 纏向遺跡のひもろぎ わが国の縄文・弥生人は、極度にけがれ、とりわけ死穢(しえ)を嫌ったというのは本当だろうか。 谷川健一はそれに対して明快にNo!と応えている。彼は、日本各地の聖地を巡って、森とはそもそも鬱蒼とした神社の杜のイメージから遠く、木が数本生えているところをもりと呼んだといっている。 ひもろぎがその典型的な例だ。要は神が降臨するための依代(よりしろ)をモリと呼んだというのだ。 古神道が死に伴う腐臭を極度に嫌い、死穢を遠ざけたというのは後の付会で、いにしえびとは、身内が死んだら土に還し、盛り土をし、そこを聖所として今日の樹木葬に通じるような大きく育つ樹木を植えたことに始まるという。その盛り土した場所からモリという言葉ができあがったというのだ。そうした祖霊の集合体がいつしか森と呼ばれ山全体を祖霊の帰るところ、そこからまた年に一度里へ降りてくるとして神体山が出来上がったものと私も思う。神社の原型をなす三輪神社、笠縫の邑の檜原神社には神殿がなく三輪山そのものが神体とされるのがそれを暗示している。祖霊をおまつりした後はそのためにしつらえた宮(庭から転じたもの。沖縄では今でも庭のことをミャーと呼ぶ)を取り壊した。そこからその宮を社(やしろ=屋代)と呼ぶようになったという。 庭や森という言葉も私たちの記憶の底から一度掘り起こしてくる必要がありそうだ。
2020年12月10日
コメント(0)
-

無縁仏の宝庫・壺阪の高取山
私は、地より湧き出でる大地の力として地蔵さんにきのこの生命力を託してきたが、ムックきのこクラブ2012.3.18の旅・春浅い雨の壺阪の高取山ではそんなきのこ地蔵を満喫できた。 壷阪寺より登っていくと、異様なオーラを発する岩々が行方に立ち現れる。以下のような立て札のついた石仏などほんのわずかで、山全体の岩という岩にはおびただしい数の仏、羅漢、天女、如来などが刻まれているのだ。 まさに三十三間堂の千体仏の野外版。各所の仏たちの様式が異なることから数百年にわたって名もない山伏や修行僧らによって刻まれ続けてきたものと思われる。 まさに、法華経でいうところの「従地湧菩薩」(じゅうちゆうぼさつ)たちのオンパレード。 そして、この道の終着点にあたる高取山(538.9m)頂上には、日本三大山城の一つ、高取城址がある。 ここは南北朝以来、山城として越智・本多・植村氏の居城として守られてきた。ここが山上の城となったのは郡山城主となった豊臣秀長の命をうけ、本多氏が本格的城郭として整備。明治政府による版籍奉還で廃城になる明治6年(1873)まで城主がいたという。 この日は霧深くますます幽玄の相を帯びた城址であった。 私はこれより以前の盛夏に、何の知識も持たずにひたすら夏のきのこを求めて壷阪寺の喧騒を避け植村家老屋敷跡の反対ルートをとってのぼったので、猿石以外には石仏らしきものとも出会わずに山巓に至った。だがらなおのこと、突如あらわれた本格的城郭には正直、仰天した。まさに東洋のマチュピチュと思ったのだ。その時以来、いつかここで、ぜひムックきのこクラブのお茶会をしたいと思ったものだ。これは近々実現したいと思っている。
2020年12月08日
コメント(0)
-

お地蔵さんに出会った・
紀州・根来寺でみかけたお地蔵様 さて、12月も2週目。身辺バタバタしはじめたぞ。 それはさておき、きのう街ですれ違った人、どこかで見たような気がしてあれこれ思いあぐねていたが、ついさっき、蕪のお漬物をコリコリ噛んでいて思い出しました。このお地蔵さんに似た人だったんだと合点。 いつか、ひまが出来たら、これまで出会ったきのこ地蔵さんの無数の写真で、イケメン地蔵のファッションショウでもやろうかな。
2020年12月07日
コメント(0)
-

大阪慕情
通天閣に赤いイルミネーションが灯り、コロナ第3波の拡散が伝えられる大阪北新地の交差点。急ぎ足で通り過ぎる際にスマホでメモった。神戸にもイタリアから贈られたルミナリエのメモリアルライトが灯ったと伝えられている。 コロナは、しかしパンデミック世紀のほんの序の口。それでもすでにこのありさまであれば、2021年はもっと悪化の方向へなだれ込んでいく以外になさそうだ。 <人はいさ、心は知らず>・・・私個人としては、目線を更にさらに低く据えてひたすら足の向くまま気のむくままに歩み続けたいと考える年の暮れがはじまった。
2020年12月06日
コメント(0)
-

つるりんどう(蔓竜胆) Tripterospermum japonicum
花は7-9月。上の写真の左にさやをつけた実がみえていますが、筒状鐘形の2-3cmと大きめの白色にうすく紫を配した清楚な花をつけます。その花から写真のように実が延びて来て艶やかな赤色を呈します。 他のリンドウの仲間との違いは、草本性のリンドウが、日おもての明るい草地に咲くものが多く種子も乾いた殻につつまれはじけるのに対し、このつる性のリンドウだけは暑さを嫌うのか、森の日陰の地にひっそりと花をつけ、赤い液果をつくること。この実の中に30粒ほどの種子を育みます。毒性はないので口にしましたが、無味。 しかし、古来薬効があり、漢方として胃を整え熱を冷ますと言われていて果実酒にして服用する趣味人もいるという。 秋から冬にかけての僕の楽しみは、きのこは言うまでもなく、草木の実と数多く出会えること。そういえば、山岳部時代、秋のアルプスの旅では夏山で出会った高山植物の実をかたっぱしから食べる旅をしたことを思い出しました。これから生きる時間の長さに比べて、これまで生きてきた時間の長さが圧倒的になると思い出話が多くなるのはおじんになった証拠ですね。気をつけなければ。来春からは、<明日>だけを語ることにしたいものです。
2020年12月04日
コメント(0)
-

2021年は、きのこ暦第Ⅳ期5年目
山口紀子 「芽吹きの種子」シリーズのひとつ 12月3日は旧暦の神無月十九夜、寝待月。「果報は寝て待て」とは、いにしえよりの伝ですが、コロナというこの初歩的なパンデミックによる人為的な淘汰圧がかけられている状況下では、寝ていてはおそらく庶民生活の大半が崩壊していくこと必定です。市民の自覚的な存在規定、すなわち「ちょっと背伸び」の脱庶民の意識形成が強く求められる時代に突入していると私は考えます。 8年ワン・クールのきのこ暦もすでに第4期の5年目となる2021年。そんな私の意識下では、すでに2021年モードに切り替わっており、新たな芽吹きに向けて土づくりを始めています。 『月のしずく』も来春よりは、1.異民族慰霊、2.きのこと発酵、3.島なみクラブ の3つの柱を中心に、その核心へすこしでも近づく努力をさらに強化するため、時代に臨機応変に即応できるフレキシブルでますます機動性に富んだものに切り替えていきます。どうぞよろしくご声援のほど。
2020年12月03日
コメント(0)
-

タンキリマメ
タンキリマメ Rynchosia volubilis 晩秋から初冬の林縁にごく普通にみられるつる性の多年草。豆莢がはじけると黒紫色の豆が2コ、莢の縁に落ちずにしがみついていてなんとも可憐である。6月~8月に黄色い小花をつけるが気づかずに通り過ぎていることが多い。 同形同色の実をつけるトキリマメ R.acuminatifolia (オオバタンキリマメ)があるが、タンキリマメは実に2~4mmの短い葉柄をつけることで区別できるという。属名の Rynchosia は、thynchos (=くちばし)に由来。ヴォルピリスは、からみついた。アクミナチフォーリアは、先の尖った葉を意味するという。 痰切り豆とは、通称かと思ったがこの実に痰を切る効能があり、正式和名だという。山道には必ずぶら下がっているのでどうぞ見つけてほしい仲間のひとつだ。
2020年12月02日
コメント(0)
-

種(tane)展に触発された私のアートへの想い
山口紀子種(tane)展 11月30日~12月05日 大阪北西天満・現代クラフトギャラリーにて コロナ禍で明け暮れた令和2年、この作家は、個人的にも交通事故に遭われたりで波風のひときわ高い場所で活動を続けてこられたので、今年はパスかとあきらめていた。ところが、案内よりもフェイスブックで特急はくたかで大阪に向かっているとの報。たちまち私の頭の中はギョギョギョの鬼太郎ならぬ魚マークで一杯となった。そこには遠慮がちに個展の案内も添えられており、日取りをみれば開催初日しかいけない。そこで、取るものもとりあえず駆けつけてきた。 今回のテーマが、作家の中でパキンとはじけてできた作品と思しきメイン作品が表通りに向かって展示。陶芸がメインの作家だから当然だが。 さて、この作品「しあわせの種」の語りと会場の個々の作品がどう響き合っているかをじっくりと眺めてきた。 しあわせの種 現代クラフトギャラリーでの歳末恒例となった彼女の作品展の面白さは、長野県北部在住ということも大いに反映している。そこは、戸隠や黒姫の森、野尻湖といった我が国の博物誌の始原の栄光を伝える地で、今も刺激的なナチュラルヒストリーを伝える活動が続けられている。彼女はそんな流れに積極的に参画し、そんな日常から立ち昇る気の流れが、おのずと地球生命誌の流れにシンクロしていてとてもトレンディ―なのだ。わたしの問題意識にも絶えずシンクロしていて、そういった意味でも目の離せない作家のひとりである。詳しくは、次号『月のしずく』31号で紹介したい。 このコーナーは種々の形の種の標本(左)を並べたコーナー。 種の標本のひとつ 私も、ラボMの標本箱用に2点ほどゲットしたが、さまざまな造形の陶器の種子から伸び始めた赤銅製のひこばえがここで提示され、それがまわりのコーナーで芽ぶき、光り、育ちたい、遠くへ行きたいという願望をそれぞれに満たしていく。そんな種子のもつ生命力をわかりやすい形で表現してくれていることだ。 これは、ある意味、目下 Calo Bookstore & Cafe で開催中のコラージュ作家・上野王香の『種葬』(ロンドン在住)と真逆の表現ながら意外にも、生と死、そして再生といった卑小かつ、かけがえのない生命の表現として、その根っこの部分では共通するものだ。 具象、抽象にかかわらず、この、わかりやすいということ(すなわち言語化できる作品)が、私のアートの中では何よりも重要なファクトであることはいうまでもない。私が親しいアーティストたちに短詩を薦めるのも同じ意味合いからである。極言すれば、言葉なきアートは私にとっては意味をなさない のである。 民藝とアートの薄明域にたちのぼる作品に私がもっとも強く反応するのはそうした心意による。飾り気のない肉声による言葉が、作家の制作意図の解説ではなくそれぞれの作品にどうしっかりと吹き込められているかが私のアートの評価では最優先される。それは「ちょっと背伸び」の庶民にきわめて親和性のあるものであり、そんな庶民の心を烈しく動かす力をもつ作品たちなのだ。
2020年12月01日
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1