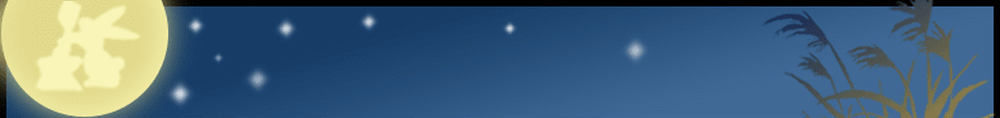2024年01月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

お地蔵さんからはじまった1月が終わる
社会福祉協議会が歳末に郵便受けに放り込んでくれたカレンダーの1月はやさしいお地蔵さんのキャプションつきのかさ地蔵の図柄(辰島一代作品)が配されていた。大地を蔵するごとしという地蔵は"きのこ"をつくる菌類そのものである。21世紀の人新世の時代のスーパースターとしてきのこの文化普及振興に努めてきた私達だが、事態は私たちの想像以上に不可逆的に進行して大地を蔵するごときさしものきのこたちも疲弊し始めている。40年前にはきのこ目を持たなくとも里山へはいるとまず目に飛び込んでくるのがきのこだった。それが今はどうだろう。四季を通じてきのこに出会うのは稀になりたまさか出会う時には群生することなど稀なきのこの大群生と相場は決まって来た。そして大群生ののちは二度と顔を現わすことはなくなる。 ゆるやかな菌糸ネットを作り版図をひろげ循環世界の潤滑を図るきのこだが、昨今のそれは断末魔の叫びに変わっている。大型菌類(きのこをつくる菌類のことの別称)がいつもと違った形できのこをつくるのは大ピンチに陥った菌類がそこでいきていけなくなったときに挙げる悲鳴に等しい。そこの大地で生きて行けなくなったのでさようならのきのこを掲げてそのことをいち早く知らせてくれているのだ。牧歌的なキノコ採りに私たちが興じているわずか半世紀にもみたない間に列島の最期まで生き延びる能力のあるはずの菌類が失調をきたし始めているのだ。NEO博物学の時代のきのこファンはそのことをもっと真剣に見つめ大衆にしめしていかなくてはならない。それが「月のしずく」50号からの使命となるだろう。法然は武家の台頭で人心が荒みきった鎌倉時代に凡夫たることの徹底自覚を訴え続けその自覚を持ちえた人に対極の救済の思想を専修念仏の易行として打ち出した。その真意を巡って諸派に分かれて行ったが、その目指すところは同じであった。日蓮でさえ法然の出現を彗星に模したほどであった。私はそれを「南無阿弥陀仏」や「南無妙法蓮華経」ではなく「ちょっと背伸び」として令和以降の現代人の徳目として訴えていきたい。脱神話化をもっと進めるがそれは新しい物語の創出のために。ここではアーテイストの役割が何よりも重要視されるというのが私の考えだ。政治経済以前の課題が「ちょっと背伸び」なのだ。なにかといえば「自分へのご褒美」をゆるしてしまう我々にはこの「ちょっと背伸び」は至難の技。それをたえず励ましていくのはアーティストをおいてない。それをこれから徐々に明らかにしていく。
2024年01月31日
コメント(0)
-

1月17日より20日余りの間に
今年のクリスマスまでの間、不在となった可憐な女神像のことを懐かしく振り返りながら、1月17日より「良弁伝」を一休みして月のしずく50号に向けて10冊ほどの書物を再度ノートを取りながら精読している。「良弁伝」もすでに10万字を超えたが、完成にはほど遠く道鏡事件への宇佐神宮の対応と平安遷都へのキーマンとになる和気清麻呂の記事を書きとどめると良弁卒去へと軟着陸できる。ここまできてはじめて全体の構成の組換えと推敲の作業を余すのみとなる。才能の無さを痛感しつつも精一杯の作業をとにかくやりおおすことに全力を傾注するが、この20日余り賜った空白の時間を、50号以降の「月のしずく」の読者とともに新たな一歩を踏み出すための作業に没頭できることを単純に喜んでいる。 斎藤幸平の『人新世の「資本論」』を中心にマルクス・ガブリエルの「なぜ世界は存在しないのか」(清水一浩訳・講談社選書メチエ)と「アートの力」(大池惣太郎訳 柿並良佑協力・堀之内出版)それと意外に思われるかもしれないが、岩田文昭の最新論考「浄土思想」(中央公論新社)の書評とともに、これから残された時間われわれがやるべきことはなになのかを一緒に考えていきたい。 私が40年以上も前にきのこと出会って以来考え行動してきたたことの集成の作業がこれからはじまる。 古代以来の渡来民・秦氏たちの思いが良弁を筆頭に空海、最澄、法然、一遍、世阿弥と流れ、芭蕉・蕪村へとつながり21世紀の目に見える微生物・きのこへと集約されていく根拠を、そしてなぜそれらが異を冠した異民族慰霊祭にまでつながっているのかも可能な限り言語化していきたい。その思いはすでに戦後70年に当る2015年に上梓した太平洋戦争外伝『光るきのこたちの賦』にしたためているので必要な人には差し上げる。残部僅少なので早めにどうぞ。 そんな"きのこのたわごと"に過ぎない私の思いではあるが、「月のしずく」の読者のひとりでも多くの人に伝わればと願っている。そして可能なら今年の昭和の日の祝日4月29日に斎行される第49年度の「異民族慰霊祭」にも足を運んでいただきたい。
2024年01月30日
コメント(0)
-

あと2日で睦月尽
生きてあるだけでしあわせ? 睦月尽 今年は元日以来異常事態の日常化が深刻化してきていることを思い知らされる毎日だが、今日は旧暦の師走の十八夜。 これまでの3400m歩行訓練では巡行、逆行あわせて8回の平均は1分82.26mだ。今日は1分89.5m。いまさら反省しても仕方のないことだが私の脇見人生を象徴するような歩行記録で、一生懸命歩いているようでもつい脇見していることが良くわかる。最速で1分 103m、最低で1分 63m。 まだ左右の体重移動のバランスは正常位にはもどっていないが、理学療法士さんは右足を大きく、左足は小股でというが、それはむしろ逆のようだ。右足を軸にして左足を前に出す際に軽く蹴って大きく前方へ出し、体重をすばやく移動しながらかかとを梃子にして足先を90度上方へ回転させかかとから着地し同時に小指側から親指へと体重をうつしながら右足へという動作を意識的かつ正確にやりおおす訓練は、左足を大股で歩く方がベターだという事が判明。その方が左足を主体的に動かすことに繋がるようだ。それが効を奏して左脚の筋力が少しずつ回復してきている。これを無意識で出来るようになるまで続けるのだ。それに連動する形でこれに左腕の可動域を広げて行ければ願ったり叶ったりの状態になる。旧正月の元旦は2月10日、それまでにもう少しおジン臭い現状を改善したい。乙女椿ちゃんも応援してくれてることだしね。
2024年01月29日
コメント(0)
-

「畏怖」ミズタニカエコ作品展
芦屋茶屋之町の月光百貨店で正月21日~2月4日まで開催中のミズタニカエコ作品展は、ペン画作家の彼女の渾身の作品が展示されている。 畏怖 if 彼女との出会いは、チチ松村がきのこ愛好家であった時に冬虫夏草を扱った作家がいると教えられ、会いに行った時に始まる。かれこれ20年近く前の事になる。その作品はオオセミタケを配した絵柄であった。以来方々で開かれる個展に足しげく訪れてきたが、一貫して無限増殖する生き物に対する畏敬の念を作品の背景に滲ませた作品を作り続けてきた。 旅人 彼女の作風は、眼球・蛾・らせんを中心に展開されてきているが、オブジェやエッチング作品も加わり、モノクロ画、彩色画と歳月を経るにつれ深化を遂げて今日に到っている。ミニチュア造本の上山榮子さんのギャラリー・ビー玉と協同でオール手作りの作品集も出版されており、近年フランスのワイン醸造家のラベルも手掛け、毎年フランスで作品展を開催するまでになっている。 エレクトリア もしあなたがその存在を怖がらずにいたら、 えもいわれぬ美しさを享受できただろうに かそけき光に鱗粉を撒いて飛ぶ蛾(ひひる) 求め彷徨うはヒトとて同じ 今回の案内状には、mothの我が国古来の言葉<ひひる>とあえてルビを打っているが、これも彼女の現在の位相を示すものとして受け止めた次第である。 ノスタルジアあるいはメランコリア(時計のオブジェ) 同じく近接 ユートピア幻想 (エッチング) 時空の羅針盤 今回の作品展ではこの作品にとりわけ心惹かれた。ぶれないために必死で自己を制御する作家本人の羅針盤の役割をも果たす作品のように感じたからである。 私の友人の多くは私の子供の世代に当たることもあって、両親の不予を抱えている。彼女の今回の個展は、そんな世代的な不安を押しての開催であったことで、とりわけ熱いものを感じた。私はアートというものも民藝にどこか通じていることに重きをおいてきた。 彼女の作品はそんな意味でも徐々に深まりをみせてきている。どうか、数々の不安や困難を乗り越えて心の平安と作品の益々の深化をお祈りしている。
2024年01月28日
コメント(0)
-

SIZMA-4 高津ゆい MIO YOSHIDA
高津ゆい作品「長き年月」 なじみやすい画風の高津ゆい作品は、観る人と同じ言葉で語りかけるのに対し次のよしだみおの作品は抽象化した言語で観る人に挑みかかる違いがあってもいずれも優劣つけがたい作品群であった。 高津ゆい作品「六角龍図」 contemporary artist MIO YOSHIDA作品「幻花」シリーズ YOSHIDA MIOの作品は鑑賞者に挑みかかると言ったが、それは「本当の感性」を忘れた「現代の人達へ」という作家自身の言葉がややとげがあるというだけでそれは飽くまで作家の他者にたいする構え方であって、作品そのものは対話に満ちているのは以下の作品を観ていただくと一目瞭然だ。 MIO YOSHIDA「幻花・波紋」 波紋と題された作品は水面に浮かぶ花と波紋を表しているしMIO YOSHIDA「幻花・増殖」「増殖」は、咲きつぐ花々を表現しており、 MIO YOSHIDA 「RISE」「RISE」は植物の重力に逆らう負の向地性を描写。 MIO YOSHIDA 「Geburt」 ドイツ語由来の言葉で起源とか出生を意味するゲバートと題された作品は巴紋の太極に通ずる記号が描かれている。 MIO YOSHIDA「Edel」 ドイツ語で「高貴な」を意味するエーデルでは炎に通じる子房あるいは胚珠が描かれておりダイアローグの可能性は開かれている。その上での何かこそがアートであり、スタート地点は高津ゆいと同じでその後の展開が異なるだけだ。 こうして大寒波と脅かされた日ならではのアートと向き合う十分なひとときを得て大満足だった。 田中佐弥さんの「青い世界で蝶の夢を見る」作品の一部作品もこうした同時代の作家たちと並べてみると作品を縛っていた枠が除かれて新たな意味を帯びてくることが理解でき、私にとっては実に素晴らしいアート空間であった。改めて田中佐弥さんにお礼を述べたい。 また、昨日は芦屋の月光百貨店で開かれているミスタニカエコの「畏怖」展へ赴いたのでその折の印象記を次回ここで述べたい。
2024年01月27日
コメント(0)
-

Sizma 3 切絵作家3名ときのこリウムと…
切絵作家という三人の作品。千木良さんの作品はきりえではないが、心にに焼き付いた。 ちぎらあやか 作品「柿」ちぎらあやか作品「柚子」伊藤史華作品「ひたむき」伊藤史華 作品「花うらら」伊藤史華作品の大作タイトル不明切絵作家 横浜在住 ひら子作品の大作「地(つち)」 存在そのものが象徴的な動物の犀を大地に見立てたのだろうか。たちどまらせるに十分な迫力が感じられた。ガラス工房ココロイロの幸小菜(みゆきさな)のきのこリウム3点もなかなかの工夫。ハタネズミを配した「きのことお散歩」。キコガサタケめくきのこが以下では鱗片をつけた ヒナノヒガサ風な微小きのこに。「きのこと宝もの探し」はきのこの迷宮で宝物探しに興ずる小動物。「きのこ集め」はハタネズミがコレクターになった図だろうか。ヒトヨタケ風のはかなさの極みのきのこを登場させなかなか飽きさせない。 この三点があることで、この異空間になんとも親しみやすい雰囲気をそえているようだ。私の言葉ではこれを<mushroom effect>と言っている。きのこのもつトリックスター性、異邦性が適材適所に配されたことでSizma空間が親和性を帯びている。
2024年01月26日
コメント(0)
-

STUDIO SIZMA-2 Kian
Kianさんと読むのだろうか。「夜鹿」と銘打たれた作品。 やや離れたところには同じく「長き年月」と銘打たれた作品。SIZMA全体の作品群と調和して存在感を際立たせている。Sizma空間に置かれた流木の台座の上で淋し気な修羅の様相を呈して空を見つめていた。
2024年01月25日
コメント(0)
-

スタジオ sizma 作家展の田中佐弥
大寒波襲来と散々脅かされながらも今里のstudio sizmaによたよたと出向いてきた。久しぶりのコアなアート展で、ついちょっとのつもりが2時間弱長居してしまったが心地良い時空を存分にさすらって来た。 一昨年、箕面のコンテンポラリーギャラリーZoneの「青い世界で蝶の夢を見る」展で非常に心惹かれた田中佐弥さんがsizmaの作家たちとの合同展に出品しているというので、昨年の雪辱を期して訪ねたのだが、寒波のお陰で客足が途絶えた会場でシャドウ・アーティストでオーナーという北野雪経(ゆきつねと読むらしい)さんとじっくり話が出来たのはありがたかった。6月には彼もZITSUZAISEIギャラリーでシャドウアートの個展を開くという。 スタジオ内はおもちゃ箱をひっくり返したような素敵な空間が広がっており昭和世代にはうれしいかぎりであった。 田中佐弥さんの作品は前回の個展の一部が展示されていたが、田中佐弥さんは現代社会はLEDの光によって夜でも至る所人工の光に満たされる。田中さんはこの作品でLEDの青い光の中で夜を奪われてしまった我々は、魂までうしなってしまったのではないかと問いかけている。 私は、神がテクノロジーに置き換わる世界で我々は何処へ向かおうとしているのかを問い続ける稀有なアーティストの登場に正直驚いている。今年はまたあらたな作品集をまとめるというので今から楽しみにしている。 SIZMAに集まった個性的な作家の作品の数々については明日以降またあらためてご紹介したい。
2024年01月24日
コメント(0)
-

逆回りで記録更新。
寒気団到来と気象予報士から散々脅かされた今朝はそれでも晴れていたのでコース逆回りでピー熊さんのところでも立ち止まらず挨拶のみすませ歩行速度を測ってみた。3.4km36分、40分台、50分を上回ることはなかったので左足にちょっと筋力がもどってきたかなという感じがした。これが1日でも間があくと元の木阿弥だから厄介だ。今日ははじめて先を行く歩行者を一人追い越せた。やったぜベイビー。 明日は本格的な寒気に覆われるというが、また遠出してみようとひそかに思っている。去年暮れあたりから今里になぜかご縁があり、先週あたりからむくむくとよからぬ想念に取りつかれ始めているので決行する予定。
2024年01月23日
コメント(2)
-

ささやかな発見
午前中、かってのMOOK『きのこ』時代に大変お世話になり、長らく音信が途絶えていた仲間できのこやオーロラのフォトグラファーからこの正月、相次いで便りが届いたので、『月のしずく』近号を送るため郵便局へ行ってきました。その帰るさ、密かに楽しみにしている乙女椿のご機嫌伺いにいったところ、何か様子がおかしい。 気を静めてしばらく辺りを見回していると…ありました。 樹上にあったときのままの姿ですこし離れた歩道の上に。 " 秘すれば花 "の令和版とでもいうのでしょうか。 私にとってもっと嬉しかったのは、乙女椿は原種の椿と同じく花のまま落花することをはじめて知った事です。 花びらを散らす山茶花や藪椿と異なり、花の完璧な姿のまま落ち(この習性ゆえに椿は打ち首を彷彿すると武家には嫌われたらしい)るのです。 些細な事ですが、なぜかうれしくなって遠まわりして帰りました。貴婦人不在のあずまやもひょっとして物憂げなご婦人が鎮座ましましているやもとおもい、のぞいてきました。こちらはいつもの通り空振りでした。ロト6の当たりと美しい女性には相も変わらずご縁がなさそう。 おじん臭い病気をわずらってからもアイリッシュ・ウィスキーは一日小さなリュームカに1,2杯、タバコは1日1本は嗜んでいますが、今日は乙女椿の秘密を知ったお祝いを兼ねて2本頂きました。世の医者は何でも禁止しますが、私は血をさらさらにする薬もやめはしませんが、様子を見てやがて半分にしようと密かに考えています。 それは今日のような愉しい事が増えるに従い減っていくものです。しかし、タバコやおいしいお酒に関してはごちそう同様やめることはありません。それは生きるのをやめるに等しいことですから。もっと言えば<百害あって益なし>なんて存在はこの世には何一つとして存在しないからです。要は用い方次第。これはきのこからの私へのメッセージです。内緒にしてきましたが、つい口をすべらしてしまいました。
2024年01月22日
コメント(0)
-

積読法からの脱出
朝からの雨もどこかへ 年初からの読書は、もっぱら過去の夥しい蔵書の再読からはじめた。日に焼けてかなり変色したページに半世紀に及ぶ書き込みを辿りながらの読書は全く身に覚えのないことばかり。だから長生きしてるんだと納得。 年末に必読書として買い求めたギョーム・ピトロン著・児玉しおり訳の『なぜデジタル社会は「持続不可能」なのか』や図書館で借りた古代史関係の6冊もはさみながら読んでいるが、これも1年後には全く新鮮な面持ちで読み返すのだろうなと思いつつ。大寒過ぎの日曜日はやや寒気もゆるんで過ごしやすい午後を迎えた。とりあえず1日前に読んだ本を再読しながら記憶に留める必要な個所はとりあえずノートをとりながら、ボケはボケなりにさあ今日もはじめるとするか。
2024年01月21日
コメント(0)
-

宮澤賢治への細道
宮沢賢治への導入口として不朽の名作と思しき著書は、中村稔の『定本宮沢賢治』(1966年・㈱芳賀書店刊)と天沢退二郎の『宮澤賢治の彼方へ』であろう。半世紀以上も前の著作であるが、本書を繙けば、夥しい赤や黒の線や書き込みが往時の問題意識からさほども隔たっていない私がいる。中村稔はその後、まもなく「長年、二流の詩人に関わりすぎた」との言葉を残して賢治と訣別したが、彼の半生に及ぶ賢治へのこだわりがなければ今日賢治がこんなに世に知られる存在とはなりえなかったと思う。 他方、天沢退二郎の『宮澤賢治の彼方へ』(1968年・思潮社刊)は賢治の作品論として独自の輝きを放っている。文字通り詩人・賢治の作品の彼方を目指して書き起こされた本書は、中村とは全く違った意味で珠玉の作品論となった。 NEO博物学の時代は、宮沢賢治再考と以前に述べたマルクス最晩年の到達点から出発した斎藤幸平の『人新生の資本論』と『コモンの自治論』を原本としての出発となりそうだ。私はきのこと関わり40年の歳月を送る間に市民という者に対して斎藤幸平らの世代の人が同じ40年をかいくぐって生き延びたとすれば思い当たるであろう実感を手にしている。それが「ちょっと背伸び」という言葉に集約されるものだ。これなくして市民の自治論は成立しない。それはすべて個人の責任に帰せられるものだというのが私の掴んだ実感である。 それは、それぞれの市民が「たった一人の革命」を遂げなければ実現できない、限りなく不可能に近いものなのだ。それなくして自治もへちまもない。それぞれが日々「ちょっと背伸び」し、自己を社会化していくことを置いて、実現しえない。その狭き門を市民一人一人の力で押し開くことこそが今試されているのだ。それは、仏教でいえば小乗から大乗へと数世紀かけて移行していっていまだその解がしめされないままのものであり、おそらくは八方塞がりの人間の生にまつわる絶対矛盾そのものなのだ。賢治はそれを詩人となることで答えを見つけ出そうとし、道半ばで果ててしまった。 ひるがえって21世紀の現在、文学も詩も極く一部のひとたちの特殊世界を除いて衰微しきってしまいヴァーチャルな幻想世界で人は生きれるのだという新興宗教にも似た他愛もない幻想が世を覆い始めている。 NEO博物学はそんな社会にとって最期の抵抗となる可能性が高いが、その担い手は、学者や知識人ではなく、ましてや政治家や経済学者でもなくちょっと背伸びの市民でしかないのだが…。しかもそのちょっと背伸びが当たり前のように可能なのが、ずぶの生活者ではなくアーティストでしかないと言うのが私の40年をかけて思い知らされた事実なのだ。残された時間はすでに僅少だが、その普及にすべてを賭けたい。
2024年01月20日
コメント(0)
-

月のしずく50号へ向けて
茶屋町一郎画伯の抽象日本画 きのこという目に見える微生物を通じて地球の明日を考える「月のしずく」も50号迎えるに当たり、筑摩版『宮沢賢治全集』を読み返している。 高校時代は山恋いとジャズと実存主義に明け暮れた日々だったが、かろうじてもぐり込んだ大学時代は、エールリッヒ・フロムの『自由からの逃走』にはじまり、筑摩が宮沢賢治全集を手掛け始めたのを機に全集を買い始め12巻揃えて読みふけった。それから筑摩は校本『宮沢賢治全集』を以後2度に亘り手掛け、様々な個人全集という形で出版史上に残る偉業を成し遂げたがそれがもとで会社が傾いたと聞く。同時期に『南方熊楠』全集も書店に並び始めていたがその当時は全集になるくらいだから有名な人だろうけど、どう読むのかなと思ったくらい私にはなじみのない人物だった。昭和42年(1967年)当時はそれが当たり前のことであったのが懐かしい。そのお蔭かどうかは知らないが賢治はポピュラーになり、日本の常識にまでなってしまい、彼の研究書や雑誌の特集がわんさか出て私がもっているだけでも50冊を優に超えるまでになった。彼を科学者として捉えた著作も多いが、私は彼は博物学趣味の人でいわゆる戦後日本の科学者一般とは無縁の人だと思っている。だからこそ広く列島人の共感を得たのだ。私は大学時代に賢治の花巻から小岩井農場、岩手山ほか、賢治の童話の舞台を訪ねて20日ほどかけて2度も岩手の方々を歩き回った。今思えば随分となつかしい気がしている。弟の清六さんも元気で突然の訪問にもかかわらず会ってくれたし、賢治の菩提寺ものぞいてきた。 賢治のような広義の博物学を手掛ける人たちを集めて地球の明日を考える会をつくろうと思ったのはその時の事だ。それにはきのこほどぴったりした対象は無い。80年代半ばにきのこと決定的に出会ったのはそのお蔭だと思っている。庶民の集いには記録が必須と考えて『きのこ通信』にはじまり、『MUSH』、『たけ取物語』、『きのこの手帖』、『ヘテロ』4巻、全国版サブカルチャー誌・隔月刊MOOK『きのこ』13巻、きのこと古代史の旅の記録『ムックきのこ』、そしてその集成としての微生物きのこを通して地球を考える『月のしずく』。そのニュースレターも50号を迎える。 この40年余りの短い期間に自然は壊滅的な打撃を受けて瀕死の状態となった。それは博物学趣味の人の間ではひっ迫した思いで感じている人も多い。そんなおりもおり斎藤幸平の『人新世(ひとしんせい)の資本論』が出て、いよいよNEO博物学の新たな地平も切り拓けた感じがしている。新しい思想には新しい言葉がともなうものであるが彼の著書にはそれが随所にちりばめられており、50号以降は彼の『人新世の資本論』と、白井聡、松本圭一郎、岸本聡子、木村あや、藤原辰史共著の『コモンの自治論』を必読書としてその戦略は全く異なるが純粋に個人としてアーティストたちを中心に世に抗う姿勢を打ち出すものにしていきたいと思っている。 目に見える微生物・きのこは異であることで特殊であり、かつ普遍的な意味をもってときおり顔をのぞかせる。地球の根源的な危機の時代にさしものきのこたちも断末魔の声をあげはじめており、50号よりはそのことを個人の倫理にアートとして訴えていく月のしずく本来の内容にしていきたいと思っている。のんびり構えている間に40年の歳月が流れてしまった。 とにかく今出来る事から始めたいと思っている。その意味で今年の昭和の日に第49回を迎える異民族慰霊祭は重要なプレイベントとなりそうだ。
2024年01月19日
コメント(0)
-

隠れ池の鴨たちも喜んだ喜雨の一日
我が家が花で満たされる1月17日が過ぎれば喜雨の一日が訪れ、隠れ池の鴨たちもいつになく寄り添って大喜びの様子だ。 1月17日は、今は亡きスモクトノフスキーのロシア映画の名作『チャイコフスキー』を観て過ごした。2時間半の大作だが、いつ観てもあっという間に終わってしまう。やはり往年のロシア映画は素晴らしい。
2024年01月18日
コメント(0)
-

我が町の初冠雪と良弁ちゃんの補遺と再考。
目覚めれば淡雪、そして初冠雪。ところが朝ご飯を大急ぎで掻き込んで戸外に出てみると、全くその痕跡すらない。 それでも小一時間歩いていると時折粉雪が舞う。とりわけ今朝は左足でしっかりと大地を踏んで歩いている感触がはじめて実感された記念すべき日になった。 曽爾村の郷土史家からの返事まちで良弁伝、止まったままだが、その間に良弁と藤原仲麻呂との意外なほどの親密さ、和気清麻呂と良弁。称徳天皇、道鏡と河内の秦氏らのことなどイメージがどんどん膨らみ手稿に大幅に手を入れる必要が出てきた。1月中にはすべて解決するだろうから一挙に書き上げるつもりである。
2024年01月16日
コメント(0)
-

お湿りの小正月
小正月の15日は、松の内の終わり。小熊三兄弟もさすがに門松を取り払い、多肉植物に替わっていました。早朝お湿りのあった北摂地方は、私が戸外へ出る頃にはお日さまも雲間から顔をのぞかせていましたが、今日は晴れたり曇ったりの一日のようです。 今年1年の精進が続く8年の射程を決めるとあって、毎日の課題にも力が入ります。まずは昭和の日の異民族慰霊祭に向けて準備を始めることとしよう。
2024年01月15日
コメント(0)
-

澤山画伯80+4馬力展
年頭恒例となった澤山輝彦展、今回の80+4馬力展は緑づくしであった。澤山とは、月のしずくでおなじみの茶屋町一郎(ペンネーム)さんのことである。今回の緑づくしは友人たちとの雑談で日本画に緑を多用した作品は比較的少ないなとの雑談から決まったというが、私はこの緑づくし、茶屋町一郎の時代意識が無意識裡に表面化したものと受け止めた。能登半島地震で始まった2024年の80+4馬力展は、画伯(私は氏のことを親しみをこめてこう呼んでいる)にとっても私にとってもグリーン回帰元年と思っている。昨13日の台湾総統選の民進党のシンボルカラーがグリーンだったことにもつながっており、その日会場で出会った彼の幼な馴染みの友人で菓子会社の会長が持参した伏見稲荷限定ニューアイテムの三笠の餡も抹茶色でそれぞれの無意識がシンクロした結果なのである。 2023年のウクライナ侵攻に続きガザのイスラエルによる大虐殺、大規模森林火災の数々が必然的に思い描いたものがエバーグリーンであったのはむしろ当然である。「月のしずく」も50号からは、より地球の根源的な危機に対処する方途について考える冊子本来の目的を深耕していきたいと思っている。 この作品は異質の紙を貼り付けて制作したものと想像できるが、この作品の皴からも樹木の影が彷彿される。氏とは、北摂から近畿一円の聖地の自然の移り変わりを30年以上も一緒に見続けてきたので、なにかにつけてその思いが投影されるのは当然なのだ。 一方、この作品にみられるような抽象画としては比較的分かり易い幾何学的な形象が数点散見されるのはうれしいが、ここで氏の作品から作家自身の言葉がなくなり、鑑賞者との間に対話が成り立つ手立てが失われてきたことにはたと気が付いた。日本画でもとりわけ抽象を手がけるこの画伯にとっては作品の制作意図は作品と作家をつなぐ唯一の手掛かりとなるだろうからである。 この作品や上の作品も同様だが、私にとって親しみやすいということは、鑑賞者にとって新しい意味での揺さぶりがない点で、作者その人にとってはインパクトという点でいささか弱い。これは抽象画を手掛けるアーティストすべてに言えることだろう。 この作品や次の作品は同じ澤山画伯の体臭を盛んに発している作品ではあっても分かり易いといった以上のものがある。それは要するに澤山節ともいえる作家の健在ぶりを伝える安堵感を伴うものであるからだ。しかし、本来抽象画家は私たちを新しい意味の場に連れ出し揺さぶり続けることでしか作品とその作家の生きる証しは得られないものなのだ。その揺さぶりに作者の意図を跡付ける唯一の手立ては言葉なのである。 この画伯の画期となった80+4馬力展を契機に、これから生まれる作品にはタイトルをぜひ復活してほしいものだ。それが100馬力展までの画伯の心象風景をより鑑賞者に的確に伝える手立てになると信じる。作品は独り歩きするものであるが、それであるからこそ作者の作品に対するオリジナルの意図がどこにあったかはもっとも重要になる。そんな意味でも80+4馬力展以後の作品は、タイトル、または時には短詩でもよいので言葉を添えることを復活していただきたい。これから10年私の貴重な旅の伴侶として、画伯には寸言ではあっても言語をともなう抽象画家として是非ともそれをお願いしたい。「無題」であっても「無題」とすることには十分に意味はあるのだから。 私が「月のしずく」49号で例に挙げたきのこポエムの意味はそこにこそある。この80+4馬力展のことは「月のしずく」50号でも私達、月のしずく同人のグリーンエポック元年の画期として触れたいと思っている。 残された9年のその始まりの年に、私にとって、そしておそらく画伯にとっても実に希望に満ちた個展となったものだと今しみじみと思い返している。願わくば共に後10年歩き続けたいものである。
2024年01月14日
コメント(0)
-

旧暦師走2日の1月12日
わが町の近隣には乙女椿は二本しかないと言ったが、今日つぶさに調べてみると花を確認したことがないだけで30本以上あることが分かった。うれしい誤解だったわけだ。その数本には花蕾が。ロシアのことわざに"ツバメ一尾で春は来ぬ" (アドナー ラースタチカ ネ ジェーラエット ベスナー) と言うのがあるがだれかさんの秘密の花園にはツバメも登場。いろいろあってもまだ春は来る。 乙女椿は山茶花の植え込みの中からところどころ抜きんでた木々が認められそれらがすべてそうであったことが判明。うれしい発見であった。 紅、ピンク、白花の山茶花も今真っ盛り。 これらの終わるころに乙女椿が花時を迎えるので、これから弥生3月まで花には事欠かない。 トウネズミモチの実も黒々と実をつけていた。夏には目立たないがかぐわしい白い花をつけて迎えてくれるのでおなじみさんだ。ネズミモチと思いきやこのあたりのそれは葉の大きさからトウがつくのに気づいたのは晩秋の頃になってから。お見それしてすみませんでした。
2024年01月12日
コメント(0)
-

昨日と打って変わって。マンネンタケと乙女椿
昨日は午後からよく冷え込んで足もつるくらいでしたが、旧暦師走朔日の今日は、また小春の一日。訪問リハの日でしたので終わってから郵便局へ。振り込もうとすると1月22日から現金支払いの際に取られていた手数料の110円が22日からは取らなくなるので急がないなら22日以降にとのこと。ゆうメール特別の「月のしずく」の送料支払いなのでもちろん願ってもないことで、そうすることにして郵便局を後にした。 そのついでに、この陽気ならマンネンタケも背伸びしはじめているのではないかと訪ねてみると、案の定、頭をもたげはじめていた。 出たついでにもうひとつわが秘かな愉しみの場所へ。近辺には乙女椿の木はふたもとしかないが、また新顔が丁寧なご挨拶を。よく見るとその二本ともに花蕾を4-50以上もつけているではないか。ダリアと交配したような美しい花序が私を魅了してやまないこの花の個性的な表情がこれからしばらく楽しめるのはうれしいかぎりだ。これが正真正銘のツバキであるのが奇蹟のように思われて飽かず眺めてきた。
2024年01月11日
コメント(0)
-

自主歩行テストの始まりに
今日から月1回歩行テストを始めることにした。コミセンがスタート地点。コミセンから保育所 800m、8分。保育所から三田谷公園入口 300m、3分。公園からサミットホテル 600m、7分。サミットホテルから宝くじ売り場 100m、3分。宝くじ売り場から博物館北端 600m、6分。北端からシュラインロード400m、6分。シュラインロードからスタート地点600m、10分。計3.4kmに43分かかった計算である。 かかとを速やかに上げて後足を持ち上げ、指先が地面を離れる際に足先の小指から親指に力を心持ち移動しながら最後に親指で微妙に蹴り上げ、前に振り出し、次にかかとから着地して小指から親指へと順次着地。そして体重を十分に移動しながら右足を持ち上げる。これを最初は意識しすぎるくらい意識してはじめ、距離が伸びるにつれ、次第に無意識に繰り返す。私の場合この体重移動を難なくしているつもりだったが、右足が秘かに代行していることにこのほど気が付た。ただ歩くだけでも大変なことがようやく身に沁みてわかった。 ひたすら歩き、途中では美しいものだけを立ち止まらずに見る40分間。100m、約1分。理学療法士の基準の6分では約500m。これが2024年1月10日のデータ。これを基準値として知らん存ぜぬを決め込んだ左足を駆使して少しずつ短縮していく。なんとか雨に会わずに終了。次回は30分に短縮できるかな?。
2024年01月10日
コメント(0)
-

そろそろ門松はきのこに・・・。
明日で私の正月モ―ドは切り替え、門松はきのこに・・・。 今年の読書は、マルクス・ガブリエルの「なぜ世界は存在しないか」の再読からはじまった。「神の問題」と「芸術の問題」を熟考するために。 乙女椿がまた開き始めた 「良弁伝」は道鏡の章で行きつ戻りつしている。道鏡という僧侶は考えればかんがえるほど可哀そうな気がしてならないのでそれをどう扱うかで筆がとまっている。 リハビリ散歩は私なりには歩行の点でちょっと改善が見られたような気がしている。その分歩く速度が速くなった。まだまだ普通の歩行感覚は取り戻せてはいないが、左右のゆれがやや少なくなったのは左足に自主的な動きが目覚めてきたからかもしれない。毎日の3.4kmコースを何分で歩けるか来週あたりから測定してみようと思っている。
2024年01月09日
コメント(0)
-

1月最初の8の日
コナラのどんぐり 切り株のサルノコシカケ ウメノキゴケと満天星の冬芽 花時を迎えいまだ夢見心地の山茶花 綻ぶを知らず固くつぼんだままの山茶花 一輪挿しの投げ入れに最適な藪椿の花 1月8日の隣人たち。深く静かに春を待っている。
2024年01月08日
コメント(0)
-

屋代なきシュライン・ロードに祈る
わが町には神社がないのにシュライン・ロードという通りがある。金沢在住のアートプロデューサー金田雅さんや陶芸家の山本優美さんの無事が確認できたこともあり、散歩がてら神社を探して歩いてきた。 シュライン・ロードのどん詰まりはかってこのあたりがまだ原野だった頃にわたしが勝手に関電道と呼んでいた境界尾根に突き当たったが、やはり神社の痕跡すらもなかった。関電道とは電力会社が高圧線設置の為に切り拓いた調査用の道のことだ。ただ、私がいつも横切るシュライン・ロードの脇に歩行者の足休めのためのあずまやがあり、左右に燈篭が設置されている。これを拝殿と見立ててのシュライン・ロードであることで納得。休みがてら能登半島の方へ向いて祈りを捧げてきた。 裸木の向こうに小春の日がはしゃいでいる。独立国家とは名ばかりの島国・日本。波瀾含みの幕開けだが、今年はきのこ暦第五期のイヴの年。カワラタケ・ハカワラタケ・シロカイメンタケ・ノウタケ・マンネンタケ・ネンドタケモドキなど、冬なお活動を続けているきのこたちにも「頼むぜ」と声かけてきた。私たちが49年護り続けてきた神戸の北方異民族慰霊碑は、何よりも異類塚であることで分断の21世紀に一石を投じ続ける。グローバルサウスという外部や異を決して作らないと言うNo more 英霊、異すなわちヘテロの智慧に学ぶことを誓う碑であってこそ、その意味があるのだ。それをしっかりと伝えることがきのこ暦第五期8年間の主目的となる。いよいよ次年度に向け「月のしずく」も正念場を迎える。よそおいも新たに少しずつ賛同者を募っていきたい。
2024年01月07日
コメント(0)
-

朋、遠方よりきたる また愉しからずや
高曇りの一日、隠れ沼と博物館の収蔵庫を散歩がてらのぞいて帰ってくると電話があって、茶屋町一郎さんが博物館まで来て新年の挨拶に伺いたいとの嬉しい声が。今日あたりひょっとしてと思っていたのがピタリ的中してやや驚きました。 飛来して沼になじんできたマガモ 自身の個展直前の繁忙期にもかかわらず、よくぞ遠くまで足を運んでくれました。 ちょうどグッドタイミングだったので、お抹茶とお菓子でもてなして、もっと話したかったがめずらしく遠慮するのでしばらく募る話をして駅まで送って行きました。 ヤグラタケとクロハツ ハシブトとハシボソカラス『月のしずく』の今年の抱負を語り合い、今年は益々過激にやろうと語り合い別れましたが、実に幸先の良い新年になりました。ありがとう。
2024年01月06日
コメント(0)
-

令和の聴耳草紙『月のしずく』
ホカホカの雲がポカポカと浮かんでいる。<小寒>前日の朝。 ホルダー・クマゴロウの落とし物。里に出没しはじめただけでシカの次には熊が殺され始める事だろう。シカも熊も増えすぎたのではない。人が増えすぎたのだ。それは言っては駄目だから言わないだけのこと。しかし、間違っても鹿や熊のせいにすべきではない。増えすぎたなんてもってのほかだ。 わが秘かな聖地は落葉まみれ。 無秩序に散り敷いた落葉だが、すでに風の作用でそこここに吹き寄せられ落ち葉だまりができはじめている。まもなく地表下の菌糸がそれらをつなぎ留め固定化しはじめることだろう。この菌糸たちの働きをホワイト・ロッドという。徐々に白化していき朽ち葉となり1年余りかけて土に還る。だから森は清浄なままなのだ。目には見えぬ世界の生きものが四六時中働いて弔っているのを知る人は少ない。その変化自体は知っていても、それがきのこたちの本体である菌糸がやりこなしていることをほとんどの人は知らない。きのこの文化とはその因果関係を知っている人たちがそのことを表現することから始まる。この菌糸たちの働きがなくなった時、地球はカオスにもどる。当然、人は現在の人のままで生きられなくなる。それでいいとでもいうのだろうか。40年近く言い続けて来て、ようやく時代はスーパーきのこ時代の直前まで来た。このプレ・スーパーきのこ時代があと何年続き、この地球にスーパーきのこ時代が訪れるかどうかもすでに分からない。危機は加速しっぱなしだからだ。 その担い手をずっと探し求めてきたが、そろそろ"It's time." 今更あせりはしないが、私に残された時間も極く僅かになってきた。 この40年あまりの間に昆虫も植物も動物も激減してしまった。それも誰もが思っているが誰も口にしない。したたかな生存戦略を誇るきのこでさえ激減してしまった。それだって特定の誰かのせいでもない。ただ、「幸せになりたい。豊かになりたい」と願う私たちの過剰な願望が招いたものだ。行為ではないから犯罪は成立しない。しかし、結局は私達一人一人のせいなのだ。だから脱成長こそが唯一の目標であることはもはや自明であるが、その達成は学者や政治家、経済人、評論家などごまんと集めても難しい。身分や肩書、知識、権力一切合財に関係なく、<ちょっと背伸び>を始めた市民だけがそれを真に変える力をもっている。そのちょっと背伸びこそが至難の技だが、それが可能なのは誰であるのかが問題だ。その人たちの特定とその人たちのなすべきことを「月のしずく」でこれから展開していきたい。ようやく聞く耳をもちはじめた人たちのために、あと少しそれを伝えるという役目を果たしたい。
2024年01月05日
コメント(0)
-

ヨージク ス グリバーミ
ス―パーきのこの時代の幕開けは激動の時代のはじまりでもあることを実感する年明けであった。遅々たるあゆみではあっても今年1年の活動が来年以降の8年の射程を決定することになる。 3ケ日を終えても、日常が戻らないのは能登半島の人たちと同様の身の上ながら、今年は私にとっては身辺総整理の日々。心して残る362日を過ごそう。ヨージク ス グリバーミ。日々の散歩道で励まされる<きのこを連れたハリネズミ>同様、心に、"永遠の異邦性の象徴たるきのこ"を刻みながら8%の可能性を掘り下げていく1年としたい。太陽の覇者の原理に代わり、人類がはぐくんできた月の原理こそが求められる時代の幕開けに「月のしずく」も今年は益々深化させたいと思っている。
2024年01月04日
コメント(0)
-

三が日の終わりは。
去年の三ケ日の終わりは、芭蕉の絵巻見聞に嵯峨野の福田美術館を訪れたが、今年は40年近い活動の澱を一掃することに明け暮れている。 近くの小公園ではカニあるいは毛無し毛虫の遊具がポツリと立ち尽くしている。異類塚の象徴としての<きのこ塚>の必要性を今春ほど強く思ったことはかってない。外部性、他者性、資本主義の爛熟はかっての植民地政策や異民族の利用によって無限に外部、他者を濫造することによってなされた。永遠の異邦性こそがきのこの本質であること。私は40年前よりその事に気づき、微生物・きのこと親しむ文化醸成こそが21世紀の疲弊した地球を明日へとつなぐと信じて日本キノコ協会を興した。その当時感じた予兆がことごとく現実化してきた"人新世"時代、きのこは目には見えないが実在し、われわれの生命を育んでいる微生物や異類全体の生存証明として我々に働き駆けてきたことを想う。 来年よりはじまるきのこ暦第Ⅴ期8年を人新世紀元年ととらえてNEO博物学を脱構築しながら新たな指針のもと、活動をはじめなければならない。その脱成長資本主義の担い手はこれまでの苦い経験から極く少数のアーティストでしかありえないことが判明した。したがってヘテロソフィア芸術のトレンドにどれだけアーティストたちを集めることができるかにかかっている。政治や経済から自立した想像力の深化がためされる時代、これこそがあらゆる意味で人新世時代を支える武器を捨てた戦士像だと思っている。
2024年01月03日
コメント(0)
-

2024年元旦
大地を蔵するごとき地蔵の智慧がもっとも重要となる2024年の元旦は恙なく明けた。 午前の追谷墓苑は常と変わらず清々しい気に溢れていた。 続いて訪れた神戸護国神社の慰霊碑は初めて赤花の山茶花が咲いているのに出会いほのぼのとした雰囲気にしばし浸ることができた。 宮司が長期療養中の神社は、ご子息に当たる若い宮司の努力で拝殿周辺はで新たな試みも見られ活気が溢れていた。 すべては順調で大旦の厳粛な雰囲気に満ちていた。 久しぶりに会うはらかららも無病息災で今年初春に是非読んで欲しい新書『人新生の「資本論」』斎藤幸平著を紹介して年頭のあいさつに代えた。そして久しぶりの会食半ばの午後四時半ばに、長い揺れを感じた。能登半島沖を震源とする最大震度7の地震の始まりだ。新年早々希望の灯をかき消された人たちも多かかったことだろう。冥福を祈る他ない。次々と広がりをみせる被害状況がその大きさを示していた。年の暮れに感じた予感が元日には早くも現実に。気を引き締めて事態を直視するほかない。
2024年01月02日
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1