2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2011年05月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
『ハンス・コパー展 20世紀陶芸の革新(静岡市美術館)』
仕事で昨日(5/23)静岡に行く。一泊したので、今日(5/24)静岡市美術館で『ハンス・コパー展 20世紀陶芸の革新』を見る。朝10時過ぎに入館。静か。画学生(古い言い方だ)らしき数人がメモを取りながら見ている。その横をすり抜け、どんどん先に進んだ。昨年もこの時期に静岡に行った。同じ月曜日に行き火曜日に帰った。月曜日は大抵の美術館は休み。静岡市も同じ。昨年は体調を崩し、美術館に寄らず火曜の朝早々に帰った。その時、今度静岡に来る機会があったらよってみようと思っていた。それで、念願叶い寄った。行ったではなく寄った。ハンス・コパーは1920年ドイツに生まれ、19歳の時単身でイギリスに渡った(亡命)。そこで、知り合った、陶芸家ルーシー・リーに出会い陶芸を始めた、という。さて、作品はつやのないものが殆どで、それが陶器、すぐに端が欠けそうな微妙な質感と姿かたち。色も黒に近い茶、またはアイボリー・白が主でどちらかといえば日本の原初的な陶器を思わせる。(感じとして)中でも、キクラデス・フォームは人体のある部分を想像させるものもあり、見ようによってはエロティック。きっと、そんな風に見ている人間はいないと思うが・・・、私にはそう見えた。また、チラシやポスターのメインに紹介されている、ティッスル・フォームは「薊の花」の形状を象っているというが、人間の足とその付け根、臀部に見えて仕方が無い。今日の静岡市美術館は閑静でゆっくりと作品を観ることが出来た。
2011.05.24
コメント(0)
-

『ブラジル・ヌーヴェルヴァーグ特集』
ブラジル・ヌーヴェルヴァーグ特集2本を見る。名古屋シネマテークのHPを引用【】すると、『マクナイーマ Macunaima (ジョアキン・ペドロ・デ・アンドラーデ)1969』【アマゾンの密林で生まれた瞬間にすでに中年の男だったマクナイーマ。おとぼけ兄弟と大都会へ! 奇想天外なストーリーが極彩色に展開するアンドラーデの野心的コメディ(?)。『エル・トポ』のごとく、D・リンチ作品のごとく、物語が脱臼しまくる105分】ということ。物語の展開も奇想だが、溢れんばかりのその色彩には目を瞠った。原色につぐ原色が登場人物たちの服装を覆い、自然いっぱいのはずの風景も人工的な色合いで満たされる。毒々しさを超えた美術の技を感じる。それと、出てくる女たちが皆色っぽい。ブラジル女性の魅力も満載だ。先日、他界した東映名誉会長でやくざ映画路線を牽引した岡田茂氏の言葉「映画は不良のもんだ」を思い出す。この『マクイマーナ』も毒が一杯の危ない映画だ。もう一本。『夫婦間戦争 Guerra conjugal(ジョアキン・ペドロ・デ・アンドラーデ)』これも同じ監督。こちらは1975年。三組の男女を通して男と女の駆け引きを見せる。こちらも、HPには【ブラジル南部の街クチバを舞台にした3つの男女の物語。クライアントの女性を誘惑しようとする弁護士、究極の快楽を与えてくれる女性を探す男、そして諍いを繰り返す初老の夫婦。艶笑コメディの形式をとりつつもブラジル社会を鋭く批評した作品。88分。】とある。例えば「究極の快楽を与えてくれる女性を探す男」の行き着いた先は、その男性の母親かそれよりも年上の老婆。しかし、色っぽいです。その役者は知る由もないが、豊満な肉体を惜しげもなく見せてくれる。60歳か70歳か・・・、いずれにしろそれくらいだろう。日本の女優にそれは無理な話?かつて『つぐない』のキーラ・ナイトレイを例に、その役者魂を見たといったことがあるが、それを思い出した。ジョアキン・ペドロ・デ・アンドラーデ
2011.05.19
コメント(0)
-
マンハッタン無宿
『マンハッタン無宿/COOGAN'S BLUFF(ドン・シーゲル)1968』久々に見る。CSのムービープラスで放送。都会を舞台にした西部劇、というのが巷の評価だが、気づいたことを一つ。アリゾナでは保安官=警察だが、ニューヨークでは市民という身分の主人公(クーガン)が、身元を引き取りにきた男を捕まえる。色々な手がかりを求めながら・・・。これって、探偵物=ハードボイルドでは?という発見。日本では1969年公開。その年のキネ旬外国映画ベスト10の50位。点を入れたのは南俊子(10位)と山田宏一(5位)の二人。また、双葉十三郎の「ぼくの採点表」は☆☆☆★★の70点。尚、原題のbluffは「ぶっきらぼうな・無愛想な」という意味であろう。もう一方の「(はったりで)だます」ではないと思う。
2011.05.17
コメント(0)
-
『NHK-BSプレミアム』 昼の映画
昼の時間。13時からの映画ラインナップ、昨日(5/9)が『十一人の侍』今日(5/10)『大殺陣』いずれも東映集団時代劇で、その代表作『十三人の刺客』は入っていない。三本とも監督は工藤栄一。明日(5/11)は『反逆児』明後日(5/12)は『関の彌太っぺ』そして、5月13日は『仇討』。この5本の共通するところが良く分からない。あえて言えば全部東映。そんなことは、どうでもいい。全てに触手が動く。追加・・・、今夜は『ノー・マンズ・ランド』です。
2011.05.10
コメント(0)
-
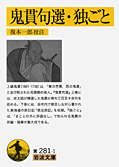
『鬼貫句選・独ごと(復本一郎 校注)』
『鬼貫句選・独ごと(復本一郎 校注)』ほんのりとほのや元日なりにけり何おもふ八十八の親持て朝も秋ゆふべも秋の暑さ哉闇(くら)がりの松の木さへも秋の風行水の捨どころなき虫のこゑおもしろさ急には見えぬ薄かなによつぽりと秋の空なる富士の山此秋は膝に子のない月見哉あたゝかに冬の日なたの寒き哉つくづくとものゝのはじまる火燵哉水鳥のおもたく見えて浮きにけりいつも見るものとは違ふ冬の月膝がしらつめたい木曾の寝覚哉灯火の言葉を咲すさむさ哉待宵の頭巾や耳をあけてゐる白妙のどこが空やら雪の空雪で富士歟(か)富士にて雪かふじの雪雪に笑ひ雨にもわらふむかし哉鰒(ふぐ)くふて其後雪の降にけり惜めども寝たら起たら春であろ人間に知恵ほどわるい物はなし「鬼貫句選」から以上を・・・。「独ごと(上)」から以下を・・・。三十四 古格を知ることいにしへ守武(もりたけ)、宗鑑(そうかん)、連歌に対して俳諧を興し、貞徳(ていとく)、立圃(りふほ)、重頼(しげより)また中興して専ら世上に此道をひろむ。しかれども其詞(ことば)かたく、式こまやかにして、初学の人の道に入りがたき所をおもひよりて、その後梅翁(ばいをう)当風を作りてうたふ。其句の姿、詞花やかに打くつろぎたれば、人皆おほく古風を捨て、その当風にかたぶき侍りぬ。それより猶(なほ)さまざまに移りかはりて、いつしか彼古風をうしなひ侍りき。其古(そのいにし)へをしれる人は次第に世をさり侍りて、風儀のうつりかはりし末より学び入たる作者、そのいにしへをしらざれば、法外なる事を法外なりともしらず。云々(以下略)以上引用(太字)三十五 「まことの外に俳諧なし」(前略)いにしへよりの俳諧はみな詞たくみにし一句のすがたおほくはせちにして(※)、或は色品(しな)をかざるのみにて心浅し。つらつらよき哥といふをおもふに、詞に巧みもなく、姿に色品をもかざらず、只さらさらとよみながして、しかも其心深し。云々(以下略)以上引用(太字)※せちにして 世智にして。かしこげであって。「東の芭蕉、西の鬼貫」と並び称された元禄期の俳人。眠る前に少しずつ読み、ようやく読み終える。気に入った句を箇条書きにしたが、俳諧というものの本質が見えたように思う。鬼貫句選・独ごと復本一郎 校注岩波文庫 黄281-12010年7月16日 第1刷発行
2011.05.09
コメント(0)
-

NHK日曜美術館「野田弘志」
『原点にして究極! 超写実絵画 野田弘志 』NHK日曜美術館。今日は野田弘志。多分20年以上前、どこで見たのか忘れたが、野田弘志展を見た。その細部に渡る描写に驚いた。そして、惹かれた。その後、野田弘志の絵は豊橋市の美術館にあると聞いた。いずれの機会があればと思っていた。そして、その機会が・・・。昨年仕事で豊橋市に行ったとき、その美術館に寄った。だが、残念なことに、企画展準備のため常設展もなく、野田弘志の絵は勿論なにも見られず帰った。そして、今日5月8日朝、TVで野田弘志の絵、その制作、アトリエを見ることが出来た。思いがけない喜びであった。今度こそ、豊橋市の美術館でその実物を見たい。手許には、代表作『黒い風景 其の三』の印刷物がある。『黒い風景 其の三』(1973年 豊橋市美術博物館蔵)
2011.05.08
コメント(0)
-
『真夜中のサーカス(三浦哲郎)』と『曠野の妻(三浦哲郎)』
七冊目と八冊目の三浦哲郎。『真夜中のサーカス』は連作短篇集。舞台は東北にある海辺の町「菜穂里(なほり)」。架空の町。「木戸が開く前に」「綱渡り」「パレード」「魔術」「寸劇」「パントマイム」「スポットライト」「檻」「空中ブランコ」「ジンタの嘆き」「鞭の音」「赤い衣装」「小人の曲芸」「火の輪くぐり」の全14篇。「木戸が開く前に」の野良犬、再び現れる野良犬は「火の輪くぐり」。一瞬読者は同じ野良犬?と思う。確か「木戸が開く前に」の野良犬は車に轢かれて死んだのでは?読者の思うとおり、最後の一篇の野良犬は、初めの野良犬とは違う。奇妙な仕掛け。「スポットライト」の長閑なユーモアと「赤い衣装」の凄惨な人生。それらが一つの連作(14篇)に置かれている。人間の営みの様々な面を、架空の町で起きる出来事になぞらえて語る、三浦哲郎の小説の醍醐味。さて、『曠野の妻』である。何でこういうものを書くのか?口を糊するため?安易なメロドラマだ。行間で語られるべきが、すべて書かれている。その分、長くなっている。三浦哲郎はこういう仕事もした。真夜中のサーカス三浦哲郎昭和55年3月15日 印刷昭和55年3月25日 発行新潮文庫 草135=04(昭和48年6月 単行本)曠野の妻三浦哲郎装幀:司修1992年11月30日 第1刷発行講談社(1990年1月号~1992年4月号 「婦人之友」連載)
2011.05.07
コメント(0)
-

『政治と金 海部俊樹回顧録(海部俊樹)』と減税日本
『政治と金 海部俊樹回顧録(海部俊樹)』昨年11月20日発行、手許は12月5日3刷。腰巻は【「この話、墓場まで・・・・・持っていくのはやめた」永田町激震!元総理が全て書いた】とは、言うものの全て書いてあるとは皆思わない。もし、そうならこの本は出た瞬間ある種の力が働き、買い占められるか、店頭から消えたであろう。既に3刷という事は、其処に書かれていることは、書かれた当人たちにとっては痛くも痒くもない事だ。一つ引く【O幹事長(※)は、辞める必要がない場面で逃げた。IOという政治家の「どうしようもない性癖」を、私が目の当たりにした最初の時だった。】(※)自民党幹事長【最初の時だった】が、ミソ。議会での与野党の攻防、質疑応答は殆どの場合は出された質問に国の役人・市町村の公務員が答弁を書き、議員がそれを基に答える(それを読む)ケースが多い。それを八百長と言えば八百長だが、議会の進行にもかかわるからそれなりに理解できるが、良い事ではなかろう。欧米はその場で質問が出され、その場で答える。それが普通。【】内 引用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さて、先日、名古屋市議会で、いきなり質問された減税日本の新人議員が応対に戸惑う場面があった。新人議員だから已むを得ないのか?代表でもある河村名古屋市長は、こう言った。「いきなり、質問されたら、答えられない。新人議員だから尚更だ。今まで質問は事前に知らされていた」と。しかし、こういう事態は予測できたこと。名古屋市議の保守派の議員たちは、多数派の減税日本の政策をどのようにして叩こうかと手ぐすねを引いて待っていたところへ、出て行く限りそれくらいは予測しなくては駄目だ。重ねて言う、市議会解散の署名活動をした時も、結果として署名は住民投票をするに十分な数を集めたが、そこに行く経緯も情けないものであった。当然色々と障碍があることを予測してやらねばならないことが出来ない。こういうのを脇が甘いという。この二つを見ても、今の減税日本は「脇が甘い」といわれても仕方あるまい。これが、勉強になればよいが・・・。海部俊樹回顧録を読んで、減税日本のことを考えさせられた。政治と金 海部俊樹回顧録海部俊樹2010年11月20日発行2010年12月5日 3刷新潮新書 394
2011.05.06
コメント(0)
-

『日・中・韓 平和絵本』シリーズ
『日・中・韓 平和絵本』シリーズ『京劇がきえた日 秦淮河(チンホアイホー)・一九三七(姚紅(ヤオホン)=作 中由美子=訳)』『非武装地帯に春がくると(イ・オクベ=作 おおたけきみよ=訳)』を、図書館で借りる。『日・中・韓 平和絵本』シリーズ10冊中の2冊。【日本・中国・韓国の絵本作家が手をつなぎ、子どもたちにおくる平和絵本シリーズ、童心社(日本)、訳林出版社(中国)、四季節出版社(韓国)による共同出版】と銘打たれている。『京劇がきえた日 秦淮河(チンホアイホー)・一九三七』は、1937年12月、日本軍が南京を占領した日の前後の話を、一人の少女を通して描いている。また、『非武装地帯に春がくると』は、南北朝鮮の国境にある、非武装地帯の四季を通して、米ソ対立による南北朝鮮の今を書いている。非武装地帯は【人びとの出入りが制限されたため、非武装地帯とそのまわりでは、ほかの地域では絶滅したり、絶滅のおそれのある動植物がたくさんみられます。そのため、動植物の「楽園」ともよばれています。しかし、よくかんがえてみると、そこは楽園ではなく、“最後のひなん場所”なのです。】このことは、様々な要素を含んだ現象がそこにあると考えさせられます。人間とそのほかの生き物との共生とは?人間が手を出せる範囲はどこまでか?等々・・・。【】内 引用京劇がきえた日 姚紅(ヤオホン)=作姚月蔭(ヤオユエイン)=原案『迷戯』中由美子=訳2011年4月1日 第1刷発行童心社非武装地帯に春がくるとイ・オクベ=作 おおたけきみよ=訳2011年4月1日 第1刷発行童心社
2011.05.05
コメント(0)
-
『イリュージョニスト(シルヴァン・ショメ)』と『ファンタスティックMr.FOX(ウェス・アンダーソン)』
『イリュージョニスト(シルヴァン・ショメ)』と『ファンタスティックMr.FOX(ウェス・アンダーソン)』このようなアニメーションが同時期に公開されるのも珍しい。近年にはないことでは?子どもを含めた家族を観客層として作られたアニメーションは多々あるにしろ大人向けは記憶にない。私が見たものでは『戦場でワルツを』か『ペルセポリス』まで遡る。意地になるつもりはないが、この二作は技術面も内容も大人の鑑賞に堪えるに十分なものである。方やジャック・タチが脚本を、方や原作ロアルド・ダールという贅沢さである。この名前だけで触手が動く。しかし、何故か?大した話題にもならずに、単館公開で終る。大人の鑑賞に堪えるとは、登場人物(一方は動物が主人公だが)の誰もが大袈裟に振舞うことも喚きたてることもなく、実に存在感がある。物語も自然な成り行きという、比較的大人しい展開では有るが、そこには足が地に着いた安定感がある。あぁそうかという切なさもあり、してやったりという快感もある。低学年は無理かもしれぬが小学生高学年以上にこういうものも見せてみたい。
2011.05.04
コメント(0)
-
『長谷川伸と日本人 第十六回「オヤ」と「コ」(山折哲雄)』波(2011.4)新潮社
『長谷川伸と日本人 第十六回「オヤ」と「コ」(山折哲雄)』波(2011.4)新潮社もう、十六回になる論文。今回は柳田国男の『国史と民俗学(1944)』のエピソードから。【むかし、ある田舎の男が親を殺した。召捕えて問いつめると、昂然と頭をあげて罪に伏しない。自分の親を自分で殺すのがなぜ悪いかと反論してきた。そこで刑をしばらく延期して、獄中で『大学』とか『孝経』とかを三年教えた。そうするとはじめて翻然として悔悟し、自分からすすんで甘んじて刑をうけたという】つづけて、山折は書く。【柳田はいう。「書物」の害は「伝説」よりもひどい。このように物騒な人生観を抱く者がもしいたとすれば、われわれの社会が今日まで存続しているはずがない。(中略)われわれの郷党社会、郷党教育においては、たしかに「人を殺すな」「盗むな」というたぐいの大文字の箇条書きなどはなかった。なぜなら日常生活のなかでは、「骨惜しみ」と「身勝手」を嘲り憎み、「臆病」や「間抜け」を口汚く笑う規律ができあがっていた。それにたいして「機敏で注意深く衆の為に身を労し」、「勇敢に任務を断行し得る」者を「よき若者」とみとめていたのであって、そのほかに漢字で記されたどんな道徳律も必要はなかったのである・・・・・。】山折の論旨は、柳田国男の「義理人情」問題から親分子分、即ち「オヤ」と「コ」へ展開される。しかし、今回この一節を引いたのは、どうしても3.11の震災とダブってくるからである。(中略)以下の文章がそれを感じさせる。特に【漢字で記されたどんな道徳律も必要はなかったのである】に興味を覚える。話は、大きく飛躍するが、小林秀雄の講演(1978.8.6)『本居宣長』で、それを指摘していることに影響されての思いである。言葉=理屈がもしかしたら人間にとっては不要のものだあるかもしれないという考えである。また、先日の『一枚の白いシャツ・・・』のときに触れた『逝きし世の面影(渡辺京一)』にある、もともと日本人が持っていた世界観に関係する。『逝きし世の面影(渡辺京一)』については、読了がまだだがいずれ書いてみたい。
2011.05.03
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- ドラマ大好き
- 終幕のロンド 第3話を観た 基本路…
- (2025-11-25 21:33:12)
-
-
-

- アニメ番組視聴録
- 11日のアニメ番組視聴録
- (2025-11-11 19:09:38)
-
-
-

- 海外ドラマ、だいすっき!
- 『THE NEXT PRINCE』※サブCPの話しか…
- (2025-11-25 22:57:25)
-







